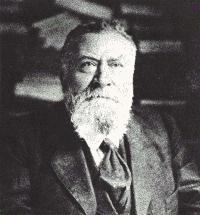 |
こんなやさしそうなおじいさんが殺されてしまうなんて・・・・ |
|
戦争とは、ある偉いサンが一般大衆を扇動し、その扇動にそそのかされた大衆が多数になったときに起こりやすい。よって戦争を起こしたくなければそのような扇動者をリーダーとして選ばないことである、といった考え方も大方あるだろう。 しかし、そのよう扇動者がリーダーとならなかった場合でも戦争は大いに起こる危険性をもつことを第1次世界大戦直前直後のヨーロッパの状況は我々に示しているように思える。 第1次世界大戦がはじまった時、多くの人民は別に偉いサンに尻押しされるまでもなく自ら熱狂的に戦争に参加していった。 そもそも、当時のマスメディアとは、せいぜい新聞くらいしか見あたらないようである。ラジオ放送は1920年の秋アメリカ東部の町ピッツバークで世界で初めて放送されたらしく(資料1)、したがってこの時代にはなかった。そんなマスメディアの乏しい時代であったので、扇動するにも後の第2次世界大戦の時のように容易ではなかったし、まして突発的に起こった戦争なので、扇動する時間もなかったと思われる。(ドイツ国内ではへんな扇動?デマが流れた説があったようだが、たいした効果がなかったように思われる。)なお、イギリスでは当時、徴兵制がなかったため地域地域の地主などが新兵募集を募ったが、別にこの地主達も、なにかすごい扇動リーダーに扇動されていたわけではなかった。 だれかに指導されたわけでもなく、あらゆる階級の多数のものが男女問わず戦争に賛同し熱狂して戦争に協力していった。まるで熱病におかされたように。(農村部では都市部ほど熱狂的ではなかったようだが) フランスでは、開戦直前に、平和主義者のジャン・ジョーレスが戦争目前の雰囲気に興奮した青年によって射殺されてしまった。(資料2) |
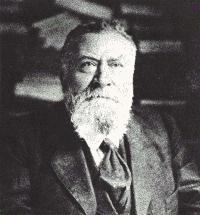 |
こんなやさしそうなおじいさんが殺されてしまうなんて・・・・ |
|
フランス軍部では、当初徴兵に応じないものが10%を越えるだろうと予想していたが、実際には1%あまりであった。イギリスでは志願兵を応募したところ志願兵が多数殺到した。志願兵など応召した兵が多く集まりすぎたためイギリス兵の新兵の多くは戦争初期に、銃の代わりに雨傘を使って教練を受けなければならないほどであった。(資料3) ドイツでは、今まで政府と対立していた反戦派であった社会民主党が、1914年8月4日に帝国政府の軍事公債案に賛成票を投じることによって(資料6)、戦争が終わるまで政府に政治的休戦を結び手のひらを返すように戦争に協力していった。いわいる「城内平和」(ブルクフリーデ)である。このときドイツ皇帝は大いに喜び、次のように言った。「もはや、政党というものはない、あるのはドイツ人だけだ。!!」 (資料4) |
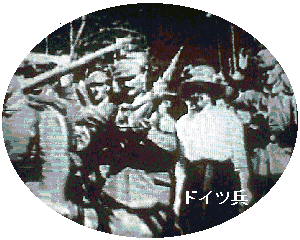


|
このドイツ社会民主党は、当時の国際労働者協会、第二インターナショナルの中心政党であった。 第二インターナショナルは、開戦以前は国際的な反戦活動を活発に行っていた。特にバルカン戦争の起こった1912年には急遽臨時でスイスのバーゼルで大会を開き、反戦決議などがおこなわれた。しかし、いざ第1次世界大戦がはじまると、この反戦決議に従がったのは、ロシアのボルシェヴィキのごとき亡命政党やイギリス独立労働党のような政治的影響力のすくない少数党のみしかなく、先に示したドイツ社会民主党と同様に戦争に協力していった。(資料5)よって第1次世界大戦のはじまった年である1914年の8月にはウィンで大会を開く予定であったが実現しなかった。そして第二インターナショナルの活動は事実上休止してしまった。 |
 |
アムステルダム大会 |
|
私ははじめは、大衆の無教養がそのような戦争への熱情へと導いたと思ったのだがどうも調べていくうちにその考えが必ずしも当てはまらないように思えてきた。科学者、文化人などの知識層も盛んに戦争に熱狂的に参加していた。イギリスでは労働者階級よりホワイトカラーや中産階級の方が軍への志願率が多かった。(資料3)(割合ではなく絶対数は労働者のほうが多かったようだが)。考えてみればヨーロッパの知識層は列強の一員である。また列強の労働者といえども、列強の一員であって列強に支配された植民地の労働者とは違う。そしてヨーロッパ列強の平和がイコール世界の平和とはならない。なぜなら列強に支配され抑圧された人民が多数存在すること自体、真に平和とはいえないからである。そのような抑圧された植民地の人民にまで心を配らなければ、真の平和活動やヒューマニズムとはいえないのであろう。いかなる理由であっても相手が宇宙人でなく同じ人間であるかぎり、戦争という行動はヒューマニズムに反した行動である。 今日ではたぶんあたりまえになっていると思うそのような認識がたとい知識層といえども少数であったのだろう。実際に、第二インターナショナル内でも、植民地を多数支配する帝国主義を容認している風潮があったようだ。(資料6)非常に極端な見方をすれば、彼ら列強にとって植民地の人間は人間と見なしてなく、家畜と同様に考えていたため何の考慮もしなかったのかもしれない。そのような未熟なヒューマニズムでは、いざ戦争が始まるとアッという間に平和への理念が薄れ、ただ祖国のみという考えに変わってしまうのかもしれない。 また、開戦時において、ほとんどの人々は戦争はせいぜい数週間から数ヶ月で終わるという幻想を抱いていたようだ。そのような短期決戦の楽観主義も戦争賛同の熱狂をあおったように思える。 20世紀にはじまった一連の軍事的緊張、1898年のファショダ事件、1905年の第1次モロッコ事件、1908年のボスニア危機、1911年の第2次モロッコ事件、1912年のバルカン戦争などヨーロッパ列強の人民はたえず戦争へ緊張感を味わっされていた。もう、一挙に短期決戦で解決してやれと思ったに違いない。 だからといって、私はそのように情熱的に戦争に協力した人々を愚弄しているわけではない。戦争に協力した人々には、狭い意味での正義というものがあった。ドイツはロシア、フランスからの祖国包囲の打破、フランスは以前にドイツに奪われたアルザス=ロレーヌの祖国への復帰、イギリスはベルギー救済、とそれぞれ、個人的な私欲ではなく、他人のために行動を起こす奉仕の精神であり、非常に立派であり、ある意味で敬意に値する感情に思える。ただし、狭い意味でである。広い視野で眺めればやはり愚行となってしまうのであろう。それゆえそのような狭い意味とはいえ、純粋な奉仕精神をもつ貴重な人材がこの戦争によって多数失われてしまったことは、なんと表現したらよいのかわからないが、私は非常に惜しくむなしく感じてしまう。 戦争にはどういう分けかそのような小さな正義への奉仕を美しくみせる能力があるように思う。べつに偉いサンが我々をそそのかさなくても戦争はそうした自らの魅力で我々に誘いの手を差しのべていくように思える。 そして、一度殺し合いをはじめれば、「父のかたき」「息子のかたき」「母のかたき」「娘のかたき」「夫のかたき」「妻のかたき」「友のかたき」と仇が連続発生し、憎悪に満ちた、血で血を洗うの復讐劇が次々と続いていくようである。そのため戦争はますます、長期化していくのかもしれない。(復讐劇の連続性はこの時代に限らないようだが。たとえば日本の南北朝から戦国時代の歴史を調べてみると多数見つけられる。) (なお、戦争が長期化にしていくにつれて、各国の偉いサン達は新聞検閲や戦意高揚のプロパガンダ(宣伝)を盛んに行うようになる。人類はこの戦争によって、一連の大量殺戮戦争システムを徐々に形成して完成させていった。) さて、だいぶ偉そうな話を長々と書きつづってしまったが、最後に当時の兵士達の気持ちをつづった文を下記のように示す。 |
|
死んで帰るものは幸福である 太古の日々、太古の地球へ 正義の戦争で死ぬものは幸福である 実った麦と収穫した穀物のように幸福である(資料3) フランスの詩人、思想家 シャルル・ペギーの言葉 (彼は1914年8月に兵役を志願し、9月7日にマルヌの戦いで戦死する(資料2)) |
|
↓ドイツ兵士の手紙より(資料1) |
|
↓アドルフ・ヒトラー「我が闘争」より(資料1) (当時、彼は美実学校の受験に失敗し失業中であったが、開戦早々に志願兵として戦争に参加し、終戦直前に毒ガスで目を負傷するまで勇猛果敢に戦った。) |
|
↓従軍したオーストリア人作家ツバイク「昨日の世界」より(資料1)
|

|
|
参考資料 資料1 NHKスペシャル 映像の世紀 第2集「大量殺戮の完成」および第3集「それはマンハッタンから始まった」のナレーション 資料2 八月の砲声 バーバラ・W・タックマン著 山室まりあ 訳 筑摩書房 資料3 J・M・ウィンター 著 20世紀の歴史 第14巻 第1次世界大戦(下) 平凡社 資料4 A.J,P テイラー 著 倉田 稔 訳「第一次世界大戦」 ㈱新評論 資料5 社会科学大辞典 鹿島研究所出版会 資料6 日本と世界の歴史 第20巻 学研 |
|
BGMについて お聞きの曲(MIDIファイル)は私の作成した曲「大いなる幻想」です。(といっても、作曲というものではなく、他の人が作曲した曲をただ、組み合わせしたものですが。) 第1次世界大戦の開戦時の熱狂と挫折をあらわしたつもりです。(^_^;) 各部分的な曲の名などを紹介します。 前半部のブラスなどは、旧ドイツ帝国で国歌と同じようによく歌われてたと思われる曲とフランス国歌をはもらせて、各国の熱狂をあらわしました。後半部は「加古 隆」さんの作曲したNHKスペシャル「映像の世紀」で使われたスポット音楽を使用して挫折をあらわしたつもりです。 |