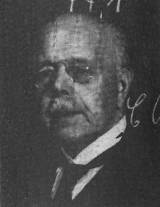|
|
(3webサーバー) |
(midiあり 3webサーバー) |
|
ご感想、ご要望等はこちらへ |
| アンモニア合成法の成功と
第一次世界大戦の勃発(1/3) (ほぼ原文+注釈)
|
|
原文著者=廣 田 鋼 藏
原文=現代化学1975年2月号に掲載
人類にとり重要な文化資産というべきアンモニア合成法はハーバーとボッシュにより完成された。通説はこの成功を第一次大戦の勃発の一因としているが、これが誤りである理由を紹介し、あわせてなぜこうなったかを説明する。しかし本法の成功がドイツに5年間の大戦を包囲下に可能とさせ、ハーバーへの不信の一因を生じている。この人類と祖国への両面への献身という、ハーバーの生涯については、次号に紹介する。
(いや、原文に”次号紹介する”と書いてあったからそう記載したまでで、今のところそれを紹介する予定はありません。(^_^;)>”) |
1913年にドイツのBASE社が完成した元素からのアンモニア合成法は、食料危機が叫ばれる現在(1975年当時のことです。(^_^;) )では、きわめて重要な化学工業となってきた。多くの日本の教科書・専門書などを読むと、このような平和的工業の誕生を第一次大戦の勃発と関連づけて紹介されている。たとえば大戦を予想してドイツ政府がその研究を援助推進したとか、研究の成功を知ってドイツ皇帝が開戦を決意したとかいう表現が珍しくない。さらに大戦開始後に、ドイツ軍指導部がF.ハーバーに研究着手を依頼し、その成果をC.ボッシュかたちまち工業化したという記載もある。したがってアンモニア合成法は、科学的研究が軍軍的要望によって支援され完成された好例としてたびたび引用されている。さらに進んで本法が、第二次大戦における原子爆弾の完成と、それから派生した原子力の平和利用に対比されるのも不思議ではない。
しかしこの説が誤りなことは、アンモニア合成注1の歴史を少し調べれぱ、直ちにわかる。それにしてもあまりにも多くの人の脳裡に通説がしみこんでいる。私はこの偉大なな文化的遺産の出生に対する誤伝を解き、正当な理解を与えるために、通説に反対する三つの理由を説明し、さらに何故このような事態が生じたか考察し、これが半ば意図的に作られた可能性さえ考えられる点を指摘したい。
注1
N2+3H2→2NH3(1)
なお、原文ではN2+3N2→2NH3となっていた。なんか無茶苦茶だな。どうして窒素の一部が水素になるの?たぶん出版社のミスでしょう。
1.アンモニア合成法の開発の背景(年代的反対理由)
本法は、種々ある空中窒素固定法の一つとして1904年に発表され、やがて本命として発展され、大戦勃発のちょうど一事前に工業化された。この点を年代的に詳しく述べて、通説に対する消極的の反対理由としよう。
19世紀末の欧州は、重大さと困難さにおいて今日のエネルギー資源問題に比べられるテーマを抱えていた。(なお原文が掲載された時期は1975年なのでちょうど石油ショックのころです。だからこのような表現になったのでしょう。)それは需要の急増しつつあった窒素化合物入手対策としての、前述の空中窒素固定法であった。その原因は18世紀にイギリスに始まった産業革命が、19世紀には欧州大陸にまでも拡がったためである。その結果、農産物の生産が対応できぬ程の人口の激増と高いGNPに伴う土木業・鉱山業の発展とが生じた。
前者は人造肥料の、後者は火薬・爆薬の需要増加をきたし、両者は共通して含窒素無機化合物の供袷不足という大きな社会問題となってきた。その要望に応えて、人造肥料対策には、産業発展と共に生産された副生硫安がまず利用された。ついでチリ硝石が、1820年以来、欧州へ輸入されて不足を補い、さらに火薬類の原料としての要望に応じた。したがってチリ硝石の輸入量は漸次増加して副生硫安の生産量を抜き、その傾向は表1にみるごとく20世紀になっても続いた。
|
年度
|
チリ硝石 | ノルウェイ硝石 | 副生硫安 | 石灰窒素 |
|
1903
|
1,485,312 | 25 | 526,000 | - |
|
1904
|
1,559,087 | 550 | 575,000 | - |
|
1905
|
1,754,605 | 1,600 | 653,500 | - |
|
1906
|
1,822,144 | 1,600 | 751,000 | - |
|
1907
|
1,846,037 | 15,000 | 837,500 | - |
|
1908
|
1,970,974(1.23) | 15,000(1.51) | 893,000(1.19) | 15,000(1.11) |
|
1909
|
2,110,961(1.18) | 25,000(1.23) | 976,000(1.15) | 25,000(1.08) |
|
1910
|
2,465,415(1.13) | 25,000(1.22) | 1,100,000(1.23) | 50,000(1.05) |
|
1911
|
2,521,023(1.21) | 25,000(1.25) | 1,157,000(1.36) | 80,000(1.06) |
|
1912
|
2,584,470(1.37) | 不明(1.28) | 1,300,000(1.45) | 109,200(1.18) |
(下のグラフは上記表1をグラフ化したもの)
( この表のデータは、肥料に含まれる窒素の重量を表すのか、それとも、肥料そのものの重さを表すのか私にはわかりましぇん〜 (^_^;) )
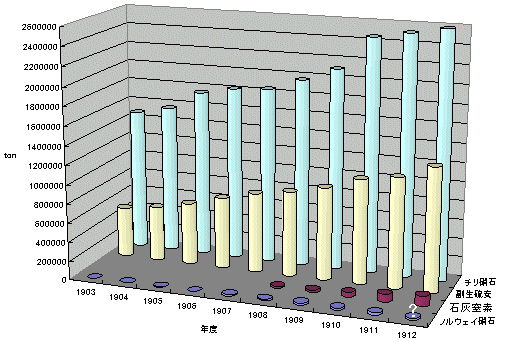 |
コークス・都市ガスなどの製造のために、石炭を乾留するとアンモニアが生成ガス中に含まれる。このガスを硫酸で洗うと、
2NH3+ H2SO4→(NH4)2SO4
の反応により硫安を生ずる。これを副生硫安という。
チリ硝石はチリに産する天然硝酸ナトリウムで、これを回収精製したものである。成因は、海鳥糞説・海藻堆積説・空中放電生成物説と種々あり、いずれにしても、その埋蔵量は急増する需要に比し、少ないと当時信じられた。チリ硝石から硝酸を作るには、複分解法によるが
2 NaNO3+H2SO4→NaSO4十 2HNO3 (2)
NH3+x02 → yHNO3 ( 3)
なお、古来火薬や花火に用いろ硝石は硝酸カリウムである。
19世紀末になると、需要の教増するチリ硝石が限りある天然資源であることから、その枯渇が心配されだした。1898年にイギリスのBristolで行われた大英学術協会の集会で、W.Crookes卿が行った有名な会長演説は、以上の危機を感知した人々の声を反映したものと思われる。彼は説いた;……今年はマルサスが「人口の原理」を出版してから満百年であるが、今や窒素肥料の不足のため食料不足の時代到来が迫っている、そのため彼が警告した事態が現実化する恐れあり……と。そして解決策として、無尽満というべき大気中の窒素をアンモニア・硝酸またはそれらの塩に、何らかの方法で変化させることを提案し、その研究の緊急性を強調した。
Crookes演説に刺戟されてか、1902年に空中電弧法がK.BirkelandとS.Eydeによりノルウェイで工業化され、1905年には石灰窒素法がA.FrankとN.Caroにより工業化された。しかし両者は共に多量の電力を消費するので、生産原価が高く、増産にも限度があった。その点は表1に示すごとくノルウェイ硝石および石灰窒素の登場によっても、1912年までチリ硝石の生産が頭打ちにならないことで示される。
空中電弧法とは、電弧の高温を利用し、空気中の窒素と酸素とを結合させて、まずNOを作り、つぎにこれを過剰の酸素で酸化してNO2(⇔1/2N2O4)とし、さらにこれを水またはアルカリに吸収させて硝酸または硝酸塩とする方法である。これを式で示せば
N2+O2→2NO, NO+1/202→NO2
2NO2+H2O→ HNO3+HNO2
で示される。肥科としては石灰塩が用いられ、 これをノルウェイ硝石という。
| 石灰窒素法は炭化カルシウムを加熱して窒素を通ずると、つぎのごとく窒素吸収が生ずる反応を利用する
CaC2+N2→CaCN2+C この反応は発熱で自発的に進行するが、原料たるCaC2の製造に多量の電気を必要とする。石灰窒素CaCN2に過熱した水素気と反応させ、アンモニアを製造できる。 したがって空中窒素固定の新方法の登場が要望された。これに応えたのが、アンモニアを元素から直接に合成する可能性を示したハーバーの研究であった。これは1000℃という高温で、ごく微量のアンモニアの生成を報告したのだが、彼の発表はきわめて注目を集めた。しかしW.ネルンストによって彼の発表した値が大きすぎるとの指摘があったりしたが、高圧炉の採用や適当な触媒(Os(オスミウム))の発見があり、1909年7月には実験室プラントが運転され、初めて液状アンモニアを製造できた。これを引継いだBASF社は、ボッシュが責任者となって工業化にかかり、1913年9月にはOppauに日産10tonの本工場の運転開始にこぎつけた。これに至るには、高温高圧に耐える反応炉の製作、工業用触媒の発見、多量の原料ガスの製造を初め、多くの技術的問題の解決が必要であった。多くの専門書にその困難の克服が詳しく紹介されているが、これを読めば、何故1904年から10年を要して工業化が成功したかわかるであろう。
|
|