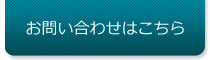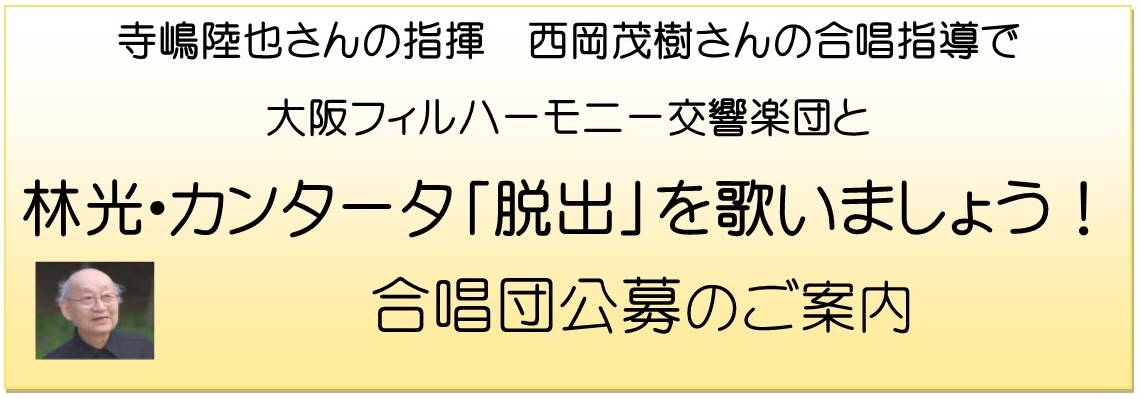大阪音楽教育の会2015年10月例会での練習(ピアノ・寺嶋陸也氏)
練習の録音を共有する方法の一つのテストとしてアップしたものです。ご参考までに。
大阪音楽教育の会2015年10月例会での練習
大阪音楽教育の会2015年10月例会での練習(googleドライブ)
練習録音の配信について
カンタータ「脱出」2016合唱団の大阪練習は、練習参加者などに練習日の2-3日後をめどに練習録音を配信しています。録音はホームページからgoogleドライブにアップロードしてある音源をダウンロードして聴いていただけます。なお、ホームページ等の容量の関係で、一定期間がすぎると録音を非公開にしますので、あらかじめご承知おきください。
練習日程表(5/17現在)
練習日程は、次のとおりです。
今後、日程や会場、開始・終了時刻などが変更されるかもしれません。
4/16の寺嶋氏による練習の会場を、大フィル会館・メインホールから都島区民センター内のホールに変更しました。
また、音楽教育の会全国委員会参加者および豊中混声合唱団との特別合同練習①-1を追加しました
さらに、5/6の第8回定期練習は寺嶋練習③に、6/12の休日練習4回目は寺嶋練習④になりました。
| 練習名 | 日時・曜日 | 会場 |
| 定期・休日練習① | 1月24日(日) 13:00-16:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習② | 1月29日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館3階 |
| 定期練習③ | 2月 5日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館3階 |
| 定期練習④ | 2月19日(金) 18:30-21:00 |
大阪市内(後日案内) |
| 定期練習⑤ | 3月 4日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館3階 |
| 休日練習② | 3月20日(日) 13:00-16:00 |
大阪市内(後日案内) |
| 定期練習⑥ | 4月 8日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 寺嶋氏による練習①-1 | 4月16日(土) 17:30-18:30 |
都島区民センター(追加!) |
| 寺嶋氏による練習①-2 | 4月16日(土) 18:30-21:00 |
都島区民センター(会場変更!) |
| 寺嶋氏による練習② | 4月17日(日) 13:00-16:00 |
大阪市内(後日案内) |
| 定期練習⑦ | 4月22日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館3階 |
| 定期練習⑧(寺嶋練習③) | 5月 6日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 休日練習③ | 5月15日(日) 13:00-16:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑨ | 5月20日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑩ | 6月 3日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 休日練習④(寺嶋練習④) | 6月12日(日) 13:00-16:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑪ | 6月17日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑫ | 6月24日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑬ | 7月 1日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑭ | 7月 8日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑮ | 7月15日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| ソリスト・ナレーター合わせ | 7月17日(日) 13:00-16:00 |
大フィル会館ホール |
| 定期練習⑯ | 7月22日(金) 18:30-21:00 |
大フィル会館ホール |
| オケ合わせ① | 7月26日(火) 18:30頃-(18:00スタンバイ) |
大フィル会館ホール |
| オケ合わせ② | 7月27日(水) 18:30頃-(18:00スタンバイ) |
大フィル会館ホール |
| ゲネプロ | 7月28日(木) 16:00-17:30(15:00スタンバイ) |
ザ・シンフォニーホール |
大阪練習レポートその2 ③2/5 ④2/19 練習 (第5,6,7,8,9章)
歌い出だしが大事 「いつも明るく元気」ではなく音色に注意

歌う前の体づくりは自分で欠かさずに
 ③と④も、前号で紹介した歌う前の体づくりの準備運動が行われましたが、西岡茂樹さんはその時間をだんだん短くされてきています。練習の際や日常で習慣化してほしいとの思いからでしょう。
③と④も、前号で紹介した歌う前の体づくりの準備運動が行われましたが、西岡茂樹さんはその時間をだんだん短くされてきています。練習の際や日常で習慣化してほしいとの思いからでしょう。
①の練習の際に、西岡さんが指揮を学んだ田中信昭さんが「野口体操」をアレンジされたことが紹介されていましたが、後日、事務局に『絶対!うまくなる 合唱100のコツ』で田中さんがいろいろな準備運動を解説さているとお知らせいただき、早速購入しました。この場で紹介します。
ヤマハミュージックメディア2014年7月発行、A5判144ページ、1,728円。
聴衆に歌詞を誤解させない 曲に応じた音色で歌おう
③は、いきなり初めて歌う第5章「引き裂かれた愛の歌(1)」に取り組みました。そこで注意されたのは、歌の出だしと音色の大切さ。日本語の歌は、出だしの音が曖昧で「だらっと歌い出す」ことがよくあるが、頭の音をはっきり出そう。また、歌詞の内容にあった音色で歌おう、と。
「歌詞に合った音色で歌いましょう。悲惨な出来事の歌詞を明るい音色で歌うと聴衆は一瞬で誤解してしまう。それは演奏者の責任です」
また、音量についても注意がありました。「ユニゾンから4声に分かれる時には大きく、逆にユニゾンに戻るときには小さく歌う。これは合唱の基本です」
④は、第9章まで練習を進めました。ここでも、音色の大切さについての注意がされました。①の練習時から、母音、とくに「あ」母音に注意するようにと指摘されていました。
保育園や小中学校で「いつも明るく元気で」を基本にして歌を歌ったり教えたりしている参加者が多いせいか、この注意は毎回の練習で繰り返されています。身についたものを変えていくのはなかなかできないことなのかもしれませんが、少しずつ歌声が変ってきているのも事実です。
合唱練習を楽しくする西岡ユーモア
こうして紹介すると、西岡さんは合唱団に注意ばかりしているように映るかもしれませんが、時折というよりも絶えず駄(?)洒落を挟んで、合唱団の皆さんから笑いを誘いながら、楽しく練習を進められています。練習時は受付にいて録音をもとにレポートを書いている私には、西岡ユーモアは完全には伝わっていないのかもしれませんが、録音を聴いていても時々ふきだしてしまいます。ぜひ練習に参加して会場で直に聴いてください。私もいいレポートを早く書けるように、ぜひそうしたいと思います。
大阪練習レポートその1 ①1/24 ②1/29 練習 (第2,3,4章)
寺嶋さんからは「内容が伝わる演奏に」 まずは「歌詞を徹底的に読む」

歌に向かう体づくり
①と②とも、歌う前に行われた「歌に向かう体づくり」は次のとおりです。(録音から事務局で文字化)
・ 立って足の10本の指を順番に意識する。1本ずつ地球をトントンする。座った時も同様。海藻のように海の底からぶらぶらと「ぶら上がる」。でんでん太鼓のように体を左右に振る。
・ 首をリラックスさせて糸の切れた操り人形のように前後、斜めに垂らす。肩の上で転がす。
・ 頭蓋骨を開いて脳に澱んでいるものを外に開放し、かわりに宇宙から新鮮なものを取り入れることを意識する。
・ 「お粥さん体操」 体をお米の少ないお粥さんにしてしまう。イメージしやすいように、まずは右手親指から一本ずつ。指の中にお粥を入れていき、お粥の中で小骨がぷらぷら浮いているのをイメージする。左手親指、右手人差し指、・・・。指をお粥と入れ替えていく。目は開けておく。次は手のひら、手の甲、手首も。暗譜で歌うならこの状態が望ましい。上腕部、腕のつけ根、胸、首、顔、鼻、目、耳の奥もお粥が生きいきと巡っているのをイメージすると、緊張が解れる。
・ 「野口体操」 西岡さんが指揮を学んだ田中信昭氏がアレンジした頸椎や胸椎の継ぎ目をマッサージする方法。まずは、目。顔の前15cm位に壁を感じて目を壁にスリスリする。次は目の後ろ。そして、鼻、口、顎、喉、喉と乳の間、乳、みぞおち、胃、臍、尻と続ける。最後には夜店で売っている蛇の玩具のように下から蹴り上げるよう体を伸ばす。
・ 薄手の紙を三角形になるようにして持ち、鼻の前に当て、息で紙がヒラヒラするのを確かめる。紙の動き方が一定になるようにすることで横隔膜のコントロールのしかたを意識できる。
楽譜の巻末の歌詞を「読む」こと
①では、西岡さんは「寺嶋さんから内容が伝わる演奏にしたい」と言われており、そのためには歌詞を徹底的に「読む」ことが大切と指摘。歌詞は普段使っている言葉で書かれ誰でも簡単に読めるが、それはむしろ危険。何度も読み、どうすれば内容が伝わるか考える。それには楽譜巻末に掲載されている漢字交じりの歌詞が役立つ。歌詞の朗読は、歌につながる朗読が必要。詩の修辞や言葉の繋がりも考えてほしいと。朗読では伝えられても歌うと変わりがち。母音とくに「あ」母音に注意して、聴く人に歌詞の意味を誤解させないようにしてほしいと。
歌の方向を合わせていこう
②では西岡さんは第3章について、「うさぎ狩りの情景が聴く人の脳裏に浮かぶかどうか、それを音楽で表現する。とても重要な章です。どうすれば伝わるか考えていきましょう」と述べられました。また「皆さん伝えたいという思いをお持ちです。今は声を合わせるよりも、歌の方向を合わせていきましょう」とも。