|
|
|
|
![]()
ホストサロン。.... 佐久間學
これはまさに「日記」、著者のマイルズが、「ザップル」が出来てから消滅するまでの、その日その日に起こったことをざっくりと書き綴ったものですが、そこに、その後の文献からの引用が多数挿入されているのが「記録」としての価値を上げています。日本で出版されたものには、その出版元もきちんと併記されているのも、とても親切。 このレーベルの最も近いところにいた人の書いたものですから、事実関係は詳細を極めていますが、それは殆どマイルズの本来のフィールドである文学的な仕事に関するもので、正直それほどの興味はわきません。ただ、その隙間を埋めるかのようにちりばめられた、「ザ・ボーイズ」(ビートルズのメンバーたちを、彼はそのように読んでいます)のエピソードは、かなり新鮮なものでした。ポールにしてもジョージにしても、とにかくお金に関してはやたら気前がいいのですね。 ジョンに関しては、ヨーコとの絡みが赤裸々に語られています。そこで暴露されるのが、ジョンの「アヴァン・ギャルド」に対するスタンスです。世間一般の受け止め方では彼はそのような芸術に理解を持っている人とされているのでしょうが、実際には彼は「アヴァン・ギャルド」への関心もスキルも全くなかったことが、ここでは明らかにされています。それは単に、ヨーコへの憧れのようなものだったのでしょう。 そのヨーコの「バックバンド」として参加した時に、彼が行ったパフォーマンスに関しての言及には、笑えます。彼は、ヨーコの「前衛的」なパフォーマンス(実体は、ただ意味のない悲鳴を上げていただけ)に合わせて、ギターアンプの前にギターを持って行ってジミ・ヘンドリックスのような(ですらない)ハウリングを出していただけだったというのですからね。 そんなものをA面に収録したアルバムが、1969年5月にザップルから最初にリリースされた「Life with the Lions」(Zapple 01)でした。そして、同時に「Zapple 02」という品番でリリースされたのが、ジョージの「Electronic Sound」というアルバムです。実は、このアルバムに関する部分が、最も興味深く読めてしまいました。 日本盤は確か「ジョージ・ハリスン/電子音楽の世界」みたいな大げさなタイトルだったように記憶していますが、実体は、その頃発表され、あの冨田勲も購入した「モーグIII」というモジュラー・シンセサイザーを演奏していただけなのですがね。そんな、なぜジョージがこの「楽器」に興味を持ったか、そして、それを購入する顛末、さらには、このアルバムに収録されている「作品」の出自(半分は別の人が演奏したもの)などが、ここでは事細かに語られていますよ。 この時には、音を出すこともできなかったジョージは、後に「Abbey Road」の中の「Because」では、モーグIIIのソロを披露できるまでになっていたんですね。でも、この件については新たな検証が必要なのかもしれません。この本によると、ジョージ(・ハリスン)より先にジョージ・マーティンも同じシンセを購入していたそうですから。 Book Artwork © Kawade Shobo Shinsha, Publishers |
||||||
でも、中には「歌を歌う」ということがどういう意味を持っているのかをしっかり認識していて、とても素晴らしい「声」でその音楽をきちんと伝えてくれる人もいます。そんな中で、最近特に気に入っているのがSuperflyです。だいぶ前からその声は耳にしていたような気がしますが、はっきり彼女だと意識して聴くようになったのは2012年の「輝く月のように」あたりからでしょうか。テレビドラマの主題歌として使われていましたね。 それは、曲自体もとてもキャッチーなメロディを持ったものでしたが、なんと言っても彼女のヴォーカルの素晴らしさには感服させられました。特に、伸びのあるハイトーンは魅力的です。それはまさに理想的な声でした。 それ以来、彼女の声はたまたまラジオなどから聴こえてきても、すぐ分かるようになりました。本当に好きな人の顔なら、どんなに遠くからでも見分けられる、そんな感じでしょうか。ですから、すでに何枚かリリースされているアルバムをなにか買って、しっかり聴いてみようと思いはじめていました。 そんな矢先に、タイミングよくこんな「オールタイム・ベスト」が発売されました。それは3枚組ですから、ちょっと全部聴くのはしんどいな、とは思いましたが、結局全39曲は届いたその日に聴き終わっていましたね。 蛇足でしょうが念のため、Superfly(スーパーフライ)というのは、元々はユニットの名前だった、という知識も付け加えておきましょうか。2007年にメジャーデビューした時点では、メンバーはヴォーカルの越智志帆とギターの多保孝一の、共に愛媛県今治市出身者の2人でした。今回のベストアルバムは、「デビュー10周年」を記念してのものです。その後田保はユニットを脱退、Superflyは越智一人のソロ・ユニットとなります。田保は、アーティストではなく、コンポーザー/アレンジャーとしてSuperflyに関わる、という体制に、その時変わっていました。さらに、プロデューサーとして蔦屋好位置(変換ミスではありません)も深く関わっています。 ですから、殆どの曲のクレジットは作詞/越智志帆、作曲/多保孝一、編曲/蔦屋好位置となっていますし、蔦屋はキーボード奏者として録音メンバーに加わっています。 このベストはCD3枚組、なんでも、曲の選択にはファンからの人気投票が反映されているのだそうです。それらを、「LOVE」、「PEACE」、「FIRE」という3つのカテゴリーに分類して、それぞれ13曲が1枚のCDに収録されています。中には、そのカテゴリーではちょっと無理があるだろう、という曲もありますが、彼女の音楽には須くこの3つの属性が含まれていて、その表出の多寡がこの分類となったのだと思えば、それは全く気にならなくなります。彼女の歌からは、常に「愛」と「幸せ」と「情熱」が聴こえてくるのですから。 ブラスやストリングスが加わった分厚いサウンドでギンギンに迫るものから、彼女が作曲まで手掛けてピアノの弾き語りだけでシンプルに歌い上げるものまで、それこそ彼女が好きだというジャニス・ジョプリンからキャロル・キングへのリスペクトを、極上の声で味わうことができる素晴らしいアルバムです。金曜日の黄昏時には、お似合い(それは「スーパーフライデー」)。 CD Artwork © Warner Music Japan Inc. |
||||||
宗教曲でも大活躍、ラトル/ベルリンフィルと共演した「マタイ」と「ヨハネ」にも参加していましたね。 ソロ・アルバムとしては、このBISレーベルにR.シュトラウス(2008年)、シューベルト(2010年)、北欧の作曲家(2014年)と、3枚のリート集を録音していました。ほぼ2年のインターバルでそれらに続いてリリースされたのが、この2015年10月に録音された、グルックとモーツァルトのオペラ・アリア集です。もちろん、ピアノ伴奏ではなく、バックにはオーケストラが付きます。 そのオーケストラは、「ムジカ・セクロルム」という、初めて名前を聞いた団体です。「セクロルム」というのは麻酔薬ではなく(それは「クロロホルム」)、ラテン語で「100年」、転じて「とこしえに」みたいな意味を持つ言葉です。オーケストラとともに合唱も併設されていて、宗教曲などにも対応できるフォーマットを持っている、ピリオド楽器のアンサンブルです。設立したのは、このCDでの指揮者、フィリップ・フォン・シュタインエッカーですが、その時に共に設立にあたったのが、彼の妻でフルーティストのキアラ・トネッリです。シュタインエッカーはかつてはチェリストとしてマーラー室内管弦楽団の首席奏者を務めていましたが、トネッリもやはりそこの首席フルート奏者、もちろん、ムジカ・セクロルムでも一番フルートを吹いています。 イタリアの南チロルを本拠地とするこのアンサンブルは、そんな、ヨーロッパ中の若くて実力のある演奏家が集まっていて、ピリオド楽器だけでなくモダン楽器での演奏も行っています(2013年には、ケルンのフィルハーモニーでブルックナーの「交響曲第1番」を演奏しています)。 まずは、このアルバムの幕開けということで、モーツァルトの「イドメネオ」序曲が、このオーケストラだけで演奏されます。それには、なにかとても新鮮な印象が与えられました。それは、かつてアーノンクールやノリントンといったちょっと前のピリオド系の指揮者の演奏を聴いたときの「新鮮さ」とはまるで異なる、「驚きを伴わない新鮮さ」でした。注目のトネッリのフルートも、少し明るめのピッチで吹いているのでしょう、ピリオド系のオケを聴いた時にいつも感じる、この楽器が全体の中に埋もれてしまうということは全くなく、とても目立って聴こえてきます。 このCDでは単なる「アリア集」とは違って、オペラの中ではそのアリアの前に演奏されるレシタティーヴォがまず歌われています。これは、特に「イドメネオ」のようなオペラ・セリアの場合はオーケストラの伴奏もしっかり書かれているパーツですから、そこでもこのオーケストラの豊かな表現力がしっかり味わえることになります。もちろん、アリアでのオブリガートも素晴らしいものばかり、「コジ・ファン・トゥッテ」第2幕のフィオルディリージのアリア「Per pietà ben mio perdona」でのホルンなどは格別ですね。 そして、ティリングの歌は完璧でした。とてもナチュラルで伸びのある声は、まるで砂漠のオアシスのように素直に心の中に沁みこんできます。コロラトゥーラも全く破綻のない鮮やかさ、なんの不自然さも感じることなく楽しめます。グルックではフランス語で歌われているものも有りますが、その発音もとてもかわいらしく響きます。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
この「マタイ」は、2007年の初演の模様がライブ録音としてリリースされていますが、それを今回はスタジオ録音で再録したのでしょう。指揮者は初演の時と同じフェドセーエフです。 この不思議な人のイメージが全く湧かなかったので、まず、彼自身が指揮までやっているアルバム(PENTATONE)を聴いてみました。 そこでは、合唱曲だけでなく、器楽曲も聴くことが出来ました。それは「合奏協奏曲」という、まるでバロック時代の作品のようなタイトルの曲でしたが、それはまさにバロックの巨匠たちの作品の完璧なパクリでした。通奏低音にチェンバロまで加わっているのですから、すごいものです。 この「マタイ」は、やはりバッハあたりの同名曲を下敷きにしているのでしょう。テキストはもちろん新約聖書のマタイ福音書から取られていて、最後の晩餐から埋葬までが4つの部分に分かれています。とは言っても、それはロシア語に訳されたものです。ブックレットには対訳はありませんが、一応英語でそれぞれのナンバーのタイトルは書いてあるので、内容はなんとなく分かります。 やはり、福音史家は登場、それはバリトンが担当していますが、ほぼその歌手のソロで歌われます。それはほとんど抑揚のない、まるで「お経」のようなものでした。そして、合唱やアリアも歌われます。バックのオーケストラは弦楽器のみの編成です。先ほどのソロ・アルバムでは、管楽器や打楽器も入ったフル編成の曲もあったので、オーケストレーションが出来ないのではなく、この曲にふさわしい編成として弦楽合奏を選んだということなのでしょう。 確かに、このモノトーンのオーケストラは、いたずらに劇的な盛り上がりを作ることは決してなく、ひたすら深いところからの悲哀、慟哭といった情感を表現してくれているようです。ただ、サウンド的にはとても抑制されたものであるのに、それが奏でる音楽にはかなり俗っぽい和声が使われているのが気になります。あまりに見え透いたコード進行で、とても心地よく聴こえる半面、その先には意外性というものが全くありません。 ソプラノ、メゾ・ソプラノ、テノール、バスの4人のソリストが、この曲の4つの部分に分かれた中でそれぞれ1曲ずつ歌っている「アリア」が、まさにそんなスタイルを最大限に駆使したものでした。それらは、一度聴いただけで虜になってしまうようなシンプルな中にツボを押さえたメロディが、クリシェ・コードの上で歌われるという、それ自体はとても安らかな幸福感が味わえるものです。ですから、ソプラノが歌う第3部の中の「アリア」などは、こんな立派な声ではなく、もっとピュアな声で聴きたいものだと、贅沢な不満まで持ててしまいます。 合唱でも、ア・カペラで歌われるやはり第3部の中の「35番」などは、まさに完璧な美しさで迫ってくるものでした。 ところが、最後の「48番」で聴こえてきた合唱には、言葉を失いました。それはなんと、あの「カッチーニのアヴェ・マリア」ではありませんか。今では、この「迷作」はさるロシア人が20世紀に作曲したものであることは広く知られていますが、この、21世紀にやはりロシアの「自称作曲家」が作った2時間に及ぶ大曲は、それとまったく同じ精神を持っていたのでしょう。とんでもない駄作です。あんたは木でも切ってなさい(それは「与作」)。 CD Artwork © Metropolitan Hilarion (Alefeyev) |
||||||
ただ、その作品のタイトルが「アンタール」というのに、ちょっと引っかかりました。スラブ舞曲ではありません(それは「アンコール」・・・ニューフィル限定)。これは、リムスキー・コルサコフの「交響曲第2番」のサブタイトルとして、記憶にありました。実はこの曲は実際に演奏したことがあり、その楽譜の改訂についてもかなり詳しく調べたこともあったのです。その成果はこちらです。ついでにこちらの曲目解説も。 そこで改めてこのCDでのタイトルを見てみると、そこには「Antar - Incidental music after works by Rimsky-Korsakof」とあるではありませんか。つまり、これはまさにそのリムスキー・コルサコフの「アンタール」を元にした「劇音楽」だったのです。 1907年に、仲間内のコンサートで友人のピアニストと一緒に「アンタール」のスコアを初見で演奏して以来、この曲の魅力に惹かれたラヴェルは、1910年に、この曲を素材とした4幕の劇音楽を上演していたのですね。しかし、そのスコアは出版社の許に保存はされていましたが、出版されることはありませんでした。さらに、その時のテキストも残っていなかったので、スラトキンが2014年に初めて録音した際には、この音楽はコンサート用に再構築され、そこでは新たに作られたテキストが朗読されています。 なんたって「初録音」ですから、これは今までに誰も聴いたことのない音楽です。それを聴くにあたってまず参考にするのは、基本は英語で書かれたライナーノーツでしょうが、手っ取り早いのは日本の代理店が作った「帯解説」でしょう。これを日夜作成している方々は、まずはこのCDを聴き込み、そしてそのライナーノーツを隅々まで読み込んだ上で、初めて聴く人がその作品に容易にアクセスできるような情報を的確に作成する技を熟知しているはずですからね。それは、こういうものでした。 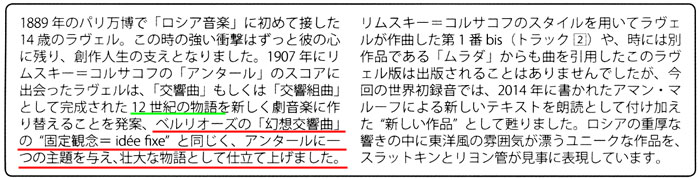 そして、もっとまずいのは、赤線の部分を読むと、まるでラヴェルがベルリオーズのコンセプトを借用したように思ってしまえること。それは完全な間違いです。ライナーノーツには確かにそのような記述はありますが、それはオリジナルのリムスキー・コルサコフの作品に関しての言及なんですからね。 問題なのは、これを読んでこの曲を聴いた人が、最初に聴こえてくるまぎれもないリムスキー・コルサコフの「アンタール」の第1楽章を、ラヴェルの作品、あるいは、ラヴェルが手を加えたものだと思ってしまうことです。ここには、リムスキー・コルサコフの「交響曲第2番『アンタール』」第2稿の全曲がそのまま(第4楽章の冒頭は第1楽章の引用なのでカット)と、同じ作曲家のオペラ「ムラダ」の一部、そして、やはり同じ作曲家のモティーフにラヴェルがオーケストレーションを施したものしか含まれてはいないのです。 残念なことに、この帯解説を書いた人は、まず正確な情報を伝える文章力を学ぶ必要があるようです。 そもそもこういうものをラヴェルの管弦楽作品として録音した時点で、NAXOSそのもののいい加減さも露わになっています。これだったら、ナレーションがかぶっていないオリジナルのリムスキー・コルサコフのCDを聴いた方がよっぽどマシなのでは。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |
||||||
この1962年に録音された「トスカ」も、そのように当初はRCAの「ソリア・シリーズ」という超豪華な装丁が売り物のパッケージとして販売されました。日本ビクターから発売された国内盤も金箔押しでそりゃあ豪華なパッケージでした。その翌年に録音された「カルメン」も、やはり「ソリア・シリーズ」で販売されています。その後、RCAとの提携が切れると、DECCAが提供した原盤(1/2インチ、38cm/secのマスターテープ)はほとんどが返還されますが、この「カルメン」だけはRCAの所有となっていて、それはこちらのように2008年に日本でSACD化されました。 そして、「トスカ」の方がやっと、こちらは24/96のBD-Aで、ハイレゾのパッケージが発売されました。「カルメン」のSACDには衝撃を受けましたから、それとほぼ同じ時期のこの「トスカ」に期待するのは当然のことです。 しかし、そのBD-Aから、前奏曲での金管楽器の彷徨が無残にも歪みまくった音で聴こえてきたとき、その期待はもろくも崩れ去りました。そこでは、天才エンジニア、ゴードン・パリーの作り出したあの豊饒なサウンドが、完膚なきまでに破壊されていたのです。その後、音楽が静かになってくると、かろうじてその繊細なテクスチャーは感じられるようになります。ソリストも同じこと、プライスやステファノの声ではそれほど目立たないものの、タッデイのバリトンでの歪みは寛容の限界をはるかに超えるものでした。 こうなることは、だいぶ前から予想はしていました。こちらに書いたように、1960年前後に録音されたマスターテープは、もはや現在では(というか、2009年の時点で)劣化が進んでいて使い物にならなくなっているのです。その頃録音されていたショルティの「指環」が今でもまともに聴けるのは、幸運にも1997年にデジタル・トランスファーされたものが残っていたからなのです(文中ではそのフォーマットが「24/48」となっていますが、現在販売されているハイレゾ・データは「24/44.1」のようです)。象徴的なのは、第2幕でトスカによって歌われる有名な「Vissi d'arte, vissi d'amore(歌に生き、恋に生き)」です。以前CD化されていたものと比較してみると、今回のBD-Aではそのアリアの8小節目「Con man furtiva」の頭で、明らかにテープをつないだ跡が聴こえます。おそらく、今回のトランスファーの時には、ここははがれてしまっていたのでしょう。 ただ、先ほどの「カルメン」では2008年にトランスファーが行われていても、そんな目立った歪みは感じられませんでした。保存や管理の状態で、個々の原盤の劣化の程度は異なっているのでしょうね。なんせ、この「トスカ」のマスターテープは何度も大西洋を横断していたのですから。 その時のプロデューサーのジョン・カルショーの著作によると、今のようにマルチトラックのレコーダーが使えなかった時代なので、カヴァラドッシが処刑される時の銃声などは、ダビングでの音の劣化を避けるために演奏しているのと同時に録音していたのだそうですが、タイミングが合わなくて何度もやり直したのだそうです。そんな苦労もすっかり水の泡ですね。 正直、マスターテープの劣化がこれほどのものだとは知りませんでした。貴重な「文化遺産」が、ダメになりかけています。もう手遅れかもしれません。 BD Artwork © Decca Music Group Limited |
||||||
そこでは、「1番」はニ長調のK.285、「2番」はト長調のK.285a、「3番」はハ長調のK.285b、「4番」はイ長調のK.298と、1777年から1778年にかけての作品群とされていました。ただ、この中で自筆稿が残っているのは「1番」と「4番」だけで、その他の作品は正確な作曲年代も、さらにはモーツァルト本人が作ったものであるのかも疑問がもたれています。実際、「4番」に関しては使われた紙の鑑定とか、この曲の中で引用されている作品(すべての楽章に「元ネタ」があります)が作られた年代などから考えて、もっと後期、1786年に作られたのではないか、という説が有力になっていました。 それでも、相対的な順番は変わらないので、この番号自体はそれなりに意味のあるものとして、長年使われ続けていたのですね。ところが、今回の2016年3月に録音されたばかりの最新のアルバムでは、曲の並びが番号順ではありませんでした。「1番」、「2番」、「4番」、「3番」と、後半の2曲の順番が入れ替わっていたのです。別に、CDの曲順は作曲順に従わなければいけないという規則があるわけではなく、聴いた時の心地よさなどを考慮して順番を入れ替えるようなことはザラにあるので、これもそんなものかな、と思ったのですが、ライナーノーツを読んでみると、実際に「3番」の方が「4番」より後に作られていたと、そこでは述べられていたのです。 その根拠は、この曲の第2楽章。これは、1781年に作られた有名な12の管楽器とコントラバスのためのセレナーデ「グラン・パルティータ」(K.370a)の第6楽章の変奏曲と全く同じもの(調は違います)なので、かつてはこのフルート四重奏曲がその原曲だと思われていて、それ以前の作品だということになっていたのですが、どうもそれは違っていたようなのですね。現在では、この四重奏曲は1786年か1787年に作られたという説が有力なのだそうです。しかも、この曲の自筆稿も存在してはおらず、わずかに第1楽章のスケッチが残っているだけでしたから、それを元に、モーツァルト以外のだれかがその楽章を作り、さらに第2楽章としてセレナーデの変奏曲を「編曲」して付け加えたのだ、とも言われていますからね。まあ、世の中、研究が進むと知りたくなかったようなことまで明らかになってしまうというのは、よくあることです。 ここでフルートを演奏しているのはリサ・フレンド、まるでモデルのような金髪の美人です。アメリカでルネ・シーバート(ジュリアス・ベイカーが首席の頃のニューヨーク・フィルの2番奏者)、イギリスでスーザン・ミラン、フランスでアラン・マリオンに師事したという、華やかな経歴を持っています。多くのオーケストラと共演したこともありますし、なんでもライザ・ミネリとの共演、などというすごいことまでやっているそうです。 ただ、この四重奏曲の録音を聴くと、なんとも雑な印象が残ります。とても軽やかでキラキラした独特のセンスは持っているのですが、いまいち詰めが甘いというか、なにか肝心なことが抜けているのではないか、という気がしてしまうのです。一番気になるのがピッチの悪さ。特にフレーズの終わりで常に音が低めになってしまうという癖が結構目立ってしまいます。ソリストとしてコンチェルトを吹きまくる分にはそんなに目立たないのかもしれませんが、このようなアンサンブルではそれは致命的です。知名度も高い曲ですし。 CD Artwork © Chandos Record Ltd |
||||||
2005年にバイエルン放送合唱団の芸術監督に就任したダイクストラは、2007年にはスウェーデン放送合唱団の首席指揮者にも就任、その他のヨーロッパの多くの合唱団とも深い関係を持って、大活躍をしてきました。しかし、2016年には、バイエルン放送合唱団のポストはイギリスの合唱指揮者ハワード・アーマンに譲り、10年以上に渡ったこの合唱団との関係にピリオドを打ちました。この「ロ短調」は、2016年4月に行われたコンサートのライブ録音ですから、彼の芸術監督としてのほとんど最後の録音ということになるのでしょう。 共演は、おなじみコンチェルト・ケルンです。ダイクストラは、この合唱団との初期の録音ではモダン・オーケストラであるバイエルン放送交響楽団との共演で「マタイ」を録音していましたが、最近ではバッハはピリオド・オーケストラで、というスタンスに変わったのでしょうね。かといって、ありがちな少人数での合唱という形は取らず、あくまでフルサイズの合唱で少人数のピリオド・アンサンブルと対峙する、という姿勢は堅持しています。 この「ロ短調」の場合、写真で見る限り、合唱団はほぼフルメンバーの45人ほど、それに対して弦楽器は全部で14人というオーケストラですから、バランス的には合唱がかなり多いという感じです。ピリオド楽器は、それ自体音も小さいですし。ですから、おそらくダイクストラはそのような形での合唱の在り方には、かなりな慎重さをもって演奏に臨んでいたのではないでしょうか。そして、その結論めいたものが、この録音からはしっかり感じられるような気がします。 それは、極限まで磨き抜かれたホモジーニアスな響きとなって現れています。冒頭の「Kyrie」のアコードで聴こえてきたのは、そんなあくまで各パートが均質な塊となったまさに大人数の合唱団としては理想的なサウンドでした。そこからは、「個」としてのメンバーたちの声は全く感じられません。これは、例えば最近聴いたガーディナーのモンテヴェルディ合唱団の姿勢とは対極にあるものなのではないでしょうか。 正直、それはうっとりするような美しさを持ってはいますが、なにか訴えかける力には欠けているような気がしてなりません。おそらく、それはダイクストラがバッハに対して抱いているイメージの反映なのでしょう。これはこれで、一つのすばらしいバッハのあり方です。ですから、この合唱団が「Et resurrexit」でのベースの長大なパートソロをどのように歌うのかとても興味があったのですが、ダイクストラはそこをソリストのアンドレアス・ヴォルフに歌わせていましたね。 他のソリストでは、テノールがケネス・ターヴァーというのが目を引きました。彼はモーツァルトのオペラのロールでは、まさに理想的な声を聴かせてくれていましたから、バッハではどのような姿を見せてくれるのは、期待が高まります。しかし、彼の「Benedictus」は、そんな期待に必ずしも応えてくれたものではありませんでした。まず、フルートのイントロがあまりに雑、というか、そもそもテンポが速すぎて、ターヴァ―はちょっと歌いづらそう。彼自身の歌も、ちょっと甘さが勝っていてバッハには合っていないような気がします。 トランペットの3人は、これもダイクストラのコンテクストに従ってのとても爽やかなアクセントを提供しています。これも、そもそもこの曲にふさわしい振る舞いなのかは、なんとも言えません。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH. |
||||||
デビュー当時は男声5人だけだったのですが、そこに女声が一人加わって6人編成となります。その後、男声が一人減って、現在では女声1、男声4という5人編成になりました。女声が一人いることでサウンド的には無理なく高音まで音域が広がって、とてもソフトな音色が得られるようになっています。このあたりが、「キングズ・シンガーズ」との違いでしょうか。 今回のアルバムのジャケット写真を見て、いつの間にかみんな年を取ったな、という思いに駆られました。最初に買った、まだQUERSTANDからリリースされていたアルバムの写真(左)と比べると、ほとんど別人のようになっている人もいますね。昔は左端、今は真ん中のカウンターテナーのクラウゼとか(昔は頭が黒いぜ)。  ただ、他の4人も、創設メンバーはクラウゼとバリトンのベーメ(右端)の2人だけ、テナーのペッヒェは2006年に加入しています。彼はソプラノのアニャ・リプフェルトと「団内結婚」(どちらの写真も並んでいます)、2010年と2016年にはお子さんも生まれています。その間彼女は産休を取り、別のソプラノがメンバーとなってアンサンブルの活動は続けていました。どんなグループでも、いろいろと出入りがあるものですね。 毎回、ユニークな企画で楽しませてくれているカルムス・アンサンブルですが、今回は「ルター・コラージュ」というタイトルのアルバムです。「ルター」というのは、宗教改革でおなじみのマルティン・ルターのことですが、今年はその宗教改革から500年という記念の年なのだそうです。音楽史の上では、彼は多くのコラールを作ったことで知られています。そのコラールは、プロテスタントの作曲家の素材として用いられ、「ルター」という名前は知らなくてもそのコラール自体のメロディは多くの人に親しまれています。バッハのオルガン曲や、教会カンタータ、受難曲には頻繁に登場していますね。 このアルバムのコンセプトは、そのようなルターの元のコラール、あるいはもっとさかのぼってルターが引用したグレゴリア聖歌から始まり、その後の作曲家がそれを用いて作った曲を一緒に演奏するという、まさに「コラージュ」の手法によって、その時代を超えた広がりを体験する、というものなのでしょう。 1曲目は、まさに宗教改革のシンボルともいえる、有名な「Ein feste Burg ist unser Gott」が、ルターが出版したそのメロディだけがソロで歌われます。そのオープニングのソロを任されたのが新加入のバス、ヘルメケだというのも、なんか思いやりのようなものが感じられませんか?コーラスではなかなか聴くことのできないこのパート、彼の声はとてもやわらかですね。それに続いて、同じ時代のハプスブルク家に仕えていたカトリックの作曲家ステファン・マフの合唱バージョンが歌われます。 そんな正攻法ではなく、それ以降の選曲には、それぞれユニークな工夫が加えられています。次の「Nun komm, der Heiden Heiland」では、まずルターの200年後に生まれたバッハのオルガンのためのコラール前奏曲が、ヴォカリーズで歌われます。それが、別のコラール前奏曲では、まるでスゥイングル・シンガーズのように、軽快なベースラインに乗ってスキャットでコラールの変奏が歌われます。このコーナーにはまだご存命のグンナー・エリクソンという人の、ちょっとニューステッドの「Immortal Bach」のようなテイストの曲も入っています。 そんな感じで、どのコーナーも驚きの連続、最後にはペルトなども登場しますから、油断はできませんよ。 CD Artwork © Carus-Verlag |
||||||
そんな、わざわざ買ってまで聴くことはなかったモーツァルトの弦楽五重奏曲を聴いてみたいと思ったのは、ひとえにこのレーベルのSACDの音を確かめたかったからです。あの「2L」と同じく、一人の人が録音から制作まですべて行っていて、サウンドに関しては確固たるポリシーを貫いているこのTACETレーベルは、最初にLPを聴いたときこそその盤質のあまりのひどさにがっかりさせられましたが、そのあとに聴いたBD-Aで本来の録音のクオリティをまざまざと知ることになりました。最近は普通のCDでのリリースの方が多くなっているようで、なんともったいないことを、と思っていたのですが(こちらなどは、CDでは全然物足りません)、以前CDで出ていたものがSACDでリイシューされたので、さっそく聴いてみました。 曲目は、モーツァルトの弦楽五重奏曲の全集から、ハ短調(K.406=K6.516b)とハ長調(K.515)の2曲のカップリングです。モーツァルトが作ったヴァイオリン2、ヴィオラ2、チェロ1という編成の弦楽五重奏曲は、完成されたものが6曲残されています。K.174の変ロ長調の曲だけはザルツブルク時代の1773年のものですが、それ以外は1787年から1791年の間のウィーン時代に作られています。この2曲は、その2番目と3番目に作られたものです。 演奏しているのは、このレーベルの顔、アウリン弦楽四重奏団にヴィオラの今井信子が加わったメンバーです。アウリン弦楽四重奏団はマティアス・リンゲンフェルダーとイェンス・オッペンマン(ヴァイオリン)、スチュアート・イートン(ヴィオラ)、アンドレアス・アルント(チェロ)という、ドイツとイギリスの4人の奏者によって1981年に結成されました。リンゲンフェルダー、オッペンマン、アルントの3人は、いずれもECユース管弦楽団のメンバーで、1981年にクラウディオ・アバドが結成したヨーロッパ室内管弦楽団の創設時のメンバーとなります。イートンは、アバドに誘われてスカラ座のオーケストラの首席ヴィオラ奏者を務めていましたが、やはりヨーロッパ室内管弦楽団の創設メンバーとなります。1982年に2つの大きなコンクールで優勝して一躍その名を知られるようになり、それ以来今日までずっと同じメンバーで活躍しています。 かつてはCPOレーベルからシューベルトの全集などをリリースしていましたが、2000年からはこのTACETレーベルと契約、ベートーヴェンやハイドンの全集をはじめ、膨大なレパートリーの録音を行っています。 このSACDの音は、期待通りでした。5つの楽器の音が良く溶け合って、それでいて個々の楽器の表情まではっきり伝わってくるという素晴らしいものです。全体がとても柔らかな響きに包まれていて、うっとりするほどのサウンドに仕上がっています。こういう音だったら、決して眠くなることはなく、いつまでも聴いていたい、と思えてしまいます。 四重奏団の音色はもちろん統一されていますが、そこに加わった今井さんのヴィオラもどちらのパートを弾いているのか全く区別がつきませんでした。 特に、ハ短調の曲は、渋い表情に引き込まれてしまいます。ハ長調の方はそれに比べるとほんの少し散漫に思えますが、それは大したことではありません。久しぶりに室内楽の悦びを感じさせてもらったSACDでした。 SACD Artwork © TACET |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |