|
|
|
|
![]()
A5版。.... 佐久間學
去年の日本公演のプログラムのメインは、このマーラーと、シュトラウスの「アルプス交響曲」でした。その「アルプス」は、ミュンヘンではマーラーの1週間前に演奏されていて、その録音もやはりCDとなり、早々と日本のコンサート会場で即売されていましたね。ただ、それはただのCDでしたし、リリースを急いだ結果編集ミスやトラック表記の間違いなどもありました。そのことを輸入代理店に教えてあげたら、何らかの手を打つような答えがあったのですが、例えばNMLなどを見てみるとそこからリンクされているブックレットやバックインレイは全く訂正されていないようですね。その後、別のレーベルのワーグナーのアルバムでもミスプリントがあったので指摘した時には、こちらにあるようにバックインレイと帯解説を速攻で訂正(あるいは改竄)したというのに。 とはいえ、このところSACDからはほとんど撤退していたようだった(最後にSACDを出したのは2010年)BRレーベルが、日本だけのためにSACD仕様のパッケージを用意してくれたというのは、輸入代理店の働き掛けによるものなのでしょう。まあ、もしかしたら「アルプス」での失態を補おうという殊勝な気持ちがあったのかもしれませんね。そのぐらいの謙虚さを、この国の首相も持ってくれるといいのに。 せっかくのSACDですから、しっかりCDとの違いを聴きとろうと、第1楽章の頭の部分を何度も聴き比べてみました。やはり、その違いは歴然としていて、弦楽器の肌触りやソロ楽器の立体感などは、全然違っていましたね。視覚的な比喩になりますが、CDでは紗幕がかかって輪郭がぼやけていたものが、SACDでは何の邪魔者もなく直接見えてくる、といった感じでしょうか。ところが、音楽が盛り上がってきて、ティンパニなども入ってすべての楽器が鳴り出すと、瞬間的にそのティンパニの音がつぶれて聴こえるところが出てきます。明らかに録音レベルの設定を間違えて入力が飽和してしまった状態ですね。ライブ録音ですから、こういうこともあるのでしょう。ただ、同じ個所をCDで聴くと、そもそも最初から音がぼやけているのでそんなことはほとんど分かりません。せっかくのSACDが、ちょっと皮肉な目に遭ってしまっていました。 会場のざわめきの中から聴こえてくるオーケストラの音は、かなり小さめ、でも、そこであわてて音量を上げてしまうと、そのあとのトゥッティになった時には耳をふさがなければいけなくなってしまいます。それほどのダイナミック・レンジが、ここでは再現できているのですから、まあ多少の歪みは仕方がないのでしょう。そこでは、ソロ楽器もホールで聴いたときと同じようにくっきりと聴こえてきます。確かに、ライブの追体験としてはこれ以上のものはありません。 ですから、あの時にヤンソンスが見せたとてもしなやかで懐の深いマーラーも、ここでははっきりと味わい返すことが出来ます。オーケストラを自在に操り、この曲の多面的な姿を存分に聴かせてくれた末に訪れる最後のピアニシモは、ここでも絶品でした。しかし、そこで一瞬会場全体が静まり返った後に、嵐のように巻き起こる歓声は、このSACDには収録されてはいませんでした。最後の静寂が現実のものであったことを知るために、そのあとの拍手はぜひ残しておいてほしかったものです。 SACD Artwork © BRmedia Service GmbH |
||||||
今回の「ヨハネ」は、キングズ・カレッジの2016年のイースターでのライブ録音です。クリーブリとキングズ・カレッジ合唱隊が演奏したバッハの受難曲は、「マタイ」が1994年、「ヨハネ」が1996年のそれぞれやはりイースターでライブ録音されたCDが、BRILLIANTのバッハ全集としてリリースされていました。さらに、こちらにあるように、「ヨハネ」ではCDとは別テイクのDVDも、別のレーベルから出ていました。ここで興味を引いたのは、CDでは普通の新バッハ全集の演奏の後に、1725年の第2稿で新たに作られた曲が演奏されていたことでした。それだけではなく、DVDでは最初からその第2稿で演奏されていたのです(厳密には、第2稿そのものではありませんでしたが)。クリーブリは、ちょっと詰めが甘いところはありますが、「ヨハネ」の異稿についても彼なりのアプローチを行っていたのでした。 ですから、今回彼らのレーベルで初めてバッハの作品を取り上げた時に、その「ヨハネ」のバックインレイにこんなことが書いてあれば、ちょっと期待をしてしまいます。 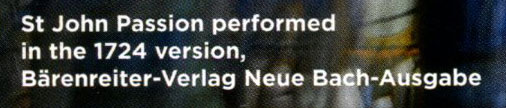 一つの可能性として、「新バッハ全集」の「付録」が関与しているのではないか、という考え方があります。この楽譜の後半には「新バッハ全集」では採用しなかった「初期稿」と「第2稿」と「第4稿」などの情報が収められているのですよ。ですから、それを使えば、「1724年稿」で演奏することも不可能ではありません。同じようにクリーブリがこの「付録」を見ながら演奏していたのが、先ほどのDVDでの「第2稿」だったのですからね。 ところが、このSACDを聴いてみると、最初の10曲は「1724年稿」ではなく「新バッハ全集」でした。もちろん、「付録」ではなく本体を使っての演奏です。つまり、「1724年稿」という表示は全く事実無根、もっと言えば、「1724年稿」が聴きたくてこのアルバムを買った人にとっては、「偽装表示」という「犯罪行為」にほかなりません。 ここで演奏しているアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックのメンバーとエヴァンゲリストのギルクリストは、2013年に「1724年稿」のようなものを実際に演奏しているのに、この間違いには気づかなかったのでしょうか。 この合唱団の場合、メンバーの入れ替えが激しいので時期によっての出来不出来の差が大きいのですが、今回はどうなのでしょう。とりあえず1996年の録音と比較してみると、こちらの方は限りなく「不出来」に近いようでした。トレブルは仕方がないとして、アルトのパートがかなり悲惨なんですね。それは、コラールなどではごまかすことは出来ても、「Wir haben ein Gesetz」とか「Lasset uns den nicht zerteilen」といったポリフォニーで各パートがソロになると、隠しおおせなくなくなってしまいます。 SACD Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |
||||||
それはともかく、きちんと10曲以上が収録された彼らの2015年の「フル・レングス」のアルバムの冒頭を飾っている「NA NA NA」というオリジナル曲までが、日本ではビールのCMの中で使われていますね。ですから、このEPの国内盤には、この曲がボーナス・トラックとして収録されています。もちろん、アルバムを持っている人にはこんなものは要りませんから、輸入盤で十分です。 このEPは、全曲カバーということで「クラシックス」と、今まで彼らのCDにはクリスマス・アルバム以外には付いていなかったサブタイトルが付けられています。もちろん、これは「クラシック音楽」とは全く別の意味の言葉で、「ポップス界の名曲」といったぐらいの意味です。まあ、「クラシック音楽」は全てカバー曲なので、完全に「別」とは言えないのかもしれませんが。 ここでカバーされている名曲は、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」、ジョン・レノンの「イマジン」、アンドリュー・シスターズの「ブギ・ウギ・ビューグル・ボーイ」、ジュディ・ガーランドの「オーバー・ザ・レインボウ」、A-haの「テイク・オン・ミー」、エルヴィス・プレスリーの「好きにならずにいられない」の6曲と、輸入盤ではボーナス・トラックになっているドリー・パートンの「ジョリーン」の、計7曲です。「好きにならずにいられない(Can’t Falling in Love)」はそれ自体がカバーですね。 彼らは、もちろん今までも数多くのカバーを手掛けてきましたが(Perfumeまで!)、多くの場合、オリジナルを大切にしたアレンジを施す、という姿勢がとられているのではないでしょうか。彼らを一躍有名にした「ダフト・パンク」にしても、それぞれの曲はかなりオリジナルに近いもの、それをいかにア・カペラで再現するかというところが聴きどころだったはずです。 ですから、最初の「ボヘミアン・ラプソディ」では、オリジナルの複雑な構成とサウンドがそのまま5人だけのアンサンブルで再現されていることに驚かされてしまいます。そこでは、フレディがピアノの弾き語りで左腕を交差させて高音フレーズを弾いている映像までが眼前に広がってくるようでした。 「イマジン」では、オリジナルは正直あまり良い曲だとは思っていませんでした。構成があまりにシンプルすぎて嘘くさいんですね。忙しい人が強いて聴くほどのものではない、と(「暇人」だったらいいのかも)。ところが、今回のバージョンでは、そんなシンプルさを逆手にとってとても細かいところで心に突き刺さってくるような憎いアレンジになっています。何より、コーラスで歌い上げられた時のメッセージの強さと言ったらジョンの貧弱なボーカルの比ではありません。まさにオリジナルを超えたカバー、聴きながら涙がこらえられないほどのすばらしさです。 最後の曲は、オリヴイア・ニュートン・ジョンのカバーも有名ですが、作ったのはドリー・パートン、ここではなんと彼女自身がフィーチャーされているというサプライズ付きです。ご存知でしょうが、このトラックは2016年9月にYouTubeにアップされたもので、今年のグラミー賞を受賞しています。カテゴリーは「最優秀カントリー・デュオ/グループ・パフォーマンス」ですね。これで、ペンタトニックスは3年連続グラミーを受賞なのだとか、「カントリー」まで制覇して彼らはますます凄さを増しています。 ただ、1日1回は目にする「パズドラ」のCMからは、おそらく、この凄さは伝わってくることはないでしょう。あれはオリジナルがひどすぎます。 CD Artwork © RCA Records |
||||||
この年号を見て「もしや」とも思ったのですが、この年に日本で勃発した大災害とは何も関係はないようです。というより、作り始めたのは2010年ですから、まだあの悲劇は起こってはいませんでした。作曲家によれば、ほぼ1世紀前、1915年から1917年にかけての、トルコによるアルメニア人の虐殺の被害者の想い出のために作られたのだそうです。それは、彼自身の家族へもおよんだ事件だったのです。 委嘱は、このCDで演奏しているRIAS室内合唱団とミュンヘン室内管弦楽団からのものでした。初演はもちろんリープライヒの指揮するこの団体によって、2011年11月19日に、ベルリンのフィルハーモニーの室内楽ホールで行われました。それに続いて、23、24、25の3日間ドイツ国内で演奏が行われ、2013年1月16日には同じメンバーによるアルメニア初演も行われました。 それ以降、今日までに韓国、アメリカ、ポーランド、メキシコ、オーストリア、エストニア、スイスなど、世界中で演奏されています。 今回の録音は、作曲家の立会いのもと、献呈者、つまり初演メンバーによって2016年1月に行われました。会場はかつてカラヤンとベルリン・フィルが使っていたベルリンのイエス・キリスト教会です。ブックレットに写真がありますが、オーケストラは弦楽器だけが6.5.4.4.2で、左からVnI、Va、Vc、VnIIと並び、Vcの後ろにCbが来るという、変則的な対向配置になっています。合唱も、左からベース、アルト、テナー、ソプラノというやはりちょっと珍しい並び方です。楽譜には特に配置に関しての指定はないようなので、これは演奏家のアイディアなのでしょうか。特にオーケストラでヴァイオリンが左右に分かれているのは、同じ音のロングトーンを受け渡すようなシーンでとても効果的です。 まずは、その会場の響きを熟知し、完璧な音を記録した「トリトヌス」のペーター・レンガーとシュテファン・シェルマンの2人のエンジニアの仕事ぶりに圧倒されました。全体はしっとりと落ち着いたモノトーンに支配され、豊かな残響に包まれています。オーケストラはそれほどの人数ではありませんが、とても充実したサウンドが広々とした音場で広がっています。そして、合唱は40人ほどですが、全く歪のない透き通った音は驚異的です。 この「レクイエム」は、伝統的なラテン語のテキストによって作られています。ただ、作品は演奏時間が45分程度とちょっと短め。それは、テキストのうちの長大なSequentiaからは、「Dies iras」、「Tuba mirum」、「Lacrimosa」の3つの部分しか使われていないからです。 なんでも、アルメニアというのは、世界で初めてキリスト教を「国教」と定めた国なのだそうです。作曲家によれば、全く同じテキストでも、ローマ・カトリックの教会での受け止め方とはかなり異なっているということです。おそらく、それはこの曲を聴いたときにはっきりと聴衆には伝わってくるはずです。時折ユニゾンで聴こえてくる聖歌のメロディは、カトリックでの音楽がベースとしたグレゴリア聖歌とは、微妙なところで雰囲気が別物です。 とは言っても、やはり死者を悼む気持ちを表現する時には、そのような些細なことはあまり問題にならなくなってきます。「Reqiem aeternam」の冒頭の和声は、まるでメシアンのように響きますし、次の「Kyrie」でのリズミカルな変拍子の応酬は、まるでバーンスタインの音楽かと思ってしまうほどです。そして、全体の雰囲気が、大好きなデュリュフレの作品とどこかでつながっているような気がしてなりません。またお気に入りの「レクイエム」が増えました。 中でも、ヴァイオリンのソリストのグリッサンドによる下降音から始まる「Lacrimosa」は、直接的に「悲しみ」が伝わってくる感動的な曲です。心の震えを抑えることが出来ません。 CD Artwork © ECM Records GmbH |
||||||
タイトル通り、ここには全部で120曲の、主に子供が歌うために作られ、時代的には「唱歌」、「童謡」、さらには「こどものうた」とその呼ばれ方を変えてきた歌の詳細なデータが掲載されています。それぞれの歌は1曲ずつ見開きの2ページに印刷されているのが、とても見やすい工夫です。左のページには、歌詞と楽譜、そして作詞者、作曲者はもとより、その曲が初めて世の中に現れたデータまでもがきちんと載っています。特にうれしいのは、今までは「文部省唱歌」という表記だけで、個別の作家の名前が全く分からなかった曲に、しっかりクレジットが表記されていることです。 明治政府がどのような姿勢で「唱歌」を作り、流布させたかということに関しては、以前ご紹介した「歌う国民」という本に詳しく述べられていましたが、そこでは作詞家や作曲家の名前は明らかにしないという方針が貫かれていたのですね。みんなとてもよく知っている曲なのに、単に「文部省唱歌」とだけ表記されて、実際に作った人の名前のないものが、かつてはたくさんありました。それが、近年の研究によってかなりのものの作者がきっちり特定できるようになりました。その成果がここでは生かされています。たとえば、1987年に出版された「ふるさとの四季」という唱歌を集めた合唱のためのメドレーには11曲の唱歌が使われていて、そのうちの6曲が「文部省唱歌」となっていたのですが、ここではそのうちの4曲にしっかり作家の名前がありました。どんな歌にも必ずそれを作った人はいるのですから、それを明確に表記するのはとても大切なことです。 「唱歌」と「童謡」との境界線はなにかということに関しては様々な見解があるでしょうが、単に楽譜が出ただけではなく、それが実際に「音」となって世の中に広まった物が「童謡」だ、という見方もあるかもしれません。ということで、初出データも、ある時期からはレコードがリリースされた時のレーベルやアーティストになってきます。こんな扱いも、おそらく今までのこの手の本にはなかったことなのでしょう。 長年気になっていたことが、初めて腑に落ちた、というものも有りました。それは「おもちゃのチャチャチャ」の作詞家の件です。この曲では作詞家のクレジットは野坂昭如となっていますが、そこに「補作詞:吉岡治」と書いてあるものも有るのです。常々、野坂の小説の世界とこの曲の歌詞との間にはあまりにも大きな隔たりがあると思っていたのですが、その疑問は氷解しました。 ただ、気になることはいくつかあります。巻末には参考文献として「インターネット」というカテゴリーもあるのですが、その筆頭がWikipediaというのは、ちょっと情けないですね。さらに、それらの文献からの「参考」では済まない、ほとんどコピペのような文章にも、しばしば出会えます。先ほどの「おもちゃのチャチャチャ」などは、その一例です。  「カチューシャの唄」を「野口雨情作詞」としているちょっと恥ずかしい誤記(134ページ)もありますし(語気を強めて抗議しましょう)。 Book Artwork © Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. |
||||||
このメシアンの有名な作品「時の終わりのための四重奏曲」が収録されたアルバムも彼女のプロデュースで2008年に録音されたもので、すでに2014年にOXINGALEからCDがリリースされていましたが、今回は同じものがSACDになってPENTATONEからもリリース、という形になっています。ただ、最近の録音では最初からPENTATONEからリリースされていますから、実質的にはOXINGALEはPENTATONEのサブレーベルになった、ということなのでしょう。 このアルバムのタイトルは「AKOKA」、そして、その下には「メシアンの『時の終わりのための四重奏曲』の再構成」みたいなコメントが加えられています。確かに、トラックリストには、このメシアンの作品の前後には「Akoka」と「Meanwhile...」という聴きなれない曲名がありますね。これはライブ録音で、これらの曲がメシアンを挟む形で続けて演奏されていたのだそうです。これはいったいどういうことなのでしょう。 「AKOKA」は、ここでクラリネットを演奏しているデヴィッド・クラカウアーの作品、曲名はメシアンの曲を初演したクラリネット奏者、アンリ・アコカへのオマージュが込められているのだそうです(あ、そうか)。ブックレットにはこの曲の楽譜までしっかり載っていますよ。たった1ページしかない走り書きのようなものなので、日本語の帯には「自筆譜の一部を掲載」とありますが、これは間違いなく「全曲」の楽譜です。というより、この曲はきっちり作りこまれたものではなく、プレーヤーの即興的な演奏で成り立つもので、この「楽譜」はその単なる「きっかけ」のようなものを記したものなのですから。 それはまず、クラカウアーのクラリネットとハイモヴィッツのチェロとジョナサン・クロウのヴァイオリンが高い音から低い音までをグリッサンドでつなげるというフレーズで始まります。おそらく、PAでディレイを入れているのでしょう、それぞれのパートは少し遅れてかすかに聴こえてきます。やがて、ジェフリー・バールソンのプリペアド・ピアノも加わり、変拍子のオスティナートの上でのインプロヴィゼーションが始まります。ヘブライ音楽のようなモードが聴こえるのは、アコカがユダヤ人だったことの反映でしょうか。やがて、静かな経過部の後に、アタッカでメシアンの四重奏の鳥の声が聴こえてきます。 もちろん、ここではピアノのプリペアは完全になくなっています。瞬時に外したような気配はありませんでしたから、このライブではピアノが2台用意されていたのでしょうか。 このメシアンは、それぞれの奏者の個性が前面に出てきた、とてもエキサイティングな演奏でした。そこには、あのTashiの録音と同質の、「醒めた熱気」が感じられます。 そして、エンディングを飾るのが、ここでは「Electronics」というクレジットで参加しているカナダのユダヤ系ラッパーSocalled(本名:ジョシュ・ドルギン)のパフォーマンス「Meanwhile...」です。メシアンの演奏をサンプリングしたもののリミックスなどを駆使して、ヒップ・ホップの世界が広がります。これが、どのような状況で「演奏」されていたのか(メシアンの演奏家たちはステージに残っていたのか、とか)、非常に興味があります。 このような形で「再構成」されたメシアンですが、「だからなんなんだ?」という感じ。この作品にこんな小手先の策を弄する必要は、何も感じられません。 SACD Artwork © Oxingale Productions, Inc. & Pentatone Music B.V. |
||||||
 そんな合唱団がオペラ・アリアを「合唱」で歌う、という触れ込みのCDを作りました。一瞬、これはオペラ・アリアをア・カペラの合唱で歌っているのだな、と思ってしまいました。あの澄んだハーモニーで、有名なオペラ・アリアを歌えば、そこにはまた新たな魅力が加わることでしょう。というか、普通にオーケストラをバックに合唱でアリアを歌ったって、なんにも面白くないじゃないですか。 ところが、そんな期待は完全に裏切られてしまいました。ここではまさにその「な〜んにも面白くない」事をやっていたのですよ。バックインレイを見てみると、そこには12曲の非常に有名なオペラ・アリアのリストとともに、「ジュリアン・レイノルズの指揮によるラトヴィア・オペラ管弦楽団」という文字があったではありませんか。 ジュリアン・レイノルズは、世界中のオペラハウスで指揮をしているオペラのスペシャリストです。ネーデルランド・オペラとかモネ劇場といった渋いところで活躍しています。そして、このオーケストラはリガにあるラトヴィア国立歌劇場のオーケストラのピックアップ・メンバーによってこの録音のために用意されたものなのでしょう。ブックレットの写真ではフルートには首席奏者ミクス・ヴィルソンスの顔も見られますが、弦楽器はおそらく8型程度の少人数のようですね。 最初の、「トゥーランドット」の「Nessun dorma」あたりは、なかなかのもののように思えました。この曲にはもともと合唱も入っていますが、それとソロとの歌いわけも納得できるような編曲で、それほど抵抗なく聴くことが出来ます。しかし、合唱のサウンドは、先ほどのア・カペラのCDとは雲泥の差でした。それぞれのメンバーがとても立派な声を持っているのはよく分かるのですが、合唱としてのまとまりがほとんど感じられないのです。創設者のイマンツ・コカーシュはもう亡くなっていて、今では息子のウルディスが指揮をしているそうですが、そのせいなのか、あるいはこんな適当なセッションなのでろくすっぽリハーサルもしていなかったのか、それは分かりません。 いや、これは決して「適当」なものではなく、それぞれの曲は合唱が映えるように指揮者のレイノルズによってかなり手が加えられているのですが、それはどうやら逆効果だったようです。「カルメン」の「ハバネラ」でティンパニが堂々と鳴り響くアレンジなどは、あまり聴きたくはありません。そして、弦楽器があまりにしょぼすぎます。 不思議なのは、写真とは反対の定位で合唱が聴こえてくること。オーケストラでも、弦楽器はそのままの定位ですが、ティンパニだけ写真とは反対側から聴こえてきます。なんか、いい加減。 CD Artwork © Sony Music Entertainment |
||||||
この団体を創ったのはジャネット・ソレルという1965年生まれの女性です。なんでも、彼女は指揮をレナード・バーンスタインとロジャー・ノリントン、チェンバロをグスタフ・レオンハルトに師事したのだそうです。1991年にはアトランタで開催された国際チェンバロ・コンクールで優勝しています。 この団体は、2016年の3月に、本拠地のクリーヴランドとニューヨークで7回「ヨハネ受難曲」のコンサートを行いました。その中で、3月7日から9日までのクリーヴランドのセント・ポール教会での演奏がこのCDには収録されています。このコンサートは映像でも撮影されていて、彼らのサイトでその一部を見ることが出来ます。それは、ちょっとほかでは見られないようなユニークな点がたくさんある、興味深いものでした。 まず、ここでは指揮者のソレルが、ポジティブ・オルガンを演奏しながら指揮をしています。それが、普通こういうキーボードを弾きながらの「弾き振り」だと座って演奏するものですが、彼女はオルガンを指揮台の上に乗せて、その前でずっと立ったまま指揮をしたりオルガンを演奏したりしているのです。彼女はパンタロンのような裾の広がったパンツを穿いているので、絵的にはなんとも華やかというか。 彼女の他にもオルガン奏者がもう一人アンサンブルの中にいて、そちらは指揮にはきちんと両手を使わなければいけない合唱の部分での演奏を担当しているようです。彼女は、ですからレシタティーヴォやアリアなどでの低音を担当しています。これがとてもいい感じ。エヴァンゲリストとの呼吸がぴったり合うんですね(阿吽の呼吸)。 合唱のメンバーは20人ほどですが、その中にはソリストも含まれています。彼らは普段は後の合唱団の中にいて、自分の出番になると前の方に設けられたステージのようなところに来て歌い始めます。唯一、エヴァンゲリストのニコラス・パーンだけは、常に前の方に立っています。そこに、イエスのジェシー・ブルームバーグやピラトのジェフリー・ストラウスが絡む時には、その二人は楽譜も持たずに登場して、ステージの上でちょっとしたしぐさを交えながら物語を進めていきます。後ろの壁にはプロジェクターで字幕が投影されていますから、英語圏の人にもその物語の内容ははっきり伝わることになります(確か、日本でも字幕付きでこの曲を演奏していたところがありましたね)。 パーンの声は、とても伸び伸びとした心地よいものでした。さらに、彼はテノールのアリアも歌います。それももちろん素晴らしかったのですが、やはりライブで両方とも全部歌うというのは大変なことですから、ちょっと苦しいところがあったのが残念です。そのほかのソリストも粒ぞろい、ソプラノのアマンダ・フォーサイスはとてもキュートですし、カウンターテナーのテリー・ウェイも深みのある声、そしてバリトンのクリスティアン・イムラーは完璧です。 合唱は、あえて感情を表に出さない、とてもクールな歌い方でした。それが、逆に恐ろしいほどの迫力を感じさせられるのですから、これはただ事ではありません。時折、指揮者の裁量でコラールがア・カペラで歌われるところなどは、背筋が凍りつくほどのインパクトがありましたよ。 常にオルガンのモーター音が聴こえているのと、CD2のトラック7の00:49から00:52にかけて録音機材に由来するノイズが聴こえるのが、ちょっとした瑕です。編集で気が付かなかったのでしょうか。 CD Artwork © Apollo's Fire/Jeannette Sorrell |
||||||
この「Electronic Sound」は、オリジナルは1969年のLPですが、それは普通のシングル・ジャケットで、録音データなどは中袋に印刷されていたようですね。今回入手したのは、2014年に新たにリマスタリングが行われた輸入盤CD、それはダブル・ジャケット仕様の紙ジャケットで、CDはLPの中袋をほぼ忠実に再現したものの中に入っています。 このCDには、オリジナルにはなかったブックレットが入っていて、そこには多くの写真と、2014年に新たに書き下ろされたライナーノーツが掲載されています。それらは資料としてはとても興味深いものでした。まず、ダブル・ジャケットの見開きの部分に、ジョージ自身が購入した「モーグ」の、2014年に撮影された写真があるのが感激ものでした。それは、「モーグIIIP」という、ポータブル・タイプでした。 さらに、ブックレットではこの同じ楽器が「アビー・ロード」のセッションで使われた時の写真なども見ることが出来ます。ライナーノーツによると、それは確かにこのアルバムが録音された時に使われたもので、1969年の8月にアビーロード・スタジオに運び込まれたのだそうです。他のデータによると、セッションでこれが使われたのは8月5日から19日までの間ですから、それは間違いありません。「アビー・ロード」には、しっかりジョージの「モーグ」が使われていたのでした。 ただ、この写真ではセットアップを行っているのがジョージ・マーティンのようで、ジョージをはじめ、他のメンバーはそれを眺めている、という感じに見えてしまいます。おそらく、音を作ったのはすでに同じものを持っていて使い慣れていたジョージ・マーティンだったのでしょうね。ジョージたちは単にキーボードでフレーズを演奏しただけなのでしょう。 もちろん、中袋のデータでもわかるように、1曲目の「Under the Mersey Wall」が録音されたのは1969年の2月ですから、ジョージがこの「モーグ」を入手した直後なのですが、2曲目の「No Time or Space」が録音されたのが1968年の11月、しかも録音場所はカリフォルニアなのですから、これと同じ楽器ということはありえません。この点こそが、「興亡記」でもしっかり述べられ、今回のライナーノーツでも語られていることなのですが、この曲を実際に「演奏」していたのは、「アシスタント」というクレジットがあるバーニー・クラウスに間違いないでしょうね。そのカリフォルニアでのセッションが終わってから、ジョージがクラウスに頼んでデモ演奏をしてもらったものを無断で録音して、それを編集しただけだ、というクラウスの主張は、「真実」に限りなく近いものなのでしょう。 実際にこの2曲を聴いてみると、それははっきりします。ジョージ自身が演奏した「Under the Mersey Wall」では、いかにも偶然に出来た音を羅列したという感じで、逆にそれがまるでジョン・ケージの作品のような味を出しているのに対して、「No Time or Space」の音は、明らかにこの「モーグ」の操作に熟達した、確かな意思を持って作り上げられたものなのですから。 CD Artwork © G. H. Estate Limited |
||||||
 しかし、今回のこの年号は、そのような意味は全く持っていないようでした。しかも、最初のあたりの曲は、ここに挙げられている4種類の年号以外の年、1739年に改訂されたものの、バッハの生前には演奏はされなかった楽譜による演奏なのですから、訳が分かりません。 しかも、この録音の場合はオリジナルのドイツ語のテキストではなく、それを英語に訳したものが使われています。その英訳を行った人の名前(ニール・ジェンキンス)だけは書いてありますが、当然これも楽譜が出版されているのでしょうから、バッハの改訂についてこれだけの年号を羅列するのであれば、その英訳の年号もきちんと表記するのが筋というものではないでしょうか。調べてみたら、それは1999年に翻訳されたもので、NOVELLOから出版されていましたね。ジェンキンスという人は歌手で音楽学者なのだそうです。 そんな、バッハの時代には存在していなかった20世紀に新たに作られた楽譜を使うのですから、当然オーケストラも20世紀のスタイルだと思ったら、そちらはピリオド・オーケストラだというのですから、ちょっとびっくりしますね。まあ、「マタイ」でも「Ex Cathedra」がこんな「英語版ピリオド」を演奏していましたけどね。 ところが、その「マタイ」では合唱の人数はリピエーノを除くと50人ほどと、様式的にはぎりぎりバッハの時代に即したものでしたが、今回の合唱団員はなんと110人なんですって。モダン楽器のオーケストラを使う時でも、いまどきこんな大人数の合唱が歌うのは、極めて稀なことなのではないでしょうか。 ここで演奏している「クラウチ・エンド・フェスティバル合唱団」というのは、1984年に合唱指揮者のデイヴィッド・テンプルによってロンドン北部の街クラウチ・エンドに創設されました。主にオーケストラ(もちろん、モダン・オーケストラ)との共演を目指していて、最近ではビシュコフ指揮のブリテンの「戦争レクイエム」とか、ロト指揮のベルリオーズの「レクイエム」といった大人数の合唱を必要とする作品のコンサートに参加しています。テンプル自身の指揮でも、マーラーの「交響曲第8番」を演奏しています。エンニオ・モリコーネやハンス・ジンマーなどの映画音楽作曲家ともつながりがあって、彼らのサウンドトラックを手掛けたり、さらにはロックのミュージシャンとの共演なども手掛けているのだそうです。 そんな、大人数を身上とする合唱団と、20人ほどのピリオド・アンサンブルという不自然なバランスは、まず録音の面での不都合となって現れていました。このレーベルでも最近とみにリリースが少なくなってきたSACDだというのに、なにか精彩に欠けています。オーケストラはともかく、合唱の音が完全に飽和しているのですね。 演奏も、合唱はとことんドラマティック、コラールは目いっぱい熱い思いを伝えようとしていますし、後半の群衆のポリフォニーなどもストレートに感情が現れています。それが英語で歌われていることで、その生々しさは極まります。ただ、それとピリオド楽器との齟齬は、最後まで解消されることはありませんでした。そごが、最大の問題です。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |