| マウス光 |
| LCD3.3V |
| PC修理 |
| USB電池 |
| 乾電池1個でLED |
| リブレットをSSD化 |
| Let's note メモリ |
| Top |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに紹介している回路は、実験としての回路であり、部品の耐久性や実用性などは考慮していません。車載用に使用することや、製品にそのまま応用するなどで、何らかの不具合や経済的損失が発生したとしても、管理人は一切関知致しませんので予めご了承ください。またそのような内容のご質問もお答えできません。 |
簡単な回路で白色LEDを乾電池一つで点灯させることができる回路です。乾電池は、0.8V位までなら使えますので、使用済みの電池を利用して、常夜灯などの応用が利くと思います。
動作説明
この回路は、弛張発振回路(しちょうはっしんかいろ)といって、回路構成が簡単な発振回路として昔から利用されてきた回路です。応用は色々あります。今回はその応用として乾電池一つでLEDを比較的明るく点灯させる試みです。
回路図
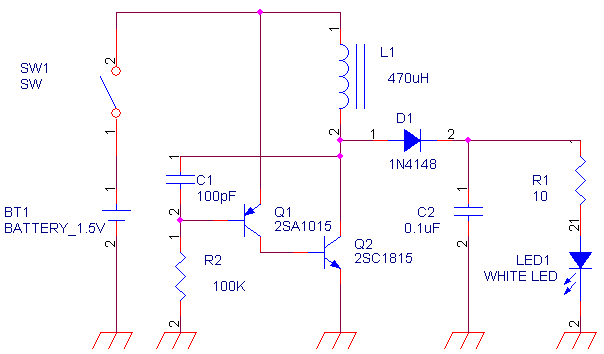
部品表
| No. | 個数 | リファレンス | パーツ名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BT1 | BATTERY_1.5V | 乾電池1.5V(0.8位まで使用可能。3V位が限度) |
| 2 | 1 | C1 | 100pF | セラミックコンデンサ |
| 3 | 1 | C2 | 0.1uF | セラミックコンデンサ |
| 4 | 1 | D1 | 1N4148 | 小信号用ダイオード(できれば電源用ショットキーが良い) |
| 5 | 1 | LED1 | WHITE LED | OSPW5111A(25000mcd) |
| 6 | 1 | L1 | 470uH | 100uH〜1mHの間で調整。ラジアルタイプの方が内部抵抗が小さくて明るい |
| 7 | 1 | Q1 | 2SA1015 | PNP型一般用トランジスタ |
| 8 | 1 | Q2 | 2SC1815 | NPN型一般用トランジスタ |
| 9 | 1 | R1 | 10 | 10Ω(10〜220Ω位で調整) |
| 10 | 1 | R2 | 100K | 100KΩ(33K〜100KΩ位で調整 |
| 11 | 1 | SW1 | SW | 必要に応じて電源スイッチをつける |
※この定数で動くという保障がありませんので、各部品はその近辺の値を用意することをお勧めします。
部品は全部入手が簡単なもので安いものばかりです。適正値はカットアンドトライで決定しました。
電源電圧は3V位が限界と考えておいた方が良いでしょう。
通電中LEDを開放して、再度接続しないように注意してください。高電圧ですぐにLEDが壊れてしまいます。LEDにはある電流以上は流れないのでR1を直結でも点灯はしますが、保護の為に一応抵抗を入れてあります。
D1とC2でパルス状の電圧を平滑(へいかつ)しています。これで直流として使用しています。この回路を取り、LEDを直接接続しても点灯しますが、パルス点灯のため、暗くなってしまいます。
性能
| 電圧 | 電流 | ワット | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力 | 1.38V | 18.4mA | 25.392mW | 発振周波数24KHz R1=100Ω LED Vf=2.7V METEXのテスターで計った為、電流測定で約10Ωの電流制限が入る |
| 出力 | 3V | 3.3mA | 9.9mW | |
| 効率 | 39% | |||
効率は良くありません。簡単な回路で点灯させる目的なので仕方ないでしょう。
シミュレーション
BLUE BACKSのCD−ROM付電子回路シミュレータ入門でチェックしてみました。LEDに入れる後段の平滑回路は省いています。
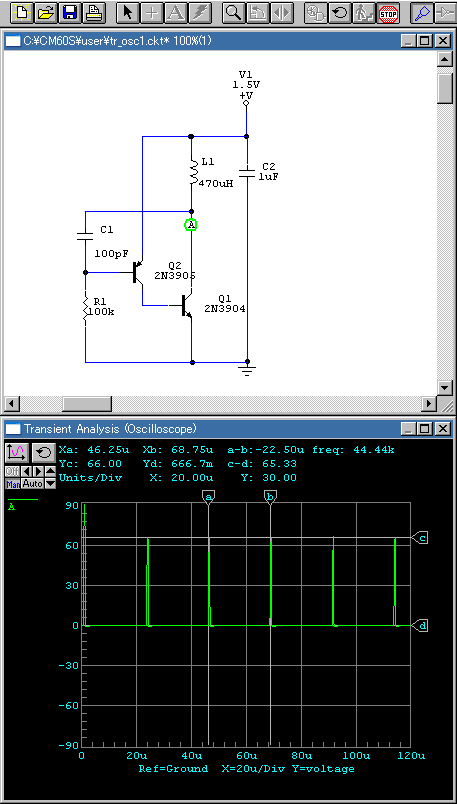
約65Vのパルス状の電圧がでております。周期は44KHzでした。
点灯させた所
回路構成は至ってシンプル。コイルは評価するため外に出しています。
新品の電池を使えば、暗くはなりますがLEDを直列に9個位まで点灯させることも可能です。こういう用途であれば、電池2本の3Vで動かしたほうがよさそうです。(表題の乾電池1つでという事に反しますが。。。)
アキシャル型のコイルでも点灯はしますが多少暗くなります。
コイルはこのように2種類の形があります。一般的にラジアル型の方が電流を流せられます。
2008/11/24 初版作成
(C)2008 air variable All Rights Reserved..