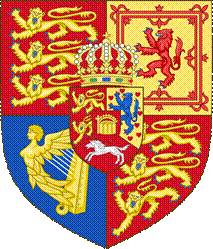ロマンセ(西:Romance)
カンティーガ(12世紀から14世紀にかけて、イベリア半島で作られたポルトガル語‐ガリシア語による民衆詩歌)に代わって、15世紀より人気を博したカスティリャ語による叙事・抒情詩。多くが無韻のトロカイオス16音節からなり、カエスーラ(中間休止)を持つバラッド(物語詩)である。詩集はロマンセロ(Romancero)と呼ばれ、その内容は下記の4種類に大別される。
1. 歴史的ロマンセ:比較同時代の歴史的な出来事や、伝説を描くロマンセ。
2.
カロリング・ブルターニュ伝説ロマンセ:フランク王国カロリング朝カール大帝や、イギリスのアーサー王など、外国の伝説を描くロマンセ。
3.
ムーア人(イスラム教徒)とキリスト教徒の戦いを描くロマンセ:8世紀から16世紀に渡り繰り広げられたイスラム教徒とキリスト教徒の戦い、特に後半の数百年の戦いを描くロマンセ。
4.
ムーア人のロマンセ:キリスト教徒の最終勝利(1492)の後のムーア人を描くロマンセ。
この他にも、聖書のテーマや、古代ギリシア・ローマのテーマや、愛と死を扱う様々な虚構を通して人間のドラマを描くロマンセなど、内容は多岐に渡った。こうしたロマンセは印刷され、ヨーロッパ中に伝播していく。
上記のロマンセは、「古ロマンセ」と呼ばれるが、16世紀に入ってからは、韻や詩節に技巧を凝らし芸術性を追求した「新ロマンセ」が創作されるようになり、1600年には、その集大成である『ロマンセ全集』が出版された。代表的な詩人としては、L.d.ベガ(Vega)やL,d.ゴンゴラ(Góngora
y Argote)が挙げられる。現代においてもこうしたロマンセは継承され、F.ガルシア・ロルカ(García Lorca)や、A.マチャードらが秀作を残している。
このロマンセと、中世にスペインやフランスで流行した「騎士道物語(Romance
de cavalleria)」を混同してはならず、また英米でRomanceといえば、専ら冒険小説やSFも含んだ近現代の大衆恋愛小説を指す。
1890年から1900年にかけて、ウィーンにおいてヘルマン・バールの周囲に集った新進作家集団。ファン・ド・シエクル(世紀転換期文学)におけるひとつの文学潮流であり、「ヴィーナー・モデルネ」とも、「若きオーストリア派」とも呼ばれる。彼らは1880年代から90年代にかけてドイツ・オーストリアを席巻していた自然主義のアンチテーゼとして、象徴主義や印象主義や新ロマン主義を標榜したが、文学的手法はまちまちであった。その機関誌は、1890年に発行された(翌年発行停止)”Moderne Dichtung”(翌年”Modern Rundschau”に改題:この雑誌は、当初自然主義的傾向を示していた)、及びバール自身が発行人を務めた”Die Zeit”(1884-1904)である。彼らは1891年頃から、所謂文学カフェとして有名だったウィーンの「カフェ・グリエンシュタイドゥル(Café Griensteidl)」に集い文学談議に興じた。その中心に位置していたのがバールであり、彼は仲間たちに外国の文学状況を伝え、出版社や新聞社への仲介役も務めていた。集団に属した著名な作家としては、フーゴー・フォン・ホフマンスタール、アルトゥール・シュニッツラー、ペーター・アルテンベルク、リヒャルト・ベーア=ホフマン、カール・クラウス(後に疎遠となる)、ヤコブ・ヴァッサーマン(ドイツ籍)などが挙げられるが、他にもロベルト・ムージル、ヨーゼフ・ロート或いはエデン・フォン・ホルヴァートなど、やや後代の20世紀文学を担うオーストリア作家たちにも大きな影響を及ぼしている。