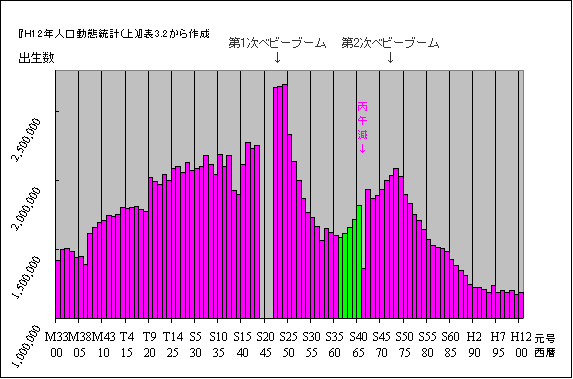
出生数の最新速報→平成15(2003)年人口動態統計年間推計
上図のデータソース最新版→『人口動態統計上巻』『人口動態統計中巻』『人口動態統計下巻』
資料所蔵機関検索→ここから
減少していた出生数が、
増加傾向に
転じ始めたころに
産まれたのが、
1960年代前半生まれ。
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → 新人類(1960年代前半生まれ)世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/死亡率/自殺率)、結婚、出産 ・仕事の状況:就業/失業/非労働、業界、職種 ・教育環境:進学率、 ©Tirom,2004. |
| 1960年代前半生まれの出生数 ― どれくらい生まれた? | ||||||||||||
|
出生数の最新速報→平成15(2003)年人口動態統計年間推計 |
減少していた出生数が、
|
|||||||||||
|
大都市圏生まれが増加傾向。 「1960年の全国出生数」に対する「1960年の各都道府県別出生数」のシェアを示したのが左のグラフ、「1965年の全国出生数」に対する「1965年の各都道府県別出生数」のシェアを示したのが右のグラフ。 東京・大阪・愛知とその周辺生まれが増えてゆく一方、北海道、新潟などのその他地域生まれが減少傾向にある。
|
|
|
||||||||||
|
行政単位としては別でも、我々の実際の活動・感覚からすると、東京・神奈川・千葉・埼玉、京都・大阪・兵庫は、不可分である。したがって、この二つの都市圏をまとめて、シェアを見るほうが、実態に即しているといえるだろう。東京・神奈川・千葉・埼玉を首都圏として、京都・大阪・兵庫を京阪神として、それぞれ一つにまとめたのが右図である。 やはり、大都市圏生まれが急増していることが目に付く。首都圏生まれは5人に1人から4人に1人にまで増加。京阪神生まれも愛知生まれも、数ポイントずつ増やしている。合計すると、三大都市圏生まれは、36%から45%までに増えたことになる。 |
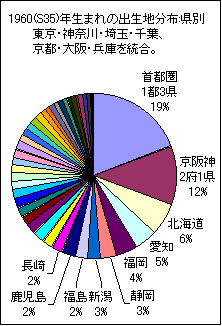 |
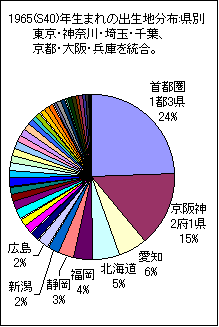 |
||||||||||
|
大都市圏生まれの膨張期に生まれたのが、 以上見てきた1960年代前半生まれ世代の出生地分布は、長期的趨勢のなかで、どのように位置づけられるのだろうか。 |
||||||||||||
|
下の帯グラフは、1935年生まれから2000年生まれまでの出生地分布を示したものである。戦争の被害のためもあってか、終戦後、大都市圏生まれのシェアは、戦前の水準から低下していた。流れが変わったのは、昭和30(1955)年。首都圏・京阪神・愛知の三大都市圏生まれのシェアが急速に膨張。そして、その絶頂が昭和45年(1970)年。これ以降、90年代まで、三大都市圏生まれのシェアは、再び、停滞ないし収縮に向かう。 この三大都市圏生まれの急速な膨張期にあたるのが、1960年代前半生まれ世代だった。 |
||||||||||||
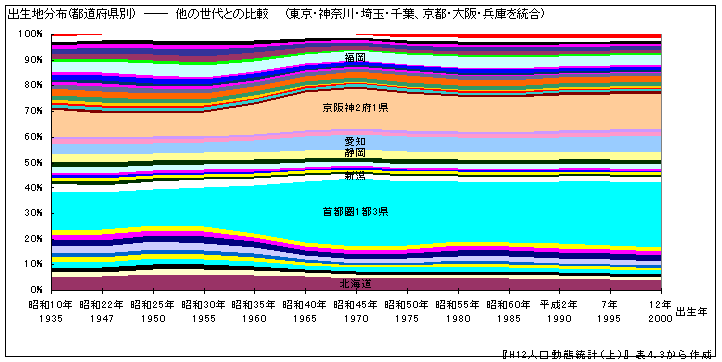 |
||||||||||||
上図のデータソース最新版→『平成14年度人口動態統計上巻』『平成14年度人口動態統計中巻』『平成14年度人口動態統計下巻』 |
||||||||||||
|
俯瞰図socio-economic macro-data on → 1960年代前半生まれ世代 ・生息状況:出生(出生数/出生地)、生存と死亡(人口/全人口に対する構成比/死亡率/自殺率)、結婚、出産 ・仕事の状況:就業/失業/非労働、業界、職種 ・教育環境:進学率、 |
(c)Tirom,2004.
![]()
|
|
||||||
|
|
||||||