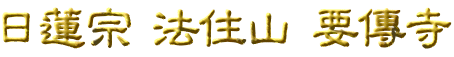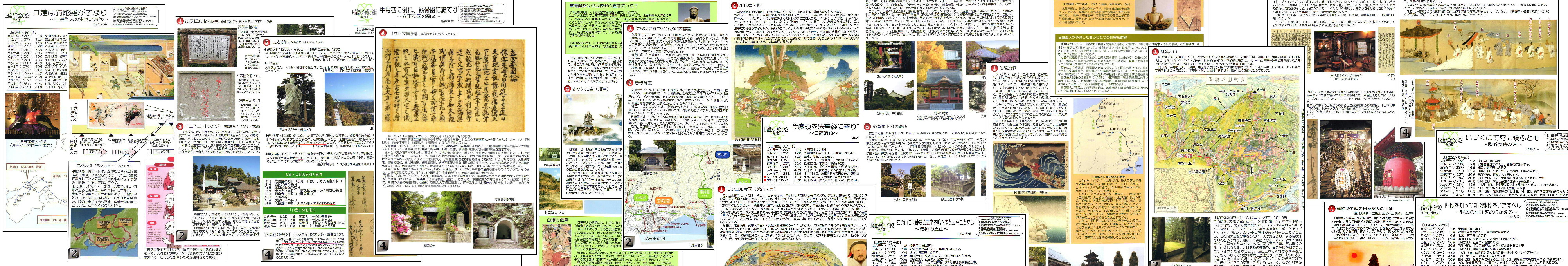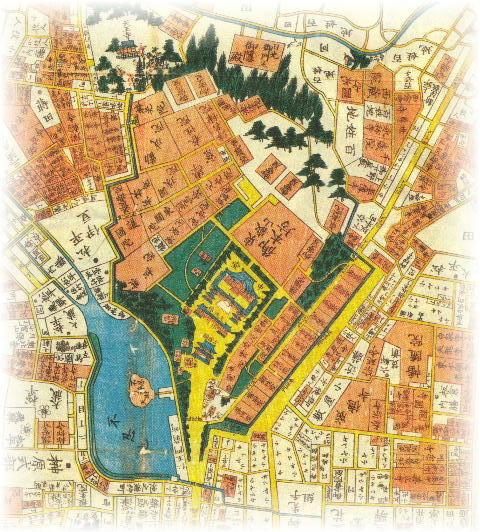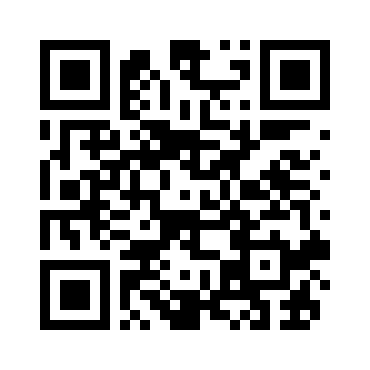�R��f��mESSAGE

���̒h�k��M�k�ɂȂ肽�����A��n��T���Ă�����A�i�㋟�{�������]�̕��Ɍ����Ă̏������ځB
�ڍׂ͉��L�̃^�u����A�R�[�f�B�I����W�J���Ă��������B
- ���R�̊J�厞�Ԃɂ��āi���m�点�j
�@�v�B���̎R��́A�����Ƃ��ČߑO7������ߌ�5���܂ŊJ�債�Ă���܂��B���ԊO�ɂ��Q�w�̍ۂ́A���O�ɂ��d�b�i0338735414�j�ɂē��R�܂ł��m�点���������B�Ȃ��A���R�Œʖ�E���V�Ȃǂ��c�܂�Ă���ꍇ�ł����Ă��A���R�h�M�k�̊F�l�ɂ͕�Q�����������܂��̂ŁA���̍ۂ͎������ɒ��ڂ������������������A���d�b�Ղł��܂���K���ł��B - ��n�Q�q�̊F�l�ցi���肢�j
�@���f���A���R��n�ɂ��Q������������A���肪�Ƃ��������܂��B���R�ł́A��n�̐��|�E�Ǘ��ɓ��X�w�߂Ă���܂����A�ߔN�A�J���X����������(������)���r���A���⋫�����������Ă��������Ă���܂��B���Q�肪���݂܂�����A��O�̂������́A�������A�肭�������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B - �Â������k�ɂ��āi���肢�j
�@���J�ɂ��炳�ꋀ���������k�́A�V���A����X�Y���o�`�Ȃǂ̔ɐB�ɂȂ���܂��B��������3�N���߂��������k�́A���R�ɂāu�����グ���{�v�������܂��̂ŁA�e�ƁE�e���ł��m�F�����肢���Ă���܂��B
�@�����g�ł̓P��������ȏꍇ�́A�������������������܂ł��p�����������B
�@�Ȃ��A��n�����Ɂu�����グ���{�����k���[�����v����݂��Ă���܂��̂ŁA�K�v�ɉ����Ă����p���������B - �s�R�ґ�ɂ��āi���m�点�j
�@�ߔN�A���R��n�ɊW�҈ȊO�̕�����������A�������̂����Ȃǂ������o�����Ă��������Ă���܂��B���R�ɂ͖h�ƃJ���������ݒu���Ă���܂����A�O�̂��߂��~�E���ފ݂ȂǎQ�w�҂̑��������ȊO�́A�����Ƃ��ē����E��ԂƂ��ɕ�n�������{�����邱�Ƃɂ������܂����B
�@��Q�̍ۂɂ́A�s�x�����������܂��̂ŁA�������܂ł����������������B - �䂤�����s�u�X�֕��������v�J�݂ɂ��āi���m�点�j
�@���̓x�i����28�N9���j�A�쎝���E���k���{���Ȃǂ̔[���ɂ��𗧂Ă���������u�X�֕��������v��V�݂������܂����B�����p������]�̐߂́A���܂ł���������܂���A��p�̕����p���������肢�����܂��B
�ً}���Ԕ������ɂ����鎖�ƌp���v��i�a�b�o�j�ɂ���
�@�h�M�k�̊F�l�ɂ�����܂��Ă��A���E���S�m�ہE�s�����l���̌����́A��{�I�ɍ��E�n�������̗̂v���E�w���ɏ]���Ă��������B
�@���A�ЊQ�̓��e�i�\���E���J�E����E�^���E�����E�n�k�E�Ôg�E���E�і�ЁE�V�����ہE�����ǂȂǁj���Q�̏i�d�C�E�K�X�E�����̃��C�t���C����ʐM�E��ʁE�����E���Z�Ȃǂ̃C���t���̂ȂNj@�\�s�S�̗L���j�ȂǁA���ꂼ��̏ɂ���đΉ����قȂ邱�Ƃ��z�肳��܂��̂ŁA�ɉ����đ���������A���m�点�v���܂��B
�@�܂��A��̓I�Ȃ���]�ɂ��܂��ẮA�e�Ƃ��ꂼ��ɂ�����قȂ�ł��傤����A���̍ۂ͎��܂ł��₢���킹����������A�ʂɂ����k�ɉ������������܂��B
�@������낵�����肢�\���グ�܂��B �@�@ �Z�E
�@�@�@�L
�i�P�j�������ɂ���
�@�ʖ�E���V�̉c�ׂ̕��@��K�͂Ȃǂ́A��������r��i���J��Îҁj�l�̂��ӌ��d���܂����A�\�ߎ��Ƃ����k���������A���f�̏�A�����艺�����B
�@���Ƃ��Ă̗v�B���̗��p�A�Z�E�ւ̓��t�˗��Ȃǂ��A���i�ʂ育��]�ɉ����܂��B�������A�������Ƃ��Ă̒ʖ�E���V��̉�H�i�ʖ�U�镑���E���������j�ɂ��܂��ẮA�����Ƃ��Ă��T���������B
�@�ꍇ�ɂ���ẮA�ߐe�҂݂̂ɂĉΑ���ł̂��Α��i�����j���ς܂�����A�������߂Ă������̍ۂɎ��ɂđ��V���i�����j���c�ނ��������\�ł��B
�i�Q�j���@���ɂ���
�@�N��̂��@���̉c�ו��@�E�K�͂Ȃǂ́A��������{��i���J��Îҁj�l�̂��ӌ��d���܂����A�\�ߎ��Ƃ����k���������A���f�̏�A�����艺�����B
�@�ꍇ�ɂ���ẮA���Ԃ̎������݂Ă��炲�@�����c�ށA���邢�͂��@�����������đ����k�݂̂������{�����Ƃ����I�������������܂��B���@��������߂���ꍇ�́A���\���t������������A��ԁE�����̂����{�A�����k�̌����Ȃǂ����ɂď���܂��B
�@�Ȃ��A���@����̉�H�ɂ��܂��ẮA�����Ƃ��Ă��T���������B
�i�R�j�N���s���ɂ���
�@�t�ފ݁E᱗��~�E�H�ފ݂Ȃǂ̗v�B���̔N���s���̂��ē��́A��N�̒ʂ�1�����O�܂łɂ����肢�����܂��B
�@���Ԓ��̕�Q�ɂ��܂��ẮA�ߑO9������ߌ�5���̊ԁA�ʏ�ʂ�\�ł����A�e���ł����f�̏�A���Q�艺�����B
�@���݂ɁA���Ԓ��A��Q���s�[�N�ƂȂ鎞�ԑт́A�T�ˌߑO10���䂩��ߌ�1����ɂȂ�܂��B���G�ɘa�̂��Q�l�ɂȂ����Ă��������B
�@�Ȃ��A�e�s���̖@�v�i�ފ݂͏t���E�H���̓��A᱗��~��7��17���A���10��8���j�Ɋւ��ẮA2�T�ԑO�܂łɎ��Ԃ̎����̖ڏ��������Ȃ��ꍇ�́A���~�ɂ���ꍇ���������܂��B���̍ۂ́A�@�v�o�Ȃł��Ԏ��������������F�l�ɂ͕ʓr���m�点�������܂��B
�i�S�j����Q��ɂ���
�@��Q�ɂ��܂��ẮA�N�Ԃ�ʂ��ČߑO9������ߌ�5���̊Ԃ̊J�厞�Ԓ��͒ʏ�ʂ�\�ł����A�e���ł����f�̏�A���Q�艺�����B
�@�Ȃ��A���ʂ̂�����ŕ�Q������Ȃ��ꍇ�́A���\���t������������A��ԁE�����̂����{�A�����k�̌����Ȃǂ��A���ɂď���܂��B
�N���s���̂��ē�
���ߑ����]�@�։�E�V�N�j����@�����O�ӓ��߂��̍ŏ��̓��j�� �ߌ�1�����
�@1��8���́A���߉ޗl�����쉑�i���A�T�[���i�[�g�j�ŏ��߂ĕ��@�̋������������ɂȂ�ꂽ�䐹���ɂ�����܂��B��N�A�v�`���ł́A�N�̎n�߂ɂ�����A�ߑ����]�@�։�̖@�v�ƐV�N�ݗ�̏j�����\�肵�Ă���܂��B�����Č�Q�����������B���A�����̓s����A��o�Ȃ̕��͂��炩���ߓd�b�i03-3873-5414�j�ɂČ�A�����������B

���t�ފ݉�@�v�@3�� �t���̓� �ߌ�1�����
�@�t���̓�������őO��3���ԁi�v7���ԁj�́A�t�̂��ފ݂ł��B�ފ݂̈�T�Ԃ́A�������������̐��E�ł��邱�̐��i���݁j��������̂Ȃ����炩�Ȑ��E�i�ފ݁j�֓n�邽�߂ɁA�Z�g�����i�Z�x�j�̍s��ʂ��Ď����̐S���k�삷�镧�����H�̊��Ԃł����B�v�`���ł́A���ފ݂̒����i�t���̓��j�ɁA�t�G�ފݖ@�v���s���A�F�l�̂��u�ɂȂ�����c�̌䋟�{��v���܂��B
���ފ݉�Z�E�@�ꁞ
����25�N3��23���t�G�ފ݉�u�S���k���������H�T�ԁ`�Z�g�����`�v
����25�N9��26���H�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��1��j�z�{�v
����26�N3��21���t�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��2��j�����v
����26�N9��23���H�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��3��j�E�J�v
����27�N3��21���t�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��4��j���i�v
����27�N9��23���H�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��5��j�T��v
����28�N3��20���t�G�ފ݉�u�Z�g�����̎��H�i��6��j�q�d�v
����28�N9��22���H�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��1��j�ϐ�����F�v
����29�N3��20���t�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��2��j��F�v
����29�N9��23���H�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��3��j����F�v
����30�N3��21���t�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��4��j��s��F�v
����31�N3��21���t�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��5��j������F�v
�ߘa���N9��23���H�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��6��j������F�v
�ߘa�T�N3��21���t�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��7��j��s�y��F�v
�ߘa�T�N9��23���H�G�ފ݉�u��F�`�Z�g�����̎��H�ҁ`�i��8��j��s��F�v
�ߘa�U�N3��20���t�G�ފ݉�u�v�B��410�N�̕��݁v
�ߘa�V�N3��20���t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��1��j���d�F�����q�v
�ߘa�V�N9��23���H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��2��j��R���q�v
�ߘa�W�N3��20���t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��3��j�������v
�ߘa�W�N9��23���H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��4��j�y�@���m�v
�ߘa�X�N3�������t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��5��j���@���m�v
�ߘa�X�N9�������H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��6��j��苗���l�v
�ߘa10�N3�������t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��7��j�E�J��l�v
�ߘa10�N9�������H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��8��j��F�v
�ߘa11�N3�������t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��9��j�\�{���q�v
�ߘa11�N9�������H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��10��j�{�ɖ����v
�ߘa12�N3�������t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��11��j�{���h���v
�ߘa12�N9�������H�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��12��j�嘬�����v
�ߘa13�N3�������t�G�ފ݉�u�ߑ��{��杂ɂ݂��F�����H�i��13��j�L�����v
�@4��8���́A���߉ޗl�̒a�����ł��B�u�V��V���B��Ƒ��v�̎p�ŕ\���ꂽ���߉ޗl�̒a�����ɁA�Ò��������ċ��{����Ƃ��납��A�ʖ��A�u��v�Ƃ��Ăт܂��B
���V�~�������{��@7����P�y�j���E���j��
�@�{�N�ɏ��߂Ă̂��~�i�V�~�j���}������̐l�l�̂����{���������܂��B����]�����ȂǏڍׂ��ẮA���߂Ă��A���̏�A�����k�\���グ�܂��B
��᱗��~��E�{��S��@�v�@7��17�� �ߌ�1�����
�@᱗��~�́A���߉ޗl�̏\���q�̂ЂƂ�Ő_�ʑ��Ə̂��ꂽ�ژA���҂��A��S���ɒĂ����S��������{���邽�߂ɁA�J�����i�J���̏I�����j��7��15���Ƃ�������I��ŁA�����̑m���W�߂Ĕނ�Ɉ��H����z�{���A�F�ŋF�������A���ɕ�̉�S�̋���~�����Ƃ��ł����Ƃ����̎��ɗR�����܂��B��������A���{�ł́A7��13���`15�����A��c���{�̂��~�̎����ƂȂ�܂����B
�@�v�`���ł́A���N7��17����᱗��~�{��S��̖@�v���s���Ă���܂��B�����́A�ߌ�1�����@�b�A���̌�A�ߌ�2�������@�@�e�i�����e���o�d�̂��ƁA᱗��~�{��S��@�v�����C�������܂��B
���u�e�i��v�́A���R��38�� �v���@������l�i���X����j�̑�Ɍ������ꂽ���@�@�L�u���@�̌ݏ��g�D�ŁA��ݎ��E�{�B���E���䎛�E�v�B���E�o�����E�̌����E�{�E���E�C���@�E���_���E����E�P�����Ƃ����䓌��J���E�r�����闢�ɏ��݂�����@�@���@12�ӎ��i�����͉����@�E���掛��2�ӎ�������14�ӎ��j�ō\������A᱗��~�{��S��E�@�c��݂̂Ȃ炸�A�l�X�Ȋ����ɑ��݂ɏo�d���A�A�g�E�������Ă���܂��B
�@�H���̓�������őO��3���ԁi�v7���ԁj�́A�H�̂��ފ݂ł��B�ފ݂̈�T�Ԃ́A�������������̐��E�ł��邱�̐��i���݁j��������̂Ȃ����炩�Ȑ��E�i�ފ݁j�֓n�邽�߂ɁA�Z�g�����i�Z�x�j�̍s��ʂ��Ď����̐S���k�삷�镧�����H�̊��Ԃł����B�v�`���ł́A�H�̂��ފ݂̒����i�H���̓��j�ɏH�G�ފݖ@�v�����s���A�F�l�̂��u�ɂȂ�����c�̌䋟�{��v���܂��B
�����@���l������@�v�i����j�@10��8�� �ߌ�1�����
�@���@���l�́A�O��5�N�i1282�j10��13���ɕ������i���݂̓����j�r��̒n�őJ������܂����B�r��{�厛�ł́A�O����10��12���̑ߖ�ɂ́A���{�e�n���W�܂��������ƓZ�̍s�Q�����������܂��B�܂��A10��13����O�サ�āA���@�@�ł͊e�n�ł���̖@�v���c�܂�܂��B
�@�v�`���ł͖��N10��8���ɂ���@�v���s���Ă���A����27�N�i2015�j����͉��L�̒ʂ�A���R�Z�E�ɂ��u���@���l�̓`�L�Ɣ�b�v�S10��̍u�b���s���Ă��܂��B�����́A�ߌ�1������u�b�A���̌�A�ߌ�2�������@�@�e�i�����e���o�d�̂��ƁA��@�v�����C�������܂��B�Ȃ��A�{�u�b�́A�e�i�����ł�����A���闢�o�����Z�E�i�����j�̊����ꗧ����w���_�����̋��߂ɉ����A�����̂���ł����b�����Ă���܂��B
���u�e�i��v�́A���R��38�� �v���@������l�i���X����j�̑�Ɍ������ꂽ���@�@�L�u���@�̌ݏ��g�D�ŁA��ݎ��E�{�B���E���䎛�E�v�B���E�o�����E�̌����E�{�E���E�C���@�E���_���E����E�P�����Ƃ����䓌��J���E�r�����闢�ɏ��݂�����@�@���@12�ӎ��i�����͉����@�E���掛��2�ӎ�������14�ӎ��j�ō\������A᱗��~�{��S��E�@�c��݂̂Ȃ炸�A�l�X�Ȋ����ɑ��݂ɏo�d���A�A�g�E�������Ă���܂��B
������Z�E�u�b�u���@���l�̓`�L�Ɣ�b�v�S10��
�i�P�j���@�͝ёɗ����q�Ȃ�`���@���l�̐���������` �i����27�N�j
�i�Q�j����{�̒��ƂȂ�ށ`�����̗����Ə@�|�����` �i����28�N�j
�i�R�j���n�J�ɓ|��A�[���H�ɖ��Ă�`���������̊����` �i����29�N�j
�i�S�j�@�،o�̌̂ɗ��߂ɋy�тʁ`�����P���ƈɓ����߁`�i�ߘa���N�j
�i�T�j�˂��͍~��J�̂��Ƃ��A�������͈�Ȃ̂��Ƃ��`�������̐n��` �i�ߘa7�N�j
�i�U�j���x�z��@�،o�ɕ��ā`���@�ÎE�` �i�ߘa8�N�j
�i�V�j��鮍��n�̍��ɂ�����ā`���~�̗��Y�n�` �i�ߘa9�N�j
�i�W�j���̎R�ɂ͖��@�̌������ւ��Ɖ]�ӂ��ƂȂ��`���_�̗�R�` �i�ߘa10�N�j
�i�X�j���Â��ɂĎ��Ɍ�ӂƂ��`�Ֆœx���̏��` �i�ߘa11�N�j
�i10�j�l����m���Ēm�����������ׂ��`�̐��U���ӂ肩����` �i�ߘa12�N�j
��������Z�E�u�b�u���@���l 10�̖��́v�S2��
�i�P�j���@���l 10�̖��́i���j�`�u��v�̑��ʂ���`�i�ߘa13�N�j
�i�Q�j���@���l 10�̖��́i���j�`�u�m�v�̑��ʂ���`�i�ߘa14�N�j
���ߑ�������@12��8��
�@12��8���́A���߉ޗl������i���A�u�b�_�K���[�j�Ō������J���ɂȂ�ꂽ�䐹���ł��B�v�`���ł́A���N���̎����ɁA�ߑ�������@�v�ƔN����|���Ȃ�тɖ]�N��i�Y�N��j��\�肵�Ă���܂��i�����Ȃǂ͕s����j�B�����Č�Q�����������B���A�����̓s����A��o�Ȃ̕��͂��炩���ߓd�b�i03-3873-5414�j�ɂČ�A�����������B
���N���N�n�J�^��F��@�v�@12��25���`1��3���i��12��30���j
�@ �N���N�n�ɕ�Q�E�o�w�Ȃ���h�M�k�Ɍ����āA�e�ƌʂ́u�N���N�n�J�^��i��������₭�悯�j�F��@�v�v���c�݂܂��B ����]�̍ۂ́A��]���̈�T�ԂقǑO�܂łɁA���d�b�i03-3873-5414�j�ɂē������������k���������B���ԑт́A12��30�����������Ԓ��A��������ߑO9������ߌ�3���A�e��15�����x�i�e��30���Ԋu�j�B�Ȃ��A���\�����݂͐撅���ƂȂ�܂��B
�@���Ƒ��E���ꑰ�̑P���F���E�����ގU�A���a�����E���Љ����A�Ɠ����S�E�g�̌��S�A�Љ^�����E�����ɐ��܂����̊w�����i�E�S�萬�A�����F�O�\���グ�܂��B���萬�A�́u�N���N�n�J�^��F��@�v�v�A����A���Q�W���������B
Microsoft Excel�̃}�N���@�\�����p���������J�����_�[�iA4���j�ł��BB1�̃Z���i����N�j��D1�̃Z���i���j��ύX����ƁA�����I�ɓ��Y�N���̃J�����_�[�̓��t�ɒu�������܂��B�Փ��E�Z�j�͔��f����܂��A�N�ԗ\��\�Ƃ��Ă����p���������B
�c�̎Q�q
 �@�v�B���ł́A�s����ɍ����O�̎��@�E���ՁE���n�E���Ȃǂ̒c�̎Q�q�i�c�Q�j���s���Ă���܂��B
�@�v�B���ł́A�s����ɍ����O�̎��@�E���ՁE���n�E���Ȃǂ̒c�̎Q�q�i�c�Q�j���s���Ă���܂��B�@�����́A���a51�N�i1976�j�̐g���R�v�����E���V�@�v�e�t�E���ʎR�h�T�@�c�Q���ŏ��ɁA���R��E�k�R�{�厛�E��{�������E�x�m���@���E���n���Ǝ��E�������鎛�E�ˌ����{���E��t�������E�����a�����E���@���E�Ř@���E���Ȍ����@�����E���s�������E���o���E���{���E��Ǝ��E�郖����x���E���R�ŏ��ׁE�@�����E���َ��s���E�D�y�o�����ق��Ɍw�ŁA���O�́A���a56�N�i1981�j�̃C���h�Z�啧����Ւc�Q���͂��߃l�p�[���E���`�E��p�E�n���C���@�@�ʉ@�Ȃǂ�K��܂����B
�@�ߋ��̒c�Q�̏ڍׂ́A���L�̃����N���炲�����������B
�����u��
�@����̗\��͐������m�点�v���܂��̂ŁA�����҉������B
�h�k�i�h�Ɓj�E�M�k�i�M�ҁj�ɂȂ�ɂ�
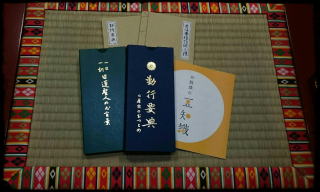
�@�w���@�@�@���x�ł́A�h�k�́u���@�@�̋��`��M�s���A���@�@�y�я������鎛�@�̌쎝�ɓ���A���@�̒h�k����ɋL�ڂ��ꂽ�ҁv�A�M�k�́u���@�@�̋��`��M�s���A���@�@�y�ыA���鎛�@�E����E���Ђ̈ێ��������A���@�E����E���Ђ̐M�k����ɋL�ڂ��ꂽ�ҁv�ƁA���ꂼ��K�肳��Ă��܂��B
�@�V�K�ɓ��R�̒h�M�k�ɓ��h�܂��͓��M������]�̍ۂ́A�u�v�B���h�M�k�K��v�ɐ��A���h�E���M�̎葱�������Ƃ肭�������B
���V�ɂ���
 �@������Ƒ��Ɍ�s�K���N����܂�����A���V�ЂȂǂɘA������O�ɁA�K���v�B���i�d�b03-3873-5414�j�Ɍ��������B���V�̎葱���E�i���ȂǁA�ǂ̂悤�ɐi�߂���悢��������Ȃ��ꍇ�Ȃǂɂ��Ă��A�����k�ɉ����܂��B
�@������Ƒ��Ɍ�s�K���N����܂�����A���V�ЂȂǂɘA������O�ɁA�K���v�B���i�d�b03-3873-5414�j�Ɍ��������B���V�̎葱���E�i���ȂǁA�ǂ̂悤�ɐi�߂���悢��������Ȃ��ꍇ�Ȃǂɂ��Ă��A�����k�ɉ����܂��B�@���ɁA�ŋ߂ł́A�ʖ�E���V�̓����𑒋V�Б��ƈ���I�Ɍ��߂��āA���R�̏Z�E�����f���ł��Ȃ��������Ⴊ����܂��B�܂��A�v�B���Ɋւ��̂Ȃ��u���V�Дh���̑m���v�ɒʖ�E���V���c�܂�A�{���K�v�Ƃ����ȏ�̑��V���𐿋�����鎖�Ă��������Ă���܂��B
�@���V���̉����������̍ۂ́A�v�`���ł̑��V�����l���������B�v�`���͓��R�̒h�M�k�̂��߂ɑ��݂��܂��B ���R�̒h�M�k�́A�Z�E�̋��āA���̖{���E�q�a�E�����n���̎{�݂������p���������܂��B���̍ۂ̉��g�p���͌����Ƃ��Ĕ������܂���B�܂��A���R�̖{���́A�������ꂽ��Ԃł�����A�֏ꓙ�̉ؔ��ȍՒd����͕K�v����܂���B���������āA��p�ʂł����S�����Ȃ��ꍇ������܂��B
�@�Ȃ��A���R�̕�n�͋�����n�ł͂Ȃ��A���@�@�ɏ������鎛�@�̕�n�i���@�@�̓��ꐫ�E�ꌠ����L���鎛�@��n�j�ł��B�u���@�@�̓T��v�ɂ��Ȃ����V���c�܂ꂽ�ꍇ�́A���ʂȎ���������ē��R��n�ւ̖������ł��܂���B���X���䒍�ӂ��������B
�@�ߔN�́A�l�X�Ȍ䎖��ő��V����o�����A������������s���Ȃ��Ƃ�����������������悤�ł��B�ǂ����䉏�����ē��R�̂��h�ƂƂȂ�ꂽ�̂ł�����A���̎��͂��C�y�ɂ����k���������B
�@�Ȃ��A������̂��Ƃ�����O�ɁA���O�̌䑊�k�������Ă���܂��B��ȕ���������ۂɁA�ǂ̂悤�ȑ��V���c�܂�邩�A�������̂����ɂ��b�������ɂȂ邱�Ƃ���Ȃ��Ƃł��B
�@���ɂ���
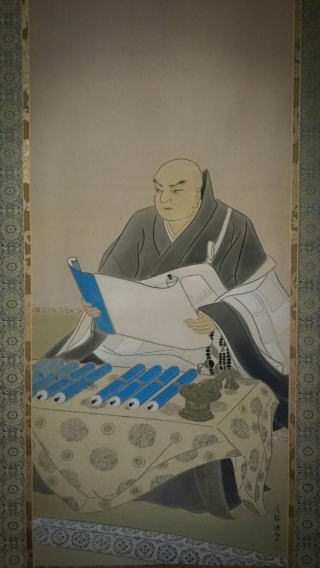 �@�̐l�l�₲��c�l�̂��@���i���@�v�j������]�̍ۂ́A�\����̂P�������O�܂łɗv�B���ɂ��A���E�����k���������B
�@�̐l�l�₲��c�l�̂��@���i���@�v�j������]�̍ۂ́A�\����̂P�������O�܂łɗv�B���ɂ��A���E�����k���������B�@����]�̓����ɁA���łɑ��̂��@���₨���V�A���邢�͗v�B���̔N���s���Ȃǂ̏����Ƃ̗\�肪�����Ă���ꍇ������܂��̂ŁA�K�v�ɉ����ē����E���Ԃ��������܂��B
�@�܂��A���̍ۂɁA�����~�����p�ӂ���W��A�o�ȎҐ��A�v�B���q�a�𗘗p���Ẳ�H�̗L���ȂǁA��܂��ȏ������m�点�������B
�@�o�Ȏ҂̍ŏI�I�l���A�����k�̎{��A���H�����e�̏ڍׂȂǂ́A�ŏI�I�Ɏ��܂Ƃ߂āA���@ ���\�����10�����O�܂łɂ��m�点���������B���H���₨���ݕ��̎�z�́A���ʂȂ�����Ȃ�����A������Ǝ҂ɔ������܂��B
�@���@���̓����ɂ́A�̐l�̂��ʔv�Ƃ���e�������Q���������B���ԁi��n�p�E�{���p�j�⋟���i���َq�Ȃǁj�͓K�X���p�ӂ��������B
�@�Ȃ��A���R�ȊO�̓��@�@�h�M�k�̕��ŁA��������ɂ���Ȃǂ̗��R�ɂ��A���R�ɂĂ��@����������]�̍ۂ́A�������Ȃ������k���������B
��n�ɂ���
 �@���R�̕�n�́A������n�ł͂Ȃ��A���@�@�ɏ������鎛�@�̕�n�i���@�@�̓��ꐫ�E�ꌠ����L���鎛�@��n�j�ł��B�u���@�@�̓T��v�ɂ��Ȃ����V���c�܂ꂽ�ꍇ�́A�����Ƃ��ē��R��n�ւ̖������ł��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���������������B
�@���R�̕�n�́A������n�ł͂Ȃ��A���@�@�ɏ������鎛�@�̕�n�i���@�@�̓��ꐫ�E�ꌠ����L���鎛�@��n�j�ł��B�u���@�@�̓T��v�ɂ��Ȃ����V���c�܂ꂽ�ꍇ�́A�����Ƃ��ē��R��n�ւ̖������ł��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA���������������B����n�Q�q�̊F�l�ցi���肢�j��
�@���f���A���R��n�ɂ��Q������������A���肪�Ƃ��������܂��B���R�ł́A��n�̐��|�E�Ǘ��ɓ��X�w�߂Ă���܂����A�ߔN�A�J���X����������(������)���r���A���⋫�����������Ă��������Ă���܂��B���Q�肪���݂܂�����A��O�̂������́A�������A�肭�������܂��悤�A���肢�\���グ�܂��B
���i�㋟�{��ƍ�����̂��ē���
�@���R�ɂ́A�i�㋟�{��Ȃ�тɍ�����i�v���ω��_�j�����p�ӂ��Ă���܂��B
�@�i�㋟�{��Ȃ�тɍ�����i�v���ω��_�j�́A����������̒h�k�y�т��̉��̎҂܂��͕�n�̌p���҂ɑ���A��n�o�c��̂ƂȂ鎛���A�i��ɂ킽���ĕ�n�̊Ǘ��E���{�𐿂��������̂ł��B
�@�O�҂́A���݂̂���Ƃ���c�̖��������̂܂܂Ɏc���������̋��{�̕��@�ƂȂ�܂��B���{�Ƃ̐Վ�肪�Ȃ��A��n�������ɂȂ�������A����c���������Ƃ��Ă�����c�������Ƃ�������]�ɓY���������ɂȂ�܂��B
�@��҂́A���R�ɂ����̂���h�M�k�ŁA��n�݂͐��Ȃ����@�،o�̓���ł��铖�R�ւ̖�������]�������A���邢�͂��{�Ƃ̐Վ�肪���Ȃ��Ȃǂ̗��R�ŁA��n�������ɂȂ邱�Ƃ�S�z����A���R�̕��ɂ��邲��c�̕�n��P�����č����ւ̉�������]�Ȃ�����̂��߂̂���ƂȂ�܂��B������i�v���ω��_�j�ւ̖����̕��@�́A�����Ƃ��ĎU���̂������ƂȂ�܂��B
�@������̏ꍇ���A������ׂ��_�������킵�A���Y��n�̊Ǘ��E���{�y�ѕ�n���|�E���������Ɏg�p���邽�߂̋��{���i�i�㋟�{���܂��͍����拟�{���j�����[�߂��������܂��B
�@�����̎����Ă����Ă�����́A�����Ȃ��v�B���܂Ō䑊�k���������B
������_��^�[����̂��ē���
�@�ߔN�́A����ɑ����̔�p�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�]�������ǂ��ɂ�������Y��ł���A�V�K�ɕ�n������܂ł̊Ԃ̈ꎞ�I�Ȉ⍜�̗a������T���Ă���A����̏����I�Ȍp���҂����Ȃ��A�g���͂Ȃ����m�l�E�F�l����Q�ł���l�悪�~�����A�Ƃ̋߂��ł���Q����������ȂǁA����ɑ���j�[�Y�����l�����Ă���܂��B
�@���R�ł́A�����������l�ȃj�[�Y�ɂ��������邽�߂ɁA�\�ߊ��Ԃ��߂Ă��⍜�����a���肷�����_��^�̔[������n�߂܂��B������̏ꍇ���A�l�l�ł����p�̏ꍇ�́A�����킲�Ƃ��[�߂ł��܂����A���ӂ���l�ȏ�ł̂����p�̏ꍇ�̓J���[�g���ւ̎U���`���ƂȂ�܂��B
�@�̐l�l�̂��⍜���苖�ɒu�����܂܂ɂ���Ă��邲�⑰�̒��ɂ́A���炭�͍ň��̐l������������Ȃ��Ƃ����v���̕�����������Ⴂ�܂��B����ŁA�a�������Ƃ��a���悪��܂�Ȃ��Ƃ������ɂ́A���R�̔[����́A���������������邲��ĂɂȂ낤���Ƒ����܂��B�[����̍ő�̗��_�́A���⑰�E�ߐe�҈ȊO�Ɍ̐l�l���Âт������X�i�����ʁE���F�l�E���d���̊W�ғ��j���A�����̊J��i�c�Ɓj���ԑтł���A���ł�����Q�肪�ł���Ƃ������Ƃɂ���܂��B������ł��Ή�����邲���S�͂������܂���B
�@�Ȃ��A�_�����������������́A���⍜�͓��Y�[����ɂP�N�ԗ��u�̂̂��W����i������j�։����������܂��̂ŁA����_��^�̔[������_���ۂɁA�ޓX�Ɏx�����������������������[�߂����������܂��i������ւ̉����O�ɉ��߂čČ_�Ċ������������邱�Ƃ��\�j�B�ߔN�A�[�����݂̂��^�c���Ă���@�l�̌o�c�s�U���Ŕ[�������������Ȃǂ̗l�X�Ȗ��ɂ���āu�⍜�̈������v���̎��Ă��������Ă��܂����A���@�^�@���@�l�̔[����́A���@�ⓝ���@���@�l�i���R�̏ꍇ�́u�@���@�l���@�@�v�j������������肻�̐S�z�͂������܂���B
�@�܂��A�{���Ƃ͏@���@�l�̌��v����S�ۂ��邽�߁A���Y��̂��g�p�́A���R�̒h�k�ł��邱�Ƃ������ƂȂ�܂��B���R�̒h�k�̒�`�ɂ��ẮA���L�u�v�B���h�M�k�K��v�����Q�Ɖ������B��h�k�̏ꍇ�ɂ́A���R�̒h�k�Ƃ��ē��h���������܂����A����b�ł͂���܂���̂ŁA�����p������]�̍ۂ͎��܂ł����k���������B
�����ɂ���
 �@�����́A�u�@���v�u�@���v�u�@拁v�u�@恁v�ȂǂƂ������܂��B���݂ł́A��i�ڂ������j�̏Z�E�Ȃǂ��玀�҂ɗ^�����閼�Ƃ��čl�����Ă��܂����A�{���́A�M�҂��t��������A���������Ɏ����閼�ł��B
�@�����́A�u�@���v�u�@���v�u�@拁v�u�@恁v�ȂǂƂ������܂��B���݂ł́A��i�ڂ������j�̏Z�E�Ȃǂ��玀�҂ɗ^�����閼�Ƃ��čl�����Ă��܂����A�{���́A�M�҂��t��������A���������Ɏ����閼�ł��B�@�̐l�₲�⑰�̂��ӌ����ӂ܂��A����c�̉����Ƃ��Ƃ炵���킹�Ȃ���A���O�ɐς܂ꂽ������A��␢�̒��ւ̍v���x�Ȃǂɉ����āA�������������܂��B
�@�Ȃ��A���R�́A���@�@�ɏ������鎛�@�i���@�@�̓��ꐫ�E�ꌠ����L���鎛�@�j�ł��B�����Ƃ��āA���@�@�̋��`�i�@�`�j�Ɋ�Â��Ȃ������i�@���j�͂������ł��܂���̂ŁA���������������B
�@�܂��A�@�|�ւ��i���@�j�Ȃǂ̗��R�ŁA���@���@�Ŏ�����ꂽ�����ł̂������E�����{�Ȃǂɂ��Ă͂����k���������B
�����O�����̊��߁�
�@���R�ł́A�\�C�������i�悵�イ���ォ�������j�Ƃ����āA���O�Ɏ���̋V�����s���āA�@�،o�̐M�҂ɂȂ����Ƃ��Ẳ��������������Ă���܂��B
�@�����g�̔[�����������������������Ƃ������S���Ɠ����ɁA���������߂铹�S���܂��萶������̂ł��B
���k�ɂ���
 �@���k�́A�������́u�����k�i���Ƃ��j�v�Ƃ����܂��B����i�ڂj��Stupa�i�X�g�D�[�p�j�̉��ʂŁA�����i�Ԃ��Ƃ��j�E���ɗ����i�Ԃ������Ƃ��j�E��_�i�ꂢ�т傤�j��\���܂��B
�@���k�́A�������́u�����k�i���Ƃ��j�v�Ƃ����܂��B����i�ڂj��Stupa�i�X�g�D�[�p�j�̉��ʂŁA�����i�Ԃ��Ƃ��j�E���ɗ����i�Ԃ������Ƃ��j�E��_�i�ꂢ�т傤�j��\���܂��B�@�ߑ��̖Ō�i�߂��j�ɂ��̈⍜�ł���ɗ��i�����j�����{���邽�߂Ɍ��Ă�ꂽ�̂��N���Ƃ��A�����ɓ`���ƒ����Ǝ��̘O�t���z�ƌ��т��A���L���E���E�O�d���E�d���Ȃǂ���������܂����B���{�ł́A�������ۂ������k�E�p���k�E�o�ؓ��k�Ȃǂ��c�싟�{�ɗp�����A�@�،o�̋����Ɋ�Â��ē��@�@�ł͌Â�����p�����Ă��܂����B
�@���R�ł������k���{�����v���܂��B᱗��~��E�{��S��E�t�ފ݉�E�H�ފ݉�E��A���邢�͂��@������ɂ́A����A����c�Ȃ�тɗL�������̏�����ɑ����k�������i�����イ�j���A�����{���������B
�@���R�ł́A�召�Q��ށi�V�ڂƂU�ځj�̂����k�����p�ӂ��Ă���܂��B�����k�̂����{���ɂ��ẮA�v�B���܂ł��₢���킹���������B
�@�Ȃ��A���̔N���s���i᱗��~��E�{��S��E�t�ފ݉�E�H�ފ݉�E�� ���Ȃǁj�̂����k�̂����{�́A�s�x�����肷�邲�ē���̕ԐM�t���ɂĂ��m�点���������B
�@���̂ق��A����c�̂��@���̍ۂ̂����k�̐\���݂Ɋւ��ẮA���L�̐\�����ݗp���������p���������B
���Â������k�ɂ��āi���肢�j��
�@���J�ɂ��炳�ꋀ���������k�́A�V���A����X�Y���o�`�Ȃǂ̔ɐB�ɂȂ���܂��B��������3�N���߂��������k�́A���R�ɂāu�����グ���{�v�������܂��̂ŁA�e�ƁE�e���ł��m�F�����肢���Ă���܂��B
�@�����g�ł̓P��������ȏꍇ�́A�������������������܂ł��p�����������B
�@���A��n�����Ɂu�����グ���{�����k���[�����v����݂��Ă���܂��̂ŁA�K�v�ɉ����Ă����p���������B �@
�쎝��ɂ���
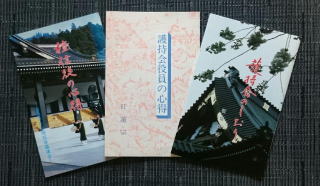 �@�@���@�l���@�@�ł́A���a24�N���A���@�@���@���̏@�叔��E���v���ƁE���F�ۑS�E�M�s�����Ȃǂ̎����̂��߁A�u�쎝��v��g�D���Ă��܂��B
�@�@���@�l���@�@�ł́A���a24�N���A���@�@���@���̏@�叔��E���v���ƁE���F�ۑS�E�M�s�����Ȃǂ̎����̂��߁A�u�쎝��v��g�D���Ă��܂��B�@���R�̌쎝��́A�h�M�k�e�ƁE�e�ʂ��炨�[�߂��������Ă���쎝���ɂ���ĉ^�c����Ă���܂��B
�@�쎝���́A���@�@�֔[�t���i�@��E�@������j�A�v�B���̓��F�̑��Q�ی�����c�U�C����A���������̌o��⎛��̈�����{��A�@�v�ɂ����鏔���̋��ԁE�������̔�p�ȂǂɊ��p���A��������@���@�l�̊����ɂ͌������Ȃ������ƂȂ�܂��B
�@�쎝���̋��z�E�����ɂ��ẮA���ꂼ��̎{��l�̂��ӌ��ɂ���Ă��[�߂��������Ă���z���قȂ�܂��̂ŁA�ʂɑΉ��������Ă���܂��B�܂��A���N�Ԗ��[�̕��A���̂ق��䎖�������̕��́A���Ɍ䑊�k���������B
�@�ڂ����͗v�B���܂ł��₢���킹�������B
�@�Ȃ��A�쎝���́A���z�{��t�͂��Ƃ͕ʂ̂��̂ł��B�쎝���A��L�̒ʂ�A�@��̔��W�ƕ�̌쎝�̂��߂̎����ł���̂ɑ��āA���z�{��t�͂��́A���[�̕��c�O��i�Ԃ�������ڂ��j�ւ̋��{�⋋�d�A�F�l�̂���c��L�������̏���ւ̉���̂��߂̂��̂ł��B
�@���������@�E�����z�����܂��܂��悤�A�X�������肢�\���グ�܂��B
�v�B���ߋ����ɂ���
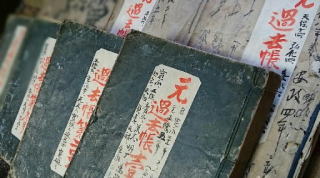 �@�v�B���ɓ`������ߋ�400�N�����ׂẲߋ����ނ̋L�^�́A�f�W�^���E�A�[�J�C�u������Ă��܂��B�ߋ����ޑS�_���ʐ^�B�e�ɂĕۑ����A�L�^���ꂽ�j���̑S�������Ƃ��ēd�q�����ĊǗ����Ă���܂��B�l���ی�̊ϓ_����A�f�[�^����Ƃ͊O�������A�Z�E�ЂƂ�ōs���܂����B
�@�v�B���ɓ`������ߋ�400�N�����ׂẲߋ����ނ̋L�^�́A�f�W�^���E�A�[�J�C�u������Ă��܂��B�ߋ����ޑS�_���ʐ^�B�e�ɂĕۑ����A�L�^���ꂽ�j���̑S�������Ƃ��ēd�q�����ĊǗ����Ă���܂��B�l���ی�̊ϓ_����A�f�[�^����Ƃ͊O�������A�Z�E�ЂƂ�ōs���܂����B�@���ɂ́A�u�N�ʉߋ����v�Ƒ��̂���鎞�n��̉ߋ����ƁA�u��Е�v�ƌĂ��h�k�̕�n���ƂɊǗ����ꂽ����Ƃ����݂��܂��B
�@�u�N�ʉߋ����v�́A���i3�N�i1626�j����吳15�N�i1927�j�܂ł́w���ߋ����x�S6���E�w���x1���E�w�V���x2���ƁA����20�N�i1887�j���畽��12�N�i2000�j�܂ł̋L�^���E���������w�N�ʈ�����L�^�x�S1���Ƃ�����A�����E�吳���̈ꕔ�͔N�オ�d��������̂́A��������f�[�^�����������Ă��܂��i�Ȍ�A���݂Ɏ���܂ŁA�N�ʉߋ����E��Е�Ƃ��ɏ�ɍX�V�𑱂��Ă��܂��j�B�������A�]�ˊ��̋L�^�ɂ́A�����̕c���i���j���L����Ȃ����̂������A�ƌn��H��̂�����Ȏ��Ⴊ�������݂��܂��B�h�M�k�e�Ƃ̂��Œd�₨�苖�Ɋi�삳��Ă���ߋ����E���ʔv�E�ƌn�}�̉��l�͂����ւ�ɑ傫���̂ŁA��ɂȂ����Ă��������B
�@�u��Е�v�ɂ͖������N���珺�a20�N�܂ł́w����Е�x�S3���Ɛ�ォ�猻�݂܂ł́w�V��Е�x�S4���Ƃ�����A���̂��т��������āA�f�[�^�x�[�X���\ �z���܂����B������́A�e�Ƃ̕�n���Ƃɖ������ꂽ����c�̋L�^�ƂȂ�܂��̂ŁA�������ȍ~�ɂ��ẮA�T�ˉƌn��H��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A�ߋ����ɂ́A�h�k�̂���c�̐��f�A�Z���A�����A�g���A�����Ȃnjl��������݂��邽�߁A��ʂɌ��J���邱�Ƃ͂ł܂���B�h�k�̎{��i��n�̌p���ҁj����̗v���ŁA�����ȗ��R������ꍇ�Ɍ���A�K�v�Ȕ͈͓��ł̂݊J�����邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���������������B
����w�@�Z�x�ɂ���
 �@���R�̌쎝��ł́A���@���l��700�������_�@�ɁA���a55�N�i1980�j��薈�N1��A�@�֎��Ƃ��Ď���w�@�Z�x�s���Ă���܂��B
�@���R�̌쎝��ł́A���@���l��700�������_�@�ɁA���a55�N�i1980�j��薈�N1��A�@�֎��Ƃ��Ď���w�@�Z�x�s���Ă���܂��B�@�h�M�k�̊F�l�ɂ́A�N���Ɋe�Ƃɂ��ꕔ���͂��������Ă���܂����A���R�W�҈ȊO�ł��w�ǂ�����]�̍ۂ́A�쎝��ւ̂�����������ɔЕz�������܂��B
�@�܂��A���̂��сA�w�@�Z�x�n��������ŐV���܂ł̊������i�o�b�N�i���o�[�j���ׂẴf�W�^���f�[�^���iPDF���j�������A�f�[�^���L�^����DVD�u�@�Z�A�[�J�C�u�v���쐬���܂����B�쎝�����ł���]�̕��ɂ͖����ł������������܂��̂ŁA���R�܂ł���������B�Ȃ��A�{���ɂ́A�ʓr�ADVD-ROM���ǂݍ��߂�@��i�p�\�R���Ȃǁj�Ȃ�тɉ{���\�t�g�iPDF�t�@�C���{���\�t�g�Ȃǁj���K�v�ƂȂ�܂��B
�@ �Ȃ��A�ȉ��Ɋ������̑��ڎ��̃����N���\�t�������܂����̂ŁA������������Ă����p���������B���ڎ��́AMicrosoft�Ђ̕\�v�Z�\�t�gExcel�ō쐬���Ă���܂��B�݊����̂���e��\�v�Z�\�t�g�ł����p�\�ł��B
�@���₢���킹�́A�v�B���i03-3873-5414�j�܂ŁB
���w�@�Z�x�o�b�N�i���o�[��������
���w�@�Z�x���������ڎ���
���E�}��
���_���w�_�����{�x�i���������Y�A2026�N�j
�@�����̓��{�l�ɂƂ��ẮA����������O�̉c�݂ł��������̂ɁA���̂��炵�������o���Ă��Ȃ������̍��̐����Ȑ��_���ƕi�i���^�����̂́A�p�g���b�N�E���t�J�f�B�I�E�n�[����G�h���[�h�E�V�����F�X�^�[�E���[�X�Ƃ����������ŏ����ɗ����������Đl�����ł������B
�@�ߑ�ɐ��܂鐡�O�̂��̍��̎p�A�����̉�X���Y���������Ă�����{�l�̌ւ�ׂ��������𐼗m�l�̎�������_�����w�_�����{�x�́A���{�l�̎����ς�@���ρE�_�ϔO�@���A�V�c���̃^�u�[�ɂ܂Ō��y�����s��ȓ��{�_�Ƃ�����B
�@�ȉ��ɁA�{���̎�ȓ��e���f�o����B
�@�E���{�l�͎�����V��ɍs�����Ƒ��ƕ�炷
�@�E�u�_�I�v�Ɓu���d�v�̗��������闝�R
�@�E���l�ʼn��[�����{�l�̂����V
�@�E���{�̕s�v�c�́u�\��P�v�Ƃ������z
�@�E���{�����͐��E�������
�@�E���������ɂ͂����Ȃ��ԕ�Q�m�̖S�N�ւ̕�
�@�E���[���b�p�����S�N�����������Ƃ��킸���O�\�N�ŒB���������{
�@�E���V�A���������������{�l�̉p�Y�I�s��
�@�E�z��I���x�������������{�l�̋C��
�@�E���E�ōł��h���������{�w�l
�@�E���e������w��ł��������V�c
�@�E���{���u�_���v�ƌĂԏ��ȁc�ق�
��ؗ��ג��w�������������_�\���T�Ŏ�����\�x�����Łi���R�ЁA2025�N�j
�@�]�ˎ���̎�ƂƂ��Ēm����x�i����i1715�`1746�j�╞���V�V�i1724�`1869�j��ɂ���Ē��ꂽ�_���̂ЂƂɁA�u��敧���o�T�͕��ɂ̐^���Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����u�����v�Ƃ����咣������B���o�T�Ɍ��炸�A�����̕����o�T�́A�㐢�̌o�T�Ҏ[�҂�o�T�|��҂̈Ӑ}�I�ȏC�������������A�܂��o�T���Ҏ[�E�|�ꂽ�����̎Љ�̗ϗ��ς⓹���ς��F�Z�����f����Ă���\�����l������_�ɂ����āA�����Ȃ���ׂĔ��ł���Ƃ�����B���̑�敧�����_�́A�ߑ�̉Ȋw�I���������̊�b�ƂȂ����B
�@�ߑ㕧���w�ł́A����o�T�̌��T�ł���T���X�N���b�g���p�[����Ȃǂŏ����ꂽ�o�T�̌�����ʂ��āA�߉ނւ̌��_��A�����߂錴����`�I�������嗬�ƂȂ��Ă���B
�@���҂́A������i�߂Ă������ŁA���������ߑ㕧���w���A���{�×��̓`�������Ƃَ͈��̉ۑ��悷�邱�Ƃɒ��ڂ��A���҂̘������ߕӂɂ����Đ����Ă��邩�ɂ��ē˂��l�߂����ʁA���ꂪ���T�̌�ǁE����ɋN�����邱�Ƃ��𖾁B�u���{�����́A�C���h�����Ƃ܂������Ⴄ�A�������q���������r�ł���v�Ƃ����w��I�������̂��̂��Ԉ���Ă������Ƃ��w�E����B
�@�w�T�����b�^�E�j�J�[���x�w�X�b�^�j�p�[�^�x�w�e�[���[�K�[�^�[�x�w�f�B�[�K�E�j�J�[���x�Ȃǂ̏������T�ɂ����āA�Ⴆ�u�F���E�F��͖��ɗ����Ȃ��v�u��p�Ɍg���ȁv�u�o�Ǝ҂͑����Ɋւ��ȁv�ȂǂƐ��������͊m���ɔF�߂��邪�A�������A���ꂼ��̌����\�����ڍׂɕ��͂���ƁA�u�o�Ǝ҂́A�o���������ōs���Ă���悤�ȋF���E�F��E��p���͍s���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u�o�Ǝ҂́A��̂̑����E�[���E�Α����邢�̓X�g�D�[�p�����Ȃǂ̈�A�̈�̏����葱�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ������̂ł����āA����̏o�Ǝ҂ɂ��F���E�F�������{���̂��̂�ے肷����̂ł͂Ȃ��Ǝw�E�A�ߑ㕧���w�ŕ`�����u�C���h�{���̕����v�ɂ͑����̉ۑ肪���邱�Ƃ��咣����B
�@����������ᔻ����{�͐��������邪�A�ߑ㕧���w�ɂ����镧�T���߂̌�T��_�j���A�C���h�����̎�����`���o���āA�w�p�I�����̂��ƌ��㑒�������̐�������_�����{���́A���ꂩ��̓��{�����̊�b���߂ɕs���Ȏw�쏑�ƂȂ邱�Ƃł��낤�B
�@������_�A�䂪���̐�l�B�������̉c�݂ɑ����̕�������荞��ł������̂́A���n�����o�T�̌�����߂�m��Ȃ����ォ����ɂ��������̂ł���A�{���Ɏw�E���ꂽ���_�I���t���������đ��������Ƃ����X�^�C�����蒅�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ͕������Ă��������B�����́A�����Ȃ�n��ɓ`�d���悤�ƁA���̒n��̐M�╗���K���Ȃǂ�ے肷�邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����_���d�v�ł���B�����ٕ����d���A�����ɂ��[���Ӌ`�Â������邱�Ƃɕ����̍ő�̖{�̂��������B�]���āA�L���X�g����C�X�������̏ꍇ�A����n��ʂ̑���͑S�����ɂȂ�Ȃ��̂ɑ��āA�����̏ꍇ�́A�C���h�����A���������A�؍������A�`�x�b�g�����A�^�C�����A���{�����Ƃ�������ɍ���n�悲�Ƃɕ��ނ���āA���ꂼ��̓��F���F�߂���̂ł���B���{�����́A�ꕶ�E�퐶�E�Õ�����ɂ����ē��{�l�̒��ɏ�������Ă������R���q��c�搒�q�Ƌ������т��āA�Ǝ��̔��W�𐋂��Ă����B�����E���q���ȍ~�̓��{�������A���{�l�̑����ɑ傫���֗^���Ă���̂́A���̂��߂ł���Ƃ��l������B
�@���������������Ă��A���{�����̒S����ł��邱�̍��̑m���������A������F��ɂ�����邱�Ƃ̈Ӌ`�ɂ��ĐS���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A���n���T�Ɉ₳�ꂽ�u�b�_�߉ނ̌��t�ɒ��Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł���Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�{���ɂ͉��l������Ǝv����B
�����^�꒘�w���ƕ���̍���\�푈�͂ǂ����w�ɂȂ�̂��\�x�i�g��O���فw���j�������C�u�����[�x617�A2025�N�j
�@�w���ƕ���x�́A���l�Ȑ��i����������X�̎j����`�����A���l�Ȏ��_�ɂ���ăp�b�`���[�N�I�Ɍp�����킳���̕���ɗZ�����Ă�������i�ł���A�P�ɐ�i�������j�����������_�b������ړI�ŕ҂܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���鎞�́A��̋��낵���E���ᔻ�Ɍ�邱�Ƃ�����A�܂����鎞�́A�l���l���E�����Ƃ̔߂��݂��������A���܂��Ɏ��ɂ䂭�҂̐S�ɕ��������Č��ȂǁA���҂𓉂ސS��ɐɕ\�����邱�Ƃ�����ƒ��҂͌����B�����������͂��A������|�\�A�h���}��A�j���Ȃǂ̍�i�𐢂ɐ��ݏo���Ă����Ƃ����̂ł���B
�@�{���ɂ�����w���ƕ���x�̏ڍׂȕ��͂́ANHK��̓h���}�u���q�a��13�l�v�ł�����ʂƂȂ����A�������ҁi������j�Ƒ�P�̔ߗ��i�{��107�Łj�A�ؑ\�`���Ɣb��O�̕���i143�Łj�A�`�o�̍◎�i173�Łj�A�F�J�����Ɠ��i189�Łj�A�`�o�Ɗ����i���̋t�E�_���i208�Łj�A�`�o�̔��z��сi282�Łj�A�m���̍Ŋ��i282�Łj�ȂnjR�L���̗��j�I�w�i���ǂ̂悤�Ɏ�e���ăh���}���n�삳�ꂽ�̂���m��藧�Ăɂ��Ȃ낤�B
�@���҂́A�w���ƕ���x���������鎞�̎��_�ɂ��āA�u�ʂ̐펀�҂̒����ɔ����镨����܂ނƓ����ɁA����S�̂Ƃ��Ă��A�펀�҂ւ̒����Ƃ�����ʂ������Ă����v���Ƃɒ��ڂ��A�u�펀�҂̍Ŋ��̂��܂���邱�Ƃ́A�����̏d�v�ȕ��@�v�ł���A�u���҂̖��O���v����邱�Ƃ͒����Ɍ������Ȃ��v�f�v�ł������Ǝw�E�A�u�����������_�̕���������ꂽ���ƁA�����āw���ƕ���x���̂��̂��A�łтĂ��������Ƃ̐l�X��ɂ��ލ��{�I�Ȑ��i��L���邱�Ƃ́A�w���ƕ���v�̍���L�q��P�Ȃ鏟�҂̑̌��k�⋻���{�ʂ̖��Z�̌��ȂǂɏI��点���A�o��l���̐S�ɕ������������q���\�ɂ��Ă������̂ł͂Ȃ����v�i285�`287�Łj�Əq�ׂĂ���B
�������m���w�������]�x�i�T���}�[�N�o�ŁA2024�N�j
�@���ҞH���A�]�͑̏d��2���̏d�������Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�l�̂Ɉ���ɕK�v�ȃG�l���M�[��20�������Q��鑟��ŁA�R��������炱���A�G�l���M�[��ߖ悤�Ƃ���N�Z������Ƃ��B�����Ɂu�D�G�v�Ƃ����l�̔]�ł��A�����Ɂu�Εׁv�Ə̂����l�̔]�ł����Ă��A�{���I�ȂƂ���ł͓����ł���Ƃ����B�u�ł��Ȃ��v���Ƃ���ɒ��ʂ��邱�Ƃ́A�]�̐������炷��Γ�����O�ŁA�u�ł��Ȃ��v���ƂŎ�����ӂ߂�K�v�͂Ȃ��A�S���ア����u�ł��Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��A�]���̂����������u��肽���Ȃ��v�����ŁA�܂�u�扄���ɂ��Ă��܂��v���Ƃ��n�߂Ƃ��������́A�]�̎d�g�ݏ��ނ����Ȃ��Ƃ����B
�@�]���{���I�ɂ��������d�g�݂ł���ȏ�A������������邽�߂̕��@���܂��A�]�̎d�g�݂𗘗p���邱�ƂɂȂ�B�u��肽���Ȃ��]�v���u��肽����]�v�ɕς���ɂ͂ǂ����邩�c�{���ł́u�h�[�p�~���E�R���g���[���v�Ƃ����]���̕�V�n�ƌĂ��d�g�݂𗘗p������@���Љ��B�ȒP�Ɍ����u���܂������ċC�����������v�Ƃ����]�̏�ϋɓI�ɍ��o�����A�Ƃ������Ƃł���B
�@�N�����ӂ��҂̔]�������Ă���͂��Ȃ̂ɁA���̒��ɂ͑f���炵�����ʂ��o���Ă���l����������B���̂悤�Ȑl�������A���o�̗L���Ɋւ�炸�s���Ă���u�h�[�p�~���E�R���g���[���v�Ƃ�����@��p���āA�u�扄���v���̉�����A�u���f�v�u�{��v�Ȃǂ̃R���g���[���@�ɉ��p���Ă����Ƃ����̂��{���̍\���ł���B
�c��L�u���w���͑��݂��Ȃ��\�Ő�[�ʎq�Ȋw�������V���ȉ����x�i�����АV���A2022�N�j
�@�����ł́A�w�،��o�x�̎O�E�B�S�����_��w��ɘ_�x�̗B���v�z�ɂ����āu�����̈ӎ������E�����v�Ƃ����T�O���������B��X���F�����Ă����ԂƎ��Ԃ́A�P�Ȃ�S�̎�i�ł����Ȃ��A��ԂƎ��Ԃ����ɐ��_�ɂ���đ���ꂽ�\�����ł���Ƃ�����A�u���v�Ƃ������̂́A��̂ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B
�@�{���́A��[�Ȋw�̌��q�͍H�w�̌����҂ŁA���E�o�σt�H�[�����i�_�{�X��c�j�␢�E���l��c�u�_�y�X�g�N���u�̓��{��\�̃����o�[�Ƃ��Ă����A���݂͑�����w��w�@���_�����߂钘�҂��A�u����̓�v�ɔ���Ƃ�����Ȋw�u�[���E�|�C���g�E�t�B�[���h�����v�ɂ��ĉ���������́B
�@�u�[���E�|�C���g�E�t�B�[���h�����v�Ƃ́A�F���ɕ��ՓI�ɑ��݂���u�ʎq�^��v�̒��ɂ���ƍl�����Ă���ꏊ�i�[���E�|�C���g�E�t�B�[���h�j�ɁA�S�F���̂����鎖�ۂ̏�L�^����Ă���Ƃ��������ł���B�����̗B���v�z�ɂ�����u�����뎯�v�̎����A�Ñ�C���h�N�w�́u���ޚ��i�A�[�J�[�V���j�v�̋���ɁA����Ƃ悭�����l�������邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�[���E�|�C���g�E�t�B�[���h�ɂ́A�ߋ����猻�݂܂ł̏o�����̏���łȂ��A�����̏o�����̏������݂��A���ׂĂ̏��͂��̒��Ɂu�g�����v�Ƃ��ċL�^����Ă���B�ʎq�����w�I�ɂ́A���E�̂��ׂẮu�g���v�łĂ��Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA���҂́A�����̏�u�g�����v�𗘗p�����u�z���O���������i�g���̊����g���Ĕg�������L�^���錴���j�v�ŋL�^����Ă���Ǝ咣����B�܂�A���҂̍����A�L�����A���̃[���E�|�C���g�E�t�B�[���h�̒��ɔg���Ƃ��Đ��������Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł���B
�@�u�l�͎���ǂ��Ȃ�̂��v�c�Y�f�╪�q�̍������ł�����̂́A���畅���ēy�ɕԂ����ŁA��������̂ƌ��т��Ă����ӎ����A�ʂ̂������Ŏc�葱����Ƃ�����Ȃ�A�@�،o�ɐ������v���̎ߑ����܂��A���͂��̐��ɑ��݂��Ȃ����A���̍��͐��������Ă��邱�Ƃ̉Ȋw�I�T�ɂȂ邩���m��Ȃ��B
�@���A����́A�ʎq�͊w�̔g��������������Ă���100�N���}����2025�N���u���ۗʎq�Ȋw�Z�p�N�v�Ɛ錾�����B�ɏ��̕����̐U�镑���𐳊m�Ɍv�Z����ʎq�͊w�́A�����̂݁A���q�͂��o��������ȂǁA�l�ގЉ�ɂ��������e���̑傫���͂͂���m��Ȃ��B���₻�̗��_�́A�z���O���t�B�b�N�F���_�A�p���������[���h�̎��݁A�f�W���u���ۂ̉𖾂��͂��߁A��X�̈ӎ��⑶�݂̐��̂ɂ܂Ŕ���Ȋw�ƌ����Ă���B
�Չ����ɕҁw�a�َq���������l�����x�i�R��o�Ŏ� �A2017�N�j
�@��������n��500�N�ȏ�̗��j�����a�َq�̘V�܊�����ЌՉ��i�Ƃ��j�́A���̓x�i����29�N�j�A���j��̐l��100�l�Ƙa�َq�̊W��Ԃ�G�s�\�[�h�W�w�a�َq���������l�����x�i�R��o�ŎЁA2017�N�j���o�ł����B�����E�j���𗊂�ɁA�����[���A�D�c�M���A�痘�x�A��{���n�A�H�열�V��A�O���R�I�v�ȂǗ��j�ɖ����c�����m��M�������ĕ����l�Ɉ����ꂽ�a�َq�̉B�ꂽ�G�s�\�[�h���G�b�Z�C���ɉ������B���M�E�Ҏ[�Ɍg������̂́A�Չ��َ̉q�������Չ����ɂ̌����X�^�b�t�A�Ō��͂���������j���E���ȗp�}��������������Ƃ��Ė������R��o�ŎЁB
�@�{���Ɏ��ڂ��ꂽ�G�s�\�[�h�́A�Չ��̌����z�[���y�[�W�ɕ���12�i2000�j�N����A�ڒ��́u���j��̐l���Ƙa�َq�v�����ƂɁA�Չ����ɂ��J�Â����W�����e�����M���A�L�x�ȃJ���[�}�ł�َq�̍Č��ʐ^��V���ɉ����āA1�b�����茩�J��2�łɎ��߂邩�����ōĕҏW�������̂ɂȂ�B�e�͖��ق��ɗp�ӂ��ꂽ11�т́u�R�����v�A���������̢�a�َq�̗��j�N�\�v�u�l���ʎQ�l�����v�A�l���E�َq�̍��ڂ��Ƃɕ��ނ��ꂽ�u�����v�ȂǕt�^���[���B
�@�o��l���̒��ɂ́A�����i44�Łj�A���@�i84�Łj�A�NJ��i196�Łj��@���ҁA���R�̃z�[���y�[�W�ɂ��Љ���������i16�Łj�A�{���i32�Łj�A�������i42�Łj�A���q���G�i46�Łj�A�L�b�G�g�i54�Łj�A��H��敁i104�Łj�A����ƍN116�Łj�A�܂��v�`���̂���䓌��䂩��̐����q�K�i198�Łj�A�����t�i236�Łj�A�X���O�i244�Łj����o�ꂷ��B
�@���ɁA��H��敂̃G�s�\�[�h�����ނ悤�ɁA�����̉��ėg�ߒc�̃G�s�\�[�h�Ƃ��ĐG�ꂽ�u�y���[�Ɛڑ҉َq�\�\�̉��ڂɂ��Ȃٖ��v�i98�Łj�A�u�S���`�����[�t�����������ًZ�p�\���{�ƃ��V�A�َ̉q��ׁv�i100�Łj�A�u�n���X�������������{�َ̉q�\�y�Y�ɂł��Ȃ��̂��c�O!�v�i106�Łj��3�тɂ́A�䂪���َ̉q�������ٍ��̐l�X�ɔ�I���ꂽ���̗l�q�����A���e�B�������ĕ`�ʂ���Ă���A�����Ė��{�E�g�ߒc�o���̑����E�i���̘a�m�َq�̐��X�����ꂼ��}�ł�Č��͌^�ŏЉ���ȂNj����[���R���e���c�ɂȂ��Ă���B
���{�O�O���w�`�h���_�ɂȂ���`�V���M�������e�B�[���l�ނ��~���x�iSB Creative�A2017�N�j
�@�V���M�������e�B�ɓ��B�������ɂ�AI�͐l�Ԃ̓��]�̂قڂ��ׂĂ�������ŁA���̔\�͂�z����₷��i�K�ɂ܂Ői�������āA���̐��E��l�ނ݂̍�������{�I�ɕς���ƌ����Ă���B���̐i���͉����x�I�ɖ����ɑ������߁A���Ă̎Y�Ɗv���Ȃǔ�ׂ悤���Ȃ��قǂ̑�ϊv���Љ�ɂ����炵�A�����E�o�ρE�i�@�E�s���E����E��ÂȂǁA����ɂ͕����E�|�p�̕��삳����AI���l�ނɎ���đ��鎞�オ��������B������̈�ɂ����āu���ӂ̍ő���v��c�����A�u�ő命���̍ő�K���v�̐��E�������ł���AI�ɂ́A�����̉\������߂��Ă���̂ł���B
�@AI�̉\����A���ꂪ�����炷�����������^�I�Ɍ���l�X�����邪�AAI�̎��͂����Ȃǂ��Ă͂����Ȃ��B���Ƃ��A�×�������̒��ɂ́u����܂��v�u�����v�������܂܂�邪�A��X�̃t�@�N�^�[���c���ɂȂ����킹�Ă��̐�������������A���Ȃ�̗��x�Ő^������ɂ߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
�@�₪��AI�́A�����≿�l�ρA�N�w��_�����̗̈�ɂ܂Ői�o���A���l���[�������J��������@���i������A��ɐi�����[�����Â���@���j���������n������Ƃ����B�{�����Ղł͏@���E�N�w�Ƃ`�h�̖��ɂ������̃y�[�W�������ȂǁA�L�͂ȕ���E�̈��[�������������҂��A���p�I�Ȏ�������V���M�������e�B���l�ނɋy�ڂ��e�����c�����s�����Ăɘ_���Ă���B
�@�{���́A�������ɏo�ł��ꂽ���щ�꒘�wAI���l�Ԃ��E�����\�ԁE��ÁE����ɑg�ݍ��܂��l�H�m�\�x�i�W�p�ЁA2017�N�j�Ƃ͑ΏƓI�ȃ^�C�g���ŁA�P��AI�Ɍx����炷���߂̂��̂ł͂Ȃ��A����܂łɂȂ����_����AI�𑨂��A���_�_��������N�B
�@���ҞH���AAI�́A�l�ނɂƂ��āu���l�v�ɂ��Ȃ�A�u�_�v�ɂ��Ȃ�A�u�����v�ɂ��Ȃ蓾��B�l�Ԃ��A���������̑��݂��ǂ̂悤�ɍl���A�ǂ̂悤��AI�ƌ��������������A��������߂�̂ł���A�Ƃ����B
�@�l�ނ̖��������邢���̂ɂȂ邩�A�Â����̂ɂȂ邩�́A�l�Ԏ���Ƃ������Ƃ����߂čl���������鏑�B
���J�������q�E�R�ݏr�j�Βk�w�����ȂƎv����肪���{���_���ɂ���`�ŐV�i���w�������������u�S�ƎЉ�v�x�i�W�p�ЁA2016�N�j
�@�s�����Ԋw�E�i�������w�҂̒��J�������q���ƎЉ�S���w�҂̎R�ݏr�j���̑Βk�`���ŕҏW���ꂽ�{���́A�����߂ƈ���������A���ʂƕΌ��A�O���[�o���Y���ƌٗp�ȂǓ��{�̌���Љ������l�X�ȉۑ���ŐV�̐i���w�E�Љ�S���w�E�]�Ȋw�Ȃǂ���g���ĕ��͂��鏑�B
�@�{���̖ڎ��͉��L�̒ʂ�B
�@��1�� �u�S�����v�u�������v�ł͎Љ�͕ς��Ȃ�
�@��2�� �T�o���i���Y�ݏo�����u�S�v
�@��3�� �u���͂���]�v�̔閧
�@��4�� �u��C�v�Ɓu�����߁v����������
�@��5�� �Ȃ��q�g�͍��ʂ���̂�
�@��6�� ���{�l�͕ς���̂�
�@��7�� �����ȂƎv����肪���{���_���ɂ���
�ȉ��͖{������̔����E��ӈ��p�i�܁A�z�[���y�[�W��Ғ��j�B
�@�Ȃ��l�Ԃ͋�C��ǂ݂����Ȃ�̂��B����́A�q�g�̐i���K���̊��̒��ł͋�C��ǂނ��Ƃ��d�v����������ł���B�܂�A���Ԃ̋C������u�x���A�W�c�̒��a�𗐂����ɍs�����邱�Ƃ́A�����̃z�����ɂƂ��Ă͐����ƒ������Ă����B�w�Z����ŋN���Ă���u�����߁v���A�q�g�̈����S�������炷�̂ł͂Ȃ��B�u�����߁v�́A�܂������ߒ��ɂ���q�ǂ������������҂ƂȂ��Ă���B�܂�A�ނ�͎Љ�̍����A�Љ�ł̐�������m��Ȃ����݂ł���A������w��ł���ߒ��ɂ���Ƃ�����B�u�����߁v�Ƃ͖{���I�ɂ́A�q�ǂ�����������I�ɒ�������낤�Ƃ���v���Z�X�̒��ŕs��I�ɋN���錻�ۂŁA�u�����߁v������Ƃ悤�Ƃ���̂́A�q�ǂ����玩��I�Ȑ�����D�����Ƃ���\���ɓ������̂ł���B�ł́A�u�����߁v���Ȃ����ɂ͂ǂ�������悢���B�W�c������ƁA���Ȃ炸�u�����߁v�����N����̂ł��邩��A�X�l�f����悢���Ƃ����A����ł͍��{�I�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�u�����߁v�́A�W�c�����̒��ł͂��ł��A�ǂ��ł��N���肤�邱�ƂŁA�q�ǂ��̐S���r�p��������N����̂ł͂Ȃ��i154�`158�Łj�B
�@�Ђ�������͋��ɂ̑ΐl�ˑ��ǂł���B�����āu�l��`�������������ʁA���҂Ƃ̌q����������A�����������v����ł͂Ȃ��B��������͎Љ�ɍv�����Ȃ�����ǂ��A�Љ��̃T�|�[�g�͎Ă��邩��ł���B�����R���ň�������������A�����Ƃ����Ԃɉ쎀�����Ă��܂��B�v�����E�C�z�肪���{�×��̔����Ƃ��镗���ł���ɂ��Ă��A�����w�͂������݈ˑ��̂ق��������Ǝv���l���A���ꂾ�������Ă���Ƃ������Ƃł���B�����Љ�l��`����������̂ł͂Ȃ��A�����������j�[�N�����D�ꂽ�\�͂́A�u���I�v�ł��邯��ǂ��A�����āu���ȓI�v�u���I�v�ł��邱�ƂƓ��`�ł͂Ȃ��B���҂����邩��u�����炵���v������̂ł���A������l�������Ȃ����E�ł́u���v��u�����炵���v���Ȃ��B�u���ǂ�����v���Ƃ͗ϗ���d�v�ł��邪�A�u���I�ł���v���Ƃ͗ϗ��Ƃ͖��W�Ȃ̂ł���i227�`228�Łj�B
�@���{�Љ�̍������Ƃ���́A���ׂē����Ō�낤�Ƃ��邱�Ƃɂ���B���������ɂȂ��Ă��܂��A�����ᔻ���邱�Ƃ͋�����Ȃ��u��C�v����������Ă��܂��B�����ŃV�X�e����ς��悤�Ƃ���ƁA�u���l�v�u����ҁv���������B�����m�푈�̓��{�͂܂��ɂ���ł������B�v�����͊m���ɑ�ł��邪�A������o�ϊ����̕���܂œK�p�����Ƃ��������Ȃ�B�܂�A���҂d���邱�Ƃ��ŗD��ɂȂ�A����������A�l���]�����邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ȃ�B�������A�{���͌��S�ȋ������s���邱�Ƃɂ���āA�j�����ʂ⍑�Ѝ��ʂ͂Ȃ��Ȃ�̂ł���i240�`241�Łj�B
�@�ǂ�����ρA�u�т��т��v�����ɗF�l������悤�ɂȂ�̂��B����ɂ́A�������u�\���\�i�v���f�B�N�^�u���j�Ȑl�ԁv�ɂȂ邱�Ƃł���B�����瑊��̐S�𐄂��ʂ낤�Ƃ��Ă��A�{���ɑ���̐S�̂��ׂĂ��킩��킯�ł͂Ȃ��B�ł��A�������g���u������₷���l�v�ɂȂ邱�Ƃ͉\�ł���B�����̉��l�ς�l���Ă��邱�Ƃ�����N���ɂ��āA�����т����s���K�͂Ɋ�Â��čs���i���s��v�j����l�ԂɂȂ�B�������邱�ƂŁA�u�M���v����鑶�݂ɂȂ�B���ꂪ�u�����v���u�F�v�𑝂₷�ŗǂ̕��@�ł͂Ȃ����B����͂��Ȃ킿�A���l�Ǝ����̈Ⴂ�m�ɂ���Ƃ������ƁA����������A�u���I�ł���v�Ɠ����Ɂu���l�������}����v�Ƃ������ƂȂ̂ł���i255�`257�Łj
�@���̒��̂������ς���ɂ́A�w�Z����̕ϊv���d�v�ɂȂ�B����͒P�Ɋw�͂̌��ゾ���ł͂Ȃ��A�Љ�̍������狳���Ă������Ƃ���ł���B���N��̎q�ǂ������ŋ�������邱�Ƃ���߂�Ƃ������Ƃ���n�߂Ă������B���܂̊w�Z����́A�u�q�g�v����l�O�́u�l�ԁv�Ɉ�Ă邽�߂ɁA�q�ǂ������ɉ���^���A�����K�v���Ƃ����l�@���s�����Ă���悤�Ɏv����B�W�c�̒��ɂ���Ȃ�����A�W�c�ɑ������ꂸ�ɋ@������R�ɒNj����Ă����ɂ́A�܂������Ȃ�́u�s�������v���m�����邱�Ƃ��̐S�ł���B����̖����Ƃ����̂́A���ꂼ��̐l�ԂɁu�R�A�v�ɂȂ���̂���������Ƃ������ƂȂ̂��Ǝv���B����́A�@���ł��������A�N�w�ł��������A���ӎ��ł������B���邢�͍������Ɋ�Â��ė��v��Nj�����ł������B�v�́A���l���猩�āA���̍s���Ɉ�ѐ����������邩�ۂ����u�M���v�u�]���v��z����Ō��ɂȂ��Ă���B�u�݂�Ȓ��ǂ����悤�v��������j�ɂ��ẮA�R�A�����o���Ȃ��\��������i267�`268�Łj�B
��w�̗��j������l�����ҁw�킩��E�g�ɂ����j�w�̊w�ѕ��x�i�匎���X�A2016�N�j
�@�����i�j���j�̈������A�T�����E�������E�w�p�_���̓ǂݕ��A�����_���̏������ȂǁA���j�w�����Ɍ������Ȃ����U�ƍH�v���w�삷�鏑�B
�@���j�w�����̑ΏۂƂȂ镪��́A�l���Ȋw�E�Љ�Ȋw�E���R�Ȋw�E�`�����w�ȂǂƂ�������������E�̈�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��ΐ����A�o�ρA�����E�|�p�A�Љ�A�S���A�@���A�N�w�A���w�A�����A�����A��w�A�y�A�H�w�A���w�A���R�A�@�B�A�Y�ƁA�_�ƁA�q�{�A�l�ÁA�̈�A�V���A�C�m�A�C�ہA�F���A���A�j�G�l���M�[�ȂǑ���ɘj��A�ނ��낻����Z��������ׂ��w��̌n�ł���Ƃ������ꂩ��A�u�����̊w��v�ł�����j�w���w�Ԃ��Ƃ��A�ŏI�I�ɂ́u�l�ԂƂ͉����H�v�u�����Ƃ͉����H�v�Ƃ����₢�����ɂ��ǂ蒅�����̂ł���Ǝ咣����B
�@�܂��A���j�w�Ƃ͗��j��Ώۂɂ���u�Ȋw�v�ł���A�u�Ȋw�v�ł���ȏ�A�u�Ȋw�I���@�v�Ɋ�Â����w�p�I�ԓx�����߂���ƌ��y�B�u�Ȋw�I���@�v�Ƃ́A�u�������E�������A�V���Ȓm���āA���̐������𗧏��Ă����v���Z�X�v�ŁA�l���Љ�Ȋw�̏ꍇ�́A�Ώۂ��ώ@���遨�l�@���遨�l�@�������ʂ�\������A�Ƃ����v���Z�X���Ƃ�B���̃v���Z�X���Ƃ�悪��ɂȂ炸�A���҂������E���ӂł���悤�ɂ��邽�߂ɁA�@�_���������A�A�������r���A�B�q�ϐ����v�������Ǝw�E�i67�ňȍ~�j�B
�@���܁A�@����B�̓��e����̓I�Ɏ����Έȉ��̒ʂ�ƂȂ�B
�@�_��������
�@�l���Љ�Ȋw�ł́A�u�����v�u�����v����ƂȂ�B���̕����⎑���������������u�����ᔻ�v�ł���A���ꂱ�����A�l���Љ�Ȋw���u�Ȋw�v�ł����̗v���ƂȂ��Ă���B�����������ᔻ���s���A�����̘_�����Ɛ��������͂��邱�ƂŁA���҂ɑ���������ƍ��������������邱�Ƃ��ł���B�ʐ����̕������������ɗp����ƁA�����Ԃ̐��������}�ꂸ�A�_�����j�]����B���̂悤�Ȃ��Ƃł́A�����͂��Ȃ��B
�A�������r��
�@�l���Љ�Ȋw�ł́A���Ȃ̎咣�������⎑���Ɋ�Â��������ɗ��r���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�B��ϓI�q�ϐ�
�@�l���Љ�Ȋw�ł́A�����E�����Ɋ�Â����F������߂́A�Ƃ��ɂ�������鑤�̎�ς���ɓ��荞�܂�������Ȃ��B���������ď��F�́A���҂̓Ƃ�悪��ɂ����Ȃ��Ƃ����ᔻ���Ȃ���邱�Ƃ�����B�������Ȃ���A���j�F���́u���݁v����l�Ԃ́u�ߋ��v�ւ̃A�v���[�`�ł���A�J��Ԃ��₢�����A�ǂݒ������̂ł���B�܂�A���̎��X�́u���݁v����l�Ԃ́u����̎�ϓI�S�v���炵���ڋ߂ł��Ȃ��B���̂悤�ɁA�l���Љ�Ȋw�ɂ�����u�q�ϐ��v�Ƃ́A��鑤�́u��ρv��K�R�I�Ɋ܂݂����̂ł���A������u��ϓI�q�ϐ��v�ƌĂԁB
�@���āA�l���Љ�Ȋw�́A���R�Ȋw�E���p�Ȋw�ɑ��āu���ɗ����Ȃ��v�ƕ]�����ꂽ���Ƃ�����B�M�҂́A����ɑ��āA�g���r�Ǝ��̎咣�i�w�u���n�w���p�~�v�̏Ռ��x�j�������Ĕ��_�B�u���ɗ��v�Ƃ͓�̎���������A��͖ړI�����łɐݒ肳��Ă��Ă�����������邽�߂̕��@��������u�ړI���s�^�v�A��߂́A���l��ړI���̂����o���u���l�n���^�v�ł���A�O�҂͗��n�̓��ӕ���ł��邪�A�ړI�≿�l�����̂��̂��ω������Ƃ��ɖ��ɗ����Ȃ��Ȃ�\��������B����Ō�҂́A�u���l�̎��𑽌��I�ɑ����鎋���v���������u�m�v�ł���A��ɕ��n�̓��ӕ���ł���Ƃ��A�X�ɉ����Ĉȉ��̂悤�Ɏ咣����B
�@�l���Љ�Ȋw�́u���l�̎��v�����o�����ƂɊ�^����Ƃ������i�������Ă���B���̂��߂ɂ́A�u���l�̎��v�����݂���p�ɂƂ���邾���̊w��ł́A�ʂ́u���l�v�ݏo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���j�w�����o���u���l�v�u�n�����v�͂��̓_�ɐ[����������Ă���B���j�w�́A�u���݁v�̎�����ʂ��āA�u�ߋ��v�̎�����F������w��ł���B�����āA�u�ߋ��v�u���݁v�Ƌ敪���āA�u�����v��F������B���́u�����v�́A�u�ߋ��v�u���݁v�Ɋ֘A�Â����Ă��邪�A�����ɁA�Œ�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ω�������̂ł���B���j�w�́A���̂悤�Ȏ��ԔF���������Ă���B���j�w�́A���̂悤�Ȏ��ԔF���̂����ɗ����A�u�ߋ��v�u���݁v�u�����v���敪���āA���ꂼ��قȂ������̂Ƃ��ĔF������B�܂��A�ΏۂƂ���n������E���ɍL�����Ă���B
�@���̂悤�Ȏ��ԁE��Ԃ̔F������A���j�w�́A���ꂼ��̎����E�n��́u���l�v�̑��l���𖾂炩�ɂ���B�Ƃ��ɁA���݂̉��l�Ɖߋ��̂���Ƃ��r���A���̕ω���ՂÂ��邱�Ƃ��ł���B�����āA���ꂪ���ʂƂ��āA���݂ƈقȂ�V�������l�̑n���ւƂȂ����Ă������ƂƂȂ�̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���j�w�́A�l���Љ�Ȋw�̂Ȃ��ł��A�ߋ��▢���ւ̃��[�`�̒�������ł��L���X�p�����������w��ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���i71�`72�Łj�B
�@
�{�� �^���w�S����Ă邱�ǂ������m �u�b�_�������x�i�i�����X�A2012�N�j
�@�q���ɓ`�������u�b�_�̌��t���W�߁A���ՂɏЉ�����B�Q�T�O�O�N�̎����o�āA�u�b�_�̋������A�q�������̗D�����Ǝv�����̐S�A�������������S����Ă�B
�@�u�����������Ƃ����Ă��܂�����A���̉��{���������Ƃ����悤�v�u�ق��̐l�Ƃ̋������������ɏ����Ƃ��厖�v�u���܂��邱�Ƃ��ꏊ��������낤�v�u���\�Ȍ��t�͎g��Ȃ��A�����ɂ�����Ȍ��t���������Ă��邩��v�u�y�������Ƃ݂͂�Ȃŕ��������Ă�����Ȃ���v�u�{��Ȃ����Ƃœ{��l�ɏ��Ƃ��A�R�����Ȃ����ƂʼnR�����l�ɏ��Ƃ��v�u���ꂽ������Ďd�Ԃ�����ƁA�����Ƃ��������̌J��Ԃ����v�u���������́A�������傤����߂�������l�������v�u�{���Ɍ����l�́A���Ȃ��ꂽ��A�ق߂�ꂽ�肵�Ă����������Ă���v�u���ꂩ�����܂�����A���ꂩ�����������肷��̂́A���������Ă͂����Ȃ����Ɓv�c�ȂǂȂǁA�w�_���}�p�_�i�@��o�j�x�ȂǂɊ�Â����u�b�_�̌��t�ɂ́A�l���������L���ɍK���ɐ����邽�߂̒m�b���l�܂��Ă���B
�@�u��邢���Ƃ��ĂȂɁH�v�u��Ȃ��Ƃ��ĂȂɁH�v�u���肪�����v�u���������܁v�Ȃnj�����̃R�������[���B
���R�N�ƊďC�w������̂ӂ��� �Ȃ��H�ǂ����āH�x�w���E������̂ӂ��� �Ȃ��H�ǂ����āH�x�i�������X�A2013�E2014�N�j
�u�����킹�Ƃ͉����v�u�����Ƃ͉����v�u�l�ԂƂ͉����v�u���̂��Ƃ͉����v�u���ƂȂƂ͉����v�u������Ƃ͉����v�u�Ƒ��Ƃ͉����v�u���[���Ƃ͉����v�u�₳�����Ƃ͉����v�ȂǂȂǁA�q�ǂ���������łȂ��A��X��l���m���Ă���悤�ŏ�肭�����ł��Ȃ��l�X�ȁu�ӂ����v�ɂ��āA���ʓI�ȃC���X�g����g���Ă킩��₷����������B�{���I�����ՓI�ȐS�̖₢�ɓ�����X�^�C���́A�w�u�b�_�������x�ɂ��ʂ�����e�ƂȂ��Ă���B
�@�ďC���������Ȋw�ȋ��Ȓ������̑��R�N�Ǝ��́A�����͌����ĂЂƂł͂Ȃ������m��Ȃ����A�e�q�Řb��������_�@�Ƃ��ė~�����ƒ�Ă���B
�����B�ƒ��w��l���������q�ǂ��̊댯�M���`�����߁E���E�E�s�o�Z�E��s�E���E�w�ƕs�U�E�F�l�W�x�i�w���o�ŁA2014�N�j
�@�����߁A�s�o�Z�A���E�A���̔Y�݂ȂǁA�����Ȏ����̐��N�̎~�ߕ���S�̃P�A�ɂ��ĐS���w�I�A�v���[�`�Ŕ������B���N�̖��s����10��ɕ��ނ��A�댯�M���iSOS�j�́E�����A���s���̌�����S���w�I�ɉ𖾂��A�w�Z��ƒ�ł̑��������E�����Ή��E�����w���̋�̍�����B����]���ҁE�ی�҂̌��C��⋳�瑊�k�̃e�L�X�g�Ƃ��Ă����p���l����B
�@���ɁA���҂́A�u���E�v�̖��ɂ��āA���E�҂̔w���10�l�̖����҂��A���̔w���100�l�̔O���҂�����Ǝw�E���A������u���E�h�~�̃J�E���Z�����O�v�����B�N����킸���E��]�̂���҂��瑊�k�����ۂɂ́A�������������ɁA�E�ϋ����b�����ƁA�����đ���̔����m�����A�����I�����������ƁA�ǓƂɂ����Ȃ����Ƃ��̐S�ł���Ƃ���B������̈ӌ����q�ׂ���A�u����������ǂ��ł����v�Ƃ��̏����E��ĂȂǂ̓^�u�[�ŁA����Ɍ��������Ǝv���Ă��A�u���Ȃ��͊Ԉ���Ă��܂��v�ȂǂƂ������t�́A�����Ă̂ق��Ƃ̂��ƁB�J�E���Z���[�́u�S�̕֊�v�ɓO����K�v����͐�����B
����ɕێq���w�L���鏗 ����Ȃ��j�x�i�}�����[�w�����ܐV���x988�A2012�N�j
�@�l�H�m�\�i�`�h�j�v���O���~���O�̌����҂��������҂��A�]�Ȋw�̕��삩��j���̐��������B�]�̐����A�����]�E�j���]�̎戵�������A�v�w�Ƃ������̂�A�E�q�̐l���P�Ɣ]�N��ȂǁA�]�̍\����m��s�������������͂̑��l�҂ɂ���āA����N��ňقȂ�]�̓����Ɋ�Â��A����Ɋ��Y�����j���]�_���W�J�����B
�@�ȉ��A�{������S�Ɏc�鎊���̈ꕔ����ӈ��p�B�Ȃ��A�z�[���y�[�W��҂̘_���u栚g�ɂ݂���@���l�̉Ƒ��ρ\�v�w�Ɋւ�������𒆐S�Ɂ\�v�i2004�N�j�������ĎQ�Ƃ��ꂽ���B
�@�j���̔]�́A���u�Ƃ��Č����Ă�A�܂������ʂ̑��u�ł���B�i�����j���R���i��_�́A�l�ނɕK�v�Ȋ�����^����ɕ����āA�j�����ꂼ��̓��W���ɓ��ڂ����炵���B��������̓��W���Ƀn�C�u���b�h�ɔ[�߂悤�Ƃ���ƁA���W���̗e�ς��i�i�ɑ傫���Ȃ邵�A�Ƃ����̔��f�����b���x��邱�ƂɂȂ�B�l�ނƂ����n�Ō���A����Ȃɍ����I�ȁu��̕ۑ��v�V�X�e���͑��ɂ��肦�Ȃ��B���̐��ɓ�̔]������Ƃ������ƁB�������j���́A��g�Ŋ����̂ł���B���̓����͑傫���Ⴂ�A�Ⴄ����C��������ǁA�Ⴄ���炱���g�ވӖ�������B�i48�`50�Łj
�@�Ȃɂ��A�ߋ�������Ȃ̂��鏗���]�ł���B���������A���ɂ̂��Ƃ�����������A�����i���A���������A���̂��Ƃ�����������̂悤�ɑz�N��������B�i�����j�Ȃɑ��ĂȂ�A�u���݂̖��X�`�����ނ��̎O�\�N�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ��݂������̂��A��[���B�݁X�Əd�˂Ă������Ƃ��A�v�w���J�Ƃ��Đ��A�������Ƃ��A�v�̂��ƂŒm�炳���B�ȂɂƂ��ẮA���Ƃ���J�߂Ă���Ȃ��Ă��A���ӂ����ɂ��Ă���Ȃ��Ă��A�_�C�������h�������Ȃ��Ă��A�l�����m�肳�ꂽ�����̏u�Ԃ��B���܂��Č��������Ȃ��̂ɁA���X�`�����͈���ł��������A��肪�Ђǂ��̂Ɂu���X�`���Ȃ��̂��v�ƌ����ċ������Ӂc����ȃl�K�e�B�u�Ȏv���o���A���ׂĂ����v���o�ɕς��B�u���̐l�ɂƂ��āA���̖��X�`�͂���Ȃɑ厖�Ȃ��Ƃ������̂ˁv�ƈ������ł܂Ƃ߂邩��ˁB�������Ƀp�^�p�^�ƂЂ�����Ԃ�A�I�Z���Q�[���̋t�]���̂悤�Ȃ��̂��B�i107�`108�Łj
�@�j�̍ȂɂȂ�A���邢�͒j�̕�ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�u�����ς�炸�A����@���ʼn��₩�ɕ�炵��a���l�ɂȂ��Ă��v�Ƃ������Ƃ��B����ȏ�ł��Ȃ��A����ȉ��ł��Ȃ��B����ȁu�����ς��ʁA��炵��a���l�v�ɐӖ����ʂ��������邱�Ƃ��A�j���]�Ɉ��J��^���A�����|�C���g���~��ς����Ă����B�������āA�����̌㔼�ɂ́A�j���]�̊m�M�̂ق����[���Ȃ�̂ł���B�Ȃ́u���̐l�������Ȃ��v�Ŏn�܂�A�v�́u���̐l�������Ȃ��v�ŏI���̂������Ȃ̂�������Ȃ��B�i169�Łj
�@�v�w�͍��d�˂閈�ɁA�s�v�c�Ȉ������Ђ��Ђ��Ɨ��܂��Ă���B�����I����āA��킭�B�]�Ȋw��A�v�w�Ƃ������̂�͂��̂悤�ɐv����Ă���B���e��Ȃ�����Ƒ��̊Ԃ̑��Ȃ��y���ނ̂��l�����Ǝv���Ă݂�A����Ⴄ���Ƃ��Ȃ��Ȃ��ɂ������낭�Ȃ��Ă���B�i�����j���̉����̉ʂĂɕv�w�̈��͂���B�����̌�ɕ���������������A�����������̐�ɉ���������A�����̉ʂĂɁA�s�ӂɎ����ΜԚL����قǂ̈�����������i�͂��ł���j�B�i179�`180�Łj
�@�����āA���̍Ŋ��̂Ƃ��A�E���Ǐ����A�]�ɃG�l���M�[���ł���u�h�E�����͂��Ȃ��Ȃ�ƁA�_�o�n�ْ̋����ɘa����]���z���������o�āA�]�́A���|����ɂ݂������������B�]�́A�l���̍Ō�̂��̓��܂ŁA�D�������̓��̂���G�X�R�[�g���Ă����B�������͔]�Ƃ������u�Ə��ɕt�������A�Ŋ��́A���ׂĂ��䂾�˂�ڂ����̂ł���B�i194�`196�Łj
�R�c�����Y���w�l�ԗՏI�}���x�S4���i���ԏ��X�w���ԕ��Ɂx�A2011�N�j
�@�w�l�ԗՏI�}���x�S4���́A1986�`1987�N�ɂ����ē��ԏ��X���o�ł��ꂽ�w�l�ԗՏI�}���x�S3���̐V���ŁB�����{���\�����O�����Ƃ̎R�c�����Y�i�R�c����j���A�������w��菬���x�i1978�N9�����`1987�N2�����j�̘A�ڍe�����A�p�Y�E�����E�@���ҁE�����ƁE��ƁE�|�p�ƁE�|�\�l�ȂnjÍ������̒����l923���̐����l�E���ɗl�����S�N��ɕ��ׂďЉ�����B�ÓT�`��w�ғ��L�̎��_�ŁA�j����`���Ɋ�Â��ė��j��̐l���̐��U�Ƃ��̎��ɍۂJ�ɐ����Ă����B
�@�{���ɂ́A���R�z�[���y�[�W�ł��G�ꂽ���`�o�E�k�����@�E�{���E���I�����E���������E���q�����g���]���Q�E���q���G�E�Ό��Ύ��E��H��敁E�����k�ցE�a��h��i�f�N��B�Ȃ��e�����N���瓖�R�T�C�g�̎�ȏЉ�y�[�W�ɃW�����v�\�j�Ȃǂ��o�ꂷ��B
�@�Ȃ��A�{���Љ�̃G�s�\�[�h�����I�����w�Ǔǐl�ԗՏI�}���x�|�p�ƕҁA����łƂȂ�w�Ǔǐl�ԗՏI�}���x�S2���A�w�}���K�ŒǓǐl�ԗՏI�}���x�A�w�}���K�ŒǓǐl�ԗՏI�}���x�������g�����҂Ȃǔh���R���e���c�������o�ł���Ă���B
�c�㑾�G�ďC�w������x�w�т����u�b�_�̋����x�i�����ЁA2006�N�j
�@�}����L�x�ɗp���āA�u�b�_�̐��U�Ǝv�z�A�������c�̌`���A�C���h�E�����E���{�̎O�������̗��j�Ȃǂ��T���B�킩��₷���ł́A���̕�����发�̒ǐ��������Ȃ������B
�@���V���[�Y�͌��݂͐�łƂȂ��Ă��邪�A���Ђ́u���j���������낢�v�V���[�Y�Ƃ��ĕ��y�ł��Ĕł���A�w�}���u�b�_�̋����x�i2010�N�j�Ƃ��ă��j���[�A������Ă���B�Ȃ��A�ق��ɂ��w�}�� ���{�j�x�w�}�� ���E�j�x�w�}�� ���E�̏@���x������B
���@�I�v�ďC�w�������t�͂����u��⎮�H���@�v�x�i��w�̗F�ЁA2005�N�j
�@���C�́A�E�ϗ͌��@�Ɏn�܂�A�����K���a�A��̉��A�T�i���j�A�A�����M�[����������i�K���j�Ɏ���܂ŁA���̌����̑唼�͓��{�l�̐H�����ɂ��邱�Ƃ��w�E�A�Ȋw�I�E���ؓI�ɓ��{�l�ɓK�����u�H�v�݂̍������鏑�B
�@�n���e�n�ɐ��������g�����l�ނ́A���̓y�n��C�y�ɓK�����H�������m�����Ă����B���ђn���Ő�������l�X�́A�̂����߁A�������߂�u�z���v�̐H�i�i���ށE���ށj��ێ悵�A�����E���������H���邱�ƂŃr�^�~���E�~�l�����Ȃǂ̉h�{���Ȃ���Ԃő̂Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł����B�G�ߖL���ȉ��ђn���Ő�������l�X�́A�u���f�v�̐H�i�i���ށE���āj��H���̒��S�ɐ����A��ؗށE�C���ށE���ނɓY����ȂǁA�A���E�z���̐H�i���o�����X�悭�ێ悵�Ă����B�M�ђn���Ő�������l�X�́A�̂��₵�Ċɂ߂�u�A���v�̐H�i�i�ʕ��E�R�[�q�[�E�����E�˗ނȂǁj���D��Őێ悵�Ă����̂ł���B���҂́A�����ɁA���{�l�ɓK�����H�����̃q���g������Ƃ����B
�@���ɁA���{�l��30�`40��̃K�����҂̐H�������q������ɂ܂ł����̂ڂ��ĒǐՒ����������ʁA���H���u�A���H�v���S�̌X���ɂ��邱�Ƃ��킩�������Ƃ������A�K���ɂ�����₷���̎��̂ЂƂɑ̉���35�x�ɉ�����悤�Ȓ�̉������邱�Ƃ��w�E����B����͑̉���������u�A���v�̐H��������U�������Ƃ����B���{�l�ɂƂ��ẮA�Q�N���ɂƂ钩�H�ɂ́A����̑̉��𐳏�ɖ߂������̂���ĔсA�̓��̓őf����菜���J���E���𑽂��܂ޖ�ؗނƈꏏ�ɒ������ꂽ�哤�`���̖��X�`�A���̒������{�l�ɓK�����A�����R���̓��_�ۂ̑�\�i�Ƃ��Ēm����Е��ȂǁA���R�����͂�Ɖu�͂����߂�H�ނ̎�荇�킹���悢�Ƃ���B
���e�I���w�]�Ȋw�҂�������q�ǂ��̒n�����悭������@�x�i�f�B�X�J���@�[�A2009�N�j
�@�ŐV�̔]�Ȋw�ɂ��ƂÂ��A�l�Ԃ̒n���͂����コ�����{�I�\��������B
�@�u�n���́v�Ƃ́A�������ؓ����Ăčl���邱�Ƃ̂ł���\�͂̂��ƁB�ߔN�ł́A�r�W�l�X�}���̕K�{�̃X�L���Ƃ��Ă����ڂ���Ă���B
�@�u�n���́v�́A��`�������ɂ���č��E����A���̓����́A�b�B����Έꐶ�U�������邱�Ƃ�͐��B���R���Ă���킯�ł͂Ȃ����w���ɏ]���Ȃ��A�ۑ�⊈�����������Ăčs���Ȃ��A�����������Ȃ��A�ɒ[�ɖ����ł���A���Ԃ�҂ĂȂ��c�ȂǂȂǏ��P�v���u�������������鎅�����n���͂ɂ���Ɛ����B
�@�u�n���́v�́A�]�̍�Ɨ̈�ł���u���[�L���O�������v�����O���t�ƁA�u���C�v�������o������̂Ƃ̊����ɂ���Č��シ�邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B�u���[�L���O�������v�Ƃ́A�L��������ꎞ�I�ɓ\��t���A�����̍�Ƃ�����u�]�̃������v�ɂ��Ƃ����܂��B���̃��[�L���O�������́A�X�g���X�̂Ȃ��P����Ƃ����Ă��鎞�͒��É����Ă��܂��B���É����Ă���Ƃ������Ƃ́A�]�̑O���t�͗��������Ă������ŁA�h�����Ȃ����߂Ɏ��͊������~���Ă����Ԃł���Ƃ������܂��B�q���Ɍv�Z�������鎞�ł��A���̎q�̃��x�������̊ȒP�Ȍv�Z�������Ă��鎞�́A�O���t�͊��������Ă��܂���B����ŁA���������点��ƁA�O���t�͓r�[�Ɋ������J�n���܂��B�ł��Ȃ��ł������Ă��鎞�̂ق����A�]�����������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�n���͂�b����|�C���g�́A���̎q�ɂƂ��āA�u�������A�����ł���v�Ƃ������C���������ɐݒ肷�邩�A�Ȃ̂ł��i58�Łj�B
�@�u���C�v����������ɂ́A��̓I�Ŏ��s�\�ȍs���̌`�Ŗ�����������悤�ȁA�������Ȃ��K�ȖڕW�̐ݒ肪�s���ł��B�i�����j�܂��A�ڐ�́u�ڕW�v�̐�ɂ́A��莟���̍����u�ړI�v�̐ݒ���K�v�ł��B�l�Ԃ̍ŏI�ړI�́u���̂��߁A�l�̂��߂ɂȂ�v���ƁB�S�[���l�S�V�G�[�V�������s���Ƃ��̔w�i�́A���ꂵ������܂���B�U�P�ł��A�p�t�H�[�}���X�ł��Ȃ��A�l�̂�����ړI�̐�ɂ́u���̂��߁A�l�̂��߂Ɂv����������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�q���̂��悤�Ƃ��Ă���ړI�▲���A�ǂ����Łu���̂��߁A�l�̂��߂Ɂv�ɂȂ����Ă��Ȃ���A�e�q�̃��`�x�[�V�����͂�����͊����Ă��܂��܂��B�u�����̂��߁v�u���ׂ��̂��߁v���́A�u���̂��߁v�u�l�̂��߁v�Ƃ����ӎ���S�ɕ`�������A�w�сA������������A�W���͂��A�L���͂����܂�킯�ŁA���ꂱ�����A�O���t�̓����A�u�l�炵���v���������ő�̕��@�A�n���͂�{�����@�Ȃ̂ł��i94�Łj�B
�@
�{��G�^���w�������~�����{�̋���x�i�p�쏑�X�A2003�N�j
�@�`���I���_������������{�̋�������S������Ƃ̌��n����A���{�̂���ׂ�����̎p��B�l���E�����E���R��Ώd����A�����̐l�Ԓ��S��`�̓��{�̋���Ɍx����炷�B
�@����͐������_���ȑ厖�Ƃł���B�u�O���������Ďt�̉e�܂��v�Ƃ�����߂�����Ƃ���ɁA���t�݂͂�����݂𐳂��A�l�i���݂����A������݂Đ��k�͐l�ς̊�b���w�Ԃ̂ł���B���ꂪ���{�̓`���I�ȋ���̐��_�ł������B���̋B�R�i������j����t��̂���ׂ��l�ԊW���A���A�u�����I���v�̈ꌾ�łԂ����킵�Ă��܂����̂��B�i�����j���t�͎��ɂ͐��k�̖ڐ��ɗ����Ƃ��K�v�ł��낤�B�����A�����鑤�̖ڐ����͂邩�����Ƃ���ɂȂ��āA���k�͉����߂����悢�̂��B�u�ߑ㉻�v�̃X���[�K���̂��ƂŁA�����̋���̎S����������͖̂��炩�ł���B�قƂ�NJʼn߂���Ă��邱�Ƃ����A�u�ߑ㉻�V�X�e���v�̋���ׂ������́A���̒��ł͗�V���������l�ԂƂ��Ă̐l�i���C��������؍l������Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@���̓��{�̎q���̑��Ԃ�A�������t�����A��V��@�̌��@�A�펯�̂Ȃ��͓��{�j��A�ň����B�ł��A�����ƈ����̂͐e�̂ق����B�e�͎q�������炷��ȏ�A�݂�������l�i�̌�����͂���˂Ȃ�Ȃ��B�q���ɑË����Ă͂����Ȃ��B�l�͐e�ƂȂ����當���I�`����S�����݂ƂȂ�̂ł���B����ɑ��Ďq���͔����������邩������Ȃ��B���ꂪ���Ɍ��S�Ȑe�q�̂�������B���̊����̒��Őe���q���������Ă����̂ł���B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��A����̓��{�Ȃ̂��B�e�͖��������Ăł��A�q���̂͂邩�y�т����Ȃ������ڐ������ׂ��Ȃ̂��B�q���ɛZ�тĂ͂Ȃ�Ȃ��B�q���ɖڕW����������ׂ��Ȃ̂��B�q���Ɠ����ڐ��ł͂����Ȃ��B�i41�Łj
�@���a��\�ܔN���܂ł͒��w�Z�ł��w�@���ƎЉ���x�Ƃ������ǖ{���p�����A�K�ȏ@�����炪�s���Ă����B�Љ�����c�ނ����Ő�����o�ς̎d�g�݂��w�Ԃ��Ƃ���ŕK�v�ł���̂Ɠ��l�ɁA�@���ɂ��Ă��w�Ԃ��Ƃ��K�v�ł���A���ꂪ���R�Ƃ���Ă������オ�������B�������A������������ɂ�����@������͊��S�֎~�Ƃ����Ȃ����B���̍����͓��{�����@�ł���B���\���O���́u���y�т��̋@�ւ́A�@�����炻�̑������Ȃ�@���I���������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ɒ�G����Ƃ������R�ŁA���ꂪ���i�ɓK�p�����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�ǂ��Ȃ������B������͊����ɉ��̎���Ɖ������B����͌����Č��������ł͂Ȃ��B���́u���@���v�ł͂Ȃ����B�ƒ{��쐶�����ɂ͑P�������Ȃ��B����������S����������߂��Ȃ��B�`�����x�̒~�ς��c����h���S���Ȃ��B�l�Ԃ͂���Ȓ{���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ�����̂��{���̋���Ƃ������̂ł���B�i26�Łj
�@���{�́A���S�̂Ƃ��ĉƑ���`�����������Ă���H�ȍ��Ȃ̂ł���B�Ƒ��Ƃ����̂͏I�g�ٗp�ł���B�ނ��\�͎�`�ł��Ȃ��B�D�G�ȑ��q�����܂ꂽ����Ƃ����āA�ׂ̉Ƒ��ɃX�J�E�g���ꂽ��A�Ƒ����m�����������悤�Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B�Ƒ��͔N������ɂ��܂��Ă���B���Ƃ����g�s���ɂȂ낤�ƁA���c������̂ق����q�⑷�����͂邩�ɒf�R���炢�̂��B�Ƒ��̂Ȃ��ł͒k�������C�ōs����B�������b�������Ō��߂Ȃ��悤�ȉƑ��͉Ƒ��̋@�\���ʂ����Ă��Ȃ��Ƃ����邾�낤�B�Ƒ��̒��ɂ͖����`�͂Ȃ��B�Ƒ��̒��ł́A���������͎�`��������`���Ȃ��B�Ƒ��̐����͕����ł͂Ȃ��B�e�ƐԂ�V�������ł���킯���Ȃ��B�u������[�v�ʼnƑ��̒������߂���悤�Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B�Ƒ��̒��ł͕��͕��̖�ڂ��ʂ��A��͕�̖�ڂ��ʂ��A�q�͎q�̖�ڂ��ʂ��B����������A�݂�����́u���v�A���Ȃ킿�u�g���v�ɊÂA���̍őP��s�������Ƃ͂�����O�̂��Ƃł���B����͌����ł��`���ł��Ȃ��B�܂�A�Ƒ��̒��ɂ́u�ߑ�I�Ȃ��́v�����肱�ޗ]�n���Ȃ��̂��B���S�ȉƑ��Ƃ́A���ɕ����I�g�������ۂ���Ă���Ƒ��Ȃ̂ł���B�⑫����ƁA���Ƃ��đ��d����̂�����̖����`�Љ�ł��邪�A���n�Ȏq���̌����̂܂ܑ��d���Ă��܂��悤�ȉƒ�ł��^���s��ꂸ�A��ؐl����Ă鉷���ƂȂ��Ă��܂��ł��낤�B����́u�O�ߑ�I�v�Œp�����������Ƃ��낤���i197�Łj�B
�G���}�[�q�O���[�o�[�����w�C�G�X�͕����k�������H�x�i�����ɁA1999�N�j
�@�h���I�ȕW�肪����ꂽ�{���́A���[���V�A�嗤�̓����̕����𗬂̒��ŁA�������C�G�X�ɗ^�����e�����ڍׂɕ��͂����������B���C�G�X�ɂ݂���ْ[�v�z�i���[�}�E�J�g���b�N�����݂Ăْ̈[�v�z�j�̉e���́A���邢�́w�_���}�p�_�i�@��o�j�x�ɐ������悤�ȕ����v�z�ɋN��������̂ł͂Ȃ����Ǝ咣�B
�@�{���̓��M���ׂ��_�́A���҂̜��ӓI�Ȏ����̈������ɑ��锽�_�⒘�҂��Љ�Ȃ��������������āu�C�G�X�����k���v���]����_�����A�{���̂��Ȃ葽���̕ł������ĕ����Čf�ڂ���Ă��邱�Ƃł���B
�@�C�G�X�ɂ́A�Ⴉ�肵���̂P�V�N�Ԃ̓������肩�łȂ��B���̊ԁA���̓C�G�X�́A�G�W�v�g�ɂ����e���y�E�^�C�ƌĂ��W�c�ɐg��u���Ă����\���������B���̃e���y�E�^�C�������A�u�b�_���Ō�̋I���O�R���I���A�C���h�̃A�V���[�J���ɂ���Ĕh�����ꂽ�����������c�̈�h�ł��������i�e�[�����F�[�_�j�̖���ł������B�C�G�X�͂��̒n�ŁA�����̗��O���w�сA�����C�s�҂Ƃ��Ă��̗��O�����H���Ă����B
�@���̌�A�p���X�`�i�ɖ߂����C�G�X�́A���_���̋����ɑR���ĕ�����`�������B�u�b�_�Ɠ��l�ɋɒ[�ȋ�s��r���A���f���̓���������B����́A����Ȃ����h�ƐT�݂̓��ł���A�^�̊댯�ɒ��ʂ��Ă����Â�ۂ��ł���B�����݂Ɩ\�͂Ƃɑ��铚���́A���Ɨ��������ł���ƃC�G�X�͐����B�M�҂����ɏ�Ɍ����ł���悤�����A����▝�S���N�����Ȃ��悤�������B�����āA���ׂĂ̍����̂āA�Ƒ���F�l�Ƃ��J��f���A��C���m�Ƃ��ĕ��Q���Ȃ���̕��@�̓`��������Ɠ`�����̂ł������B
�@�ŏ��̐M�҂����͔M���I�ɃC�G�X���}�����B�������A���̔M��ȐM�҂������A�C�G�X�����S�ɗ������Ă���Ƃ͌���������B�ނ�͂��܂�ɂ����_�����I�ȋ~���僁�V�A�����̊�]�Ɏ���ꂷ���Ă����B���������̎t�Ƀ��V�A�ƂȂ邱�Ƃ����҂��A�ނ̋~���ɂ������낤�Ɩ]�݂������B����ɑ��āA�C�G�X�̊������Ԃ͒Z�������A�����҂̈ӎ��̒��ɕ��@�̋��������t������ɂ͎���Ȃ������B�C�G�X�́A�s�K�����Y�i�͂���j�ɂ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�p���X�`�i�́A�C�G�X�̖���D���قNJ댯�ȏꏊ�ƂȂ�A��q��M�҂��������̒n�ŃC�G�X�̊�{�������L�߂悤�Ƃ��������܂������Ȃ������B
�@�������A���[�}�Ƃ̑Η����A����66�N�Ƀ��_���푈�ւƔ��W�����Ƃ��A�ނ�ɂ���]�̌����������B�u���̐��̏I���v�̕��͋C�̒��A���`�����߂�l�X�̖��ƂƂ��ɁA�C�G�X�َ͖��I�����̒��ɑg�ݍ��܂�A���̋����͋��M�҂̎�ɓn��A�����̓`���҂���~���僁�V�A�ɕϗe�������Ă��܂����B�i286�`288�Łj
���z�[���y�[�W��Ғ��B�������́u���f�v�ł͂Ȃ��A�u�����v�B���f�Ƃ͑Η��T�O�̍m��ŁA�u�`�ł�����A�a�ł�����v�Ƃ�������B�����Ƃ́A�Η��T�O�̔ے�Łu�`�ł��Ȃ��A�a�ł��Ȃ��v�Ƃ�������B�u��i��s��`�j�ł��Ȃ��A�y�i���y��`�j�ł��Ȃ��v�u�ߋ��ɂ��ł����A�����ɂ��������v�Ƃ������ꂪ�����Ȃ̂ł���B
������g���w����̏��a�j�`��E��Z�����ւ̓��Ɠ��@��`�ҁx�㉺�i�����V���ЁA1988�N�j
�@�^�C�g���́u����v�Ƃ́A�@�،o�̉���g�i�ɗR��������̂ŁA���Ƃ��Ƃ͕��ɂ��O�������ɓ������߂ɗp�ӂ������̏�̈ӁB�{���́A��O�̏��a�j�����́u����v��栂��A���B���ρA��C���ρA�܁E������A��E��Z�����Ɏn�܂鏺�a�����̌R���ƍق�֘A����l�X�Ȏ��ۂɑ��āA�Ό��Ύ���k��P��̓��@��`�҂��ǂ̂悤�Ɋ֒m�������𒆐S�ɁA���ے���c�����i�X�p�C�E�]���Q�����j�ŌY���������G���i������
�ق݁A1901-1944�j�����f���Ƃ����ˋ�W���[�i���X�g�u����v�̎��_����`�������j�����B
�@���҂̎�����g�i1921-2008�j�́A��y�@�@�������A�����ő��㎛��87��@����C������y�@�m���ŁA���؏܍�ƁB�{���͐��c�L�P�B�咘�Ɂw��������x�w�O�łЂ���O���u�x�w����Ɛ��`�x�Ȃǂ�����B
�@�{�������́u���Ƃ����ɂ����āv�i����301�Łj�̒��ŁA���҂́A��w������ɁA���F������c�̎ʐ^��������ꂽ���A�������X���[�K�����f���Ă��Ȃ����ɁA�ЂƂ���ڗ��u�얳���@�@�،o�v�̐��ꖋ���������Ă������ƂɏՌ������̌����q�ׂĂ���B���N�A���{�R���@���̑m���̋s�E�����ƂȂ�����C���ς��N����A�₪�Č܁E����������E��Z�����ւƎ�����{�t�@�V�Y���̌`���ߒ��ŁA�����Ɋ��`��������@��`�҂����̑��݂�m��ɋy�сA����͒��҂̒��ŏd��ȊS���ɂȂ��Ă������Ƃ����B
�@�����ň�����Ȏ����́A���B���ρi1931�N9���j�A��C���ρi1932�N1���j�A�܁E������i1932�N5���j�A��E��Z�����i1936�N2���j�A���̂��c�����i1937�N2���j�A�]���Q�����i1941�N9���`1942�N4���j�Ȃǂł���A�o��l���́A���B���ς̐Ό��Ύ��i�����͂� ���F1889-1949�j�A�����c�̈������i���̂��� �ɂ����傤�F1886-1967�j�A��E��Z�����̖k��P�i���� �������F1883-1937�j�Ɛ��c�Łi�ɂ��� �݂��F1901-1937�j�A������̓c���q�w�i���Ȃ� �������F1861-1939�j�A�����i1935�N8���j�̑���O�Y�i�������� ���Ԃ낤�F1889-1936�j�A�_���������i1933�N7���j�̑O�c�Y�i�܂��� �Ƃ炨�F1892�|1953�j�A�V�������N�����̖����`�Y�i���̂� ���낤�F1889-1961�j�A���̂��c�����̍]������i������ �����ǂ��F1905-1938�j��ł���B�쒆�ɂ́A�{���i�݂₴�� ���F1896-1933�j���o�ꂷ��B
�@���a11�N�i1936�j�̓�E��Z�����ŁA�k��P�E���c�ł��������Z�Ƌ��ɏ��Y�����ƁA�V���L�҂Ƃ��ē��@��`��Njy���Ă�����l���̉���͓��ĊJ��̒��O�ɃX�p�C�e�^�őߕ߁E�����B�����ŗNJ��́w�@�ؓ]�x��ǂ݁A���@��@�،o�̌����ɖv�����Ȃ���A�����m�푈�I��̑O�N�A���a19�N�i1944�j�ɏ��Y�����c�Ƃ����̂��{�삠�炷���ł���i�Ȃ��A�����́A�O�f�u���Ƃ����ɂ����āv�̒��ŁA���݂̔���G�����ӔN�R�����j�X�g������@��`�ւƓ]�g���Ă������Ƃ�����̈₵��������������f����Ƃ��Ă���j�B
�@�{��̒ꗬ�ɗ����u���@��`�v�ɂ��ẮA��J�h�꒘�w�ߑ���{�̓��@��`�^���x�i�@���فA2001�N�j�A���w���@��`�Ƃ͂Ȃ����̂��\�ߑ���{�̎v�z�����x�i�u�k�ЁA2019�N�j���Q�Ƃ��ꂽ���B
�@�O�q�̒ʂ�A��l���̃W���[�i���X�g����́A�\�A�ԌR�Q�d�{���̒�������q�����g�E�]���Q�iRichard Sorge�F1895-1944�j��}�b�N�X�E�N���X�e�B�A���[���E�N���E�[���iMax Christiansen-Clausen�F1899-1979�j�ƂƂ��ɑ������A�����S�u���ŌY���������G�������f���Ƃ��ĕ`����邪�A�������]���Q����c�i�����[�C�@�ցj�̎�v�����o�[�Ƃ��ė��������W���[�i���X�g�ɁA�u�����R�E�h�E���P���b�`�iBranko Vukelic�F1904-1945�j�������B���P���b�`�́A�c�����[�S�X�����B�A�̐V���w�|���e�B�J�x��t�����X�E�A���@�X�ʐM�Ёi���݂�AFP�ʐM�̑O�g�j�̃W���[�i���X�g�Ƃ��āA���{�̏Љ�L���Ǝʐ^�𑗂�q�\�r�̎d�����������A�q���r�ł̓W���[�i���X�g�̐E�������������ʐ^�B�e�Ǝ��W�������̕��͂�C���Ƃ����������s���Ă���B���ƂƂ̓ʐ푈�������ׂ��Γ��H��ɈÖ��]���Q�A���P���b�`�A�N���E�[���A�����̊����ɂ���ē��{�͓�i����ւƓ]���A���ʁA�\�A�͓ƃ\���ɒ��͂ł���悤�ɂȂ�������A���{�͑ΕĊJ��ւƓ˂��i�ނ��ƂƂȂ�̂ł���B�^��p�U���O��1941�N10��18���A���P���b�`�́u�]���Q�����v�ɘA�����đߕ߂���A�I��̔N��1945�N1��13���ɖԑ��Y�����ō�������B
�@�]���Q�����O�N��1940�N1��26���Ƀ��P���b�`�̍ȂƂȂ����R��i�q�i��܂��� �悵���F1915-2006�j�̕Ғ��w�u�����R�E���P���b�` ��������̎莆�x�i���m�J�A2005�N�j�́A�S������Ă������P���b�`�Əi�q�����Ƃ肵��247�ʂ̉������Ȃ����^�������̂ł���B
�@2003�N���J�̓��{�f��w�X�p�C�E�]���Q�x�ł́A�C�A���E�O�������]���Q���A�{�؉�O������G�����A�E�H���t�M�����O�E�Z�b�V���}�C���[���N���E�[�����A�A�[�~���E�}�����X�L�[�����P���b�`���A���Ⴊ�R��i�q�����ꂼ�ꉉ���Ă���B�@�@�@�i���ӁF���X���j
copyright©2016 Yodenji Vihara all rights reserved.