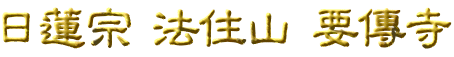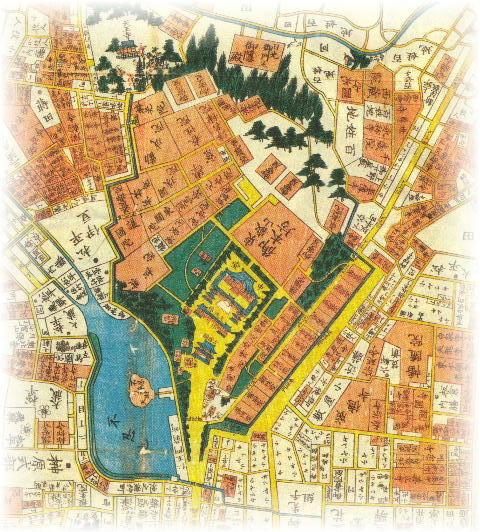『法住』バックナンバー巻頭言prefatory notes

本誌は、日蓮聖人の700遠忌を契機に、昭和55年(1980)より毎年1回発行し、寺の護持会会員の皆様に無料頒布しております。
詳細は下記のタブからアコーディオンを展開してください。
平和への提言
『法住』42号(2019年1月号)掲載予定
人類存亡の危機
昨今の世界情勢を鑑みると、いま人類は、経済の混乱、過激思想の瀰漫、紛争難民の問題などなど、大きな課題を抱えているように思われます。しかし今日の人類は、もっと恐れなければならない危機を抱えており、二一世紀はまさに人類存亡の岐路にあると言っても過言ではありません。
UNITED NATIONS POPULATION INFORMATION NETWORK (POPIN)の調査に基づいて人類の人口推移を概観すると、一九世紀以前は明確なデータが存在しないため研究者ごとに数値に大差があるものの、約一万年前に五〇〇万人だった人類は、今から三五〇年前には総人口約五億人に達したと推定されています。単純計算で年間五万人程度の緩やかな増加です。ところが、その後、医学や科学の進歩もあってか人口は急速に増え、産業革命がおこった二〇〇年ほど前には一〇億人を突破、その後、一九世紀・二〇世紀の二〇〇年間で六〇億人に、二一世紀に入り二〇年足らずで人類は七〇億人に到達する勢いで増殖しています。過去二〇〇年間は、年間約三〇〇〇万人ペースの劇的な人口増を示しているのです。
いま人類は、資本主義経済の崩壊による世界恐慌などの経済危機、環境破壊によるオゾンホールの拡大と地球規模での生態系の変化、人為的に作り出された新種ウイルスによる伝染病などの生物学的災害、核や生物兵器を保有する小国によって引き起こされる小規模な核戦争の危機などをはじめ、これまで想像もしていなかった数々の危難と向かい合っており、もはやいつ転落してもおかしくない崖っぷちに立たされているといった状況です。そうした中で、あまり危惧されていない、しかしながら、最も恐ろしい人類滅亡の起爆剤となると考えられているのが、人口増加や気象変動による世界的な食糧危機とエネルギー危機です。
岐路の選択を誤らないために
その最も平易かつ安直な解決方法は、原始的手段とも言える領土争奪・他国殲滅・異民族掃討でしょう。しかし、これを防御するために、武装強化を図ることもまた、原始的な短絡的発想にすぎません。
よく「平和のための軍隊」といった欺瞞に満ちた自己矛盾や、「抑止力のための軍備」などと都合の良いことが言われますが、兵器の価値というものは、決して「抑止力」にあるのではありません。兵器の真価は、「攻撃力」にあります。それが兵器です。相手の抑止力が高まれば、それを上回る攻撃力・打撃力をもった兵器が用意されるまでです。むしろ、兵器を保有している国が頑なに抵抗すれば、民間人をも犠牲にする無用な戦禍が拡大します。
更に、劣化ウラン弾・クラスター爆弾、貧者の核兵器といわれる生物兵器・化学兵器、電算化されたすべての兵器の発射機構を無効にする電子兵器、人間が遠隔操作するドローン兵器すら時代遅れにする、決して失敗を恐れず躊躇という観念を持たないAI兵器などなど、兵器の近代化・殺傷能力の増大化により、これからは核兵器以上の恐怖が待っています。
人類は今すぐ、すべての軍備拡張・兵器生産を停止し、人類の存亡をかけて食糧危機・エネルギー危機の問題を早期解決し、太陽の活動期の終息や地球のポールシフトなどによって曾て北米大陸が厚さ百メートル以上の氷で覆われたような氷河期の到来、あるいは地球近傍小惑星・浮遊惑星の接近や衝突、ガンマ線バーストの直撃による生態系絶滅など太陽系規模・宇宙規模の未曾有の災害といった新たな危機に備える時に来ているのです。
レスター・ブラウン氏は、世界の貧困の根絶のために、風力発電、太陽電池、太陽熱・地熱利用、小規模水力発電、有機性資源など石油資源以外の資源の開発に世界的な協調と努力が求められると指摘します。その目標達成のためには、年間六八〇億ドルの追加支出が必要となるそうです。森林・漁獲・河川の流量を回復し、地下水位を安定させるためには、更に追加で九三〇億ドルかかります。かくして地球環境を回復するためには合計一六一〇億ドルかかる計算になるのです。世界はいま、年間九七五〇億ドルを軍事目的(軍事費)に使っています。何に財源を投入すればよいかの判断を、いまだに人類は誤り続けているのです。近年脚光を浴びている水素エネルギーなどの再生可能エネルギー、テロや災害の恐怖に晒されている原発の核分裂原理とは真逆の核融合炉の開発にも、もっと人類は心血を注ぐべきでしょう。
宗教教育こそが平和を実現する
もし軍備拡張や戦争以外に解決策を見いだせないのであれば、もはや人類の未来はないでしょう。急速な人口増加により次々と新しい世代が増殖していく状況において、「対話」などという悠長なことは言っていられません。戦争は、いつも大人が始めるからです。そこで大切となるのが、「教育」なのです。マララ・ユスフザイ氏は、教育こそが、世界の貧困・差別・紛争・対立などの諸問題を解決する、ただ一つの解決策であると国連で訴えました。しかし、私に言わせれば、言語や科学や技術の習得以前に、宗教教育が最優先されるべき課題だと考えます。思想や哲学や信条や信仰を超えた、全人的な宗教教育が人類を最も早期に「進化」させる手段だと思っています。
それでは、どういう宗教教育が求められるのでしょうか。排他的・独善的な未熟な宗教、生贄や殺生を容認する暴力的な宗教によっては、元も子もありません。しかし、多くの高度に発達した宗教には、また一部の原始的な宗教ですらも、ひとつの共通する観念を有しています。それは、同族同士の殺人を許さないことです。これが問題解決の糸口となるのです。
「どうして人を殺してはいけないのか」、ある討論会で高校生にそう聞かれた識者の誰もが、その正当な理由を答えられなかったということが話題になりました。人の命を殺めてはならないということを、われわれはどうして知っているのでしょうか。
宗教の中にこそ、その答えがあるのです。例えば、日本国憲法は殺人罪を犯せば刑に処すと決めていますが、「殺してはいけない」と定めているわけではありません。実は日本国憲法には、「殺してはいけない」といった規範も、なぜ殺してはいけないかという理由も、一切書かれていないのです。そこには罰則規定しかありません。その罰則を定めた法律すらも、犯罪の抑止には全く役立っていないのが現実です。理由は簡単です。法律は人の感情を抑制できるものではないからです。
所詮、「殺人は非である」という規範は人々の心の中にあるという前提で、法律にはそれに違反した場合の罰則を定めているだけなのです。規範が確立されていない人間には、法律は無用です。ですから、早期からの宗教教育、すなわち「こころの教育」が必要なのです。
ちなみに、「人を殺すことなかれ」という規範は宗教の中にあるため、多くの宗教が、第一義として原則的に「同朋」の殺人を禁止しています。ただし、基本的に多くの宗教は寛容と非寛容との二面性を持ち合わせていますので、異端者を敵対視した場合の改宗や排除、殺害行為や戦争は容認されます。キリスト教も例外ではありません。ただ原始仏教だけは、同朋の殺害のみならず、一切の殺生を禁じており、非寛容という観念もありません。人類がいまだ到達することのできない、たいへん高度な宗教であることがわかります。
更に言えば、法華経の結経と言われる『観普賢菩薩行法経』には、心で殺意を感じただけで、その人は殺生を犯したのと同じ罪になるという誡めがあります。実際に行動に起こさなければいいのではなく、心に一瞬でも念じただけで罪になるという考え方は、「内心の自由」を認める日本国憲法をはじめ、人類の現行法にはありません。現在の日本の法律では、自白・自供だけでは犯人を特定することができません。物的証拠・アリバイなど、犯行の外堀がしっかりと立証できないかぎり、犯人と決めつけることはできないのです。しかし、これでは他人に冤罪をなすりつけたり、証拠を隠蔽して無罪を主張する被疑者が増加するばかりで、いっこうに世の中はよくならないのではないでしょうか。冤罪工作は、科学や技術の進歩した現代社会では、たやすいことになりつつあります。
歴史から学ぶもの
もはや人類が救われるためには、人類の精神文明を発展せしめる以外に道はありません。その実現が、対話であれ、教育であれ、決してたやすいことではないことも言うまでもありません。しかし、仏教的な不殺生・非暴力の慈悲を全人類が共有するまで、私たち仏弟子たる者の戦いは続きます。途中で投げ出したり、妥協するという選択肢はありません。それには相応の覚悟が必要です。たとえ、その過程で亡ぼされることがあっても、そうした歴史を仏教界は繰り返し体験してきましたし、それはそれで仏陀の説いた「諸経無常」の理に過ぎませんので、まさに「諦める」だけのことです。自らの亡びを恐れるのではなく、自分の心の中にある「悪」を恐れよと、仏陀は説いています。
歴史を振り返れば、かつて仏教界は度重なる廃仏・破仏の歴史を経てきました。印度では、弗沙弥多羅王・屹利多王・檀弥羅王・弥羅掘王・設賞迦王らの諸王による廃仏毀釈が、中国では北魏の太武帝・北周の武帝・唐の武宗・後周の世宗の各皇帝よる三武一宗の廃仏、最近では文化大革命による弾圧が起こります。いずれも、それまで仏教を庇護し平和国家を維持してきた国が滅ぼされた後、平和を標榜する仏教界も壊滅的な打撃を受けてきました。しかし、破仏の国は、その度に次の政権や他国の王に滅ぼされるという末路を辿っているのです。
日本では明治維新の廃仏で仏教界は弾圧を受け、その後、軍国主義に邁進した日本は結局戦争に敗れました。その悲劇は、ヒロシマ・ナガサキでは終わりませんでした。スリーマイル島の原発事故以来、国内での原発建設は行なっていないアメリカの、その核兵器開発の一翼を担った日本の原子力発電所は、フクシマの悲劇を生みました。それはまた、自然界に対する畏敬の念を喪失した日本人の傲慢さが招いた因果応報でもありました。明治維新に始まった日本の亡びの道は終わってはいません。
我々は、もういい加減に目を覚まさなければなりません。過去十数回にも及ぶ破仏と破国の連鎖の歴史は果たして偶然でしょうか。印度・中国では、いずれの時代も、その後、仏教を庇護する新たな国主が登場すると、平安の世が築かれてきました。これは仏教の非暴力の思想と無関係とは思えません。釈尊の不殺生の教えを法律に取り入れ、それまで殺戮の限りを尽くしてきた自らの悪逆を悔い改めた印度の阿育(アショーカ)王は、平和な時代を築きました。非暴力に敗北はありませんが、暴力の果てには必ず敗北が待っていることを、わたしたちは歴史からも学ぶのです。しかし、それを全く意に介さない人たちは、同じ過ちを繰り返します。
「一切の害心を捨て、苦難を恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め」との仏陀の命に従い、悔いなく終わる命でありたいと思う今日この頃です。
住職 高森大乗
仰ぐところは釈迦佛、信ずる法は法華経
『法住』41号(2018年1月号)掲載予定
日蓮宗の本尊は、宗祖の日蓮聖人が、法華経に生きる者たちの信仰の対象とすべく定められた、「本門の本尊」と称される佛です。具には、法華経本門の教主たる久遠実成の釈迦牟尼佛世尊を言い、「本門の教主釈尊」「本師釈迦牟尼佛」「久遠実成の佛」「久遠本佛」などと様々に呼ばれます。
この佛は、釈尊の一代の説法(佛教・一代聖教)の中でも、釈尊の最晩年に説かれた法華経(妙法蓮華経)の後半、すなわち「本門」と呼ばれる部分で初めて明らかにされた佛なのです。
法華経が説き示される前までの経典(爾前経)の所説では、釈尊はインドの伽耶の菩提樹下で初めて成道した佛(始成正覚の佛)であると説かれ、弟子たちもそのように思っていたのですが、法華経の如来寿量品に来って、釈尊自ら、それは方便の教えであったと打ち明けて、「我、実に成佛してより已来、無量無辺百千万億那由佗劫なり」と、本当は気の遠くなるような久遠の過去世に成佛し、それ以来常に裟婆世界にあって衆生を教え導いてきたと明かされるのです。
私たちがよく唱える「自我偈」は、この如来寿量品の後半部分にあたり、そこでも、釈尊は、繰り返し「我常にここに住して法を説く」「常にここにあって滅せず」「常に霊鷲山にあり」などと説いて、約二千五百年前にこの世を去った釈尊の魂は、それ以前も、そして現在も、永久に法華経説法の霊場であるインドの霊鷲山、およびこの娑婆世界に留まり続けているというのです。
釈尊の寿が久遠であるということは、釈尊の慈悲の心も、その救済も永遠であるということになります。自我偈の結文の「毎自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就佛身(毎に自らこの念をなす。何をもってか衆生をして佛道に入り、速やかに佛身を成就することを得せしめんと)」の四句は、まさに釈尊の大慈悲の発露たる大願の表明で、ここに久遠の釈尊による永遠の救済が約束されるのです。
この釈尊の教えを正直に受け止めて、日蓮聖人は、その主著『報恩抄』の中で、「日本乃至一閻浮提、一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし」と明言され、『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』では、「末法に来入して始めて此の佛像出現せしむ」と説示されるのです。
つまり、日蓮宗で仰ぐべき本尊は、「本門の教主 釈迦牟尼佛」以外にはないということです。まさに「あを(仰)ぐところは釈迦佛、信ずる法は法花経なり」(日蓮聖人遺文『盂蘭盆御書』)なのです。
日本のみならず全世界が、法華経の本門の教主である釈迦牟尼佛を本尊として仰いだ時(すなわち人々が法華経の教えを信じ、その精神に基づいて行動した時)、この苦悩に満ちた娑婆世界に釈尊の永遠の浄土(自我偈の中で「我が此の土は安穏にして」「我が浄土は毀れざるに」と釈尊が表明された娑婆即寂光土)が顕れます。
この浄土の有様を図様化して表現したのが、日蓮聖人が晩年に考案し、数多く図顕した、「大曼荼羅」と呼ばれるものです。中央上部に「南無妙法蓮華経」の題目七字が大書され、その左側に法華経の「本門の本尊」である釈迦牟尼佛が勧請されているので、大曼荼羅そのものを便宜上「本尊」などと呼ぶ場合もありますが、実際に「本尊」と呼ぶべきは、久遠の釈迦牟尼佛ただ一佛であって、大曼荼羅の意義と機能は、あくまでも「曼荼羅」なのです。
ところで、釈迦牟尼佛をはじめ、佛(佛陀・如来)と呼ばれる存在は、「相好」という大小様々な身体的特徴を有し、大きいものに「三十二相」、小さいものに「八十種好」があると考えられてきました。代表的なものに、足下安平相(足の裏が扁平足になっいる)、身金色相(身体が金色に輝く)、広長舌相(舌が長く、顔を覆うほどに広い)、頂上肉髻相(頭頂部に隆起した部位がある)、眉間白毫相(眉間に光明を放つ白い巻き毛がある)、梵音声相(法を説く清浄なる音声)などがあり、佛像や佛画でも、代表的な相好は、ある程度、表現されています。
ただひとつ、彫刻や絵画等で表現できないものがあるとすれば、それは佛の声である「梵音声相」です。そこで、日蓮聖人は、佛像の前に経巻を置いて三十二相を整えることができると教示されます(日蓮聖人遺文『木繪二像開眼之事』)。
つまり、造立された佛像が、法華経の本門の教主である久遠実成の釈迦牟尼佛であることを示したければ、その像の前に法華経の経巻(自我偈でも可)を置けばいいのです。
なお、このように、日蓮聖人の教義では、法華経本門に説かれる久遠の釈迦牟尼佛こそが、唯一の「本尊」に定められているのですが、檀信徒各家の佛壇には、日蓮聖人の祖師像はあっても、釈尊の佛像は安置されていない場合も多いかと思われます。そのかわりに、法華経本門の本尊である久遠釈尊を書き込み、その釈尊による救済の浄土を具現化した「大曼荼羅」を祀ることが一般に行われているのです。
住職 髙森大乗
大人の価値 ~「人間」は社会的・歴史的に生きる存在~
『法住』第40号(2017年1月号)
人類学では、人類をふたつの側面から分析する時に、ひとつには生物学的・自然人類学的な側面である「ヒト」として捉えるという視点があります。これはカタカナで書く「ヒト」です。もうひとつは、文化的・社会的な側面、文化人類学的・人間学的側面でとらえた、漢字で書く「人」です。こちらは、あるいは「人間」と言い換えてもいいかも知れません。
我々は、自分が大人かどうかを考えた時、カタカナで書く「ヒト」という観点から言えば、個人差はあるものの、第二次性徴期を迎える十代前半には、生物学的には、もう立派な「大人」であるといえるでしょう。
しかし、人間は動物と違い、単なる生物として生きているわけではありません。「人間」は単なるカタカナ表記の「ヒト」とは違うからです。
「人間」という字を、国語辞典で引くと、第一義には、古くは「じんかん」とも読む。人と人の間にあるもの。社会・世間・世界に同じ、と定義されております。つまり、「人間」とは、人と人の間にあるものを大切にして生きる存在だから、人間というのです。
では、その「間」にあるものとは、いったい何でしょうか。この間は、人と人との絆のような空間的な「間」だけを言うのではありません、時間的な「間」もそこにはあります。ちなみに、「世界」の語も、「世」は時間の概念、「界」は空間の概念を表す言葉です。つまり、私たちは、空間的・時間的に生きる存在であるから「人間」なのです。言い換えれば、「人間」とは、社会的に生き、歴史的に生きる存在であると言ってもいいでしょう。
社会的に生きるということは、法律・道徳・規範を守って、社会性・協調性をもって生きるということだとも言えます。ただし、法律には、普遍性も不変性もありません。また、法律で定められた年齢にならないとできないからといって、それが大人かどうかの判断基準では決してありません。物事の善悪を弁えない幼児は、まだまだ大人になりきっていません。しかし、法律で禁止されていることをしっかりと守ることができれば、たとえ十代であっても立派な大人なのです。なぜなら、それでしっかりと社会的に生きているわけですから。
一方、歴史的に生きるということのほうが、難しいかも知れません。過去を振り返れば、両親や祖父母・祖先あるいは人類の先人たちから大切なものを託されて生きているという自覚、未来に目を向けると、自分のした行為が子供や孫の代まで影響を与えるという責任、そうした自覚と責任をもちながら生きていくということが、歴史的に生きるということです。
こうした生き方がしっかりとできる人が、本当の「大人」なのです。すなわち、大人の人間には、歴史的・社会的に自分をしっかりと位置づけて行動することが求められるのです。ですから、この「大人の人間」に、年齢制限はありません。
十二歳で仏門に身を投じ、十六歳で出家した宗祖日蓮聖人も、まさにそのひとりでした。聖人は、日本史上では武士政権誕生の時代、仏教史上では末法という時代に、大陸の辺境の島国に生を受けたとの自覚に立ち、立正安国の仏国土の建設のために行動を起こしました。同じ鎌倉時代に、大陸の蒙古襲来の脅威に立ち向かった鎌倉幕府の執権北条時宗は、当時弱冠十八歳で日本の命運を任されました。
世界に目を向ければ、児童労働の非を唱えて十二歳でフリー・ザ・チルドレンを設立したクレイグ・キールバーガー氏や、戦争・差別・貧困の解決のために教育の重要性を訴え、十六歳で国連で演説、十七歳でノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイ氏のように、十代でも大人になり得るのです。彼らは、歴史を学び、その中に自らの立ち位置を見つけ出して、社会に貢献することで、若くして自立できたのです。我が国においても、幕末・明治・大正・昭和初期くらいまでの十代の多くは、精神的にはもう立派な大人でした。その多くが戦争で命を落としました。
つまり、成人式を迎えたから、酒が飲めるから、運転免許が取れるから、選挙権があるから、大人になるわけではないのです。二十歳を過ぎても、社会的・歴史的に生きることのできない人は、大人ではありませんし、本当の意味での「人間」になりきれてもいません。ともすると、動物と同じ「ヒト」になりさがった者もいるでしょう。
今だけを生きるのみにあらず、自分独りで生きるにあらず…それが「人間」の大人なのです。
住職 高森大乗
戦後七十年特集
『法住』第39号(2016年1月号)
戦後七十年が過ぎ、日本では、「戦争を知らない子供たち」が七十歳になる時代を迎えました。もう二度とこんな辛い思いはしたくないと、世界中の多くの人々がそう思ったはずですのに、いまだ世界に不幸な戦争や紛争、卑劣なテロや焦(きな)臭(くさ)い諍(いさか)いが、絶えません。なぜ、先人たちの教訓は活かされていないのでしょうか。
人間は、歴史的に生きる存在である以上、私たちは、人類の祖先の成功も失敗も含めて、彼らのたどった試行錯誤の成果を受け継いで、現代に生きているという自覚が必要です。人は求むべき高貴な精神も、避くべき愚かな行為も、すべて歴史から学ぶものです。ですから、先人に対しては、彼らの努力や犠牲の上に今の私たちがあるのだと言うように感謝の念を抱き、敬意を表するのが人間社会における礼儀なのです。今、日本が、そして世界が、向かおうとしている行く末を案じるのであれば、我々は辛い過去に学ぶしかありません。
人類の歴史は、戦争の歴史でもありました。世界のいかなるところにおいても戦争がなかった期間、つまり「平和の時代」よりも、どこかで一定規模の戦争があった期間、つまり「戦争の時代」のほうがはるかに長いということです。さらに憂慮させられることは、二十世紀以降は、戦闘員だけでなく一般人も攻撃の対象になり、その面での被害が大幅に増えていることです。
このような悲惨なる運命の繰り返しを防ぐには、戦争の悲劇を風化させることなく、犠牲となった多くの方々や遺族の悲しみを後世に伝え、いかなる暴力も蛮行も許さないという段階にまで人類を進ませる以外にありません。犠牲壇に立たれた人々の、苦しい悲しい末期が、人類を救うための大きな功徳となりますことを願って止みません。
住職 高森大乗
第三の選択
『法住』第37号(2014年1月号)
武士が政権の座を朝廷から奪い、「幕府」を開いて日本の政治を司るようになった鎌倉時代以降、欧米列強の植民地化を回避するために志士たちが立ち上がり、後に涙ぐましいまでの欧化に注力することとなった明治維新、更に東アジア唯一の列強国に成長し、白人至上の優生主義に対して人種差別撤廃を訴えて真っ向から立ち向かった日清日露戦争と二度の世界大戦終結まで、アジアの小国であるこの日本を下支えしていた先人たちの気高い精神性は、いずれも「武士道」の精神文化に根ざすものでした。
「隷属か、戦争か」…太平洋戦争開戦直前の一九四一(昭和一六)年一一月、米国から提示された「ハル・ノート」を最後通牒と理解した日本には、その時は、もはや「戦争」という選択肢以外に国民と文化を守る術はないと判断されたのです。未来の子孫たちが虐げられることなく、日本が独立国家であり続けるためには、欧米列強に対して民族の不屈精神を誇示するしかありませんでした。
当時、海軍大将だった永野修身(ながのおさみ)元帥(げんすい)は、次のように語っています。
戦わざれば亡国と政府は判断されたが、戦うもまた亡国につながるやもしれぬ。しかし、戦わずして国亡びた場合は、魂まで失った真の亡国である。しかして、最後の一兵まで戦うことによってのみ死中に活路を見出しうるであろう。戦ってよしんば勝たずとも、護国に徹した日本精神さえ残れば、我等の子孫は再起三起するであろう。
彼らにとって、抵抗なき敗北は、日本人の武士道に反するものでした。日本人は隷属を選ぶ民族にあらずとの自覚に立った人たちによって、日本は、一億総玉砕をスローガンに掲げ、凄惨な戦争へと突き進んでいきます。しかし、それは、決して希望に満ちたものではなく、民族自決覚悟で挑んだ決死戦だったのです。「不幸な選択」でした。この戦争の犠牲になった人々たちが遺した痛々しく切ない悲しみの数々は、「わだつみのこえ」にも語り継がれています。
◇ 非暴力・不服従
「服従し奴隷になるか、銃を把って敵を倒すか」…そのどちらでもない第三の方法によって「奇跡の人」と呼ばれた人物を私たちは知っています。インド独立の父、マハトマ・ガンディー(一八六九~一九四八)です。圧倒的な武力と権力でインドを植民地支配していた大英帝国に対し、武器ひとつ持たないガンディーがインド独立のためにとった方法、それが「非暴力・不服従」でした。決して暴力をふるわず、しかしインド人を差別する支配者には決して服従せず、人間としての自由と尊厳を手にするために、相手が痛みを感じるまでその懲罰を甘んじて受ける、それこそがガンディーが辿り着いた「第三の選択」でした。
ガンディーの呼びかけは、人々の心を捉え、やがてインド全体で大きなうねりとなります。その結果、各地で民衆と警官隊とが衝突することになりました。しかし、それはもはや衝突と呼べるものではありませんでした。警官隊は機械的に棍棒を振り下ろしましたが、人々は一切逆らわず、ただただ打ちのめされるまで前進を続けるだけだったのです。自らの身を犠牲にして、直接相手の良心に訴えるというガンディーの教えを人々は守り続けました。カンディーのメッセージは、大英帝国の支配を揺るがし、第二次世界大戦を経て、一九四七年、ついにインドを独立へと導いたのです。
ガンディーの言葉には、徹底した不殺・非暴力の信念が込められています。
・目には目を、という考え方では世界中の目をつぶしてしまうことになる。
・握り拳と握手はできない。
・弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。
・暴力によって得られた勝利は敗北に等しい。一瞬でしかないのだから。
・自分が行動したことすべては取るに足らないものかも知れない。しかし、行動したということが重要なのである。
ガンディーはヒンドゥー教徒でしたが、その言葉には、はるか昔にインドに登場した、仏教の始祖ブッダ釈尊の教えに通ずるものがあるのです。
◇ プンナの決意
ブッダ(仏陀)が、仏弟子との間で交わした問答の中にも、不殺生・非暴力・不抵抗・不服従の教えが示されています。
ある日、竹林精舎にいるブッダを訪ねた弟子のプンナ(富楼那(ふるな))は、丁寧に礼拝すると、西方のスナーパランタという国に布教に行きたいと申し出ました。この国の国民は気性が荒く、凶暴で知られていました。そこでブッダは、プンナに対して次のように尋ねました。
「おまえが目指す国の人々は、気性が荒く、乱暴そうだ。もし彼らが、おまえをののしり辱めたらどうするね」
プンナは、次のように答えました。「私は思うでしょう。この国の人々はよい人だ。なぜなら私を棒で殴ったりしないから…」
すると、ブッダはまた尋ねました。「では、棒や石で殴ってきたらどうするね」
「私は思うでしょう。この国の人々はよい人だ。なぜなら、私を刀で斬りつけたりしないから…」。このようにプンナはブッダの質問に次々に答えていきます。
そして最後に、「では命まで奪うようなことがあったらどうするね」という問いに、「師よ、世の中には自ら命を絶つ者もおり、また死はいつか我が身に訪れます。…私は思うでしょう。この国の人々はよい人たちだ。私の命を絶ち、この世の悩みから私を解放してくれた。私は我が手に刃物をとらずとも、死ぬことができた…と」
プンナのこころがけに感心したブッダは、「もう私に教えることはない。よく耐え忍ぶ心を学んだ。その心がけがあれば、まだ安らかでない人々を救えるであろう」といって、プンナの旅立ちを見送ったというのです。
◇ 最古の仏典
不殺を説いたブッダの教えを、ほかにも紹介しましょう。
現存最古の経典類と言われる『ダンマパダ』や『スッタニパータ』は、仏教の観念や倫理を説いたパーリ語の詩文で、主に南方アジア諸国の上座部(じようざぶ)(部派(ぶは)仏教・小乗仏教)で用いられ、その成立は前三世紀以前と考えられています。いずれも後世の仏典にみられる煩瑣な教理は少なく、人間そのものへの深い内省や生活の指針や人間として清く生きる道が風格ある簡潔な句に表されるところから、これらの経には仏陀の本来の言葉が遺されていると考えられています。いま、その中からいつくかを取り上げてみたいと思います。
・すべての者は暴力におびえ、すべての者は死をおそれる。己が身にひきくらべ、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。
・身の装いはどうであろうとも、行ない静かに、心おさまり、身をととのえて、慎みぶかく、行ない正しく、生きとし生けるものに対して暴力を用いない人こそ、道の人というべきである。
・怨みをいだいている人々のあいだにあって怨むこと無く、われらは大いに楽しく生きよう。怨みをもっている人々の間にあって、怨むこと無く、われらは暮らしていこう。
・勝利からは怨みが起こる。敗れた人は苦しんで臥す。勝敗をすてて、やすらぎに帰した人は、安らかに臥す。
・怒らないことによって怒りにうち勝て。善いことによって悪いことにうち勝て。わかち合うことによって物惜しみにうち勝て。真実によって虚言の人にうち勝て。真実を語れ。怒るな。請われたならば、乏しいなかから与えよ。
・一つの岩の塊が風に揺るがないように、賢者は非難と賞賛とに動じない。
・四方のどこにでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々の苦難に堪えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
深い人間愛と慈悲のこころで包み込むようにして、限りない自己浄化の道を示したブッダの教えは、『ダンマパダ』『スッタニパーダ』のみならず、多くの経典にくりかえし説かれております。
◇ むすびに
昨年は、東アジアの情勢が緊迫の度合いを強めた一年でした。国会では改憲論争も起きました。日本がどのよう選択肢をとるべきなのか、過去の教訓に学ぶことの大切さを痛感いたします。
非暴力に敗北はありませんが、暴力の果てには必ず敗北が待っていることを、私たちは伝えていかなければなりません。
住職 高森大乗