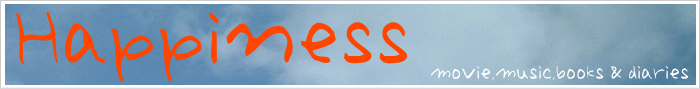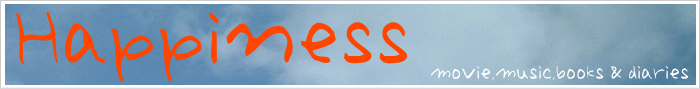| Brendan Benson |
| The Alternative To Love |
|
 |
 |
Spit It Out
Cold Hands (Warm Heart)
I Feel Like Myself Again
Alternative To Love
Pledge Of Allegiance
Them And Me
Biggest Fan
Flesh And Bone
Get It Together
Cold Into Straw
What I'm Looking For
Between Us |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2005.03.22 Release Date : 2005.03.22 |
|
 |
つくづく思います。
ミュージシャン(芸術家と言い換えても可)
という職業はおそろしい、と。
どれだけ美しいメロディを奏でることができたとしても、
どれだけ完璧な詩を歌ったとしても、
どれだけ伸びやかな声を発することができたとしても、
それが認められるかどうかの保証は一切ないんだから。
そのミュージシャンの作る音楽が
たまたまその時代にマッチしていたり、
超巨大な販売戦略の上に乗っかることで
たまたま売れ行きが良かったり、
音楽とはまったく関係のないところで
(たとえばルックスとか)人気が出たり。
実際の音楽が評価される場合にせよ、されない場合にせよ
そうやって世の中に広く認知される人って
ミュージシャンを目指す人たちの中の、ほんの一握り
氷山の一角であることは確かだと思うんですよね。
さて、今日ご紹介するブレンダン・ベンソンさん。
お世辞にも「世の中に広く認知されている」とは言えませんが、
かと言って、オレの記憶の中からその名前を消去するなんて
もったいなくてできない!し、彼自身も決して消えるつもりなど
なかったであろう、非凡なアーティストの一人です。
1996年、『One Mississippi』という
超強烈な美メロ・オタクポップなアルバムを引っさげて
デビューしました。(うちではいまだに愛聴盤!)
が、その後すぐにレコード契約は打ち切りに…。
それにもめげず、彼は全財産を元手に
自宅にスタジオを建て、地道で音楽一筋な活動を続けながら
ようやく2002年に『Lapalco』を発表。
その才能がまだ錆びていなかったことを証明しました。
そして今年、前作から3年という短い(?)スパンで
3枚目『The Alternative To Love』を発表するに至ったのです。
と、ブレンダン・ベンソンの歴史を、ここを参考に
書いてみましたが、涙なくしては語れない苦労の連続
だったんじゃないかと思います。
でも、そこまで大変な思いをしてでも、作りたい音楽があって
奏でたい楽器があって、スタジオにいる時間が一番楽しい!
そう思えるものがあるってことは、
何事にも替えがたいのかもしれませんね。
と、肝心の中身について何も触れぬまま
ここまで来てしまいましたが、まぁいいでしょう!
今回も、ブレンダン・ベンソン独特の
"ナックルボールのように無回転でゆらめく"音世界は健在。
そして最終ミックスを御大チャド・ブレイクに任せたことで
ユラユラ感と甘いメロディが増幅、さらに磨きがかかってます! |
| posted on 2005.03.25 |
|
| ▲TOP |
| Yoshii Lovinson |
| White Room |
|
 |
 |
Phoenix
Call Me
欲望
Wanted And Sheep
Rainbow
Just A Little Day
Final Countdown
Naturally
トブヨウニ [Album version]
For Me Now
What Time |
 |
 |
 公式サイト(日本語) 公式サイト(日本語)
 Release Date : 2005.03.09 Release Date : 2005.03.09 |
|
 |
Yoshii Lovinsonとなって2作目のアルバム。
前作『At The Black Hole』は、ドラム以外の楽器を
すべて本人自身が演奏して仕上げられましたが、
今回はアメリカの有名ミュージシャンに加えて
元The Yellow Monkeyのエマをギターに迎えて
録音されたようです。
クロ(『At The Black Hole』)から
シロ(『White Room』)へ。
変わりましたねぇ、変わりましたよ!
吉井さんの髪型と同じくらい、変わりました。
変わったというか、ハジけた!と言ったほうが
いいかもしれません。
前作を作ることで、
自分の目の前に広がる暗黒の霧を振り払い、
自分の周囲にまとわりつくしがらみを打ち破って、
ついに太陽の光を浴びたぞ!という
今の吉井さんがここにあり、この音楽がある。
なんかそんな気がするんだよなぁ。
そうじゃなきゃ、
と、悲しげな自問自答をしたり、
So She Was Crazy
まぼろしの
Sweet Candy Rainが降り
救いだった神にすらもう
Say Goodbye Say Goodbye
もう誰のせいにもしない |
なんて、一年前にはこう歌っていた人がですよ、
と言えたり、
どうしたのうつむいて
どうしたの振り向いて
過去も未来もここにはないんだよ
徐々にで そう 徐々にでいいから
もっと重たいもの持てるよ
捨ててしまったもの 戻ってこないけれど
なくしてしまったものなら
急に帰ってくることあるんだぜ
Open Your Eyes
Open Your Mind
Open Your Life
Open Now |
なんて歌えるようになるとは思えないんだもん。
すご〜くいい変化だとは思いませんか!?
吉井復活!を大きく宣言する、すがすがしい傑作。 |
| posted on 2005.03.22 |
|
| ▲TOP |
| Yuki |
| Joy |
|
 |
 |
舞い上がれ
JOY
ハローグッバイ
Walking On The Skyline
スウィートセブンティーン
サイダー
AIR WAVE
WAGON
ブレーキはノー
キスをしようよ
ティンカーベル
愛しあえば
Home Sweet Home |
 |
 |
 公式サイト(日本語) 公式サイト(日本語)
 Release Date : 2005.02.23 Release Date : 2005.02.23 |
|
 |
こういうことを考え出すと、
いかに自分が時代の波に乗っていなかったかを
痛感してしまうのですが、
(いや、時代の波に乗ることが善だと言うつもりはありません)
わたくし、ジュディ・アンド・マリーの音楽なんて
マトモに聴いたことがございません。
だれかが歌うカラオケで耳にする程度ですし、
それを聴いたからといってさほどの興味を示すわけでもない。
へぇ〜、これがジュディマリってやつねぇ、って感じです。
思えば、オレの場合、BOOWYもTMネットワークも尾崎豊も
どれにも興味を示さなかったよなぁ〜。ヘンなヤツだ。
と、そんなわたくしがYUKIさんに興味を持ったのは
ちょうど3年前の今頃の話。
当時「天使が舞い降りてきたかのような」と表現した
彼女の音楽が、また再び帰ってまいりました!
-----
このアルバムを聴いてると、
オレが子ども時代、大好物だったお菓子を思い出します。
それはゼリービーンズ。
外側を色とりどりの砂糖で塗りかためられた
粒状のゼリーです。オレ、これがとにかく大好きで
毎日一袋ぐらいは平らげてたと思います。
しかもモーレツな勢いで食らいついてたので、
鼻血が出てしまったことも一度や二度では済まなかったはず…。
そう、YUKIさんの音楽も、まるでゼリービーンズのよう。
彼女の歌声は砂糖のように甘く、ゼリーのように柔らかく。
歌詞を聴いていると、明るく前向きな気持ちになると同時に
さりげなく深みを帯びていることに感心したりもします。
そして、それをコーティングしている演奏やアレンジは
色とりどりでピカピカしてて、ぜんぜん飽きが来ない。
で、いくら食べても飽きないからといって
バクバク食べてばかりいると、
脂肪がついたりた虫歯になったりして
ちょっとブルーになるけど、でも、だいじょうぶ!
「人生、こんなこともあるさ。ドンマイドンマイ。」
っていう気分になるのです。不思議と。
これぞゼリービーンズ・ポップだ!(ketsu命名)
-----
彼女が歌いたいことと、
彼女自身のキャラクターと、
リスナーが彼女に求めているものが
ここまでイヤミなく融合していることって
すごく幸せで珍しくて理想的なことなんじゃないかと
思いますね。
このCDには、春という季節が良く似合う♪ |
| posted on 2005.03.21 |
|
| ▲TOP |
| Doves |
| Some Cities |
|
 |
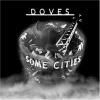 |
Some Cities
Black And White Town
Almost Forgot Myself
Snowden
The Storm
Walk In Fire
One Of These Days
Someday Soon
Shadows Of Salford
Sky Starts Falling
Ambition |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2005.02.23 Release Date : 2005.02.23 |
|
 |
先ごろの全英アルバムチャートで初登場1位を記録した、
ダヴズの3枚目のアルバム。
(ちなみに前作も初登場1位でした)
いやぁ、いよいよ国民的バンドの仲間入りですなぁ〜。
ダヴズ愛好者としては感慨もひとしおです。はい。
今回も、ジャケットは黒、音楽もダヴズワールド全開!
漆黒の闇の中を、純白のハトが優雅に飛び立つ感じ。
なのですが、今までとはまた一味違った一面を
見せることに成功した一枚にもなっている印象がありますね。
その「一味違った」一面とは、ズバリ!
生々しさ
これですよ♪
デビュー作よりも2作目、2作目よりも3作目と
彼らの持つ躍動感がCDの中にどんどんあふれ出してくる
ようになりました。だから、聴いててすごく楽しいし、
カラダが勝手に反応してしまう感じがいいんですよ♪
彼らがダンスフロア出身のバンドであることが
改めて浮き彫りになっているんだと思います。
ほんと、こういうライブ感って、大事ですよねぇ。
そして、こういうライブ感を
CDの中にバチッと吹き込めているということは
このバンドが非常に良いコンディションにある
という証拠なんだと、オレは思うのです。
あぁぁ、これを聴いてたら、
また彼らのライブに行きたくなってきたぞ〜!
今年のフジロックには来ないのかなぁ??
来てほしいなぁ、ぜひ来てほしいなぁ!!
できれば、土曜日の夜中あたりにやってほしいなぁ。
そしたら、ずうぇったい("絶対"の最上級)に行くんだけどなぁ!! |
| posted on 2005.03.14 |
|
| ▲TOP |
| Toad The Wet Sprocket |
Welcome Home :
Live At The Arlington Theatre, Santa Barbara 1992 |
|
 |
 |
Walk on the Ocean
One Little Girl
Scenes from a Vinyl Recliner
All I Want
Jam
Before You Were Born
Butterflies
Torn
Chile
Nightingale Song
Brother
Hold Her Down
Come Back Down
Stories I Tell
Know Me
Way Away
Is It for Me
Fall Down
I Will Not Take These Things for Granted |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2005.01.11 Release Date : 2005.01.11 |
|
 |
タイトルどおり、1992年、彼らの故郷である
サンタバーバラにて行われたライブの模様が
バンド解散から数年を経た今、リリースされました。
1992年、Toad The Wet Sprocket(以下TTWS)にとっては
一大転機の年でした。
シングル"All I Want"と"Walk on the Ocean"のヒットを
きっかけに、3rdアルバム『Fear』がブレイクしたのです。
当時のアメリカは
「産業ロック」と呼ばれた売れ線ハードロックと
のちに「グランジ」と呼ばれるようになるオルタナロックが
世代交代しつつあったころ。
(ちょうどNirvanaが現れたのが1991年ですから)
そんな厳しい時代のなかで、
TTWSが奏でる、時代の流れに乗らない繊細で切実な音楽は
一服の清涼剤的な役割を果たしていたのかもしれません。
そんな上昇気流が吹きまくっている時期に
地元へ帰っての凱旋公演なんだから、
観客もバンド自身も盛り上がらないわけがない!
とても引き締まったいい演奏が繰り広げられています。
気合いというか集中力がビンビン伝わってきますよ。
ほんと、このライブ盤には彼らの魅力がてんこ盛り♪
繊細でありながら力強い歌声と演奏。
バンドとしての一体感。
彼らの音楽に対する真剣さからくる、観客との距離感。
そして、なによりも若さを感じます。
まっすぐなんだな、音が、声が、雰囲気が。
あぁ、彼らのライブも、ナマで見てみたかったなぁ。
っていうか、日本では最後までライブできなかったもんなぁ。
(業界関係者向けのライブを開いたのが最初で最後なはず)
もうすでに解散してしまったバンドの全盛期を
こういう形で知ってしまうのはとても残念なことですが、
まぁ、そんなこともあるさ、ってことで。
もうすぐリリースされる、TTWSの中心人物
グレン・フィリップスのソロアルバムにも期待しましょー! |
| posted on 2005.03.12 |
|
| ▲TOP |
| Train |
| Alive At Last [live] |
|
 |
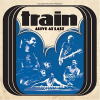 |
Calling All Angels
She's On Fire
Meet Virginia
Save The Day
Get To Me
Landmine
All American Girl
When I Look To The Sky
Latin Interlude
I Wish You Would
Sweet Rain
Free
Drops Of Jupiter
Stay With Me
Ordinary
New Sensation |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2004.11.02 Release Date : 2004.11.02 |
|
 |
たとえば、Mr.Childrenという、日本の音楽界の中で
最高峰に位置するようなロックバンドがあります。
でも、彼らが今の音楽を
アメリカやイギリスやヨーロッパに
そのまま持っていって活動したとしたら、
日本と同じような支持を受けられるだろうか?
そう考えるとギモンです。
日本人から見ると、
「あんなにいい音楽、世界中どこに行っても認められる、
受け入れられるに決まってる!」
と考えますよね。実際そうであってほしいと思います。
でも、世界にはいろんな音楽があり、いろんな人種がいて、
いろんな気候があり、いろんな国民性がありますから、
どこでどういう受け入れ方(拒絶のされ方)をされるのか
オレみたいなシロウトには見当もつきません。
-----
さて、本題のTrainの話。
このアルバムは、彼らの最新作『My Private Nation』に伴う
アメリカ・アラバマ州バーミンガムでのライブの様子
プラス新曲2曲(映画『スパイダーマン2』で使われた
"Ordinary"が収録されてるのがうれしい!)が収められた一枚。
でね、ライブの様子を聴いてると、
とにかくお客さんの盛り上がり方がすごいの!
最初から最後まで一字一句すべての歌詞を
観客全員がバンドとともに歌ってる感じ。
その大歓声に負けない、パット・モナハンの超絶ヴォーカルは
さらにすさまじいんですけれども!
だから、
「あぁ〜、アメリカ人って、やっぱ、こういう
正統派アメリカンロックが大好きなんだなぁ!」
って思ったんですよ。
日本ではほとんど知名度がない、このTrainというバンドを
(実はグラミー賞だって獲ってる実力派なんですけどね)
こよなく愛しているアメリカ人が大勢いるという事実。
これは日本にいたら決してわからないことなんだと思いました。
そして、この音楽がなぜ日本でヒットしないのかも
釈然としないモヤモヤとして残ります。
すごくいい音楽なんだけどなぁ〜。
彼らのような「自国ほどの知名度が日本ではほとんどない」
ミュージシャンってけっこういるけど、
(たとえばTom PettyとかCounting Crowsとか)
なぜ人気が出ないのか、不思議ですよね。
それを実感するという意味でも
もちろん純粋に音楽を楽しめるという意味でも、
このライブ盤は貴重っす。 |
| posted on 2005.03.09 |
|
| ▲TOP |
| Jeff Hanson |
| Jeff Hanson |
|
 |
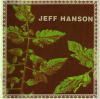 |
Losing A Year
Now We Know
Welcome Here
I Just Don't Believe You
I Know Your Name
Someone Else
This Time It Will
Let You Out
Long Overdue
Something About |
 |
 |
 公式サイト(英語) 公式サイト(英語)
 Release Date : 2005.02.22 Release Date : 2005.02.22 |
|
 |
前作『Son』を初めて手にしたのが、2年前の冬でした。
この「オトコなのかオンナなのかわからない、中性的な声」と
「美メロ満載にもかかわらず、あくまでマイペースな感じ」が
ヒジョーに好感触で、この年の10枚に選んでしまったほどでした。
そして、この2枚目のアルバムが発表されるまでの間に
ジェフ・ハンソンが目指すべきアーティストの手本である
エリオット・スミスが自殺して、この世からいなくなりました。
エリオットの音楽と、ジェフの音楽はとても似ています。
ささやきかけるようなヴォーカル。
必要最小限の楽器構成とアレンジメント。
美しいがゆえに、どこかはかなげなメロディ。
無駄な曲がひとつも存在しない、そのストイックさ。
似・て・い・る!
エリオットの音楽人生も、ソロ初期の頃は
ほとんどの曲がひとりで弾き語っているものでした。
"たくさんの誰かに聴いてもらいたくて歌ってる"という感じではなく、
たったひとりの誰かのために歌ってるような気がしました。
ジェフのデビュー作もそんな雰囲気。
雪に閉ざされた山小屋の中で、春を夢見ながら
ひとりギターを爪弾いてる感じ。
でも、エリオットがメジャーレーベルと契約して
彼の音楽を待つたくさんの大衆と向き合うようになったのと
同じように、ジェフ・ハンソンもまた、このアルバムで
小さな一歩を踏み出したようです。
その証拠は、アルバムの1曲目"Losing A Year"の
3分54秒にあります!
もう、この曲を、この瞬間を聴いてるだけで鳥肌ゾクゾク!
ジェフ・ハンソンの見てる世界が、色彩が
パァ〜と目の前に広がってくるようです。
優しい音楽に癒されたい人、
小さな元気をもらいたい人、
トゲトゲした日常からしばしの逃亡を図りたい人、
美しいメロディに身を任せたい人、
柔らかな声にうっとりしたい人におすすめです。
エリオット・スミス亡き今、その音楽を継ぐのはジェフ・ハンソン。
自分らしさと、自分の持つ可能性を信じつつ、
あくまでマイペースでがんばれ! |
| posted on 2005.03.03 |
|
| ▲TOP |