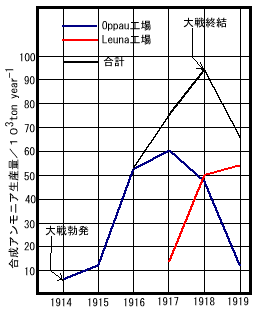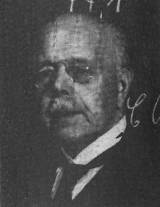|
|
(3webサーバー) |
(midiあり 3webサーバー) |
|
ご感想、ご要望等はこちらへ |
| アンモニア合成法の成功と
第一次世界大戦の勃発 (2/2) (要約+注釈)
|
プリと思われるので訂正した。 注2・・・・・・・原文では”硫酸”となっていたが、それだ と本文(アンモニアの酸化の部分)とあまり 関連性がないので”硫酸”はミスプリと判断 し”硝酸”に訂正した。
|
2 .大戦勃発時のドイツ国内の雰囲気
(政治的反対理由) 結果的にみて、第一次大戦は第二次大戦と同じく、国の全資材を動員する形態で終わった。しかし前者の開戦時にドイツ軍指導部は、そのようになると予想してはいなかった。彼らは食料と火薬の必須原料であったチリ硝石の輸入が、優勢なイギリスの海軍力により不可能となるにしても、そうなるまでに戦争は勝利に終わると考えていた。したがって「クリスマスには帰りますよ」といって、ドイツの青年は出征していった。こんな状況は多くの歴史書にかかれている。Boschを助けて工業化に必要な触媒を発見したA.Nittaschは、「開戦時まで、軍指導部の最高責任者は誰一人として
BASF社の工場を尋ねなかった」と記してそれを裏付けている。永世中立のベルギーへの侵入という国際条約を破る暴挙を行ったのに、九月中旬のマルヌの戦闘に破れた軍部は、以後ようやく短期隊利をあきらめ、化学工場の重要性に気付いたとMittaschはいう。
戦争遂行に必要な火薬を製造するには硝酸が必要である。火薬原料の使いやすさを、チリ硝石とハーバー・ボッシュ法で得られたアンモニアとで比較すると、チリ硝石のほうが使いやすいと思われる。なぜならば、チリ硝石は硝酸ナトリウムであるから、すでに硝酸イオンが存在していて、ただ硫酸と混ぜれば硝酸が得られる。しかしアンモニアの場合は、触媒を利用した複雑な管理で酸化しないと硝酸が得られないからである。
|
|
しかし、肥料としては硫安は硝石に劣るとの説もあったため、BASF社はオストワルド法によらないアンモニアの酸化研究だけは1914年3月にその酸化法を完成させていた。この酸化法を利用した工場は開戦時にはなかったようだ。その酸化法を利用した工場建設の着手は1914年10月であった。着手のきっかけはちょうどそのころ戦争が長期戦の様相が表れ始めたためドイツ軍部が慌ててBASF社に窒素問題の解決を依頼してきたことによるようだ。工場は、すでに酸化法が確定していたため1915年5月には操業開始できた。ここでおもしろいことに、工場建設着手当初の合成アンモニア量はその工場の硝酸生成量をまかなうほどの量よりかなり少なかったようだ。そのことは出来上がっ |
(まあここでは、それでは片手落ちの計画だから政府がそんな愚かなことはするはずないので通説を否定できる、と、いっているみたいです。だけどさぁー、歴史的に見ると、そういう場当たり的で片手落ちな計画をする政府って結構見あたるような気がしますけどねぇー・・・・・(^_^;) ちょっと俺、ひねくれてるかな?(^_^;) )
4 .誤った通説を産んだ一原因と結語
以上のごとく、アンモニア合成法は軍国主戦的要望造成のためドイツで着手され、その教府により支援され、完成され、あるいは開戦の一因となったとの通説がある。しかしこれらは全て妥当でないことを異なる三つの方回から示した。どうしてこんな通説が広まったかは大いに検討する必要がある。
まず本法の完成が開戦少し前であったため、一般人はもちろん、化学者にまで、その全貌が知られなかったこと、しかも戦争により国際間の情報収集が困難となり、機密保持を意図するBASF社にいよいよ好都合となった事情があげられる。
BASF社は、戦後数年間も連合国占領地区にあったが、第二次大戦後と違って特許こそ敵国資産として没収されたが、ノウハウまでは公開させられなかった。
しかも戦後まもなく現われた連合国側の見当違いの文献が、上述の疑惑を増幅し、通説を信頼させるに役立ったと思われる。二つの例によって説明しよう。第一は、”世界攻撃戦争の協力者としてのドイツ学者連”と題するフランスの一雑誌に載った評論である。これによると多数のドイツ学者は以前から戦争準備に参加していた。その結果、開戦時にはチリ硝石を初め各種の資源不足を解決し、長期戦を可能としたとしている。第二は、アメリカの一技術将校が、イギリスの有力雑誌に寄稿した空中窒素固定法の総説である。彼は序文に”この重要な方法を急速に進歩させたのは、戦争であって平和ではない”と断定し、”ドイツは冷血な打算的立場から、この研究に奨励金を出して支援した”。そしてハーバー、オストワルドらの研究により、”チリ硝石への依存の心配なくなるまで、宣戦布告をおさえていた”と書いて、それから本文にはいっている。
戦争の余波とみられる、こんな事実を意図的にゆがめた記述を読んだ人々、それを間接的にきいた人々が、何らかその影響を受けるのは不思議でない。しかし年月の経過は戦争の悪夢を薄らげ、正しい事実を浮び上らせると期持される。ところが依然として消えさらぬ原因の存在を、ここに注意しておきたい。
第一は、本法の成功が科学の進歩と戦争との関連する好例として示され、化学者を含めて全科学者の研究目的の反省や検討の資料とされる場合である。序文にも触れたごとく、この傾向は第二次大戦後に特に認められる。第二は、科学技術の振興が国防上に重要なことを強調するため、これを引用する場合である。その例は両次の世界大戦間に出版された我国の各種の書中にみられる。著者は恐らく政府と民間人に、純正と応用化学の重視を認めさせようと意図したのであろう。
しかし論理的にきわめて辻褄が会っていても、いずれの主張をも誤りとわかった以上、正しい化学史の立場から、これらを無視するに止まらず、積極的に消し去ることが望ましい。
対象とする事項がアンモニア合成法という、人類にとって貴重な文化の資産の誕生に関係しているからである。
(完)
←1ページ目へ