100. やっとこさ#3
懸案のマフラーステーとリアブレーキロッドの短縮が完了。
ロッドを6cm程度切断し、ブレーキペダル側の先端を1cmくらい万力に咥えて直角に曲げ、
そのあとΦ2の穴を開けました。
(いい加減ですので、確認して行ってください。)
何とかあんばい良く収まりました。
次はマフラーステーです。
さすがにアングル材で済ますわけにもいかず、社外品のステーを購入。
タケガワのマフラーは、排気抵抗を下げるためでしょうかエキゾースト入口付近の曲がりが緩く
下側に張り出し気味になります。
しかしそこからほぼ地面と水平にリア側に取り回しされているので、大きく車体から離れ、
ボディとエキゾーストパイプの間から向こうが丸見えになることはありません。
これで、この落書き100回目で目標だった
「60km/hまで一気に加速し、80km/hまで楽に達して、60km/hで巡行できるオートバイ」
は、なんとか達成できました。
2017年7月に88ccにボアアップを行ってから、2年ちょい。
ボアアップ、ビッグバルブ化、マフラー交換を行ってきましたが、やっと完結。
これで意識せずに車の流れに乗って行けます。
でもこれ以上最高速が上がると、車体剛性、ブレーキ容量が完全に不足し、危険な領域になります。
莫大な資金を投入してカスタムすれば何とかなるかもしれませんが、オーナーには不要。
それ以上の速さはDucaやNinjaで楽しみます。
CD50S最高速アップの一考察 (エンジンはモンキー用のリターン4速です)
まずはオーナーの仕様です。
1、エンジン デイトナニューハイパーヘッド 88㏄+ビッグバルブヘッド(ハイカム)
2、キャブレター PC20 + 専用インテークマニホールド + エアフィルター
3、マフラー タケガワ モンキー用
4、ギア スプロケット F:16T R:36T
エンジンはチューニング度が高くないと言われているデイトナ製ですが、12000rpmまで回ります。
この2年間、ちょっとづつ改造したことでいろいろ判りました。
①75ccへのボアアップでは、ほんの少しトルクが上がる感じ(=加速改善)で、マフラーもCD90用ならなんとか行ける。
②88ccにボアアップすると、明らかにトルクは上がるが、最高回転数は上がらない。
(頭打ちがはっきりする感じです。)
なので、Benlyで88ccボアアップを行う場合のオーナーが思う手順は、
① フロントフォークオイル交換+固めオイル、リアサス交換、ブレーキ強化(シュー交換、レバー交換)
② 88ccボアアップ、PC20、インテークマニホールド、強化クラッチ交換でトルクアップ。
③ ヘッド、マフラー交換でフルパワー化。 12000rpmまでいつも回す場合は2次クラッチに交換。
マフラーは、しっかりしたメーカーのマフラーがいいと思います。
中華の新品を買っても、音がうるさすぎて使えなかったというHPをよく見ますので。
まあ、20万円もあれば上記の部品は新品で手に入りますので、一気にやるのも良いと思います。
オーナーはどの部品がどんな効果を持っているかを見たかったので少しづつゆっくりやりましたが。
さてあとは、ちょこちょこした部分ですので、暇を見つけて改良していきます。
2019/12/28
99. やっとこさ #2
そして、次はマフラー。
ステップの交換によりマフラーの交換が必要となります。
マフラーの選択ですが、ヘッド交換後、純正マフラー+穴あけでは8000rpm以上の回転上昇は遅く、
折角のヘッドの高回転があまり使えていなかったので、ちゃんとした物を物色することにしました。
(当然中古ですが)
使えるマフラーは大きく分けて2タイプ。
CL50のようなボディ横を取りまわすスクランブラータイプと、車体の下を通るタイプ。
スクランブラーにも興味がありますが、選べるものが少なくパワーが上がるものも少ないようです。
なので今回は車体下を通るタイプにすることにしました。
また他の方々のHPを参考にBenly50S+モンキーRバックステップに適用できるマフラーを選びました。
しかしモンキー用は車体とマフラーの隙間が大きく最低地上高も低くなり見栄えが良くないものが多く
なかなかピタッと取り付くものが少ないようです。
それで色々物色していたのですが、やっとタケガワの古いタイプのマフラーを見つけて購入。
JMCAのプレート付ですが、ちゃきちゃき堂が住宅地にあるため、アルミのバッフルも取り付けました。
マフラーステーは取付位置を検討するため、アングル材で一時的に代用。あとで改善します。
そして試走結果です。
まずは音
アイドリング:キャブトン系のポコポコ音でちょっとびっくり。
バッフルを外すとそんなに大きい音ではありませんが、ポコポコ音が気に入ったので、
バッフルは付けたままにします。
中高回転:他と一緒のブォーン。
乗った感じ
走り出すと、抜けが良いのか少しトルクが薄くなった感じですが5000rpm位まであまり変化なし。
しかし上昇が鈍る7000rpm以上が激変しました。
3速なら12000rpm以上までふけ切ります。
8000rpmから回転の上昇が早くなる感じです。
4速は平坦地で5000rpmからゆっくり回転が上昇してましたが、その回転上昇が早くなりました。
4車線の道路でも車をリードできる加速と最高速が手に入りました。
結局、CD90ノーマルマフラー+穴あけでは、88ccでも8000rpm以上は抜けなかったということです。
2019/12/22
98. やっとこさ #1
年の暮れも迫ったこの休み、これまで懸案だったカスタムを実行することにしました。
やっと社外品や流用部品を買いそろえ、カスタムの開始です。
今回は3回に分けて報告します。
まずはハイスロットル。
今までの純正のスロットルホルダーは、フルスロットルまで結構な開度があり、持ち直したりしていました。
でも全開になるので使っていたのですが、ワイヤーの外側のチューブがひび割れてきてしまいました。
このチューブがひび割れる水が入りやすくなりワイヤーが錆びます。
なので、キタコのモンキー用のハイスロットルを購入。
2種類のうちワイヤーが長いほうを選んだのですが、通常の取り回し(ステムの外側を通してキャブへ)
ができず、ステアリングステム手前で曲げてそのままキャブレターへ。
でもハンドルを左右に切ってもワイヤーの引っ掛かりもなく、少ない開度で全開にできます。
前回交換したスピードメーターと合わせて、ハンドル周りはほぼ完了です。
続いてステップ。
Benlyのステップバーは実用車ベースのため、おもいっきり前にあります。
平坦地を走る分には楽ですが、ギャップを超える時のスタンディングは前に立つ感じになるため
立ちにくく、またコーナーでも踏ん張りがきかないため、お尻で荷重をかけるような走りになります。
そこでステップバーが普通のオートバイの位置になるバックステップを物色しました。
しかしBenly用の社外バックステップは位置が悪いとかブレーキが効かないとか高いとかーーー。
いろいろ検討した結果、評判の良いモンキーR用のステップを流用することにしました。
このステップを付けるとお気に入りだった純正のすっきりしたマフラーが使えなくなりますが、
正しいステップ位置は安全にも繋がるので、ステップ交換を優先しマフラーは社外品を使うことに。
そしてヤフオクでなんとかモンキーR用のステップを落札。
入手はしたものの取り付け方法はよくわかりませんでしたが、何とか取付完了しました。
まずはマフラーとブレーキペダル、シフトペダルを外します。
モンキーR用のステッププレートは、2か所の取付穴が付いています。
上の穴はスイングアームピボットシャフトと共締め。(穴はちょっと大きめです)
スイングアームのピボットシャフトを抜いてワッシャをかませて共締めすればOK.
下の穴はブレーキペダルのシャフト(φ12)が通っていた貫通穴 (CD50ではメインスタンド用)に固定。
しかし、ステッププレートの下の穴はΦ8。
位置も少し違うので、プレートの下の穴をセンター位置そのままで穴をΦ12に拡大しても入りそうにありません。
なので強度的に不安ですが、Φ8×300位の全ネジ+高ナット+ナットで固定します。
高ナットを使って強度アップさせているとはいえ、ちょっと不安。(やるなら自己責任でお願いします)
取り付けた結果、全ネジのブレーキ側が30mmほど余ってますので、あとで要調整です。
またペダルへのブレーキスイッチのエクステンションスプリング取付穴あけが必要です。
(今はインシュロックで仮止めしてます)
キックアームは以前購入していたKITACOのものを取り付けました。
ステップバーがホンダの大型車用(現行のCB400FSのものが付きました。ピンはモンキーR用を使います)で
キックするときにキックアームと干渉するので今はステップバーのリターンスプリングを外し、ステップの取付を少し狭めて
バーの動きをきつめにしています。
そうするとキックするときに畳んでも自重で戻らなくなり、キックアームに当たりません。
多少手こずるのはリアブレーキロッドの取り回し。
オーナーはリアブレーキアームを上向きにして強引に取り付けました。
(本当はロッドを数cm位短くするとよいのですが)
チェンジペダルは、ロッドの長さもドンピシャでそのまま取り付けOKでした。
そして純正のサイドスタンド+ステップを取り外し、適用車種不明のサイドスタンドを取り付けました。
スタンドの仕舞い忘れ防止のスタンドスイッチも他の方のHPを参考にしてキャンセルしました。
問題のステップバー位置ですが、高さはほとんど変わらず、後方に20cmくらい移動します。
これでやっと普通のオートバイのステップ位置になり、ちょうど踏ん張りが効く位置になります。
ステップに立っても撓むこともないのでΦ8全ネジでなんとか行けそうです。
また、チェンジペダルはストロークがいい具合に大きくなり、軽くまた正確にギアチェンジできます。
皆さんが言われるようにポジションはモンキーRのものが一番かも。
2019/12/22
97. バチバチッ
朝、ベンリィのエンジンをかけた時です。
スロットルを煽ったときに バチバチッ っていう電機がショートしたような音が。
エンジンをかけて暫くすると止まります。
ヘッドを変えてそろそろ1000km、ヘッドボルトの緩みでしょう。
増し締めをすると、案の定、ヘッドボルトが緩んでました。
ヘッドの熱による変形、爆発によるボルトの緩みだと思いますが、結構緩んでました。
規定トルクで締めた後、エンジンを掛けましたが、バチバチッ 音は消えました。
エンジン、結構無理してるかもしれません。
暫く様子見です。
あっ、スピードメーター交換しました。
購入したときに付いていた社外のメーターの走行距離はだいたい25000kmでした。
またこれからです。
2019/11/20
96. 素人整備の問題点
この休みも少し乗ってみました。
出足が少しかったるいのですが、その分2速、3速の守備範囲が思いのほか広がり、街中では
非常に乗りやすくなりました。
また、これまで使っていたDaytonaのエアフィルターの網の部分が錆びてみっともなくなったので、
キタコの網付きファンネルにしてみました。
ま、パワーも音も特に変化はなく、これに適当なスポンジのカバーを付ければいいかなと思ってます。
そのファンネルを付けて60km/h+αで走行中に、リアブレーキを踏むとリアが「うにゅ」って撚れました。
なんじゃこりゃって思いながらおとなしく帰宅。
リアブレーキで「うにゅ」ってときは、だいたいホイールの固定ができていないとき。
可能性としては、リアアクスルの締め付け不足、スイングアームの固定不良、サスの固定不良 etc。
で結果はアクスルシャフトのナットの締め付け不足。
チェーンを短くしたときに締め付けが甘かったのか締めてなかったか。
やっぱ素人整備ですね。
次からマジックで締め付けチェックをしないとと思う今日この頃です。
2019/10/28
95. ドリブンの適正化 2
ちょっと50kmほど走ってみました。
本日、この時期にしては珍しく30℃近くまで上がりました。
R246を通って山北までの往復です。
そこで気づいたこと。
1)各ギアの守備速度が広がり、チェンジのタイミングが伸びて、運転が楽になりました。
3速7000rpmで70km/hまで引っ張れるので、4速80km/hの到達が楽になりました。
2)1速のエンジンブレーキが緩やかになり、ぎくしゃくしなくなりました。
3)エンジン回転数が落ちたことで、今日の気温でも油温が100℃を超えることはありませんでした。
4)さすがに加速は落ちましたが、本来のまったり系の乗り味に磨きがかかりました。
とはいえ、2速で60kmが可能になったので、ほとんどの坂は流れに乗って登っていけます。
4速は予想通り緩い上り坂のみ。
まあTopギアですから小排気量では本来そんなもんですが。
もうちょっとクロス(ドリブンを大きくする)にして38Tくらいが丁度いい気もしますが、特に我慢できない
レベルでもないので、暫くこのままで乗ります。
2019/10/05
94. ドリブンの適正化 1
マフラーもなかなか見つからないので、以前から考えていたドリブンを変更しました。
オーナーのBenly50Sは購入時よりモンキーのエンジンを積んでいます。
で、ギア比はというと、1速が気が遠くなるほど低く、2~4速はそれなりに繋がっていきます。
最終的には4速60km/hで約6000rpm。
この6000rpmが曲者で、少し振動が出てくる回転数です。
折角原付2種にしたので60km/hでの巡行は楽にしたいと思い、振動が出ない5000rpmで60㎞/hを
出すために、ドリブンギアを41→36Tにしてみました。
当然、全体的にロングになり、最悪4速での加速がなくなるかもしれませんが。
で交換です。
リアタイヤを外し、スプロケットを交換。
更にチェーンが余るので、切りました。
ほんで試乗。
これまで1速はどう頑張っても30km/hちょいがいいとこだったのですが40km/hまで引っ張れます。
1速の加速は当然落ちますが、さすがに88ccまでボアアップするとそんなに気になりません。
それより1速で引っ張れる時間が長くなり、2速へ忙しくギアチェンジしなくて良くなりました。
そして4速60km/hは5000rpmになりました。
振動もなく、快適な回転数ですが、当然加速は落ちました。
でも3速8500rpmで80km/hまで引っ張れそうなので、4速は巡行用でもいいかもしれません。
あと思いのほかありがたいのは、エンジンブレーキの利き方が甘くなったこと。
これまで1速、2速はエンジンブレーキが激しく、峠とかでは結構きつかったのですが、
エンジンブレーキがオーナーには丁度良い感じになりました。
チェーンにも少し優しくなるはずです。
暫く走ってみて、4速の加速を見てみます。
2019/09/29
93. マフラー
さて、油温の心配も思い込みで解決し、あとは80km/hの巡行をどれだけ楽にできるようにするか。
キャブ、エンジンはすでに100㎞を狙える状態。
また車体もBenly50Sなのでモンキーやシャリーに対してタイヤが大径で細い分、最高速には有利。
(ただし乗り手分のウエイト80kgは、大きなハンデですが)
やはり最後はマフラーです。
現在のマフラーは、抜けが悪い分、低中速のトルクがあるため、街中では乗りやすいのですが、
以前書いたように長距離を走るときは80km/hまでの到達時間が短いほうが疲れません。
ではどのマフラーにするか。
Benly50用のマフラーは少ないのですが、モンキー用を流用という手があります。
しかしネットに書き込まれている方々は、結構工夫しておられるようです。
オーナーがモンキー用のマフラー流用で気になるのは、最低地上高。
街乗専門ではなく、ツーリングにも行くオートバイです。
最低地上高は犠牲にしたくありません。
なので気長に探します。
2019/09/05
92. 油温確認
油温計を取り付けました。
M12の別売りセンサーを購入したのですが、どうも違う機種のものだったらしく、コネクター、抵抗値
が違うものでした。
再度購入しなおし、取付完了。
さて、どこまで温度が上がるやら。
今日、朝から確認のツーリングです。
気温は朝9時で30度 晴れ時々曇り。
自宅を出て、R246で御殿場に向かいます。
御殿場は、標高400mちょっとですが、小山から御殿場までの最後の登りは結構長く、最初の
確認には 打ってつけかと。
で、走ってみると、小山までの市街地走行では100℃前後、御殿場までの登りは60㎞キープで
6000~8000rpmで御殿場の道の駅に着くころには112℃に。
信号で待っていると最終的には118℃まで上がりました。
そこで、ここらあたりで最も標高が高い場所で、登りが長い道の沼津→芦ノ湖のR1を走ることに。
登りに入ってからは常時6000rpm以上で回しました。
110℃あたりまで油温が上がりましたが、その後気温も下がるためかそのままの温度で芦ノ湖に到着。
結局家に帰るまで、120℃になることはありませんでした。(強化オイルポンプの効果?)
今回は結構回し気味+真夏ですので、オーナーの走り方でこれ以上の温度になることはないと思います。
ですので、まずはオイルクーラーは装着せず、早めのオイル交換でやってみようと思います。
2019/08/19
91. 油の温度
エンジンは少しづつ思うようになってきていますが、今回はヘッドを変えたため、圧縮比も上がり
発熱量も増しているので油温が上がるはずです。
特に夏、ちょっと気になって油温計を付けることにしました。
購入した油温計は、回転計のメーカーと同じ。
ついてきたセンサーは、ベンリィのドレンボルトのM12ではないため、改めてM12の別売りセンサーを
購入するか、アダプターを購入するか----。
当然アダプターのほうが安いのですが、ネットを見るとネジがもげたとか物騒な話が載っていました。
なので、別売りセンサーを購入することにしました。
夏休みに届いたら、早速つけてみます。
2019/08/4
90. 最終仕上げ
今日はベンリィの最終仕上げです。
いつものように工具をトップケースに入れ、箱根を目指します。
天気は台風の後の曇り。
湿度、気温ともにキャブセッティングにはあまりよくありませんが、段々晴れてくるとのことですので決行。
メインとパイロットジェットは、Daytonaの指示通り#85と#38。 ニードルはクリップが下から2段目。
走り出して温まって来ると、アイドリングからアクセルを少しクイックに開けたときにストールしそうになります。
ゆっくり開けると回転は付いてきます。 どうもガスが濃いようです。
そこでニードルのクリップを下から4段目にしました。
すると、アクセルを開けたときのストールは回避されましたが、今度は中速でアクセルを開けたときにタイムラグが
出来てしまい微妙についてきません。 少し薄いようです。
なので、クリップを一つ低く(下から3段目)にしたところ、なんとかうまく繋がるようになりました。
そうやってだんだん回転を上げていくと、8000rpm以上がなかなか回りません。
これはもしかして、マフラーの詰まり?かもしれないということで、マフラーを「焼く」ため急遽ツーリングルートを変え、
自宅→箱根旧道→箱根峠→沼図→修善寺→戸田峠→沼津→御殿場→246で帰宅としました。
マフラーを焼いて中のカーボンを出すため、2~3速を意識して多用して見ました。 殆ど6500rpm以上でした。
暫く走っていると、思惑通りマフラーの音が変わり9000rp以上まで回るようになりました。
もともと濃い目のセッティングとしていたことと、街乗りばかりだったため、マフラーの中にカーボンが
詰まっていたようです。
社外マフラーの様に10000rpm以上楽に回るわけではありませんが、このマフラーでも
3速:70km/h、4速:80km/hオーバーは可能になり、到達時間も早くなったので、ストレスも減りました。
まずは満足です。
あとは、時間かけて良いマフラーを探していきます。
2019/07/22
89. またまたキャブ調整
今日は朝からベンリィの調整です。
まずは走らなきゃわからんということでいつもの御殿場の道の駅へ。
ところが、途中ガス欠のような状況でエンスト。当然ガス欠ではないのですが、なぜかエンジンが落ち着きません。
結果ストールしてしまします。
調整のためのツーリングでしたので、工具は満載。
キャブのフロート室にはガソリンが入っています。
ちょっと油面が高いかーーーって感じだったのででフロートを調整。
そして走り出すと今度はまたまたガス欠。今度はガスが入っていません。
やりすぎました。
そんなことを数回繰り返し、ガス欠しながら帰宅。
真面目に油面調整です。
PC20の油面を確認したところなんと基準-3mm。そりゃガス欠状態になりますわね。
どうも最後に調整したときに下げすぎたようです。
基準通りにすると、アイドリングも安定し、低速から中速は思いのほかトルクが増えました。
しかし7000rpm以上はちょっとボコボコします。
今度の休みに改めてジェット類の調整です。。
また楽しみが先送りになったわけです。
初心に帰るつもりで 明日が楽しみです。
2019/07/21
88. ヘッド交換
今日は朝からヘッド交換。
まずはエンジンをばらし、各部品の確認。
そしてヘッドのロッカーアームに新規購入したシャフトを通し、ヘッドの組付け。
ノーマルに比べると、バルブ、IN/EXの穴径が大きいことは一目瞭然ですが、フィンが大きくなっていて
見た目大きなヘッドに見えます。
またマニホールドもPC20のNewハイパーヘッド用です。
(劇的な変化はありません。)

トルクレンチでの確認を念入りに行ったことと、年のせいか途中組み間違い等あって結局午前中かかりました。
組み付けが終わり、エンジンを掛けると大きな変化はありませんが、すこし排気音が低くなった感じです。
ただ、低回転が安定しません。
キャブのパイロット、メインジェット類を掃除して何とか安定しました。
あとは実走でジェット類の選定です。
昼ご飯を食べて類をさて試乗----という時に、あいにくの雨。
まあ、組みつけたボルト類のなじみも明日になれば落ち着くと思いますので、丁度良いかと。
明日が楽しみです。
2019/07/20
87. 心機一転
とうとうビッグバルブヘッドにします。
オーナーは、Benly でもNinja Ducaでも一日中乗り続けるツーリングをします。
この長距離ツーリングで疲れないためには60km/h巡行が楽にできて車の流れにストレスなく乗ることが必要。
そのためには、80km/hまでは楽に達することが必要です。
そうなるとオーナーの経験上10Ps程度は必要です。(オーナーの物差しは昔女将用だったTDR80。)
これまで8,000rpmまでのトルクを上げ、4速・8000rpm・80km/hまでの到達時間を短くするため,
ノーマルヘッドのポート拡大、バルブスプリング強化、ハイカム、PC20、マフラー改造、点火強化、88㏄ボアアップ等を行い、
それなりの効果が出ました。
この仕様としてはいい状態だとは思います。
しかし結局6000~8000rpmまでのトルクは思うように上がらず、また8000rpmあたりから頭打ちが始まり、トルクが
ないまま10000rpmまで回るエンジンです。
このため現在は、各ギアで8000rpmまで回し、3速で頭打ちが始まる8000rpm・65km/hまではいい感じなのですが、
4速に上げた後は、6500rpmから8000rpm・80km/hまで伸びをじっと待つという状況です。
また登りになると4速60km/hの維持が難しく3速に落とすのですが、3速・8000rpm・60km/hで頭打ちのぎくしゃくした
余裕がない状態になります。
トルクが上がらない以上、ギアをロングにすることも難しい状況です。
これまで色々やりましたが、結局80km/hへの到達時間を短くするには、10000rpmまで回るエンジンにして3速で80kmが
出るようにすることが現実的ということのようです。
前回、Benlyのエンジンは最高回転数で10000rpm(レッドゾーンのイメージ)位と勝手に決めつけています。
10000rpmで巡行するわけでもないので大丈夫のはず(全く保証なし)
また4速・8000rpm・80km/hでの巡行も可能性が出てきます。
ちなみにもし4速で10000rpm回った時は、3桁に達します。
そこで、ビッグバルブヘッド+ハイカムによる高回転化です。
やってみることにしました。
シリンダーがDaytonaですので、ヘッドはそのバージョンアップ用のニューハイパーヘッド。
既にオイルポンプとクラッチは強化していますので、ヘッド交換と強化カムチェーン交換で完了。
カムチェーンはヘッドを交換するときにやる計画でした。
カタログでは、PC20とマフラー交換で10Psとのこと。TDR80と同じ。
高回転化に対して問題があるとすればオーナーの純正改造マフラー。
その時はまた穴をあけますかーーー。
最初からボアアップとビッグバルブヘッドに改造すればお手軽なのにという声もあるでしょうが、
ボアアップの効果、ビッグバルブの効果を確認したかったのであえて遠回りをしました。
それをやったことで、色々遊ばせてもらい、いろんなことが判りました。
趣味なので。
さて、どうなることやら。
2019/07/14
86. 最高回転数
以前、「今の仕様はトルクのピークが6500rpm、最高出力が7500rpmくらい」と書きましたが、
横型エンジンで許容される最高回転数はいくつ?と思い、調べてみました。
横型エンジンの高回転高出力で最も有名なのは有名なベンリイSS50。
そのスペックは、
最高出力 6ps/11,000rpm
最大トルク 0.4kgm/10,000rpm
最高速 95km/h
5速リターンマニュアルクラッチ
JKカムシャフト
φ17キャブレター
最高出力と、最大トルクの発生回転数がこんなに近いエンジンも珍しいですが、あの時代に
すでに市販車で10,000rpmを実用回転数としていたHONDAはとんでもないです。
数十年前に比べ、エンジンとして良くなっている点は
①ベアリング等の軸受けその他部品の高精度化
②潤滑オイルの高性能化
これに対して当時のベンリイSS50のスペシャル仕様が普通のベンリィ50Sより変更されていた点(可能性含め)は、
①点火タイミング
②クランク、コンロッド、等の精度(動バランス)
③ピストンのハイコンプ化、キャブレター、マフラー、 カムシャフトetc
かな。
しかし最高回転を許容するのは、エンジン内の加工精度と強度、そして潤滑。
だとすれば、数十年にわたって改良されたちゃきちゃき堂のBenlyも保険見て常用10,000rpmまで可能
(=レッドゾーンの始まり)ではないかなと都合よく思うことにしました。
横型エンジン、恐るべし。
2018/10/20
85. タンク干し
気が向くと行うタンクの水抜き。
錆防止のためですが、2~3年に1回くらいです。
丁度ガソリンが少なかったので、燃料ホースを外し、コックをON。
そしてタンクをゆすりながら中のガソリンをオイルパンに排出。
でも、コックのガソリン取入れ部が少し高い位置にあるため、コックごと外してまたタンクをゆすります。
ガソリンが出きったところでオイルパンに溜まったガソリンを見ると、細かい錆が結構出ています。
しかし、水はほとんど入っていませんでした。
しばらくタンクを干して、中のガソリンを揮発させます。
ガソリンが揮発しきったら、改めてガソリン注入。
次は、900SSとNinjaですな。 2018/ 8/16
84. 結局電気系って----。
車体のレギュレターが正常ということで低損失レギュレターのパンク原因もはっきりしないままですが、
タコメーターの表示が消えるときにじわじわと暗くなっていったこと、燃えたコンデンサーが低損失レギュレター
にほぼ接触していたことを考えると、振動で部品同士がだんだん近づき、それらの接触で過熱して
損傷したのかもしれません。(結局わかりませんが)
しょうがないので、低損失レギュレターを取り付けたときに、アクセサリーの - ではノイズが入ったのですが、
ボディーアースでノイズが入らなくなったことから、ダメもとで低損失レギュレター無しで同じように繋いでみました。
すると、アイドリングから高回転域まで安定して回転数を表示しています。
なんじゃそれ。
これまでバッテリー(アクセサリー)から直接 + と - を取ればノイズが少なく、ボディアースより効率の良い
電源が取れると思っていました。
しかしアクセサリー回路の中にノイズ源の - が流れているとその - からもノイズが入るようです。
また、ボディーアースは(素人考えですが)、バッテリーまでのボディーが抵抗になり、電子部品に影響する
レベルのノイズを低減するようです。(ほんまかいな? でもタコメーターが正確に表示するのは事実)
とは言ってもMFバッテリーと解放式バッテリーでまた違うのかもしれません。(BenlyはMFバッテリー)
オーナーにとっては、「結局電気系って、知識が乏しく、やってみなきゃわからん世界」です。
2018/ 8/16
83. 濡れエアフィルター。
ツーリングに行きました。
結局雨が降ってきて、ほぼ半日雨中走行。
すると、当然の如くエアフィルターが水を吸ってボコつきました。
30km/h位しか出ないのと、「ウィーン(正常)、ボー(かぶって失火)」を数秒ごとに繰り返します。
ただ、何故かエンストはしませんでした。
やはりツーリングに使う時は雨対策が必要です。
皆さんクリアの筒を加工したりして取り付けられているようです。
しかし、開口部の向き、大きさ等色々考えないといけないようです。
まず材質を選ぶにあたり考えるのは振動と熱ですが、熱はエンジンから結構離れているので
除外します。
次に振動ですが、エアフィルターはラバーダクトでキャブレターに繋がっていて、結構振動しています。
ですので、割れやすいものならできるだけ軽いものにする必要があります。
また、日常的にはカバー無しの状態で、雨が降ったときにのみ簡単に取り付けられる
カバーが理想です。
そうやって見ていると、コンビニのおでんの容器とかはサイズ的にも材質的にもほど良くて、
雨が降ったらコンビニでおでん食って、その容器をカバーにする---ちょっと気になってます。
2018/ 8/16
82. 濡れ衣。
ということでBenlyのレギュレターを確認。
エンジンかけて、配線で電圧確認しました。
その結果、9000rpmまで回しても14.2~14.5V。
またバッテリー単体でも12.5V。
全く問題ないとは言えないものの、低損失レギュレターがパンクするほどの
電圧にはなってません。
またまた原因が判らなくなりました。
2018/ 8/10
81. 低損失レギュレター 炎上。
地元のお祭りで、その下っ端の実行委員で、土日は熱中症覚悟でお祭りの準備をする予定でしたが、
足の皮膚の炎症が酷くなり、土曜の午前中、病院に行きました。
靴は履けるのですが、歩くとつま先が靴と擦れて痛い状態。
靴の代わりにサンダルなんかで祭りの準備して、足怪我したら元も子もありません。
ということで土日暇になってしまいました。
土曜日は午後、ディーラーでリーフのタイヤのローテーションを行い、おとなしく帰宅。
そして今日日曜日。
靴は履けるので、レギュレターの確認含め、Benlyでちょっとフラフラしてみようと出かけました。
家を出て、いつもの御殿場・箱根・小田原と順調にツーリング
ところが、家まであと20㎞という時に、タコメーターの表示が暗くなりました。
またエンジンを切ってキーをオンにするとアクセサリー電源で点くはずのタコメーターが点きません。
ただエンジンを掛けると暗く点きます。
その状態で帰ってきていましたが、家のすぐ近くでその薄く点いていたデジタル表示も消えました。
いやーな予感。
早速ヘッドライトをばらして中の配線を確認。 先週セットした低電圧レギュレターも確認‐‐‐‐‐。
げ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐、レギュレーターを入れていたフィルムケースが溶けてます。

なんと、ベロベロに溶けてます。
このケースをカッターナイフでばらして中を見ると、セラミックコンデンサーが焼けてなくなってました。
原因は、過電流? ということはやっぱりBenlyのレギュレターがパンク?
また調べることが増えました。
その対策が完了するまで、元の単三電池で12Vを供給するバッテリーボックスで駆動させることにします。
2018/ 8/5
80. タコメーター用レギュレター
台風で外にも行けなかったので、単三電池2本で動かしていたタコメーター用電源をオートバイから
取り出すために、低損失レギュレターを製作しました。
とは言っても秋月電子さんの100円のキットで、説明書通り適当にハンダ付けすれば完了。
直接部品同士をハンダ付けするのも何なんで、小さな基盤を使って作成。
防水のこともありますので、グルーガンで適当に防水加工し、カメラのフィルムの容器に穴をあけて
その中にセット。それが下の写真。

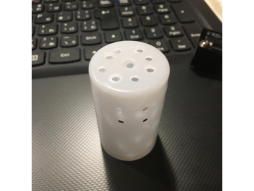
電子工作は趣味ではありませんので、本当に適当。 見た目はまったく気にしていません。
(秋月電子さん、ありがとう)
そして翌日、配線を行いました。
配線は下記の通り
①インプットの+は、アクセサリー電源(キーを回すとONになる配線。Benlyの場合、スタンド警告灯)に接続
②アウトプットの+は、当然タコメーターの +へ接続。
③レギュレターの-とタコメーターの- は、そこいらの-コードに潜りこませて接続。
そしてエンジン始動。
------だめでした。
アイドリングは安定しています表示するのですが、ブリッピングすると9000rpmとか3000rpmとか示します。
どうもノイズがまだ乗っています。
そこで一服しながら考えました。
+側は、アクセサリーから取っておりこれ以上ノイズがない電源はBenlyには存在しないので、問題無し。
とすると問題は-側。
あ、レギュレターには発振防止のコンデンサーを付けていて、その-とタコメーターの-を一緒にしたことで、
発信ノイズを拾っている?
そこで、タコメーターの-コードをボディーアースしたところ-----
何事もなかったかのように安定して表示するようになりました。
せっかく取ったノイズをまた取り込んでいたようなもんでしょうか。
原因はよくわかりませんが、まずはちゃんと表示しています。
結果、100円で単三乾電池2本の電源を廃止し、100gの軽量化ができました。
2018/ 7/29
79. ハブダンパー
ハブダンパーがダメみたいです。
ハブダンパーがへたると、クラッチを繋いだ時にへたって出来たクリアランスのため、一瞬遅れて駆動が伝わります。
通常走行しているときは特に気にならないのですが、低速で街中を散策すると、そのクラッチを繋ぐときの
タイムラグと衝撃でガクガクします。
また衝撃的な力が加わるようになるので、クラッチやチェーンにも悪い。
で、本日交換。
タイヤを外して、スプロケットハブはずして、ダンパーを新品と比べるとだいぶ痩せて小さくなってます。
新品を嵌めるときは、結構キチキチなのでドライバーとかで少しづつ入れていきます。
交換した結果、思いのほかガクガクがなくなり、すっごーくまともなオートバイになりました。
交換してもさすがにBenlyなので、多少ガクガクするのかと思いきや、まったくそれはなし。
1000円くらいの部品ですが、効果は結構大きいです。
さて次はNinjaのハブダンパー交換です。
2018/ 7/14
78. 現状把握
タペット調整も終了し、ちゃんと爆発するようになったなったので、スプロケットを14→16Tに交換しました。
そして、高速テスト。
エンジンが温まったところで、テスト開始。
色々やった結果、一番加速が良い(=頭打ち直前でシフトアップ)各ギアの最高速はそれぞれ、
1速 25km/h:7500rpm
2速 40km/h:7100rpm
3速 60km/h:7400rpm
でした。
そして4速でちゃんと加速するのは 70km/h:6600rpmまで。
そのあとは、加速が鈍りじわじわと 80㎞/h:7500rpmになります。
この結果からすると、今の仕様はトルクのピークが6500rpm、最高出力が7500rpmくらいのようです。
もともとのモンキーの最大出力は7500rpm、最大トルク発生回転数が6000rpmですので、
ハイカム+88㏄のボアアップ(ノーマルヘッド)にはしたものの、最高出力、最高トルクの発生回転は、殆どノーマルと
変わらない状態になったということみたいです。
1~3速まで7000rpm以上回ったのは、ギア比が低く、ピークを過ぎてトルクが落ちても回せたからでしょう。
でも4速ではやっぱり6500rpm以上でのトルクが不足し、伸びが悪い。
以上考慮すると、最高出力の7500rpmで80km/hを達成する仕様にしていくことが必要だということですが、
現在の仕様が丁度4速7500rpmで80km/hです。
なんとかエンジンにできるだけ負担を掛けず、実用的な80km/hを実現したいもんです。
2018/ 7/ 1
77. タペット
タコメーターを変えて回転数を確認しながら乗っていたのですが、トルクが落ち込む回転数がだんだん下がってきて、
低回転もスカスカになってきました。
なんか、エアが足りない感じで回るには回るのですが、力がない。
ガス不足を疑って、エアフィルタ、キャブの調整を行ったのですが、効果なし。
となると、あとは考えにくいのですがタペットクリアランスがなくなってちゃんと閉じていないこと。
バルブが閉まらないことで、トルクが下がるのかわかりませんが、まずは確認。
その結果エキゾースト側のクリアランスがキタコハイカムSPL規定値に対して半分以下の0.02㎜になっていました。
これが原因でトルクが下がるのかわかりませんが、規定値に調整。
そして乗ってみると、なんか元に戻りました。
ただクリアランスが減ってしまったということは、バルブシートが磨滅しているということで、修理は専門業者に
お願いすることになります。
寿命になったら、あっさりビッグバルブヘッドに交換ですね。
2018/ 7/ 1
76. 電気式タコメーター考
確実なチューニングを行うため、タコメーターを新調することにしました。
一番安心できるのは、機械式のメーターギアです。
しかし、一般的な1:4のメーターギアはキタコ製で1万円。それにメーターが5千円くらい。
一番良いとは解っているのですが、セッティングの時に必要なくらいのタコメーターとしては高い。
(ギア比とホイール径が判れば、速度は計算できますし)
でも、タコメーターがあれば、走行中の(特に最高速付近)の回転巣が認識できることで、クラッチの滑りも
確認できます。(買うための強引な理由)
で買いました。
KOSO スーパースリム タコメーター ブルー表示。
南米密林地帯で購入し、直ぐに取り付け。
でも、苦悩の1週間が始まったのはそこからです。
取り付け終了したのが休み前の夜で、ご近所のご迷惑を考えて機能確認をしませんでした。
そして翌日、軽くツーリングへ。
そうすると、アイドリングが3000rpm、エンジンを回すといきなり10000rpmを超えたり3000rpmになったり。
----またか。
そう、以前付けていたの中華製の’タコ!メーター’と同じ。
電気式タコメーターは、このような不具合が多く出ます。
前回は、針式の超安価メーターで、設定ボリュームもいい加減だったので、全くメーターを信用しせず、
ちゃんと動くような対応はしなかったのですが、今回は一応業界では知られたメーカー製。
ですので、ちゃんと原因を潰すことにしました。
表示の不具合の原因は、色々調べると概略下の2つのようです。(3つ目は、メーターの不良)
① 点火パルスの取り方
点火コイルへの電源供給コードに繋ぎこんで信号を取るか、ハイテンションコードに巻きつけて取るか。
② 電源のノイズ (ちなみに取り扱い説明書では、供給電源は8V~18Vとのこと。)
細かいところは、専門のHPで確認して頂ければよいのですが、
・バッテリー、レギュレートレクチファイヤーの劣化による過電流。
・もともとの発電時のノイズ(Benlyは、発電機構上電源にノイズが出やすいタイプです。)
ということで順番に確認することにしました。
まずは簡単な点火パルスの取り方で確認。
点火パルス信号用の配線の
・ハイテンションコードへの巻き数
・イグニッションコイル端子への繋ぎこみ
さらに他の配線からのノイズ防止として
・イグニッションコイルやその他の配線からの隔離
残念ながらいずれも確認して改善なし。
ま、想定内です。
やっぱ電源からのノイズのようです。
小さいオートバイは構造やバッテリーの小ささで起きやすいので。
そこで、丁稚 虎とその昔のめり込んだ電動ラジコン用の安定化電源を持ち出し、12Vでタコメーターを繋いで確認。
すると、案の定これまでとは嘘のように安定して表示。
やっぱね。
そこでまずバッテリーとレギュレートレクチファイヤーの劣化確認ですが、もしこの二つがダメな場合、交換費用は1万円----。
全開走行してもライトが切れたり他の不具合もないので、原因の一つである可能性は高いのですがそのままにすることに。
ちなみにバッテリーはエンジンをかけない状態で12.8V。
となると、ノイズへの対処になります。
低ドロップアウトタイプの3端子レギュレターでノイズ除去フィルターを自作するか、ノイズの少ない別系統の12Vを準備するか。
価格的には、自作で500円程度。 別系統の12V電源(簡単に言うと電池で電源供給)でも1000円。
今回は、手っ取り早く正しい数値を知りたかったため、お手軽な別系統の12V電源から供給することにしました。
(もしバッテリーとレギュレートレクチファイヤーがノイズの原因なら、ノイズ除去フィルターを装着しても効果が判らない可能性がある)
またこの電源があれば、今後ノイズ除去フィルターを自作した時も、その効果を確認できます。
そこで電源として自動車の電装部品DIYで有名なエーモ×の電源ボックスを使うことにしました。
これは、LED発光用の電源で、単三電池2本で12VをOUTPUTできます。(DCDCコンバーターの昇圧タイプですな)
リチウムのコイン電池のものがあればと思ったのですが、12Vが取り出せるボックスが見当たりませんでした。
早速カー用品店に行き、製品を確認しましたが、出力電流が120mAとのこと。
メーターの使用電流は表示がなくわかりませんが、まあ足りるだろうと購入しましたが、少し心配。
帰宅早々取り付けて試走すると、見事メーターは動きました。
またギア比、ホイール径で計算した40km/h、60km/hでの回転数をバラつくことなく安定して示しました。
そして取り付けた状態が下の写真です。
(メーターの下がバッテリーです。バッテリーにスイッチがついてますが防水ではありません)

このタコメーターで見ると、前回計算した通りの結果でした。
以前お話ししたように車の流れに乗るには60km/hまでの加速で車についていけることが最低限必要です。
更にそれから80km/hまではスーっと伸びることが必要だと感じでいます。
ということは、最高速は90km/h以上必要です。
しかし耐久性を考えると当然できるだけ低回転で80km/hを出したい。
(横型エンジンの耐久性を考えるとMAXでも8000rpm位でしょうか。)
とすると、ドライブスプロケットを14T→16Tにして7500rpmで80km/hにするのも手かもしれません。
でもトルク不足になって伸びない可能性も----?
やっぱりヘッド交換して高回転型にするしかないのでしょうか。
まだ悩んでます。
2018/ 6/17
75. ヘッド交換
オーナーのベンリィが7500rpmあたりからトルクが落ちることが判りました。
その確実な対策の一つは、ヘッドの交換(ビッグバルブ化)です。
Netで、ビッグバルブ化、ボアアップすると耐久性が落ちると言われています。
よく言われている原因は
①排気量増による過熱。
②振動増
これらによって焼き付いたり、クラッチなどが機械的に破損するみたいです。
でも破損を助長するのはエンジンの回しすぎです。
ヘッド、カム(あと良いマフラー)を変えるとパワーが出て、12,000rpm以上まで回るようです。
そこまで回るようになると頭打ちまで引っ張って最高速を出したいと思うのは当然です。
今まで憂さを晴らすように。
その結果、12,000rpmまでガンガン回すようになる。
そうなると、設計以上の高トルク、高回転で回すため、ケースや色んなものが変形し、無理が出ます。
また増えた熱量を処理できない場合潤滑性能が落ちます。
加えてまたノーマルクランク対して重量バランスがずれているピストンであれば、メーカーが考えている振動レベルを
超えるかもしれません。
そりゃ壊れます。
その対応として二次側クラッチやその他に手を加えていくと、オーナーにとっては獣道になります。
なのでいかに8,000rpmまでのトルクを上げ、最高速度にどれだけ早く到達するか、です。
トルク型のカムってあるわけないかぁ。
2018/ 5/13
74. またまた調整
88ccの慣らしも終わり、調子もまあまあだったのですが、高回転で失速して頭打ち。
あたりが取れて上までスムースに回るようになってきて、より判りやすくなってしまいました。
それと、アイドリングからアクセルを煽ると一回回転が落ち、それから回ります。
これが起きると、カーブの立ち上がりでアクセル開けたときにブレーキがかかったようになるので、
結構ヒヤッとします。
で、まずはキャブレターの掃除。
致命的な汚れはありませんでしたが、やはりスロージェットの穴が少し狭いようなーーーー。
アイドリングからの回転落ちの原因? 一番細い針金で穴を掃除し、フロート室も適当に掃除。
ついでにニードルのクリップ位置を上から一段下にしました。
また高速での頭打ち対策でメインジェットを#85→#90に交換。
汚れていたエアフィルターも交換。 デイトナ パワーアドバンスパワーフィルター φ35 ストレート です。
あと、エンジンを回しきるために、ドライブスプロケットを16Tから14Tにしました。
それと今回最大のレストア、シートの交換です
表皮の張替も検討したのですが、中のスポンジ(ウレタン?)の劣化もあり、交換。
アウトスタンディングのNo9です。
思いの外、しっかりしたシートで、長時間のツーリングも大丈夫そうです。
やっぱりシートが新しいと、見た目が締まります。
で、試乗ですが、時間がなく10㎞くらい。
試乗はいつも通り、加速のみで確認。
その結果は、3速で60km/hまでの加速はよくなりましたが、それ以降は加速が落ちます。
4速で70km/hまではスッっと出るようになりましたが、そのあと80km/hは我慢--思惑通り。
計算すると、3速60km/hで8000rpm、4速70km/hで7500rpm。
7500rpmあたりからトルクが落ち込むようです。
カムシャフトを入れているとはいえ、ヘッドがノーマルですので、こんなもんでしょうか。
2018/ 4/21
73. バルブクリアランス
乗っていて気づいたのですが、エンジンがあったまるとカチャカチャ-----。
直ぐにバルブクリアランスを確認。
IN側が0.08㎜、Ex側が0.09㎜
広すぎました。
いずれも0.04㎜が入って0.05㎜が入らないようにしました。
(狭すぎかもーーーー)
エンジンをかけるとなんか低速での爆発力が上がったような気がします。
気がするだけだと思います。
2017/ 7/ 30
72. ぼちぼち
3速で走ってみました。
結果、低速は少しトルクがないもののそれから加速し3速70㎞までは元気に回ります。
計算すると、9500~10000rpmくらい。
でも、フルスロットル状態では、グォーン --- ボー グォーン-- って安定しません。
はい、低速側で薄くて高速側で濃いみたいですね。 夏だし。
でMJを#90→85に戻してニードルのクリップ位置を一番上から真ん中に変更。
低速のトルクは少し上がり、グォーン --- ボー グォーン-- も解消。高速回転も安定しました。
しかし4速での伸びはないまま。
でも4速で60~70㎞/hの巡行はできるようになりました。
60km以上は、ブレーキの能力を考えるとちょっと必要ないかもしれません。
でもなんかの時に最高速として80km/hは出たほうが安全です。
4速で80㎞だと8500rpmです。
8500rpm前後のトルクを増すか、ドライブスプロケットを小さくして回し切るか。
でも、これをまた空気の密度が変わる初冬にやり直す訳ですな。 ( - -);
まあ、楽しいもんです。
2017/ 7/ 29
71. トルク不足発覚
これまで、75㏄+ノーマルヘッドで走ってましたが、やはり60km/hへの到達が遅く、大きな道では
ちょっと怖い思いもしてました。(安心してください。黄色ナンバーです。)
これから、少し遠くへのツーリングを考えるとこの60km/h到達をどれだけ早くするかが課題になります。
ということで、とうとゔアアップすることにしました。
すでに75㏄になっているので当然88㏄です。その後のヘッド交換も見越して。
また、巷で必要だとか不必要だとか言われているオイルポンプ容量アップ、強化クラッチについては、
やった結果NGという情報がないようなので、やることにしました。
そうなると、セットで一番リーズナブルなデイトナのエントリーキットです。
どうせなら、ヘッドもセットになっているものを買えばと思われるでしょうが、まずは60km/hまでの
到達時間を短くすることが第一目的で、おまけで80km/h出ればラッキーというステップです。
(デイトナの強化クラッチはギア比がノーマルより高速側になっていて最高速度の向上が見込めます。)
また、趣味の世界で一段一段ステップを確認しながら進めていくことが楽しみなわけです。
コストが少し高くなりますが、それも楽しみのうち。
全部一気にやると何が効いたかわからないのは楽しくないので。
組付け方法については、他の方々のほうが説明がうまいし、写真も載せておられますので
ここでは省きます。(ちなみにオイルのオリフィスはφ2.0mmにしています。)
で、乗ってみました。
クランクと二次側のギア比が変わったことで、3速までのギアの最高速が上がり、またボアアップの
効果なのか最高速に到達するまでの距離が改善しました。
2速で40km/h、3速で70km/h 60km/hまで100mです(これまでは150m以上) -----------。
ところが、4速での伸びがいまいち。
メインジェットは75㏄の時に#85だったのでまずは#90にしていますが、4速で70km/hからの伸びが
遅いということはキャブかスプロケットの減速比が合ってないのでしょう。
まずはキャブの調整を3速でやってから、ギア比をどうするか考えます。
また楽しい時間を過ごせそうです。
2017/ 7/22
70. 確認
いい塩梅の改造。
果たして、今の状態がいい塩梅か?
思いつくままに弄り倒したベンリィ。 本当に効果が出ているのか?
これまでの改造と、その効果を考えてみました。
キャブレター PC20(タケガワキット?)+Kitacoパワーフィルター(スポンジのやつ)
MJ:#85、PJ:#38、 ニードルクリップ位置:上から2段目(夏仕様)
判断 〇 比較出来てませんが、ノーマルよりはどう考えてもいいでしょう。
インマニ CF Posh ノーマルシリンダーヘッド用
判断 ? 変化なし
カムシャフト キタコ ハイカムシャフトSPL
判断 ◎ 最高回転数は向上
バルブスプリング キタコ ノーマルヘッド用 強化バルブスプリング(2重)
判断 〇 カムシャフトと同時交換のため、効果は?
でも高回転エンジンには、たぶん必要。
コイル C .F. Posh製 レーシングコイル+Kijimaハイテンションコード
判断 ? 比較できてません。
クラッチ キタコ 強化スプリング
判断 ? 滑ったことはありません。
マフラー CD90用 + φ8×4箇所穴あけ。
判断 ? 比較できてません。
スプロケット F:16T R:41T
判断 〇 低速から80km/hまでカバーできてます。
フロントサス オイルは規定(87.5cc ±2.5cc)上限の90cc。 #10
判断 〇 思ったよりまともになります。
リアサス YSS RD220-340Pに交換
判断 ◎ コスパいいと思います。お勧め。少し錆びやすいですが。
フロントブレーキアーム タケガワ製ロングアーム
判断 〇 最後の効きは凄い。でもストロークが増えるので、フワフワ感あり。
自作品目
エキサイター パチモン ホットイナ×× 容量増Version
判断 〇 低速でのトルクがほんの少し上がります。
ただこのエキサイターは、その機能上、弱ったバッテリーに使った時に
効果が確認しやすいようです。
バッテリーを管理されている方々は、あまり効果は見られないかも。
進角 純正28°+進角4.3° = 32.3°(固定) センサーずらしのみ。
判断 〇 最高回転11000rpmの構成要素の1つです。
ということで、巷で効果が期待できるとよく言われるのは言われるキャブレター、カムシャフト、マフラーですが、
それを実証する結果でした。(マフラーは最初からCD90用で、交換していないので、効果はわかりません。)
排気量が小さいこともあり、電気系のチューニングは、バッテリー、コイルなどが正常であれば、大きな効果は
出ないようです。
あと効果があったのは、フロントサスのオイル量変更、リアサス交換でした。
思いのほか安心して走れるようになりました。
色々弄りましたが、この結果今後効果が見込める改造は、ヘッド交換+ボアアップということです。
2017/ 7/ 2
69. 改造
これまでいろいろやってきて、さてこれからどうしたもんか、考えてます。
皆さんのブログ等を見ると、小型二種の枠を超えた改造や、フレーム、足回りまで変えた
原形を留めない改造も色々行われています。
どこまで改造するかって考えるのも楽しいもんですが、大事なのはそのオートバイの守備範囲で
どこまで安全を確保した改造ができるか。
ベンリィなら、90ccの設定もありますが、フレーム強度、ブレーキなどの状況を考えるとぎりぎり100km/hが
守備範囲だと思っています。
それ以上を望めば、フレーム、サス、エンジン、クラッチ---に手を入れることになります。
そこまで、手を入れると生半可では安全性も確保できないと個人的に思っています。
なので、オーナーは100km/hまでの速度域でいかに適に走れるかだと思っています。
とすると、エンジンは88ccくらいでしょうか。
それ以上の速度で走りたくなったら、NinjaかDucaで走ります。
オートバイは工業製品です。
基本設計が命です。金に糸目をつけずに改造するなら別ですが、設計以上のものにするなら
その費用は、とんでもなくなります。(しっかりしたショップほど改造費用が高いのはそのため。)
いい塩梅の改造レベル設定が大事ですね。
2017/ 6/ 27
68. メンテナンス。
まずは外観。
ホイールのスポーク、リムが錆び錆び。
錆び取り剤+真鍮ブラシで磨きまくり、なんとか錆び取り完了。
ただ、錆防止の茶色い被膜ができるため、スポークは見た目あんまり変わらず。
次は、エアクリーナー。
インシュレーター部分にクラックが入り、もうボロボロ。
迷わずDaytonaの紫のエアークリーナーを入手。
シルバーメッキのコーン型も考えましたが、少し派手なのでこちらに。
吸入抵抗は、どれもあまり変わらないので。
次は、エンジン。
①高回転は7000rpmで頭打ち。
②高回転まで引っ張り、その後スロットルを閉じて再度スロットルオープンするとぐずつく。
スタートでたまにストールしそうになる。
色々試してみましたが、
①については濃すぎたことが原因。MJを#85にしてOK。
#90~95程度もありでしょうが、気温、湿度も上がった状態のため、この仕様で固定。
②についてはPJ とMJの切り替わりが問題。
PJが頑張っているときに、MJから多めのガスが出て、ストールしそうになっているようです。
なのでニードルのクリップを上から3段目だったのを2段目に変更。
ニードルの位置を下げて、ガスの出を悪くする方向です。
調整の結果、高回転、出足ともに問題なくなり8?km/hとなりました。
そうなると、ブレーキのキャパ不足が露呈しました。 止まらない!!
ドラムグレーキのブレーキシューって、経年劣化と熱により硬化して効かなくなるんですよね。
そこで、フロントとリアのブレーキのシューを交換。
効かないとはいえ、2人乗りの90㏄と同じサイズのブレーキを持つベンリィです。
ちゃんと初期状態にすれば、効かないなんてことはないはずです。
更にフロンドレーキアームはTakegawa のアルミロングアームに交換していますので、このブレーキとしては
最も高いパフォーマンスを出すはずです。
で交換の結果、この手のオートバイレベルではありますがちゃんと効くようになりました。
このほか色々細かいUpdateも必要な状態ですが、またぼちぼちやっていきます。
2017/ 5/ 28
67.久しぶりに。
3年ぶりのベンリィです。
実は2015年に、丁稚 虎 が地方に修行に行ったときに、一緒にベンリィも
持って行ったのですが、免許取得と同時に車が思わぬ所から頂けたため、ほとんど
ベンリィに乗ることがなくなっていました。
虎に聞いたところ、「もう乗らないと思う」とのこと。
まあ、車があれば、無理してオートバイに乗る必要もありません。
そんで、先月 虎 の下宿に行って、ベンリィに乗って持って帰ってきました。
虎の下宿からちゃきちゃき堂まで120km。
途中、大都会東京の下道を原付一種でで抜けるという、大冒険のツーリングでした。
乗ってみるとエンジンの調子が??
高回転は7000rpmで頭打ち。
高回転まで引っ張り、その後スロットルを閉じて再度スロットルオープンするとぐずつきます。
なんとかちゃきちゃき堂にたどり着きましたが、いろいろメンテが必要みたいです。
2017/ 5/ 28
66.暇です。
どうも、ベイツ型のヘッドライトは気に入りませんでした。
また、ライトのハウジング内に入れられない配線を自作のアルミボックス内に収めてましたが、
ぐちゃぐちゃだし、メンテナンス時にボックスを外すのが大変。
ライトの明るさは問題なかったのですが、ベイツライトはやっぱ50'sのブリティッシュシングル用。
日本の70'sトラディショナルオートバイとは違う。
で、パーツ屋さんに行ってTakegawa のマルチリフレクターヘッドライトを購入。
でもそれで小遣いを使い果たし、ブラケットが買えません。
しょーがないので、配管用のクランプとアルミの板の切り出しで対応。
配管用のクランプは、20A用の物。(20Aって外径φ26位のパイプ用みたい。)
インナーチューブにクランプするために1mmのゴム板をインナーチューブの保護を兼ねて間に
巻いて固定。
クランプからヘッドライトまでのステーは手持ちの3mm厚のアルミ板で切った張ったで完了。
取り付けたところ、スピードメーターのケーブルが自作のステーに当たるため多少調整を行い
スピードメーターを真直ぐに。
で、結果です。
 →
→ 
ヘッドライトの高さも調整し、あの頃のイメージで。
やっぱこれですよね。
持ち主の 丁稚 虎 に 「凄いだろー!」 と見せたのですが、気付くまで3分。
ま、そんなもんですが。
あっ、メーターもポツポツ錆があったので、黒のテープでマスキングしてます。
このライト、明るくてGoodです。
2014/ 6/ 8
65.またまた。
またまた3000+α rpmあたりで一回回転上昇が止まり、それから上昇する症状が
出始めました。
何でかなー。
どうもスロージェットの目詰まり。
今度の休みにでも目詰まり解消メンテを実行します。
で、メンテで問題解消しました。
2014/ 4/ 13
64.いまさらながら
モンキー系のエンジンは、プライマリースターターではありません。
通常のオートバイはどのギアに入っていてもクラッチ切れば、キックスタート出来ますが
プライマリースターターではないモンキー系のエンジンは、エンジンスタートの時にはニュートラルにしなければ
キックしてもクランクシャフトが回りません。
判っていたこととは言え、最近 丁稚 鈴 が車の免許を取り始め、バイトに行くための
足としてBenlyを狙っているのですが、慣れない時期のエンスト多発はちときついかと。
とはいえ、プライマリースターターにするためには、ギアケース内の大改造になり、エンジン交換
レベルの改造、部品購入が必要。
何故HONDAは、このモンキー系エンジンをプライマリースターターにしなかったのか。
オーナーの最初のオートバイのMT50(1979式)ですら既にプライマリースターターでした。
変更のタイミングはいくらでもあったはず。
やっぱりこのエンジンはHONDAとしては路地を走り回る配達が正しい使い方で、大通りの
右折時の信号待ちでのエンストなんか想定していないのでしょうか。
そんなときは、ニュートラルで信号を待てと----?
理解不能ですね。
しょーがないので 丁稚 鈴 が乗るときには、またスパルタで教えますか。
2014/ 1/ 7
63.息継ぎ
スピードメーターギアを交換し、スピードメーター物色ついでにツーリングへ。
気持ちよく晩秋の秦野近辺を走っていたとき、なぜかスロットルを開けていくと3000+α rpm
あたりで一回回転上昇が止まり、それからまた上昇します。
しばらくぶりのツーリングなので、少し様子を見ましたが、改善傾向なし。
原因は、多分パイロットジェットの詰まり。
そうこうしていると、NAP'Sの近くにたどり着きました。
吸気をきっちり見直すため、まず1年使った中華製の500円パワーフィルターを交換。
Kitaco製のスポンジのフィルターを購入。
すると、上の伸びが良くなりましたが、当然息継ぎの改善はなし。
帰宅してスロージェットを外し、内径を覗くと明らかに内径が小さくなってます。
細い針金で内径を突き、汚れ(スラッジ?)を取り除いたところ、内径が大きくなりました。
走ってみると、下から上まスムースに吹け上がります。 OKです。
エンジンの息継ぎで悩んでいる方がいますが、それってスロージェットの内径の詰まり?
低回転はパイロットジェット、そして回転が上がると共にメインジェットが効き始めますが、
メインジェットはだいたい4000rpm以上で効き始めるイメージだと思います。
このため、パイロットジェットが詰まった(番手が小さすぎる、内径が小さすぎる)場合、
メインジェットが効き始める回転までをパイロットジェットがカバー出来なくなり、ガスが足りない
回転領域が出来ます。
ここで回転の上昇が鈍り、メインジェットからガスが出てくるまでの間、いわゆる「息継ぎ」
になるのかなと。(--と、思い込んでます)
いずれにしろ、不具合は改善され、気持ちよく走れるようになりました。
2013/11/15
62.スピードメーター
で、スピードメーターが死にました。
原因は、フロントホイールハブにあるスピードメーターギアの破損。
早速、部品発注。
ついでにトリップメーターが死んでいるスピードメーターも交換しようかな。
2013/10/ 5
61. フロントブレーキ
Benlyのフロントブレーキ。 効きません。
ブレーキシューは、某有名パーツメーカーのもので、斜めに溝もある強化タイプです。
しかし効かない。
それに、タッチがどーも変。
握り始めで一度効き、それを過ぎるとぐにょぐよで最後でまた効く。
早速ばらして状況確認です。
で、解ったこと。
Benlyのフロントもリアもシングルリーディングのドラムブレーキ。
で、シューの当たりを見ると、当然シューを広げるカム側はドラムと当たっています。
ところが、シューが広がるときの支点になる側の端っこも磨耗している-----。
良くシューを見ると、その部位のライニングが少し厚めでした。
多分、握りはじめでまずこの支点近くのライニングがドラムに当たり、その後更にシューが広がる
ことでこの部分は当たらなくなり、その後に正規の位置が当たっていたようです。
ドラムブレーキは、、シューがアウタードラムに全面当たりしたときに一番効くはず。
しかし、シングルリーディングは片方しか開かないため、当たり面を増やすには、結構難しい
ライニング厚さになります。
原因が判れば、支点側のライニングをヤスリで削り、当たりを無くします。
これでいいはず。
また、利かないフロントブレーキなので、何とか効くようにと、フロントブレーキアームをタケガワ製の
長いものに交換。
このアームは、長くなることで位置が下がるワイヤー止めアダプターがついていて、ワイヤーが
無理なく動きます。(ちと高いですが)

ブレーキを効くようにするためには、当然ディスクブレーキ化が一番良いのでしょうが、どう見ても
Benlyには合わないし、交換しても強力なブレーキに耐えるフォーク、フレームではありません。
なので、ドラムブレーキをできるだけ強化し、それに走りはそれに合わせる。
あと、この長いアームにすることで、効きは同じでもモーメントの関係でワイヤーの張力(負担)が
少なくなるので、ワイヤー切れも起き難くなるはずです。
取り付けた後に確認すると、最初の変な硬さはなくなり、効きも良くなりました。
ばっちりです。
ディスク化する前にお試しください。
2013/10/ 5
60. 自戒
本日、Benlyで買い物に。
すると、なーんか様子がおかしい。
エンジンを上まで回すとどこからともなくビビリ音が。
そして何となくフラフラ。
何かなーと思い、帰ってきてまずはホイールを締めているアクスルシャフト確認。
大丈夫です。
何かなーと思いながら、スイングアームのピボットシャフトを締めると、「ぎゃぁー」でした。
ナットが2回転するくらい緩んでました。
いえ多分、オーナーが整備したときに占め忘れたモノと思われます。
(そんなに緩むほど距離を乗っていないので)
いかんですね。
整備後は、もう一度閉め忘れの確認せねば。
教訓
オートバイを整備したら、締め忘れがないか、も一度確認。
2013/ 9/22
59. 確認!
オイルキャッチタンクの必要性の確認です。
オイルキャッチタンクは、このように取り付けています。


ね、タンクは前回書いたとおり、ペンキの小分け缶です。
で、問題の缶の中。
オイルが少しでも入っていれば、オイルキャッチタンクは必要と言うことになります。
で、中身。

あーあ、残念というか、やっぱりと言うべきか、オイルのオの字もありません。
薄っすらもオイル付着は無し。
やっぱり、オイルキャッチタンクが必要なのは、88cc以上でピストン往復によるギアボックス内の
体積変化の大きいエンジンなんでしょう。
(もしかすると、オイルキャッチタンクに取り付けたプラグの内径が小さすぎかも知れませんが。)
ま、そんなに重いものでもないので、すっきりしたステーを作り直して再度取付けました。
教訓
小さいエンジンにオイルキャッチタンクは???です。
2013/ 8/18
58. また暇でした。
また弄くりました。
HONDAの横型エンジンには、ギアボックスにリザーバーニップルがあります。
でもホースは、無しの開放。
さらにオイルフィラーキャップをリザーバーホース取り付け用に交換したものの、そのホースも解放。
なので、そのホースたちの行き先のオイルキャッチタンクを作りました。
とは言っても、本当に必要かどうかわからないオイルキャッチタンク。
わざわざ5k円以上出す気になれません。
そこで、自作。
タンクは、ドライバーなんかで蓋を開ける所謂ペンキ保存用の缶。
鉄製200ccで、無塗装です。
更にその缶に取り付けるニップルは、エアー工具配管用のもの。
合計1000円
ちゃちゃっと作って(とはいえ、リューターでえっちらおっちら)、ステーもアルミ板で製作。
缶の鉄板の肉厚が薄いので、ニップルがグラグラしますが、まあ問題なし。
設置場所は、あのアルミ板の自作サイドカバーの中。
高さ調整を行ったので、ステーに余分な穴が出来ました。

↑ 取り付けた状態。 缶のチラ見せがいい感じ??
さて、本当にオイルキャッチタンクが必要なのか??
しばらく走って、判断しようと思います。
あっ、インマニを低く短くしたので、スロットルワイヤー足りなくなって、ハンドルを切ると回転数が
上がります。
これもワイヤーを最短でセットして、インシュロックで固定して対策完了。
でも、インマニを低くした結果広がったタンク下の空間をどう埋めるか。
やっぱ、オイルクーラーしかないかな。
2013/ 7/15
57. エンジン最終確認
これまで、色々弄くってきたわけですが、どーも高回転の回りが不満。
13000rpmまでは回るのですが、なんかしゅいーんと回りません。
現在は10000rpm過ぎると、なんか咳きしてみているような状態です。
色々考えた末、マニホールドが長すぎるのではと思ったわけです。
CD50系は、とっても長いマニホールドで、直立していて「立派!」です。
長いマニホールドは、低回転でも吸入の流速が増し、充填が出来るのでトルクは上がります。
しかし高回転の時には充填が追いつかず吸気不足になりがち。
そこで CF PoshのPC20+ノーマルヘッド用のインマニを取り付けました。
ヘッド側のポート系はφ14とのことですが、なぜか拡大したヘッド側の径φ18とほぼ同じ。
?????ですが、まあいいかと。

↑ なーんかキラキラしてるインマニです。捻りもそこそこ。
早速試乗。
アイドリングは安定しています。
ところが低回転では、体感出来るくらいにトルクが落ちました。
なので、出だしで回さないといけません。
これ結構、大変です。
大排気量に慣れてしまい、普段出だしの回転数を殆ど気にしないで乗っているので、
結構気を使います。
しかし4000から12000rpmOverまで、しゅいーん----です。
低速から高速まで滑らかに繋がるようになりました。
でも、スロットルフルオープンから全閉でアイドリングに落とすと、止まりそうになります。
まあ、アイドリングを上げればいいんですけど。
やっぱりこの排気量でも、マニホールドの長さって効くんですね。
ただ、ツーリングには、ロングマニホールドの方が楽かもしれません。
2013/ 7/ 7
56. 「あーあ。」の後始末。
割れてしまったバックミラー。
純正風のメッキのキンキラキンのやつにしました。
あんまり変わり映えしませんでした。
2013/06/30
55. 「あーあ。」
Benlyの塗装したフロントフェンダーに錆が少し浮いてきたので再塗装をすることにしました。
フロントを持ち上げるため、新作した改造ジャッキでエンジン下から持ち上げ、フロントホイールを外し、
フェンダーを外しているとき、Benlyが、ゆっくりと傾き、横になられました。
横になっただけなら良かったのですが、その時バックミラーが木っ端微塵に破壊されました。
「あーあ」
またバックミラーを購入せねば。
今度は純正のメッキのキンキラキンのやつにしましょうか。
2013/06/24
54. 4Miniの楽しみ。
初夏です。
気温も湿度も上がってきました。
Benlyもそれに合わせる様に、調子がいまいちになってきました。
エンジンが小さい分、これらの自然影響が結構効くようです。
MJやジェットニードルのクリップ位置を見直しました。
こんなに、気温と湿度の影響を受けるとは思っていませんでしたが、小さなエンジンは、
こんなもんなのでしょう。
本当に一年中遊べます。
あっ,フロントブレーキの効きを改善するため、ブレーキレバーをロングタイプに変更しました
(クラッチレバーもーーー)
フロントブレーキに力が掛かりやすくなりました。
で最近思うのですが、オートバイの改造って何処にラインを引くかですね。
どれだけ速くなっても、「バォー」っていう吸排気音にはしたくない。
でも吸気の「シュコー」という音と、排気の「ボッボッ」音は何か好きですが。
オーナーの目標は、どれだけうるさくしないでパワーを上げていくか。
ほんと難しいですね。
2013/06/02
53. やっぱりね。
針のふらつきが一時的に納まった「タコ! メーター」でしたが、すぐ再発。
針がふらついたり、0rpmを示したり。
どうも内部の接触不良みたいなので諦めて、「タコ! メーター」を外し、分解。
中の基盤を見ると
「やっぱりね。」
抵抗のハンダが外れてました。
それも2箇所。
その外は、問題が無かったので、その2箇所を強力にハンダ付けして完了。
試乗すると、購入時と同じ動き。
(と言っても「タコ! メーター」、購入時から4000rpmで一瞬引っかかります)
これでしばらく動いてくれれば、まずはOKです。
2013/06/01
52. あらーっ #2。
本日、近くのホームセンターの安売りでジグソーが2500円とのこと。
ジグソーは、木材はもとより薄い鉄やアルミの板くらいなら切断してくれます。
今後のメンテナンスに必要と判断(ほんとかっ?)し、朝からホームセンターへ。
と、そのときです。
駐車場に止めた横にカブの90cc(キャブ)が置いてあり、ふとそのマフラーを見ると、なんと
Benlyのマフラーと穴径が同じ。
あらーっ。
でもエンジン側のエキパイにBenlyにはあるエキゾーストカバーがない。
よく見ると、デザイン変更で一体化したように見えるカバーが付いてました。
でも穴径が同じ------。
慌ててジグソーを購入し帰宅して調べてみると、どうも現在のマフラーは、CD90用ということ
が判明しました。
ということは、φ8の穴をあけまくってしまったBenlyのマフラーは、完全にスカスカだっちゅう
ことです。
まあいいか。
124ccまで使えるかもしれないし。(??????)
それから暇に任せて、針がフラフラする「タコ! メーター」を気合を入れて修理。
Benlyは、各種ワーニングなどをLED化したりして、配線が増加してます。
この増加した配線は、全てギボシで接続。
そこで元配線までの接続部(ギボシ)を全て確認すると、数箇所嵌め込みが緩いところが
ありました。
メスの方をペンチで絞り、はめ込み直したところ、針がフラフラしたり、0指示で止まったり
しなくなりました。
(でも中華製なので、いつか壊れることは覚悟してます。)
カムを変えて 10000rpm以上回るようになった以上、回し過ぎ防止としてはタコメーターが
必要です。
それが10%レベルで誤差のある 「タコ! メーター」 でも。
(精度が良いタコメーター欲しいな---)
2013/05/25
51. カブエンジンの最高回転。
カブ系のエンジンの最高回転数は、大体ノーマルでもボアアップしてもクラッチを二次側に交換
しないと10000rpmが限度だと言われています。
メーカーによっては、一次側強化クラッチで12000rpm可能と言いますが、なんか疑わしい-。
じゃなんで、一次側だとリミットが10000rpmで、二次側に交換すると15000rpm可能なのか。
答えは、クラッチ自体の回転数?。
一次側にあるとエンジンの回転数=クラッチです。
でも2次側にあれば回転数はクランクシャフトから減速された分下がります。
クラッチはクラッチアウター+ドライブプレート+フリクションプレート+スプリングなどで構成されていて、
回転時のバランスはとっても取り辛い構造です。
それをまんま10000rpm以上で回すのは他のオートバイでもやってません。
ちょっとしたバランスのずれで振動が出ることからすれば、クラッチのようなバランスの悪い物は
出来るだけゆっくり回したい。
でもそもそもカブ系のエンジンは、低速で回す乗り方をするオートバイ。
よって、そんなクラッチでも問題ないというのがメーカーの設計思想です。
なので、カムシャフトやキャブレターを交換したり、ポートを削り、マフラーに穴をあけまくり、エンジンが
10000rpm以上回るようになっちゃった方は、早々に二次側クラッチに交換するか、オーナーの
ように折角入れたカムシャフトでも10000rpm以上回さずに我慢するかを選択されたほうが
良いかと。
ということで、二次側クラッチの導入判断は、パワー増加以上に最高回転上昇を考える必要が
あると言うことを理解したオーナーでした。
2013/05/22




