50. �ďo���B
�@�@�{���A��ײ���۹�Ă�14T��16�s�Ɍ������A���߂Ď��悵�܂����B
�@
���]���獂��]�܂ł̌q������ǂ��A�S���ł̽�߰�ނ̐L�т��ǂ��Ȃ�7�~km/h�܂�
�����Ƃ����ԂŁA�Ԃ̗���ɏ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B
�@
�b���́A���̎d�l�ŋl�߂̍�Ƃ��s���Ă����܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/19
�@
49. ��{�ɖ߂�B
�@�@�{���N�x��������āA�Ƌ��̍X�V�ɍs���܂����B
�߂��̌x�@���ŏo����Ƃ̂��Ƃł������A������t�ł͂Ȃ��A�ꃕ����Ɉ��S�u�K��
�Ă�����炤�Ƃ̂��ƁB
���ׂ�ƁA���x���̈��S�u�K�̓��́A�d���ŏo���B
���̓��ȊO�ɂ��邽�߂ɂ́A�ēx����ς��Đ\�����݂����蒼���ł��B
�@
����Ȃɉɂł͂Ȃ��̂ŁA���̖Ƌ������ɍs���A�����X�V�Ŋ����B
�@
���̖Ƌ������ɂ́ABenly50S�Ō��������̂ł����|�|�|�|�B
�@
�Ƌ������ւ́A���\�傫�ȓ���ʂ��Ă����̂ł����A��͂�Benly50S����ܰ�ł́A�o������
�Ԃɒǂ�����A���\��Ȃ����Ԃ̏ł����B
���̑O�A�����ɍs�����Ƃ��́A�c�ɓ��ŁA�Ȃ�Ƃ��^�]�ł��܂������A�v���Ԃ�̓s���
�傫�ȓ��ł́A���̏o�����̽�߰�ނ́A�܂��߂Ɋ댯�B
�X�Ɂ@�Ձ@�����ꂩ��X���𑖂�̂ɂ͕s�����ł��B
�@
�A��č�N�w��������Ԃɖ߂����Ƃ����ӁB
�@
���̂�1���Ԃōw�������Ƃ��̏�Ԃɖ߂��AMJ,PJ,����ح������Ď����B
�@
����ς�y�`���B
�o���������ʂ̎Ԃɂ͕����Ȃ����炢�ɂȂ�܂����B
�@
�ł��A�U���A�r�E�z�C���͑傫���Ȃ�A���S�n�͈����B
�@
�ł��܂��A����Ȃ���ł���B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/17
�@
4�W. �����玟�ɁB
�@�@�{�����@7�����点������Benly50S�̏C���B
�A
��װ�O������ފO���ā|�|�|�|�|���āA��ފO������A���ΰق̊O���ɵ�ق�����
���܂��Ă܂����B
�@
��ނ�����������̱��ݸނ���ނ����ܯ���̊Ԃɱ��ݸނ̒[�q�����荞�܂���
���߁A��ق���������Ȃ��Ȃ����݂����ł��B
�ł��A�����ɵ�ق����邿�イ���Ƃ́A����ς荬���C�ɵ�ق������Ƃ������ƁB
�@
���ĵ�ُオ�肩��ُオ�肩�H�H�H�H�H
�@
���������킭�킭���Ȃ���i�����ϑԂ̈�ł��jͯ�����ĊO����-------�B
���\��ƂɂȂ�܂����B
�@
����ް�܂ŊO�����Ƃ���ŁA�߽�݂Ƽ���ް���ǂ��m�F�B
�߽�݂Ɉُ�͖����A�߽���ݸނ̏�ԁA�������n�j�B
�܂�����ް���ǂɂ��ςȏ��͂���܂���B
��ُオ��͖����悤�ł��B
�@
����ς������Ѽ�ق���̵�ى����肩�H�H
�@
ͯ�ނ���ׂ��A�����Ѽ�ق��O���Ɓ@�|�|�|�@�����ɍd�����Ă܂����B
�����ň��������ĐV�i�ƌ������Aͯ�ނ�g�ݏグ�܂����B
�܂��A����ر�ݽ���A�C�����L�߂ɂ��܂����B
�@
���v��3���ԁB(���Ɗ|���肷���j
�@
�ݼ�݂��n������Ɖ����w�nj����Ȃ��Ȃ�A��ق̏Ă���L���������Ȃ�܂����B
�����o�Ă���̂́A��݂��Z�����߂݂����ł��B�i�ڂ������ށj
����ح������Ă݂�ƁA�������ߍ��݂����i�Z���Ȃ�j
��ح�������ƁA���������Ȃ�A��̏L�������ʂ̔r�C����ۂ��Ȃ�܂����B
�@
Mission�@Comp!
�@
���ƁA����܂ŕt���Ă�����ނ̔Ԏ��������܂����i������NGK�ł��j
13000rpm���ƌ����Ă��A�w�ǂ�5000rpm�ȉ��B
�Ԏ���グ��K�v�͂Ȃ����ƁB
�@
�܂��A�ق�̏�����݂��Z����Ԃ������̂ŁAMJ����90����85�Ɍ����B
����ɍ��킹�ļު��ư��ق̸د�߂��ォ��2�i�ڂ����i���Ƃ��܂����B
�iҲݼު�Ă͔��߂ɂ��āA�ު��ư��قŏ����Z���ڂɁB�j
�@
���ʁA�������܂Ō��\���������ł��B
�����A�ᑬ�ŏ����Z�������Ȃ̂ŁA�د�߂�߂���MJ�����������܂����ˁB
�@
�ł�----------
�@
���q�̗ǂ�Benly50S�ŋߏ������ׂ��Ă�����A�Ȃ�Ɓu���IҰ�-�v�̐j�����ׁB
�ڐG�s�ǂ��ƁAҰ������o�Ă���z�������傱���Ƃ�蒼���܂������A���炸�B
���ؐ��́u���IҰ���v�{�̂�������Ă��܂����H
�@
�����玟�Ɂ|�|�|�|�|�B
�@
�ł��߰��Ұ���������낢�̂ŁA�ްŽ�Ŏv�����Ľ�߰�ށ{��Ұ�����������悤���ȁB
�@
�ł�Duca�̸ׯ���������I�I�B
�@
���Ə����C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł����A��������iPC20�j�̲��Ƃ̱�����������삵�āA
���t���Ă��܂����A���̊p�x�������`�B
�@�@�@�@�@�@�@�@
���\�A�X���Ă܂��B
����ς�A�����Ƃ�����ΰ��ނŒ����ɂ����ق����۰ĂƂ̈ʒu�W�܂߂Ă����̂�
���R�ł����A���ꂪ�ǂ̂��炢�e������̂��A�܂��s�̂���ΰ��ނ͒Z�����̂�����ŁA
�ᑬ���ǂ�����̂���---�B
�@
�Y��ł܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/12
�@
4�V. �����F�X�ρB
�@�@�ݼ�݂́A�܂��܂���ԂɂȂ�܂����B
�@
�Ƃ��낪�A�ǂ���2����9000rpm�ȏオ�����ςł��B
�ݼ�݉�]�Ƌ��ɽ�߰�ނ��オ���Ă����Ȃ��B
�@
3���ł́A10000rpm�����Ȃ��̂ŁA����Ȃ��̂ł����A2�����Ƃ���ȏǏo�܂��B
�@
�ׯ��������Ă܂��B
�܂��A���Ƃ��Ə����ׯ��́A10000rpm������t�̂Ƃ����13000rpm�܂ʼnĂ����
�ł����炵�傤���Ȃ������B
�@
��ŁA�ׯ��̋����ł��B
�Ƃ͂������̂́A���F�����B
����������т��M���Ă���Ƃ͌����A�ǂ�������Ă�6PS�������Ƃ��B
�@
�Ȃ̂ŁA�����ׯ��{��������ݸނőΉ����܂��B
�@
����߂�
�@�@�����F�ظ����ި��
�@�@����̋�������ݸ�
�@�@���̨�����ذ݁i�܊p�ׯ���ް�O���̂Ō����j
�@�@�ׯ�������ް���āiHex�j
�@�@�ׯ���ް����
�@�@��ݸ��ް����
�@�@�����ѵ�ټ��
�@�@�ׯ�ۯ�ůā�ܯ���
�@�@�ݼ�ݵ�ف@�@
�ȏ���w�����A�J�ɂ�������炸��������ׯ������B
�@
���S�Ɏʐ^�Y��Ă܂����A��邱�Ƃ͑��̕��X��ΰ��߰�ނ��Q�l�ɁB
�@
�����A�����ȎG���ɏ����Ă��邱�ƁA�Ȃ��������Ƃ�����A���\��J���܂����B
�@
�܂����́A�ׯ���ް���O���Ƃ��ɁA�ï�߂��O���Ȃ��Ƃ����Ȃ����ƁB
�܂��ʹݼ�݉��Ɏԗp���������̎��̼ެ���Ŏԑ̂��Œ�B
���̂��ƽï���ް���O���̂ł����A���ꂪ���\���ɗ��܂��B
�@
���̖��́A��������ݸނ�g�ݍ��ׯ�����ײ�ذ��ײ�ޱ���ꏏ�ɸ�ݸ���Ă�
�g�ݕt����Ƃ��B
�@
���̂Ƃ��A��ײ�ذ��ײ�ޱ�̊O���Ƹׯ��ظ����ި���̓��������ݍ��킹�A
�X����ײ����ڰĂ���ײ�ذ��ײ�ޱ�̌��̾��������킹�Ȃ��ƁA��ݸ���Ă�
�g�ݍ��߂܂���B
�@
�G�������Ă����܂肱�̂��Ƃɂ��Ă͋L�ڂ������A�F����ǂ����Ă���̂��ȁ[�Ǝv��
�Ȃ���A��ײ�ذ��ײ�ޱ���������ϰ�źº@���Ȃ���A�������o���܂����B
�i�\���̸�ݸ���Ăʼn��g�ݕt�����Ă�����t���Ă���̂ł��傤���H�j
�@
�������炨������Ȃ�Ƃ��g�ݕt�������B
�@
��ق����āA�ׯ��̏�Ԃ��m�F���āA�ׯ��������B
�@
��Ŵݼ�ݎn���I
�@
������ł��B
�@
�ł��A�|�|�|�|�|�|�|�@����[���B�@�|�|�|�|�|�|�|
�@
������װ���甖�[���������������|�|�|�|�B
��ނ�����ƁA�^�����B
�@
�ݼ�݂������ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B
�@
��ى�����?�@��ُオ��H
�@
��ُオ��́A�߽���ݸޕs�ǂ̂͂��B
�����߽���ݸޕs�ǂȂ�A�ݼ�݂̈ى�����������Ƒ傫���͂��ł��B
�@
���Ƃ���ƁA��ى�����H
�m���ɍŋߍ���]���Ă���̂ŁA�����Ѽ�قɂ͉��x�܂߁A���\�ȕ��S��
�|�����Ă��邩������܂���B
�@
�����܂�������ēx�ݼ�����ł��B
�@
�i���\�y�����@�|�|�|�|�|�@���ꂪ�S�l�������n���H����H�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/05/11
46. �������I
�@�@���āA�۰�ު�Ă�#35����ɓ���A�ŏI�����ł��B
�@
Ҳݼު�Ă�#90�ŕς��Ȃ��ŁA�۰�ު�Ă̂�#38��#35�ցB
�@
���ʂ́A���]�ł��ٸ���オ��܂����B
�������A�܂�����Z�����߁A4000rpm�t�߂ł�·�����܂����B
�@
�����ŁA�ު��ư��ق̸د�߈ʒu���ォ��4�i�ځ�2�i�ڂցB
�i��������Ȃ�����j
�@
����ƁA·�����P�������ݸނ���13000rpm�܂ŽѰ��ɉ��܂��B
�@
�܂��A�������ɽۯ�ق�߂����Ƃ��ɋN���Ă�����u�ݼ�݉�]�����オ���ĉ�������
�ς�·�̌��ۂ͖����Ȃ�܂����B
���̕ς�·�́A�����䂪�K���ł͖�����Ԃʼn������Ă����Ƃ��ɽۯ�ق�߂����Ƃ�
�����䂪�K���ɂȂ�A�����͂��オ���āA�u������v�Ɖ�]�����オ��̂��ȂƎv���Ă܂��B
�i�Z���A�����͂��̎��̏�ԂŐF�X���Ǝv���܂����j
�@�@���ꂪ�o��ƁA�����������ł����ɂ����Ȃ�܂��B
�@
�ł��A���₷���Ȃ����Ƃ͂����A����ς菃���B
�@
6�~km/h�܂ł͂����ɏo�܂����A����ȏ�͂Ђ�����҂̂݁B
�ł��A�O���U��������A�ݼ�݂�Ѱ��ɂȂ������Ƃ��l����ƁA�����ł��B
�@
�d�グ�ɁA��ނ��������ďI���B
�@
�@
�����A
���ݼ�Ű�̽���ݸނ𒍕�����̂�Y��Ă܂������A�{���������܂����B
���T�̓y�j���ɂ́A���K�̽���ݸނ����t���܂��B
�iΰѾ����̽���ݸނł����̂Ƃ���A���͂���܂��B�j
�@
����ƁA��װ���ڰтɎ��t���Ă�����������ڰĂ̓����������{�B
�S�Ō���3mm�ʁB
���\�ʐς��傫�������̂ŁA�O����������������ȂƎv���Ă܂����B
�����ި�����ް��ح����Ōy�ʉ��B
�܂��A��װ�Ɏc���Ă�����������į�߰�������܂����B
�y�ʉ��́A�C�t����Ȃ��悤�ɂ��̂���ہB
�i�ł�����Ȓn���ȍ�Ƃ́A��J�̊��ɖڗ����Ȃ���ł���ˁB�j
�@
�����ɰ�ق����ׂ�ƁA
�@�Eر̪��ް���O���B
�@�Eð����ߌ����i���^���j�B
�@�E��ݶ����^���B
�@�E����̪��ް����߱��߁B
�@�E���ذŰ�ޯ�����O��
�@
�Ȃ̂ŁA�T�����ȏ�y���Ȃ��Ă���͂��|�|�|�|�|�|�ł��B
�@
����ƁA����A��ݸޱ�т���ް�ɓh�����Ă݂܂����B
�i����܂���ʂȂ��݂����ł��B�j
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/13
45. ����[��
�@�@�����ɕύX��A�ݼ�݉����Â��ɂȂ������߂��A�ݼ�݂́u�����v�������ɕt��
�悤�ɂȂ�܂����B
���̉��͂ǂ������ް�t�߂���o�Ă��܂��B
�@
�u������������A�߽���ݸނ����ꂽ�H�@�߽����ݸد�߂��O�ꂽ�H�v
���������Ƃ��ɉ����s����������̂��H�H
���M���Ȃ�������Ű�́A�����ݼ�ݍ��㕪���B(�ȒP�ł����B�j
�@
ͯ�ނ��O���A����ް�������āA�߽�݂̏�Ԃ����܂������A���Ȃ��B
(���\�A�ǂ��d�����Ă��鵰Ű�ł����B�j
�@
�ق�ǂ�����u�����v�����o�Ă���̂�?
�Ȃ�čl����܂��Ȃ������́A�u�����݁H�H�H�v
�@
���R���Ȃɂ��u�����v�Ƃ������ł��邱�ƁB
�@
�����Ŋm�F����̂Ͷ������ݼ�Ű�B
����ݸނ����āA�����t���͂����������̂ł͂ƁB
�@
�����A�������ݼ�Ű�������Ă������ݸނ�Ƃ߂����Ă����O���B
�i����܂��H�B��ݸ������̂���������ނƂ悭�ԈႦ��ƌ����Ă���߂Ɏh����
���ó��B�j
�@
����Ɓ|�|�|�|�|�|�Ȃ�ƒ��ɂ���͂��̽���ݸނ������Ă܂���B
�F�X�����ƁA���������Ă�ٌ������ɊԈႦ�ĊO���Ă��܂��A�g�ݕt�����ɽ���ݸނ�
���ꂸ�ɁA���Ă����Œ��߂Ă����܂����Ă��Ƃ��ǂ����邻���ł��B
�@
�@�@�@OBK��HP������ƁA����ݸނ͕K�v�����ƌ������X�����܂���-------�B
�@�@�@�K�v�Ȃ��͂��Ȃ��ł���B
�@
�@�@�@�������ݼ�Ű�ł���B
�@
�@�@�@�����݂́A��]���オ��ƒ��͂��オ��̂ŁA�����ݸނ���]����
�@�@�@����ĕς��܂��B
�@�@�@�Ȃ̂ŁA��������èݸނ��ł��܂���B
�@
�����A�߂��̼���߂ɂ����ɓd�b���āA�����̽���ݸނ̍ɂ��m�F���܂������A��������
�����ĂȂ��ł���ˁB
�Ȃ̂ŁA����ݸނ̓��錊�̌a�ׂāAΰѾ����ŏo���邾����Ȓ萔�̍�������
����ݸނ��w���B
(�K���Ȃ̂ŁA�����i�͕ʓr�������܂��j
�@
���̓K���Ƚ���ݸނł����t����ƁA�u�����v�����R�̂悤�ɏ����A���̶�ތn�ݼ��
�̉��ɂȂ�܂����B
����ς�A���ݸނ�����ɂȂ������ʂł����ˁB
�@
-----�@�܂��A���Â̵����ɂ́A�ǂ����邱�Ƃł����B------
�@
���イ���A����܂Ł@���IҰ���̐��l�Ƃ͂���13000rpm�Ă���Ű�B
�@
�u�����Ԃˁ[�v�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/07
�@
44. ������
�@�@�����ɁA�C�̖����ŕύX������A�@�@�@�@�@�@�@
MJ�F��90�ASJ:��38�A�@ư��ٸد�߈ʒu�F�ォ��R�i��
�ő����Ă��܂������A��肪���o���܂����B
�@
4000�������ȏ�ł́A�S�����Ȃ��̂ł����A�����ݸނŎb���ق��Ă����ƁA�ݼ�݂��u��݁v
�Ǝ~�܂�܂��B
�@
��ނ�����ƁA�^�������B
�@
�����ŁA�ު��ư��ق̸د�߈ʒu���ŏ�i(��݂����Ȃ��Ȃ�j�ɕύX�B
�����ݸނ͏������P����A�ق��Ă����Ă�ݼ�݂͎~�܂�Ȃ��Ȃ�܂������A����]
(8000rpm�ȏ�j�Ŵݼ�݂����܂���B
�@
�ǂ����A�۰�ު�Ă�#38�ł́A�����ɂ͑傫������悤�ł��B
�۰�ު�Ă̎���͈́i4000�������ȉ��j���܂��͒��߁A����]�ł̒��q���o�����Ƃ�
���܂����B
�ƌ����Ă��A���Ǽު��ư��ق̸د�߈ʒu���ォ��4�i�ڂɂ��������B
����ŁA13000�������܂ł��ꂢ�ɉ��܂��B
�@
���́A�۰�ު�Ă��������̂Ɍ������āA�ēx�ײ�ł��ˁB
�@
�ł��@------�@�۰�ު�Ă��āA������ł���ˁB�@---------
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/04/07
43. �ύڔ\��
�@�@�{���A���t�@��@�̂��߂ɁA���[�ޯ����Benly�Ŕ��o���ɍs���܂����B
�@350�@�~�@400�@�~�@250(mm�j�̈����o�����ޯ��2�B
�@
�@�w�����A�����ċA��邩������ƐS�z�ł������A������Benly�A���Ȃ��B
�@
�@2��ر��[���肬��ɾ�Ă��A��тʼn������܂����B
�@�P�O�����ȏ㼰ď�ɂ��܂������A�����߰��́A�S���]�T�B
�@
�@����Ȃ�A����ߓ�����[���ς߂܂��ˁB
�@
�@�g�����Ȃ�����A�@���t�@�Ձ@�Ɂ@Benly50S��ā@�ǂ����ɉ����s�������ȁB
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/31
42. �����@���̌�
�@�@��ٌ��������Ă��Ȃ����ƂɋC���t���܂����B
�@����́@�Ȃ�ƍ�N��6�����Ɍ������Ă��疳�����ŗ��Ă���͂��B
�@�ظ���۽�ጸ���l���ɓ���āA�_�炩����ق�T���Ă݂܂����B
�@
�@�܂��͏���
�@�@�@�E���g�� G4 �@0W-30�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�́u�����v
�@
�@�ق�ŎЊO
�@�@�@Silkolene�@�@�@ PRO R RacingOil�@�@�OW20 ���i�́u�������v
�@
�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@XT-3825�@�@�@0W20�@�@�@�@�@�@���i�́u�Ё[���v
�@
�@�ǂ����ЊO�̵��Ұ������� �OW�́A�p�r��ڰ��p�̂��̂������A
�@���̌��ʁA���Ƃ��ƍ����̂�HONDA�ȊO�͂SL�ʂ����Ȃ��A���i�́|�|�|�|�|�B
�@
�@�������ƕ����]�����A�܂��͍���Motul�@5100�@15W-50���_�炩�����̂Ŋm�F���邱��
�ɂ��܂����B
�@�����Ĉ�Ԉ����@ Castrol��4T 10W-30�@�PL���w���B
�@
�@Castrol�́A��Ű���w������Ɉ��|�I�Ȏx�����Ă�����قł��B
�@RS�Ȃ�ē����@�PL�@2500�~���Ă܂����B
�@���ł́A�܂���{�ɂȂ鵲�Ұ���ł��ˁB
�@
�@����ւ��Ă݂�ƁA����܂ł�Motul�@5100�@15W50���n�����͌y�����܂����A
�g�܂�Έꏏ�B
�@
�@��]���V�������A���炩�ł����A�ō���]���́A�ς�炸�B
�@
�@���ꂩ�絲ق�ς��Ă������Ƃ��ɁA�ǂ��܂ŕω����������邩�B
�@�t�Ɋ�����ꂽ�炢����ق����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/31
4�P. ���́@����
�@�@����܂ŁA�Ղ̵����ŐF�X����Ĉ�i�������Ƃ��A�ӂ�
�u�������Ăǂ�Ȃȁv
�v�����������~�܂�܂���B
�@
��ŁA�����̕��i�����ď���������B
�@
�@
�܂��́A�ȉ��̕��i�����O���܂��B�B
�@�@�@��װ�B
�@�A�@��������B
�@�B�@�����߁A���B
�@�C�@����ްͯ��ůāA����ްͯ��ް�B
�@�D�@��ݸ�����ް�B
�@�E�@����ްͯ����ް
�@�F�@����ްͯ�����āi����ް�Ƃ̒������āj
�@
���āA�����܂ł炵����A
�@�G�@�ѽ��۹�����Ď��O���B
�@�@�@�@���Ă��ɂ߂�Ƃ��́A�ײβ�ق���ł������艟�����āi����Ɗ�Ȃ��j�B
�@�@�@�@���Ă��O�ꂽ��A�����݂ƽ��۹�Ă����ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA
�@�@�@�@���۹�Ă̌����g���Đj���Ōy�������Ă����܂��B
�@�@�@�@�i������ݸލ��킹�鎞�Ɋy�ł��j
�@�H�@ͯ�ޔ������B
�@�@�@�@����݂Ōy���@���Ȃ��甲���܂��B
�@�I�@����ް���Ď��O���B
�@�@�@�@����ް��ޱ����ɒ������Ă������Ă��O���܂��B
�@�J�@����ް�O���B
�@�@�@�@����݂Œ@���Ȃ���B
�@
�@����������ׂł��B
�@
�����ɷޱ����Ɉٕ�������Ȃ��悤�ɳ���ōǂ��܂��B�i��ۯ�ނ���яo���Ă����ԁj
���̏�ԂŁA�߽����ݸد�߂������ŊO���A�߽����݂����߽�݂��O���܂��B
�@
�߽�݂́A�܂����ʂ̏�ԁB�i�܂��g�������j
�@
�@
�V�����߽�݂��߽���ݸނ�ݼ�ݵ�ق܂݂�ɂ��Ȃ���Ƃ߂܂��B
�����������Ă����������i�́Aį�߁A����ށA�������ނɕ�����Ă��炸�A�P�̔��ɁB
�ݸނ́A�t����ꏊ�ƌ����i�\���H�j������̂ł����A����ɂ������߁A����ƭ��
�ȂǂŊm�F���Ă��������B�i�ԈႤ����ׂ����g�ݕt���ő�ςł��j
�@
�߽���ݸނ��t������A��ۯ�ނ֑����B
��ɕБ����߽�ݸد�߂�t���āA�߽�݂ƺ�ۯ�ނ��߽����݂ŘA��������ɁA���ꂽ����
�߽�ݸد�߂����t������߽�ݎ��t�������B�i��ݸ����̌��͍ǂ����܂܂ō�Ɓj
�@
���ӂ́A�߽���ݸނ̐�Ԃ�į�߁A����ށA�������ޕv�X120�������炷���ƁB
����A�����ꏊ�ɂ���ƁA���k���オ��܂���B
�܂��߽����ݸد�߂̐�Ԃ��A�߽�݂ɂ����߽����ݸد�߂����邽�߂̐茇��
�Ɣ��Α��ɂ��邱�Ƃł��B
�����ЂƂA�߽�݂̌����ɂ����ӁB�h�m�̒��o���������ð����ɂ��ľ�āB
�@
�߽���ݸނ̌������m�F������A����ް�����ё��ɽ�������Ă�ɯ����2�Ƃn�ݸނ�
���t���A����ް���Ă�Ă����߽�݂����ް�ɓ���Ă����܂��B
�߽���ݸނ͈��������ϲŽ��ײ�ް�ʼn����k�߂Ȃ������Ă����܂��B
�i�ײβ�ق��A���Ȃ��悤�ɌŒ肵���ق�����Ƃ��y�ł����j
�@
3���߽���ݸނ�����Ί����B
�@
���́A���̼���ް��į�ߑ���ɯ����2�A��ް�߯�݂ƶװ�A����ްͯ���Ă�
�ƭ�ْʂ���t���Ķѽ��۹�Ă�ͯ�ނ̌��ɒʂ��Ȃ���Aͯ�ނ����t���܂��B
�@
���Ƃ́A�炵���Ƃ��̋t�őg�ݗ��Ă�Ί����B
�i�K���ٸ�Œ��߂邱�Ƃ�Y�ꂸ�Ɂj
�@
�@
�@
��������B
MJ�F��100�ASJ:��38�A�@ư��ٸد�߈ʒu�F�ォ��3�i�ڂ̂܂܂ő���ƁA���Ƃ�����܂��B
�ᑬ�ٸ��������A5000rpm�ȉ��̒��]��łͽۯ�قւ�·���@�~�B
�������A���͏��Ȃ��Ȃ�A5000rpm�ȏ�͒J���������炩��13000rpm�܂ʼn��܂��B
�@
�ߏ���������ċA���Ă����Ƃ������ނ�����ƁA�u�^�����v�B�i����ς�j
MJ��#90�ɕύX���Ă܂�����B
�@
���x�͒��]��ł̽ۯ�قւ̕t�����悭�Ȃ�i�ٸ�͉��������܂܂ł����j���]�悩��
13000rpm�ȏ�܂Ŋ��炩�ɉ��܂��B
ȯĂׂ�ƁA49cc�{ʲ�с{PC20����MJ��#85������̂悤�ł����A�߰Ċg�傪
�����Ă��邩��Ȃ̂��A#90�ő��v�ł����B
�@
���������̌��ʁA6�~km/h�܂ł͑����A����ȏ�͉䖝�B
�ł����ɖ��Ȃ��̂ł��̏�Ԃł��炭�l�q�����܂��B
�@
�@
����̏�����A�ł��A�z�肵�����دĂ͓�����܂����B
�������A�������𑖂��Œጸ�������U�����啝�Ɍ���܂����B
�����́A��ݸ�i��������āj���߽�݂Ɣ����͂����ݽ���Ă��邽�߂ł��傤�B
���ݽ�����ꂽ���ƂŐU���������Ă�����ł��ˁB
�@
���P
�@�߽�݂Ƹ�ݸ���ẮA�������厖�B
�@
���āA��͂Ƃɂ����ظ��݂̒ጸ�ł��ˁB
�OW�̵�قł��l���܂����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/27
40. �ꎟ�܂Ƃ߁B
�@�ݷ��p�̴ݼ�݂́A���ǔR����m�ۂ��邽�߂ɍŒ���̔n�͂ŏ������Ă܂��B
�iHONDA���ꂵ�������̂��ȁB�j
���̌��ʁA����ށA�߰Ă����������āA����ɍ��킹�ķ��ނ����a���B
�X�ɶт���l�����Ȃ��Ă܂��B
�����A�R����`�ł��B�i�����͈�Ԗʔ����Ȃ��j
�@
���ꂩ��Benly50S�i�ݷ��@12V�ݼ�݁j����ɂ���l�ւ̵�Ű�̱�����ł��B
�@
�|�|�|�@�܂����Q�l���x�ƌ������ƂŁ@�|�|�|�|�|�|�|
�@
�܂��͑����������ł��傤���A�����A��ڰ����ǂ����悤���Ȃ��̂ł܂��͂���B
�@�@ر�����ЊO�i�����B�������ǂ����́A5000�~�o������܂��B
�@�@ ���Ă͵�ًK��lMax�{��ٔS�x�Œ����B
�A�@��ڰ�����
�@�@�@���Ȃ��Ƃ����Ă���ڰ�����͍����\�Ȃ��̂Ɂi�C�x�߂ł����j
�@�@�@�Ղ̵����ɂ͊��ɕt���Ă܂����B
�@
���\���肵�����S�n�ɂȂ�܂��B
�@
���āA���ʹݼ�݁i����j�ł��B
�A�@�ł���ζѼ��āA�������ݸށA��������iPC18��PC20�j�A
�@�@���Ư��ݺ�فiʲ�ݼ�ݺ��ށj�͓����w���Ō����B
�@�@ ���ǂ���4�_�Z�b�g����Ԍ����܂����B
�@�@�@�S���w�����Ă�2��5��~�ʂł��B
�B�@������װ�������B
�@�@�@�Ղ�ɰ�ق���װ���ǂ��ƌ����̂ŁA������װ�Ɍ������B
�@�@�@������Ă����ނł��B
�@�@�@�ł����ʁA�ЊO����װ�w���ł��ˁB�i�������̂ق����y�����j
�@
���Ƃ͋C������̶���
�C�@�_�Ύ��������B
�@�@�@�s�̂�CDI�����܂�傫�Ȍ��ʂ������悤�ł��B
�@�@�@��Ű�́A������4.3���i�p�����܂������B
�D�@���������݁@ίā~�~�~�~�A���ݸނ͂��D���ɂǂ����B
�@�@ ��Ű�̏ꍇ�A���������ɍs���܂���ł����B�傫�Ȍ��ʂ����������ł����B
�@�@��A���삷���3��~������܂���B
�@
�@
88�������ޱ���߂��s���A������ܰ�Ή��Ƃ��āA�ׯ��A�������߂̋����A
�۽Я��݂��K�v�ł��傤�B
�ł�75�����܂ł̴ݼ�݂Ȃ�A��L�̉��������肾�Ǝv���܂��B
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/17
39. ���ǁ|�|�|�|�B
�@12000rpm�ʂ͌y������ė~�����B
���t�Ƃ͌����A4���فA�����HONDA�Ȃ̂ŁB
�����v���Ȃ�����P�i���H�j�𑱂��Ă��܂����B
�@
�ł����݂̍ō��ݼ�݉�]�́A10000rpm�B
���̌��ʁA������Ă������7�~km/h�B
�@
�N���Ă��錻�ۂ�\������ƁA
�i�P�j�@���̋z��������Ȃ�
�i�Q�j�@�������ݸ�
�i�R�j�@���E
�i�S�j�@ɰ�ف{����������װ�̌��E
�@
���̂��炢�ŁA����܂��A��邱�Ƃƌ����A
�@�@�@��ð��A���ް�Ă��߰Ċg��
�@�A�@�������ݸދ���
�@�B�@�Ѽ��Č����B
�@�C�@��װ����
�ł��B
�@
�ƌ������ƂŁA�ӂ������Ă��̎l�A���Ԃɂ���Ă݂邱�Ƃ����ӁB
�@
�������̑O�ɁA�O��̌��ʂłǂ����傫������Ǝv����Ҳݼު�Ă�#100�ɕύX�B
�ު��ư��ق�3�i�ڂɁB
�ł��ς��܂���ł����B
�@
�Ƃ������Ƃł܂��͇@��ð��A���ް�Ă��߰Ċg��
Benly50S�i�ݼ�݂��ݷ��ł����j�̋��r�C�n�̌��ƌ������͔N�X�������Ȃ��Ă܂��B
�R����グ��ׂ������̂ł��傤���A���ɖ߂����߂ɍ�ƊJ�n�B
�@
��ð��́A����ތa��19���l�����A���ƂƂ�ͯ�ގ��t�����Ń�18�_���ɂ��܂��B
ح����{���d�������g���āAͯ�ޑ�������ނ܂ł̊g��A���Ƃ��o���邾���[���܂�
�g��B
���ް�Ă�����Ȃ�Ɋg��B
2���ԂŊ����B
�g��O��̎ʐ^�������g���݂̂ł����A��18�ł��B
����l������Δ��邩�ȁH�H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�m�F�̂��ߎ��悵�܂����B
6000rpm�ȏ�ŏ����ٸ�������܂������AMax10000rpm�͕ς�炸�B
�傫�ȕω��Ȃ��B
�ł��߰Ċg�傪�������Ƃ͏ؖ��ł��܂����B
�i�߰Ă̍����́A�����ȕ��X��HP���Q�l�ɂ����Ē����܂����j
�@
�@
���������A���������ݸނ̋����B
�F�X�l��������A�������̂��̂Ɍ���B
ɰ�قͽ���ݸނ��P�d�ł����A�������̂ͽ���ݸނ̒��ɂ����ЂƂ�
����ݸނ��������߁i�Q�d�j
������������ݸ���گ�����g���Č������܂����B
�i�������ݸ���گ���́A�ق�Ƃɕ֗��ł��B�j
�@�@�@�@�@�@
�@
���悵�����ʁA10000rp�͕ω��Ȃ��B
�ō��������Ԃ�������7�~km/h������Ƃ͕ς�炸�B
�@
����ŁA�ݷ��n�̴ݼ�݂́A10000����m�łͻ���ݸނ��Ă��Ȃ����Ƃ�����܂����B
�@
��ŁA�����ćB�@�Ѽ��Č����B
�ǂ��̶Ѽ��Ăɂ��邩�Y�݂܂������A��������SPLʲ�Ѽ��ĂɌ���B
ɰ��ͯ�ޗp�ŁAذ�����فB
���̎ʐ^�A���Ō���ł���������������SPLʲ�Ѽ��ĂŁA�E�������B
���ł�����̨�ق̈Ⴂ�������Ǝv���܂��B
�э����A���ްׯ�߂����|�I�ɈႢ�܂��B
����ł�ɰ��ͯ�ޗp�ł��B
�iɰ��ͯ�ނ́A���������Ă���悤�ł��B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@
���̂�30���ŶѼ��Č����I���B
�i���t����тɵ�ق�h�z������A���\��Ԋ|����܂����A����܂����B�j
�@
���̌��ʁA�����ׂ��ω����B
�@
�@
��������̒����Ȃ��łȂ�ƁA�ȒP��12000rpm�܂Ōy�����܂��B
�Q���܂ł�13000rpm�B
�܂��A6000�`9000rpm�܂ł��ٸ���オ��A�����ǂ��Ȃ��ď��Ղ��Ȃ�܂����B
�@
�{���ɋ����ł��B
�r�C���͑����ς��Ȃ�܂������A�P�C���炵�����ł��B
�@
�ō��������サ�܂����B
����܂ł�
�@5�~km/h�܂ł͑����B
�@6�~��m/h�܂ł͏����䖝
�@7�~km/h�́A���R�n�������Ȃ��Əo�Ȃ��B
�@
�ł������A�����
�@6�~km/h�܂ł͑����B
�@7�~km/h�܂ł͂ق�̏����䖝
�@8�~km/h�́A���R�n����������Ώo��B
�@
�ƌ��������ł��B
�����Ēᑬ��͈ȑO�ƕς�炸�B
�r�C���́A���܂�傫���Ȃ��Ă܂��A�z���������������ɂȂ�܂����B
�@
���[��A����Ȃɏ����ȴݼ�݂ł�Ѽ��Ăő傫�Ȍ��ʂ��o��Ƃ́B
�@
����ȂɌ����̂Ȃ�A900SS��Ninja�ɂ�����Ă݂����Ȃ�܂��B
�i�ł��A�z��͍̂������Ŗ����ł����j�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/16
38. �Ȃ��ȁ[
�@�O��̑��p����ł����A������s���O����̨ܰ����̶�ް�̉����ł��B
�ǂ����ް��t�������̨ܰ����Ƃ̸ر�ݽ���������C�ɓ���܂���B
�@
�����œ����̶�ް�ɁA��6�̌����������Ƃ����ς��J���܂����B
����ŁA�z������OK�ł��B�i�J�����ڊ|����Ȃ��Ⴂ�����Ɓj
�@
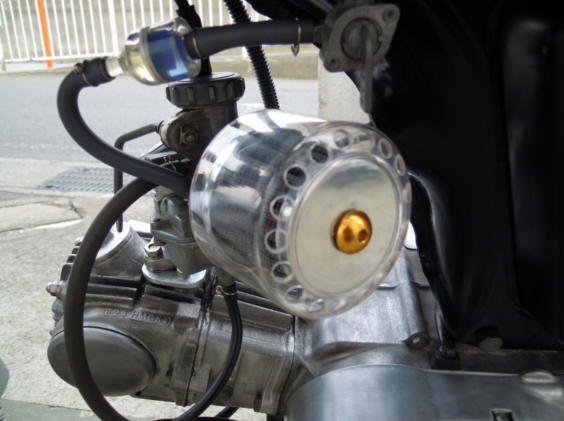
�@
���̏�Ԃŏ���Ċm�F����ƁA�F�X����܂����B
�@
�܂��́A4000�������̑��p���ł����A���̕����͔Z����������ŁB
�@
�X�ɁA����]����10000�������œ��ł��B�i����܂ł�11000�������߂��j
����]���ێ����đ������㒼������ނ�����Ƃق�Ƃɐ^�����B�@����ϔ��߁H
�@
�����A�����������̨ܰ������t���ɂȂ������ƂŁA���������Ĕ����Ȃ����l�ł��B
�@
��Ƃ��āA�S�̂�Z�����邽�߂�Ҳݼު�Ă���100����105�ցB
���łɼު��ư��ق̸د�߂���ԏ�i��Ԕ����j����A��ԉ��i��ԔZ���j�ɕύX�B
������Ƃ�肷���H�ł����܂��������ƁB�i���ꂪ���s�j
�@
����Ă݂�Ɖ���5000�������������܂���B
���S�ɔZ�����B
�@
�����ɖ߂�A�ު��ư��ق̸د�߂���ԏ�i��Ԕ����j�ɁB
�@
����ƁA���p���͖����Ȃ�A�����������ٸ�ő���悤�ɂȂ�܂����B
�Ƃ��낪���ł��͂���ς�10000�������B
�@
�د�߂��ォ��2�i�ڂɂ��܂������A�Z���݂�����10000��������B
�@
�Ƃ������Ƃ́A�����������̨ܰ����̊Ԃ�ΰ���p�~�������Ƃɂ��̋z����R�́A
ư��ټު�Ă̸د�߈ʒu�̒������x�ōς����ق��������Ă��ƁH
��100�̂܂܁A�د�߈ʒu�Œ��������ق����ǂ����������B
��105��Ҳݼު�Ăł͑傫�����Ȃ̂����H
�ł��A�X�������ɂ͖��Ȃ��̂ŁA���̋x�݂܂ł��̂܂܂ɂ��܂��B
�@
���̌�A����߂ɍs���ď������Ă��܂��܂����B
SHIFT�@UP�������ذ�ް���̨װ����߁B
�����ł���]�̒�R������Ǝv����-------�B
�@
�@���ʁA�u�ق�̏����y������Ă邩�ȁv���x�ł����B
�܂��A���̓�����ٷ����ݸ��t���鏀���ƌ������ƂŁB
�@
���Ȃ݂�SHIFT�@UP����̷����т́A���\���ɂ͂ݏo�Ă��܂��̂ŁA��������
�������|�|�|�|�|�|�ł�KITACO�����TAKEGAWA�����������ȁ[�B
�@
 �A
�A
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/10
37. ����ς�--�ɂł����B
�@�@���̋x�݂��A�ɁB�@�i����ް�@�ɂ����ς��j
��ŁA�K���ɁABenly50S���ݼށB
�܂��́A����ް�`��ύX�B
������Ƒ傫�������̂ŁA�K���ɶ�āB
�@
���́A���삵����ð���ΰ��ޱ�������̐��`�B

�@
�Ō�́A��ð���ΰ��ނ��������ɂ��Ďg��Ȃ��Ȃ������ذŰ�q�����ڰт̌���
�d�����ݼނōǂ��A��������ʲ�ݼ�ݺ��ނƱ��ݸނ̺��ނ����o���܂����B
�@

�@
����ŁA����B
�@
�Ƃ��낪�A4000�`5000�������ӂ�ő��p���������B
�@
�z���������オ�����̂ł��傤���A���Ȃ��Ƃ�4����4�~����/h������B
�@
ư��ق̸د�߈ʒu���ȁ`�B
������ƒ������܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/09
36. �܂�--�ɂł����B
�@�@���t�̂Ђ��ȓ��j���A����܂Ō��Ăɂ��Ă������Ƃ���邱�Ƃɂ��܂����B
�@
���݂́@�Ձ@��Benly50S�́A���ނɎ��t����ΰ����ޯ�ذ���܂ŐL���A�ޯ�ذ������
���̨ܰ����Ɍq���ł��܂��B
�@
������A���Ƃ̌�����ς��ķ����������̨ܰ����t���ɂ������B
�@
���R�́A����܂�ΰ��̈��e���͌����Ă܂��A�ǂ��l���Ă��ǂ��Ȃ����B
�ł��A���̂܂ܷ��ނ���̨ܰ����t������Ʋ��ƑO�����ɂȂ�܂��B
�i���R���ނ��ނ̂悤�ɑO�����j
�@
���ނ��ނ��o���ɂȂ�Benly50S�ł́A�����̏����́B
�����ŁA�ݷ��̵�Ű�̕��X�����K���āA���ނ̌�����ς��悤�ƁB
�@
�������A���ɒ����p���ް���Benly50S�B
�܂��͂��̈ٗl�ɒ������ƁB
���p�Ԃ��̂ɁA���]�ٸ���グ��ׁA���Ƃ����邱�ƂŶ�̗��������߁A���
�[�U�����グ�Ă���̂ł��B�i����j
�@
�O�ɂ������܂������ABenly50S�̒ᑬ�ٸ�������߲�Ăł��B
�Ƃ��Ă����₷���B
�Ȃ̂ŁA���̒ᑬ�ٸ�͖����������Ȃ��B
�@
�������A���̒����ʼn������������Ƃ͔̔�����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@
�ƂȂ�ƁA���Ƃ̕�����ς����������ł����A�������͖̂�4000�~�B
���Ă��o���Ă��铯�����̂ł�2000�~�ȏ�B
���������Ƃ��A��Ű�͎d�����A�����l���܂��B
�u2000�~�ȏ�́A�����|�|�|�|�|�B�v
�@
�ŁA����������ɂ͎���ł��B
���ǁA�ݼ�ݑ��Ʋ��Ƃ���]�������������ł��̂ŁA�ޗ��́A�����̔̂݁B
����ͱ�Ђ̔��g�p�B�iW50�~L250�~T5�@�Ł@500�~�@ΰѾ����œ���j
�@
���̔ɲ�ð��̌��i��14�j�Ǝ��t������M6��4�ӏ����H���Ă����܂��B
�i�Ƃ͌����Ȃ���Aح������Ō������킹��Ƃ�����A2���Ԃ�����܂������B�j
�@
�ŁA����Ȋ����B

�@
���������ڰĂ͂܂��l�p���܂܂ł��B�i����A�`��͌����ł��j
���ƂƱ�������́A�t�̶��ĂŐڒ��B�i���������͂ݏo���Ă܂��j
�@
�����̂悤�ɁA���̊p�x����ͯ�ނւ̎��t�����Ă����Ƃ���ݼޕ����Ɗ�����̂ŁA
���Ƃ���ݼނ�ح����ō��܂����B
�i�t���́A���Ȃ��čς݂܂����B�j
�@
���x�́A��Ђ�5���������̔ł��B�܁A���v�ł���B
�ŁA���ނ̌����͂ƌ����Ƃ���Ȋ����B

�@
��̨ܰ����́A500�~�Ŕ������ǂ����̍��̂��́B
�J�����̓����ȶ�ް���t���Ă܂��B
�@
�ŁA�|�|�|�|�|�|�|�|�@�v���̂ق�Good�ł��B
�@
�ᑬ�����ܲ����݂ɂ������ƕt���ė��܂��B
�ٸ�����Ȃ��B
������Ǝv�����̂́A���̋z����������܂ł��Â��ɂȂ��Ă��邱�ƁB
�i�J�����̓����̂Ղ����������ް�������Ă���̂��H�@���R�͕s���ł��B�j
�@
��ð����������A���ނ̏d���ƐU���Ŋɂ�ł��܂���������܂��A��������́A
�\�����Ċm�F���Ă���ΑΉ��\�ł��B
�i���Ȃ݂ɱ�������Ʋ��Ƃ́A���ܯ��������Ă܂��B�j
�@
�Ō�Ɂ@�Ձ@�ɊO�ϊm�F�����܂����B
�@
���ʁ@�|�|�|�|�|�@Good�B�i�悩�����B�j
�@
���Ƃ́A�Ղ�°�ݸނł̲���گ��ݑ҂��ł��B
�@
�Ƃ���ō���ABenly50S�̴ݼ�݂��ڰт����Ă��Ďv�������ƁB
�@
�����ׂ��āA���^�ݼ�݂ł́ABenly50S����Ԏ������̂ł́H�H
�ݼ�݂��ڰт̌��Ԉ�t���邵-----�B
�@
�����ׂ̃�22�ʂ��ǂ�������Ă���Ȃ����ȁB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/03/03
35. ���꺲فB
�@�O��̑����ł��B
�O��́A���ނ�V�����������̂́A��ق���o�Ă��麰�ނɱ���������g���Đڑ����������B
��������́ANGK�̂��̂Ŗ��͖����̂ł����A��͂��������ł̑�����
�l����ƁA���R�Ȃ���ʲ�ݼ�ݺ��ނͺ�ق���q���Ȃ��̈�{����ԁB
�@
�ŁA�܂��͏�����ق���ʲ�ݼ�ݺ��ނ����O���܂��|�|�|�|�|�B
�@
�o���܂���ł����B
�@
������Benly50S�̺�ق́Aʲ�ݼ�ݺ��ނ������ł����ȯĂł͏����Ă���܂������A
���ۂͺ�ق�ʲ�ݼ�ݺ��ނ͌q�����Ă���A���ނ݂̂̌����͏o���܂���B
(�@�Ձ@�̵������������m��܂��A�uMP 13�v�@�Ƃ�����ق́A�����s�j�@
�@
�������炪ȯĂ̕|���ł��B
�m�F�͌ȂŁ|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�B
�@
�ł��A���ꂪ���������_�ź�ق͊��������ׁB�@
�����g���Ȃ��`���ƁB�i��������`�j
�@
��ŁA�ǂ����t����Ȃ�ڰ�ݸޗp�̺�قƂ������ƂŁA�T���܂����B
�����ڂ͔���܂��AC.F.Posh���纲ْP�̂̂��̂��o�Ă��܂����B
���t���͓����݂����ł��B�i������獇�킹��̂݁I�I�j
��ٌa�͂قڏ����Ɠ����ŁA������������ɒ����B�@��ܰ���肻���B
�@
�����w�����A�O��]����ʲ�ݼ�ݺ��ނ��g���Ď��t���B
�@
���̖�������ʲ�ݼ�ݺ��ނ����p���s�v�Ŏ��t���I���ł����B
�@
�܂��A����܂���ł������߂�t���Ă��܂������Aʲ�ݼ�ݺ��ނɎh���[�q��
�K�тĂ����̂ŁANGK�������߂Ɍ����B
�@
�Ƃ������ƂŁA�_�Όn�̏W�听�ƂȂ鍡��A�ǂ��Ȃ�܂����B
�@
�ݼ�ݎn���B
�@
-----------
-----------
-----------
�@
���I�ȕω��Ȃ��B
�����A�����ݸނ����肵����A����]�Łu��邼�I�I�v�I�Ȕ������ٸ���߂��������
�܂����B�����ݸނ̐U���������B
�@
�u�ق�̏����ˁI�I�I�v
�@
�@
���ꂩ���́A�������g����ͯ�ށA�сA��װ�Ȃǂ�Power���グ�Ă������E�B
�����A���g���������̐��E-------���Ԃ������肻���B
�@
�Ȃ̂ŁA��Ű�͂ǂ��܂ł�
�@�u�����Č��ʓI�ȉ����v
���s���čs�������ȁ[�Ǝv���Ă��܂��B
�@
�|�|�|�|�|�ł��邩�H�H�|�|�|�|�|�|�|
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/02/�Q�S
34. ʲ�ݼ�ݺ��ށB
�@�@900SS��ʲ�ݼ�ݺ��ތ����̂��߂ɔ�����Kijima��ʲ�ݼ�ݺ���1������{
�]�����̂ŁA����Benly50S�̺��ނ��������܂����B
�@
�������ABenly50S�̺�ق��O���Ă݂�ƁA�O�̵�Ű���Aʲ�ݼ�ݺ��ނ̓r������
��ւ��p����ނ��g���Ă܂����B
���̺��ނ�Kijima���B
Benly50S�̲��Ư��ݺ�ق́Aʲ�ݼ�ݺ��ނ��O���͂��Ȃ̂ł����A�Ȃ���ւ�
��ނ��g���Ă���̂��B
�������A�~�̊����[���A���Ԃ����������̂Ŋm�F�������ɂ��̐�ւ���ނ��g�p���āA
��ޑ��̂ݺ��ނ������B
�����������ނ́A�܂��d�����Ă܂���ł����B
�@
���Ƃ��ƁA�����߂��O���Ɨ̕��������Ă����Ԃ������̂ŁA���ʂ��y���݁B
�@
���ʁA�~�̊����[���ɂ�������炸�A�ݼ�݂͈ꔭ�n���B
�܂������ݸނ����肵�Ă��܂��B�i����ȋC������j
�@
������ɂ���A����Benly50S���V�́A�C�������Ă��˂B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/02/10
33. 12V�@�d���B
�@�@�ޯ�ذ����12V������ȸ����ݒu���܂����B
�@�i�[�d�ɂ��g���܂��B�j

����݁@ίIJŁ~�~�̏�ɂ���̂��d�͎��o���ȸ���B
�ɂ������̂ŁA���̺ȸ������d������鼶ް���ĺ��ނ����슮���B
�@������°�ݸނ෬��߂�����Ł@OK �ł��B�@
�@
�@�ł�ȸ���͖h���ł͖�����ł���ˁ[�@---------�@�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@18
32. �l�@�B
�@�@�Ȃ�ƂȂ��ABenly50S�ɑ��Ă͂�邱�Ƃ͂�����ȂƎv���Ă��������B
�@����l���邱�Ƃ������܂����B
�@
�@�ݼ�݂ɂ��ẮA�܂��͂Ђƒi���B���̎d�l�ł̍ōD���ɂȂ��Ă���͂��B
�@
�@�ł��A�ԑ̎��肪�H�H�ł��B
�@
�@ر�����������Ȃ������B
�@���Ƃ���Benly50S�́A�Ȃ��K�𒆐S�ɂ������Ă����E�ɓ����ĺ�Ű���Ȃ����Ă���
�悤�Ȋ����̵����ł��B
�@����܂��H
�@�܂�����ݸޒ��̽ۯ��ON�ɂ�����ĉ��d�������āi�����ق�̏����j�X������ق�
�y���Ȃ��ā|�|�|�|�|�|�|�B
�@
�@������β��ް����Z�����ƂƁA�����ʒu��ر��Ԃ��ł��邱�ƁH
�@
�@�ƂȂ�ƁA��ݸޱ�т��������邱�Ƃő�͏o�������ł��B
�@
�@�����ABenly50S�p�̽�ݸޱ�т́A����߂̂��̂ł��@�d�}���ȏ�B
�@�i���������ł́A��ނ�100EX�p��ݸޱ�т���ݕt���o����炵���j
�@
�@��ݸޱ�т��ς̂��̂��Ė����ł����ˁB
�@����ň�ԗǂ������̂��̂����Ԃ����ĒT���̂��������ȁ[�B
�@�����Ȃ�ƁA������������ݼ�݂��K�v�ł����B
�@
�@�����A�ԑ̂��ި�ݼޮ݂���������̂͊��S�ɂ����̓��ɂ͂܂�ƌ������ƁB
�@
�@������ƍl���ā|�|�|�|�B
�@
�@�Ȃ���Ȃ��ƍl���Ă܂��B
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@18
31. �܂��܂��B
�@�@�~�x�ݖ�����������I���Ȃ��y���B
�@�ȁ[�C�ɂȂ��Ă���������������ƁAͯ�ނ̑|�������{�ł��B
�@�C�ɂȂ��Ă������R�́A
�@�@�@�@�w��������A�۰�����ް�Ɩ{�̂��AO�ݸށ{��ٍ܂Őڍ�����Ă���B
�@�@�@�@�@�i�{���́A�ٌ`���O�ݸނ̂݁j�@
�@�@�A�@���ނ̖��ʂ̍������܂��m�F���Ă��Ȃ��B
�@�@�B�@ͯ�ނ́A��������݂��܂���ςȂ��̏�Ԃł���B
�@�ȏ�̗��R�ł���Ă݂܂����B
�@
�@
�@�܂��͇@�A�̷��ނ̵��ްΰفB
�@�ۯ������ނ̶��āA���ނ���ΰ��ނ�O�ݸށA��ΰ��ނ�ͯ�ނ̶��āA
�@�������۰�����ް�̶�ݔr�o���Ă�O�ݸނ��������܂��B
�@
�@�����Ė��ʊm�F�B
�@�i���ʂ̊m�F���@�́A�����Ȑl���A��������Ă���̂ŁA��������Q�l�Ɂj
�@�����������ʁA���ʂ��K����1.5������߂ł����B�i���߂ɂȂ�j
�@�����Œ������s���A�K���20�����ɂ܂ł����Ă����܂��B
�@�������������āAɷ���ق�20.0�����ɒ����B
�@
�@������A�۰�����ް�̎��t�ł��B
�@�O�̵�Ű����O�ݸށ{��ٍ܂��g���Ă������R�́A��݂̘R��h�~�̂͂��B
�@�@�i�ʏ��O�ݸނ݂̂Őڍ��j
�@���������Đڍ��ʂ̖ʐ��x���@�H�@���イ���ƂŁA�܂��ͼ�ٍ����B
�@���\��Ԏ��܂������A��ڲ�߰��疇�ʂ����g���ĉ��Ƃ������B
�@���ꂩ�絲ٽİ݂Ŗʏo���B
�@����Ă݂�ƁA��ϑ�Ŗʂ��o�Ă܂���ł����B
�@30�����炢�ʏo�����ĂȂ�Ƃ�����Get�B
�����āA�۰�����ް�����t���A��ݺ����ON�ɂ��Ďb�����u�B
�@��݂̟��݂������A����őS�����������B
�@
�@���āA����ͯ�ނ̔R�Ď��̐��|�ł��B
�@���ɖ��͋N���Ă��Ȃ��̂ł����Aͯ�ނ̔R�Ď����Y��ȕ��������͂��B
�@�Ȃ̂ŁA�|���ł��B
�@
�@�܂���ͯ�ނ��͂����A�R�Ď��̶���݂J�ɏ����B
�@������߰Ă̌������s���܂���ł������A�߰Ă��߰¸ذŰ�Ő��B
�@����A����ނ������Ă̓������Ԃ����邽�߂ɁA�т��㎀�_
�@�i����ނ�IN,EX���ɕ܂��Ă����ԁj�ɶт������Ă����Aͯ�ނ𗧂Ă���Ԃ�
�@�@�߰¸ذŰ���ʂ�IN,EX�����߰Ă��畬�o�B
�@����ŔR�Ď������߰¸ذŰ���R��Ȃ���Γ�����͂܂���OK�B
�@�߰¸ذŰ�́A�Z�����������A������Ƃ������Ԃł������Ă����܂��B
�@
�@���ʁA���݂�����OK�B
�@�i���������̕��@�ł́A����ނƼ�Ă������悤�ɕό`���Ė����ۂ���Ă���ꍇ�ł�
�@�@���ʂ͓����ɂȂ�܂��B��͂�����ނ��͂���������ނƼ�Ă��m�F����̂��������B�j
�@
�@���ł��߽�ݏ�ʂ��^�J��ܲ���ž����Ƒ|���B
�@�܂��y��������ł��B
�@
�@�������Y��ɂȂ���ͯ�ނ�g�ݍ��݂܂��B
�@�ѽ��۹�Ă�ͯ�ޑ��̐茇��ϰ������킹�Ċ����B
�@
�@ͯ��ް�ƶѶ�ް(���̊ۂ���ް�j�̶��Ă��V�������Ă��ċK���ٸ�őg�ݕt���B
�@�iͯ��ް���Ķ�ް�̓����ɂ����������i�n�ʑ��j�ɂȂ�悤�Ɏ��t�������
�@�@���������A����߂̕����狳���Ă��������܂����B
�@�@�߽�݂������������ł��B��̗�������������Ă���悤�ł��j
�@
�@����B
�@
�@�����ݸނ́A���ʂɉ���Ă܂��B�@�@
�@����o���ƁA�܂��ق�̏��������ٸ���オ�����悤�ȁB
�@����]�ł��A�ق�̏��������@���C���o���悤�ȁB
�@
�@����ݽ���������������ŁA���ʂȂ�C�̂����ŕЕt�������ȕω��ł��B
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@12
30.�@�~�x�݂̍H��ŏI�B
�@�@�~�x�݁A����ωɂł����B
�@�Ȃ̂ŁA����܂ŋC�ɂȂ��Ă����_�Ύ������l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B
�@
�@���낢��ȕ����A�_�Ύ����ɂ��ď�����Ă����܂����A�Ƃɂ��������B
�@�_�Ύ�����ݸ��]�p�i�ײβ�فj�Ō��܂��B
�@
�@�܂��Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂��ݷ��p��12V�Ɋ�������Ă��܂��B
�@�i���Ȃ݂��ײβ�ق�MITSUBA���j
�@�@�E�@�ײβ�ْ��a�@�F�@110mm
�@�@�E�@F�@�́@T�����@�@�F�@ 28mm
�@�ƌ������Ƃ́A
�@�@�@�@360���@�~�@28.0mm�@���@�i110mm�@�~�@�@�j�@���@29.2��
�@
�@�i�p�́@BTDC27��or 28���Œ肪�������l�ł����AT Fϰ�����ǂ������Ă�̂�
�@����Ȃ���H
�@����Ƃ��@1�`2�������Ă�H
�@
�@���āA�����i�p�����čs���킯�ł����A�����܂ō���͉����ł̑Ή��Ƃ��܂��B
�@�i�s�̂�ڰ�ݸ�CDI�Ȃǂ͎g���܂���j
�@���^�ݼ�݂̂���܂ł̍ő�l��SS50��42���i�ő�i�p���j�������ł��B
�@����������Ͷт��Ⴄ������ށA�߰Ă�����Ă��āA�Q�l�ɂȂ�Ȃ��B
�@
�@�s�̂̌Œ�i�pCDI�ł悭����@�{3���@(��30��)���ƌ��ʂ͌����Ȃ��ꍇ�������炵��
�@�̂ŁA�����͎v�����Ĕ{��33���iɰ�ف@+6��--�@�v��������߂��H�j�Ō������܂�
�@
�@�i�p����������́A2�ʂ�B
�@�ЂƂ́A�����̷������H�����ײβ�ق�i�p���ɂ��炷���@�B
�@�����ЂƂ́A��ټݸݻ���i�p���Ɉړ���������@�B
�@
�@�ŏ��̳����̷����H�ł����A����ͳ����̷���۰���Ƃ̍��킹�ʂ����A۰����
�@���炷���@�̂悤�ł��B�i����߂�����o�Ă���悤�ł��j
�@�ł����̕��@�́A����]���ɔ����Ȃ��������̷����j�����₷���炵���ł��B
�@����ɂ���ĸ�ݸ��۰���������Ȃ肸��邱�Ƃ͖����ł��傤���A°�ݸޒ��ɋN������
�@OUT�@�ł��B
�@�Ȃ̂Ō�����������Ă݂܂����B
�@
�@�@�ݷ���R��ݸ��۰�����t���a�̓�15�H�B�ið�߰�Ȃ̂ł�����K���j
�@�����̷��̕��́@4mm�@�ł����A�ڕW�́@6���@�i�p��������ʂ�
�@�@�@6���@���@360���@�~�@�i��15mm�@�~�@�@�j�@���@0.79mm
�@����Ȑ����ɍ��܂���B�@�i�~�ʂƒ����̌덷����j
�@
�@�܂��s�̂̉��������̷��́A2mm�i�p���ɂ��点��l�ł����A�قɂ��炵���ꍇ�ɂ�
�@�@360���@�~�@�i�@2mm�@���@�i��15mm�@�~�@�@�j�j�@���@15.3��
�@
�@28+15.3=43.3�� �ɂȂ����Ⴂ�܂��H�@�ȂŒ�i�p�ɂ͖����H�B
�@�v�Z����Ă�H�@�������݂����H
�@�����Ȃ�SS50�ȏ�H�B
�@���炵�ʂ����Ȃ�����t�����ł����ˁH
�@
�@
�@�����ŋC����蒼���Ė{������ټݸݻ����̂̈ړ��B
�@
�@�ݻ��́A�ޱ������琶���Ă���Q��ϳ�Ă���ٻ�������߰�Ƌ����߂ł��B
�@����āA������ټݸݻ��̎��t�������ɂ��Ĉʒu�����炵�܂��B
�@�܂�6���i�p������̂ɂǂꂾ���̈ړ��ʂ��K�v���v�Z�|�|�|�B
�@
�@ϳ�Ă̂˂��������ʒu�́A�ײβ�پ������炨�悻�@65.5mm�B
�@�ƂȂ�ƌv�Z���͈ȉ��̂Ƃ���B
�@�@65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�~�@�@6���@���@360���@���@6.8mm
�@�ړ��ڕW�́@6.8�����ł��B
�@
�@���Ď��;ݻ��̂��炵���B
�@
�@�ۖ_�₷��ł������炨�����炬�肬��܂ōL�����
�@�@�@ɰ�ٌ��a�@��5mm�@���@�����̒��a�@10mm
�@�ǂ�������Ă��@���ꂪ���E�ł����B����ȏゾ�ƾݻ��{�̂�����Ă��܂��܂��B
�@���́@5mm�@���炵���Ƃ��̐i�p��
�@�@�@360���~�@�i�@5mm�@���@�i65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�j�@���@4.3��
�@���܂���ʂ͊��҂ł��܂��Aɰ�ى����ł́A���ꂪ���E����----�B
�@�@ �@
�@
�@
�@�s��CDI�ƖڕW��6���̂����������ԁB�@����Ȃ��ȁB
�@
�@�C����蒼���A�g�ݕt�����ς܂��Aý��݁B
�@
�@�������A4.3���ő�������؉����������܂��B
�@�߯āi�����̎���ԏ�j�ɖ߂�A�i�p��M�������Ƃ���A0.5mm�߂��i4.5mm���i�p�j��
�@���؉����~�܂�܂����B
�@�@ 360���~�@�i�@4.5mm�@���@�i65.5mm�@�~�@2�@�~�@�@�j�@���@3.9��
�@
�@���̏�Ԃł��炭����܂������A���I�ȕω��͖���(���R�ł����B�j�B
�@�������A5000�������`8000�������ł̉����͗ǂ��Ȃ�A6�~km/h�܂ł����\�����Ȃ�܂����B
�@�܂�����܂ł�1�A2����11000�������A3���͂����Ƃ�8000�������ł�����9000�������܂�
�@�y�ɂ����Ă�����悤�ɂȂ�܂����B
�@
�@�������A9000�`11000������������͏�����������������ٸ�����ł��B
�@�����ōŏI�̷��������èݸށB
�@����܂Ł@�@�@�@�@�@MJ�F��95�@ư��وʒu�F3�i��(�^�j
�@���ʂ́A�@�@�@�@ �@MJ�F��100�@ư��وʒu�F1�i�ځi��ԏ�j
�@
�@����]�ł������ٸ���o���|�|�|�|���������܂��B
�@
�@�����ŁA�ʖڌ��ł�����x�قɂ��炵���Ƃ���4.3�����ײ�B
�@����Ɖ��̂�ɯ�ݸމ��͂��܂���ł����B(ׯ���H�H�j
�@
�@�s�̂�CDI�́A���q����̷���������̾�èݸނ����·���l���ā@3���ʂɐݒ�H
�@�m���ɂ���ȏ�̐i�p�𐳊m�ɍs���Ƃ���A۰���t��CDI��Ă̍w�����K�v�ŁA
�@��������ɂ́A����Ȃ��ͯ�ށA�Ѽ��Ă��K�v�ł��B
�@
�@�ł����Ⴋ���Ⴋ���́@���t�@�Ձ@�̵����Ƃ��Ă͍��͂���ŏ[���B
�@
�@�c��������ݽ��۹�āi35T)�ł����A�߂��̼���߂ɍɂ������Aȯļ����ݸނ�
�@���łɔ�������Ȃ̂ł����A�ŋ�ȯļ����ݸގ��̂���Ă��Ȃ��̂ł��a���ł��B
�@�܂��A7�~km/h�͏o��̂ŕs���R�͖����͂��ł����B
�@
�@���āA�����Benly50S�ł̓~�x�݂̍H��͊����ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@5
29.�@�蒼���B
�@���Ƃ����t�����d�C�n���̎^�ۗ��_���тł����A���̓~�x�݂𗘗p���ď����蒼���B
�@
�@����݁@����ݻ����݁@�Ɓ@���Ɛ����ݸށB
�@�e�Ɋp���ʂ����邽�߂ɁA�z����K���i�m���ł͂���܂����j�ɍs���Ă����̂ŁA�C���B
�@����̎^�ۗ��_���тɂ��A+����2�n���A-����3�n�����ޯ�ذ�Ɍq���܂��B
�@�i-��������̂́A���ݸނ̐��̂��߁B�j
�@
�@�������ABenly50S���ޯ�ذ�[�q�́A��������`���B
�@�܂��@+�@���ɂ�˭��ނ��t���Ă��܂��B
�@˭��ޕʑ̂Ł@+�@-�@�[�q���纰�ނ�����Ă������̂ł����A���̱�������Ͷ��Ď���
�@���\�m���ɾ�Ăł��܂��B
�@�Ȃ̂ŁA���̱�������𗘗p���Ď��t���邱�ƂɁB�@�@
�@
�@�܂��A���̱�������́@+�@�Ɓ@-�@�́A���̂܂�ʰȽ�q�����Ă��邽�߁A�K���Ȉʒu��
�@+�@-�@���ɐؒf�B
�@
�@�����ı�����������B
�@�܂��́@+�@���B
�@+�@���Ɏ��t����̂́A����݁@����ݻ����݂́@+�@�[�q�̂݁B
�@����āA�ޯ�ذ�[�q����˭��ނɍs���Z�����ނ��ؒf���A�ޯ�ذ�[�q���ɓ�҂�
�@ҽ��������ނŐڑ��B
�@���̂����̈������݁@����ݻ����݂́@+�@�����A�������˭��ނɍs�����ނ�
�@����Ōq���A˭��ނ̌�͂܂��܂������ʰȽ�ցB
�@
�@���Ɂ@-�@���B
�@�������͂�����Ɩ��ł��B
�@-�@�̒[�q���痈�Ă��麰�ނ��O���ɂ��Ȃ��Ⴂ���܂���B
�@�����Ƃ��ẮA
�@�@�@�@�@��҂��܂��t���āA���̂����̈�ɂ������҂�����B
�@�@�@�A�@��҂ɷ����ҽ�����ޕt�����ĎO���ɂ���B
�@��Ű��������͔̂z�������Ȃ��Ă��އA�B�@
�@�O���̃��X����삵�A�ޯ�ذ�́@-�@�[�q�����ޕt���B
�@�����Ă����ɁA����݁@����ݻ����݂́@-�@�[�q�ƁA���ݸނ̺��ށAҲ�ʰȽ��
�@�@-�@��ڑ��B
�@
�@���ꂪ����B
�@�@�@�@ �@�@
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@���@�蒼���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�蒼����
�@����ɂ�����������܂��A�܂�����Ȋ����ł��B
�@���ޕt�������̂́A�����ł��ڑ���ǂ�����ׂ̂��܂��Ȃ��݂����Ȃ���ł��B
�@
�@���ƁA���ݸނ���{�lj��ł��B
�@
�@���ݸނ̌��ʂ�F�X�������܂������A�ǂ��Ƃ��ǂ����q���Ƃ������A�����Ă��̌��ʂ�
����̂������̂���Ű�̒m���ł́H�H�H�H�H�H�B
�@
�@�����ŁA�܂��͂���Ă݂邱�Ƃ�g��Ƃ��鵰Ű�A�����܂����B
�@��ނ̓_���������邽�߂ɂ́A���d����ϲŽ���ޯ�ذ�ɕԂ������킯�B
�@
�@�Ȃ̂ŁA
�@�@�@�@��ނ�ܯ������ײ�Œ͂݁A��ނ���ܯ�������O��
�@�@�A�@8�����̺��ނɃ�10�̌����J���Ă���[�q�����ޕt�����A��ނɎ��t��
�@�@�B�@�ēx���ܯ������ײ�Œ͂����ނ��˂�����
�@�������A���ΰَ����̨݂��ז��ɂȂ�A���ݸނ�ΰ����������Ă��܂��܂��B
�@���傤���Ȃ��̂ŁA�S�O����ح����Ŋ�����̨݂������܂����B�@
�@���̌��ʂ�����B
�@�@�@
�@
�@ �Ō�ɁA���̖��̎O�p�n�т̏����B
�@
�@���t�@�Ղɕ����ƁA�߲�߂͍��������Ƃ̂��ƁB
�@�܂��A�Ƃ�B������ڰĂ������p�𗎂Ƃ����ق��������炵���|�|�|�|�|�B
�@���łɁA�莝���̽ï���@�iMichelin�F�����AHRC�F�E���̂݁j���Ƃ�B���ɓ\��t���B
�@
�@���ǂ����Ȃ�܂����B
 �@���@
�@���@
�@
�@�܁A�ɂȂ킯�ł��B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013/�@1/�@3
28. �ɂł����B
�@�܂�����Ă��܂��܂����B
�@
���̋x�݁A�ɂ������̂ŁA�C�ɂȂ��Ă���ر��Ԃ��ڰтƂ̌��Ԃɏ���������܂����B
�@
�܂��́A���萻�̻���ڰт̑��������āA�ׂɁB
�߲�߂́A��20�œS�߲�߂���ڽ���i0.1�����ʂ̌����j�Ŋ������s�̕i�B
�i���S���ڽ���ƁA���H�d���{�S�������̂Œׂ��⌊�����ő�ςȂ̂ŁB�j
�@
�����𑪂��Đؒf���A���[����ϰ�Œׂ��܂��B
���ʂ���ϰ�ł�����̂ŁA���\�߲�߂��ʉ��ɁB
��������炵�āA���قŌ����J���đ����B
����ɍ��킹�Ļ���ް�i�����̱�Дj���`��K���ɁB
�@
�ŁA����Ȋ����B
 �@���@
�@���@
�@
���[��B�@����ް�̌`�͓���B
�@
����ς軲��ް�ƁA����ڰт͍��ɂ���������H
�@
�����ł�CB550F�̍��ɋ߂Â��悤�ɁB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/23
27. �^�ۗ��_���с@2�B
�@�@�܂��܂��A�����ɂ���܂����B
�@
�v���Ԃ�ɓd�q�H���ȯĂŌ��Ă�����|�|�������ݻ����݂̍������ڂ��Ă܂����B
����ݻ����݂��Č����A�^�ۗ��_�ł����A����Ă݂Ȃ����Ƃɂ́A���������Ȃ��̂�
����Ă݂邱�ƂɁB
�@
�^�ۗ��_���с@1
�@
��H�ɂ��ẮA���낢��ȕ���������Ă��܂��̂ł�����Q�l�ɁB
�@
�ʏ�́A25V��470��F�A2200��F�i1000��F�j�A4700��F��3�Œᑬ�`�����܂őΉ�����
�Ƃ̂��Ƃł����A���ꂾ�ƒᑬ�������P����Ȃ��̂ŁA100��F��220��F��lj������ق���
�����Ƃ̏�������A�m��Ȃ����Ƃ͂����L�ۂ�+���Ȃ��m���������鵰Ű�́A��������
220��F�A470��F�A1000��F�A2200��F�A4700��F��1���A���t���邱�Ƃɂ��܂����B
���v�@8590��F�I�I�@
����ݻ��́A�w��1�@200�~�ȉ��ł��B
�@
�����A���l�̓d�q���i���X�ōw����A�ƂɋA���Ċm�F�����Ƃ���A�ϔM105������
���肪�A85�����w�����Ă܂����B(�͂Ƃ肽������܂���j
�@
�܁A85���ȏ�ɏオ��Ƃ��͂Ȃ�炩�̂Ƃ�ł��Ȃ��ُ킪�N���Ă���Ƃ��B
�܂��������ƁB
��������ް�ي�ՁA125V�@10A��˭��ނ������Ƃ��܂����B ���v�ł�1000�~���炢�B
�@
�v���Ԃ�����ނ��Ău����o���āA�����B
�d�q�H��̏ꍇ�A��Ű�ɂƂ��Ĉ�Ԗ��Ȃ̂��d�q���i��ڲ��āB
�Ȃ��������́A����Ƃ������ݽ���K�v�ȋC�����܂��B
���낢�댩��ƁA�u�����������v�ƍ��ꍛ�ꂷ��悤��ڲ��Ăɂ��Ă�����X�����܂��B
�@
�A�]�B
�@
�ł��邾���z�����Z���A������ϲŽ�̔z�����ł��邾������A����ݻ����m�̌��Ԃ�
�m�ۂ���l��ڲ��Ă�30���قǍl���܂������A��Ű�͂��̒��x�B
 �@�@�@
�@�@�@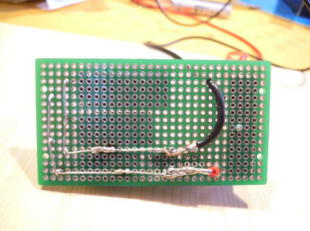
�@
 �@�@�@
�@�@�@
�@
���Ȃ݂Ɋ�Ղƺ���ݻ��ͼغ݂ŌŒ�B
�@
�ޯ�ذ�̱�����������O���Ē����Ŕz�����悤�Ǝv���܂������A���ʂ������ꍇ��A
��ꂽ�Ƃ��̕������l���ı�������͎c���܂����B
�{�̂́A�ޯ�ذ���̶�ް�����ɂ���ԍڍH����t�����ĂŶ�ް���Ɏ��t���܂��B
�i��̨ܰ����ŋ����ޯ�ذ��������ɂ����Ⴎ����j
�@
�^�ۗ��_���с@�Q
�@����݁@����ݻ����݂����\���߂ɏI������̂ŁA���ݸނ����{�B
�@
�{���̱��ݸނ̖ړI�́A
�@�@�@��ޔ��Ύ���ϲŽ�d�������������ޯ�ذ�ɕԂ��B
�@�A�@���ި�����Ō����̗����Ă������ߗނ�ϲŽ�d�����ޯ�ذ�ɕԂ��B
�ȏ�ɂ����ނ̉ΉԂ�����������A���߂𖾂邭������A�d�Cɲ�ނ����炷�����ł��B
�@
�ŁA���t���Ă݂܂����B
���ނ́A8�����̍��A��6�p�̒[�q�ŁA���삵�܂����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@
�{���̖ړI���炷��A��ނ�ܯ��������ɱ��ݸނ�����̂��������p�ł����A
��ނ�����[�q(��10�j�̎莝�������������̂ŁA���ƃ�6�̒[�q���g���Ĵݼ�ݑ��ɁB
�i���Ƃł��A��C�̗���Ŕ�������Ód�C������Ƃ������Ƃ��B�j
�����ċt�����ޯ�ذ��ϲŽ�ɒ�������Ί����B
�@
���Ă��āA�����ł��B
�@
�܂��ʹݼ�ݎn���B
�@�n�����Ɋւ��Ă͕ω��͂���܂���B
�@�����ݸނ͏����ω�����ł��B
�@�ȑO�̂ق����ݼ�݂����ۉ���Ă��Ċ��炩�Ȋ����ł������@�������߂��Ă���������
�@�����Ŕ����������Ȃ���+�����U�����ɂȂ�܂����B�@�i�ق�̏����ł���j
�@
���s
�@�ᑬ�E������]��́A���قւ�·���ǂ��Ȃ�܂����B
�@�i�����܂Ł@�u����ȋC�����܂��B�v�@���x�j
�@
�@�Ƃ��낪�A������]��ł͌��\�ȕω��B
�@�Ȃ�Ƃ���܂�8000�������œ��ł��������̂�10000������+���܂ʼn��܂��B�i1�A2���Łj
�@�ȂA�������ݻ����݂Ʊ��ݸނ����t�������ƂŁA����܂�8000������Max������
�@�����������Ȃ����̂�������܂���B(�ڐG�s�ǁ{�ޯ�ذ����܂߂āH�H�H�j
�@
�@4����10000����������9�~km/h�ł锤�Ȃ̂ł����A��������7�~km/h�i8000�������j�ȏ�
�@�łʹݼ�݂̐L�т��������ŁA8�~����/���i9000�������j�܂ŏo�����Ƃ���ƒ���������
�@�K�v�ł��B
�@
�@��۸ނȂǂŁA���\�ݼ�݂̐U�����Ȃ��Ȃ�Ƃ�������گ��݂�����܂����ABenly50S�ł�
�@���]�̐U�������������܂����B
�@
�@�ݼ�ݐv��A��ۯ��+�߽�݂̏d�ʂƸ�ݸ���Ă̶�������Ă����ݽ���Ă���A�s��
�@�����i���킾������A�����ォ������A��������j�Ÿ�ݸ��]�ɂ��������ꍇ��
�@�U����������Ǝv���܂��B����͑��C���Ō����Ȃ͂��B
�@������A���݁@����ݻ����݂ŐU��������Ƃ����͕̂s���������������Ă������̂��A
�@������Ɣ�������悤�ɂȂ������ʂł͂Ȃ����ƁH
�@�Ȃ̂ŌÂ�4���̵������ޯ�ذ������Ă���ꍇ�ȂǂŁA���\���ʂ�����H
�@
�@������Benly50S�͒P�C���B
�@�����́H�H�H�H�H�H�H�@�ł��B
�@
�@�ނ��Ⴍ���Ⴂ���悤�ɂɉ��߂����------
�@
�@�ޯ�ذ�����A�ڐG�������������ߔ����͂��ォ��������܂ł́A�߽�݁E��ۯ�ށE
�@�N�����N������Ɖ����ĉĂ����ԁB
�@���������ۂŐU�������B
�@
�@����A����݁@����ݻ����ݐݒu�i+�ǂ����̐ړ_�H�j�ɂ��
�@�@�@�@�����͂��オ�������ƂŔ����H�����߽�ݽ�߰�ނ��オ���ݸ�̉�]���x���㏸
�@�@�A�@���k�H���ł́A���k�䂪�ς���Ă��Ȃ����߁A���܂łƓ�����]���x�܂Œቺ
�@�@�B�@���ʁA4���ٓ��ł̉�]���x�̑����E�x���̍����L������
�@
�@Ű��Ă��Ƃ��Ȃ��ƁB
�@�����́A�Ȃ̌����ŕs���������Ă��邾���������肵��-------�i�l�������Ȃ��j�@
�@
�@���ƁA���̂��r��̓������ς��܂����B
�@�O�͏�����ݏL�������̂ł����A����3��̔r�K�X�̓����ɋ߂��Ȃ�܂����B
�@�i�����ƔR�Ă��Ă���H�H�j
�@
�@���_
�@�@��������݁@����ݻ����݂Ʊ��ݸނ��ɂ�����̂ŁA�ǂ��炪�������̂��A
�@�܂������̐ړ_+�ޯ�ذ�������̂��͔���܂��A���t�@�Ղ�Benly50S
�i���s�F20.000�����ȏ�A���ށFPC20,�@��װ�Fɰ��+���ނɌ������j�ł̌��ʂ́A
�@�@�E�ᑬ�`������]�ł́A�����͂������A�ٸ���オ�����|�|�|�|�|�|�u�C������v�B
�@�@�E����]�ł́A���IҰ���łȂ���10000������+���܂ʼn��悤�ɂȂ����B
�@
�@�����ޯ�ذ��V�i�ɂ������Ɏ^�ۗ��_����2�̗L�薳���̌��ʂ��m�F���܂��B
�@
�@�܂������Ȉ�����[�ł��Ȃ����[�ł��Ȃ��Ɗy���݂Ȃ���K���ɂ��܂������A���ʂɂ�
�@�������Ă܂��B
�@�����A�������킩��Ȃ����Ƃ��s���Ƃ����Εs���B
�@�ł��A1000�~�ʼnɂԂ��ɂ͂Ȃ����̂ŁA�܂��������ƁB
�@
�@���㏭�������ķ�������̍Ē�������낤�Ǝv���Ă��܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/16
26. �T�ρA�ꉞ�����H�B
�@�{���A�T�ύŏI�ύX�B�i����������Ɩ߂邩������܂��B�j
�@
������̂́A
�@�@�@�ݸ�̉����i���ð�ߎg�p�j
�@�A�@ر̪��ް��̪��ްڽ��
�@�B�@���̎O�p�n�Ѷ�ް���t���B
�@
�܂��͇@�@�ݸ�̉����B
���\Benly50S�͍��������������A�ݸ�ɐF�X���݂��l���܂������ǂ��������܂���B
�i�ݽ���Ȃ������|�|�|�|�|�|�j
�Ȃ�ŁA���܂ł��ׯ���قł͈�ԍD����CB550F�̍����ݸ�݂����ɂ��悤�ƌ������Ƃ�
���ð�߂ʼn����B�i�s�̂������ް���Ɛ������܂��ĎK���i�s����̂Łj
����肷�邱�Ƃʼn��̂��ݸ���ۂ����������A��������CB550F�̲Ұ�ނɋ߂Â��A�������
���t�@�Ղ��C�ɓ����Ă���܂����B
��Ẳ�������������ȁ[�B
�@
�@�@�@�@�@ ��CB550F�@�Ȃǂ��ł���B
��CB550F�@�Ȃǂ��ł���B
�@
�@
�����ćA�@ر̪��ް��̪��ްڽ��
̪��ް�������F�X���Ă݂܂������A��͂肠�̓S��̪��ް�͌y�������邱�Ƃ�����A
�l�ɂ���ẮAү���������������肳��Ă��܂����A����ł��d�����Ȋ������|�|�|�|�|�B
�@
�Ȃ̂ŁA�v������̪��ްڽ�ł��B
�@
��Ђ�1�����̔��ė��āA�ި�����ް�ł��Ⴟ����Ƃ����܂������A�ڰт���
ر���̵��ް�ݸނ̕����́A��͂�1�����̔ł͋��x�s���łӂɂ�ӂɂ�B
�����ŁA������1.5�����̔����킹�����ĂŌŒ肵�ĕ⋭�B
��ݶ�ײĂ����肬�跬ر�̓����ɓ���܂����B
ر̪��ް��������������ƂŁA���\�y�ʉ��ɂ��v�����Ă܂��B
�@
�Ō�̇B�@���̎O�p�n�Ѷ�ް���t���B
��ĉ��̖��̎O�p�n�т́A̪��ް���Ȃ��Ȃ�X�ɑ傫�ȋ�ԂɂȂ�̂ŁA�ēx0.5������
��Д�ؒf�A���t���܂����B
�@
����17���߂��܂ł̍�ƂɂȂ�A�I������Ƃ��͂�����͐^���ÁB
�ŁA���̏�ԂŎʐ^���B�����̂�����B
�@


�@�@���@CB550F�ɂ͂܂��������ł��ˁB ���@���Ɛ�̪��ްڽ�I�I�I
�@
���Ԍ��Ă݂Ȃ��ƍŏI�I�ɂ͂Ȃ�Ƃ������܂��A�܂�����ƁB
�@
�O�p�n�т̔́A���̋x�݂ɂł��A�F��h�낤�Ǝv���Ă܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/12/�@2
25. �u���[���v�̏��B
�@24.�ŁA�Ѽ��Ă���ւ��˂Ƃ������ƂɂȂ�܂������A�ɂȓd�Ԃ̒��ŁAȯĂ����Ă���
�Ƃ���A�߂��������܂����B
�Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂��ݷ��p�œd���n��CD50�B
�@
�|�|�|�@CD50�̂a�s�c�b��27�x�ŌŒ�|�|�|�|�|
�@
�u���[���v�@�ł��ˁB
���^�ŋ���SS50�Ȃő�i�p��40�x�ȏ�I�B
�@
��������S��ȯĂ̏��Ȃ̂ŁA�M�����͂ǂ����킩��܂���|�|�|�B
�@
�m����30km/h�K����50�����̵����ōł��d�v�ȓ����͍����ᑬ�ٸ�B
���Ƃ���A�i�p���Œ肾�Ƃ����̂������܂��B�@
�т��A�ᑬ�ٸ�����߂�����ł��傤�B
�m���ɁA�����̐É�������̍⓹��4���ŏ�肫���Ă��܂��܂��B
�@
�Ȃ̂ŁA�a��������������]���o�͉����邽�߂ɂͶсi����ݸށj+�i�p�i�b�c�h�����j���K�v�B
�@
�ǂ�����������̂Ȃ�ͯ�ނ������������Ȃ�܂��B
��������Ɠ��R�ׯ��̕��ׂ��オ��A2���ׯ��Ȃǂ։������A�X��
���]���ٸ��₤���߂�5���A6���̸۽�~�b�V�������B
��ق̉��x���オ��̂ŵ�ٸ�װ���t���B
��]���オ��̂ŁA���ްΰق��K�v�B�|�|�|�|�|�|�B
�@
��+�i�p�i�b�c�h�����j���s���ƁA��Ű�͐^�������ɂ��́u���^�ݼ�݂̋a�n���B�v��
�ׂ鎩�M������܂��B
�����Ȃ�ƁA���\�ȏo��ł��B
�@
�l�������B
�@
�|�|�|���݂̂͒ᑬ�ٸ�^�B����ŊX���͏[���|�|�|�|�|�|
�@
�傫�������]���ł�
�@
�M����̂͂܂��������ݽ��۹�ĂŁB
���݂�41�s����œK�ȷޱ��T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�i������ײ�ނ�16T�B�@�j
�@
�����܂ŋC�����悭�����ޱ��B
�@
�߰���8000�������ł��̂ŁA�ϋv�����������҂ł��܂��B
�|�|���̑O�ɂ�邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂����|�|�|�|
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/25
24. ���Ȗ����B
�@����̪��ް���y�������ɂ��邽�߂�̪��ް���אg�ɂ����̂͗ǂ������̂ł����A
̪��ް�������������C���ɂȂ������Ƃ͂��`�����܂����B
�����ŁA���t�������������āA��ԂƂ̌��Ԃ߂邱�ƂɁB
�@
Benly50S��̪��ް�́A�����̂悤��̪��ް����̂悤�Ƚð�����тĂ���A�����
̫�������Ď��t�����Ŏ~�߂Ă��܂��B
�Ȃ̂ŁA���̽ð�̌��ʒu����Ɏ����Ă����A�s��̪��ް��������A��ԂƂ̌��Ԃ�
�����Ȃ�܂��B
�@
�����A̪��ް���͂����܂������A���������������B
���t�����̏㕔�́A�y�ʉ��H̫���Ƃ̓����H�̂��߁A������������������Ă���A
�X�ɂ��̓��������́A��ڽ�œ����ɋȂ����H�����Ă���܂��B
�@
����20mm���x���ʒu���グ���������̂ł����A���̈ʒu�͒��x���̋Ȃ����H�̕����B
�@
�ð�삵�āA�̾�Ă����邱�Ƃ��l���܂������A̪��ް���Č��\����������Ă��Ȃ���
�����Ă��܂��A��ԂƂ̊����N���܂��B
��Ԃ̉�]�������炵�āA̪��ް�̌�둤������������ԂɐڐG����ƁA�ň��̏ꍇ�A
̪��ް���ό`���邩�A��Ԃ��ް�Ă��܂��B
�����܂ł��ň��̏ꍇ�B
�@
���傤���Ȃ��̂ŁA20�������炢�����Ă���ϰ�Ŏ��t�����𖾂�����悤�ɁA���̋Ȃ�
���H��ɂ��܂����B
�����ʒu�̌��͏����݂��Ƃ��Ȃ��̂��ި����ײ��ް�Ő���A���߂Ď��t������
�����܂����B
�@
�����Ď��t�����̂��A����Ȋ����B

�@
�ω��̑O��ŁA�����ʐ^���B���Ă��Ȃ������̂ō������܂�킩��܂��A����ς�
�������肵�܂����B
�@
��������Ă̍�Ƃł������A�����Ɏ��Ȗ����̐��E�ł��B
�@
�@�@�@�@���@�ω��O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�ω���
 �B
�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/15
23. �p���[�A�b�v�I
�@����܂ŁA�F�X����ݽ�A�������Ă��܂������A�ō���7�~km/h�i�v�Z��7500rpm�j
�ȏ�͉���Ă���܂���B
�r�C�ʂ��炵�Ă��傤���Ȃ��̂ł����A7�~km/h�܂ł̓��B���Ԃ𑁂��������B
�@
�Ղ�Benly50S�́A�ݼ�݂�12V�ݷ��p�̴ݼ�݂Ƃ������Ƃ͈ȑO�A�����܂����B
�ݷ���Benly50S�ł́A�ō��o�͂�1�n�͂��炢�Ⴂ�܂��B
�ݷ��p�̴ݼ�݂Ȃ̂ʼn��Ȃ��̂��H
�@
�ݷ��́A���ذŰ�A��������A��ð���ΰ��ނŋz�C�����炵�A�_�Ύ����������M��A
��װ���i���Ă���̂��H�H
�@
�������Ȃ���Benly50S�́A��ð���ΰ��ނ܂Ŋ��ɎЊO�i�ł��̂őΏۊO�B
�܂���װ�͏����ŁA���ނɌ����J���Ă܂��B
�@
�����Ŏc��́A�Ѽ��Ă�CDI�B
�@
�܂��ͶѼ��Ăׂ܂������A��������Ɠ������̂ł��邱�Ƃ������B
�@
�c��́ACDI�B
���܂�傫���e�����Ȃ��Ƃ͎v���܂����ABenly�ɂ��Ă�����̂��m�F����ƁA
Benly50S�p��CDI�ł����B
�@
�܂�ݼ�݂̂��ݷ��p�ŁA�d���n�͂��ׂ�Benly50S-------�B
�܂��A�ԑ̻��ނ��Ⴄ�̂ŁA�ݷ��̔z�����g���킯�ɂ��s�����ABenly50S�̔z����
�g�������߂Ǝv���܂��B
�@
���āA�ǂ����悤���ȁB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/11
22. �y�ʉ��I
�@�@�Ђ��ȋx�݂̓��A�܂��܂�����Ă��܂��܂����B
Benly50S�����Ă���ƁA���̪��ް���傫�����B
ر�����Ă��A�[�������肷���āA�ǂ����d�����Ȋ��������܂��B
�@
���ڰ���܂łƂ͌����܂��A��͂茩���ڂ̌y�����ق����B
�@
�Ȃ̂ŁA���܂����B
�܂�������̪��ް�̽�щ��B
�镝�́A��̔@�����������B
�@
�܂��́A�K���ɉ��M�Őؒfײ݂������܂��B
�����ă�3�����ق�ײ݂ɍ��킹�Č������B
�����Ă��̌��Ƀ�6�����ق�ʂ��A�����m���q����悤�ɂ��邱�ƂŐؒf���悤�ƁB
�@
�������A������d�����ق��g���Ƃ͂����A���\�̌������ŁA�ʒu������������
�Ȃ��Ă��܂��A�����m���q��������q����Ȃ�������B
���ǁAƯ�߰�Őؒf�B
���̂��ƁA���ߏ����f���ڂ݂��A�ި�����ް�ŁA���`�B
�Б������ł����A���ɂ����Ӱ�ށB
�@
�����Е��́A�ި�����ް�ŁA�ŏ�������ؒf�A���`�B
(�����Ƃ������̂ق��������ł��B�ި�����ް���I�I�j
�@
�����O�Ɖ�����͂���Ȋ����B
�@
�@ �@���@
�@���@
�@
���\�y�������ɂȂ�܂����B
�������A���Ƃ���Benly50S������̪��ް�́A�[����Ɍ��\β�قƂ̸ر�ݽ���傫���A
̪��ް���щ�����ƁA̪��ް�����������Ȃ�܂��B
�i�ʐ^�͏ォ��B���Ă�̂Ŗڗ����Ȃ��j
20�������x�ł����A̪��ް��������K�v������悤�ł��B
�@
̪��ްڽ�i����j�ł���Ă݂�����ȁB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/9
21. ���傱���傱�ƁB
�@�@���IҰ�����t���A�C���悭���čō������ݼނ��s���Ă���ƁA6000����������オ
���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�@
�z���W���������܂������A���Ȃ��B
�@
��[�B������B
�@
��̔@���A
�@�@�@��������|���B�@���ɖ��Ȃ��B
�@�A�@�����ߊm�F-------��肠��B
�@
����ނ��A�����߂���ۂ���ƊO��܂����B
�܂��A����ߑ��̺��ނɍ������ޒ[�q���A�ΐF�B
�@
�����ɻ����߰�߰�Ŗ����A�O�̂��߂ɺ��ނ̐�[����A����߂����t���܂����B
�@
����Ɓ@--�Ȃ��Ă��Ɩ�����Ԃ�����8000���������悤�ɂȂ�܂����B���IҰ���ł����B
�@
����ϓ_�Όn�͑厖�ł��I�I
�@
���Ɖɂ������̂ŁABenly50S�̶��тňȑO����ر�̻���ڰсH������Ă݂܂����B
Benly50S�́A�ڰѕ��ւ̎x���ɂȂ��ڰт�����܂���
����̪��ް���ڰт̊Ԃɏo����O�p�̌��ԁ@�u���̎O�p�n�сv�����邵�B
�����炻�����ڰт��ۂ����̂�t������ǂ����ȂƁB
�@
�ڰэނ́A���h�������Ȃ̂ŁA��Ђ̃�13���߲�߁B
�߲�߂��A���[��@���Ēׂ��A���Ă̌����J���Ċ����B
�@
�F�͍��̏�Ԃ��ƍ��B�@������ر̪��ް���͂������肵���ꍇ��--------�Ƃ������ƂŁA
ð�߂�\���Ă܂��͍��ɁB
�@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ȋ����ł��B�@
�@
Benly50S�̼���ڰѕ��ɂ́A�E��3�ӏ��A��2�ӏ���M6�˂���������܂��B
CD50�ł́A�T�C�h��ް�̎��t�����Ă��ȂȂ̂ł��傤���A���̌���̪��ް�̎��t��
���Ă��q���܂����B
���t���Ă͌��܂������A�ޯ��ް��ڰт̑����ɕ����Ă܂��B�@
�P�Ȃ�ð�ɂ���-------�@�B
�����Ƒ�������Ηǂ������B�@��20�ȏ�ł��ǂ����������B�@�@���ȁB
�@
�ł����ꂩ��A��ٷ����ݸ�t������A�F�X���Ƃ��ɖ��ɗ����̂ƐM���Ă܂��I�I�I
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/4
20. �^�R�I���[�^�[�B
�@�@����Ƃ̂��ƂŁA��Ұ������B
�@
�ݼ�݂�F�X�M�鎞�ɁA����ς���Ұ��������ƕ֗��ł��B
�ʂ�50���������ق̐��x�͕K�v�Ȃ��A������èݸނ�ς����Ƃ��̕ω������邽�߁B
���Ǒ��ΓI�ȕω��A��]�����オ���������������������邽�߁B
�@
�G�������ȯĂŒT���܂���܂����B
�����@�B�����ق����Ɍ��܂��Ă܂����AҰ���ޱ����Ұ����2���~���炢�B
�Ȃ̂œd�C���̈�Ԉ������ؐ���Ұ�����w���B�@
2980�~�@�@12�u�p��13000�������܂ŕ\���B
�@
�{�������������܂����B
�@
Ұ��������ƁA�C�����ύX�̽����͖����B
�܂��A���ؐ��Ƃ͂����A4Mini���X�Ŕ����Ă����̂œ��R4�����P�C���p���낤�ƁB
�@
�܂���Ұ���̏Ɩ��pײāB
����́A��߰��Ұ����ײēd�����Đڑ��B
�ł�����ނ́A�������{�ł͏��Ȃ��S�̂����łł����������߂̂��́B
�@
��������Ұ���d���B
�@��Ұ���ɂ́A+�A-�@�ɉ�������ٽ���E�����ށ@���v3�{����܂��B
�@+�@-�@�́A��Ұ���̐j�������߂̂��̂ł��B
�@+��-�ͱ���ذ���番��B
�@
�ƁA�����܂ł͂Ƃ��Ă������B
�@
�Ō����ٽ�i��]���j���E�����ނ́A���Ư��ݺ�ق́@+�@�Ɍq���Ƃ̂��ƁB
�ŁA���́@+�@�ɺ��ނ����ڑ����Aܸܸ�̴ݼ�ݽ��āB
�@
�ƁE���E��E���I�I�I�I
�Ȃ�Ɖ�]���������ݸނ�4500�������|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����A����]����4�{���炢�B
�ȁ[��ł��ȁ[�B�i���ؐ��ł��A�Q�Ă��|�|�|�j
�@
�����Ƃ��čl������̂́A
�@�@�@�Ȃ�ɲ�ނ��E���Ă���B
�@�A�@����i�������A�����������j�@
�@
�@ɲ�ނ��E��Ȃ����߂ɱ���ذ���� �{-�@�d����������̂ł����A�m�F�̂���
�@�ޯ�ذ���璼�Ł@+�@-�@������Ă݂Ă����ʕς�炸�B
�@��ނ͒�R����B
�@
�A���ق�P��ƴݼ�݂̉�]�̏㏸�ƂƂ��ɁA�j���オ��܂��B
�i����������10000������---����͂���Ŗʔ��������|�|�|�j
�Ȃ̂ŁA�{�̂̾�èݸނ����������H�@���ʌ����H
�@
�d�C����Ұ���ɂ́A�_�̕��@�ƁA�C�����ɂ���Ď�ނ������;�èݸނ��ς��܂��B
4�����̒P�C���́@���k�������c�����|�C���z�C�@�̍H����
�@
�@�@�O�x�@�@�@180�x�@�@ �@360�x�@�@�@ 540�x�@�@�@0�x�@ �@180�x�@ �@360�x�@�@ 540�x
�@�@���@�@�@�@�@ -�@�@�@�@�@�i�_�j�@�@�@�@�@�]�@�@�@�@�@���@ �@ �@-�@�@�@�@�@�i�_�j �@�@�@-
�@
����Ȋ����ł����A��ݸ���āi�ɕt��β�فj���߯����ߕ���1�B
���ꂪ�ݻ���1��]�Ɉ��ڋ߂��邱�Ƃœ_�Ύ��������m���Ă���̂ŁA0�x��360�x��
�_�Ύ��������m���܂��B
�������Ȃ��甚�������m���āA�u���̏㎀�_�͈��x�݁I�v�������ȉ�H�͂���܂���B
���̌��ʁA0�x��360�x�i�|�C�I�����j��2��_���Ă܂��B
���ɖ��Ȃ��̂ŁB
�@
���ꂪ�Ѽ��Ă���_�Ύ�����������߂��ƁA��ݸ���Ăɑ��ĶѼ��Ă�1/2�̉�]��
�Ȃ��Ă���̂ŁA�ق�Ƃɓ_���K�v�Ȉ��k�I�����ł̂ݓ_���܂��B
�i�ł�720�x��360�x�Œ�������̂ŁA�����Ȓ�����������j
�@
�����[���B
�@
����̒�����Ұ���́A�������ݸނ�3�{�߂��������Ă��܂��B
4st�P�C����Benly50S�́A��ݸ1��]����ٽ�M��1��B
��ٽ�M����3�{���Ă���킯�ł����A����Ȍv�Z��K�v�Ƃ���ݼ�݂�------�Ȃ��͂��B
�@-------�@�p�r�s���ł��B
�@
�Ƃ������Ƃŕ������o��B
�@
�������AҰ���į���ݸނ́A��҂��Ă���A���傤���Ȃ��̂ŁA��҂�ϲŽ��ײ�ް��
����т���ыN�����ĕ����J�n�B
�@
�ƁE���E��E���I�I
���������̂Ƃ���ŁA��ײ�ް�ɗ͂�����߂��AҰ���̶�������Ă��܂��܂����B
�@
�@�@�@���[�Q�����B
�@
�߂����ɕ������A����������Ɓ@�|�|�|�|�|�|�|�|�@����܂����B
�@
��]�\�������p�̖��i�K����ح�сB
�@
�ݼ�݂��|���A��ح�т�ϲŽ��ײ�ް�Œ�������Ɖ�]���������Ă����܂��B
Benly50S�̱����ݸނ͂�������1500�������ʂ��낤�Ə���Ȏv�����݂Œ��������B
���ǁA��ԍ�����]��������Ԃŏo�ׂ���Ă����悤�ł��B
���������B�@�ǂ�ȎԎ�ɂ��g���܂���B
�@
�@�ق�ƂɁ@�u���I�@Ұ���v
�@
�܂���ٽ�p�̺��ނ́A��ق�+�Ɍq�������A����َ�������ĂɌq�������A��]���A
���������͓����B
�H�H�H�H�ł����AҰ���ð�̎��t���{���g����ٽ�p�̺��ނ��q���܂����B
�i���ނ��Z���ėǁB�j
�@
���āA���ꂽ���̏C�����ǂ����邩�B
���͖����Ȃ̂ŁA���U��ΰѾ����ɍs���A���ٔ��w���B
���̌a�ɍ��킹�Đؒf�i�ƌ����Ă��AƯ�߰�ŏ������܂�܂����j�AԽō��A
���Ƃ��̍ق𐮂��܂��B
�@
�����āA���ق��͂ߍ��ݶ�҂𐔉ӏ��s���A���Ƃ���ư�ð�߂Ŋ����܂����B

������Ȋ����B


�������ݸށi1500�������H�H�j �@�@�@�@�@�@ ���������������Ƃ�
�@
�ŁA�����m�F�B
�@
��Ԍa����1���A2���A̧��ٌ�������l�����Čv�Z����ƁABenly50S�̍��̎d�l�ł�
4���@40km/h�̂Ƃ���4300�������ɂȂ�܂��B
���ā|�|�|�|�B�@
�Ȃ��40km/h��4400�������I�I
Ұ���̌덷����������̂ŁA�Ђ����ڂɌ��Ă�1�����x�̌덷�͂���̂ł͂Ȃ�����
�v���܂����A����+���ȉ�����Ұ��ł��B����Ȃ���ł��傤�B
�@
�ݼ�݉�]�𑊑ΓI�Ɍ���Ƃ��������̖ړI�͒B���ł������ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/11/3
19. YSS ر���B
�@�@ر����̐��������������������Aر�̍Ō�̎d���A���܂̻���ݼ�����B
�@
����ݼ�݂Ƃ����@���ݽށAWP�AQuantum�|�|�|�|�|�F�X�B
�ł��A�܂����ꂼ�ꂪ�A�Ƃ��Ă������B
�����i���\�j�����߂邽�߁A�ļ�ق��ʏ�̏����i�ɔ�ׂĊȈՓI�ŁA1�`2�N��
���ްΰق��Ȃ��Ɛ��\�͈ێ��ł��܂���B(��ڰ�����߰�������j
����ɂ����̵��ްΰق́A����߂ɔC�������Ȃ��̂ŁA�����ł��B
�܊p�A�������̂��Ă��A���ްΰق��邨�����Ȃ�������A���\�͂����ɏ����i
�ȉ��ɂȂ����Ⴂ�܂��B
�@
���������Ȃ��B
�@
�Ȃ̂ŵ�Ű�̏������ł��Ȃ�A�c�����������Ƃe�y�q400�q�q�r�o���ȁB�@
�m����������Benly50S�͐��\���ϋv�����d�����܂��B
�@
�ŁABenly50S�p��ر���́A���Ɍ��߂Ă��܂��B
�@
YSS�@RD220-340P�@TOP UP340�ł��B�i���b�L�@5000�~��ł��j
������Top��Bottom�̌��Ԃ�330�����B
10�����オ��ɂȂ�܂����A1G�ł����۰�ނŒ������܂��B
�@
YSS�́A�����m�����ނ̉�ЁB
�ŋ߁Aڰ��ւ̎Q��������Ă���A����ݼ��Ұ���̋Z�p�҂����������ĊJ����
���Ă���Ƃ��A���Ă��Ȃ��Ƃ��B
YSS�́A�m�荇���ł��t���Ă���l�͂��Ȃ��̂ł����A�ŋߌ��\����Ă���炵���A
Ninja�p������悤�ł��B
����A�ǂ����Ninja�ł��|�|�Ȃ�čl���āA�܂����ײ�قƂ������Ƃ�WebShop��
�w�����A�{�����t���B
�@
�@
�����J���Č���ƁATop��Bottom�̎��t�����a����10�B
Benly50S��Top�̂݃�12�Ȃ̂ŁA�t���̓��a��12�̶װ�Ɏ��ւ��Ȃ��Ƃ����܂���B
�@
�ŁA�܂��͓��a��10�̶װ���O���A
����ǂ�����Ă͂����̂��ȁ[�Ǝv���āA�l���܂��������10�̖_��˂�����ŏ���
��ظ����Ƃ͂���܂����B�i������Ɣ��q�����B�j
WD40�𐁂��ē��a��12�ɓ���ւ��B
�@
�������t�������m�F�B
�@
�����������͔ėp�̂��߁A���̎��t�����̒����i���t�����j���Z�߂ɂł��Ă��܂��B
�Ă̒�A�������́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�����@�@�@20�����@�@�@�@24�����@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@YSS�@�@�@21�����@�@�@�@20����
�@
�Ȃ̂ʼn�����β�ّ���2������ܯ�������Ď��t�������B
�@
���ʁA����Ȋ����ł��B
�@
 �@���@
�@���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@������
�@
�@
�@�@�@�@ �@
�@
�@�@�@�@�@�i������ƁA���ڂ̊��������܂����A���Ȏ咣�����イ���ƂŁj
�@
0G�ł́A��Ԃ�̪��ް�̌��Ԃ��L�����Ă��܂����A1G�Œ��x�ǂ��Ȃ�܂��B
�@
����Č���ƁA�т����范�ρI�I
�@
��Ԃ̕ω��́Aر���̓����ł͂Ȃ�ر�S�̂̍�������������ƁB
����܂łͽ�߰�ނ������Ķ��ނɓ���ƁA�u��Ƭ��Ƭ�v�@����銴���ł������A�������
�@�u��ƭ�v�@�ʂň��S���ċȂ���܂��B
���S�n�౽̧�Ă̌p���ڂ��̓ʉ��ł����܂����A6�~km/h�ȏ�ł����肵�Ă��܂��B
�@
���ʑ�ł��B
�@
�����̻���ݼ�݂́ABenly50S�iS�ͽ�߰ƌ����Ӗ��̂悤�ł��ˁj��搂��Ă��銄�ɂ�
����ݸށA����߰���ɗe�ʕs���Ł@�u���܁v�B
5�~km/h���o���ƁA�����t���ė���Ȃ��Ȃ�܂��B
�i�u30km/h�ȏ�o���Ȃ��������v�Ȃ�Č��������ȓ˂����݊��فB�j
�@
Benly50S�ɏ���Ă���F����͖w�ǂ�5�~km/h�ȏオ�����̂͂��B
�Ȃ�A�ݼ�ݘM������A�܂����ł��B
���ẮA��ٔS�x�Ƶ�ٗʂŒ����Aر�͌�����Benly50S���ς��܂��B
�i����ł��S���łU�O�O�O�~���炢�B�j
�@
�@
���炭���悵����A��Ű�i75�����j�́A����ݸނ����۰�ނ�5�i�̿�đ�����3�i�ځB
���t�@�Ղ́A55�����Ȃ̂ſ�đ�����2�i�ڂł��B�i1�i�ڂł����������j
�قڏ��S�҂̌Ղł��A���̕ω�������炵���A�u��߰�ޏo���Ă��|���Ȃ��v�ł��ƁB
(��߰�ޏo�����߂���Ȃ����I���Ė����H�j
�@
YSSر���̐��\�́ABenly50S�ɂ͏[���̂悤�ł��B
�@
���Ƃ́A�ǂ��܂őϋv���i����ݼ�ݐ��\�A�h�K�A��٘R��@etc�j�����邩�ł��ˁB
�@
�@
���j��Ű���w����������ݼ�݂ɂ́A���۰�ޒ����p��������t�����Ă܂���ł����B
�@�@�ł��AΰѾ������Ŕ����Ă܂��̂ŁA������ق̌a���m�F���čw�����Ă��������B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/27
18. ر����@�M��܂� #2
�@ر��̪��ް�́A��͂菭���������������āA���ް���[�ōēx�����Őؒf�B
�܂��A����Ȃ��Ȓ��x�ɂȂ�܂������A���x�����đ���̪��ް�̑傫�����~�B
���傤���Ȃ��̂œD�������ڱ������������ł��������ؒf�B
�p���ި�����ް�ł��ア�[��~���E
�@
�ŁA����Ȋ����ł��B
�@


�@
���@ر���X�ɶ�ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���ł����Ă��B
�@�@ �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@
ر���Ƃ��́A��ر���͂����Ă������ߋC�Â��܂���ł������A��ر������ƁA
�����Z�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�ݸ�ق��ۂ�������Ă����t����A����������Ƃ͌��h���ǂ��Ȃ邩������܂��A
����Ȃ̂��ǂ����ȂƁB�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/14
17. ر����@�M��܂�
�@ر����́Að����߂��������A�����������肳�����̂ł����A���̕�ر̪��ް��
���炭����������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@
���傤���Ȃ��̂ŁA�K���ɉ��H���܂����B
W.W�U���R�̵����݂����Ȃ���̪��ް�ł܂��ǂ������̂ł����A��͂肱��
̪��ް�ɂ́A��Ԃ��ؚ������Ă�����Ʊ����ݽ�ł��B
�܂��ABenly50S��̪��ް�́A�����т����Ƃ�����Ԃ����S�ɶ�ް����悤��R��������
�Ȃ��Ă��āA����ނ������Ă���Ƃ��́A��Ԃ̏㕔��̪��ް����Ԃ̌��Ԃ��O������
�悤�Ɍ����܂��B
���ꂪ�@���\�@�Ԕ����Ȋ����Ł@�Ձ@�̋C�ɓ���Ȃ��Ƃ���B
�@
�����ŎO�����Ɍ����Ȃ��悤��̪��ް��ر�����������ި�����ް�Ő���A�p��
�₷��ł��[�����[���B
���ʂ���B
 �@
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@
��[�́A�����p���ۂ�������ǂ��Ȃ邩�ȁ[�Ǝv���Ă���Ă݂܂������A��͂��Y���
R��t�������������悤�ł��B
�@
�����Ȃ�ƁA����̪��ް���C�ɂȂ�Ƃ���ł����A����̪��ް�͒Z������Ɣ@����
�J�̓���������Ԃ̐����˂������܂��B
�@
�܂��A�l�q�����Ȃ���A����������čs���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/14
16. ������o���K�̎K���
�@
�@����ȯĂŕK�v��Ҳݷ���Ă��ݸ����߂F�B
����ƁA�ݸ����߂́A�ݷ����A���ׂ����p�̂��̂�500�~��2�·��t�Ŕ����Ă܂����B
���̼���߂ɂ́A�ޯ��װ�����E��500�~�Ŕ����Ă���A���킹�čw���B
�������AҲݷ���ẮA��͂菃�������S�B
�@
�Ƃ������ƂŁA����߂ɏ����i�𒍕��B
�@
������2����B
�@
�͂��܂����B
�ݸ����߂͂��̂��邭���鷰��ް�����ް�ł���ȊO�͂�����̍��B
�@
�ݸ�Ɏ��t���Ă݂܂��������Ȃ��|�|�|�|�|�|�|�|�|��������܂����B
�@
�ǂ����ݸ����߂̎��t���p�x���ݷ���Benly50S�ł�90���Ⴄ�炵���A����ް��
���������Ă��܂��܂��B
�@
�Ղɂ��̂��Ƃ�b���ƁA�u������v���ƁB
�܁A�����Ȃ����C���Ȃ��̂ł܂��������B
�@
���t���Ă݂܂������A�܂��܂��B
�����A������500�~�̷���߁B
�����ł�����݂��R��Ă��܂��B
�@
���傤���Ȃ��̂ŁA�����̔j������߂��缰ٺ�т����O���ė��p�B
��݂̘R��͌���܂����B
�@
Ҳݷ��́A�������ɏ����A�������Ȃ����t�������B
�@
���̌�ɂ������̂ŁA����܂Ō��Ă������d���ٓ���ð����߂̌y�ʉ������{�B
�@
ð����߂�DS2�֊قōw�����A�ð�͎莝����1.5������ДŐ���B
�ؼ��ق�ð����߂́A���ݗp���Ƃ������炢�傫���A��ï�Ƃ��������ł����A
����ł���Ə����y�������܂��B
�@
�܂��ڰт�ر̪��ް�̊Ԃ̋�Ԃ߂Ă�����Д��O���܂����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/10/09
15. �g����o���K
�@���с[��|�|�|�|�|�|�ł��B
�@
�{���A�v���Ԃ�ɒ��t�@�Ղ�Benly50S�Œփ��C�������쁨�������A���200����°�ݸނ�
�o�������̂ł����A����������ƂŋA��Ƃ����Ƃ��ɁA�����Ȃ����Ƃ������I�I�B
���Ƃ����Ă��Ƃ̌��ł͂Ȃ��ABenly50S�̌��B
�@
�����ł��BBenly50S��Ҳݷ��́AON�ł������Ă��܂���ԂŁA���߂Ɍ������悤�Ǝv����
�����̂ł����Z�����Ɋ����Ă��̂܂܂ł����B
�@
�����A�ǂ����̷ެ��߂ŷ��������Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B
�����ɷ����g�����L���̂������Ƃ܂Ŗ߂�A���ꂩ�緰��{���Ȃ���^�]���܂�����
�����炸�B
�@
�A��āA�u���Ăǂ��������̂��B�v
�@
��߱��������Ή��̖����Ȃ������̂ł����A�Ղ̵����������A����1����
�t���Ă��܂���ł����B
�ʏ�Ȃ璼���ɽ�߱���삷��̂ł����A����͂Ȃ����Y��Ă܂����B
����B
�@
�Ƃ͂����A��邱�Ƃ͌��܂��Ă��āu�����v�B
�@
���ŋ��p���Ă���̂́A�ݸ����߁A��ү����ް�A�ñ�ݸ�ۯ��B
�@
�Ղɂ́A��үĂ͵������~�肽��K����Ŏ��Ăƌ����Ă���A�X�ɽñ�ݸ�ۯ���
�S���ƌ����ėǂ�������h�~�ɂ͖��ɗ����܂���B�i���x������Ȃ��j
�Ƃ������Ƃ���ү����ް�ƽñ�ݸ�ۯ��́A�͂����Ă��܂���OK�ł��B
�@
����2�{�ɂȂ�܂����AҲݷ�����������\�肾�����̂ŁA���Ȃ��B(�Ղ��[���ς݁j
�Ƃ������ƂŁAҲݽ������ݸ����ߌ����ōs�����Ƃɂ��܂��B�i�͂����Α����̌y�ʉ��j
�@
�������A�����ݸ����߁B
�����Ȃ����ƁA���������j��̂݁B
�@
���i��ׂ�ƁA������
�@�@Ҳݽ����i���t�j�@2310�~
�@�@�ݸ����߁i���t�j 3997�~
���v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 6307�~
�@
��������߂��O��Ȃ�������ݸ���������ꍇ�A����߂݂̂ŗǂ��͂��̏o��A
����ߕt���̶���ݸ8000�~�߂��ɒ��ˏオ��܂��B
---��ɔ����Ȃ���A-----
�@
�T�d���ݸ����߂�ϲŽ��ײ�ް����ϰ�ŏ������j�Ă����܂��A
�@
30���قǂ����āA���Ƃ�����߂̔j��ɐ����B����߂��O��܂����B
����ŁAҲݽ����i���t�j���ݸ����߁i���t�j �݂̂ł����܂��B
�@
�����A���i�𒍕�����A�Ηj���ɂ͓���ł���͂��B
�@
�������@�u�����Ȃ������̂͵�Ű�v�ł��̂ŁA�����́A��Ű����------�B
�|�|�|�@�������ł��B�i��B�فj�|�|�|�|
�@
�����°�ݸނ̋��P�B
�@
�@�@�s��́A�݂����璼���ɒ����Ă����܂��傤�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/9/29
14. �܂��܂��������� #3
�@��O�e�B
���̨װ����߂�����܂��߶�߶�d�l�ɕύX�B

�@
�����O�́A�P�镔������������邩�S�z�ɂȂ邭�炢�\�ʂ������ނł����B
��������߶�߶�߂���̂���_�ł����A�܂�OK�ł��B
�@
���́A���ް�̎��t�����Č����B
�悭�A���ް�ɒ��F��������t�����Ă̏����牺�Ɍ������Ē����Ă��鵰��
������܂���ˁB
����͗��^�����������ް�ƈꏏ�ɂ��炤���Ă�ůĂ��K�тāA���̎K�����ް��
����Ē��F�ɂȂ�����������̂ł��B
�@
�����ŁA���ڽ��۰�ޯ�ܯ����@�{�@���ڽ���ā@�����ް�ێ��B
�܂��܂��ł���B
�܂��A���ް���K�т�ΈӖ�������ł����B
�@

�@
��������---�ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/22
13. �܂��܂��������� #2
�@��ײ���۹�Ă̌����ŁA��߰�ނ��m�ۂł��A�܂��܂��������¶��т��Ă܂��B
�@
���r�C�ʎԂ́A�ݼ�݉��x�A�C��Ȃű����ݸނ����肵�ɂ����X��������A���̓s�x
�����ݸނ��������Ȃ�܂��B
�Ƃ��낪�A�o�b20�̱���ٽ�ح��́AϲŽ��ײ�ް�ʼn����߁B
���̂��߁A�����ݸޒ������ʓ|�ł��B
�@
�����ŁAC.F.Posh�̱����ݸޱ�ެ�Ľ�ح����w���B�i1000�~������ƁB�j
������ح����O���Ē��̽���ݸނ����̂܂g���Č������邾���B
�����ڂ͂���Ȃ�ł����A��͂肢�ł���ݸނ������ł���͈̂��S�B
�@
 �@������ٽ�ح������B�@
�@������ٽ�ح������B�@
�@
�����C�ɂȂ����Ƃ���ŁA�C�ɂȂ��Ă������ނ����ݱ�ެ����ڰĂ������B
�w��������K���炯�ŁA�Ȃ�Ƃ������������Ǝv���Ă��܂������A����߂̂��̂�
2��2000�~�ȏ�B�@�@�����B
�����ŁA��������ڰĂ���肵�A���������B
������ڰẮA���Ė����ł����Б��P�Q�O�~�B�@������ү����Ă���܂��B

�Ƃ��낪�A��ڰĂ��Y��ɂȂ�ƁA���߂Ă���ůāi�ʐ^�̔��Α��j�̎K���ڗ����Ă��܂�
�܂����|�|�|�|�B
�@
���ƁA��߰��̎K�����ꏏ�ɂ��܂����B
(�����̒���ƂɂȂ肻���ł��B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/21
12. �܂��܂��������� #1
�@�@����3�A�x�A�܂��͎ԌɁi���������H�j���̫�тł��B
���̉�������A�����䖝�ł��Ȃ���ԁB
�Q�~4�̖؍ނ��w�����A���̓���ւ��ł��B
�@
1���ŏI���͂��������̂��A��͂���N�g�ɂ͏��Ă��A�Ȃ�₩�����^�o�R��
�z���Ă鎞�Ԃ��������āA����2���|���Ċ����B
�����āA�d�x�̍��ɂƂ̐킢�ɓ˓��B
�@
�o���オ���������́A�O���͐̂̂܂܁B�@
���g�͂Ƃ����Ƃ�͂�̂̂܂܂ł��B
�@
�܂��ADucati��Ninja�̏����ł�����B
�@
������3���ځB
Benly50S�̉����ł��B
�@������A���ɂ����܂����܂��̍�Ƃł��B
�@
�ŏ��ɂ�����̂́A̭��ײ݂ւ�̨������t���B
KIJIMA��̨����������āA���t�����s���܂��B
�@
���ʉ��������A�������������ł��B

�����F��̭��̨����A�����܂��H
�@
�������������A���ǻ���ް�́A�ڰт���Ԃ̌��Ԃ߂����Ƃż��ް�ł����ݽ��
�����Ȃ����̂ō��ɓh��Ȃ����܂����B
�����A�^�����ł͖��C�Ȃ��̂ŁA���ނ̳�ݸ�ϰ��𗼑�������B
�@
����Ȋ����ł��B
 �����ꂪ�A�����Ȃ�����
�����ꂪ�A�����Ȃ�����
�@
���ƁA��ײ�ޱ�����݂�15T����16T�������Ă݂܂����B
�����ݑ���F�X�M����O�ɁA��ײ�ނ̎������Œ肵�悤�Ǝv���A���肬�萡�@��16T��I��
�i17T������܂����A�����������繰��ɓ����肻���������̂Łj
���̌��ʁA
�@�@�@ɰ�ف@ F13-R42�@���@3.23
�@�@�@�w�����@F15-R41�@���@2.73
�@�@�@����@�@ F16-R41�@���@2.56
����܂łɑ���6.7�������Aɰ�ٔ��23�������ł����A7�~����/��(7500rpm)
�������y�ɏo��悤�ɂȂ�܂����B(8�~km/h�͖����j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/16
11. ���������
�@�ՂƐe�q�̉�b���ABenly50S���݂̘b�ɂȂ�܂����B
�՞H���A�uر��Ԃ��ڰт̌��Ԃ��傫�����v�@�ł��ƁB
�@
�m����Benly50S�́A�ޯ��ް��ڰтŁA���h��ر̪��ް�Ƃ̊ԂɁA�u���̎O�p�n�сv
������܂��B
�@
�����Ă݂�Ίm���ɁA���ꂪ���邨�����Ŏ�����������܂��B
�@
�����ŁA��Ű�l���܂����B
�@
�����ꂻ���ɂ͑�����ٷ���ݸ����������̂ł����A���̊ԂȂ�Ƃ��Ƃ�B����
���Ȃ��Ⴂ���܂���B
�@
�ŁA���ʱ�Д@����0.5�����@�ŏƂ�B������邱�ƂɁB
�@
�܂����ڰт̌E�݂�R�ɍ��킹������ްقœK���Ɍ`�����߁A��Д��������B
���������́A�����h�~�̂��߂ɂ₷����߰�߰�|�����܂��B
�@
�ق���ڰтɎ��t���B
(Benly50S�͌��\�ڰтɃl�W���������Ă���̂ŊȒP�B�j
�@
���t����Ƃ���Ȋ����B

�@
�ȁ[�A���R�����悤�ȵ������ۂ��Ȃ����Ⴂ�܂����B
�i̪��ް�̍Ō�̔��肪�A�R����үĂ��ۂ��j�B
�܂��A�\�z�ɔ����ďd�����ȕ��͋C�ɂȂ�܂����B
�@
���ꂩ��A�������y�������o���悤�ɂ��Ă݂܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/8
10. ���������`���
�@�܂��́A���h���H���̖����|���B
Benly50S�́A���Ⴋ���Ⴋ���̂��̑��̵����Ƃ͈قȂ�A���ڽ�iȲ���ށH�j�ŁA
�ݼ�ݔ����o���ł��B
�Ƃɂ����������ƂɁB
�^�J��ܲ���łЂ��ȋx���A�ݼ�݁A�~�b�V�������---�Ƃɂ��������|���܂����B
���̌��ʂ��A����B
 �����ꂪ�����Ȃ�����
�����ꂪ�����Ȃ�����
�@
���Ď��ł��B
���͂���Benly50S�A�����ʒu���Ʒ����т��ï�߂ɒu�������ז�����̂ŁA���t��
�p�x����ɐQ�����Ă܂����B
�ł�-----�B�@
�����ڏd���ł��B
�Ȃ��Ȃ��̏������Łi�Ղ́A������������Ɏg���܂�------�jSIFT UP���̕������B
�����ʼn|�����߶�߶���߂ɕύX�B
�������ƁA�����悹��ʒu������܂łƂ͈Ⴄ�O���ɂȂ�̂ň�a��������܂������A
�Ղ��@�u���v�v�Ƃ̂��ƁB
���łɴݼ�݉E���������|���܂����B
�@
�@����|���邾���̂��̌��h���H���ł͂���܂����A��͂��߲�ĂɂȂ镔�i�́A�K�v�B
�@
�@�Ղ���A�������������悤���Ȃ��`�B
�@
���̂��ƁAͯ��ײČ����̔z�������B
�܂���ײĂ̌�̔z�����ނ��܂Ƃ߂��߰�����邽�߂ɱ�Д�ײĂ��O����50����
�قǏo��ð��B
�z�����̂ͱ�ЂŶ�ް������Ď��t���܂����B

�Ƃ���ŁA����Benly50S,�w�����̎ʐ^�ɂ���悤�ɁA��Ű����ނ����\�K�тĂ܂����B
���ɽ�т̱��ް�̐^���̕����́Aү���ʂ�z���n�������ɂȂ��Ă܂����B
�@
���̕����́A��Ű����ނōł��Ȃ����͂��|���镔���ŁA���ɍ�ү��ł͋��x�܂�
�オ��Ȃ��̂ŁA�w������������̏��������Ă܂����B
�@
�������A��Ű����ނ̐V�i�ׂ�ƁA1�{��1���~-------�B
�����ŁA����2�����ԁA����ȯĂŒT���܂���A���x�̂������Â���ɓ���܂����B
�͂���̫���́A�Ȃ��Ȃ��̗Ǖi�ŁA�������͊����A���̕����ɂ͑���������
�K�͂���܂����A�C�ɂȂ�Ȃ����فB
 ���E�������肵�����Õi�B���x�ǁB
���E�������肵�����Õi�B���x�ǁB
�@
�����A̫����ق��������A�K�����ŵ�ق𒍓��B
���������ı�������ނ�h�����Ď��t���B
����ň��S���ď��܂��B
�@
���ł�����̪��ް���h���������Ă��镔�����������̂ŁA�ēh�����Ċ����B
�@
�@�\�����Ŏc��́A�ӂ�ӂ��ر���B
�����ڏd���́A���炭���������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/7/6
9. �����ڏd���H����
�@�@�fOver60km/h��ۼު�āf�����ǁA�����Ȃ��܂I���B
�@
�@�Ȃ̂ŁA�����ڏd���̕ύX���s���܂��B
�@
�@�܂��́A�Ԃ��ׯ�ܲ����فB
�@�������������邽�߂�ܲ�ׂ�ƌ��\�Ȓl�i�B
�@�ǁ[����[���ȁ[�B�i�ł����B��Ű�̋C�܂���H���j
�@
�@���ǁA����قɓd���p�̕ی�ΰ���t���Ċ����B
�@�܁A�����Ȃ�܂����B
�@
�@
�@�����āA�܂��߂ɋC�ɂȂ��Ă����A�������ܰ�ݸ����߁B
�@�Ղ����ɐ���A������ނ��グ�Ȃ��ŃM�A����ꂽ�u�ԴݽĂ��o�����Ă��܂��B
�@�ޱ������O�ɻ�����ނ��グ������̂ł����A�������o���Ȃ��̂����S�ҁB
�@���̲ݼ������߂����t���܂��B
�@
�@������ނ̽�������o�Ă��麰�ނ͍�/���ŁA�m���ɂ��̺��ނ��]���Ă܂����B
�@���̺��ނ�LED���߂́@+�@���q���@-�@�𱰽�����̂ł����A�_�������B
�@
�@�H�H�H�@
�@
�@�Ȃ��ȁ[�B�@�������Ă�̂��ȁ[�B
�@�w�������Ƃ��́A��тɕt���Ă��黲�����ܰ�ݸ����߂�ƭ�������߂Ɋ�������
�@�������Ƃ��l����ƁA��������������Ă�̂��ȁ[�B
�@�Ȃ�ĐF�X�l�����̂ł����B
�@
�@���Ǎ�/���̺��ނ��@-�@���ȁ[�Ǝv���āA��/���̺��ނ�LED�́@-�@��t���Č����Ƃ���
�@-----�������B
�@̪�پ�̂̍l���Ȃ̂��A���������Ă�ܰ�ݸނ��_����������l�ɂȂ��Ă�̂��ȁH
�@
�@�܂��������ł��B
�@
�@�ƌ������ƂŁA����̲ݼ���������ڰĂɂ�������������Aگ�ނ����߂�lj��B
�@���Ȃ݂ɃL�W�}��LED�ł����A����Ȋ����ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@گ�ނ�������ށA��ذ݁i������2�Ԗځj��ƭ���فB
�@گ�ނ͌��\�Ȕ��F�œ_�����Ă���̂ł����A��Ȃ̂Ŋ��ق��Ă��������B
�@
�@������A����������Ղ́A�@�u�����A���肪�ƁB�v�@�ł����B
�@���ꂾ�������I�I�B�@
�@
�@�܁A�������B
�@
�@�Ƃ���ŁA�Ղ�Benly50S�́AײĂ������߂ɕύX����Ă��܂��B
�@���̂��߁Aɰ�قłͽ�߰��Ұ���ƈꏏ�ɂȂ��Ă���ͯ��ײ�ʳ��ݸނ̒��̔z����ײ�
�@�̌�ŁA�ނ��o����ԂƂȂ��Ă��܂��B
�@
�@���̔z�����������肷�邽�߁AײĈʒu�������O�ɏo���AײČ�ɔz���ޯ����u��������
�@�ȁ[��Ďv���Ă��鍡�����̍��B
�@
�@���ƁAβ�قƽ�߰��̎K�ю����@�Ձ@�����܂����B
�@���\�K�тĂ��܂������A�^�J��ܲ���Ŗ������Ƃ���A�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B
�@ �@���@����Ȋ���
�@���@����Ȋ���
�@�i���[�����A����2�N��FJ1200�@�Ɓ@FZR400RR SP�@�Ɓ@Benly50S�B
�@�@�^�J�̖�������10�{�߂����������܂����B�|�|�|�|��J�j�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/6/17
8. �fOver6�~km/h��ۼު�āf
�@�@���[���ƁA�fOver6�~km/h��ۼު�āf(�����炻���Ȃ������m��܂���j
�@
�@�C�������u�n��̐��v��BGM�ɂ��Ă��ײ�قł��B
�@
�@Benly50S���ݷ��̴ݼ�݁iZ50JE�@12V�j���ڂ������̵����A������x������B
�@
�@�@��߯ẮAIN0.05�����AEX0.045�ŋK�i���B
�@�A��������͑|���ς݁B�i���q:�������ʁj
�@�B��װ�́A������������8�֊g��A�X�ɃӂW�̌���4�lj��B
�@�@�@�ቹ�����\�������r�C���B
�@�C���ذŰ�́A�z����R���Ȃ��B
�@�D��������́APC20�iҲ݁�95�A�߲ۯā�38�j�@
�@�E��Ԃ͏������ނ�MICHELIN�@M35�@�iF:1.7kgf/cm2�@R:2.0kgf/cm2�j
�@�F�_�Ύ����@ɰ��CDI
�@�GZ50JEɰ��ͯ��
�@�H���۹�Ắ@F:15-R:41�ō����^�BDrive+2T,Driven-1T
�@�ƂȂ��Ă���܂��B
�@
�@�����ŁA�r�C�ʂ��܂�����Ȃ��ƚ��������Ȃ��̂ŁAͯ�ނ��炵�܂��B
�@
�@�菇��
�@�@�@�@��װ���O���B
�@�@�A�@����������O��
�@�@�B�@ͯ��ް���O���B
�@�@�C�@�ѽ��۹�Ķ�ް�����āi�t������L�тĂ��钷�����āj���O���B
�@�@�D�@ͯ�ނƼ���ް�̒������Ă��O���B
�@�@�E�@�ѽ��۹�Ă��O���B
�@�@�F�@ͯ�ނ��O���B
�@�ȏ�ł��B
�@
�@����o�����߽�݂́A���\���܂݂�ŁA������ƔR�����Z���̂��Ȉʂł��B
�@
�@�ēx�t�̎菇�őg�ݏグ�A��װ���āAͯ��ް���Ă��������āA�Ō��ͯ�ނ�
�@���t���́A�ٸ������g���Ē��ߕt���B
�@
�@�܂��A��Ԃ��ō����_���Ł@F:2.3kgf/cm2�@R:2.5kgf/cm2�@�܂ŏグ�Ă݂܂��B
�@
�@�����āAýāB
�@
�@����Ă݂�ƁA�Ȃݼ�݂��y�������ʼn���Ă��܂��B
�@
�@�c�ɂ̒����ŁA4���ň�������ƁA�Ȃ��6�~����/h�܂ł̓��B�������Ȃ�A���̂܂�
�@7�~km/h��A�i��8000�������j�܂ŐL�т܂��B
�@
�@������Ԃ̴����������Ă���Ƃ͎v���܂����A�ݼ�݂��y������Ă��܂��B
�@
�@����������ͯ�����Ă��ɂ߂�Ƃ��A4�����Ă̒��܂�����A���ł����B
�@4�{�ŁA�������ݸ�������L�т��ׂ���������ĂŒ��߂Ă��܂��̂ŁA������������A
�@���ߕt���ٸ�̂���ŁA����ް�Aͯ�ނ��c��ł����̂����B
�@�������ݼ�݂ł��肪���ł����B
�@
�@�������Ȃ���A8000�������������Ȃ����Ƃɂ͕ς��Ȃ��A�����I�ȉ��P�͂Ȃ��B
�@�ł��AOver6�~km/h��ۼު�ẮA�������Ȃ��B������܂����B
�@
�@����ȏ�̍ō��������߂�ƁA�Ղ̖Ƌ��̓_�������������Ă�����Ȃ�����
�@�Ȃ̂ŁA���ꂩ��͑����A�O�ς�����ݸނɈڍs���܂��B
�@
�@�i�ݼ�݂́A100�����@4����ނ�\��B�@�ȁ[��Ă��ɂȂ邱�Ƃ��B�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/6/3
7. �^�C������
�@�@�O��̊m�F�̌��ʁA�@
�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j�@���@��߯ĸر�ݽ�K����
�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��
�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B
�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B
�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B�@���@�����E�����B
�@�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�@�@�@�i�b���ۗ��j
�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B
�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�ƌ������ƂŁA�E����Ԍ������{�B
�@
���́AMICHELIN��PILOT�@ACTIV�B
��������ԉ�����Ɋm�F����ƁA���ɖ{����͐��Y���~�ŁA�ɖ����Ƃ̂��ƁB
���[��B�@�Ȃ�Ί�{�ɖ߂���M35�B
�ʔ̂�2.25-17��2.50-17���w��(������5000�~���炢�ł����B�j
�@
�����Ė{����Ԍ����B
�@
�Ղ��A��`�킹�Ă̌�����Ƃł������A�Ȃ������Ԃ��O��80/90-17
�Ő��K�̻��ނɔ�ׂ��2�`3���ނł������߁A�Ȃ��Ȃ��ް�ނ������܂���B
�Ղ���Ԃɏ悹�ĉ��Ƃ��O���AM35�Ɍ����B
�����͋K���F:1.75kgf/cm2�@R:2.0kgf/cm2
�@
������A����Ă݂܂������A������MICHELIN�B�����ł��@�_�炩���A���������ł��B
�����A���т��������������p�̕E�͏����c�O�ł����B
�@
����ŁA�h�J�AFZR��PILOT�@POWER�Ɠ���MICHELIN�ɂȂ�܂����B
�@
�����čō����ײ�B
�@
�����[���B
���n�ł�6�~����/����Max�ŕς�炸�B
�@
��������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/27
6. �p���[�A�b�v�I�I ����3�B
�@�@���̑O�̑����ł��B
�@�O��̊m�F�̌��ʁA�@
�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j
�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��
�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B
�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B
�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B
�@�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B
�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�@
�@�ƂȂ����킯�ł����A���̈�T�ԁA��Ű���F�X�������܂����B
�@
�@�܂��́A�o����Ƃ��납��Еt���邽�߁A�@�����{�B
�@�ر�ݽ���m�F�����Ƃ���0.05�����łقږ��Ȃ��ł����B
�@�Ƃ������ƂŇ@�������܂����B
�@
�@�����������ŁA��^�₪�B
�@Benly50S�̋z�C�̒����ł��B
�@Benly50S�͂��Ƃ��Ɖ��^�ݼ�݂ł��ð���ΰ��ނ������ɂ��т����悤�ɒ����A
�@�܂����̴݂��ذŰ�́A����ذŰ�ޯ�������݂����ڰѓ��܂ł����čs�����߂ɁA
�@���������ΰ����q���ł��܂��B
�@�ŁA��ð���ΰ��ނ�10�������x�Aΰ���15�����B
�@����ΰ�������ƒ������H�H
�@�m���ɒ����ƒᑬ��ڽ��ݽ�͂悭�Ȃ�͂��ł����B
�@
�@�����ɲ�ð���ΰ��ނ��ނƓ��������Ɏ��t���A���ذŰ�t�������ײ�B
�@�ł��A��͂�6�~km/h�ȏ�o�܂���B
�@ΰ��͊W�Ȃ��H
�@�i������ΰ��ނ͖����H�H�H�ł��j
�@
�@���̌�A�_�Όn���m�F�������߂�ʲ�ݼ�ݺ��ނ��O���Ă݂�ƁAʲ�ݼ�ݺ��ނ�
�@�����ΐF�i�c�������Ȃ̂ŗΎK�j�ɂȂ��Ă܂����B
�@�@�@�@
�@�����߂ƺ�ّ���2�����قǐؒf���A���t���Ȃ����B
�@�����A�ق�̏����A�ٸ���オ�����悤�ȋC�����܂����A�ō����͕ω��Ȃ��B
�@
�@
�@����܂肢����������ł��ʔ����Ȃ��̂ŁA�܂��{��������120������°�ݸނցB
�@
�@����[�A�|���B
�@4�~����/h�ȉ��ő����Ă���ƁA�Ԃ����������ݔ����Ă����܂��B
�@���|�ł��B�i30�N�O�͕|���Ȃ������͂��ł����|�|�|�j
�@50�����������āA�������ꂽ���A�ō����ײ�B
�@�Ȃ��[���Ȃ��[���ɂ₩�ȍ⓹�ł������A�Ȃ��75�H�H�H���L�^�B
�@����]�ł�C.D.I�͂��Ă͂��܂����A�i�p�́H�B
�@�ł��悭����Ȃ��̂ł���ŇF�́A�ۗ��B
�@
�@�ƂȂ�ƁA�G�H�H
�@����Ȃ͂��͂Ǝv���Ȃ��炻�̂��Ɣ����̎R��o�����̂ł����A�É�������o�铹��
�@�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ�����܂����B
�@�Ȃ�ƍ�̖w�ǂ�4���ŏ���Ă��܂����̂ł��B�i4�~km/h�ʂł����B�j
�@�������A��ײ�ޱ��2T���B�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H
�@�펯�I���ٸ��啝�ɒ����Ă܂��B���肦�Ȃ��H�H
�@�ǁ[���A4�~����/h�܂ł̉��������炭�ǂ��ȁ[�Ǝv���Ă����̂ł��������܂łƂ́B
�@
�@�����Ȃ�ƁA����]�����Ȃ������͇G��ͯ�ށA��װ���r�C�ʂɍ����Ă��Ȃ����A
�@��Ԃ��������邩�B�H
�@�ł��ł���B�@75�����܂łȂ�Aɰ��ͯ�ނŏ[���Ȃ̂ł́H
�@��������ȏ�Ȃ�Aͯ�ށA���ƁACDI�A��װ�A�ׯ������������K�v�|�|�|�B
�@���̵�������!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
�@�܂��A���������ް�Eͯ�ނ��炷�Ǝv���܂��̂ŁA���̂Ƃ��̂��y���݁B
�@
�@�ł����ꂾ���ٸ������A�H��f���ɂ�����ق����ǂ������B
�@
�@
�@�e�Ɋp�A6�~����/h�܂ŽѰ��ɉ�������悤�ɂȂ����̂ŁA���iײ݂ɂ͓��B�ł��B
�@���Ȃ݂ɁA����܂�Ȃ������{���̔R��A60�����^�k�B�@�Ƃ�ł��ˁ[�B
�@
�@���݂̏�
�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j�@���@��߯ĸر�ݽ�K����
�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��
�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B
�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B
�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B�@���@�����E�����B
�@�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�@�@�@�i�ł��r�C�ʑ啝UP�Ȃ�C.D.I�ύX�K�v�B�j
�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B
�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/20
5. �p���[�A�b�v�I�I ���̂Q�B
�@�@�@GW������1�T�ԁA�܁[����1�T�Ԃł����B
�@�@����Ƃ̂��Ƃŋx�݂ɂȂ�܂������A���t�@�Ձ@�́A�w�Z�̒�������ԋ߂ŵ�����
�@�@���ǂ���ł͂���܂���B
�@�@����āA��Ű���A���̑O�̑������|�|�|�|�B
�@
�@�@�܂��́A
�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j
�@�@�A�@��������l�܂�
�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j
�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j
�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B
�@�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B
�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�@
�@�ŁA�@�͂߂�ǂ������̂ŁA�ȒP�ł���A����B
�@
�@���̑O�ɁA��{����ނ��m�F�B
�@����ƁA��ނ̔Ԏ�́A�W����NGK�@CR6HSA�ƈ���ā@CR7HSA�B
�@�Ȃ����A�ȁ[�����ނ͔��ƌϐF�̊ԁB
�@�@���̑O�A�w����������������40�����𐧌����x������ċA����
�@�����ɂ�������炸�|�|�|�|�B
�@
�@�H�H�H�H�H�H�H�@�����H
�@
�@�@���ނ��O���A��̔@�����Ƃ��������߰¸ذŰ��ʂ��܂��B
�@�����āAҲݼު�Ă��߲ۯļު�Ă̔Ԏ���m�F�B
�@�Ȃ�ƁAҲݼު�Ắ�100�A�߲ۯẮ�38�B
�@�ʏ�A�傫���Ă�Ҳ݂́�95�����肾�Ǝv���܂����A����ȏ�B
�@�Ȃ�ŁA�������ނ������́H�H
�@���̎��_�ŇD�͌����Ȃ��B
�@
�@�����Ȃ�Ƽު��ư��ق̸د�߈ʒu�������H
�@�@�iư��ق�������̂ŁA���߂ɂȂ�j
�@�m�F���Ă݂�ƁA�N���b�v���ォ��2�i�ځB�i�����ق�����2�ځj
�@���ꂩ���[�H�@�@
�@�N���b�v���ォ��4�i�ڂɕύX�ł��B
�@���̏�ԂŁA�܂��͎����B
�@�ł�5�~km/h�܂ł͌��\�ȉ����ł����A����ς肻��ȏオ�L�т܂���B
�@�ŇA�������B
�@
�@�@���B
�@
�@�B��װ�H�@�C�ɺ�i���ذŰ�j�H
�@�m�F�̂��߁A�܂����ނɕt���Ă���ΰ��{�ɺ�̷��ޑ������ɕt���Čċz���Ă݂܂��B
�@�|�|�|�|�@�w�ǒ�R�����ċz�\�B
�@�z����R�͖w�ǖ����悤�ł��B
�@�Ȃ̂ŇC�͖���
�@
�@��͇B����װ�̔����B
�@�O��v�Z����163�����Q�̕s����₢�A������ǂ����܂��B
�@����5��������̂��ʓ|�������̂ŁA�܂��͐�������4����6�ցi�{16�����Q�j
�@����Ń�6���ف{ذϰ�Ń�8���H�ł��B
�@
�@����肵�Ȃ���܂���2�B�i�{100.5�����Q�j
�@���͂܂��Â��̂Ȃ���ł��B
�@����Ŏ����B
�@�����B�@6�~km/h�܂ŐL�т܂��B�����ē��B���Ԃ��Z�k�B
�@�ł����̌㓪�ł��B
�@6�~����/���Ƃ����Ʒޱ��A��ԊO�a����v�Z����Ɩ�7000rpm��B
�@7000rpm��œ��ł����āH�H�H�H�H
�@
�@�@���Ⴀ�Ƃ������ƂŁA�������8�i50.3����2�j
�@����ō��v166.8����2�B
�@�J���ʐς����Ȃ�ڕW�ر�B
�@�ł��A��͂�60km/h�ȏ�͐L�т܂���B(�����܂ł͌��\�����j
�@����3��������ƁA�����ݸނ͖��Ȃ��Ă��A�ݼ�݂��Ɖ����傫���Ȃ��Ă܂��B
�@�������́A���������E�H
�@�ŁA�B�͊����B
�@�@�@�@ ������Ȃ��ƂɂȂ��Ă܂��B
������Ȃ��ƂɂȂ��Ă܂��B
�@
�@���ĂƁA�ǂ����邩�ȁ[�B
�@
�@���۹�Ă�����Ɛ��K��F13-R42�ɑ���F15-R41�B
�@�������ɕύX����Ă��܂��B
�@
�@������2T�ł����A��ײ�ޱ��2T�͌����܂��B
�@�ޱ����ׂĂ݂��
�@�@�@F13-R42�@���@3.23
�@�@�@F15-R41�@���@2.73
�@�@�@2.73�^3.28�@���@85���@�@�@15���ς���Ă��܂��B
�@
�@�ł��A��ʓI���ޱ���߂���ƁA�ޱ���ύX����͕̂��ʁB
�@(�ޱ���߂��Ă��ō���]�͏オ��Ȃ�����j
�@��Ζ��Ȃ����x���B
�@
�@�Ƃ������ƂŁA����ȏ�̍ō��������߂�ꍇ�A�c���
�@�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j
�@�@�A�@��������l�܂�@���@�|��
�@�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j���@�������B
�@�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j���@�ɺ�O���B
�@�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B
�@�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ���r�C�ʂƍ����Ă��Ȃ��B
�@�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�@
�@���������܂��܂��Ȃ���m�F���Ă����܂��B
�@�i�D�́A�F�����܂��K�v�ł��B�j
�@
�@�����܂łŁA6�~km/h�܂ł́A�Ԃ̗�����ז����Ȃ����x�ɂȂ����̂ŁA
�@������Ƃ�������ł��Ƃ������ƂŁA�H���ς��°�ݸނɍs���܂����B
�@
�@
�@
�@����ς�A�����������͏����̏���ł��X�s�[�h����������A
�@����ͽ�߰�ނ��o���肷��̂ŁA�F��ȏꏊ�̒n�`���킩��܂��ˁB
�@
�@�傫�ȵ������ƁA��C�ɑ������Ⴂ�܂����B
�@
�@���\�A�y�����B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/12
4. �p���[�A�b�v�I�I�B
�@�Ղ��A���i�ł̸ׯ�����ɂ�����A�܂��܂��̉����Ŕ��i
�ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@
�����ŁA�ڍׂ�Benly50S�̏��m�F�B
�@
�܂��n��������A�����ݸނ͈��肵�Ă��܂��B
���ۂ��Ċ����ł����A�����Ʊ����ݸޏo���Ă܂��B
�@
�ł���肪�B
�@�@�@�g�@���I����Ă��A�����ݸނ���}�ɽۯ�ق�P��ƁA�ݼ�݂��İق������ɂȂ�B
�@�@�@�@�i���������ނ̓����ł����A����ł����������j
�@�A�@75�����̵�Ű�����ƁA5�~km/h�܂ł͂����ɏo����̂́A����ȏ�͂����[������
�@�@�@�L�тĂ����܂��B
�@
�́A��Ű�́ACUB70�ɏ���Ă܂������A����CUB�́A���Sɰ�قɂ�������炸�AҰ��
�ǂ݂�1�~�~�����o�Ă܂����B
(���̓����͑̏d90�����j
�@
�J�u�n70������ͯ�ނ́A����ތa��IN25mm�AEX22mm�ŁA12V�n��IN19mm�AEX16mm�Ƃ�
������ƈႢ�����B�@
�܂��͌��݂̍\���iPC20���ށAɰ����װ�j�������Ȃ����Ƃ�O��i��������j�ōl���܂��B
�����Ȃ�ƍl������͉̂��L�B
�@�@�@��߯Ē����s�ǁB�i�ر�ݽ�������j
�@�A�@��������l�܂�
�@�B�@��װ�̗e�ʕs���i�����������j
�@�C�@�z���ł��Ă��Ȃ��i�ЊO�̷ɺ��OK�̂͂��ł����j
�@�D�@�۰�n��Ҳn�������Ă��Ȃ��B
�@�E�@��Ԃ��������@
�@�@�@�@�@����F2.25-R2.50�ɑ���F��R��90/80�i�������3.50�H�B�j
�@�F�@�r�C�ʕύX�œ_�Ύ����������Ă��Ȃ�
�@�G�@ͯ�ށi����ތa�A�����ݸށj�A��װ������Ȃ����炢�r�C�ʂ��傫���B
�@�H�@���۹�Ă������d�l�ɂ���B
�@
�ŁA��߂�̏��Ȃ����Ԃ��炵�Ă܂��͇@�`�A�����{�B
��߯Ă̸ر�ݽ��0.05�����Ƃ悭�����Ă��܂��̂ł���Œ����B
��������́A�۰Ă����A�j���Ō��ƌ�������|���B
�����Ă܂��͊m�F�B
�@
�����ćB����װ�B���̔�����ǂ����܂��B
�@
��װ�̌��a���肷��Ƒ�̃�20�ʁA����ɐ������̌�����4���炢�ł��B
�Ȃ̂ŁA�r�C�ʐς́A
�@��20��314�����Q�@�{�@��4��12.5�����Q�@��326.5�����Q
���ތ����Ŕr�C�ʂ�1.5�{�i�H���Ɂ|�j���Ƃ��āA326.5�~0.5��163�����Q�@���s���̂͂��B
�@
�����������Ă������ق̍ő�a����6�Ȃ̂ŁA�܂��͐������̌�����4����6�ɂ��邱�Ƃ�
�@�{16�����Q�Ȃ̂ŕs�����́@163-16��147�����Q
147/�i3�~3�~3.14�j��5.�̌��lj��H�@�@�@�i����ȍl����OK�H�j
�@
�����m�F���Ȃ���J���Ă݂܂��B
�����A��Ű�̌��E�����璆�~�ł��B
�@
����ł��߂Ȃ�A�C�ōw�������ɺ�^�̴��ذŰ�O���Ă݂܂��B
�@
����ł����߂Ȃ�A�D�̂߂�ǂ�����������������ɓ���܂��B
�ު�ĊW����肵�Ȃ���|�|�|�|�|�|�B�@����������i�[�B
�@
�E�ƇF�́A���̂����B
�G�Ȃ炍����������
�H��Drive������15T�Ō��\�傫���̂�Driven��41��35T���炢�H
�@
�����A�Ղ��C�ɂȂ��Ă����Ԃ��ׯ�����ق��A��ް��t���č��ɁB
����ƁA������ڰ����̶��݂ɑ��ẮA��ނ�̫���̷��̊Ԃ�0.5�����̱�Д�
�ł����݁A���݉����ł��B
�@
�������́A�i�����Ă܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/7
3. �ՁA���n�߁B
�@Benly50S�̐������������A���āA�@�Ձ@�ւ̵�����苳���ł��B
�@
�Ղ́A�N�Ɏ����̂���Ű�̂悤�Ɏ��O�ɐF�X���K����悤�Ȑ��i�ł͂Ȃ��A�Ƌ�������
���i��ɏ�齸������A���܂�Ďn�߂Ă̌����@�t���̏�蕨�������悤�ł��B
�@
���̌Ղ��ׯ��t���i�H�j
�@
���t�ͽۯ�ق���ڰ�����݂̂ŏ���A����������������ƂŁA�����ɂ����S�җp��
��Ǝv��ꂪ���ł����A���ꂪ�~�b�V�����t���ɂȂ�ƴݼ�݂���͂ȕ��A����Ȃ�܂��B
��ܰ����ނ������Ɉێ����邩�B�@�����ė���ɏ��Ȃ��琧�����x��@���Ɏ�邩�B
��Ű����������̓���������m�����Ǝv���Ă��܂��B
�i�r�C�ʂ��傫�������̂ق����A�y�Ȃ��Ƃ���ł��ˁB�j
�@
�����Ă܂��͈��S�����B
�@��үāB
�@�@�Ȃ��Ȃ��̏������Ŕ�����Arai�@RX7�@RR4�@���ՂɁB
�@���͐Ґ��߯�ށB
�@�@�߯�ޕʑ̂ŕt����A������T�̍b�����ՂɁB
�@��۰�ށB
�@�@RS����̂��Â̸�۰�ށB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[��B�i�܁j
�@
�ŁA�Ղւ̋���J�n�B
�@
�����̍\�����y�������A�悹�܂��B
��Ű�́A���]�ԂŒǑ��B
�@
�ŏ��̔��i�B
���z���ʂ�A�ŏ��ʹݽāB
���̌�ݼ�݂���肷���ċ}���i������ݽĂ�����B
�ł�20����������ƁA���\��肭�Ȃ��Ă܂����B
�@
�����A��͂�ر��ڰ����Ȃ��Ȃ��g���Ă��Ȃ����ƁA�ޱ��ݼނ̑����𑖂�Ȃ���
���Ă��܂����ƂȂǁA��Ű��33�N�O�Ɍo���������Ƃ��A�܂�܍Č����Ă���܂����B
�@
�Ō�́A��Ű��Ninja�ɏ�芷���A��̶̂�ݽ���ނ܂ōs���A�Ղ�Benly50S�Ƶ�Ű��
Ninja�̶�݂��݂ɂ��āA�A��B
�Ղ̂�ʲ���ł�600�~�Ŗ��^���B
Ninja��3000�~���|����܂�----�ƂقفB
���̏�6L�ݸ��Ninja�̖��^���Ɠ���300��������----�B
������ƑA�܂����Ȃ��Ă܂����A�r�C�ʂ́@1/18������ˁB
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/5
2. ��Ű�A�{�̔�������B
�@�@Benly50S,�悭�悭����ƁA�F�X��肪�B
�@
1.�K�B�@
�@�@���鏊�ɎK�����B�ł��[���ȎK�͂��܂�Ȃ��B
�@
2.����̫���B�@
�@�@���������ɂ͎K�͖������߁A�����悢���A�O�����t���������́A
�@�@�K�œʉ��B�����͌����K�v�B
�@ ��ٌ������K�v�B
�@
3.���ذŰ�Ȃ��B
�@�@���ނ̲�ð����ɐ��p���߲�߂�˂����݁A�ޯ�ذ���ŊJ���B
�@�@�J���[�ɂ́A�ꉞү���ׂ̍�����݂̖�
�@
4.��Ԃ̂Ђъ���B
�@�@��������̂݁B
�@
5.���݂̂����
�@�@��������̂݁B
�@
6.ر̪��ް�̕����I�h���͂���
�@�@�h������̂݁B
�@
7.��ݶ��Aʲ�ްт̲ݼ������ߖ���
�@�@����͐[���B
�@�@���S�҂́@�Ձ@����邱�Ƃ��l����ƕt���Ȃ�������܂���B
�@
8.������ڰ����|�����Ƃ��ɁA���ݔ����B
�@�@��ނƱ�������ނ̷��̶����������ڰ����|�����Ƃ��ɁA�����V��ł��܂��B
�@
9.�ݼ�̵݂�ٌ���
�@
10.�ǂ����悤���Ȃ����炢���܂̻�
�@
�ƌ������ƂŁA��Ű�A����GW���ɂƂ�ł��Ȃ������܂����B
�@
�@�܂���1-2�̎K���B
�ԑ̂����ݸ�܂őS�ĎK�����s���܂��B
(�Ղ̏��߂Ă̵����Ȃ̂Łj
�ԍ炩G�̎K�����ݸ�ذŰ����g���A�Ȃ�Ƃ��K�͌����B
����̫���́A��ٌ��������łɍs���Ȃ���A��Ű����ނ��|���܂��B
��ق̘R��͖����A���q�ɏ���ı�������ނ��h�����Ȃ����Ė������t�������B
�@
�@������3
���U�ŷɺ�^�̴��ذŰ��^���X�Ŋi���ɂ�Get�I�i�o���s���j
�����ΰ��̊J���[�Ɏ��t���܂��B
�ł෬���������痈�Ă���ΰ��ƴ��ذŰ���q���Ȃ��Ă͂����܂���B
������ΰѾ����ʼn��r�߲�߂̊O�a32�����̂��̂��Ű�Ɏg���߲�߂ƴ��ذŰ��
�������ĂŒ��ߕt���܂��B
����ŁA�z�C���������ԐÂ��ɂȂ�܂����B
�@
�@4�́A���������Ď��{���邱�Ƃ�
�@
�@5-6�͋C���Ŋ���
�@
�@����7�ł��B
�@Benly50S�́AҰ�����ɳ�ݶ���ƭ���ق̲ݼ������߂�����܂����A�ǂ���
ʲ�ްт̲ݼ����͖����悤�ł��B
�X�ɍw�������a����l��50S�́A�������Ă��賲ݶ��ݼ�����������ԁB
������āA���S�҂́@�Ձ@�ɂ͌��\�s�s���ł��B
�@
�Ȃ̂ŕ��͍��܂����B
�@
 �@�ˁ@
�@�ˁ@
�@�@�@�@���ꂪ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ����B
�@
2�����̱�Д��g���ALED���߂�4���ׂĊ����B
�@
�z���́A��������K�v���������炢�ȒP�ł��B�i���w�Z���x���j
���[�͵�ݼނ̳�ݶ��ݼ����A������2�ڂ̸�ذ݂����߂�ƭ���فA������3��
����ٰ��ʲ�ްтł��B
LED�Ȃ̂Œ��Ԍ����邩�S�z�ł������A���Ȃ������Ă��܂��B
Mission�@Comp!!
�@
�W.�́A���Ԃׂļт����܂��B
�܁A��镪�ɂ͂��܂�W�Ȃ��̂ŁB
�@
9.�ł����A��قɎ莝����MOTUL�@5100��15W-50��������܂���B
�Y����A�e���̵�Ű�A����܂����B
�i�ł��A����϶�ތn�̴ݼ�݂ɂ�15��-50�́A�n�����ɃL�c�C�����ł��j
�@
�Ō��10.�́A�������̊W�Ŏ��Ԃ����Ă���Ă����܂��B
�@
�ł����āA�����͊����ł��B
�@
�@�@�@�@�@��ꂽ�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/5/4
1. ���t�@�Ձ@�̐S�ς��B�i4��߁[�B�j
�@�ǂЂ�[�B
�@
���炭�o�ꂵ�Ă��Ȃ������@���t�@�Ձ@�B
�@
���Ƃ��ẮA�d�グ���e�y�q�̎�O�A�������ʓ�֖Ƌ������悤�ɑE�߂��̂ł����A
�ŋ߂ʹڷ�����ɂ����S�B
��Ű���Ղ̂��߂ɁA�����Ď����̎�Ŏd�グ���e�y�q�Ƃ͂����A����Ȃ�ɍH����
��Ă��|�����Ă���܂��B(�w�ǐV�ԏ�Ԃ���Ԃ��߲ۯ���ܰ�����j
�@
���̌Ղ��A�u���Z�̊Ԃ͌��t�ł����v�ȁ[��āA��Ű�Ƃ��Ă�῝������ȐM�����Ȃ�
���t���̂��܂��A�l���̕s�𗝂������A�ł��̂߂��ꂽ�̂�3���B
�@
�����āA�Ղ͓K���ɕ����ĂS�����߂Ɍ��t�Ƌ��擾�B
�i���t�Ƌ���������ꐶ��Ű�̌������Ƃ��Ƌ����܂������j
�@
�@���[���B
���ʂ̐e�Ȃ絰���֎~�����B
���ʓ�ւ̵����A��������ض�ŏI���ق��킴�킴�p�ӂ��Ă��e�������ɂ���B
�����̌b�܂ꂽ����S���������Ă��Ȃ��|�|�Ƃ͌����Ă��A�Ձ@�̐l���B
�@
�܂����t�ɐ��ʐ��Č��������A���̌o���t�@�Ղɐς܂���̂��܂��ǂ��B
��Ű�����Z�̎��u�R�Ȃ��^���v�Ō��t�݂̂��������B
�i�������肾���͂Ƃ��Ă�������Ű�B�j
�@
�������A�ǂ�Ȍo����ς܂��邩�����B
����̌Ղ̕��ʁA��^��ւƑ�������ײ́i�Ǝv���Ă���̂͵�Ű�����H�j
�́@�u�ŏ��v�@�ɉ����o�������邩�B
�@
���R�Ȃ���Aư��د�߂��ł����ݸ�����鵰��ޯ���Ȍ`�A��Ԃ�17����ȏ�A
�����ķޱ�A�ׯ��t���B
�ݼ�݂�2�������]�܂������ǁA�c�O�Ȃ��玞����l������4�����B
�@
�����͵����̊�{���o���邽�߂ɕK�v�����A�܂��Ղ�(�u��Ű���v�H�j
���㷬�ށAͯ�ށi�сA����ޓ��j�A��װ�A����F�X��������邱�Ƃ��厖�ł��B
�����Ȃ�ƁA4���� Mini�ʼn����߰��������ނɂȂ�܂��B
�@
�ƌ������Ƃ��l���������T���B
�@
��L�̏������ƁA���ُ݈�ɍ������ݷ��A���ׁA�ޯ���A��ذ�AR&P�AAPE�Ȃǂ�
���aβ�ٕ��͂��̎��_�ŏ��ŁB
����ɵ�Ű�͏�������Ԍa�̂��̂ͽ����������������Ƃ͂���܂��A�Ȃ�
�ł���ˁB�������B
�������Ԍa���������̂Œi���ȂŐU���邵�B
������Ղ̏��߂Ƃ����Ƃ��Ă͎��i�B
�@
���Ȃ݂ɂ����̵����͂ǂ�Ȃ������ۂł�10���~���܂��B
�܂�������߂ŕ��F���Ă��A�Œ�ł�5���~�ł͗����Ȃ����i�������K�v�����ق�
���̂���B
85�N�����Ȃ炱�̎�̵����́A�l�i���t���Ȃ��ʂ̎ԗ�������܂����B
Mini �S�@�l�C�ɂ����̂ł����A������Ԃł��B
�@
��Ű�̌o����A�V�ÎԂł�����Ȃ�����A�ǂ�ȵ����ł��w������o���܂ł�
3���~�ʂ�����ݽ���������܂��B(��فA���۹�āA��ڰ��A���etc�j
�ǂ�����������̒��É��i�������̂́A��������ݽ�����������邩��Ȃ̂ł����A
����൰������������قɂ��܂���ˁB
�@
�l�C�Ԃ̍w�����l���Ă�����́A���ꂽ�l�ƈꏏ�ɍs�����ق����ǂ��ł��B
�@
����Ȃ���Ȃ̛������s�˂Ȃ������ȯĂŒT���܂���A�����ɍ����������B
�@
Benly50S�B
�a���|�|�|�|�|�a������B
�@
�n�͂�3�n�͂��������B
�ł����^�ݼ�݂ŐF�X�y���߂����B
�������͎̂O�Y�����̐���ۂ̵���������B
�@
�ՂƉ����ɍs���A��������w�����Ă��܂��܂����B
�@
�ς��ƌ��A����فAҰ���Aͯ�����߁A��ݶ��A��ݼ�����فA��āiBenly90S�p�j�A
��������������ς݁A����̫����ް�͎��O�����̫���ްɂȂ��Ă��܂����B
����Ԃ�TT900��90/80-17�I�I�I(�W����F60/80.R70/80��--�������j
�@
�܂��A���x�͂���Ȃ�B�i10�N�ȏ�O�̂ł�����B�j
���X�ł́A�ݼ�݂��|���ĐF�X���܂������A�傫�Ȗ��͖����B
���s������17000�������Ă��܂����AҰ�����������Ă���̂ŁA����ȏ�ł��傤�B
�@
�����Ė{���A���X�܂�3���Ԋ|���ēd�Ԃŏo�����A�_����ς܂�����A���Ⴋ���Ⴋ���ւ�
°�ݸށB�i�Ղ͊w�Z�ł��j
�@
�o���̑O�ɁA�X�������4��۰�ذ�ł���˂Ɗm�F�����ɂ�������炸�A�Ȃ���4�����݁H�H�H�B
Benly50S�́A�{��۰�ذ4���̂͂��B
�ݷ������̴ׂݼ�݂ɕύX����Ă���悤�ł��B(ׯ���H�j
�ł������Ȃ�Ǝ����́A�X�Ɂ������E�E�E�E�E�B�@�܁A�������B
�@
ͯ�ނ�ɰ�قł����A����ް�ɁuDAYT0�~�~�v�̕������B
�X�ɷ���������@KEIHIN�@P10C----�@�B
�@
�܁A�������Â�����A�F�X����̂͊���Ă܂��B
�C�ɂ����v���Ԃ�̌��t°�ݸށB
���̌y���A��ܰ�̖������y���݂Ȃ���C�ݐ���2���ԁB
�@
�������ꂽ���H���A���t��4�~km/h�ȉ��ő���ƁA�i�F���ς��܂��B
��ܰ���Ȃ����A�o��A���肪�悭����A����̌i�F���������߂��Ă����܂��B
�����A���̽�߰�ނł́A�i���ɂ��Ⴋ���Ⴋ���ɒ����Ȃ��̂ł͂Ǝv�����炢���Ԃ�
�|����܂����B�i��U���j
��50������2���Ԋ|���Ă��Ⴋ���Ⴋ���ɋA�҂��܂����B
�@
��������Benly50S������B
�����ɂ��ڰ����ް���炷���CD50ST
�@

�@
 �@�@
�@�@
�����͐F�X�ł����A�ǂ��ɂ����܂��B
�@
��ԑ厖�Ȃ��Ƃ́A�Ղ����̵�����ʂ��āA�����ւ̒m�����L���A�������Ȃ���
���S�ɑ��邱�Ƃ�g�ɂ��Ă����B
�@
���ꂪ��Ű���A��������̐e���Ə��������Ⴄ�Ƃ���ł��B(���掩�^�I�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 2012/5/�P



