|
****************************************
Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録
二章 鎌倉〜戦国期の小田原
1
相州武士の時代
武家政権と小田原/石橋山の戦い/御恩と奉公/
相州武士の他国進出/湯坂路と酒匂(さかわ)宿/
南北朝の動乱/大森氏と小田原 |
1 相州武士の時代
武家政権と小田原
一一八〇(治承四)年八月の源頼朝の平家討滅の挙兵は、日本歴史に初めて武士の政権を出現させる端緒となった画期的な事件であった。
彼の、貴族政権に対する反乱は、実にこの相模国西部の地域でスタートした。
小田原市の南方の石橋山での合戦がそれである。
鎌倉幕府という武家政権を創立したのは、確かに源頼朝という英雄の輝かしい功績によることは事実であるが、その実際の原動力は、彼を自分たちの旗印としてかつぎあげた相州武士をはじめとする東国の在地領主たちであった。
土肥実平・和田義盛・三浦義澄・大庭景義などの名だたる御家人は、いずれも相州の各地に地盤をもつ農村の領主であった。
実平とその子の小早川遠平は、小田原の前身ともいうべき早河庄や成田庄に一族を分布させていたし、のちに九州の戦国大名として有名になった豊後国の大友氏は、大友郷を本領とする相州武士の後裔である。
従って彼らが西国や九州に拠点を移しても、なおこの相模国の本領は、永くく重視されていた。
一四世紀の前半、鎌倉幕府は後醍醐天皇の計画によって打倒されたものの、間もなく足利尊氏の室町幕府が出現した。
武家政権は形をかえで存続した。
しかし、幕府が京都におかれたことは様々の波紋をこの東国各地に呼びおこした。
武家政権発祥の本拠ともいうべき鎌倉をもつ相模国をはじめ、その他九か国を管轄する鎌倉府がおかれて、東国とさらに北方の東北地方を掌握することになった。
その体制のなかで、鎌倉府の長である公方(くぼう)足利氏を補佐したのは、執事=管領の上杉氏であるが、鎌倉以来命脈を保って来た各地の領主たちは、一族の分裂と対立に悩み、中々ひとつの勢力に結集することがなかった。
そして互いに対立し抗争を続けるのであるが、公方のおひざ元の相模国の西半を擁して京都の将軍権力に対抗する有力な部将が、小田原に拠った大森氏の一族である。
彼は駿河国駿東郡の大森を本領としたものであるが、禅秀の乱の功績によって相模国に進出した。
大森氏は、一五世紀の末期、伊勢新九郎長氏(ながうじ)に攻められて小田原を失った。
代ってこの要衝を占めた長氏こそ、北条早雲その人である。
以後、氏綱・氏康・氏政・氏直と一世紀にわたる北条氏の関東制覇の戦国時代の出現までの経緯を本章では扱うこととする。
先にも述べた通り、小田原が、町として成立するのは実にこの北条氏の時であった。
従って、本章においても、視野を足柄平野の各地に拡げておかねばならない。
石橋山の戦い
平家追討のために諸国の源氏の挙兵を促す以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)が、伊豆国の北条館(やかた)の頼朝の所に達したのは、一一八〇(治承四)年の四月の末であった。しかし宮とその後楯となった源頼政や子の仲綱らは五月に宇治の戦で、あえなく平氏軍のために敗れてしまっていた。
清盛の頼朝に対する警戒心は強く、駿河・伊豆・相模の平家方の武士に向けて、頼朝攻撃の準備を急げとの意が伝えられた。
そのため、頼朝と舅(しゅうと)の北条時政らが急邃挙兵したのは八月一五日、伊豆国一宮の三島神社の祭礼の日であった。
伊豆国目代(もくだい)平兼隆(たいらのかねたか)を殺してこの国を収め、相模国に進んで土肥郷(湯河原町)に入ったのが二〇日、そして二三日の夜には、平家方の総帥大庭景親に率いられた三〇〇〇の軍に攻められた。
わずか三〇〇ほどの頼朝軍はさんざんに敗れ、闇を利して箱根山中にちりぢりに逃げこんだ。この敗戦こそ、石橋山の戦いである。
頼朝方の敗北にはいくつかの理由があった。
第一に戦備すなわち味方する伊豆の武士が意外に少なかったこと。
祖父為義・父義朝以来の累代の源氏の家人でも、山内経俊とか波多野義常とかが味方しなかった。
渋谷重国も動かず、敵将大庭景親の兄景義は味方したものの、景親や俣野・梶原らの一族は皆、敵となっていた。
武蔵の武士はほとんど、畠山・熊谷・秩父・川越氏など皆、大庭方であった。 |

石橋山合戦場跡
|
相模の最大の豪族三浦氏は一族の和田氏と共に味方するはずであったが、石橋山の戦いに間に合わなかった。
第二に腹背を伊豆の伊東氏や駿河の橘氏などの平家側におさえられ、はさみうちの形勢にあった。
このように、頼朝の挙兵当初、かれの勢力はまことに微々たるもので、舅時政とその子の宗時・義時ら北条一門、加藤景員とその子景廉兄弟、工藤介らの伊豆の武士の他、土肥実平と子の小早川遠平、その一族の土屋氏、平塚市付近の岡崎義実と子の佐奈田与一(さなだよいち)あたりが目立つ程度の、わずかな兵力にすぎなかったのである。
土肥の椙山(すぎやま)に逃げこんだ頼朝主従は、実平の尽力で八月二八日、真鶴岬から船で安房(あわ)国に逃げた。
その間、走湯山権現に政子をかくまった覚淵とか箱根権現の行実・良暹(りょうせん)兄弟らのかくれた庇護をうけつつ、実平の秘計を以て脱出することができた。
酒匂川の洪水のため行手を阻まれて合戦に間に合わず、退却して衣笠城に平家の寄手を引受けた三浦氏の義澄たちも、城の陥落後船で安房に逃げ、ここで頼朝だちと再会することができた。
そして、安房・上総・下総と経由して、一〇月の始めに鎌倉に入ることができたが、この敗軍の将がこの時は何と三万の大軍を部下としていたのである。
そして、はるばる京都から下向して来た平維盛(これもり)の軍を駿河国富士川の戦いで破ったのが一〇月二〇日、彼は敗走する平氏軍を追って上洛することを断念して、鎌倉に帰った。
途中、相模国府で論功行賞を行ない、降参したものの帰伏を許した。
もっとも、波多野義常はその前に一〇月一八日に自殺し、所領を没収されており、大庭景親は足柄山に逃げこんで行方知れずになったが、やがて捕えられ斬られた。
頼朝の挙兵は、見事に成功した。
御恩と奉公
頼朝の奇跡の脱出に功のあった土肥実平は本領を安堵され、その後平家討滅の侍大将として源義経に従って一の谷・屋島に転戦し、備前・備中・備後三ヶ国の総追捕使を兼ねた。
この職はのちの守護の前身で、一国の御家人の総指揮官という重要な役割をもつものであった。
子の小早川遠平は、その名からも早河庄に本拠をもっていたことが知られるが、この荘園の「惣領地頭」といわれている。
おそらく功績によって、筥根(はこね)権現領となった早河庄の地頭職を頼朝から公認されたのであろう。
曾我郷の曾我祐信(すけのぶ)は、大庭方であったから本領を没収されても当然のところを許され、この本拠地を安堵された。
それより北の大友郷にいた大友氏では、後の史料から逆推すれば、その「地頭郷司職」が頼朝によって認められた。
松田では、波多野氏の一族のために波多野義常(よしつね)の子の有経(ありつね)の松田郷は没収され、大庭景義に与えられた。
同族の河村義秀も同様囚人として景義に預けられたが、後年二人とも許されて、頼朝の御家人となることができた。
鎌倉に山内庄という荘園があり、ここを本拠とした武士に山内首藤経俊というものがあった。
彼は頼朝の乳母の子であり、義朝の代以前から源氏譜代の家人であったにもかかわらず、挙兵に参加せず、かえって頼朝を石橋山で射殺そうとさえした。
降伏して来た時、母が涙ながらに命乞いをしたもののその時は頼朝も許さず、自分の鎧にささった矢に経俊という名が刻んであることを母に見せたという。
しかし結局は助命し、これを実平に預けた。
実平は子の遠平のもつ早河庄内に田地と屋敷を与えてここに住まわせた。
今の大雄山線井細田(いさいた)駅近くの若宮八幡を含む多古(たこ、田子と表記されていた)一帯に屋敷があり、早河庄の一得名に田畠があったことが、後年の文書から知られる。
酒匂(さかわ)川の東岸に酒匂太郎という武士がいた。
彼が挙兵時にどんな活躍をしたのかは分らないが、おそらくこの川の渡しの船を管理していた実力者であったようである。
彼のもっていた柳下郷は、伊豆山の文陽房覚淵に恩賞として与えられた。
覚淵が新しい支配者として酒匂太郎の免田を認めずにこの郷の年貢をすべて手にしようとしたのに抵抗したため、その地位を追われてしまった。
走湯山権現は政子をかくまっただけでなく、その僧兵が頼朝を大いに救けたから、恩賞として、柳下郷と千葉郷が頼朝によって寄進された。
また長墓郷(長塚郷)の一所も常行堂に寄付された。
高田郷と田島郷は鎌倉の鶴岡八幡宮の建設の時に寄進されている。
このように、帰属した武士の、従来からの本領を安堵し、功によって新らしく土地を与える。
寺院や神社に荘園内の土地や、郷とよばれる国衙領の一単位を寄付する。
あるいは郷司とか地頭という、その村落内の支配者の一人としての地位に任命する。
こういう恩恵を一括して「御恩」(ごおん)といった。その場合与えられるものは、敵対者の没収地である。
のちに平氏を亡ぼしてからは、それまでに平氏がもっていた荘園や諸職は、没官領といって頼朝の手に入った。
頼朝に服属して、戦闘に参加して功績をあげる。これが奉公である。その奉公を遂げれば恩賞が入る。
これが、相模や武蔵、あるいは房総の豪族たちが、この、源氏の血統をひいた「貴種」頼朝の挙兵に参加し、彼を支持した理由であった。
ただ、この場合、頼朝の恩賞の給付や寄進は、相模国の国司や京都・奈良の荘園領主の支配権を完全に無視したもので非合法とさえいってよい。
明らかに彼は、この挙兵以後、一一八三(奉永二)年に後白河法皇から東海道と東山道二道の諸国の行政権を公認されるまでは、国家に対する反乱をおこし、その軍事的な実力を以て、東国に実質的な武家政権をうち立てる努力を進めていたのであった。
その間、同じ源氏の木曾義仲、平宗盛以下の平氏一族、そして弟の源義経や範頼までをも倒して競争者を排除し、全国に鎌倉幕府の権力を植えつけて行ったのである。
相州武士の他国進出
この全国平定の事業を実行したのは、いうまでもなく相模・武蔵の御家人たちであった。
土肥実平や小早川遠平、そして許された山内経俊らは中国地方に進出し、そこにまた恩賞地をもらった。
小早川一族は安芸国沼田庄、山内氏は備後田地比(ちひ)庄、大友氏は豊後国大野庄、という工合にそれぞれ進出した。
しかし、彼らの足柄平野にある本領は永く一族の拠点としての重要性を保っていた。
鎌倉に軍役を奉仕する時の宿泊地として、小早川氏は本領北成田郷に屋敷をもっていたし、御家人がすべての財産を子や一族に分割して譲与する時には、本領とその内の屋敷は、必らず惣領の手に讓られた。
この足柄平野の武士たちの一族が、西国の各地にしだいに移り住むようになった背景には、二一一三(建保元)年五月の和田合戦での和田氏の敗北がある。
北条時政・義時が有力御家人を圧迫し、梶原・畠山などを倒して幕府内に優位を占める勢いに反抗して、侍所(さむらいどころ)別当(べっとう)の和田義盛が一族をあげ
て戦いを挑み、敗れたのである。
この時、義盛方に多くの相州武士が味方して敗れた。
しかし一族の所領全部は没収されず、本領と一部の所領は、一族の他のものに与えられて家名は続けられた。
そこで、北条氏の権勢がいよいよ強くなる状況の相模国から西国の地へと移った武士が少なくない。
と同時に執権としての地位を確立する北条氏の嫡流(得宗(とくそう)という)に接近し、その家臣となるものも現れた。
こういう武士を、「得宗御内人(みうちびと)」といったが、曾我氏もその一人である。
曾我氏は、一一九三(建久四)年に祐信の養い子の祐成・時致の兄弟が富士の巻狩で父の仇と称して工藤祐経(すけつね)を殺し、しかも頼朝の幕営をも襲ったという事件のあと、幸いに罪には問われなかったものの、しだいに北条氏に近づいた。
そして鎌倉期の幕末には、得宗領の陸奥国津軽の代官として大いに勢威をのばしている。
西へ北へと、武士の勢力圏は拡大したのであった。 |
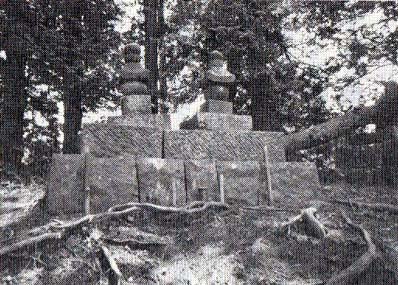
曾我兄弟の墓(小田原市下曾我、城前寺)
|
湯坂路と酒匂(さかわ)宿
足柄平野を貫流する丸子河(現酒匂川)は、中世末期まで流路が定まらず乱流し、常に氾濫を繰返していた。
石橋山の頼朝の敗戦も、大庭軍の渡河直後の台風と出水で、味方の三浦一族が渡河できなかったことが直接の原因であったといえなくもない。
もちろん、橋はなかった。
かの源義経が壇ノ浦で平家を滅亡させて凱旋して来た時、兄頼朝はその武功と声名を嫌い、義経の鎌倉入りを拒否した。
腰越まで来てもこれを京都に追い帰した。
この時、彼とその郎党たちは、酒匂宿で滞留し、兄の許しが得られるように交渉に日を送った。
このことから当時、酒匂がひとつの集落でありかなりの人馬を宿泊させうる能力をもっていたことを知ることができる。
鎌倉時代以前、足都と東国を結ぶ官道は、前章で述べた通り、足柄峠をこえていた。
峠の東側の坂本(関本)から松川付近で丸子河や川音川をわたり、千代・曾我付近から、ひとつは六本松峠をこえて中村・二宮・大磯へと通し、ひとつは海岸沿いに酒匂まで南下して東行していたようである。
ところが、鎌倉に武家政権の府が開かれると、京都政権との交渉や軍勢の上洛、御家人の大番役での上京と、両者間の交通量は激増した。
その後、伊豆の国府の三島から直接箱根山をこえる通路が開発整備された。湯坂路(ゆさかみち)と呼ばれる。
この道の整備には、将軍自身かあるいはその代理が毎年参詣する「二所詣」という行事との関りがあると思われる。
二所とは、挙兵の時の因縁浅からぬ箱根権現と走湯山権現であるが、これに三島大社への参詣をも含めて行なわれるのが通例であった。
『吾妻鏡』の記事を拾うと、将軍その他の公式旅行に見る「酒匂宿」の記事は、一一九〇(建久元)年の源頼朝のはじめての上洛以後、七回見出せる。
また「二所詣」は、頼朝・政子・実朝・藤原頼経(摂家将軍)北条泰時・頼嗣(摂家将軍)・示尊親王(親王将軍)など、将軍と執権のそれについて、代参を含めて四一回も見出せる。
さらに、一二三一(貞応二)年の『海道記』の作者、一二五三(建長五)年の藤原為家の下向(『夫木和歌集』)、一二七四(文永一一)年四日蓮の身延山行などにも記事があり、かの実朝の『金快和歌集』を見ると、彼が二所詣の折「下向に浜べの宿まへに前川という川あり」として一首を詠んでいる。
酒匂宿は浜部御所ともいわれていたが、前川の近くであるとすると、これを今日の「国府津付近の中村川」とする説もあるが、確固たる現在地を比定することは困難である。
筆者は、それより西の、今日の酒匂の八幡宮の近辺と考えてもよいと思っている。
一二七七(建治三)年阿仏尼(あぶつに)という女性は白子藤原為相の所領の播磨国細川庄が異母兄の為氏に押領された事件を訴訟で解決してもらおうと、はるばる鎌倉に下向して来た。
その時の印象をまとめたのがかの有名な『十六夜(いざよい)日記』であるが、その中で、足柄路は遠いから湯坂路をえらんだといい、「さかは」に泊った。
その時、おそらく今の早川河口辺から海岸沿いに来て「まり子川」を渡るのであるが、「あまの家のみぞある」その浦の名を人に問うても誰も知らないので、
“あまのすむ その里の名も しら浪の よする渚(なぎさ)に 宿やからまし”
と詠んだ。
これを信ずると、まだ丸子河西岸にはさしたる集落はなく、まして小田原という地名も普及していなかったと思われる。
かえって、左岸の酒匂の方が集落として発達していたのである。
今日の史料で、もっとも早く小田原という地名が見出されるのは、一二六五(文永二)年八月付の刀剣の銘であるといわれている。
それには「相州小田原住泰春」とある。阿仏尼の紀行文の記述と矛盾するようにも思えるが、大きな集落でなかったことだけは確実であろう。
南北朝の動乱
鎌倉時代の末期、足柄平野の御家人の所領の様子を見ると、全国的な現象ではあるが、惣領と庶子の対立が目立っている。
本来、鎌倉期には惣領が一族・庶子を掌握し、その統率のもとに軍役その他を勤めていた。
平時には庶子は所領内の各地に分布して経営に当り、農民から収奪する年貢その他も惣領のもとに集結させていた。
小早川一族を見ると、成田庄内の飯泉郷には飯泉景光という庶子の領有する四丁余の田地があったが、彼は惣領とは無関係にこの土地を妻に譲っている。
また北成田郷内の鶴丸名について、惣領の小早川茂平と庶子の竹三丸(定平)との間で、安芸国沼田庄の地頭幟の問題ともあわせて激しい相論(訴訟)が起っていた。
そしてこの係争は、成田庄藤太作屋敷田をめぐって、実に南北朝内乱期を通じて繰り返された。
先に述べたように、早河庄が惣領の所領とすると、庶子家が開発した成田庄内に、惣頷け統制を及ぼそうとし、これに対して庶子家は反発し、独立を目ざしているのがよく分る。
詳しいことは省くが、早河庄内一得名をもつ山内首藤氏でも事情は同じであった。
また豊後国大野庄に惣領が移住した大友氏でも、大和蓮景・詫磨(たくま)能秀という庶子と惣領親秀との間に対立がおこっている。
しかも、矢田与一というものに、謙倉幕府が新田義貞らによって倒滅される混乱の中で本領をのっとられてしまうという事態までおこっていた。
後醍醐天皇が、北条氏の得宗と御内人が権勢をほしいままにして御家人たちの不満を浴びている状況を利用して、正中の変をおこし、これには失敗したものの、つづく元弘の変でついに討幕に成功した経緯についてはここでは触れない。
が、足利高氏らが河内の楠木正成の赤坂城攻撃に上洛したこと、正中の変の責任者として日野俊基らが捕われて鎌倉に下向したこと、また元弘の変の初期に天皇の陰謀に加担した公卿の一人平成輔が、早川尻で斬首の刑に処せられたことなど、東海道を上下する軍勢兵士、あるいは貴族などがかもし出すあわただしい様子は、箱根山をひかえた酒匂・小田原周辺の住民にもじかに伝わったことであろう。
とくに天皇の建武中興が成立したものの、北条高時の遺子時行が旧臣に助けられて鎌倉を奪回し、そのために捕われの護良(もりなが)親王を殺した足利直義があわただしく脱出して三河国まで逃げた時には、これを助けるために兄の尊氏が天皇の許しを得ぬままに東下して時行軍を破った。
このいわゆる中先代(なかせんだい)の乱は、天皇の中興政治を瓦解せしめる直接の契機となった。
この時の尊氏の軍勢は、時行に味方した旧北条方の軍を、箱根水呑・葦河上・大平下・湯本地蔵堂で激破し、その夜は小田原上の山で野宿、翌日相模川辺、翌々日辻堂・片瀬で戦って鎌倉を奪回した。一三三五(建武二)年八月の一七日から一九日にかけてのことであった。
鎌倉を占領したのち尊氏は、天皇の召命に逆らって上京せず、そのため新田義貞らが官軍を引きつれ、海道で勝ちを収めながら箱根山に迫った。
その時官軍の一将大友貞載は、竹ノ下の戦で義貞を裏切り尊氏に味方した。
このため官軍は総くずれとなって京都に逃げかえるのであるが、この大友氏の裏切りは、先に触れたように、その本領の大友郷の支配の危機を切り抜けるための策であったろう。
武家政権の後継者としての尊氏に服属し、その陣営の一人であらねばならないと考えた武士の素直な姿である。
こうして尊氏は、武家政権の新らしい首長として、貴族政権の復活を夢見た後醍醐天皇の政府を倒し、室町幕府をスタートさせたのであった。
しかし、一族が分裂抗争している諸国の武士層を、まとめるには長い時間を要した。
それが南北朝の動乱とよばれる一四世紀中の約六〇年の歴史であるが、この時期にもうひとつ注目すべき社会現象がおきていた。
それは、荘園制という一〇世紀以来の土地領有体制の変質である。
すなわち、荘園を管理経営して来た武士層は、所領の拡大をねがって互いに戦い合う。
そこでその間の農業経営を維持するために直接生産者の立場を向上させ、これらを農業の専従者として所領経営に参加させる途を拓いたのであった。
そのため、作人とよばれた生産者層が力をもち、みずからのために団結するようになった。
そして彼らの反発に対抗するために領主たちは、党とか一揆とよばれる地域的な連合を遂げ、自分たちの階級的利益を代表し代弁する権力を支持し、その味方について、反対側と戦った。
南北朝の対立が、単に皇位の問題でなく、社会的動乱であったのは、このためである。
そして地域的な権力の頂点になったのは、室町幕府が任命した守護であった。
動乱は全国に広がっていたが特に東国の場合、謙倉公方・謙倉府という存在が、この情勢の激動に拍車をかけた。
大森氏と小田原
足利尊氏は、京都に幕府を開いた時、鎌倉の重要性に鑑(かんが)み、はじめ長子の義詮(よしあきら)、続いて次子の基氏(もとうじ)をここに公方(くぽう)としておき、上杉氏をその補佐とした。
基氏とその子孫を鎌倉公方又は関東公方、上杉氏を関東管領といい、その権力を鎌倉府という。
伊豆・甲斐二ヵ国のほか、関八州の八ヵ国計一〇ヵ国の守護の任命権その他をもち、機構は京都室町の幕府の機構にならう、一個の小幕府であった。
しかし、室町の将軍家もすべての権限を与えたのではなく、将軍と在地領主との間の主従制原理に由来する行為は保持し、一つの地域の統治権に属する権限を委譲していたといってよい。
ところが、尊氏が、もし京都の将軍の地位が危機に瀕(ひん)した時は、鎌倉公方が上京し代って権力を握れと遺命していたため、基氏以後、室町将軍家に対して鎌倉公方はつねに対立的であった。
中国地方と和泉堺をもつ大守護の大内氏が足利義満に反抗した応永の乱の時、公方足利満兼は挙兵して大内氏に呼応して将軍を倒そうとしたほどであった。
満兼の子の持氏が鎌倉公方となり、京都で義満のあと義持を経て義教が将軍となった頃、両者の対立は露骨なものとなった。
持氏は、義教が僧侶の身から還俗(げんぞく)して将軍となり、各地の強大な守護大名を圧迫した形勢のなかで、露骨に反抗した。
なかでも、一四一六(応永二三)年、かって持氏を補佐した管領の上杉氏憲が室町将軍の意向をうけて持氏に反旗をひるがえした時、持氏は京都の息のかかった東国の皇族や武士を徹底的に弾圧した。
禅秀は、上杉氏の中でも犬懸(いぬかけ)流であった。
上杉氏もまた一族が山内(やまのうち)・扇ヶ谷(おうぎがやつ)・大懸の三流に分れて対立していたのであるが、持氏が京都扶持衆とよばれた豪族たちを強圧する形勢の中で反乱をおこした。
氏憲は出家して禅秀といったので禅秀の乱という。
関東の各地の一揆や、小山氏などの豪族もこれに加わった。持氏の勢力が弱化することは、室町将軍家やその政権を支えている細川・斯波(しば)・畠山氏などの管領たちにとって願わしい。
しかし、持氏が禅秀側に負け、東国に足利氏に背反した政権が独立してしまっては困る。
はじめ禅秀らを陰から援けた京都側も、ついに駿河の守護今川氏を総大将として禅秀側を攻撃させた。将軍の後盾があると信じて味方した禅秀与力の武士たちはたちまち背反し、あっけなく、禅秀側は敗北し禅秀は自殺した。
乱ののち、持氏は反抗した前歴のある各地の豪族や武士を強圧したため、ついに一四三九(永享一一)年に永享の乱とよばれる内乱をおこすに至り、
持氏もまた今川氏を総大将とする大軍に攻められ自殺せざるを得なかった。
さて、この禅秀の乱の時、持氏が鎌倉から命からがら脱出して最初に身をよせたのが駿東の大森氏であり、さらにその働きで駿府の今川氏の館まで落ちのび、京都からの援軍の力を得て鎌倉を回復することができた。
従って戦後の論功行賞で、大森一族が大いに優遇されたのは当然であった。
大森氏は駿東郡の大森(裾野市)を本領とする鎌倉以来の御家人であり、大沼藍沢(あいざわ)御厨(みくりや、御殿揚市)を領有する領主であったが、鎌倉期の幕末には得宗の御内人であった。
一族に葛山(かつらやま)・御宿(みしゅく)・藤曲(ふじまがり)などの地名をもつ庶子があった。
また箱根権現に一族の一人を出家させて入山させ、この権現の最高の別当という地位をももっていた家である。
禅秀の乱で、相模の土肥氏・土屋氏などが禅秀に味方して敗れたため、そのあとを拝領して相模国の西部に進出して来た。
この時恩賞にあづかったのは大森頼春であった。
彼は相模国進出以前、伊豆国府中(三島)や箱根水呑(芦ノ湯)に関所を設け、通行する人馬から関銭を徴収してそれを寺社に請負って納入するだけの実力の持主であったが、「土肥・土屋のものどもの跡」を賜った。 |

土肥一族の墓
|
しかし、その「跡」が具体的に何処であったかは明らかでない。
ただ、いきなり小田原を本拠としたのではなく、南足柄市の沼田城や山北町の春日山城に拠ったらしい。
永享年代に入って公方持氏の命によって小田原に関を設け、その収入を鶴ヶ岡八幡宮に納入していたことが知られている。
それは、頼春の子憲頼の弟氏頼が家督をついでいた一三三二(永享四)年のことである。
頼秀の乱の直後、相模国の西部の狩野庄や小松郷など各地の田畠を本領ともいうべき御殿場の般若梵篋寺(はんにゃぼんきょうじ)に寄進している史料が残っているので、頼春(出家して道光)が相模国にはじめて進出したことは疑いない。
大森氏も一族がきちんと一本にまとまって行動していたとはいえない。
持氏が永享の乱で死んだあと、東国には主がなく混乱がつづいた。
のちに、その子成氏が擁立されたものの管領上杉憲実と対立し、そのため、足利政知が京都より伊豆国堀越に下向して来た。
成氏はこれをきらって下総国古河に移り、ここに古河(こが)公方と堀越(ほりこし)公方の対立、両者をそれぞれに推戴する領主層の対立で、東国一帯は混乱を極めるが、その間、大森氏の惣領は終始、堀越公方とその背後の室町将軍側であった。
それに対して、古河公方成氏に与力した一族もあり、必ずしも一族の行動は単純ではなかった。
相模国に進出してからの大森氏のうち、持氏の一字をもらって元服した信濃守氏頼が有名である。
寄栖庵(きさいあん)と号したが、彼の代に大森氏はもっとも強勢であった。
だが果して、北条氏が築城した現在の小田原城の地域に大森氏頼が築城したがどうかけ確認できない。
彼は管領扇谷上杉定正とその家宰太田道灌(どうかん)と結び、山内上杉の顕定の一派と対立して、よく西相模をおさえていた。
南足柄市の大雄山最乗寺の再建、湯河原町の保善院、早川の海蔵寺、久野の総世寺、箱根塔尹沢の阿弥陀寺の建立など、曹洞禅の普及に貢献した。
その中心をなした安聖禅師は、実にこの氏頼の伯父であった。
甥氏頼の物質的な保護と応援をうけて、これらの名刹を今日に遺したのである。
氏頼は一四九四(明応三)年に小田原で卒した。
その翌年、あとをついだ藤頼は、伊豆国でかの堀越公方政知の子茶々丸を殺してここに韮山城を築いていた伊勢長氏(いせながうじ、早雲庵宗瑞、ふつう北条早雲という)によって、小田原を奪われ、岡崎城(平塚市)に逃げた。
こうして小田原は、いよいよ後北条氏の時代を迎える。
大森時代の小田原について、築城や町の建設その他にいろいろな説が主張されている。 |
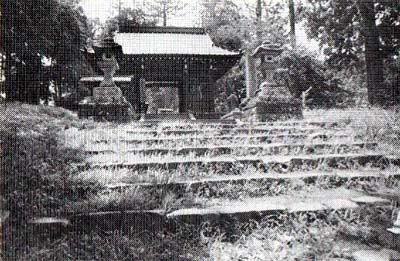
大雄山最乗寺山門
|
しかし、少なくとも信頼に値する史料を科学的に検討する限り、小田原の関の在り場所もその機能もよく分らない。
大森氏の小田原城というものは場所も結構も、存在自体すら謎につつまれているのである。
top
****************************************
|