|
|
|
|
![]()
ƒpƒ`ƒ“ƒRچD‚«‚âپB چ²‹vٹش›{
چ،‰ٌ‚جک^‰¹‚حپA2018”N11Œژ29“ْ‚ئ30“ْ‚ةƒtƒ‰ƒ“ƒNƒtƒ‹ƒg‚جƒ[ƒ“ƒfƒUپ[ƒ‹‚إچs‚ي‚ꂽƒRƒ“ƒTپ[ƒgŒ`ژ®‚جڈم‰‰‚ًژûک^‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌپAژہچغ‚جƒRƒ“ƒTپ[ƒg‚ج‘OŒم‚ة‚à“¯‚¶ڈêڈٹ‚إƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ک^‰¹‚àچs‚ي‚ê‚ؤپA‚»‚ê‚ç‚جƒeƒCƒN‚ً•زڈW‚µ‚½‚à‚ج‚ھچإڈI“I‚بگ»•i‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAڈي“…ژè’i‚إ‚·پB ‚±‚جƒIƒyƒ‰‚حپA•پ’ت‚ة‰‰‘t‚·‚é‚ئ‚Qژٹش‚ً’´‚¦‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚جک^‰¹‚حƒgپ[ƒ^ƒ‹‚إ‚Pژٹش56•ھ‚ظ‚ا‚إ‚·پB‚»‚ê‚حپA‚±‚جڈم‰‰‚إ‚حƒoƒCƒچƒCƒg‚جƒJƒ^ƒٹپ[ƒiپEƒڈپ[ƒOƒiپ[‚ھپuƒhƒ‰ƒ}ƒgƒDƒ‹ƒNپv‚ئ‚µ‚ؤژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚·پB”قڈ—‚حپA‚±‚جƒWƒ“ƒNƒVƒ…ƒsپ[ƒ‹‚إ–{—ˆ‚ح‰‰‚¶‚ç‚ê‚éƒZƒٹƒt‚ج•”•ھ‚ًپA’Z‚¢ƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ة’u‚«ٹ·‚¦‚½پA‚¢‚ي‚خپuƒtƒ‰ƒ“ƒNƒtƒ‹ƒg”إپv‚ًژg‚ء‚ؤڈم‰‰‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‚½‚ك‚ةپA‘S‘ج‚جڈم‰‰ژٹش‚à‚±‚ٌ‚ب‚ة’Z‚‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ثپB ‚»‚جƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ج‘ن–{‚حپAƒJƒ^ƒٹپ[ƒi‚ئپAƒoƒCƒچƒCƒg‚إ”قڈ—‚ج‰‰ڈo‚جچغ‚جƒhƒ‰ƒ}ƒgƒDƒ‹ƒN‚ً–±‚ك‚ؤ‚¢‚éƒ_ƒjƒGƒ‹پEƒEƒFپ[ƒoپ[پiگVچ‘‚إ‚جƒJƒ^ƒٹپ[ƒi‰‰ڈo‚جپuƒtƒBƒfƒٹƒIپv‚إ‚à“¯‚¶ƒ|ƒXƒgپj‚ھ‹¤“¯‚إژ·•M‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤڈo—ˆڈم‚ھ‚ء‚½‚ج‚حپAŒ³پXƒZƒٹƒt–ً‚¾‚ء‚½ƒUƒ~ƒGƒ‹‚ئپAچإŒم‚جڈê‚ة‚¾‚¯“oڈê‚·‚éپu‰Bژزپv‚ئ‚ج“ٌگl‚ھپA“K‹X–{—ˆ‚جƒZƒٹƒt‚ً—v–ٌ‚µ‚½ƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ًŒê‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB‚µ‚©‚àپA‚»‚جƒUƒ~ƒGƒ‹‚حپAŒ³پX‚حپuˆ«–‚پv‚ب‚ج‚إ‹^‚¢‚à‚ب‚’jگ«‚¾‚ء‚½‚à‚ج‚ًپu–‚–@ژg‚¢‚ج‚¨‚خ‚ ‚³‚ٌپv‚ة•د‚¦پA‚±‚±‚إ‚»‚ê‚ً‰‰‚¶‚ؤ‚¢‚éƒRƒٹƒ“ƒiپEƒLƒ‹ƒqƒzƒt‚ئ‚¢‚¤—L–¼‚بڈ——D‚³‚ٌ‚ھپA‚µ‚ي‚ھ‚êگ؛‚إŒê‚é‚ئ‚¢‚¤گف’è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚¤‚¢‚¦‚خپAچً”N“ٌٹْ‰ï‚ھ‚±‚جƒIƒyƒ‰‚ًڈم‰‰‚µ‚½ژ‚àپA‰‰ڈo‚جƒyپ[ƒ^پ[پEƒRƒ“ƒ”ƒBƒ`ƒ…ƒjپ[‚ھƒUƒ~ƒGƒ‹‚ةڈ—گ«‚ًƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒO‚µ‚ؤپA“oڈêڈê–ت‚à‘ه•‚ةٹg‘ه‚µ‚½ƒvƒ‰ƒ“‚ًچج—p‚µ‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB‚»‚µ‚ؤپA‰Bژز‚ج•û‚حپAچإŒم‚ة‰ج‚¤‚ئ‚±‚낾‚¯‚ح–{—ˆ‚جƒ[پ[ƒٹƒq‚ھ‰ج‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ح•ت‚جگl‚ھچإڈ‰‚©‚çٹç‚ًڈo‚·‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إ‚·پB ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپA‚±‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚©‚ç‚حپA‚ ‚éˆس–،ƒ~ƒ…پ[ƒWƒJƒ‹‚ج‚و‚¤‚بƒZƒٹƒt‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤپA‰¹ٹy‚ج‚ف‚ھƒXƒgƒŒپ[ƒg‚ة’®‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚ پA‚»‚ê‚ح‚»‚ê‚إ‚½‚¾’®‚•ھ‚ة‚ح‰½‚ج–â‘è‚à‚ب‚¢‚¾‚낤‚ئ‚حژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA’®‚«ڈI‚¦‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‚©‚آ‚ؤƒJƒCƒ‹ƒxƒ‹ƒg‚ج‘S‹ب”ص‚ً’®‚¢‚½ژ‚ة–،‚ي‚¦‚½پuƒhƒCƒc“I‚بƒIƒyƒ‰پvپAŒ¾‚¢ٹ·‚¦‚ê‚خپu“cژةژإ‹ڈپv‚ج•µˆح‹C‚ح‚±‚±‚©‚ç‚حٹ®àّ‚ةڈء‚¦‹ژ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚حپAŒ¾‚¢ٹ·‚¦‚ê‚خ“ْ–{Œê‚إ‚جپu–‚’e‚جژثژèپv‚ئ‚¢‚¤ŒأڈL‚¢–َŒê‚ج’†‚ة‘ƒ‚‚ء‚ؤ‚¢‚éƒNƒ‰ƒVƒbƒNٹE‚جƒXƒmƒrƒYƒ€‚ھپA‚±‚±‚إ‚حٹ´‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ‚»‚¤‚ب‚ê‚خپA‚»‚ٌ‚ب‹آپX‚µ‚¢‚à‚ج‚ً’E‚¬ژج‚ؤ‚½ƒXƒ}پ[ƒg‚بپuƒtƒ‰ƒCƒVƒ…ƒbƒcپv‚ً‘¶•ھ‚ةٹy‚µ‚ق‚±‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤‚©پBƒ„ƒmƒtƒXƒL‚جژwٹِ‚ش‚è‚حپA‚ئ‚ؤ‚àŒy‰ُ‚إپAپuƒچƒ}ƒ“”hپv‚ئ‚¢‚¤ٹ´‚¶‚إ‚ح‚ب‚پuƒoƒچƒbƒNپv‚جگ¶‚«گ¶‚«‚ئ‚µ‚½ƒeƒCƒXƒg‚³‚¦ٹ´‚¶‚ç‚ê‚é‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚ب‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àƒ‰ƒCƒvƒcƒBƒq•ْ‘—چ‡ڈ¥’c‚جچ‡ڈ¥‚جƒXƒ}پ[ƒg‚ب‚±‚ئپBپuژëگl‚جچ‡ڈ¥پv‚ب‚ا‚حپA‚ي‚´‚ئپu“cژة‚‚³‚¢پv‰ج‚¢•û‚ً“ü‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA“s‰ïگl‚جƒZƒ“ƒX‚ج—ا‚³‚¾‚¯‚ھ–ع—§‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئ‚¢‚¤ƒJƒbƒR‚و‚³‚إ‚·پB ƒ\ƒٹƒXƒg‚إ‚ح‚â‚ح‚èƒ_ƒ”ƒBƒhƒZƒ“‚جچ‚‹M‚³‚³‚¦•Y‚¤ƒAƒKپ[ƒe‚ح‘fگ°‚炵‚©‚ء‚½‚إ‚·‚ثپBƒGƒ“ƒqƒFƒ“‚جƒtƒHƒ~ƒi‚àگL‚ر‚â‚©‚بگ؛‚ھ”ü‚µ‚©‚ء‚½‚إ‚·پBƒ}ƒbƒNƒX–ً‚جƒVƒƒپ[ƒKپ[‚àپA‚â‚ح‚èچ،‚جژ‘م‚جƒeƒmپ[ƒ‹‚إ‚·‚ثپBƒLƒ‹ƒqƒzƒt‚جƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚©‚ç‚حپA‚ب‚؛‚©پu–‚“Jپv‚جƒpƒpƒQپ[ƒi‚ھکV”k‚ة•¯‚·‚éƒVپ[ƒ“‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپAچ،‰ٌ‚جک^‰¹‚ةژQ‰ء‚µ‚½ƒپƒ“ƒoپ[‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ھ‚»‚جN‹؟‚جƒRƒ“ƒTپ[ƒg‚ئڈd‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚ ‚½‚è‚ھپA‚ـ‚¾‚ـ‚¾“ء’è‚ج‰‰‘t‰ئ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚µ‚©“éگُ‚ف‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہ‚ًکI’و‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB ‚آ‚ـ‚èپAچ،‰ٌ‚جک^‰¹‚إ‚جƒ\ƒٹƒXƒg‚ھپAƒ\ƒvƒ‰ƒm‚àƒoƒٹƒgƒ“‚à‚ئ‚à‚ةN‹؟‚إ‰ج‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒ‹ƒTƒlƒ“ژo’ي‚إ‚·‚µپAچ‡ڈ¥‚à‚»‚جژ‚جƒGƒXƒgƒjƒAچ‘—§’jگ؛چ‡ڈ¥’c‚ب‚ج‚إ‚·‚وپB‚µ‚©‚µپAچ،‰ٌ‚ح‚»‚جچ‡ڈ¥‚ھپA‚³‚ç‚ة‚à‚¤ˆê‘g‰ء‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ح’nŒ³ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‚جپuƒ|ƒٹƒeƒNچ‡ڈ¥’cپv‚إ‚·پB‚±‚جچ‡ڈ¥’c‚حپA2017”N‚ةچ،‰ٌ‚جژwٹِژزƒٹƒ“ƒgƒD‚ھ—ˆ“ْ‚µ‚ؤ“Œ‹“sŒً‹؟ٹy’cپi‚آ‚ـ‚èپA1974”N‚ة“n糋إ—Y‚ئ‚±‚جچى•i‚ج“ْ–{ڈ‰‰‰‚ًچs‚ء‚½ƒIپ[ƒPƒXƒgƒ‰پj‚ئ‚±‚جچى•i‚ً‰‰‘t‚µ‚½ژ‚جچ‡ڈ¥’c‚إ‚µ‚½پB ‚؟‚ب‚ف‚ةپA‚±‚جچ‡ڈ¥’c‚حپA1996”N‚ةک^‰¹‚³‚ꂽƒTƒ‰ƒXƒe”ص‚ة‚àژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚جژ‚حپuƒwƒ‹ƒVƒ“ƒLچH‰ب‘هٹw’jگ؛چ‡ڈ¥’cپv‚ئ‚¢‚¤ƒNƒŒƒWƒbƒg‚إ‚µ‚½‚ثپB‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚¢‚¸‚ê‚à“¯‚¶چ‡ڈ¥’c‚إ‚·پB ‚ا‚؟‚ç‚جچ‡ڈ¥’c‚àپu’jگ؛پvچ‡ڈ¥’c‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚جCD‚ج‘ر‚إ‚ح‚±‚ٌ‚ب•—‚ةڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB  ‚ب‚ٌ‚©پA‚¢‚«‚ب‚è‚ب‚و‚ب‚و‚µ‚½ƒCƒپپ[ƒW‚ھ—N‚¢‚ؤ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚©پHپu‚¨‚ء‚³‚ٌ‚¸ƒ‰ƒuپv‚ف‚½‚¢‚بپB‚â‚ح‚èپA‚±‚جژڑ–ت‚إ‚حپA’jگ؛چ‡ڈ¥‚جژ‚آ—ح‹‚³‚ح“`‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚ثپB ‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚جپuƒNƒbƒŒƒ‹ƒ”ƒHپv‚إ—v‹پ‚³‚ê‚é’jگ؛چ‡ڈ¥‚حپA’P‚ةپu—ح‹‚¢پv‚¾‚¯‚إ‚ح‚·‚ـ‚³‚ê‚ب‚¢پA‚à‚ء‚ئچ‚“x‚جƒXƒLƒ‹‚ھ—v‹پ‚³‚ê‚é‚ح‚¸‚إ‚·پB ”ق‚ç‚ھ“oڈê‚·‚é‚ج‚حپA‘و‚Rٹyڈح‚ئچإŒم‚ج‘و‚TٹyڈحپA‚»‚ꂼ‚ê‚ةپu•¨Œêپv‚جŒê‚è•”‚ئ‚µ‚ؤپA”ٌڈي‚ةڈd—v‚ب–ً–ع‚ً’S‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“ء‚ةپA‘و‚Tٹyڈح‚جپuƒNƒbƒŒƒ‹ƒ”ƒH‚جژ€پv‚إ‚حپA‘O”¼‚ح‚ئ‚ؤ‚à‚ب‚ك‚ç‚©‚بڈîٹ´‚ً’X‚¦‚½چ‡ڈ¥‚ھ‰ج‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپA‰¹ٹy‚ھگ·‚èڈم‚ھ‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إŒ}‚¦‚éƒQƒlƒ‰ƒ‹پEƒpƒEƒ[پi‚±‚ê‚حپA‚ئ‚ؤ‚àƒVƒ‡ƒbƒLƒ“ƒOپj‚جŒم‚إ‚حپA‚»‚ج—l‘ٹ‚ھˆê•د‚µ‚ؤپA–\—ح“I‚إ‚·‚ç‚ ‚錃‚µ‚³‚ـ‚إ—v‹پ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB چ،‰ٌ‚جچ‡ڈ¥‚حپA‚Q‚آ‚جچ‡ڈ¥’c‚جڈW‚ـ‚è‚إ‚ ‚éٹ„‚ة‚حپA‚»‚ê‚ظ‚ا‚جڈd—تٹ´‚ح‚ب‚پA‚©‚ب‚è‘@چׂبˆَڈغ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‘و‚Rٹyڈح‚جچإڈ‰‚ج‚±‚ë‚حƒ†ƒjƒ]ƒ“‚¾‚¯‚إ‰ج‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚çپA‚ ‚ـ‚èٹ´ڈî‚ًچ‚ك‚¸‚ة’WپX‚ئ‰ج‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·پB‚»‚ê‚ھپA‘و‚Tٹyڈح‚جŒم”¼‚إ‚حپA‹°‚낵‚¢‚ـ‚إ‚ج”——ح‚إ”—‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚ة‚ح‹ء‚«‚ـ‚µ‚½پB•\Œ»‚جƒLƒƒƒpƒVƒeƒB‚ھ”ٌڈي‚ة‘ه‚«‚¢‚ج‚إ‚·‚ثپB‚»‚ê‚ئپA‚â‚ح‚èƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‚âƒGƒXƒgƒjƒA‚ئ‚¢‚ء‚½چ‘‚ةˆç‚ء‚½گl‚إ‚ب‚¯‚ê‚خ‰ج‚¦‚ب‚¢“ء•ت‚جپu–،پv‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB ƒ\ƒٹƒXƒg‚إ‚حپA‚â‚ح‚èƒ\ƒvƒ‰ƒm‚جƒˆƒnƒ“ƒiپEƒ‹ƒTƒlƒ“‚ج”——ح‚ة‚حˆ³“|‚³‚ê‚ـ‚·پBN‹؟‚جƒ‰ƒCƒu‰f‘œ‚إ‚àپA‚»‚ج‘¶چفٹ´ˆى‚ê‚é‘ج‚©‚çگ¶‚ـ‚ê‚éگ؛‚ة‚حپA‘fگ°‚炵‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ة”ن‚ׂé‚ئƒoƒٹƒgƒ“‚جƒ”ƒBƒbƒŒ‚‚ٌ‚حپA‚؟‚ه‚ء‚ئ‚¨‚ئ‚ب‚µ–عپB ƒٹƒ“ƒgƒD‚جژwٹِ‚حپA‚±‚جژلڈ‘‚«‚جچى•i‚جڈ‰پX‚µ‚³‚ً‘هگط‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB‚»‚ج‚¹‚¢‚©پAƒIپ[ƒPƒXƒgƒ‰‚¾‚¯‚ج‘و‚Sٹyڈح‚ھƒeƒ“ƒ|‚à‘¬‚پA‚±‚ج”كŒ€“I‚بچى•i‚ج’†‚إ‚حپA‚؟‚ه‚ء‚ئˆلکaٹ´‚ً”؛‚¤‚©‚ب‚è—z‹C‚ب‰¹ٹy‚ة’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚¨‚»‚ç‚پA‚»‚ê‚حˆسگ}‚µ‚ؤ‚»‚ج‚و‚¤‚ب•\Œ»‚ً‚ئ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ک^‰¹‚حپAƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ•¨‘«‚è‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپi‘½•ھƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ک^‰¹‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپAچ‡ڈ¥‚ً‚à‚¤‚·‚±‚µچL‚°‚ؤ—~‚µ‚©‚ء‚½پjپA‰¹‚ج‰ً‘œ“x‚ح‚©‚ب‚è‚‚ء‚«‚肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚إ‚·‚©‚çپA‘و‚Rٹyڈح‚ج“ھ‚إƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹‚ھکA‘إ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‚و‚•ھ‚©‚è‚ـ‚·پBچإڈ‰‚ة‹“‚°‚½ƒ”ƒ@ƒ“ƒXƒJ‚جک^‰¹‚إ‚ح‚»‚ج‰¹‚ج—±‚ھ‚آ‚ش‚ê‚ؤ‚¢‚ؤ‘S‘R•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚©‚ç‚ثپB SACD Artwork © Ondine Oy |
||||||
‚±‚جƒVƒٹپ[ƒY‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA‘Oچى‚إ‚حپA—ل‚¦‚خپuƒwƒ“ƒfƒ‹‚جƒXƒ^ƒCƒ‹‚ة‚و‚éƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒgƒOƒچƒbƒ\‘و‚P”شپv‚ج‚و‚¤‚ةپA‹ï‘ج“I‚بŒ³ƒlƒ^‚ً’ٌژ¦‚µ‚ب‚¢‚إپA‚»‚±‚ةƒrپ[ƒgƒ‹ƒY‚ج‹ب‚ً“–‚ؤ‚ح‚ك‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBچ،‰ٌ‚حپA‚»‚جگ¸“x‚ھ‚³‚ç‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤپAƒoƒbƒn‚ئƒ”ƒBƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB‚ج‚»‚ꂼ‚ê‚جچى•i‚ً‚µ‚ء‚©‚è’ٌژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚çپA‚»‚جٹy‚µ‚³‚ح‚³‚ç‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚ـ‚¸‚حپA‚¢‚«‚ب‚èƒsƒAƒm‚جƒ\ƒچ‚ھŒ»‚ê‚é‚ج‚إپAپu‚ب‚ٌ‚إƒoƒچƒbƒN‚إƒsƒAƒmپHپv‚ئژv‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ê‚حƒoƒbƒn‚جپuƒsƒAƒm‹¦‘t‹بƒj’Z’²پiBWV1052پjپv‚ھŒ³ƒlƒ^‚¾‚©‚ç‚إ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌپAƒoƒbƒn‚جژ‘م‚إ‚حƒ`ƒFƒ“ƒoƒچ‚ھژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپAŒ»‘م‚إ‚ح‚»‚ê‚ًƒsƒAƒm‚إ‰‰‘t‚·‚邱‚ئ‚à‚ـ‚ê‚ة‚ ‚è‚ـ‚·‚©‚ç‚ثپB‚»‚ج‘و1ٹyڈح‚إژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éƒrپ[ƒgƒ‹ƒYپEƒiƒ“ƒoپ[‚ھپAپuAbbey Roadپv‚جƒIپ[ƒvƒjƒ“ƒO‚ًڈü‚ء‚ؤ‚¢‚½پuCome Togetherپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ةپA‚ـ‚¸‹ء‚©‚³‚ê‚ـ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚àپA‚±‚جژè‚ج•ز‹ب‚à‚ج‚إ‚حپA‚ب‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àƒپƒچƒfƒB‚ج”ü‚µ‚¢‹ب‚ھ‘I‚خ‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚ج‚ةپA‚±‚ج‹ب‚إ‚ح‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚و‚è‚حپAپuƒٹƒtپv‚ئ‚¢‚¤پA“ء’è‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ًŒJ‚è•ش‚·‚à‚ج‚ھڈd—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚·پB‚ئ‚±‚ë‚ھپA‚»‚جپuƒٹƒtپv‚ھپA‚±‚±‚إ‚حƒoƒbƒn‚ھ‚±‚ج‹ب‚ة—p‚¢‚½پuƒIƒXƒeƒBƒiپ[ƒgپv‚ةپAŒ©ژ–‚ة“¯ˆê‰»‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB‚ب‚ٌ‚ئ‚¢‚¤ژaگV‚بƒAƒvƒچپ[ƒ`پB ‚إ‚·‚©‚çپA‚à‚ج‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اƒپƒچƒfƒB‚ج—قژ—گ«‚ب‚ا‚حٹ´‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢‚à‚ج‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خپAپuWhile My Guitar Gently Weepsپv‚ًپuƒuƒ‰ƒ“ƒfƒ“ƒuƒ‹ƒN‹¦‘t‹ب‘و2”شپv‚ج‘و2ٹyڈح‚ة‚ح‚كچ‚ٌ‚¾‚à‚ج‚ب‚ا‚حپA’ل‰¹‚جگiچs‚¾‚¯‚ً—ٹ‚è‚ة•ز‹ب‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚çپAŒ¾‚ي‚ê‚ب‚¯‚ê‚خ‚»‚جˆّ—p‚ح‚ـ‚¸•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ئ‚¢‚¤‚©پA‚»‚±‚إ’®‚«ژè‚جپuƒrپ[ƒgƒ‹ƒY“xپv‚ھژژ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚وپB ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAƒuƒŒƒCƒiپ[ژ©گg‚àپA‚©‚ب‚è‚جپuƒrپ[ƒgƒ‹پEƒ}ƒjƒAپv‚إ‚ ‚邱‚ئ‚àپA‚و‚•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB‚·‚²‚¢‚ج‚حپAپuƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‹¦‘t‹بƒC’Z’²پiBWV1041پjپv‚ج‘و2ٹyڈح‚ة‚ح‚كچ‚ٌ‚¾پuSomethingپv‚إ‚·پB‚»‚±‚إ‚حپAƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‚جƒ\ƒٹƒXƒg‚ھپAƒWƒ‡پ[ƒWپEƒnƒٹƒXƒ“‚جƒ\ƒچ‚ًٹ®ƒRƒs‚µ‚ؤ’e‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚ç‚ثپB ‚±‚ج‚و‚¤‚ةپA‚±‚±‚إ‚حپuAbbey Roadپv‚©‚ç‚جˆّ—p‚ھ‘½گ”چs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‚â‚ح‚èچ،‰ٌ‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚ھƒٹƒٹپ[ƒX‚³‚ꂽ2019”N‚ھپA‚»‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚جƒٹƒٹپ[ƒX‚ج50ژü”N‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ب‚ٌ‚¹پAپuB–تƒپƒhƒŒپ[پv‚جŒم”¼‚ب‚ا‚ئ‚¢‚¤ƒ}ƒjƒAƒbƒN‚ب‚à‚ج‚ـ‚إپA‚à‚ح‚âƒoƒbƒn‚⃔ƒBƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB‚ً—£‚ê‚ؤپAƒoƒچƒbƒN•—‚جٹ®ƒRƒs‚¾‚¯‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚ç‚ثپBپuThe Endپv‚إ‚حپAƒٹƒ“ƒSپEƒXƒ^پ[‚جƒhƒ‰ƒ€پEƒ\ƒچ‚ًƒ`ƒFƒ“ƒoƒچ‚ھ‘م‚ي‚è‚ة‰‰‘t‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚µپA‘±‚3گl‚جƒMƒ^پ[پEƒoƒgƒ‹‚àپA‰تٹ¸‚ةƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‚إچؤŒ»‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ة‘±‚پuHer Majestyپv‚ًپuƒuƒ‰ƒ“ƒfƒ“ƒuƒ‹ƒN‹¦‘t‹ب‘و3”شپv‚ج’†‚إ’®‚©‚¹‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA‚»‚جƒGƒ“ƒfƒBƒ“ƒO‚إ‚حƒ`ƒFƒ“ƒoƒچ‚ھپuLet It Beپv‚جƒAƒEƒgƒچ‚ًپAچإŒم‚جڈIژ~Œ`‚جˆê‚آ‘O‚جƒRپ[ƒh‚ـ‚إ’e‚¢‚ؤپAژ~‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حˆس–،گ[‚إ‚·‚ثپB ‚½‚¾پA‚±‚ꂾ‚¯‚ج‚±‚ئ‚ً‚â‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©‚çپAپuAbbey Roadپv‚جژc‚è‚ج‹ب‚à‘S•”ژg‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚©‚ء‚½‚إ‚·‚ثپB“¯‚¶ƒoƒbƒn‚جپuƒچ’Z’²ƒ~ƒTپv‚جƒpƒچƒfƒB‚ھپA‚»‚ê‚ظ‚اٹy‚µ‚ك‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚©‚çپB Œآگl“I‚ةˆê”ش‹C‚ة“ü‚ء‚½‚ج‚حپAƒ”ƒBƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB‚جپuژl‹Gپv‚جپuڈHپv‚ج‘و2ٹyڈح‚ةپAپuBecauseپv‚ً‚ح‚كچ‚ٌ‚¾ƒgƒ‰ƒbƒN‚إ‚·پB‚¢‚âپA‚±‚ê‚حƒCƒ“ƒgƒچ‚جƒ`ƒFƒ“ƒoƒچ‚©‚炵‚ؤپAپuBecauseپv‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پB‚à‚µ‚©‚µ‚ؤپAƒpƒN‚ء‚½‚ج‚حƒ”ƒBƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒB‚ج•ûپH CD Artwork © Naxos Rights(Europe)Ltd |
||||||
‚»‚±‚إپAگe‰ïژذ‚إ‚ح‚·‚إ‚ة10”N‘O‚ةپuCD—£‚êپv‚جگ錾‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پBCDپA‚ ‚é‚¢‚حSACD‚جچؤگ¶‹@ٹي‚ح‘S‚ؤگ¶ژY‚ًڈI—¹‚µپAچؤگ¶‰¹Œ¹‚حLP‚ئƒfƒWƒ^ƒ‹پEƒfپ[ƒ^‚ج‚ف‚ة‚·‚é‚ئ‚¢‚¤گ錾‚إ‚·پBŒ»چف‚إ‚حپAƒ\پ[ƒX‹@ٹي‚ئ‚µ‚ؤ‚حƒlƒbƒgƒڈپ[ƒNپEƒ~ƒ…پ[ƒWƒbƒNپEƒvƒŒپ[ƒ„پ[‚ئƒ^پ[ƒ“ƒeپ[ƒuƒ‹‚µ‚©گ»‘¢‚µ‚ؤ‚¨‚炸پACDƒvƒŒپ[ƒ„پ[‚ح•”•i‚جچفŒة‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ً——R‚ة‰ك‹ژ‚ة”ج”„‚µ‚½‹@ٹي‚جڈC—‚·‚ç‚àژَ‚¯•t‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‘جگ§‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚ٌ‚بڈَ‹µ‚إ‚حپALINN RECORDS‚ئ‚µ‚ؤ‚حCD‚ً”ج”„‚·‚邱‚ئ‚³‚¦œف‚ç‚ê‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA‚ـ‚µ‚ؤSACD‚ب‚ا‚ًڈo‚¹‚é‚ح‚¸‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ثپB‚½‚¾پA‚à‚؟‚ë‚ٌپuƒlƒbƒgپEƒIپ[ƒfƒBƒIپvŒü‚¯‚جƒfپ[ƒ^‚حپA‚µ‚ء‚©‚è”zگM‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA2ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚إ‚جƒnƒCƒŒƒ]‰¹Œ¹‚ح“üژè‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپAƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‰¹Œ¹‚ح“üژè‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚³‚ç‚ةپASACD‚ج“üژè‚à‚à‚ح‚â•s‰آ”\‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚حپAƒTƒ‰ƒEƒ“ƒhچؤگ¶‚ج“¹‚حٹ®‘S‚ة’f‚½‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚»‚ٌ‚ب•—‚ةپuƒ_ƒپپv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½LINNƒŒپ[ƒxƒ‹‚إ‚·‚©‚çپA‚à‚¤‰½‚ج–£—ح‚àٹ´‚¶‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAƒeƒBƒ`ƒAپ[ƒeƒB‚ھƒfƒ…ƒٹƒ…ƒtƒŒ‚جپuƒŒƒNƒCƒGƒ€پv‚ًک^‰¹‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚µ‚½‚çپA’®‚¢‚ؤ‚ف‚ب‚¢‚ي‚¯‚ة‚ح‚¢‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپA‹v‚µ‚ش‚è‚ة‚»‚جƒpƒbƒPپ[ƒW‚ًژè‚ة‚µ‚½ژ‚ة‚حپA‚³‚ç‚ب‚é‹ء‚«‚ھ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جƒŒپ[ƒxƒ‹‚حپA‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©OUTHEREپiƒAƒEƒgƒqƒAپj‚جژP‰؛‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ثپBچإ‹ك‚إ‚حALPHAƒŒپ[ƒxƒ‹‚ً‹zژû‚µ‚ؤ‘ه–ôگi‚ًگ}‚ء‚ؤ‚¢‚éƒtƒ‰ƒ“ƒX‚جƒŒپ[ƒxƒ‹OUTHERE‚إ‚·‚ھپALINN‚ح‚»‚±‚جƒTƒuƒŒپ[ƒxƒ‹‚ةگ¬‚è‰؛‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB‚©‚آ‚ؤ‚حSACD‚ًŒ،ˆّ‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒŒپ[ƒxƒ‹‚¾‚ء‚½‚¾‚¯‚ةپA‚±‚ٌ‚بژc”O‚ب‚±‚ئ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‹ئٹE‚إ‚حپA‚à‚ح‚âپASACD‚حپuگâ–إٹ뜜ژيپv‚ئˆ‰‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB‚ ‚éˆس–،پAƒnƒCƒŒƒ]‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒXƒyƒbƒN‚ة‚ح•sڈ\•ھ‚ب‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚©‚çپA‚»‚ê‚àژd•û‚ج‚ب‚¢‚±‚ئ‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپEپEپEپB چ،‰ٌ‚جƒeƒBƒ`ƒAپ[ƒeƒB‚جƒfƒ…ƒٹƒ…ƒtƒŒ‚حپAƒhƒrƒ…ƒbƒVپ[‚جپu–é‘z‹بپv‚ئ‚جƒJƒbƒvƒٹƒ“ƒO‚إ‚µ‚½پB‚»‚جƒhƒrƒ…ƒbƒVپ[‚حپA‚ب‚ٌ‚ئ‚à”ق‚炵‚‚ب‚¢‚ا‚ٌ‚‚³‚¢ژdڈم‚ھ‚è‚إ‚µ‚½پB‚¢‚©‚ة‚àƒhƒCƒc‚جƒIپ[ƒPƒXƒgƒ‰‚炵‚¢گ¶گ^–ت–ع‚بƒeƒ“ƒ|ٹ´‚ًپA‘S‚•¥گ@‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپBˆب‘O’®‚¢‚½ƒXƒRƒbƒgƒ‰ƒ“ƒhژ؛“àٹاŒ·ٹy’c‚ئ‚جپuŒ¶‘zپv‚جگ¶پX‚µ‚³‚ب‚اپA‚ا‚±‚ة‚àŒ©“–‚½‚è‚ـ‚¹‚ٌپB”ق‚ھ‚±‚جƒxƒ‹ƒٹƒ“پEƒhƒCƒcŒً‹؟ٹy’cپi‚©‚آ‚ؤ‚جRIAS•ْ‘—Œً‹؟ٹy’cپj‚جƒVƒFƒt‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚Q”NˆبڈمŒo‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚ـ‚¾ژ©•ھ‚جگF‚ًڈo‚·‚ئ‚±‚ë‚ـ‚إ‚ح’B‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ‚½‚¾پA‚»‚ٌ‚ب‘ق‹ü‚بپu–é‘z‹بپv‚ھپAچإŒم‚جپuƒVƒŒپ[ƒkپv‚إڈ—گ؛چ‡ڈ¥‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚‚é‚ئپA‰â‘R–£—ح“I‚ب‰¹ٹy‚ة•د‚ي‚é‚ج‚ح‚¨‚à‚µ‚êپ[‚تپB‚»‚جڈ_‚ç‚©‚ب‹؟‚«‚ً’®‚‚ئپA‚±‚±‚إ‚جچ‡ڈ¥’cپAƒxƒ‹ƒٹƒ“•ْ‘—چ‡ڈ¥’c‚ةƒTƒCƒ‚ƒ“پEƒnƒ‹ƒWپ[‚جŒم”C‚ئ‚µ‚ؤپA2015”N‚©‚çژٌگبژwٹِژز‚ةڈA”C‚µ‚½پA1978”Nگ¶‚ـ‚ê‚جƒwƒCƒXپEƒŒپ[ƒiپ[ƒX‚ئ‚¢‚¤گl‚حپA‚±‚جچ‡ڈ¥’c‚جƒŒƒxƒ‹‚جˆغژپA‚¢‚âپAŒüڈم‚ة‚حچvŒ£‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·پB ‚إ‚·‚©‚çپA‚±‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚جƒپƒCƒ“پAƒfƒ…ƒٹƒ…ƒtƒŒ‚جپuƒŒƒNƒCƒGƒ€پv‚àپA‚»‚جچ‡ڈ¥’c‚ج‘fگ°‚炵‚¢‰‰‘t‚ھ’®‚¯‚½‚ج‚ة‚حپAٹى‚ر‚à‚ذ‚ئ‚µ‚¨‚إ‚·پB‚»‚ê‚حپA‚ئ‚ؤ‚àگô—û‚³‚ꂽپA‚ـ‚³‚ةپu‘هگl‚جپvچ‡ڈ¥‚إ‚µ‚½پBƒeƒBƒ`ƒAپ[ƒeƒB‚جƒIپ[ƒPƒXƒgƒ‰‚àپA‚±‚±‚إ‚حژگـƒnƒb‚ئ‚³‚¹‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ب•\Œ»‚ًŒ©‚¹‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBپuIntroïtپv‚إپAƒIپ[ƒPƒXƒgƒ‰‚ھƒOƒŒƒSƒٹƒIگ¹‰ج‚جƒeپ[ƒ}پAچ‡ڈ¥‚ھ‚»‚ê‚ج‘خگù—¥‚ً“¯ژ‚ة‰ج‚ء‚ؤ‚¢‚éژ‚ةپA‚»‚ê‚ھ—¼•û‚ئ‚à‚ح‚ء‚«‚è‚ئ’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚½‚ئ‚«‚ة‚ح‚³‚·‚ھپA‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚½‚ثپB ‚½‚¾پAƒRƒWƒFƒiپ[‚جƒ\ƒچ‚حپA‚ ‚ـ‚è‚ة‚àڈêˆل‚¢‚إ‚µ‚½پB CD Artwork © Outhere Music |
||||||
”قڈ—‚½‚؟‚جƒŒƒpپ[ƒgƒٹپ[‚حپA’†گ¢‚©‚猻‘م‚ـ‚إ•چL‚ƒJƒoپ[‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚³‚ç‚ةپAگV‚µ‚¢چى•i‚ً‘½‚‚جچى‹ب‰ئ‚ةˆدڈْ‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ة50‹بˆبڈم‚جچى•i‚ھگ¶‚فڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB چ،‰ٌ‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚إ‚حپA‚»‚ٌ‚ب’†‚إ2013”N‚ةپAƒsپ[ƒ^پ[پEƒMƒ‹ƒoپ[ƒg‚ئ‚¢‚¤1975”Nگ¶‚ـ‚ê‚جƒAƒپƒٹƒJ‚جچى‹ب‰ئ‚ةˆدڈْ‚µ‚½پAپuTsukimiپv‚ئ‚¢‚¤‹ب‚ھک^‰¹‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒ^ƒCƒgƒ‹‚ح“ْ–{Œê‚إپuƒcƒLƒ~پvپA‚آ‚ـ‚èپuŒژŒ©پv‚إ‚·‚ثپB•د‘ش‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپi‚»‚ê‚حپuƒuƒLƒ~پvپjپB‚±‚ê‚حپAڈ¬‘q•Sگlˆêژٌ‚ج’†‚ة‚ ‚éکa‰ج‚ج’†‚©‚çپAپuŒژپv‚ةٹض‚·‚é‰ج‚ً‚Wژٌ‘I‚ٌ‚إپA‚»‚ê‚ًƒeƒLƒXƒg‚ة‚µ‚ؤچ‡ڈ¥‹ب‚ًچى‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚·پBپu“V‚جŒ´پ@‚س‚肳‚¯Œ©‚ê‚خپ@ڈt“ْ‚ب‚éپ@ژOٹ}‚جژR‚ةپ@ڈo‚إ‚µŒژ‚©‚àپv‚ف‚½‚¢‚ب‰ج‚إ‚·‚ثپBپuŒژ‚©‚àپv‚ب‚ٌ‚ؤپA‚ب‚ٌ‚¾‚©Œ»‘مŒê‚ف‚½‚¢‚بٹ´‚¶‚إ‚·‚ثپB ‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚±‚ê‚ç‚ج‰جڈW‚ح•½ˆہژ‘م‚©‚çٹ™‘qژ‘م‚ـ‚إ‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·‚©‚çپAگ¼—m—ً‚¾‚ئ‚Wگ¢‹I‚©‚ç12گ¢‹I‚®‚ç‚¢‚ـ‚إ‚ج•چL‚¢ژ‘م‚ةچى‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚جƒAƒ“ƒ\ƒچƒWپ[‚إ‚·پB ‚»‚ج‘¼‚ةپA‚»‚ê‚ئ“¯‚¶چ ‚©پA‚à‚¤ڈ‚µŒم‚ةگ¼—m‚إچى‚ç‚ꂽ‹بپAƒJƒٹƒNƒXƒgƒDƒXژت–{پi12گ¢‹Iپj‚ئ‚©ƒgƒٹƒmژت–{پi15گ¢‹Iپj‚ةژc‚³‚ꂽچى‰ئ•s–¾‚جƒIƒ‹ƒKƒkƒ€‚âپA15گ¢‹I‚جچى‹ب‰ئƒMƒ‡پ[ƒ€پEƒfƒ…ƒtƒ@ƒC‚جƒ‚ƒeƒbƒg‚ب‚ا‚àژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ƒAƒ‹ƒoƒ€ƒ^ƒCƒgƒ‹‚جپuIMPERMANENCEپv‚حپAپu‰i‹v“I‚إ‚ح‚ب‚¢پvپA‚آ‚ـ‚èپuˆêژ“Iپv‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بˆس–،‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB1000”N‚جƒXƒpƒ“‚ًژ‚آچى•i‚ً•ہ‚ׂؤ’®‚‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚»‚ꂼ‚ê‚جژ‘م‚إ‚جپuˆêژ“Iپv‚ب‚à‚ج‚ھپAŒ»‘م‚إ‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚بژp‚ة’®‚±‚¦‚é‚ج‚©پA‚ ‚é‚¢‚ح‚¢‚ة‚µ‚¦‚جکa‰ج‚ًŒ»‘م‚جچى•i‚جƒeƒLƒXƒg‚ة‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚ا‚ج‚و‚¤‚بˆس–،‚ًژ‚آ‚ج‚©پA‚»‚ٌ‚ب‚ئ‚±‚ë‚ً’®‚‚à‚ج‚ةچl‚¦‚³‚¹‚éپA‚ئ‚¢‚ء‚½ˆس–،چ‡‚¢‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB “ء‚ةپA“ْ–{‚جکa‰ج‚جڈêچ‡‚حپA‚»‚ج”wŒi‚ة‚حگ¼—mژذ‰ï‚جڈ@‹³ٹد‚ئ‚حˆظ‚ب‚éپA•§‹³“I‚ب–³ڈيٹد‚ب‚ا‚àچ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA‚»‚ê‚ة‘خ›³‚µ‚½چى‹ب‰ئ‚ج”½‰‚ب‚ا‚àپA–،‚ي‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‚ـ‚ پA‚»‚ٌ‚بڈ¬“‚¢‚±‚ئ‚ًچl‚¦‚ب‚‚ئ‚àپA‚±‚جƒŒپ[ƒxƒ‹‚ب‚ç‚إ‚ح‚ج‹ةڈم‚جƒTƒEƒ“ƒh‚إ’®‚پA‚ـ‚³‚ة‹ةڈم‚ج”§گG‚è‚ًژ‚ء‚½ڈ—گ؛ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹‚ج‰جگ؛‚ة‚حپAƒIپ[ƒvƒjƒ“ƒO‚©‚çˆّ‚«چ‚ـ‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ꂼ‚ê‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ح‚©‚ب‚è‚ج—ح‚ًژ‚ء‚½ƒvƒچƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹‚بƒVƒ“ƒKپ[‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚©‚çپA‚»‚ê‚ھ‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚½ژ‚جƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ح‚©‚ب‚è‚ج‚à‚ج‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ًپA”قڈ—‚½‚؟‚ح“¯‚¶ƒxƒNƒgƒ‹‚إ•ْڈo‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚·‚©‚çپA‚»‚±‚ة‚ح‚à‚ج‚·‚²‚¢‘¶چفٹ´‚ھگ¶‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌپA•\Œ»—ح‚ج•‚àژ©—R‚ةƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚إ‚«‚ـ‚·‚ج‚إپAƒXƒgƒŒپ[ƒg‚ة”قڈ—‚½‚؟‚ج‚â‚肽‚¢‰¹ٹy‚ھ“`‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB ‚»‚ٌ‚بپu‘fچقپv‚ًپA—]‚·‚ئ‚±‚ë‚ب‚“`‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‚±‚جک^‰¹‚إ‚·پBƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ج‰¹ڈê‚حپA‚½‚ئ‚¦‚خ2LƒŒپ[ƒxƒ‹‚ج‚و‚¤‚بژü‚è‚ًژو‚èˆح‚ق‚و‚¤‚بƒvƒ‰ƒ“‚حژو‚ء‚ؤ‚¨‚炸پAƒtƒچƒ“ƒg‚ة”¼‰~ڈَ‚ةچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إ‚·‚ھپAڈ\•ھ‚ب‹َٹش‚جچL‚³‚حٹ´‚¶‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB ‚»‚±‚إ‰ج‚ي‚ꂽƒMƒ‹ƒoپ[ƒg‚جپuƒcƒLƒ~پv‚حپA1•ھ‘«‚炸‚ج‹ب‚جڈW‚ـ‚è‚إ‚·‚ھپA‚»‚ꂼ‚ê‚ة‹Z–@‚ً•د‚¦‚½ژaگV‚بچى‚è•û‚ً‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚¨‚»‚ç‚چى‹ب‰ئ‚حپAŒ¾—t‚جˆس–،‚و‚è‚حپA‚»‚ج‚TپE‚VپE‚TپE‚VپE‚V‚جƒٹƒYƒ€ٹ´‚ئپA“ْ–{Œê‚جپu”‰¹پv‚ة‹»–،‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خپAپu‚ظ‚ئ‚ئ‚¬‚·پ@–آ‚«‚آ‚é‚©‚½‚ًپ@’‚ق‚ê‚خپ@‚½‚¾—L–¾‚جپ@Œژ‚¼ژc‚ê‚éپv‚إ‚حپAچإڈ‰‚جپu‚ظ‚ئ‚ئ‚¬‚·پv‚ة•qٹ´‚ة”½‰‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ً‘f‚ء“ع‹¶‚بƒTƒEƒ“ƒh‚ةڈو‚¹‚ؤ•sژv‹c‚بŒّ‰ت‚ًڈم‚°‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB ‚»‚ج‚ظ‚©‚ةپA•گ–“O‚جپu•—‚ج”nپv‚ج‘و1ƒ”ƒHƒJƒٹپ[ƒY‚ئ‘و2ƒ”ƒHƒJƒٹپ[ƒY‚à‰ج‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپu‘و1پv‚حڈ—گ؛چ‡ڈ¥‚ج‹ب‚إ‚·‚ھپAپu‘و‚Qپv‚حƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ح’jگ؛چ‡ڈ¥پA‚إ‚àپA”قڈ—‚½‚؟‚ة‚©‚©‚é‚ئ’jگ؛‚و‚è‚àŒْ‚ع‚ء‚½‚¢چ‡ڈ¥‚ھ’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB CD & BD Artwork © Sono Luminus, LLC. |
||||||
چ،‰ٌ‚جƒoƒbƒnپEƒRƒŒƒMƒEƒ€پEƒWƒƒƒpƒ“‚حپA8.8.6.5.3.‚ئ‚¢‚¤Œ·ٹyٹي‚ة30گl‚ظ‚ا‚جچ‡ڈ¥‚ئ‚¢‚¤پA‚ب‚©‚ب‚©ƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ج—ا‚¢•زگ¬‚إ‚µ‚½پBچ،”N‚ج1Œژ‚ة“Œ‹ƒIƒyƒ‰ƒVƒeƒB‚جƒRƒ“ƒTپ[ƒgƒzپ[ƒ‹‚إچs‚ي‚ꂽƒRƒ“ƒTپ[ƒg‚جƒ‰ƒCƒuک^‰¹‚ئپA‚»‚ج‘OŒم‚ة“¯‚¶‰ïڈê‚إچs‚ء‚½ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ک^‰¹‚ً•زڈW‚µ‚ؤپAژdڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB —ل‚¦‚خپAN‹؟‚ ‚½‚è‚ھ‰‰‘t‚·‚é‚ئ‚«‚ج”¼•ھ‚جگlگ”‚µ‚©‚¢‚ب‚¢Œ·ٹyٹي‚إ‚·‚ھپA‚±‚جک^‰¹‚إ’®‚Œہ‚è‚حڈ\•ھ‚ب‹؟‚«‚ھ–،‚ي‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹t‚ةپA–طٹا‚ ‚½‚è‚ھ‚ ‚ـ‚è–ع—§‚½‚ب‚¢‚ظ‚ا‚إ‚·پB‚»‚ê‚ئپA‘و4ٹyڈح‚جƒ\ƒٹƒXƒg‚ھپA‚ب‚ٌ‚ئ‚àƒIƒt‚بٹ´‚¶‚إپA‚ع‚₯‚½‰¹‘œ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ‹C‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚µ‚©‚µپA‰½‚و‚è‚à‹C‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚ھپA‘و1ٹyڈح–`“ھ‚جƒzƒ‹ƒ“‚جA-E‚ئ‚¢‚¤‹َ‹•Œـ“x‚ج‚ ‚ئ‚ة‚ذ‚ئ‚‚³‚èچ‡‘t‚ھ‚ ‚ء‚ؤپAچ،“x‚حD-A‚ج‹َ‹•Œـ“x‚ھƒzƒ‹ƒ“‚ئƒNƒ‰ƒٹƒlƒbƒg‚إژn‚ـ‚ء‚½ژ‚جپAƒsƒbƒ`‚إ‚·پB‚»‚ê‚حپA‚ئ‚ؤ‚àˆلکaٹ´‚ج‚ ‚é‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB ‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپAƒ‰ƒCƒu‚جƒeƒCƒN‚ب‚ج‚إٹاٹyٹي‘tژز‚ھ•s–{ˆس‚ب‰‰‘t‚µ‚©‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚»‚¤‚إ‚ ‚ê‚خ‚»‚ج‚ ‚ئ‚جƒZƒbƒVƒ‡ƒ“‚إ‚¢‚‚ç‚إ‚àڈCگ³‚µ‚½‚à‚ج‚ئچ·‚µ‘ض‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ح‚¸‚ب‚ج‚ةپAک^‰¹ƒXƒ^ƒbƒt‚ح‚»‚ج‚µ‚‚¶‚è‚جƒeƒCƒN‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـپuڈ¤•iپv‚ئ‚µ‚ؤچج—p‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB‚ب‚ٌ‚ئ‚¢‚¤‚¨‘e––‚بپu•iژ؟ٹا—پv‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‰‰‘t‚»‚ج‚à‚ج‚حƒhƒ‰ƒCƒuٹ´‚ة‚à‰جگS‚ة‚à–‚؟‚½‘fگ°‚炵‚¢‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB“ء‚ةڈIٹyڈح‚جچ‡ڈ¥‚ح‚ـ‚³‚ةٹ´“®“IپA•پ’ت‚جپu‘و9پv‚إ’®‚¯‚é‚و‚¤‚ب‘هژG”c‚بچ‡ڈ¥‚ئ‚ح‚ـ‚é‚إژںŒ³‚جˆل‚¤پA‰¹ٹy‚ج–{ژ؟‚ة”—‚é–¼‰‰‚إ‚µ‚½پB“ء‚ةپA’jگ؛ƒpپ[ƒg‚ج—]—T‚³‚¦ٹ´‚¶‚ç‚ê‚é‰ج‚¢•û‚حگâ•i‚إ‚µ‚½‚ثپB ‚ب‚ة‚و‚è‚àپAƒeƒLƒXƒg‚ة‘خ‚·‚éٹ´ٹo‚ھ‚ئ‚ؤ‚آ‚à‚ب‚‰s•q‚إپAŒ¾—t‚ھ“Iٹm‚بƒپƒbƒZپ[ƒW‚ئ‚µ‚ؤƒ_ƒCƒŒƒNƒg‚ة“`‚ي‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚حپA‹ءˆظ“I‚إ‚·پB ‚±‚±‚إ—é–ط‚³‚ٌ‚ھ‚ا‚ٌ‚بٹy•ˆ‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©‚حپA”ٌڈي‚ة‹C‚ة‚ب‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚؟‚ه‚ء‚ئ‘O‚إ‚ ‚ê‚خپAƒsƒٹƒIƒhŒn‚جگl‚½‚؟‚ح‚ـ‚¸ƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپAچإ‹ك‚ح“¯‚¶Œ´“T”إ‚إ‚àƒWƒ‡ƒiƒTƒ“پEƒfƒ‹پEƒ}پ[‚ھ‚©‚ب‚èژhŒƒ“I‚بچZ’ù‚ً‚¨‚±‚ب‚ء‚½ƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚إ‚ح‚ب‚پA‚à‚¤ڈ‚µ‰¸‚â‚©‚بپAƒyپ[ƒ^پ[پEƒnƒEƒVƒ‹ƒg‚جچZ’ù‚ة‚و‚éƒuƒ‰ƒCƒgƒRƒvƒtگV”إ‚ھ“oڈꂵ‚½‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA‚»‚ج‚ ‚½‚è‚ج—l‘ٹ‚ھ•د‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚©‚ç‚ثپB چ،‰ٌ‚ج‰‰‘t‚إ‚حپA‚ـ‚¸‚حچإڈ‰‚جƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒgپA‘و1ٹyڈح‚ج81ڈ¬گك‚جƒtƒ‹پ[ƒg‚ئƒIپ[ƒ{ƒG‚جŒم”¼‚ج‰¹‚ھپAپuDپv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پi‡@پjپB‚±‚ê‚حپAƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚ة‚¾‚¯‚ةŒ»‚ê‚鉹پA‚»‚êˆبٹO‚جŒ´“T”إ‚إ‚حپA‘S‚ؤڈ]—ˆ’ت‚è‚جپuBbپv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚©پAچإ‹ك‚ح–¾‚ç‚©‚ةƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éک^‰¹پi‚½‚ئ‚¦‚خپAگو“ْ‚جƒlƒ‹ƒ\ƒ“ƒX”صپj‚إ‚àپA‚±‚ج‰¹‚حپuBbپv‚ة’¼‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚©‚çپA‚±‚ê‚ح‹v‚µ‚ش‚è‚ةƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚ة’‰ژہ‚ب‰‰‘t‚ھ’®‚¯‚é‚ج‚إ‚حپA‚ئٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB ‚µ‚©‚µپA—é–ط‚³‚ٌ‚½‚؟‚حپA‚»‚ج‚à‚ء‚ئ‚àƒGƒLƒTƒCƒeƒBƒ“ƒO‚بپu‰ü•دپv‚إ‚ ‚éپA‘و‚Sٹyڈح532ڈ¬گكˆبچ~‚جƒzƒ‹ƒ“‚ة•t‚¯‚ç‚ꂽƒ^ƒCپi‡Aپj‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پi‚²–³‘ج‚بپjپB‚³‚ç‚ةپA‘و‚Sٹyڈح767ڈ¬گكˆبچ~‚جƒ\ƒٹƒXƒg‚ج‰ج‚¢‚¾‚µ‚ج‰جژŒ‚àپAƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚إ‚حپuTochter, Freude, Tochter, Tochterپv‚ئ‚¢‚¤ƒCƒŒƒMƒ…ƒ‰پ[‚بŒ`‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ھپA‚±‚±‚إ‚ح‘S•”پuTochterپv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚ٌ‚ب•—‚ةپAƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إ‚جپu–ت”’‚¢پv‚ئ‚±‚ë‚ً‘S•”–³ژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚é‚‚¹‚ةپAپu‡@پv‚¾‚¯‚حƒxپ[ƒŒƒ“ƒ‰ƒCƒ^پ[”إˆبٹO‚إ‚ح‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً‚ئ‚è‚¢‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚©‚çپA•sژv‹c‚إ‚·پB 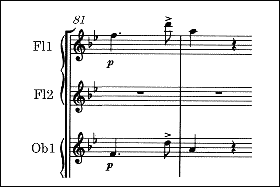 ‡@ ‡@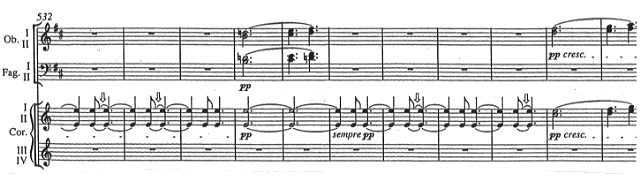 ‡A ‡ASACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
ک^‰¹‚حƒ‰ƒCƒu‚إ‚ح‚ب‚ƒXƒ^ƒWƒI‚إچs‚ي‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·‚ھپA‚»‚جƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚جƒvƒ‰ƒ“‚ح•ت‚ة‚S‚آ‚جٹyٹي‚ھژl•û‚ةچL‚ھ‚é‚ئ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚²‚‰¸Œ’‚ةƒtƒچƒ“ƒg‚ة‚س‚‚ç‚ف‚ًژ‚ء‚ؤ’èˆت‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‚â‚ح‚èƒ~ƒ…پ[ƒWƒVƒƒƒ“‚ة‚و‚éک^‰¹‚¾‚ئژv‚ي‚¹‚ç‚ê‚é‚ج‚حپA‚»‚ꂼ‚ê‚جٹyٹي‚ج’®‚©‚¹‚ا‚±‚ë‚ھ‚«‚؟‚ٌ‚ئ’®‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚ئ‚¢‚¤“_‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚à‚؟‚ë‚ٌپAژ©•ھ‚جٹyٹي‚¾‚¯‚ً–ع—§‚½‚¹‚é‚و‚¤‚ب•i‚ج‚ب‚¢‚±‚ئ‚حˆêگطچs‚ء‚ؤ‚ح‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ‚»‚ê‚ا‚±‚ë‚©پA‚±‚جƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^پ[‚ئ‚¢‚¤گl‚حپA‰‰‘t‚·‚é‚ئ‚«‚ة‚حƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹‚ة‚ئ‚±‚ئ‚ٌ‚±‚¾‚ي‚ء‚ؤپAژ©•ھ‚ج–ًٹ„‚ج’²گ®‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB—ل‚¦‚خپAƒC’·’²‚جژlڈd‘t‹ب‚ج‘و‚Pٹyڈح‚ح•د‘t‹ب‚إپA‚»‚ꂼ‚ê‚جٹyٹي‚ھƒ\ƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ب‰‰‘t‚ً”âکI‚·‚é‚و‚¤‚ةچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚±‚إ‚حپAƒ”ƒ@ƒ‹ƒ^پ[‚ح‘¼‚جٹyٹي‚ھƒپƒCƒ“‚¾‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚إ‚حپA“O’ê“I‚ةژ©‚ç‚ج‘¶چف‚ًڈء‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚ثپBچإŒم‚ج•د‘t‚ب‚ا‚حƒtƒ‹پ[ƒg‚ھƒeپ[ƒ}‚ً‰‰‘t‚µ‚ؤ‚¢‚éڈم‚إپAƒ`ƒFƒچ‚ج•د‘t‚ھŒJ‚èچL‚°‚ç‚ê‚éپA‚ئ‚¢‚¤گف’è‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA‚»‚جƒeپ[ƒ}‚³‚¦پA”ق‚ح‹ة—ح–ع—§‚½‚ب‚¢‚و‚¤‚ةگپ‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚وپB ‚»‚ج‚و‚¤‚بƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹‚ج’Bگl‚½‚؟‚ھڈW‚ـ‚ء‚½چ‡‘t‚إ‚·‚©‚çپA‰‰‘t‚ح‚ئ‚ؤ‚àƒXƒٹƒٹƒ“ƒO‚إ‹ظ”—‚µ‚½‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒپƒ“ƒoپ[‚»‚ꂼ‚ê‚ھپA‘¼‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ج‚ا‚ٌ‚بچׂ©‚¢ژd‘گ‚ة‚àڈuژ‚ة”½‰‚µ‚ؤ‚ـ‚é‚إˆê‚آ‚جٹyٹي‚ج‚و‚¤‚ة‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚ؤ”—‚ء‚ؤ‚‚é‚ج‚إ‚·‚©‚ç‚ثپB ‚±‚¤‚¢‚¤‰‰‘t‚إ’®‚‚ئپA•پ’ت‚ح‚ئ‚ؤ‚à‚آ‚ـ‚ç‚ب‚¢‹ب‚ج‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚éپi‚¨‚»‚ç‚‹Uچىپjƒg’·’²‚جژlڈd‘t‹ب‚ـ‚إپA‚µ‚ء‚©‚è‚ئ‚µ‚½ˆس–،‚ج‚ ‚鉹ٹy‚ئ‚µ‚ؤ’®‚‚±‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB ’تڈيپAپuƒ‚پ[ƒcƒ@ƒ‹ƒg‚جƒtƒ‹پ[ƒgژlڈd‘t‹بپv‚ئ‚¢‚¦‚خپAƒj’·’²پAƒg’·’²پAƒn’·’²پAƒC’·’²‚ج‚S‹ب‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚إ‚ح‚à‚¤‚P‹بپuƒg’·’²پv‚جژlڈd‘t‹ب‚ھژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA•ت‚ةگV‚µ‚”Œ©‚³‚ꂽ‹ب‚إ‚ح‚ب‚پA“¯‚¶ƒ‚پ[ƒcƒ@ƒ‹ƒg‚ھچى‚ء‚½پuƒIپ[ƒ{ƒGژlڈd‘t‹بƒw’·’²پv‚جƒIپ[ƒ{ƒG‚جƒpپ[ƒg‚ًƒtƒ‹پ[ƒg‚ة’u‚«ٹ·‚¦‚ؤ‰‰‘t‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚àپA—ل‚¦‚خƒSپ[ƒ‹ƒEƒFƒC‚ھ1991”N‚ة“Œ‹ƒNƒڈƒ‹ƒeƒbƒg‚ئ‹¤‰‰‚µ‚½ک^‰¹‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ثپB ‚½‚¾پAƒSپ[ƒ‹ƒEƒFƒC‚جڈêچ‡‚حپAƒIپ[ƒ{ƒGژlڈd‘t‹ب‚جٹy•ˆ‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـژg‚ء‚ؤپA‚à‚؟‚ë‚ٌ“¯‚¶’²‚إ‰‰‘t‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپAچ،‰ٌ‚جک^‰¹‚إ‚ح‘S‰¹چ‚‚ˆع’²‚³‚ꂽٹy•ˆ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¢‚؟‚¨‚¤پA‚»‚جپu•ز‹بپv‚ًچs‚ء‚½‚ج‚حپAƒ‚پ[ƒcƒ@ƒ‹ƒg‚ئ“¯ژ‘م‚جچى‹ب‰ئ‚إٹy•ˆڈo”إ‚àژèٹ|‚¯‚ؤ‚¢‚½ƒtƒ‰ƒ“ƒcپEƒAƒ“ƒgƒ“پEƒzƒtƒ}ƒCƒXƒ^پ[‚ئ‚¢‚¤گl‚إ‚·پB ‚»‚جژ‘م‚ج•پ’ت‚جƒtƒ‹پ[ƒg‚إ‚ح’ل‰¹‚حپuDپv‚ـ‚إ‚µ‚©ڈo‚¹‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ةپAƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚إ‚جچإ’ل‰¹‚ھپuCپv‚¾‚ء‚½‚ج‚ئپA‚»‚جٹyٹي‚إ‚حƒVƒƒپ[ƒvŒn‚ج‹ب‚ج•û‚ھ–آ‚è‚â‚·‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚±‚ج‚و‚¤‚ب‘[’u‚ً‚ئ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB ‚½‚¾پAƒzƒtƒ}ƒCƒXƒ^پ[‚حپA‚ ‚‚ـ‚إƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‚جˆ¤چD‰ئ‚ج‚½‚ك‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚ب•ز‹ب‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚إƒvƒچ‚ج‰‰‘t‰ئ‚ً‘z’肵‚ؤچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‰طپX‚µ‚¢ƒpƒbƒZپ[ƒW‚ًپAƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAŒü‚¯‚ة‚₳‚µ‚پi‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپAڈ\•ھ‹ZچI“I‚إ‚·‚ھپj’¼‚µ‚½‚肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¨‚»‚ç‚پAچإ‘ه‚ج“ïڈٹ‚حپA6/8‚إڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‘و3ٹyڈح‚ج“r’†‚ةڈo‚ؤ‚‚éپAƒIپ[ƒ{ƒG‚¾‚¯‚ھ4/4‚إڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é•”•ھ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA‚»‚±‚حپA•پ’ت‚جƒٹƒYƒ€‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB 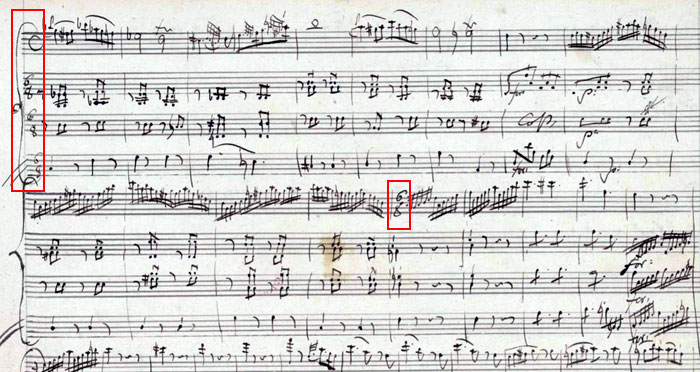 SACD Artwork © Ars Produktion |
||||||
‚»‚ٌ‚ب‚ي‚¯‚إپA”ق‚ھ–S‚‚ب‚é‚R”N‘O‚ج1844”N‚ةپA‚³‚éƒCƒMƒٹƒX‚جڈo”إژذ‚ھ”ق‚ة‚R‹ب‚جƒ”ƒHƒ‰ƒ“ƒ^ƒٹپ[پiƒIƒ‹ƒKƒ“‹ب‚جˆêژيپj‚جچى‹ب‚ًˆث—ٹ‚µ‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤƒپƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ]پ[ƒ“‚حپA‚»‚جˆث—ٹ‚جپu”{•ش‚µپv‚ج‚U‹ب‚جƒIƒ‹ƒKƒ“پEƒ\ƒiƒ^‚ًچى‹ب‚·‚é‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إ‰‚¦‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ح1845”N‚ةپAƒCƒMƒٹƒXپAƒhƒCƒcپAƒtƒ‰ƒ“ƒXپAƒCƒ^ƒٹƒA‚ج‚S‚©چ‘‚إ“¯ژ””„‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إڈo”إ‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚·پBگ¦‚¢‚إ‚·‚ثپB‚¢‚©‚ة”ق‚ھƒIƒ‹ƒKƒjƒXƒgپAچى‹ب‰ئ‚ئ‚µ‚ؤپu”„‚ê‚ؤپv‚¢‚½‚©‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB ‚»‚جٹ„‚ة‚حپAŒ»چف‚إ‚ح‚±‚جƒپƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ]پ[ƒ“‚جƒIƒ‹ƒKƒ“پEƒ\ƒiƒ^‚حپA”ق‚جŒً‹؟‹ب‚ب‚ا‚ة”ن‚ׂé‚ئ‘S‚’m–¼“x‚ح’ل‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚µ‚©‚µپA’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپACD‚ب‚ا‚إ‚حˆسٹO‚ئ‘½‚‚جپuƒIƒ‹ƒKƒ“پEƒ\ƒiƒ^‘S‹ب”صپv‚ھƒٹƒٹپ[ƒX‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸NML‚جƒٹƒXƒg‚إ‚حپAƒ\ƒiƒ^ڈW‚ھ11ژي—قپA‚³‚ç‚ة‚»‚ج‘¼‚جƒIƒ‹ƒKƒ“چى•i‚ً‚·‚ׂؤڈW‚ك‚½پu‘SڈWپv‚à‚Tژي—ق‚ ‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚»‚êˆبٹO‚ة‚à‚ ‚é‚ح‚¸‚إ‚·پB ‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA‚¢‚‚炽‚‚³‚ٌ‚جک^‰¹‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إپA‚»‚ê‚ç‚ح‚²‚Œہ‚ç‚ꂽگl‚½‚؟‚جٹش‚¾‚¯‚إ’®‚©‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚¢‚¤‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB“¯‚¶‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ھپAƒtƒ‹پ[ƒg‚جˆ¤چD‰ئ‚جٹش‚إ‚ح’Nˆêگl‚ئ‚µ‚ؤ’m‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚ح‚¢‚ب‚¢‚ئژv‚¦‚ؤپAژہچغ‚ة–³گ”‚جک^‰¹‚ھ‘¶چف‚·‚éپA—ل‚¦‚خپuƒVƒƒƒ~ƒiپ[ƒh‚جپwƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒeƒBپ[ƒmپxپv‚ئ‚©پuƒ‰ƒCƒlƒbƒP‚جپwƒEƒ“ƒfƒBپ[ƒkپxپv‚ة‚à“–‚ؤ‚ح‚ـ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚±‚ٌ‚ب–¼‹ب‚ح’N‚إ‚à’m‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚낤‚ئژv‚ء‚ؤ‚àپAŒˆ‚µ‚ؤپuƒNƒ‰ƒVƒbƒN‰¹ٹyپv‘S‘ج‚جگ¢ٹE‚إ‚ح’m–¼“x‚ج“_‚إ‚ح‘S‚’ت—p‚µ‚ب‚¢‹ب‚¾‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚و‚‚ ‚邱‚ئ‚إ‚·پB چ،‰ٌ‚حپA‚»‚ê‚ًƒXƒEƒFپ[ƒfƒ“‚جƒIƒ‹ƒKƒjƒXƒgپAƒnƒ“ƒXپEƒ_پ[ƒ”ƒBƒhƒ\ƒ“‚ھ2016”N‚ةک^‰¹‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB‚±‚ج6‹ب‚جƒ\ƒiƒ^‚ً‘S•”‰‰‘t‚·‚é‚ئ‚ظ‚ع80•ھ‚©‚©‚é‚ج‚إپACD‚ج‹KٹiƒMƒٹƒMƒٹ‚ج‚ئ‚±‚ë‚إژû‚ـ‚è‚ـ‚·پBڈع‚µ‚’²‚ׂ½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAگو‚ظ‚ا‚ج‚½‚‚³‚ٌ‚جƒ\ƒiƒ^‘SڈW‚àپA‚¨‚»‚ç‚CD‚¾‚ء‚½‚ç1–‡‚إژû‚ـ‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½‚ج‚إپAچى‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB پuƒ\ƒiƒ^پv‚ئ‚¢‚¤–¼‘O‚à•t‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‚µ‚ء‚©‚èپuƒ\ƒiƒ^Œ`ژ®پv‚ً‚»‚ب‚¦‚½ٹyڈح‚إڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚±‚إ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب”z—¶‚ح‚ ‚ـ‚èٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ê‚و‚è‚àپAپuگFپX‚ب—v‘f‚ًژ‚ء‚½ٹyڈح‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‹بپv‚ئ‚¢‚ء‚½‚و‚¤‚بƒjƒ…ƒAƒ“ƒX‚إپuƒ\ƒiƒ^پv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ژہچغپA‚»‚ج‚»‚ꂼ‚ê‚جٹyڈح‚إ‚حپAژ©—R‚بٹy‘z‚ھژںپX‚ة“oڈê‚·‚éپu‘O‘t‹بپv‚ ‚é‚¢‚حپuƒgƒbƒJپ[ƒ^پv“I‚ب‚à‚ج‚âپAŒµٹi‚بپuƒtپ[ƒKپv‚إچى‚ç‚ꂽٹyڈح‚ھ‚½‚‚³‚ٌŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚³‚ç‚ة‘ه‚«‚ب—v‘f‚حپAپuƒRƒ‰پ[ƒ‹پv‚ً‘fچق‚ة‚µ‚½‚à‚ج‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚±‚ê‚ç‚ح‚ـ‚³‚ةپAƒIƒ‹ƒKƒ“‰¹ٹy‚ج‚¨ژè–{‚إ‚ ‚éƒoƒbƒn‚جچى•i‚جƒpپ[ƒc‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پB ‚»‚µ‚ؤپAƒپƒ“ƒfƒ‹ƒXƒ]پ[ƒ“‚حپA‚»‚±‚ة‚ـ‚³‚ةƒچƒ}ƒ“”h“I‚بپu‰جپv‚جƒpپ[ƒc‚ً‰ء‚¦‚ـ‚µ‚½پB‚»‚±‚©‚ç‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا”ق‚جچ‡ڈ¥‹ب‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ب‰¸‚â‚©‚بƒeƒCƒXƒg‚ًٹ´‚¶‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB ‚»‚ꂼ‚ê‚ج6‚آ‚جپuƒ\ƒiƒ^پv‚حپA4‚آ‚جٹyڈح‚إڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚âپA2‚آ‚µ‚©‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚©پAٹyڈح‚جگ”‚à”÷–‚ةˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚و‚èپA‚à‚ح‚â‚·‚ׂؤ‚جٹyڈح‚ًٹـ‚ٌ‚¾پu18‚جٹyڈح‚ة‚و‚é‘ه‹K–ح‚بƒcƒBƒNƒ‹ƒXپv‚ئ‚µ‚ؤپA‚±‚ê‚ç‚جƒ\ƒiƒ^‘S‘ج‚ً‚ئ‚炦‚é‚ׂ«‚¾پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھپA‚±‚±‚إ‚جƒIƒ‹ƒKƒjƒXƒg‚جƒ_پ[ƒ”ƒBƒhƒ\ƒ“‚جژه’£‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB ٹm‚©‚ةپA‚»‚ج‚و‚¤‚ب’®‚«•û‚ً‚·‚é‚ئپAژںپX‚ةŒ»‚ê‚ؤ‚‚é–£—ح“I‚بٹy‘z‚ة•ï‚ـ‚ê‚ؤپA‚ئ‚ؤ‚àچK‚¹‚ب‹Cژ‚؟‚ة‚ب‚ê‚ـ‚·پB‚±‚جپA1806”N‚ةچى‚ç‚ꂽ’†‹K–ح‚جƒTƒCƒY‚جƒIƒ‹ƒKƒ“‚àپA‚¢‚©‚ة‚àƒچƒ}ƒ“ƒeƒBƒbƒN‚ب’g‚©‚¢‰¹گF‚إ’®‚‚à‚ج‚ً•ï‚فچ‚ٌ‚إ‚‚ê‚ـ‚·پB CD Artwork © Loft Recordings |
||||||
‚µ‚©‚µپuƒAƒrپ[پEƒچپ[ƒhپv‚ح“ء•ت‚إ‚·پB50”NٹشپA‚±‚ئ‚ ‚邲‚ئ‚ة’®‚«‘±‚¯‚ؤ‚«‚½‚±‚جژى‹ت‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚ھƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚إژûک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éBD-A‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚¾‚¯‚إپA‚©‚ب‚èچ‚‰؟‚ب‚±‚جپuƒXپ[ƒpپ[پEƒfƒ‰ƒbƒNƒXپEƒGƒfƒBƒVƒ‡ƒ“پv‚ئ‚¢‚¤چإچ‚ˆت‚جƒOƒŒپ[ƒh‚جƒZƒbƒg‚ًچw“ü‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB ‚±‚جƒGƒfƒBƒVƒ‡ƒ“‚جچ\گ¬‚حپAƒWƒƒƒCƒ‹ƒYپEƒ}پ[ƒeƒBƒ“‚ة‚و‚ء‚ؤƒٹƒ~ƒbƒNƒX‚ھچs‚ي‚ꂽƒtƒ‹ƒAƒ‹ƒoƒ€‚جCDپA‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ج24/96‚جƒnƒCƒŒƒ]‚ة‚و‚é2ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹ƒXƒeƒŒƒIپA‚³‚ç‚ة‚حپADTS-HDƒ}ƒXƒ^پ[ƒIپ[ƒfƒBƒI5.1‚ئپAƒhƒ‹ƒrپ[پEƒAƒgƒ‚ƒX‚ج2ژي—ق‚جƒtƒHپ[ƒ}ƒbƒg‚جƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ھژûک^‚³‚ꂽBD-AپA‚»‚µ‚ؤپAپuƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ƒYپv‚ئ–¼•t‚¯‚ç‚ꂽگ³‹KƒAƒ‹ƒoƒ€‚ة‚حچج—p‚³‚ê‚ب‚©‚ء‚½ƒAƒEƒgƒeƒCƒNڈW‚ج2–‡‚جCD‚ئ‚¢‚¤4–‡‚جƒfƒBƒXƒN‚إ‚·پB ‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ç‚ھژû”[‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھپA•ھŒْ‚¢•\ژ†‚جLPƒTƒCƒY‚جپA100ƒyپ[ƒW‚ة‚à‹y‚شƒuƒbƒNƒŒƒbƒgپA‚ئ‚¢‚¤‚©پAچ‹‰طژتگ^ڈW‚إ‚·پB ‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚¨–ع“–‚ؤ‚حBD-A‚إ‚·پB‚ـ‚¸‚حپA‚»‚جƒXƒ^پ[ƒg‰و–ت‚©‚炵‚ؤ‹ء‚©‚³‚ê‚ـ‚·پB‚½‚¾پA3ژي—ق‚جƒtƒHپ[ƒ}ƒbƒg‚ًگط‚è‘ض‚¦‚邽‚ك‚ة‚حپA•پ’ت‚حژg‚¦‚é‚ح‚¸‚جƒٹƒ‚ƒRƒ“‚جƒJƒ‰پ[ƒ{ƒ^ƒ“‚إ‚ح‚ب‚پA–îˆَƒLپ[‚إ‹ب–ع‚جڈم‚©‰؛‚ًƒTپ[ƒ`‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚ھپA‚؟‚ه‚ء‚ئƒ„ƒ{‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ‚»‚µ‚ؤپAƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚إ’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚½پuCome Togetherپv‚ح‚ـ‚³‚ةڈصŒ‚“I‚إ‚µ‚½پB–`“ھ‚جپuƒ^ƒJƒ^ƒ^ƒJƒ^پv‚ئ‚¢‚¤ƒnƒ“ƒhƒNƒ‰ƒbƒv‚ةƒfƒBƒŒƒC‚ً‚©‚¯‚½ƒpƒ‹ƒX‚ھپA‚»‚ꂾ‚¯”²‚«ڈo‚³‚ê‚ؤƒٹƒA‚©‚ç’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚·پB‚»‚ꂾ‚¯‚إپA”ق‚ç‚ھک^‰¹‚جژ‚ة‚ا‚ꂾ‚¯ƒAƒŒƒ“ƒW‚âƒTƒEƒ“ƒh‚ة‚±‚¾‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ھ‚ح‚ء‚«‚è“`‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB ‚³‚ç‚ة“ء’¥“I‚ب‚ج‚حپAƒRپ[ƒ‰ƒX‚ھ‚µ‚ء‚©‚è‹َٹش“I‚بچL‚ھ‚è‚ًژ‚ء‚ؤ’®‚±‚¦‚ؤ‚‚邱‚ئ‚إ‚·پB‚±‚ê‚àپAچ،‚ـ‚إ’®‚«—¬‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ھپA‚ح‚ء‚«‚èƒRپ[ƒ‰ƒX‚ة’چ–ع‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‚»‚جٹ®àّ‚بƒRپ[ƒ‰ƒXƒڈپ[ƒN‚ة‰ü‚ك‚ؤ‹ء’Q‚³‚¹‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB ‚»‚µ‚ؤ‰½‚و‚è‚àپA‰¹‚جƒNƒIƒٹƒeƒB‚ھٹi’i‚ةڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚à‚»‚àپAپuI Want Youپv‚ ‚½‚è‚إ‚حƒCƒ“ƒgƒچ‚ئƒ”ƒHپ[ƒJƒ‹‚جچ‡ٹش‚ة”hژè‚ة’®‚±‚¦‚ؤ‚¢‚½ƒqƒXƒmƒCƒY‚ھپA‘S‚ڈء‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB چ،‰ٌ‚جƒٹƒ~ƒbƒNƒX‚إچإ‚àŒّ‰ت‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚é‚ج‚حپA‚ب‚ٌ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àپuThe Endپv‚إ‚جƒMƒ^پ[پEƒoƒgƒ‹‚ج•”•ھ‚إ‚µ‚ه‚¤پBƒhƒ‰ƒ€پEƒ\ƒچ‚ھڈI‚ي‚ء‚½Œم‚ةپAƒ|پ[ƒ‹پEƒ}ƒbƒJپ[ƒgƒjپ[پAƒWƒ‡پ[ƒWپEƒnƒٹƒXƒ“پAƒWƒ‡ƒ“پEƒŒƒmƒ“‚جڈ‡‚ة2ڈ¬گك‚¸‚آ‚»‚ꂼ‚ê‚ة“ء’¥“I‚بƒ\ƒچ‚ً‰‰‘t‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ƒpƒ^پ[ƒ“‚ھ3‰ٌŒJ‚è•ش‚³‚ê‚éڈê–ت‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپAƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚إ‚ح‚»‚ج3گl‚ج‰¹‘œ‚ح‚·‚ׂؤچ¶ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚ةŒإ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ھپAچ،‰ٌ‚ح2ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚إ‚àƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚إ‚àچ¶پiƒ|پ[ƒ‹پjپ¨‰EپiƒWƒ‡پ[ƒWپjپ¨ƒZƒ“ƒ^پ[پiƒWƒ‡ƒ“پj‚ئپA‚ح‚ء‚«‚è•ھ‚©‚ê‚ؤ’®‚±‚¦‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚·پB ‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپA‚±‚ج‚و‚¤‚بچى‹ئ‚حƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ة‘خ‚·‚é–`“ہ‚¾پA‚ئژv‚¤گl‚à‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپA‚±‚ê‚حƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ئ‚ح‘S‚•ت•¨‚جپAپuگi‰»Œnپv‚ئ‚ئ‚炦‚é‚ׂ«‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ç‚ھ‚±‚ê‚ًک^‰¹‚µ‚½”¼گ¢‹I‘O‚حپAپuƒXƒeƒŒƒIپv‚·‚ç‚àˆê”ت“I‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB‚إ‚·‚©‚çپA‚à‚µ”ق‚ç‚ھƒTƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ب‚ا‚جƒeƒNƒmƒچƒWپ[‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ب‚çپA‚«‚ء‚ئ‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ًچى‚èڈم‚°‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئچl‚¦‚é‚ج‚حپA‚ئ‚ؤ‚àٹy‚µ‚¢‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ƒuƒbƒNƒŒƒbƒg‚جڈî•ٌ‚ج‘½‚³‚ة‚àپA‹ء‚©‚³‚ê‚ـ‚·پBƒZƒbƒVƒ‡ƒ“‚جچإŒم‚ة‰ء‚¦‚ç‚ꂽƒXƒgƒٹƒ“ƒOƒX‚جگlگ”‚ـ‚إ‚à•ھ‚©‚é‚ج‚إ‚·‚©‚ç‚ثپBپuHere Comes the Sunپv‚إ‚حپAƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‚ح‚ب‚پAƒ”ƒBƒIƒ‰ˆب‰؛‚جŒ·‚ةƒNƒ‰ƒٹƒlƒbƒgپAƒtƒ‹پ[ƒgپAƒAƒ‹ƒgƒtƒ‹پ[ƒgپAƒsƒbƒRƒچ‚ھ‚»‚ꂼ‚ê2–{‚¸‚آ‰ء‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ٌ‚ؤپA’®‚¢‚½‚¾‚¯‚إ‚حگâ‘خ‚ة‚ي‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚وپB‚ـ‚³‚©پAƒAƒ‹ƒgƒtƒ‹پ[ƒg‚ـ‚إ‚ھ‚ ‚é‚ئ‚حپB CD & BD Artwork © Calderstone Productions Limited |
||||||
‚»‚µ‚ؤپA‚»‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‚ًڈü‚éƒWƒƒƒPƒbƒgژتگ^‚ھپA‚»‚à‚»‚à‚©‚ب‚è‚جƒCƒ“ƒpƒNƒg‚ًژ‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB‘ه‚«‚Œٹ‚جٹJ‚¢‚½ƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‚ئپAƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒjƒXƒg‚جپuگ¶ژٌپv‚ھ•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚éپA‚ئ‚¢‚¤چ\گ}‚إ‚·‚©‚ç‚ثپB ‚»‚ê‚ç‚ھ‰½‚ًˆس–،‚·‚é‚ج‚©‚ح‚»‚±‚إژو‚èڈم‚°‚½‹ب‚ة‚و‚ء‚ؤ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‘O”¼‚جƒپƒCƒ“‚ج‹ب‚ح1905”Nگ¶‚ـ‚ê‚جƒhƒCƒc‚جچى‹ب‰ئپAƒJپ[ƒ‹پEƒAƒ}ƒfƒEƒXپEƒnƒ‹ƒgƒ}ƒ“‚ھپAƒiƒ`ƒX‚ة‘خ‚·‚éچR‹c‚جˆس–،‚ًچ‚ك‚ؤ1939”N‚ةچى‚ء‚½پAپu‘’‘—‹¦‘t‹بپv‚إ‚·پB‚ـ‚³‚ة‚»‚جپuژپv‚إ‚ب‚¯‚ê‚خچى‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پAŒƒڈî‚ئœشڑL‚ھچ‚ك‚ç‚ꂽ‚S‚آ‚جٹyڈح‚©‚çگ¬‚郔ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‹¦‘t‹ب‚إ‚·پB ‚±‚±‚إ‚حپAƒRƒpƒ`ƒ“ƒXƒJƒ„‚ح‚»‚ꂼ‚ê‚جٹyڈح‚إŒƒ‚µ‚¢ƒٹƒYƒ€‚إƒGƒlƒ‹ƒMƒbƒVƒ…‚بڈîٹ´‚ً•\Œ»‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚¦‚خپAچإŒم‚ج‰¸‚â‚©‚بٹyڈح‚إ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚·‚·‚苃‚‚و‚¤‚بƒ\ƒچ‚ً’®‚©‚¹‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚ج‹¦‘t‹ب‚ھƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“پEƒ\ƒچ‚ج’´ƒsƒAƒjƒVƒ‚‚ة‘±‚ƒAƒRپ[ƒh‚إƒGƒ“ƒfƒBƒ“ƒO‚ًŒ}‚¦‚½Œم‚ة‚حپA‚Rگl‚جڈڈ—‚ة‚و‚é–¯—w•—‚ج‹ب‚ھ‰ج‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ح–¯‘°“I‚بڈ¥–@‚ة‚و‚é‚ئ‚ؤ‚à‘f–p‚ب‰ج‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA‚»‚ê‚ة‘±‚¢‚ؤپuگي‘ˆ‚جƒJƒfƒ“ƒcƒ@پv‚ئ‚¢‚¤ƒ^ƒCƒgƒ‹‚ج‘¦‹»‰‰‘t‚ھŒJ‚èچL‚°‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚»‚±‚إ‚حƒVƒ…ƒvƒŒƒbƒqپEƒQƒUƒ“ƒN‚إ‰½‚â‚çƒپƒbƒZپ[ƒW‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚àŒê‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حپAگو‚ظ‚ا‚ج‹¦‘t‹ب‚جƒپƒbƒZپ[ƒW‚ئƒٹƒ“ƒN‚µ‚½‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB Œم”¼‚إژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA‚â‚ح‚胔ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‹¦‘t‹ب‚جŒ`‚ً‚ئ‚ء‚½ƒtƒ‰ƒ“ƒNپEƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“‚ج‚Q‚آ‚جŒ·ٹyچ‡‘t‚ئƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“پEƒ\ƒچ‚ج‚½‚ك‚جپuƒ|ƒٹƒvƒeƒBپ[ƒNپv‚ئ‚¢‚¤چى•i‚إ‚·پB”ق‚جچإ”س”NپA1973”N‚ةƒ†پ[ƒfƒBپEƒپƒjƒ…پ[ƒCƒ“‚ج‚½‚ك‚ةچى‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBپuƒ|ƒٹƒvƒeƒBپ[ƒNپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚إ‚«‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پi‚»‚ê‚حپuƒ|ƒٹپ[ƒvپvپjپAکA‘±‚µ‚½ڈ@‹³‰و‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپA‚±‚±‚إ‚ح14گ¢‹I‚ةچى‚ç‚ꂽƒLƒٹƒXƒg‚جژَ“ï‚©‚ç•œٹˆ‚ةژٹ‚é‚PڈTٹش‚ً•`‚¢‚½‚U–‡‚جٹG‰و‚©‚çژَ‚¯‚½ˆَڈغ‚ھ•\Œ»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒuƒbƒNƒŒƒbƒg‚ة‚ح‚»‚جٹG‰و‚àچع‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‹ب‚حپuƒGƒ‹ƒTƒŒƒ€“üڈé‚جˆَڈغپvپAپuچإŒم‚ج”سژ`‚جˆَڈغپvپAپuƒ†ƒ_‚جˆَڈغپvپAپuƒQƒbƒZƒ}ƒl‚جˆَڈغپvپAپuژَ“ï‚جˆَڈغپvپAپuگ_‚ج‰hŒُپiپپ•œٹˆپj‚جˆَڈغپv‚ئ‚¢‚¤‚U‚آ‚جٹyڈح‚©‚çڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ؤپAƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“پEƒ\ƒچ‚حƒCƒGƒX‚جŒ¾—t‚ً•\‚·ƒŒƒVƒ^ƒeƒBپ[ƒ”ƒH•—‚ج‰¹ٹy‚ً‘t‚إ‚ـ‚·پB ‚½‚¾پAƒRƒpƒ`ƒ“ƒXƒJƒ„‚ح‚»‚ê‚ً’Pڈƒ‚ة‰‰‘t‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚P‚آ‚جٹyڈح‚ھڈI‚ي‚邲‚ئ‚ةƒoƒbƒn‚جپuƒˆƒnƒlژَ“ï‹بپv‚ج’†‚إ‰ج‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚Sگ؛•”‚جƒRƒ‰پ[ƒ‹‚ًŒ·ٹyچ‡‘t‚إ‰‰‘t‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB14گ¢‹I‚جٹG‰وپA18گ¢‹I‚جƒoƒbƒn‚جƒRƒ‰پ[ƒ‹پA20گ¢‹I‚جƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‹¦‘t‹ب‚ئ‚¢‚¤پA‚»‚ꂼ‚ê‚جپuژپv‚ةچى‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ھ“¯ژ‚ة•\‚ي‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAپu•œٹˆپv‚ئ‚¢‚¤پu‰i‰“پv‚جژp‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB ‚½‚¾پAژہچغ‚ة•`‚©‚ꂽٹG‰و‚ح‚V–‡‚©‚çگ¬‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“‚حپAچإŒم‚©‚ç‚Q”ش–ع‚جپuل÷ŒYپv‚ة‚ح‰¹ٹy‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚±‚إ”قڈ—‚حپA‚»‚ê‚ً–„‚ك‚邽‚ك‚ةƒ‹ƒ{ƒVƒ…پEƒtƒBƒVƒFƒ‹‚ئ‚¢‚¤ƒ`ƒFƒR‚جŒ»‘مچى‹ب‰ئ‚جپuCruxپv‚ئ‚¢‚¤’Z‚¢‹ب‚ً‰‰‘t‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حپA‚Q‚آ‚©‚R‚آ‚ج‰¹‚¾‚¯‚جƒeƒBƒ“ƒpƒj‚جƒrپ[ƒg‚ةڈو‚ء‚ؤپAƒ”ƒ@ƒCƒIƒٹƒ“‚ھ”ك–آ‚ًڈم‚°‚½‚è‹ZچI“I‚بƒpƒbƒZپ[ƒW‚ً”âکI‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‹ب‚إ‚·‚ھپAژگـپuDies iraeپv‚ج’f•ذ‚ھ’®‚±‚¦‚ؤ‚‚é‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚é‚ج‚ح’P‚ب‚éچِٹo‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBچإŒم‚ة‚حپAƒ`ƒ…پ[ƒuƒ‰پ[پEƒxƒ‹‚جکA‘إ‚إپA‚±‚ج‹ب‚حڈI‚ي‚è‚ـ‚·پB ‚»‚µ‚ؤپAپuƒ|ƒٹƒvƒeƒBپ[ƒNپv‚جچإŒم‚ج‹ب‚ھپA‘S‚ؤ‚ًڈٍ‰»‚·‚é‚و‚¤‚ةڈء‚¦‹ژ‚ء‚½‚ ‚ئ‚ةپA‚±‚ê‚ـ‚إ“xپX“oڈꂵ‚ؤ‚¢‚½ژiچص‚ة‚و‚éƒiƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚إپuƒCƒGƒX‚ح•œٹˆ‚µ‚½پv‚ئŒê‚ç‚ê‚ـ‚·پB چإŒم‚ًڈü‚é‚ج‚حپAپuƒˆƒnƒlپv‚إ‚حچإڈ‰‚ة“oڈê‚·‚éƒRƒ‰پ[ƒ‹پuO große Liebeپi‚¨‚¨پAˆج‘ه‚ب‚鈤پjپv‚إ‚·پB’Z’²‚ج‹ب‚إ‚·‚ھپA‚à‚؟‚ë‚ٌ‰ü’ùŒم‚جچإŒم‚ھ’·’²‚إڈI‚ي‚éƒsƒJƒ‹ƒfƒBڈIژ~‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éŒ`‚ھ‰‰‘t‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAƒ`ƒ…پ[ƒuƒ‰پ[پEƒxƒ‹‚ج—]‰C‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‚±‚جƒAƒ‹ƒoƒ€‘S‘ج‚ج–‹‚ھ‰؛‚낳‚ê‚é‚ج‚إ‚·پB CD Artwork © Alpha Classics |
||||||
‚¨‚ئ‚ئ‚¢‚ج‚¨‚â‚ہ‚ة‰ï‚¦‚éپA‚©پB
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |