|
|
|
|
![]()
ペッパー警部。.... 佐久間學
ここで取り上げられている作曲家は、なんと言っても外せないシベリウス以外では、録音セッションが持たれた時点ではすべてご存命だった、まさに「現代作曲家」ばかりです。それは、録音が完了した数日後に亡くなってしまったラウタヴァーラと、サーリアホという重鎮、そして1955年生まれのユッカ・リンコラ、1970年生まれのリイカ・タルヴィティエという名前を聞くのも初めての方々です。  次の、東京混声合唱団からの委嘱で1993年に作られたという「我が時代の歌」では、その構成はさらに複雑になっていくにもかかわらず、訴えかける力はより強くなっているようです。2曲目の「最初と最後の瞑想」は、キラキラしたオスティナートのなかを、ゆったりとテーマが歌われるという形ですが、そこからラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲の冒頭の夜明けの部分が連想されてしまいました。 それが、まさにこのSWRの委嘱で、この録音の直前に完成した「Orpheus singt」では、テキストがリルケということもあるのでしょうが、まるでロマン派の合唱曲を思わせるようなホモフォニックでシンプルなものに変わっています。 1952年生まれのサーリアホの「Nuits adieux」という作品は、1991年に四重唱とエレクトロニクスのために作られたものを、1996年に4人のソリストと無伴奏混声合唱のために作り直したものです。オリジナルは聴いたことがありませんが、まるで電子音のような効果音を出している合唱と、「無調」のフレーズを歌うソリストという組み合わせはまさに「前衛」音楽です。ただ、合唱は時折しっかりハモっているというのが、「現代的」ですし、後半になってはっきりとリズミカルな部分が登場するのには和みます。 初体験の作曲家、リンコラが2003年の「月の手紙」という作品で見せてくれたのは、まるで合唱コンクールの自由曲にでも使えそうな、適度に難解さを残した手堅さです。そして、タルヴィティエの方は、紛れもない「ジャズ・コーラス」です。ここにヴォイパが入ればそのまんまPENTATONIXになってしまいそうなリズムとテンション・コードの応酬、その中から北欧っぽい抒情性が漂うのですからたまりません。 そして、アルバムの最初と最後を締めているのが、シベリウスです。「恋人」は、彼の代表的な合唱曲、1893年にYL(ヘルシンキ大学男声合唱団)のコンクールで第2位となった作品です。ここでは1898年に改訂された混声バージョンが演奏されています。さらに、1912年には弦楽合奏のバージョンも作られました(↓ブックレットには、なぜかこの弦楽合奏が作られた年代が)。 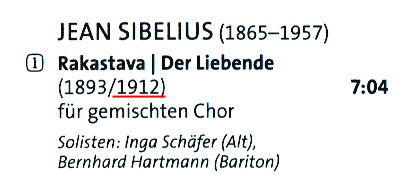 期待通り、これだけ異なる様式で作られた曲たちを、この合唱団は万遍なく完璧に歌い上げています。極端に遅いテンポで迫る「フィンランディア」などは、まさに絶品です。いや、むしろエロい(それは「インランディア」)。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |
||||||
録音年代を見てみると、1964年以前、まだ谷口さんが加入していない、おそらく小保方さんがトップ・テナーを務めていたころのものもありました。それは、いかにも和やかな、まるで「ダーク・ダックス」のような端正な味わいを持ったコーラスに聴こえます。それが、谷口さんに替わってからのものになると、ガラッとそのテンションが別物になっていることが感じられます。さらに年代を経て、谷口さんから飯野さんに替わっていると思われる時期のものが2曲ほどありますが、ここでは確かに別の人が歌っていることは分かりますが、コーラス自体の音色やベクトルはほとんど変わっていないことも気づかされます。ここでも、飯野さんが必死の思いでデュークの黄金期のサウンドを守り続けようとしていたことがはっきりと伝わってきます。 今でこそ、CMに使われる音楽は最初からタイアップを前提に制作されたり、既存のヒット曲そのままだったりするので、音質的には単独で聴いても何の問題もありませんが、この頃はまさに「使い捨て」のノリで作られ、録音されていたのでしょう。しかも、このCDに使われているのはそもそもオリジナルのテープではなく、何度かのダビングを経たり、場合によってはエアチェックされた物だったりしますから、音質から言ったらひどいものです。しかし、そんな劣悪な音で聴いても、デュークのハーモニーは完璧に聴こえてきます。それはまさに、今まで聴けなかった「宝の山」です。だから、こんなところでもデュークのしっかりとした足跡が聴けるのはとても幸せです。 そして、そんな現場で作られた曲たちは、もちろん後世に残ることなどは全く考えられずに作られていたはずなのに、「作品」としてもしっかりしたレベルに達していることにも、驚かされます。それだけの才能をもった作曲家が、この頃はいたのでしょうね。 前田憲男などという大御所は、服部時計店のCMではルロイ・アンダーソンの「タイプライター」を下敷きにしたユニークな曲を作っていましたね。小林亜星も、本田技研のCMなどは、よく知られているキャッチーで親しみやすい作風ではなくもっと尖ったジャズっぽいテイスト満載の曲でした。彼は、普通に考えられているよりはるかに優れた作曲家だったのでしょう。 同じように、CM界で大活躍していたのがいずみたくです。この人の場合はまさに予定調和の積み重ねで曲を作るというタイプなのでしょうが、その中に時折キラリと光るようなものを発見できる瞬間があります。デュークにとっては、いずみたくとのCMの仕事と、「にほんのうた」シリーズとは、まったく同等の価値をもって取り組むことが出来た対象だったのではないでしょうか。日本生命保険の「♪ニッセイのおばちゃん〜」というCMは、そのまま「にほんのうた」の中の曲になっていてもおかしくないほどです。 実際、彼らはコンサートではこれらのCMもきちんとレパートリーにしていましたからね。その片鱗は、このCDの最後のトラックの、コンサートのライブアルバムからのメドレーでうかがうことが出来ます。 ただ、ぜひ聴きたかった「♪光る光る東芝〜」という、「東芝日曜劇場」のオープニングテーマが入っていなかったのは残念でした。これは、最初はダーク・ダックスが歌っていたということで、遠慮したのでしょうか。 それと、ジャケットで和田誠による最新のメンバーの似顔絵が使われているのは、全く理解できません。トップとセカンドは、このアルバムの中では1曲も歌っていない人たちなのですからね。 CD Artwork © Universal Music LLC |
||||||
ベルリン時代の主君フリードリヒ大王は、ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツにフルートを師事し、自身のフルート作品もあるフルーティストでしたから、1755年にエマニュエルは大王のために普通のフルートではなく「バス・フルート」のための曲を作りました。バス・フルートと言えば、現代でもそれほどなじみのある楽器ではありませんし、そもそもそんな時代にこの楽器があったのか、という疑問が最初に湧いてくるのではないでしょうか。写真でその姿を見れば、それはいかにも近代の工業技術が産んだもののように思えます。頭部管はきれいにU字型に曲がっていますから、18世紀の木管の楽器ではこんな形に出来るわけがありません。   ここで演奏されているのは、バス・フルート、ヴィオラと通奏低音のためのヘ長調のトリオ・ソナタです。ただ、ここでライナーノーツを書いているフォルテピアノ奏者のヴォルフガング・ブルンナーによれば、この曲には2つのヴァイオリンと通奏低音、そしてバス・フルートとファゴットと通奏低音という、他の楽器編成のバージョンもあるのだそうです。  アルバム・タイトルの「四重奏曲」は、作曲家の最晩年、1788年に作られたト長調、ニ長調、イ短調の3つの作品です。「四重奏曲」という割には楽器は3人だけ、つまり、フォルテピアノの右手と左手で「二重奏」分を賄っている形です。バロック時代にはこのような編成では左手のパートが始終チェロなどで補強されていたものですが、この曲の場合はそのような楽器は要求されておらず、あくまで3人だけでの合奏で、よりクリアなサウンドが目指されているようです。まさに、音楽の様式が変わりつつあった時代を象徴するかのような楽器編成なのではないでしょうか。 いずれも3楽章形式、真ん中の楽章はゆったりと歌い上げるというイタリア風の作品です。その、アダージョもしくはラルゴ(ニ長調では「Sehr langsam」というドイツ語表記)の楽章の深い味わいはとことん魅力的、これらの曲のどこをとってもエマニュエルでなければ作れなかったセンスであふれています。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |
||||||
そこで、ウィーン国立歌劇場のライブ録音を行っているオーストリア放送協会の音源を多数CDでリリースしてきたORFEOから、彼の追悼の意味が込められたアルバムがリリースされました。1996年2月にこのオペラハウスにデビューしたボータは、2015年の4月にここでの最後の公演を迎えるまで、全部で222回もの出演回数を誇っています。そこで歌った役も、全部で21種類にのぼっています。そんな膨大なアーカイヴの中から、1997年の「ローエングリン」に始まって、2014年の「ナクソス島のアリアドネ」に至るまでの8つのシーンが、ここには集められています。 曲順は年代とは関係なく収録されていますが、録音された年代を意識しながら聴いていくと、ボータの歌の変遷がよく分かります。というか、この人は年齢を重ねていく中で、こんなに変わっていってしまったのかと、驚かされます。最も若い時の「ローエングリン」とか、1999年に録音されたシュトラウスの「影のない女」のカイザーなどでは、本当に若くて伸びのある声を聴くことが出来ます。そこにはほのかな甘さがありますから、音だけ聴いているとどんなにスマートなイケメンが歌っているのだろう、と思ってしまうほどです(彼は、外見ではだいぶ損をしていました)。ただ、幾分線が細く、あまり力強さは感じられません。 それが、2004年のベートーヴェンの「フィデリオ」のフロレスタンやシュトラウスの「ダフネ」のアポロ、そしてパルジファルになると、その声に俄然張りが出てきます。表現力もさらに高まってきて、おそらくこのあたりがボータの最も輝いた時期なのではないか、と思えてしまいます。これは間違いなく当時の「世界一のヘルデン・テノール」でした。 余談ですが、この「フィデリオ」は、2002年から2010年まで音楽監督を務めていた小澤征爾の指揮で歌っています。ボータが小澤と共演したのは、この年の「フィデリオ」が5回と、翌2005年の「さまよえるオランダ人」のエリックの3回しかないのだそうです。「オランダ人」はあいにく録音が残っていないので、この「フィデリオ」の2004年の録音が唯一の記録となりました。ただ、この演奏はボータの声には圧倒されるものの、バックの小澤がなんとも緊張感の薄い音楽に終始しているのがとても気になります。ワーグナーなどは途中で拍手が入る隙はありませんが、ベートーヴェンはジンクシュピールですから、アリアの切れ目がちゃんとあります。そこで、ボータが歌い終わるやいなや、まだ後奏が演奏されているというのに盛大な拍手が起こります。お客さんは、小澤ではなくボータを聴きに来ていたのでしょうね。 ところが、2010年の「タンホイザー」や2012年の「マイスタージンガー」(ヴァルター)、そして2014年の「ナクソス」あたりになると、声がかなり重たくなってきます。明らかにペース配分を考えて力を抜いているところも見られますし、ちょっと歌うのが辛いのでは、と思えるようなところまで出てきます。それは、2008年に別のところで録音された「ローエングリン」を聴いた時にも感じていたこと、どうやら、このあたりで彼のピークは終わっていたのでしょう。 ルネ・コロのように、長生きをして醜態をさらすことなく、コロッと亡くなったのは、彼にとって幸せなことだったのかもしれません。 CD Artwork © ORFEO International Music GmbH |
||||||
ですから、彼らは今までとは何ら変わらない、非常に価値のあるコンサート、そしてそのライブ録音によるアルバムのリリースに邁進することになるのです。最初に耳にした「幻想交響曲」こそ、演奏も録音もいまいちでしたが、その後バレエ・リュスのレパートリーに着手したあたりから、彼らはどんどん進化を始めていますからね。ただ、ジャケットのデザインは確実につまらなくなりましたし、彼らの新しいロゴマーク(右)からも、以前(左)のスタイリッシュな味はなくなっています。  もちろん、ロトたちは全曲を演奏してくれています。例によって、楽器に対するこだわりはハンパではなく、弦楽器はガット弦、管楽器も極力20世紀初頭にフランスで作られたものが集められています。ちょっと興味深いのが、キーボード・グロッケンシュピールの表記です。ラヴェルの楽譜には「Jeu de Timblesジュ・ド・タンブル」と書いてありますが、このCDの楽器リストでは「Glockenspiel à clavier Mustel」つまり「ミュステル製の鍵盤グロッケンシュピール」となっています。私見ですが、「ジュ・ド・タンブル」といった場合には、普通はトイ・ピアノのような外観の平べったい楽器を指し示すような気がしますが、ミュステルの楽器はそうではなく、チェレスタと同じような縦型なので、そのあたりを正確に記したかったのではないでしょうか。 さらにロトは、楽譜そのものもきっちり検証し、多くの間違いを正しています。さらに、合唱の位置に対する細かい指示(「ステージの後ろで」、「ステージの上で」、「近づいて」といったもの)も、ステージの両翼を使って実現させているのだそうです。ただ、この録音では合唱が「ステージの後ろ」で歌っている部分でも、とてもくっきりと聴こえてきますから、おそらく実際の音響ではなく視覚的な効果によってその位置を表現していたのでしょう。第1部の最後で合唱がア・カペラで歌われる時には、ステージは真っ暗になっていたのだそうです。 おかげで、コンサートホールを埋め尽くした聴衆も、その録音をこのDCで聴いている人たちも、このアンサンブル・エデスという2005年に結成されたばかりの若々しい合唱団の卓越した演奏を存分に味わうことが出来ることでしょう(とてもええですよ)。この曲で、合唱がこれほど重要なパートだということに、初めて気づかされました。 オーケストラでは、管楽器は言うまでもありませんが、弦楽器のなんとも言えないソノリテはやはりこの曲からは初めて味わえるものでした。 フルート・ソロのマリオン・ラランクールは、いつものルイ・ロットから甘い音を引き出しています。ただ、「パントマイム」の大ソロは、あくまで、アンサンブルの中のフルートという感じで、それほどの存在感はありません。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |
||||||
彼らは、フランス東部のスイスにも近い都市ディジョンにあるディジョン・オペラとはレジデントという関係で共同作業を行っています。とは言っても、ピットに入って演奏するわけではなく、そのカンパニーが主催しているオーケストラコンサートを、その本拠地であるディジョン・オーディトリアムで継続的に行っている、ということなんですけどね。そこで行われたこれまでの演奏のライブ録音が、このCDには収録されていま。もちろん、ライブ映像も、ここで撮影されました。 まずは、2010年から2013年にかけて収録されたベートーヴェンです。基本的にノン・ビブラートでピリオド的なフレージングというきびきびしたスタイルがとられていますから、テンポもかなり速めな設定です。それが、指揮者がいないとは思えないほど自由自在にテンポが変わるのがとてもエキサイティング。というより、指揮者に強制された無茶なテンポではなく、あくまでプレーヤーの自発的なテンポなので、説得力があります。もちろん楽譜は原典版が使われていますが、「5番」の第3楽章ではベーレンライター版にはない繰り返しが採用されていたりします。 問題はシューベルトの「7番」(CDの表記は「8番」)。いくらピリオドでも、これは早すぎるだろうというテンポ設定は、ちょっとついていけません。特に第2楽章は、まるでワルツのようですからね。さらにちょっとしたユーモアのつもりなのでしょうが、そのあとに「第3楽章」を、オーケストレーションが完成している20小節まで演奏して、そこでプッツリやめる、ということをやっています。お客さんには受けているようですが、笑えません。それと、この曲だけ明らかに他のものとは音響が違って聴こえます。確かにデータには「フィルハーモニー・ド・パリ」とありますし、そこで演奏している写真もあるのですが、録音されたのが「2013年」というのは、このホールが出来たのが2015年ですからありえません。 最近録音されたモーツァルトは、管楽器がメイン。「オーボエ協奏曲」ではメンバーのアレクサンドル・ガテがソロですが、とても穏やかな演奏で、第3楽章のテンポなどはなんとも和みます。弦楽器はコントラバスだけで、あとは管楽器セクションだけで演奏される「グラン・パルティータ」でも、それぞれの奏者は気持ちよさそうに歌っています。最初の楽章の序奏で、しっかり複付点で演奏してくれているのもうれしいですね。 CD Artwork © Dissonances Records |
||||||
「クッレルヴォ」というのは、おなじみ、北欧叙事詩の「カレヴァラ」に登場する人物の名前です。その悲劇の主人公が描かれた部分をテキストに使っていますが、そのお話は主人公が鍛冶屋に奉公に出されるとか、死んだはずの妹が実は生きていて、それとは知らずに関係を持ってしまうとか、なんだかワーグナーの「指環」とよく似たエピソードが登場します。このあたりのルーツは一緒なのでしょうね。そんなテキストの中のクッレルヴォのセリフをバリトンが歌い、クッレルヴォがナンパする女性3人のセリフをメゾ・ソプラノが歌います。3人目の女性が、実は妹だったんですね。そして、それ以外の情景や感情の描写が、男声合唱で歌われます。ですから、基本的にこの作品は劇音楽としての性格を持っています。ただ、全く声楽の入らない楽章もあって、それぞれがソナタ形式をとっていたり、スケルツォ的な性格を持っていることから、交響曲としての要素もあります。ここには、後のシベリウスの音楽のエキスが、数多くちりばめられています。ちょっと辻褄があわないところはあるにしてもこの涙を誘う物語は、まるで大河ドラマのような(@新田さん)壮大な音楽に彩られて、深い感動を誘います。 この作品は完成直後の1892年4月に作曲家自身の指揮によって初演され、大好評を博しました。しかし、彼の生前には出版もされず、全曲の演奏も長い間行なわれませんでした。ブライトコプフから楽譜が出版されたのは、1966年のことです。日本で初演されたのは1974年、渡邉暁雄指揮の東京都交響楽団による演奏でした。余談ですが、今年はフィンランド独立100周年ということで、同じ東京都交響楽団が11月にハンヌ・リントゥの指揮でこの作品を演奏するのだそうです。もちろん、2015年には新田ユリさん指揮のアイノラ交響楽団も演奏していたのは、ご存知の方も多いことでしょう。いずれにしても、演奏される機会は非常に少なく、録音でも北欧系の指揮者以外でこの曲を取り上げているのはコリン・デイヴィスとロバート・スパノぐらいしかいないのではないでしょうか。 そんな珍しい曲を、2度録音してくれた人がいます。それは、フィンランドの指揮者オスモ・ヴァンスカ。1回目は2000年のラハティ交響楽団との録音、そして今回2016年のミネソタ管弦楽団との録音です。どちらもレーベルは同じ、さらに、合唱団(YL=ヘルシンキ大学男声合唱団)とメゾ・ソプラノのソリストまで同じです。演奏時間もほぼ同じ、第5楽章だけ、今回の方が1分ほど早くなっていますが、別に聴いた感じそんなに違いはありません。ただ、録音は今回の方がワンランク上がっています。それに伴って、合唱の表情などがより生々しく伝わってきているでしょうか。 これが演奏されたのは、フィンランドから北アメリカへの移住が始まってから150年を記念するコンサートでした。そこでは、ミネソタ管弦楽団とヴァンスカが1955年生まれのフィンランドの作曲家オッリ・コルテカンガスに委嘱した「移住者たち」という作品が初演されています。どこかの国の大統領や総理大臣ではありませんよ(それは「異常者たち」)。この作品では、その「移住150周年記念」というテーマの他に、このシベリウスの「クッレルヴォ」との相似性も追及されていると、作曲家は言っています。ここでも、男声合唱は大活躍、ア・カペラの合唱だけで演奏される楽章もあります。 そして、最後にもう1曲、シベリウスの「フィンランディア」でもこの男声合唱団があのテーマを高らかに歌い上げています。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
結成されたのは1955年ですが、その時のメンバーで今日まで歌い続けているのはバリトンの谷道夫さんだけです。ただ、1958年までにセカンドテナーの吉田一彦さんとベースの槇野義孝さんが加入した後は、この3人は2014年までの57年間変わることはありませんでした。これは驚異的なことです。イギリスの「キングズ・シンガーズ」などは、やはり50年近くの歴史を誇っていますが、メンバーの中で最も長く在籍したデイヴィッド・ハーレイ(カウンターテナー)の在籍期間は「たった」26年ですからね。 何度も代わっていたのはトップテナーのパート。初代(最初はセカンドでした)の和田昭治さんは1960年に小保方淳さんに代わり、さらに1964年には谷口安正さんに代わって、ここからこのグループの黄金期を迎えます。永六輔といずみたくのチームが作った「にほんのうた」シリーズが次々にリリースされたのはまさにこの時代ですね。この中からは、「女一人」とか「いい湯だな」といった、今にまで伝えられる名曲も生まれています。「筑波山麓合唱団」も、ある意味男声合唱の定番ですね。 さらに、トップテナーの人事異動は続きます。1991年からは谷口さんの急逝を受けて飯野知彦さん、そして2010年からは大須賀ひできさんに代わっています。 2015年に60周年、つまり「還暦」を迎えるにあたって、デューク・エイセスはその前年に「感謝還暦」というアルバムをリリースします(「還暦」が「感激」もじりだということは説明の必要はないでしょう)。ここでは、彼らの鉄板のレパートリーであるニグロ・スピリチュアルズやジャズ・コーラスのスタンダードの他に、かつて永六輔が作詞、中村八大が作曲をし、永自身が歌った「生きるものの歌」の、永のセリフ入りバージョンと、新曲の「友よさらば」が加わっていました。それを引っさげてのツアーが、同じ年の10月から始まるのですが、そのステージにはセカンドテナーの吉田さんの姿はありませんでした。彼は体調を崩して療養中だったので、代役の岩田元さんがそのパートを務めていたのです。翌年の3月には吉田さんの引退が発表され、岩田さんが後任となることが決まりました。 そして、それから2年後に、デューク・エイセスの解散が告げられました。今年の末には、この男声カルテットは62年の歴史に幕を下ろすのです。決して19(ジューク)年で終わることはありませんでした。 岩田さんが加入してから最初の、そしておそらく最後となるアルバムが、この「60周年記念盤」です。5年前にも55周年記念アルバムhttp://www.ne.jp/asahi/jurassic/page/oyaji2/oyaji_84.htm#dukeを出していましたが、これも同じような内容のベストアルバムです。何曲か、55周年盤と同じ曲が収録されていますが、「おさななじみ」の続編と続々編、そして「ここはどこだ」を除いては全て別テイク、オリジナルではなく、1992年にリリースされた「新世界」というタイトルのセルフカバーアルバムのために録音されたものです。ただ、それはいろいろ調べて分かったことで、このアルバムにも55周年盤同様録音データは一切記載されてはいません。 そして、新録音として、2015年の3月の、最後のメンバーによるライブ音源が2曲入っています。これを聴いて、デュークはトップテナーが大須賀さんに代った時点ですでに終わっていたことを強く感じました。先ほどのセルフカバーでは、飯野さんは極力谷口さんのコピーに徹しようとしていましたが、この人は最初からそんな努力とは無縁だったようです。そこに素直な声の岩田さんが加入して、この異質な声はより際立って聴こえます。なぜこんな人を入れたのか、理解に苦しみます。悔やまれてなりません。 CD Artwork © Uninversal Music LLC |
||||||
1986年に、現在の指揮者トーヴェ・ラムロ=ユースタによって創設されたこの合唱団のメンバーは、全員がアマチュアですが、それぞれの音楽に対する真摯な姿勢は、とても熱いものがあるのだそうです。世界各地で行われた合唱コンクールでも堂々たる成績を収めていて、その実力は折り紙つきです。もちろん、それだけでは単なる「上手な合唱団」で終わってしまい、全世界でリリースされているレーベルからアルバムがリリースされるほどの「商品価値」はありません。彼女たちは、先ほどのレビューにもあったように、ディズニーのアニメのサントラに起用された、という幸運によって、一夜にして世界を相手に出来る合唱団になっていたのです。 その、「Frozen」のオープニングで、まるでミュージカルのオーバチャーのような扱いで登場するのが、彼女たちによって歌われた「ヴェリイ(Vuelie)=歌」というア・カペラの曲でした。この曲を作ったのが、指揮者のラムロ=ユースタとは音楽大学時代からの知り合いで、自身も サーミ人でノルウェーの民族音楽の伝承者である作曲家のフローデ・フェルハイムです。彼は、この合唱団とは創団時からなにかと相談を受けていたそうで、1996年に彼女らの2枚目のCDとなるクリスマス・アルバムのために「Eatnemen Vuelie(大地の歌)」という曲を作りました。これは、サーミ人独特の民族的な唱法である「ヨイク」のフレーズと、ヨーロッパ全土で親しまれている讃美歌が一緒に歌われるものです。これを聴いたディズニーの制作者から、「Frozen」のバックボーンであるスカンジナビアの世界を現すものとして、この曲を使わせてほしいというオファーが届いたのです。最終的に、その曲は少し手直しされて彼女たちによって歌われ、「Vuelie」というタイトルでサントラに流れることになったのです。冒頭ではア・カペラだったものが、最後に呪いが解ける部分でリプリーズとして再現されるときには華やかなオーケストラがバックに流れ、見るものに感動を与えるという重要な役割を果たしています。 元々力のあったこの合唱団は、この曲で大ブレイク、2LからはSACDとBD-Aというハイレゾメディアがリリースされますし、アメリカへのツアーも行われるようになりました。そして、さらにワンランクのアップが、このDECCAというメジャー・レーベルからのアルバムのリリースです。もちろん、メインタイトルは「Vuelie」、さらに、全ての曲がそれを作ったフェルハイムの作品(1曲だけは彼の編曲のみ)となっています。 「Vuelie」では、2L盤では入っていたフェルハイムのダミ声はなくなっています。さらに、編曲もキーボードとパーカッションというシンプルなものではなく、もっと大規模なオーケストレーションが施されています。その他にも何曲か同じ曲が歌われていますが、一番変わったと思えたのが、元々はヨイクだったものがベースになった「Njoktje(白鳥)」という曲です。2L盤とは歌い方も違っていて、民族的な味わいがすっかり消え去っていました。 もしかしたら、今回のアルバムも2Lのリンドベリによる録音では、と思ったのですが、そうではありませんでした。まずは、音圧が異常に高いポップス仕様のものでした。もちろんハイレゾではありませんからその音は2Lとは比較にもなりません。明らかに、そのような需要を狙ったものなのでしょう。メジャー・デビューというのは、そういうことなのです。 CD Artwork © Decca, a division of Universal Music Operateion Limited |
||||||
 The Beatles Album Visual Book(2000年リットーミュージック刊)より ジャイルズが行ったのは、現代のリスナーにとって聴きやすい音に仕上げる、ということだったのでしょう。半世紀前はまだステレオというのは特別なものでしたから、このアルバムもイギリスやアメリカではステレオ・ミックスとモノラル・ミックスの2種類が用意されていました。ステレオにしても、今聴くと単純に「右」、「真ん中」、「左」とヴォーカルや楽器を割り振った、というものでした。それが、ここではすべてのメイン・ヴォーカルは真ん中に定位させています。そして、コーラスはその周りに広がりを持って定位、ということまで行われていて、真の意味での「立体感」が表現できるようになっています。もちろん、それぞれの音のクオリティも格段に向上しています。 それはそれで、初めてこれらの作品に触れる人にとってはありがたい配慮なのですが、長年聴きなれたファンにとっては、ちょっと納得のいかないところもあるのではないでしょうか。たとえば、「A Day in the Life」では、ジョンのヴォーカルは右から始まって真ん中、左と移動するという形が曲の印象として刷り込まれていますから、それを真ん中に固定されてしまうと戸惑ってしまいます。 そして、もっと重要な問題も。このアルバムでは何曲か、ミキシングが終わったところで、全体のテープスピードを少し操作してピッチを変えているものがあります。その、最終のカッティング用のマスターでリマスタリングを行っていた分には何の問題も出てこないのですが、ジャイルズの場合、元のスピードのままのテープでミックスを行って、それを最終的にデジタルでテープスピードを変化させているために、オリジナルとはピッチが変わってしまっているのですよ。それは、同梱されていたCDの中に入っていた「When I'm Sixty-Four」で最終的に採用されたテイクと聴き比べて分かったことです。オリジナル、つまり2009年のリマスター盤ではほぼ6%早くなっていたのに、今回のリミックス盤では4%しか早くなっていませんでした。実際に聴いてみると、オリジナルでは半音高く聴こえますが、リミックス盤ではとても微妙、製作者の意図とは別物になっています。 正直、「With a Little Help from My Friends」でのポールのベースを聴いた時には、そのクリアな音に狂喜してしまいました。しかし、こんないい加減なことをやっていたのには、本当にがっかりです。おそらく、これからも他のアルバムのリミックスは行われるのでしょう。しかし、非常に残念なことですが、それを聴く時にはオリジナルとは別物であるという意識で接する必要がありそうです。 CD Artwork © Calderstone Productions Limited |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |