|
|
|
|
![]()
餌食った猿ねん。 佐久間學
おそらく、最近はすべてこのレーベルだけで制作するのではなく、もっと手広く他のプロダクションも扱うようになったからなのでしょうね。生き残るためには、ある程度の妥協は必要なのでしょう。 ですから、今回のCDも、プロダクションはここでヴァイオリンを演奏しているガイ・ブラウンシュタインの名義になっています。かつてベルリン・フィルの第一コンサートマスターだった人ですね。あの樫本大進をベルリン・フィルのコンサートマスターになるように誘った人としても知られています。そして、樫本が入団してしばらくしたら、彼はベルリン・フィルを退団して、アンサンブルなどに精を出すようになりました。 そんな彼がイニシアティブをとって制作したアルバムには、「Old Souls」という、クラシックらしからぬ粋なタイトルが付いていました。 「古い魂」という意味なのでしょうが、ここではロマン派の音楽という「古い」ものに新しい「魂」を込めた、といったような意味合いなのでしょうか。ゴシゴシこするんですね(それは「古いタワシ」)。 実際に演奏されているのは、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第4番、ヴォルフの弦楽四重奏のための「イタリア風セレナード」、クライスラーのヴァイオリンとピアノのための「シンコペーション」、そして、ドヴォルジャークの弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」を、フルート四重奏曲、またはフルート五重奏曲に編曲したものです。編曲を行ったのはブラウンシュミット、これまでアンサンブルで共演してきたフルーティストのギリ・シュワルツマンとアイディアを出し合って、作り上げました。 まず、ベートーヴェンをフルート+弦楽四重奏というフルート五重奏に編曲されたものを聴いてみましょう。全部で5つの声部が使えるので、オリジナルのヴァイオリンとピアノのパートをそのまま移しただけでは楽器が余ってしまいますから、フルートがソロで聴こえてくるところはあまりなく、ほとんどがヴァイオリンとのユニゾンになっています。そこでは、フルートはあまり出しゃばりませんから、全体的に弦楽器たちの響きの中に溶け込んだ、落ち着いたサウンドに支配されています。ですから、ほんの一瞬フルートだけになるところは、かなり目立ちます。 最後に演奏されているのが、ドヴォルジャークの「アメリカ」ですが、これはオリジナルの弦楽四重奏の第1ヴァイオリンのパートをほとんどそのままフルートに置き換えたという素直な編曲です。実際、フルートでは出せない低い音はほとんど使われてはいないので、弦楽四重奏の楽譜をそのまま使って演奏することも可能です。 しかし、この曲の場合、楽器が一つ変わっただけなのに、全く別の曲のような印象を受けることになってしまっていました。あまりに原曲に親しんでいたせいもあるのでしょうが、聴きなれた「アメリカ」とは、ことごとく違和感があるのですよ。もっともそれが顕著なのが、最後の楽章です。あの軽やかなメロディが、フルートで歌われることによって、それが弦楽器たちから浮き上がってしまって、アンサンブルとしてのグルーヴが完全に別物になっているのですね。ちょっと、フルートにとってはかわいそうな結果に終わってしまいました。 同じ弦楽四重奏をフルート四重奏にしたヴォルフの曲は、あまり聴きなれていない分、結構楽しめたのは、ちょっと皮肉な感じですね。 クライスラーの曲も初めて聴きましが、これはもろスコット・ジョプリンの「ラグタイム」から影響を受けたものなのでしょうね。 CD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
いずれもオルガン伴奏によるバージョンですが、これもそれぞれ別のオルガニストが演奏していて、「クム・ユビロ」はランドール・ハーロウ、「レクイエム」はマリコ・モリタという、この大学で教鞭をとっている方々です。「モリタ」さんは日本人ですが、どのような漢字表記なのかは、調べた限りでは分かりませんでした。なんでも彼女は、インディアナ大学のジェイコブス音楽院で、オルガン演奏の博士号を取った最初の日本人なのだそうです。 このコンサートは、「ミサ『クム・ユビロ』」から始まったようです。演奏が始まった瞬間、なにか今まで聴いてきたものと比べてテンポがかなり速いような気がします。そして男声合唱が歌い出すと、そのあまりのいい加減な歌い方に驚かされることになります。この曲は、全て男声がユニゾンで単旋律を歌うという、徹底的にグレゴリオ聖歌を模倣した形で作られているのですが、それがユニゾンに聴こえないほどピッチはバラバラ、さらにこのテンポですから、細かい音符は全然歌えていません。 確かに、「本家」のグレゴリオ聖歌では、現代の合唱のような均質性は求められてはおらず、逆にそのバラバラな声の集まりがアイデンティティとなっているのでしょうが、この演奏は別にそれを目指しているわけではなく、単に現代の合唱団としてのスキルが不足しているだけのことのように思えます。 なによりも、オルガンの伴奏がとてもきっちりした演奏に徹しているので、合唱のダメさ加減はさらに強烈に伝わって来ることになっています。何箇所かでソロ(テノール?)が登場しますが、これは立派な声なので合唱のメンバーではなく、ちゃんとしたソリストなのでしょう。 続く「レクイエム」もこんなんだったらいやだな、と思って聴きはじめると、最初の「Requiem〜」という男声の歌い出しがとっても穏やかだったので、まずは一安心です。やはり、この混声合唱団のメンバーはさっきの男声合唱団とは別のメンバーのようですね。その後に入る女声の「アー」というオブリガートもとても爽やか、これだったら、全然格の違う合唱が楽しめそうです。 ところが、です。その女声が、音楽が盛り上がって「et lux perpetua」あたりになった時に、その表情が一変します。今までおしとやかな少女だったものが、突然年老いた魔女のように変貌してしまったのです。もう激しいビブラートはかけるわ、制御不可能なまでに叫びあげるわで、正気の沙汰とは思えない情景となってしまったのですよ。 ですから、他の楽章でも、最初はおしとやかな女声で始まったとしても、油断はできません。そんな可憐にふるまう姿の後ろには、常にあの強烈なビブラートの萌芽が隠されているのが、もはやわかっているのですから、その先のクライマックスを想像するだけで、恐ろしくなってしまいます。案の定、そのクライマックスでは、これでもかというような阿鼻叫喚が何度も何度も繰り返されることになるのです。こんな演奏にはとても共感できません。 ここでは、最近よく使われる、バリトン・ソロのパートを合唱のバリトンパートのトゥッティで歌う方法が取られています。これは、そこそこ穏やかな歌い方でまずは安心して聴いていられます。中で、管理されない声が多少混じっているぐらいは我慢しましょう。 「Pie Jesu」では、普通にメゾ・ソプラノのソリストが歌っています。この方も、とても平板な歌い方と、情けない低音で、がっかりです。 CD Artwork © Centaur Records, Inc. |
||||||
ですから、当時の音楽愛好家が、オペラハウスで演奏されていたモーツァルトのオペラを追体験するためには、本当はもう何度かその劇場に足を運ばなければいけないのでしょうが、もっと手軽に自宅でその音楽に浸りたいと思っている人には、その人が自分で演奏するか、あるいは専門の音楽家に演奏させるために、オペラの聴きどころをフルートやヴァイオリンの二重奏で弾けるような楽譜が盛んに出版されていました。 そのような「編曲」は、作曲家自身が手掛けることもありましたが、それよりもっと頻繁に行われたのは、作曲家「以外の」人がその作業を行うことでした。当時は、音楽を記録する機械と同様、著作権という概念も存在していませんでしたから、楽譜を売りたい出版社は勝手に人気作曲家の作品を手軽に「お茶の間」で演奏できるように、その辺にゴロゴロしていた作曲のスキルを持った人に編曲させたのです。 ということで、まず「魔笛」の2本のフルート、または2挺のヴァイオリンのためのハイライト集が、モーツァルトが亡くなった翌年の1792年にショット社から出版されます。ただし、これに関しては、モーツァルト自身が編曲に関与していた可能性もあるのだそうです。 そして、それに続いて、彼のヒット作「フィガロの結婚」、「後宮」、「ドン・ジョヴァンニ」の同じ編成の編曲が、1809年ごろまでの間に相次いで出版されました。現在では、UNIVERSALから1970年代に新しく校訂された楽譜が出版されています。この楽譜はフルートの中級者程度でも容易に演奏できるぐらいの難易度なので、おそらく多くのフルート愛好家たちがこぞって手を染めていたのではないでしょうか。 ただ、「プロ」がこの4曲をまとめて録音することは、あまりなかったようです。そんな中で、今回マスサンス・ラリューがこの全曲を録音してくれたのは朗報です。ラリューと言えば、1935年生まれで、もうとっくに80歳を超えていますが、まだ活躍していたのですね。もっとも、ペーター=ルーカス・グラーフなどはすでに90歳となってもまだ現役ですから、それに比べたら80歳なんてまだまだ「若手」です(冗談です。分かって下さい)。 もちろん、ラリューは1番フルートのパートを演奏しています。そしてここでは、2枚組のCDの1枚目の「魔笛」と「フィガロ」では東條さん、2枚目の「ドン・ジョヴァンニ」と「後宮」では清水さんと、それぞれラリューの日本人のお弟子さんであるお二人が2番フルートを担当しています。 というのも、このCDはフランスのSKARBOというレーベルからリリースされていますが、録音が行われたのは東京の五反田文化センターホールという、キャパが250人の小さなホールですし、レコーディング・エンジニアはALMレコードの小島幸雄さんなのです。ラリューは2018年の5月に来日して、東京(22日、東條さんと清水さんも参加)と大阪(27日)でコンサートを行いましたが、その前の17日と18日のたった2日間でこれだけの曲を録音してしまいました。 そして、出来上がったCDは、とても完成度の高いものでした。ラリューの音からは、さすがに往年の輝きと伸びやかさはほんの少し失われてはいますが、テクニックの冴えはいささかの衰えもありません。そして、2番を務めるお二人も、ラリューとぴったり息の合った素晴らしいアンサンブルを作り上げています。 この編曲は、「魔笛」だけ他の3曲とプランが異なっていて、1番と2番が交代でメロディを吹くようになっています。ですから、そこではラリューと東條さんとの音の違いを聴き分けることができるのですが、そのニュアンスやフレージングは全く同じように感じられますからね。 CD Artwork © Skarbo |
||||||
それ以降、このレーベルによって作られたベートーヴェンの交響曲全集と言えば、カラヤンの3度目の録音を除けば、ガーディナー、アバド、プレトニョフといった、「巨匠」には程遠い指揮者(諸説あります)によるものでした。と同時に、この頃はベートーヴェンの演奏に対するアプローチが劇的に変わっていった時期とも重なります。その要因は、新しく校訂された楽譜の刊行と、ピリオド楽器の台頭です。ガーディナーはピリオド楽器のオーケストラによるコンパクトなベートーヴェン像を提示、アバドは新しいベーレンライター版の楽譜を使ったことを前面に出し、プレトニョフは「伝統」にとらわれない自由な解釈の可能性を見せてくれたのです。 そして、世の中のベートーヴェン像そのものも、それまでとは打って変わって「軽い」ものに変わっていきます。人々は、それまでは「伝統」と思われていたものにはなんら敬意を払う必要がなかったことに気づいてしまったのです。 しかし、「伝統」はしぶとく耐えていました。やがて、ベートーヴェンの生誕250年を迎える頃には、もはや「原典版」や「HIP」からはかつての新鮮さは失われていました。そんなタイミングでDGが放ったのが、伝統的なオーケストラが伝統的な解釈で演奏した、この交響曲全集です。 このCDとBDのパッケージはとても立派な装丁なのですが、その中のブックレットは、普通は必ずあるはずの演奏者のプロフィールが一切掲載されていないという不完全なものです。ですから、もちろん楽譜の情報などは一切記されてはいません。ただ、この中の写真にあるスコアの表紙の色(↓)と、ネットの動画でのページの変わり目をチェックすると、指揮者のネルソンスはベーレンライター版のスコアを使っていることが分かります。  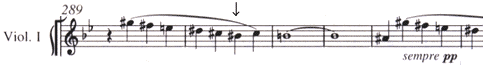 ただ、サウンドに関しては、レーベルとしての「伝統」は、もはやここにはありません。すでに録音スタッフは全て外注になってしまったDGでは、かつてのトーンポリシーは完全に失われてしまいました。その代わり、再生メディアについては、CDと一緒に全曲がBD-A1枚に収まったものも入っています。もちろん、録音フォーマットは24/96のハイレゾですから、ウィーン・フィルの繊細な弦楽器がCDとは比べ物にならないほどの美しさで聴こえてきます。 ところが、そのBD-Aにはなんと2チャンネルステレオしか入っていないのです。この演奏は映像でも収録されているようで、サラウンドでの録音も行われていたはずですから当然サラウンドも聴けることを期待していたのですが、それは見事に裏切られてしまいました。皿うどんを頼んだら、きつねうどんが出てきたようなものです。 半世紀前のカラヤンやバーンスタインがBD-Aでリイシューされた時には、本来のサラウンドのフォーマットで聴けるようになっていたのに、最新録音でそれが出来ないのはなぜなのでしょう。 CD & BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
つまり、確か「生誕200年」にあたる1970年に向けて、DGでは1969年から全12巻、LP76枚の「ベートーヴェン・エディション」のリリースを始めましたが、それは全部集めると当時は11万8千円かかったからです(こちらに当時の広告があります)。これは、今の貨幣価値だと50万円ぐらいでしょうか。 そのDGが今回も作った「全集」は、CDが118枚、BD-Aが3枚という、NAXOSを大幅に超える枚数になっています。ただ、よく見てみると有名な曲は複数の演奏家による録音が収録されているのですね。交響曲などはそれぞれ4種類の別の録音のものや、別に「歴史的録音」や「ピリオド楽器」もありますから、曲目の正味の数はNAXOSとほとんど変わらないでしょう。それでいて価格は4万円ですって。1枚300円ちょっとですから、すごいですね。ついでに、交響曲も歌曲も1曲として曲数を数えてみたら延べ570曲ぐらいありましたから、1曲あたり70円ですね。安すぎます。 それとは別に、DGでは交響曲とピアノ協奏曲の最新録音の全集も作りました。そのうちのピアノ協奏曲を聴いてみました。 まず驚くのが、この記念プロジェクトを任されたのがかつての天才少年、1995年生まれのヤン・リシエツキだということです。さらに、ここでは彼が「弾き振り」をしています。 とは言っても、今回の「相方」はアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(最近は「アカデミー室内管弦楽団」とは言わないのですね)という8.6.4.4.2の編成の「室内管弦楽団」ですから、指揮者がいなくても演奏できる団体です。おそらく、コンサートではコンサートマスターのトモ・ケラーの弓に合わせて演奏していたのでしょう。そんな体制で2018年12月にベルリンのコンツェルトハウス(かつて「シャウシュピールハウス」と呼ばれていたコンサートホール)でのライブ録音です。 ネットでは、プロモーション用の映像が流れていますが、それを見るとチェロパートで譜面台にタブレットを置いてあるところが見えました。   もう一つ気になる写真も見つかりました。ピアニストの足元にモニタースピーカーが置いてあるのです。オーケストラの音が聴こえにくいのでしょうか。  どの協奏曲も、これまでの数多くの名演に、もう一つぜひ聴いておきたいものが加わったな、という印象を持ちました。かつての「巨匠」のようなとびぬけたスケールの大きさこそないものの、オーケストラと一体となって気持ち良い音楽を作ろうとしている姿勢が強く感じられます。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
しかし、その他の曲となると、ほとんど知られてはいないのではないでしょうか。このアルバムでは、「フルート作品全集」の「第1集」ということで、その「フルーティストの休日」も含めて、彼がフルートのために作った曲が集められています。彼の作品はオペラやバレエ、オーケストラ曲、多くの楽器(オンド・マルトノも!)のための協奏曲や室内楽そして歌曲など数多く残されていますが、フルートが加わったものは9つぐらいしかないようです。今回の「第1集」ではそのうちの5曲が収録されていますので、あと1枚で「全集」は完成するのでしょう。 1926年に生まれたカステレードは、小さいころからピアノ教師のところに通っていましたが、最初は数学を勉強していました。しかし、結局パリ音楽院へと進み、作曲家、ピアニストとなります。そして、1953年には「ローマ大賞」も受賞しました。ただ、この時の受賞規定では独身者でないと資格がなかったのですが、彼はすでに結婚していました。そこで、彼は各方面に掛け合ってその規定を変えてもらって、晴れて受賞できたのだそうです。 2014年に亡くなったばかりのカステレードは、紛れもない「現代作曲家」でしたが、20世紀を席巻した「ドデカフォニー」とか「セリエリズム」とは距離を置いた作曲の姿勢をとっていました。彼は、ちょっと時代遅れではあっても、少し前の「フランス六人組」あたりの音楽に非常にシンパシーを持っていたのです。とは言っても、音楽院ではメシアンのアナリーゼのクラスにも参加していて、「新しい」音楽に対するアプローチも忘れてはいませんでした。 このアルバムの中では最も初期の作品、1962年に作られた先ほどの「フルーティストの休日」は、もろ「六人組」風の瀟洒な曲です。ここで演奏しているのは、南アフリカ生まれで、アメリカを中心に世界中で活躍しているコブス・ドゥ・トワ(とは、本人の発音)という方です。ここでは彼の仲間の3人のフルーティストも参加して、素晴らしいアンサンブルを披露してくれています。1曲目などは、同じフレーズがそれぞれのパートに順番に登場するのですが、それがすべて同じ人が吹いているように聴こえるほど、音色もフレージングもぴったり合っています。 それが、1980年に作られたフルートとピアノのための「空」になると、ガラリと作風が変わります。1曲目の「11月の空」は、フルートがグリッサンドなどで神秘的な雰囲気を漂わせ、全体的に無調感が漂う曲、2曲目の「3月の空」では、ほとんど「ミニマル」とも思えるような音列が繰り返され、それがとても技巧的なパッセージへと変化していくという、とても不思議な作品です。 1987年に作られた「コローの絵画による楽興の時」は、フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピアノという5つの楽器のアンサンブルです。フランスの印象派の少し前の画家ジャン=バティスト・カミーユ・コローの3つの絵画から得られた作曲家のインスピレーションを表現したものなのでしょう。1曲目は有名な「モルトフォンテーヌの想い出」による「モルトフォンテーヌ」ですが、それぞれの楽器がもやもやと動き回り、薄暗い印象を表現しているという、ドビュッシーとは別の意味での「印象派」と言えるような作品です。 そして、1985年にはフルートとギターのための「4月のソナチネ」、1999年にはフルートとハープのための「5月のソナチネ」という、2曲の「ソナチネ」が作られています。ここでは、また流麗さや美しいメロディ、軽快なリズム感などが満載の素直な音楽を聴くことが出来ます。 なかなか油断のできない作曲家、第2集もとても楽しみです。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |
||||||
マウチェリという名前を聞いて、親しみを持てる人はそれほど多くはないはずです。自転車ではありませんよ(それは「ママチャリ」)。そのレパートリーは多岐にわたり、普通のクラシック音楽の他に映画音楽やミュージカルの指揮も行っています。一時はトリノのオペラハウスの音楽監督も務めたオペラのスペシャリストでもあります。 とは言っても、現在はどこかのオーケストラの音楽監督といったようなポストには就いておらず、名前の知られたオーケストラとともに来日したことも、東京のオーケストラの定期演奏会に客演指揮者として登場したこともたぶんないはずですから、日本でも知名度は決して高くはありません。唯一オーケストラを伴って来日したのは、彼が創設時から16年間音楽監督を務めていた「ハリウッド・ボウル管弦楽団」との日本公演でしたし、最近では、東京フィルを指揮した、ティム・バートンの「ナイトメア・ビフォー・クリスマス」のムービー・コンサートという、かなり特殊なものでした。 余談ですが、この「ハリウッド・ボウル管弦楽団」というのは、LAフィルの事務局が、かつてストコフスキーが作った「ハリウッド・ボウル交響楽団」の流れをくむメンバーを集めて、セカンド・オーケストラとして1990年に創設したものです。したがって、マウチェリが「春の祭典」を演奏することを計画した時には、それはLAフィルの音楽監督のサロネンだけに許されたレパートリーだったので、マウチェリは断念するしかなかったことが、本書では悔しそうに語られています。 そんな、彼の尊敬する人や、影響を受けたり、一緒に仕事をしたことのある同業者たちが、ランダムに登場して、彼から見たそれぞれの秘話が語られるのは、かなり興味深く、本書では最も読み応えのある部分でしょう。中でもバーンスタインに関しては、師であるとともに、彼が亡くなるまでの18年間という長期にわたって個人的なアシスタントを務めていたのですから、その包み隠さない逸話の数々は、とても貴重な資料となることでしょう。そもそも、巻頭の「ツカミ」が、1975年のザルツブルク音楽祭で、カラヤンがバーンスタインを自宅でのランチに招いた時の二人の会話、という衝撃的なものですからね。 個人的には、マーラーの「交響曲第4番」の冒頭の部分で、初めてファースト・ヴァイオリンが入ってくるところに少しリタルダンドをかけるという楽譜の指示がある半面、それまでリズムを刻んでいたフルートと鈴にはそのような指示がないことから、これは「クロスフェード」だと解釈しているのが非常に興味深いですね。彼の楽譜に対する厳格な態度は、本書の中では頻繁に表れています。 たとえば、コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲のテーマは彼の映画音楽から借用されているというこれまでの常識は間違っていて、最初にヴァイオリン協奏曲の構想があり、映画音楽を作るときにそれを使ったのだという指摘も新鮮です。 もう一つ、ワーグナーがバイロイトに自分の劇場を建てた時に、初めてオーケストラ・ピットが作られたという指摘にも、目から鱗が落ちました。実際に、それ以前のオペラハウスのように、客席と同じ高さにオーケストラを置いて、指揮者はオーケストラとステージの間でステージを向いて指揮をするということを、マウチェリは実践したそうです(もちろん、オーケストラのメンバーは客席に背を向けます)。 そして圧巻は、ガーシュウィンの「ポーギーとべス」の、初演に基づく録音の経緯です。これは、その現物を聴いていたので、とても納得できます。 多くのエピソードが各所にちりばめられているので、人名による索引があれば、「資料」として読むときには助かったのに、という気がします。 Book Artwork © Hakusuisha Publishing Co., Ltd. |
||||||
今回のアルバムでは、カンタータが2曲と、モテットで最も有名な「Jesu, meine Freude」BWV227が収録されています。これは合唱にユニゾンでオーケストラが合わせるだけですが、カンタータではそれぞれにソロのメンバーが登場しているので、ヴァラエティ豊かな選曲となっています。 最初に演奏されているのは、BWV5の「Wo soll ich fliehen hin」です。弦楽器がかなり大人数の編成です。テノールとバスがそれぞれアリアを歌いますが、その時のオブリガートがなかなかソリスティックで聴きごたえがあります。テノールのアリア(このラファエル・ヘーンという人の伸びやかな声は魅力的)では、ちょっと珍しいヴィオラによる渋い音色で、華やかなオブリガートを聴くことができます。 そして、バスのアリアでのオブリガートは「tromba da tirarsi」という楽器が使われていました。トランペットの仲間なのでしょうが、「tirarsi」はイタリア語の動詞「tirare(伸ばす)」の形容詞形ですから、「伸ばすトランペット」となるのでしょうがそれはいったいどういうものなのか、ちょっとイメージがわきません。そこで、知り合いのトランペット奏者に聴いてみたら、親切に教えてくれました。これは、ルネサンス期に存在した「管が伸び縮みするトランペット」、英語では「スライド・トランペット」と言うのだそうです。それだと、「トロンボーン」と同じことになりますね。実際は、この「スライド・トランペット」から「サックバット」が出来て、それが進化したものが「トロンボーン」だと言いますから、トロンボーンの先祖ということになるのでしょうか。 バッハの時代には、すでにこの楽器はほとんど使われてはいなくなっていたのですが、彼は7曲のカンタータの中で、あえてこの楽器を指定しているのだそうです。おそらく、カンタータの中では一番有名なBWV147「心と口と行いと生活をもって」も、その中の1曲なのだそうですよ。知りませんでした。 ここでは特に「スライド」感を聴きとることはできませんでした。名人なのでしょう。 「Jesu, meine Freude」では、ここの合唱団のスキルの高さを再確認です。先ほどのテノールのヘーンも合唱団のメンバーで、この中でもソロのパートを歌っていましたね。ルッツは、例によってコラールの間にオルガンに即興演奏をさせたりしていますから、とても新鮮な味わいがあります。 最後のカンタータBWV157「Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!」は、お葬式のための曲ということで、編成も弦楽器は各パート1人と小さくなっていますが、弦楽器のパートに「ヴィオラ」ではなく「ヴィオレッタ」とあるのが、気になります。小さめのヴィオラなのでしょうか。特にソロはないので、その違いは分かりません。 そこにフルートとオーボエ・ダモーレが加わります。オーボエ・ダモーレのオブリガートは、そんなしっとり感を演出しています。フルートは、ヴァイオリンとともに後半のいくらか快活さのあるアリアを彩っています。 気になるのが、こんな「トロンボーン」奏者の写真がブックレットに載っていることです。   CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |
||||||
それはもしかしたら、1979年に、クロノス・クァルテットの創設者のデイヴィッド・ハリントンがライリーに弦楽四重奏曲を作ることを勧めたことが、なんらかの影響を与えていたのかもしれません。1980年に、初めての弦楽四重奏曲「Sunrise of the Planetary Dream Collector」を作って以来、彼は彼らのために作品を書き続け、2002年には、このアルバムに収録されている、演奏時間が1時間を超える長大な作品「Sun Rings」が作られることになるのです。 そのそもそものきっかけは、2000年にハリントンにNASAからの電話があったことでした。1977年に始まったNASAの「ボイジャー計画」が25周年を迎えるにあたって、その記念になるような曲を演奏してほしいと頼まれたのです。巨乳ではありません(それは「ボインじゃ〜」)。そこで、ハリントンは作曲家としてライリーを指名し、さらに「宇宙からの音」に関して造詣の深かったアイオワ大学教授、ドナルド・ガーネットとコンタクトをとり、彼をライリーに引き合わせます。 ライリーたちはガーネットのオフィスを訪問し、彼が収集した「宇宙の音」のカセットテープ(!)を聴かせてもらい、それと弦楽四重奏のコラボレーションの構想を固めます。しかし、2001年9月11日の出来事によって、その作業はいったん休止されてしまいます。 ライリーは、その出来事の直後、ラジオで著名な作家、アリス・ウォーカーが語った「One earth, One people, One love」という言葉に心を打たれ、それまで作っていた20分ほどの弦楽四重奏と「宇宙からの音」のための曲に、合唱とさらにこの言葉をタイトルにした曲を加えて規模を拡大、10曲から成る全部で1時間20分の作品「Sun Rings」を完成させました。それは、2002年に初演が行われ、これまでに世界中で幾度となく演奏されてきましたが、全曲が録音されたのは2017年11月のこと、それがこのCDです。ただ、最後の「One earth, One people, One love」だけは、2014年に単独で録音され、CDもリリースされています。 ここで使われている「宇宙の音」というので思い出すのは、冨田勲が1984年に作った「Dawn Chorus」というシンセサイザーのアルバムです。それにとても良く似たサンプリングの音が、このライリーの作品からも聴こえてきます。こちらでは、単なるSEとしてではなく、その音源だけでリズムパターンを作ったりもしています。さらに、1曲目と最後の10曲目には、通信中の宇宙飛行士の声らしいものも挿入されています。 ただ、弦楽四重奏によるメインの音楽は、意外とまとも、というか、特に「宇宙」を意識させられるようなものではなく、ライリーならではの東洋的な音階やグリッサンド満載のフレーズがあふれています。さらに、なにやら有名なラテン音楽をそのまま引用している部分もあったりして、ちょっと和みます。 5曲目と8曲目には6声部、24人編成の混声合唱が加わります。5曲目はそのうちの女声だけでグレゴリオ聖歌のような単旋律をユニゾンで歌う中に、弦楽四重奏がアルペジオで伴奏するというパターンです。8曲目になると、合唱は全員が参加して、まずはポリフォニーを披露した後には、ペルト風の穏やかな部分や明るくリズミカルな部分など、様々な形で盛り上がります。最後にはソプラノのメンバーのソロも出てきます。テキストがどこにも書いてないので歌詞の内容は分かりませんが、最後には「Amen」と歌っているようですね。 10曲目には、「One earth, One people, One love」というフレーズをアリス・ウォーカー自身が語っている音源がバックに流れる中、チェロがとても美しいメロディを奏でます。おそらく、この曲がなければそれまで聴いてきた1時間10分は何の意味も持たなかったことでしょう。 CD Artwork © Nonesuch Records Inc |
||||||
そして、この音楽祭のメイン会場として、パトリック・ブシャンの設計により1993年に竣工したのが、「La Grange au Lac(ラ・グランジュ・オ・ラック)」という名前のホールです。「湖畔の納屋」という名前の通り、このホールはまるで巨大な「農家の納屋」のような造りになっていま。 外観はこんな感じ。素朴な木造建築です。   2018年には、このホールが出来てから四半世紀経ったことを記念して、この音楽祭のためのヨーロッパの主要オーケストラからメンバーを集めて、新しいオーケストラが作られました。その名は「シンフォニア・グランジュ・オ・ラック」、弦楽器の編成は12型で、ちょっと大きめの「室内管弦楽団」、言ってみれば、かつてアバドが作っていた「マーラー室内管弦楽団」のようなエリート集団なのでしょう。ただ、このオーケストラの場合は、平均年齢は35歳と言いますから、「若者」の集団ではないようですね。 木管楽器のトップは、フルートはウィーン国立歌劇場のシルヴィア・カレッドゥ、そして、オーボエのヘレナ・ドヴィエヌーヴ、クラリネットのニコラ・バルデイルー、ファゴットのジュリアン・アルディはフラン放送フィルのそれぞれの首席奏者です。 このCDは、そのお披露目コンサートがエサ=ペッカ・サロネンの指揮で2018年の7月に行われた時の録音です。 メインのベートーヴェンの「交響曲第3番」の前に演奏されたのは、弦楽器だけによるリヒャルト・シュトラウスの「メタモルフォーゼン」です。ベートーヴェンの第2楽章「葬送行進曲」のテーマの断片が時折顔を見せるということで、前曲として使われていたのでしょう。これはもう、このホールの中で、うっとりするようなとても美しい響きを作り上げていました。なにより、一体感を持った呼吸が素晴らしいですね。 そして「エロイカ」です。これは基本的には最近のベートーヴェンの流れに乗った、軽快そのものの演奏です。それが、サロネンの思惑通り、時折ハッとさせられるような表現が織り込まれていますから、ひと時も聴き逃せない時間が続きます。第1楽章は提示部の繰り返しはなし。エンディング近くで、急にトップギアに入って疾走するのには、驚かされました。 しかし、第2楽章だけは、ちょっと意外な「巨匠的」な演奏に変わります。ここでは、極端な弱音での演奏がベースになっていて、とても粘っこいルバートが多用され、時にはほとんどゲネラル・パウゼかと思われるほどに息絶える瞬間があります。葬送のラッパが聴こえる直前がそんなところ、一瞬何が起こったかと思ってしまいました。3,4楽章では、1楽章の躍動感が戻るので、一安心。 特に最初のあたりで、管楽器と弦楽器のアンサンブルが乱れていたのが、やはり新しいオケだという感じです。カレッドゥのフルートは、今年のニューイヤー・コンサートの時のように「華」のないものでした。終楽章の大ソロでも、後半にパッションがなくなっていました。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music France |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |