|
|
|
|
![]()
ダフ屋の黒江。.... 佐久間學
それから1年経って、今度は「マタイ」が録音されました。これは、バージョンについてはそれほど問題のない作品なので、きっちり聴いてみることができました。 それは、思いがけずなかなかのものでしたね。 ここで指揮をしているラルフ・オットーは、このバッハのような時代の音楽はもちろん定評がありますが、現代の音楽に対してもそれと同じほどの情熱を注いでいるようです。同じように、彼が首席指揮者を務めているこのマインツ・バッハ管弦楽団というオーケストラも、ルネサンスから現代までの作品に対応できるような体制が出来ているのだそうです。 合唱団の方は、1950年ごろにディートハルト・ヘルマンによって創られました(この方は、こちらの「マルコ受難曲」の修復版を作った人として記憶にありました)。そして、1986年にラルフ・オットーが指揮者を引き継ぎ、先ほどのオーケストラと密接な関係を持って活動をしています。もちろん、この合唱団も「バッハ」だけではなく、広く現代までのレパートリーを誇っています。 そんな指揮者と演奏家が繰り出す演奏は、ピリオド演奏にありがちな堅苦しさからは無縁のものでした。かなり早めのテンポで進むその音楽は、現代人と共有できる感覚で、とても分かりやすい情熱を放っていたのです。 それは、とてもドラマティックな歌い方で、この曲のドラマ性を見事に描き出していたエヴァンゲリストのゲオルク・ポプルッツによるところも大きかったはずです。もちろん、それはあくまで作品の時代様式にしっかり沿った中でのものですが、その豊かな表現力には圧倒されます。 そして、合唱も、それぞれの場面での歌い分けがとても見事、コラールはあくまで癒し系、群衆の声はあくまでアグレッシブです。歌い方もとても端正で、かなり高レベルです。 さらに、ソリスト陣も、特に女声の4人はやはり的確な様式感を持ったうえで、しっかり熱いものが込められたアリアを提供してくれていました。それに対して男声、特に第1コーラスのテノールと第2コーラスのバスの人が、ちょっと危なっかしいピッチだったのが残念です。 録音は、あのTRITONUSが担当していました。前作の「ヨハネ」も同じスタッフでしたね。さらに、録音会場は、この合唱団とオーケストラが、もう60年間もホームグラウンドとして使っている、マインツのクリストゥス教会です。ここは非常にすぐれた音響なので、南西ドイツ放送(SWR)も、録音スタジオとして使っている場所なのだそうです。たしかに、これは2つのオーケストラと合唱を持つこの曲の広大なパースペクティブを存分に表現している、素晴らしい録音でした。もはや「NAXOSだから音はいい加減」などとは言うことはできなくなってしまっているのでしょう。 バッハは、この「マタイ」では、「ヨハネ」ほどではありませんが改訂を行っています。現在普通に演奏されているのはその最終稿ですが、最近では改訂前の初期稿を使った録音も出てきています。このCDでは、全曲の演奏は最終稿によるものですが、それが終わった後に、56番と57番の初期稿が「おまけ」として演奏されています。これは、バスによるレシタティーヴォとアリア「Komm, süsses Kreuz」ですが、初期稿ではオブリガートがヴィオラ・ダ・ガンバではなくリュートになっていたことが分かります。少し流暢に聴こえますね。「マタイ」でこのような試みを行った録音には、初めてお目にかかりました。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |
||||||
ここでは、1947年の「交響曲第1番」、1961年の「ヴェネツィアの遊び」、1992年の「交響曲第4番」と、作曲年代がかなり異なる作品が集められています。多くの「現代作曲家」と同様、ルトスワフスキもその生涯で大きく作風を変えてきていますから、その変遷を1枚のアルバムで体験できるのはなかなか興味深いものなのではないでしょうか。 「戦後」間もなくの時期に作られた「交響曲第1番」は、まだ「後ろを向いた」作曲技法によるものでした。古典的な4つの楽章で出来たこの交響曲は、第1楽章などはおそらくソナタ形式に近い形を取っているようにも思えます。そして、そのテーマの快活なメロディラインと、いくらか古典からは逸脱している和声感は、まさにちょっと前の潮流「新古典主義」そのものでした。この楽章と最後の楽章は、まるでプロコフィエフの「古典交響曲」を彷彿とさせるものです。 ただ、その間の楽章では、ルトスワフスキの個性のようなものが垣間見られます。アダージョの第2楽章でホルンが奏するメインテーマは、ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」を、ちょっとグロテスクに変換したもののようですし、中間部では全く異なる刺激的な音楽が展開されています。スケルツォ楽章である第3楽章では、ちょっと無調っぽいテイストまで顔を出していますね。 ですから、彼は長くはその作風にとどまっていることはありませんでした。なんでも、1960年にラジオでジョン・ケージの「ピアノ協奏曲」(この頃のケージに「Piano Concerto」というタイトルの作品はありませんから、これは1958年に作られた「Concert for Piano and Orchestra」のことでしょう)を聴いて衝撃を受けたルトスワフスキは、そこでケージの「偶然性」を取り入れた技法に新たに挑むことになるのです。 それは、「Controlled Aleatorism」と呼ばれる技法でした。「Aleatorism」とは、ラテン語で「さいころ」を意味する「alea」に由来していますから、「管理された偶然性」ということなのでしょう。 その技法によって最初に作られた「ヴェネツィアの遊び」が、ここでは演奏されています。タイトルの「ヴェネツィア」というのは、これがヴェネツィアのヴィエンナーレからの委嘱によって作られたという意味しかなく、例えば「ヴェネツィアの謝肉祭」のテーマが登場するようなことはありません。 全部で4つの短いパートから出来ていますが、最初のパートは確かにそんな「偶然性」の産物のような気はします。しかし、それは、「本家」のケージの作品のように、演奏するときに「偶然性」が求められているわけではなく、あらかじめ「偶然」を装って作られたものをきちんと演奏する、というスタイルであるような気がします。作曲家の指揮によるものも含めて何種類かの録音を聴いてみたのですが、確かに微妙に異なるところはありますが、それらは基本的に「同じもの」に聴こえてしまいます。ケージの場合は、同じ演奏家によるものでも録音された時期が違えば全く別物になっていますからね。 3つ目のパートでは、フルートが(吹いているのは小山さん?)延々と難しいソロを吹き続けていますが、それもきちんと記譜されているはずです。 いずれにしても、そこには確かにケージ流の混沌感が漂っていることは確認できるでしょう。 そういうものを経て晩年に作られた「交響曲第4番」では、また「メロディ」が戻ってきますが、作品全体はおのずと「第1番」とは全く異なるテイストを持つことになります。この曲の最後に現れる複数のヴァイオリンのソロのバックで聴こえてくる、まるで電子音の様なサウンド(実はマリンバの超ピアニシモ)からは、SACDサラウンドの精緻な音と相まって、確かな「未来」が感じられます。 SACD Artwork © Ondine Oy |
||||||
ただ、今回のCDの案内にも、「ブルックナー音楽祭のライブ録音」とありますが、これが録音されたのは2018年の8月となっていますから、ちょっと時期が合いませんね。なぜでしょう。実は、その音楽祭の期間より前に開催される「Brucknertage」というもう一つの「ブルックナー音楽祭」があるのですよ。 この「Brucknertage」は正式には「St. Florianer Brucknertage」というもので、先ほどの「Brucknerfest Linz」とは全く別物です。こちらはブルックナーの没後100年に当たる1996年から始まったようですね。名前の通り、ザンクト・フローリアン修道院が中心になって開催されています。 そして、このSACDで演奏している「ザンクト・フローリアン・アルトモンテ管弦楽団」という1996年に創設されたオーケストラも、やはりその修道院と、このBrucknertageに深い関わりがあります。ちなみに、「アルトモンテ」というのは、この修道院の天井のフレスコ画を描いたバロック期の画家の親子の名前なのだそうです。絵の具の代わりにケチャップを使います(それは「デルモンテ」)。 2013年にこのオーケストラの首席客演指揮者に就任した人が、レミ・バローという1977年生まれのフランスの指揮者です 彼は元々ヴァイオリニストを目指していて、パリの高等音楽院を卒業しますが、16歳の時から3年間、パリで静養していたチェリビダッケの個人レッスンを受けることが出来たのだそうです。それは、チェリビダッケの最晩年になりますから、バローはほとんど「最後の弟子」となるわけですね。そこでは、最初は室内楽のレッスンでしたが、後には指揮者になることを勧められ、指揮者としてのレッスンも受けるようになったそうです。 そして、バローは2004年にはウィーンへ移り、ほどなくしてウィーン・フィルのメンバーとなり、さらには指揮者としても活躍することになるのです。 バローは、2013年からこのBrucknertageでブルックナーの交響曲を1曲ずつ演奏し、それを録音してCDをリリースしてきました。翌年からはフォーマットがSACDに変わり、サラウンド録音になっています。そのようにして、2017年までに5曲(3、5、6、8、9番)のリリースを終え、今回は7番がリリースされました。 まずは、その録音に注目です。この礼拝堂の豊かな残響をたっぷり取り入れたそのサウンドは、まさにサラウンド映えするものでした。オーケストラそのものの音像もとても立体感のある広がりを見せていますし、なんと言ってもその残響に包み込まれる感じがたまりません。特に、フォルテシモになった時の金管はその残響成分がまるでリアにバンダが設置されているのではないかと思えるほどに、しっかりとした存在感を持って聴こえてきます。木管だけのアンサンブルでも、増員はしていないのに、とてもくっきりと響き渡っています。 バローの指揮ぶりは、確かにチェリビダッケの影響が感じられる堂々としたテンポがベースになっているものでした。ただ、そんなテンポの割には重苦しさは全く感じられないのは、次のフレーズに入る時のタメがないせいでしょう。時には、まるでカラヤンのようにフライング気味に入ったりしますから、音楽が停滞することは決してありません。 ただ、ライブ録音で修正は一切行っていないようなので、アンサンブルの乱れなどは結構目立ちます。特に第3楽章あたりでは、疲れてきたこともあるのでしょうか、弦と金管がズレまくっていましたね。 それでも、ライブならではの熱気というか、緊張感は最後まで続いています。フィナーレの最後が、とてつもないクレッシェンドでいったいどうなってしまうのかと思っていると、いともあっさりと終わってしまったので、おそらくお客さんは唖然としていたのでしょう、拍手が始まるまでには20秒近くもボーッとしていた様子が、そのまま記録されています。 SACD Artwork © Gramola |
||||||
この作曲家は1970年にイギリスで生まれています。小さい頃は教会の聖歌隊で歌っていたようですね。現在では作曲家であるのと同時に、ジャズ・ピアニストとしても活躍しているそうです。このアルバムのタイトルとなっている2つの作品も、「ジャズ」のイディオムが満載になっています。 まず、2018年に出来たばかりの「Passion Music」です。これは、「セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ」というロンドンの教会からの委嘱で作られました。この名前を聞いて、半世紀以上前にネヴィル・マリナーによって設立され、DECCAからおびただしい数のアルバムをリリースしていた合奏団を思い浮かべる人も多いことでしょうね。今では直接の関係はなくなったようですが、そもそもはこの教会の合奏団だったことから、このような名前が付けられていました。 この教会は、現在でも音楽には深くかかわっていて、合唱団もグレードの異なったいくつかの団体が存在しています。ここで演奏している「セント・マーティン・ヴォイセズ」というのは、その中でも最高のランクの合唱団とされていて、プロフェッショナルな歌手が集まって作られています。 この曲は「受難曲」と訳されるべき作品なのでしょうが、その中身はいわゆる「受難曲」とはかなり異なっています。テキストも、もちろん聖書の中の言葉は使われていますが、それだけではなくもっと幅広いジャンルからのものも使われています。 そして、音楽も伝統的な「受難曲」とは全く異なっています。なんと言っても、ここで主役を務めている女声のソロ・ヴォーカルは、もろ「ゴスペル・シンガー」なのですからね。そして、伴奏はジャズのピアノ・トリオにホーンが3本加わったというアンサンブルです。 録音のやり方もクラシックとはだいぶ違ったもので、あらかじめアンサンブルとゴスペル・シンガーのパートは録音スタジオで録音してあって、合唱はそれをヘッドフォンで聴きながら教会のアコースティックスの中で録音する、というオーバーダビングが行われています。 そうなると、ここでのコーラスはもはや主役ではなく、単なる「バックコーラス」のような役目しか果たしていないように思われてしまいます。曲の作り方も、そんなに手の込んだものではなく、歌い方も一本調子、なんか、合唱がかわいそうになってくるような曲です。 後半には、有名になった「私のお墓の前で泣かないでください」のテキストや、黒人霊歌の「Were You There When They Crucified My Lord?」をそのまま使った曲なども入っています。まあ、ジャンルの壁を越えた作品といえば聞こえはいいのでしょうが、なんか、どっちつかずの仕上がりという感は免れません。 それに比べると、ラテン語のテキストをそのまま使った「Jazz Missa Brevis」(ここには、ソロ・シンガーは登場しません)の方が、数段まとまりのある作品です。それこそ、ボブ・チルコットやジョン・ラッターの作品のような、上手にジャズとコーラスを合体させた成果が感じられます。 ただ、そのような、ジャズマンとの共同で演奏されている時の合唱は、なんとも主体性を欠いた表現に終始しているのが、とても気になりました。 というのも、この2曲の大作のほかに、トッドが作ったあまりジャズっぽくない、ア・カペラで歌われる小さな曲が4曲ここには収められているのですが、そこで聴かれるこの合唱団が女声はノンビブラートの伸びやかな声ですし、男声は多少ハスキー気味の、それでいて完璧なハーモニー感を持った人たちばかりですから、とてもなめらかでピュアなサウンドが楽しめるのですよ。それを聴くと、2つの大曲では、なんかとてももったいないことをやっていると思えて仕方がありません。 CD Artwork © Signum Records |
||||||
そんな中では、バッハの「ヨハネ受難曲」などは1981年11月15日まで全曲が自国のメンバーだけで演奏される事はありませんでした。その時の音源が、おそらく初めてCD化されました。 そんなものが今頃になって出てきたのは、2015年がソ連の合唱音楽界に多大な貢献を果たしてきた、アレクサンドル・スヴェシニコフの生誕125周年に当たっていたからなのだそうです。 スヴェシニコフというのは、オールド・ファンには懐かしい名前でしょうが、自身が創設した「国立アカデミー合唱団」を率いて多くの録音を国営レーベルMELODIYA残していましたね。日本ではビクターが販売していたので、ラフマニノフの「晩祷」を本字の漢字のフォントでデザインしたジャケットで出していました。  実は、この「ヨハネ」が演奏された年はスヴェシニコフが亡くなった翌年です。ここでは、そのスヴェシニコフが育て上げてきた合唱界の逸材が、この演奏を実現するための中心的な役割を果たしていたのです。 まず、合唱は「モスクワ国立合唱学校少年合唱団」とでも表記するのでしょうか(今回のCDの団体名は、キリル語で表記されたものの英訳しかわからないので、かなりいい加減になってしまいます)。この合唱のための学校こそが、スヴェシニコフが作った教育機関でした。そして、その合唱団の指揮者と芸術監督がスヴェシニコフの弟子であるレフ・コントロヴィチとヴィクトル・ポポフなのです。 さらに、このオーケストラ(当時は「レニングラード古楽と現代音楽室内管弦楽団」という意味不明の名前でしたが、後に「サンクト・ペテルブルク国立交響楽団」と改名)の常任指揮者のエドゥアルド・セーロフも、最初の先生がスヴェシニコフでした。彼は後にムラヴィンスキーにも師事するのですが、彼の指揮にはスヴェシニコフの影響が強く残っていたそうです。 このオーケストラの名前には「古楽」などという言葉が見られますが、もちろんソ連時代ですから「古楽器」を使うことなどあり得ません。普通にモダン楽器が使われていますし、30番のアルトのアリア「Es ist vollbracht」で楽譜に指示のあるヴィオラ・ダ・ガンバのオブリガートはモダン・チェロに替わっています。 ソリストも、5人しかいません。テノールはエヴァンゲリストとアリアを掛け持ち、さらにレシタティーヴォで登場する他の役までも歌っています。バスは2人いて、イエスがアリアと掛け持ち、もう一人はピラト役だけを歌っています。それに、アリア用のソプラノと、アルトのアリアを歌うメゾソプラノが一人ずつです。いずれも、とても力の入ったたくましい歌を聴かせてくれています。 しかし、最も充実しているのは、合唱のパートでしょう。名前の通り、女声パートは少年が歌っていますし、大人のパートもちょっと弱々しいのですが、それはもう徹底的に訓練されているという感じがありありとわかる、とても高度なアンサンブルを聴かせてくれています。なんと言ってもコラールの響きがとても充実しているのが感動的です。時には低音を補強してそれこそ「晩祷」のようなサウンドを出しているのですからね。 それに比べるとオーケストラはちょっとお粗末でしょうか。レシタティーヴォの低音などは、オルガンが数字付低音をそのまま伸ばしているだけで、何の即興性もありません。このあたりが、1980年代のソ連なのでしょう。 CD Artwork © AO"FIRMA MELODIYA" |
||||||
まずは、このジャケットに注目。これ以前の3枚のジャケットでは、いずれもまりや自身の写真がフィーチャーされていましたが、ここにはそのような「アー写」はなく、「M」という文字をモティーフにした抽象的なデザインになっています。 リアルタイムでこのアルバムに接したことはありませんし、その後のベストアルバムでの案内では本当に小さな画像しか見ることは出来なかったので、ここに使われている画像はいったい何なのかという疑問がずっとありました。今回、LPサイズではありませんが一応写真の詳細が分かるジャケットを見てみると、どうやらこれは「編み物」だったことが分かりました。つまり、こういうニットのセーターかなんかがあったので、それを撮ったものなのでしょう。 と思ったら、ライナーにはこれは「橋本治さんの作品」とあるではありませんか。つい先日お亡くなりになった、1977年に「桃尻娘」でデビューした小説家ですね。というより、その前のこんなイラストで、一躍注目を集めていた方でした。 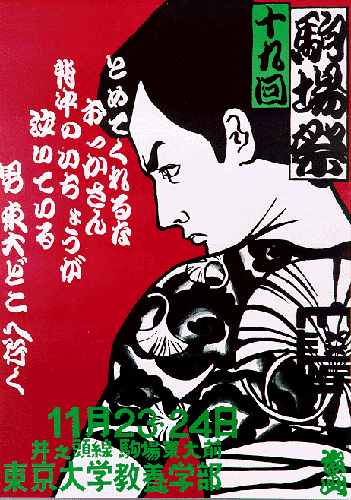 これ以降のアルバムでは、ベスト盤やライブ盤を除いては、全てまたまりやのアー写がジャケットを飾ることになりますから、これはアートワークとしては非常にユニークなものとなっています。一応「裏」にはまりやの写真もありますが、これはまるで別人のようですね。  1曲目の「Sweetest Music」などは、シングル・カットもされていてお馴染みの曲ですが、曲もあちらのヒット・メーカーが書いたもの、それを一流のスタジオ・ミュージシャンをバックに歌い上げるまりやは、まさに「洋楽」のアーティストそのものです。ホーン・アレンジも素敵、リズムもそれぞれのプレーヤーの個性までもが感じられるグルーヴに満ちています。 山下達郎が作り、自身でもカバーしている「Morning Glory」も、やはりカッコいいLAのサウンドがとても魅力的です。コーラスだけは東京で入れていますが、何の違和感もなく溶け込んでいますね。5曲あるこのパートには、すべてそんな「洋楽」感があふれていて、感無量です。日本のアーティストもようやくここまで来たのか、と。 それがB面になったとたん、いきなりアイドル然とした「Jポップ」感に変わります。冒頭の「二人のバカンス」もやはりシングルでしたが、林哲司の曲とアレンジは、洗練された緻密さはあるもののなにかチマチマしていて、A面では確かに感じられたおおらかさは全くなくなっていました。 この面の残りの3曲は、全てまりや自身の曲と歌詞による作品です。そこからは、明らかにアイドルとは一線を画した「プロ」のソングライターとしての意気込みはしっかり感じることはできますが、それはまだ手探りの段階、という気もします。最後の「Farewell Call」などは、明らかに強い志は感じられるものの、スキルが伴っていないな、というもどかしさがひしひしと伝わってきます。というより、この大袈裟な歌い上げは、後の「人生の扉」という愚作にもつながるものだったのではないでしょうか。 ボーナストラックでは、リリースの翌年の8月に行われたコンサートのライブ録音が収められています。そこでは「Sweetest Music」も演奏されていますが、バックのホーンがきっちりアルバムのコピーを決めているのがすごいですね。 CD Artwork © Sony Music Labels Inc. |
||||||
 今回使われた楽譜は、ここで演奏しているピアニスト、ジャン=フランソワ・エッセールが30年ほど前から手掛けていたものだそうです。複雑に入り組んだベルリオーズのスコアをピアノで再現するには、やはり一人では限界があるでしょうし、二人で分担するにしても連弾では音域も限られてしまいますから、2台ピアノというスペックには期待できます。 実際に聴いてみると、まず「1台」の楽器ではあっても、アクションの位置は左右に離れていますから、定位はしっかりその位置になっていて、それぞれの奏者の分担ははっきり聴き分けることができます。そうなると、オーケストラでは隠れてしまってほとんど聴こえないようなパートのフレーズもしっかり聴こえてくるので、色々新しい発見もありました。ただ、やはりオーケストラとしてのサウンドはすっかり染みついているので、別にそのようなものが聴こえても、それがこの作品に対する価値を高めるものではないような気もします。 逆に、オーケストラでは弦楽器が弓の木の部分で演奏(コル・レーニョ)したり、駒のそばで演奏(スル・ポンティチェロ)するような指定があって、そこではとても効果的なサウンドが実現できることになっているのですが、残念なことにピアノではそのような効果を出すことは絶対にできません。本当にやりたければ、もう1台「プリペア」された楽器が必要になってくるでしょうね。 ただ、第5楽章でその「コル・レーニョ」をバックに管楽器がこんな難しいことをやっているような場面では、ピアノはその機能性を発揮できるはずです。  実は、リスト版でもここはトリルではなく前打音でごまかされていましたね。  もう一つ、今回のCDで気になったのが、同じ第5楽章の「鐘」の音です。ここではベルリオーズはしっかりCとGの音を指定していて、今ではオーケストラで演奏するときにはそのピッチの鐘を使うことが当たり前になっています。さらに、作曲家は「不正確なピッチの鐘しかない時は、ピアノで演奏した方がよい」とまで言っています。それを、ここでは半音を重ねて、わざわざ「不正確」な音で演奏しているのですね。これは全く理解不能です。  CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |
||||||
このグループのリーダーのレイ・コニフはもともとはジャズのトロンボーン奏者でしたが、編曲の腕を見込まれて多くのバンドで編曲に携わっていました。それが、1955年にコロムビア・レコード(CBS)でA&Rとして活躍していたミッチ・ミラー(自身も男声合唱団を率いてアーティストとしても有名)の目に留まり、その年にシングル・レコードをリリースすることになります。それは、ビッグバンドにコーラスが加わるという、それまでにはなかった画期的なスタイルで、スタンダード・ナンバーを演奏するというものでした。コーラスは歌詞は歌わず、楽器の一部としてホーン・セクションとユニゾンでスキャットを歌っていたのです。 これは大ヒット、翌年にはアルバムもリリースされ、結局レイ・コニフ自身が亡くなる2002年までに100枚以上のアルバムが制作されることになるのです。 そんなにたくさんのアルバムを作れたのは、演奏されていたのがオリジナルではなくほぼすべてがカバー曲だったためです。それは、初期にはスタンダード・ナンバーでしたが、やがて最新のヒット曲を直ちにカバーするようになり、それらはイージー・リスニングとして多くの人に支持されました。 その編曲は、あくまでもさわやかでハッピーなものでした。リズムもきっちり8ビートで統一され、コーラスはあくまでそのタイトなリズムの上で、適度にジャジーなシンコペーションやフェイクを加えたメロディを歌っています。それはバックのオケのホーンと見事にシンクロして、軽快なグルーヴを醸し出しています。 録音も、それこそ「ミッチ・ミラー合唱団」譲りのたっぷりエコーがかかったゴージャスな仕上がりです。ですから、1970年代にはこのレーベルの戦略だった「4チャンネル」の波に乗って、多くのアルバムがノーマルLPとクワドラフォニックLPの2種類のフォーマットでリリースされていたのも当然です。エンコードはもちろん「SQ」でしょうね。 ネットで検索したら、当時のCBSソニーがSQ4チャンネルのデモ用に作ったコンピレーションアルバムが見つかりました。その中に、このレイ・コニフのトラックもあったので、おそらく日本でも実際に4チャンネルのアルバムがリリースされていたのでしょう。 昨年から今年にかけて、DUTTON/VOCALIONからそのレイ・コニフの4チャンネルのアルバムが、マルチチャンネルSACDで何枚かリリースされました。アルバム自体はすでに多くのものがCD化されていて、それらは2枚のLPを1枚のCDに収録した「2 on 1」でした。ほとんどのアルバムは11曲ぐらい入って30分程度の収録時間ですから、CDなら余裕で2枚分は入ってしまいますからね。 今回も、カップリングは変わっていましたが、やはり「2 on 1」で、1971年に録音された「Love Story」と、1974年に録音された「Happy Sound of Ray Conniff」という2枚のアルバムが全て入っています。 いずれも、すでにCDで持っていたものですから簡単に比較できますが、その違いは歴然たるものでした。もちろん、コーラスはリアに定位していたり、時折フロントにも一部が残って掛け合いをするなどというサラウンドならではの魅力があるのは当たり前ですが、音自体がCDとは比べ物にならないほどクリアに変わっていたのです。 最初に彼らを聴いたのは、LPによってでした。その、特に外周付近のトラックは、とてもヌケが良くてスピーカーのセッティングのテストなどによく使っていたものでした。ところが、それがCDになった時には、なんとものっぺりとした音になってしまっていたので、がっかりした記憶があります。それが、今回のSACDではまさに最初のLPの音に戻っていたのですよ。 LP並のクオリティとサラウンド、もうすっかりCDが色あせて見えるようになってしまったので、残りの3枚のSACDも全部買ってしまいました。これは、かつてなかったほどの幸せな出来事です。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |
||||||
もうこんな感じで、マンゼは漫然とコンサートをこなしているうちに、いつの間にかツィクルスが完成している、という幸福な環境にあるのですね。今のところ、モーツァルトに関してはこれからツィクルスに発展していくかは不明です。このアルバムの評判次第、といった感じでしょうか。 今でこそ、フツーのシンフォニー・オーケストラのシェフとして、さまざまな時代のオーケストラ作品を指揮しているマンゼですが、かつてはヴァイオリニストとして、ピリオド楽器のフィールドでとても異色なアプローチを試みていた演奏家でした。モーツァルトでもそのスタイルは変わらず、ソナタや協奏曲ではとてもアグレッシブな演奏を聴かせていたはずです。 ですから、彼が指揮者となった時には、どうしてもそのような「特色のある」演奏を期待したくなってしまいます。しかし、実際にそのような録音を聴いてみると、それはあまりにも「フツー」のものだったので、ちょっと失望してしまいました。 ただ、メンデルスゾーンを聴き続けていくうちに、どうやらその「フツー」さが、今のマンゼのスタンスなのではないか、と思うようになってきました。もしかしたら、彼はアーノンクールやノリントンの轍は踏まないようにしてきたのではないか。と。 今回のモーツァルトでは、そのあたりがとてもうまくオーケストラともかみ合っているような印象を受けます。ここには、モダン・オーケストラにピリオド楽器の演奏法を導入した時の不自然さが、全く感じられないのですね。 確かに、弦楽器はほとんどビブラートなしで演奏していますが、そこからはピリオド楽器にありがちなギスギスとしたところが全く感じられません。特に、どちらの曲でも第2楽章の弦楽器のサウンドは、ビブラートがかかっていないにもかかわらず、とても芳醇なものになっています。 そこに加わるのが、普通の奏法でモダン楽器を演奏している木管楽器のプレーヤーたちです。彼らは、きっちりしたハーモニーで弦楽器に色を施すと同時に、ソロの受け渡しでも見事な均質性を披露してくれていました。特に心地よいのがフルートのピッチです。ピリオド楽器のオーケストラでいつも不満に感じてしまうのがこのパート、確かに、そこで的確な演奏を聴かせてくれる名手がいないわけではありませんが、モダン・オーケストラの心地よさに慣れた耳には、わざわざ無理をしてそんなものを聴くこともないようにも思えてしまいます。 そんなことは、ここでは全く感じることはありません。何のストレスもなく、ほどよいストイックさを伴ったモーツァルトを味わうことができるのです。 41番になると、そのサウンドがさらに明るいものへと変わります。それは、ティンパニがとても目立つようにフィーチャーされているためです。これもおそらく、バロック仕様のチマチマした楽器ではなく(改めてホグウッドとAAMの録音を聴いてみましたが、そこではティンパニの音がほとんど聴こえませんでした)、それこそブルックナーあたりで使われるような大きな楽器なのではないか、と思えるほど、その音は迫力満点に響きます。 まるで、ファッションが一回りして、昔に戻ったようなしっとりとしたモーツァルト、しかしそこにはマンゼならではの隠し味もしっかり込められていました。例えばこの曲のフィナーレのコーダが始まる前のブリッジの部分などでは、今まで誰からも聴いたことのないような不思議な音楽が出現していました。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
今回のリマスターにあたっては、アメリカ盤ではなく日本盤のタイトルと(アメリカ盤は「Bolero」)とジャケットが使われていました。それが、この磯野宏夫によるイラストです。お気づきのように、これは一種の「だまし絵」になっていますね。これはもちろん、「ダフニスとクロエ」(第2組曲)の世界を再現したものなのでしょう。遠くには中間部の「無言劇」で大ソロを吹くフルーティストまでリアルに描かれていますね。  冨田は、この「ダフニスとクロエ」を作るにあたっては、ラヴェルが書いた楽譜をほぼ忠実に再現しているようでした。というか、もう少し時代が進んで、MIDIなどを使って自由にオーケストラの個々の楽器が再現できるようになると、シークエンス・ソフトさえあれば、スコアをそのまま入力すれば簡単にラヴェルのサウンドが再現できるようになってしまいます。冨田の時代でも、かろうじてローランドの「MC-8」というシークエンサーが出来ていましたから、それらの細かい音符を入力するのはそれほど面倒なことではなかったはずです。 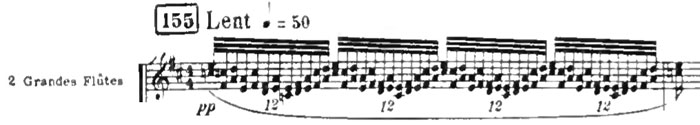 次の「ボレロ」では、冨田は最初から楽譜に忠実に「演奏」を行うことを諦めてしまっているようです。原曲の最大の魅力は、全く同じメロディを楽器やオーケストレーションを変えてただひたすら繰り返す中から、サウンドの変化が味わえることなのではないでしょうか。それを実現させるために、ラヴェルは細かく楽器の組み合わせを変えて、巧みに音をブレンドしているのです。 ところが、冨田は最初のうちはそのプランに従って、音源を細かく変化させているようですが、それだけではなかなか「変化」がつけられないとなると、そこに新たなメロディを加えるなど、別の小技を挟んでくるようになります。ただ、そこまでしても、結局もうアイディアが底をついてしまって、原曲よりもかなり早い段階で曲を終わらせてしまっています。オリジナルのオーケストレーションにシンセが「負けて」しまったんですね。ですから、エンディングも原曲のようなスリリングな展開は起こらず、だらだらとフェイド・アウトで終わらせてしまっています。 ただ、そんな退屈な編曲も、サラウンドで音たちが空間を動き回っているのを聴いていると、俄然魅力的になってきます。このミキシングを行ったのは冨田自身のようです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |