|
|
|
|
![]()
フリチン・ウーマン。.... 佐久間學
ただ、ペダルはセコンドの人が踏むことになっているようですね。もちろん、右のダンパーペダルのことで、プリモの方が足が近いので踏みやすそうですが、そういうことではなく、音楽的にセコンドが担当している和声のパートで、和音が切り替わるタイミングで踏めるように、ということなのだそうです。 ただ、そういう大まかのテリトリーはありますが、楽譜の上では時折それぞれが担当する音符が同じ場所に出てくる時があったりします。そんな時には、お互いの指が鍵盤の上で絡み合ったりするのでしょうね。  こんな感じ。そういえば、今回のセコンド担当の高橋悠治は、かつてコンサートでのトークで「作曲家は自分のかわいい生徒(もちろん女性)と演奏中にイチャイチャしたいから、そのために連弾曲を作ったのだ」というような意味のことを語っていましたね。 ですから、先ほどの2台ピアノ版のCDの時にもご紹介したように、マイケル・ティルソン・トーマスがこのバージョンの世界初演を行った直後の1968年に、彼と共演していた悠治が同じ曲をそれから半世紀後に録音した時には、迷わず「連弾版」を選んだのでしょう。相方は女性ですし。 というのは冗談ですが(こういうのを真に受けて怒りのコメントを送ってくる人がいたりします)そもそも作曲家がドビュッシーと一緒に世界で最初にこの曲を音にした時には「連弾」でしたから、この方がオーセンティックだと考えただけのことなのでしょう。 その、ドビュッシーのスペシャリストとして活躍している青柳いずみこが、悠治から連弾の誘いを受けた時には、自分はドビュッシーがこれを弾いたときのパートであるセコンドをやるのだと思っていました。しかし、悠治は彼女にプリモをやるように勧めたのだそうです。これも、別に悠治が歳をとって(もう80歳!)プリモの早いパッセージを弾けなくなったためではなく、昔からセコンド、あるいは第2ピアノを弾きたがっていたようですね。実際にコンサートでピーター・ゼルキンや佐藤允彦と共演していた時には、どちらも悠治は第2ピアノを弾いていましたから。ただ、普通2台ピアノというと奏者が向い合せになるように配置するものですが、その時には同じ方向に並べて、2人がすぐそばにいるという配置になっていました。これだと、連弾と同じように互いの呼吸を間近に感じることができるのでしょう。 今回の連弾でも、そんな悠治が目指しているアンサンブルを感じることが出来ます。というか、ソロの時もそうですが、彼は常に何か周りを煙に巻くようなオーラを漂わせていますから、そんな尋常ではない雰囲気が、ここからもぷんぷんと伝わってくるのですね。つまり、彼のパートは確かにアンサンブルは作っているのに、そこから彼ならではの個性的な弾き方がはっきり聴こえてくるのですよ。一度それに気が付いてしまうと、一瞬、そこで彼はいったい何をやりたかったのかを考えたくなってしまいます。そんなことが次々に押し寄せてくるスリリングな体験が味わえる、稀有なSACDです。 SACD Artwork © R-Resonance Inc. |
||||||
ここで注意しなければいけないのは、それらの「稿」は必ずしも個別の楽譜としては存在していないこともある、という点です。つまり、「第1稿」を五線紙に書き上げた後にそれを改訂しようとした時、新たにまっさらの五線紙に最初から書きはじめるのではなく、それまであった例えば「第1稿」の五線紙の上に直接書き込みをしてそれを「第2稿」とする、ということが良く行われているからです。 バッハもそんな作曲家でしたから、「ヨハネ」を何度か演奏する際には、パート譜に直接その変更点を記入して演奏に使っていました。そんなごちゃごちゃの楽譜を、後年の研究者が分析して、それぞれの書き込みがどの年の演奏の時に使われたものであるかを特定して、そこからスコアを再構築し、それぞれに「第〇稿」(あるいは「〇年稿」)という名前を付けたのです。そのような「楽譜」が、「第1稿(1724年稿)」、「第2稿(1725年稿)」、「第3稿(1732年稿/年号には諸説あり)」、「第4稿(1749年稿)」と、全部で4種類存在していることが知られています。 そして、「第3稿」と「第4稿」の間の1739年には、もう1回予定されていた演奏のために、バッハ自身が新たにそれまでのものとは細部がかなり異なっているスコアを、新たに書き起こし始めます。しかし、その演奏がキャンセルされてしまったので、それは途中まで書いたところで終わってしまいます。しかし、10年後の1749年にその先を第1稿のスコアをそのまま弟子に写譜させて、全曲のスコアを完成させます。これは「未完のスコア」と呼ばれていますが、最近では非公式ですが「第3.5稿(1739/1749年稿)」という具体的な年号が入った呼び方も提案されているようです。現物はこちらで見ることが出来ます。バッハ直筆の20ページまでと、その先では筆跡が全く違っているのがよく分かります。 この「第3.5稿」は、曲がりなりにもバッハの自筆の部分が残っているので、実際にバッハによって演奏されてはいないにもかかわらず、これが新旧のバッハ全集のベースになっていて、演奏家は長い間これから派生した楽譜だけを使い続けてきたのでした。 しかし、そんなわけで最近では実際に4回演奏されたとされているそれぞれの機会に作られ、実際に演奏されていた楽譜のことはかなり詳しいところまで分かっていて、修復不可能な「第3稿」以外は、実際に全曲が演奏され、録音もされるようになっています(こちらを参照)。 その最後のもの、バッハが亡くなる前の年に演奏された「第4稿(1749年稿)」では、これまでに4種類ほどのCDがリリースされています。その中には、鈴木雅明指揮のバッハ・コレギウム・ジャパンの演奏などもありましたね。そこに、5枚目の録音としてこの2017年に録音されたばかりのNAXOS盤が加わることになりました。  ところが、このCDから聴こえてきたのは、紛れもない新バッハ全集、つまり「第3.5稿」なのです。もうすでに何十種類もリリースされている、ごく普通のバージョンですね。つまり、このCDではジャケットとブックレットでとんでもない間違いをさらしているということになりますね。 もちろん「第4稿」と「第3.5稿」とは全くの別物です。そもそも、第9、19、20曲では、歌詞まで異なっていますからね。それは、1749年に演奏された時に、当局からの横やりが入って歌詞を変更させられたためです。「第3.5稿」ではそのようなことはあり得ませんからね。 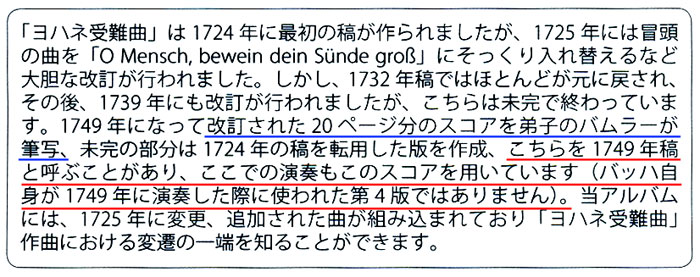 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd. |
||||||
 ただ、最近は、この出版社が発行している雑誌が、目に見えてページ数が減っているように感じられます。もしかしたら、それはこの出版社自体の体力が次第に弱ってきているせいなのかもしれませんね。 ですから、このムックにしても、かつてのような勢いが失われて、以前雑誌に掲載されていたものを、特定のテーマに沿って集めて一つの本にするというような、まあCDで言えば「コンピレーション」のような手法によって作られるものが非常に多くなっているな、という印象を強く受けるのですね。これであれば、一度発表されたものをそのまま使えますから、経費も手間もかかりませんからね。 ただ、そのようなネガティブな側面だけではなく、雑誌に長期で連載されたものなどをまとめたものでは、通常はその雑誌に目を通すことが無いような人に対してはとても親切なものが出来上がるかもしれません。 今回のムックが、まさにそのようなものです。ここでは佐伯茂樹さんが「音楽の友」という雑誌に2年半にわたって連載していたコラムを、まとめて読むことが出来ます。 正直、この「音楽の友」も、同じ出版社から刊行されている「レコード芸術」(これが、先ほどのページ数がみるみる少なくなっている雑誌)も、毎月購入するような習慣はとうの昔になくなっていました。こういう本はあまりに内容が薄いので、とてもお金を出して読むだけの価値が見出せないのですね。 とは言っても、ごくたまに本屋さんで流し読みをしていると、中にはちょっと目を引くような読み物に出会えることもあります。佐伯さんの連載が、そんなものでした。彼の著作はそのとことんマニアックな楽器の話で非常に魅力のあるものですから愛読していますが、それは主に管楽器に対する知識が膨大だという点での魅力でした。ですから、そのような興味とはちょっと離れたところにある「音楽の友」での連載というのがちょっとミスマッチだったのですが、たまたま見かけた号で「キーボード・グロッケンシュピール」のことを語られていたのですよ。この楽器に関しては、かつてかなりのところまで調べたことがあったのですが、資料がなくて一部は分からないところが残ってしまっていました。佐伯さんのその記事は、そんな疑問点に見事に答えてくれていたのです。それは、彼に対するイメージが、単なる「管楽器オタク」から、「すべての楽器のオタク」に変わった瞬間でした。 それっきり、雑誌連載を読む機会はありませんでしたが、それが全て1冊にまとまってムックになったというのですから、これは買うしかないじゃないですか。そこには「楽器博士 佐伯茂樹」という、まさに彼にぴったりの肩書まで付いていましたからね。 しかし、確かに、「マリンバ」と「シロフォン」との違いについての記述では、あの「キーボード・グロッケンシュピール」と同等のサプライズを与えてもらえましたが、それ以外の大部分はこれまで別のところで読んできたことの焼き直しだったのには、軽い失望感を覚えてしまいました。 それと、連載にはなかった、まさに「書き下ろし」のフルートとバセットホルンの話が巻頭に追加されているのは良いのですが、そこに使われている歴史的フルートの写真のあまりの解像度の低さには、もろに、この本を作るスタッフの熱意のなさを感じてしまいました。 Book Artwork © Ongaku No Tomo Sha Corp. |
||||||
ということで、今年はバーンスタインがらみのCDのリリースやコンサートが相次ぐことになるのでしょうね。とりあえず、今週末にはあのNHK交響楽団までが「ウェストサイド・ストーリー」を全曲上演してしまうのだそうですからね。 今回のSACDは録音されたのはおととしですし、リリースも去年だったのですが、やはり同じようにこの「100周年」に合わせて制作されたものなのでしょう。ここでも、その1957年に作られた「ウェストサイド・ストーリー」から、その中からのダンスナンバーを集めた「シンフォニック・ダンス」が演奏されています。 とは言っても、アルバムのメインタイトルは「波止場」になっています。これは、マーロン・ブランドが主演を務めた1954年の映画ですね。バーンスタインは、この映画のために彼にとっては唯一の「映画音楽」を作っていたのです。このジャケットは、その「波止場」のワンシーンを、ここでロイヤル・リヴァプール・フィルを指揮しているクリスティアン・リンドベリがマーロン・ブランドになりきって撮ったものなのでしょう。リンドベリが着ている革ジャンはブランド品?  その他にも、ここではバーンスタインが劇場作品のために作った曲を元にした曲が演奏されています。まずは1944年に作られた、彼にとっては最初のメジャーな作品である「ファンシー・フリー」です。これは、振付師のジェローム・ロビンスが脚本も書いたバレエのための音楽です。そこから作られた「3つのダンス・ヴァリエーション」が演奏されています。 これは、3人の水夫が寄港地のニューヨークで過ごした1日の物語ですが、このプロットはのちに「オン・ザ・タウン」というミュージカルとして、1946年に結実します。その時の音楽も、もちろんバーンスタインが作っています。その中のナンバーから作られたのが、「3つのダンス・エピソード」です。 さらに、そのミュージカルは1949年にジーン・ケリーやフランク・シナトラなどがキャスティングされて映画化されます(邦題は「踊る大紐育」)が、その際には、音楽は他の人の作品も加わって作られていました。 そして、このアルバムのオープニングは、1957年に作られたミュージカル「キャンディード」の序曲です。このミュージカルの中のナンバーをちりばめて構成されていて、かなり高度な作られ方をしているにもかかわらず、とてもキャッチーに受け止められる曲に仕上がっているために、もはや完全にコンサートの定番となった感がありますね。それに加えて、さるテレビ番組で長年テーマ音楽として使われていたというヘビー・ローテーションがありますから、「名曲」としての地位は確かなものがあります。 それらのオーケストラ曲が5曲、最新のサラウンド録音で聴いてみると、この序曲と、やはり聴きなれた「ウェストサイド・ストーリー」が、パーカッションの配置なども手に取るようにわかって聴きごたえがあります。「プロローグ」で警官の警笛は後ろから聴こえてきますしね。 しかし、それ以外の曲は、単に聴きなれていないというだけではない、なにか頭でっかちな技巧だけに頼って作られたもののように聴こえてなりません。もしかしたら、そちらの方がバーンスタインの本来の姿だったのではないでしょうか。「ウェストサイド・ストーリー」は、クレジット上は歌詞での共作となっているスティーヴン・ソンドハイムの影響が色濃く出た結果、これほどの「名作」になったのでは、という思いは、このアルバムを聴き通したことによってさらに強まります。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
その間、ソプラノのイリア、アルトのユリア、テナーのペーター、ベースのマティアス、というメンバーはずっと変わっていなかったようです。というか、一時期テナーが別の人になっていたことがあったようですが、また元の人が復帰したのでしょうか。それと、ソプラノのイリアのラスト・ネームが前のアルバムとは変わっているので、ご結婚でもされたのでしょうかね(そんなことはどうでもいりあ)。 その4人の織り成すハーモニーは、まさに極上でした。今回も前半にはクラシックの「合唱作品」が並んでいますが、彼らはそれをとてものびやかに歌っています。もちろん、ソプラノのイリアの、さりげない歌い方の中に確かな情感を秘めるといういつものスタイルが徹底されていますから、それぞれの曲の持つメッセージはすんなりと伝わってきます。 特に彼女のピアニシモでの緊張感には、思わずハッとさせられるような美しさが感じられて、絶句すらしかねません。 エリック・ウィテカーの「This Marriage」などという多くの合唱団が取り上げている最近の「ヒット曲」なども歌っていますが、この曲の持つ細やかな情感は、4人という最小限の編成だからこそ、そのピュアな魅力が最大限に楽しめます。 その後に、なんとボビー・マクファーレンが作ったシリアスな曲「詩篇23」が取り上げられていました。もちろん歌詞は英語ですが、時折語りかけるような部分に驚かされます。 かと思うと、モーリス・デュリュフレの最後の作品「Notre Père」を、「Vater unser」とドイツ語のタイトルに直し、もちろんドイツ語で歌っていたりもします。不思議なもので、歌詞が変わるだけで音楽そのものまでドイツ的な雰囲気が漂ってきます。この曲の新たな側面ですね。 ソプラノが主導権を取って、他のメンバーはしっかりバッキングに務める、というのが、基本的なやり方なのでしょうから、例えば、イェイロの「Northan Lights」などでアルトのユリアがソロを取ったりすると、ちょっと物足りないと感じてしまうこともあります。 そして、後半には例によってビリー・ジョエルやジェームス・テイラーのような「ポップス」を編曲したものも演奏されています。こちらも、あくまで端正に歌い上げられているのは、いつもと変わらない姿勢の表れでしょう。 ただ、今回の最後の2つのトラックだけは、ちょっと趣向が変わっていました。メンバーに新たにビートボックス(ヴォイスパーカッション)のメンバーのゲオルク・ハーゼルブロックを加えて、いまどきの「ア・カペラ」を披露してくれています。しかも、両方ともメンバーが書いた曲というのも新機軸です。いや、正確には前アルバムでも「ララ」名義の曲はありましたが、きちんと個人名がクレジットされているのは、今回が初めてです。 ベースのマティアスが書いた「Peace in You」は、6/8のビートに乗ったバラード・ナンバー。あくまでキャッチーで癒される曲です。テナーのペーターは、ここでは彼のストリート風の外見をそのままに「Ella Stella」という、ロウ・ファイで始まる、まるで「スキャットマン・ジョン」のような曲を提供しています。  これで見ると、ヴォイパの人がまっとうな外見のイケメンなので、ちょっと意外な感じがしてしまいます。 CD Artwork © hänssler CLASSIC |
||||||
もちろん、ソロのパートを合唱で歌う、という試みもありました。男声合唱のものは良く聴く機会がありますし、ア・カペラの混声合唱で伴奏パートまで編曲したものも有りましたね。 ですから、「女声合唱」でこの曲が歌われた録音が出たと聴いた時には、さぞやさわやかな印象の仕上がりになっているのだろう、と思いました。これまでの男声や混声のバージョンは、ちょっと重たすぎるような感じがありましたからね。 そんな演奏を試みたのは、オランダの「ココ・コレクティーフ」というアンサンブルです。朝ごはんみたいな名前ですね(それは「コーンフレーク」)。デン・ハーグ王立音楽院で知り合い同士だった5人の女声歌手と1人のピアニストによって結成されたユニットです。この歌手たちは、リサイタル活動を主に行っている一人を除いて、あとの4人はすべてオペラ歌手としてのキャリアを持った人たちです。ピアニストのモーリス・ランメルツ・ヴァン・ビューレンは伴奏者として定評のある方で、ここでは編曲も担当しています。 その編曲のプランは、ブックレットのそれぞれの曲の演奏者を見てみると、様々に異なっているようでした。そもそも、全員が揃って歌うのは1/3ほどしかありません。それ以外はソロ、もしくはデュエットやトリオ、さらにピアノだけで歌はなし(雪融けの水流)とか、ピアノなしのア・カペラ(道しるべ)もありますから、全ての組み合わせをこの24曲の中で追及しているのでしょうね。 最初の「おやすみ」は、全員の演奏で始まります。最初は全くのソロで歌われ、次に二重唱からもっと人数が増えていく、というプランになっているようですから、「合唱」という感じはあまりしません。いや、冒頭から歌い出した人はとても伸びやかで澄んだ声でしたから、こういう人たちが集まっているのだったら、とてもきれいなハーモニーが聴けるのだろうと期待したのですが、その後で声が重なると、それはあまり溶け合わないような歌い方になってしまっているのですね。聴きすすんでいくと、どうやら彼女たちは、お互いの声をきれいに「ハモらせる」のではなく、それぞれに目いっぱい自分自身の声を主張する、といった歌い方に徹しているようでした。 こんな歌い方がデフォルトの場面を思い浮かべてみると、それはオペラのステージだったことに思い当たりました。彼女たちは、まさに「オペラ」のスタンスでこの「リート」と対峙していたのですよ。 別に、それはアプローチとしては新鮮なものであることは否定できません。この曲の中には、充分に「オペラ」として耐えうるだけのポテンシャルは秘められています。しかし、彼女たちがそのような新たな魅力をここから引き出しているとはとても思えないのです。 このメンバーの中には、さっきのきれいな声の方だけでなく、とても「個性的」な声の持ち主も混ざっていることが、それぞれのメンバーがソロを歌う曲で明らかになります。具体的に名前を挙げると、その「きれいな声の方」がニッキ・トゥルーニート。それに続いて、あくまで個人的なランキングですが、声の伸びはあるがちょっと弱いエレン・ファルケンブルフ、伸びはあるがビブラートがきついヴェンデリーネ・ファン・ハウテン、軽めの低音だがきつい音色のヤネリーケ・シュミート、そして、とんでもない悪声で、この人が入っただけでアンサンブルが完全に崩壊してしまうのが、メーライン・ルニアです。 ブックレットのプロフィールを読むと、彼女たちは「緊密なアンサンブルを作り出しているが、決して『合唱のサウンド』を真似することは目指してはいない」のだそうです。その結果生まれたこのおぞましい「サウンド」には、ちょっとついて行けません。 CD Artwork © Quintessence BVBA |
||||||
というか、今回のオーケストラのバイエルン放送交響楽団は当時クーベリックが首席指揮者を務めていたところで、なんと言っても「真打」になるのですから、それをもって完結なんてことになるかもしれませんね。 この「第9」の録音会場は、当時のこのオーケストラの本拠地のヘルクレス・ザールです。ここも響きのよいホールとして知られていますし、全くお客さんを入れないセッション録音ですから、リア・スピーカーからは空っぽの会場ならではの残響がたっぷり聴こえてきます。特に、打楽器や金管楽器が、よく響いていますね。ティンパニの強打は特に目立ちますし、終楽章のシンバルなどもビンビン聴こえてきます。おそらく、お客さんが入った時のライブ録音ではここまでの残響は聴こえないでしょうから、聴いている者はまるでホールを独り占めしているようなぜいたくな気分に浸れるのではないでしょうか。 それと、今回のリマスタリングではしっかりDGのサウンド・ポリシーが伝わってきたのは、うれしいことです。もちろん、かつてのDGのCDに比べると、格段に楽器の解像度が上がっています。そこからは、まだ粗野な味の残る、いかにもドイツ的なオーケストラの響きがストレートに伝わってきます。 この録音を最初に聴いた時からはかなりの年月が経ち、再生メディアとともに再生環境、さらにはリスナーとしての立ち位置も大幅に変化しています。なによりも、実際にオーケストラ・プレーヤーとして音楽を「内側」から聴くようになったことで、同じ音源でもそれに対する感じ方はかなり異なっていることに気づかされます。 もちろん、それは世の中のベートーヴェン演奏に対する判断基準が劇的に変わってしまったことも無関係ではありません。そういう意味で、このクーベリックの演奏は、逆に新鮮な魅力を持って目の前に現れてきました。 特に強烈な印象を与えてくれたのが、第2楽章のトリオの部分のテンポ設定です。あくまで本来の「トリオ」の意味を持たせて、とてもゆったりとしたテンポで、まるで夢見るように歌い上げるこの部分には、たとえばオーボエが必死の形相で難しい指使いに挑戦しなければいけない昨今のテンポからは絶対に感じられない安らぎがあります。 かと思うと、終楽章の最後に見せる劇的なギア・チェンジ。一瞬低速に切り替わったかと思うと、間髪をいれずに訪れる総攻撃、それを演出しているのは、ピッコロ奏者の熟達の技、ずっと楽譜より1オクターブ高い音で勝負していましたから「もしや」と思っていたら、やはり最後は4オクターブ目の「D」を見事に決めての着地です。 そんな「暴れ馬」のようなオーケストラに、合唱も負けてはいません。「Seit umschlungen」で始まる男声合唱の何と力強いことでしょう。いや、ここでは低音専門のベースのパートの人が無理をして高音を出そうとしてとんでもない声になっている様子までがしっかり聴こえてくるほどの「気合」が感じられます。そして「über Sternen muß er wohnen」の神秘的な響きの後に出てくる二重フーガでの、普通はソプラノに消されてほとんど聴こえてこないはずのアルト・パートのぶっとい声といったら。 このオーケストラも合唱団も、かつてはこんなにエネルギッシュだったんですね。同じ団体が、今ではすっかりスマートになってしまいました。 SACD Artwork © PENTATONE MUSIC B.V. |
||||||
  このオーケストラは、この施設のプロジェクトに沿った連続コンサートなども催しています。2015年に音楽監督に就任したフォークトが、2016年から2017年にかけて行ったのが、ベートーヴェンのピアノ協奏曲の全曲演奏でした。2016年の9月30日に「トリプル・コンチェルト」、10月29日に「第1番」、11月18日に「第5番」、2017年3月17日に「2番」と「3番」、6月10日に「第4番」と「合唱幻想曲」が演奏されています。 余談ですが、この6月10日のコンサートでは、それ以外にも「交響曲第5番」と「交響曲第6番」、そしてコンサート・アリアとミサ曲まで演奏されていました。この曲目を見て「もしや?」と思った人はかなりの通。そう、これは、これらの曲が初演された1808年12月22日のアン・デア・ウィーンで行われたコンサートを再現したものだったのです。すごいですね。 これらの「6つ」の協奏曲が、それぞれ2曲ずつ収まったCD3枚として、このレーベルからリリースされて「全集」が完成したようです。できれば「合唱幻想曲」もどこかに入れてほしかったと思うのですが、ちょっとカップリングが難しかったのでしょうかね。「トリプル・コンチェルト」まで入れたのですから、それこそ、「ヴァイオリン協奏曲」のピアノ版も演奏して「完全な全集」を作ればよかったのに。 ということで、普通の「全集」ではまず入っていない「トリプル」が入ったこの1枚を聴いてみることにしました。ここでフォークトと共演しているのは、彼の親友クリスティアン・テツラフと、その妹のターニャ・テツラフです。 この曲は、たとえば往年のリヒテル、オイストラフ、ロストロポーヴィチをソリストに迎えたカラヤンとベルリン・フィルの録音に見られるような、なんか、身の丈に合わない「立派すぎる」演奏が横行しているために、逆に引いてしまうところがあるという不幸な目に遭っています。この曲本来の魅力がどこかに行ってしまっているのではないか、という気が常に付いて回っていましたね。 しかし、ここでの3人のソリストたちは、そんな変な因習を一蹴してくれるような小気味の良い演奏を聴かせてくれていました。なんせ、それぞれがほとんどソリストとは思えないようなスタンスでまず登場してくれますから、ちょっと肩透かしを食らった感じがしたぐらいですからね。それは、オーケストラの一員がたまにソロを取るといった、「合奏協奏曲」のスタイルを持つこの曲に対しての、まさに望ましいスタンスだったのですよ。 ソロ・コンチェルトの「3番」になると、今度はピアニストとオーケストラの「掛け合い」とか「対話」といった、アンサンブルの妙味がストレートに感じられるものに仕上がっています。唯一短調のこの曲が持つ重さのようなものをほとんど感じさせないクレバーさも、とても心地よいものでした。 CD Artwork © Deutschlandradio/Ondine Oy |
||||||
そのスホーンデルヴィルトさんが、なんとモーツァルトの「レクイエム」を指揮したアルバムを出したというではありませんか。この曲にはフォルテピアノのパートはありませんから、ここで彼はポジティーフ・オルガンを弾きながら指揮をしているようでした。 録音は、ブザンソンにある教会でのセッションで行われました。どうやらこのセッションでは、指揮者(オルガン)を中心にメンバーが真ん中を向いて円形に並んでいるようなのですね。面白いことに、指揮者の向かい側にいる合唱は、指揮者から見ると左にベース、右にソプラノという並び方になっています。 ただ、録音上は聴衆からの視線を基準にしているので、あくまで合唱はその逆、左がソプラノ、右がベースという定位になっていますね。これは普通の2チャンネルステレオですが、サラウンドでは合唱が後ろから聴こえてくることになるのでしょうか。  楽譜は基本的にジュスマイヤー版をそのまま演奏しているようですが、例えば「Benedictus」ではトランペットに、楽譜にはないティンパニを重ねています。今までの修復稿で、こんなことをやっているものはありませんでしたね、 いや、それよりも重大なのは、ここでは、当時のウィーンで行われていただろう実際の葬儀での典礼を再現しようとしていることです。ですから、音楽以外に、グレゴリア聖歌で何ヶ所か「祈りの言葉」が挿入されています。さらに、モーツァルトは作っていなかった「Libera me」が演奏されています。それはモーツァルトの死後、1800年頃にイグナツ・フォン・ザイフリートという人によって作られたものです。ザイフリートはあのエマニュエル・シカネーダー(「魔笛」の台本作家)の劇場の音楽監督を務めていた人で、これはモーツァルトの「レクイエム」の「おまけ」として作られ、なんでもベートーヴェンの葬儀の際に演奏されたのだそうです。 このCDがまさにその「世界初録音」になるのですが、それはなんともインパクトに欠けた凡庸な作品でした。いや、正確には2か所ばかりとんでもない「インパクト」はあります。それは、「Dies illa, dies irae」と「et lux perpetua luceat eis」というテキストの部分。そこでは、それと似たようなテキストのモーツァルトの「本体」の部分を丸ごと引用(「パクリ」とも言う)しているのですからね。 「世界初録音」はもう一つありました。「Lacrimosa」の後に、「Amen」が入っているのですが、それが、例えばレヴィン版のように、モーツァルト自身が作ったとされるテーマではなく、スホーンデルヴィルトの「オリジナル」が使われているのですよ。これも、意味不明。 そんなもろもろの付け足しがあるにもかかわらず、全曲の演奏は「たった」63分33秒しかかかっていません。それは、テンポがあまりにも素っ気ないため。ただでさえ人数が少なくてスカスカなところに、こんなあっさりしたテンポでは、とても「死者を悼み悲しむ」ような気にはなれません。何よりも、ここからは心に伝わる「歌」が全く聴こえてこなかったのには、別の意味で「悲しく」なってしまいます。 CD Artwork © note 1 music gmbh |
||||||
実際、彼が立て続けにヒット曲を出していたのは1960年代でした。それが、晩年の1980年後半には、元ビートルズのジョージ・ハリスンが結成したバンド「トラヴェリング・ウィルベリーズ」のメンバーとして「リバイバル」することになります。しぶといですね(それは「サバイバル」)。このバンドでオービソンの声の魅力にとりつかれ、さらに映画に後押しされてファンになったという人も多かったのではないでしょうか。それほど、彼の声はその辺のロック・ヴォーカリストとは一線を画した格別の魅力を放っていました。 亡くなってから30年近く経って、去年の11月にこんなアルバムがリリースされました。これは、オービソンが残した音源から彼のヴォーカルだけを抜き出し、そのバックを新たに録音して新しいバージョンを作った、というものです。 マルチ・トラックの中の彼の声に合わせて、リズム・トラックを新たに録音します。そして、さらにそこにストリングスを加えるのですが、そこにスタジオ・ミュージシャンではなく、ロイヤル・フィルという「普通の」オーケストラを使ったというのが、このアルバムの目玉です。 実際は、このクラスのオーケストラがスタジオの仕事をするのは日常茶飯事ですから、それほどありがたがることはないのですが、ここでは確かにその間違いなく大人数の弦楽器が演奏している厚ぼったいサウンドには、とてもゴージャスさが感じられます。 それと同時に、ここではコーラスも新たに加わっていました。それは10人以上のメンバーが参加している、ちゃんとした「合唱団」ですから、こちらの深い響きにもとても魅了されてしまいます。 つまり、そんなキレキレの、最新の録音によるバックの中に、半世紀以上前に録音されたヴォーカルが入っても、全く何の違和感がないということに、本当は驚くべきなのでしょうね。それだけ、彼の歌声には時代を超えた普遍性があるということになりますね。 60年台の録音と言えば、ヴォーカルには派手なエコーがかかっていたものです。ここでも、オービソンの声はその「エコー込み」で使われていて、まわりのサウンドもそれに合わせてかなり深めのエコーがかかっています。そうなると、あの頃の例えばフィル・スペクターが作り上げたびしゃびしゃのエコーの世界が、方向性は同じでも全く異なる景色で現れてきます。 それが、80年台の曲になると、そのエコーが控えめになってストレートな声とサウンドに仕上がっているのも、面白いところですね。この時代の「I Drove All Night」や「You Got It」では、オリジナルでは当時の仲間のジェフ・リンなどがギターやバッキング・ヴォーカルで参加していました。ですから、今回のプロジェクトではオービソンの声と一緒にそれらのパートもそのまま残して、新たに別のパートを付け加えていましたね。 いや、なぜか入手したのはドイツ盤だったのですが、そこにはボーナストラックでヘルムート・ロッティという、ベルギーのシンガーがオービソンと「デュエット」までしているんですよね。これが傑作、歌っているのが60年台の「Only the Lonely」なので、ロッティにもおんなじエコーがかかっているんですよ。  CD Artwork © Sony Music Entertainment Germany GmbH |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |