|
|
|
|
![]()
蝦蟇色の髪の乙女。.... 佐久間學
そのオルガンが、ストックホルムにある聖ヤコブ教会にある楽器だと知って、ちょっと懐かしい思いに駆られています。同じBISレーベルで1993年にリリースされたデュリュフレの「レクイエム」(オルガン・バージョン)などを収めたアルバムが、やはりこの教会で録音されていたのですよ。それは、合唱がとても澄み切った響きでお気に入りでした。 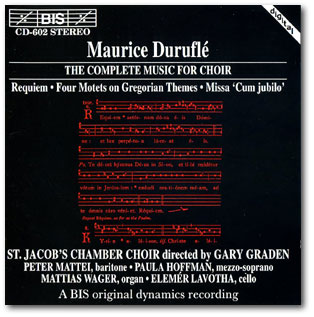 CD-602 その時の録音セッションの写真がこれです。  それは確かに、今回のジャケットのバックになっているオルガンと同じものでした(ブックレットの裏表紙に、もう少し遠景の写真があります)。 なんでも、この教会はオッターにとっては若いころからのお馴染みの場所で、ここの合唱団に所属していて、バッハの「ヨハネ受難曲」のソロ(「Es ist vollbracht」でしょうか)を初めて歌ったところなのだそうです。 この楽器、一見、バロックオルガンのようなファサードですが、作られたのは1976年、実際はデュリュフレにはとてもマッチしたフランス風の響きのする楽器だったような記憶があります。それが、今回、まさにそのデュリュフレの「レクイエム」からのメゾ・ソプラノのソロ・ナンバー「Pie Jesu」をオッターが歌っていたのには、感激です。録音も今回は別物のようにクリアになっていますから、そのオルガンのフランス風のビブラート(「Vox Humana」というストップ)がはっきりと聴こえてきます。クレッシェンドやディミヌエンドも出来るようなので、スウェルの機構もあるのでしょう。そこに彼女の朗々とした声が加わって、とても情熱的なデュリュフレを味わうことが出来ます。 ここで選ばれている作品は全部で17曲ですが、その最初と最後にクラシックではなくミュージカル・ナンバーが歌われているのが目を引きます。最初はバーンスタインの「ミサ」からアルバムタイトルでもある「A Simple Song」ですが、そこではオルガンの他にエレクトリック・ギターとハープ、そしてシャロン・ベザリーが吹くフルートが加わります。ここでのベザリーは、いつものあくの強い押し出しはあくまで控えて、オブリガートに徹している吹き方でなにか安心できます。彼女が参加しているのはこの1曲だけという贅沢なキャスティングです。 そして、最後を飾るのが、ロジャース/ハマースタインの「サウンド・オブ・ミュージック」から、ミュージカルの中では修道院長が歌うナンバー「Climb Ev'ry Mountain」です。彼女の声にはピッタリですね。 ここでは、マーラーの作品も2曲歌われています。それぞれ「子供の不思議な角笛」のテキストで、いずれも交響曲の中で歌われているもの。まずは「3番」に登場する「Es sungen drei Engel」と、「2番」の「Urlicht」です。彼女の声はとても素敵ですが、やはりこれをオルガンだけで演奏するのは、かなりしょぼいものがあります。しかも、それがフランス風の音色なのは、ちょっと抵抗があります。 もっとも、メシアンやプーランクの歌曲の伴奏にはまさにうってつけの楽器です。メシアンの「Trois mélodies」はピアノ伴奏の曲ですが、それがオルガンによって奏されると彼の和声がより魅力的に聴こえてきます。 アルヴォ・ペルトの作品もそれぞれオリジナルの編成で2曲取り上げられています。したがって、「Es sang vor langen Jahren」ではオルガンは入らず、ヴァイオリンとヴィオラによる伴奏です。もう一つの「My Heart's in the Highlandd」は、元々はカウンターテノールとオルガンのための作品、2000年の作品ですが、歌は同じ音だけを延々と歌うとてもシンプルな曲です。そんな、スタティックなアプローチでの彼女も、素敵です。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
この「折り白鳥」はただジャケットを飾っているだけではなく、これを使ってプロモーション用のコマドリ動画が作られていました。双子の演歌歌手(それは「こまどり姉妹」)ではありません。なぜか、最初に登場するのが蛙(これももちろん折り紙)というのが面白いですね。 「白鳥の湖」と言えば、チャイコフスキーが作ったバレエ、いや、すべてのバレエの中で最も人気のある演目なのではないでしょうか。ただ、ご存知のようにこれが1877年に初演された時にはそれほどの評判にはならなかったものが、作曲家の死後の1895年に「改訂版」が上演されたことによって、現在の人気につながるブレイクを果たしたのですね。 「改訂版」と聞くと、まずは楽譜のことだと思ってしまいますが、このバレエに関しては大きく「改訂」されたのは脚本の方でした。ここでは、チャイコフスキー自身も関わって作られた初演の時の脚本が、大幅に変えられていたのですね。それに伴って、脚本と振付に合わせるために音楽のテンポが変えられ、曲の順序の差し替え、カット、さらにはチャイコフスキーの別の作品の挿入などの措置が取られました。それが、ここでの「改訂」の実態です。バレエに関しては全くの門外漢なので、詳しいことは分かりませんが、現在上演されている「白鳥の湖」は、ほとんどがこの改訂版が元になった形のようですね。 しかし、チャイコフスキーはこの音楽を単なる「バレエのための伴奏」として作ったわけではありません。それは、まるでそれ自体が巨大な交響曲のような、綿密な設計の元に作られていたのです。それは、曲の構成やテーマの扱い、そして調性の設定までに及んでいます。1895年の「改訂」では、そのような作曲家の思いが完全に破壊されてしまっているのでしょうね。 ですから、コンサートでこの曲を「全曲」演奏する時には、1877年の初演の時のバージョンで演奏するのは当たり前のことなのですよ。実際、楽譜として出版されているのはこの形ですからね。それを、このSACDではわざわざ「1877 world premiere version」と謳っていますが、そんな風に特別扱いする必要は全くないのですね。 もうひとつ、これは例によってこれを扱っている日本の代理店の仕業ですが、そのインフォでは「セッション録音」と表示されています。これは、ブックレットの中で指揮者のユロフスキが「2017年2月に行った一晩の演奏を録音」と言ってますから、全くのデタラメです。確かにクレジットではもう1回、2018年2月にも録音が行われたことになっていますが、これは前の年の録音のミスなどを修正するためのセッションで、メインの音は2017年のコンサートで収録されたものです。こういうものは普通は「ライブ録音」と言いますよね。実際、「セッション録音」ではありえない会場ノイズや、アンサンブルの乱れもあちこちで聴こえますし。 なんせ、トータルで2時間半の演奏時間ですから、「交響曲」としてはかなり長め。しかし、ここにどっぷりとつかって、その時間軸の中でのテーマの関係とか、全体の構成などを考えながら聴いていると、全くその長さを感じることはできません。 なんたって、チャイコフスキーはそれぞれのシーンに美しすぎるメロディを惜しげもなく使って、聴くものを全く退屈させることはありません。そのメロディの中でもっとも有名なあの「情景」のオーボエ・ソロは、紛れもなくワーグナーの「ローエングリン」の中のモティーフのパクリなのですが、これはもはやそんなレベルの問題ではなくなってしまいますね。 逆に、ここからパクられた曲があるぐらいですから。第4幕の第27番「小さな白鳥たちの踊り」は、絶対「夜来香(イエライシャン)」の元ネタです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
まず、その「ヴァイオリン・ソナタ」が、イザベル・ファウストのヴァイオリン、アレクサンドル・メルニコフのピアノで演奏されます。ここで聴こえてくるファウストのヴァイオリンの、なんと繊細なことでしょう。いや、繊細というよりは、余計なものを切り捨てて純粋なものだけを抽出したような音、それは、同時に虚飾を廃した一抹の寂しさを伴うものでした。 メルニコフのピアノも落ち着いた音色で、この作曲家が最後にたどりついたものが、ほとんどモノクロームのような中での「印象」を感じさせることを気づかせてくれます。 次が、フルート、ハープ、ヴィオラというとてもユニークな組み合わせのトリオによるソナタです。ここでは、楽器自体もドビュッシーが生きていた当時に実際に使われていたものが使われています。フルートは、まさに「名器」として現在でもその魅力にとりつかれた多くのフルーティストに使われている「ルイ・ロット」です。ここで、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者、マガリ・モニエが吹いているのは、1880年に作られた楽器、この時期のフルートの収集や、「フレンチ・スクール」という近代フルート奏法の基礎を作ったアカデミズムの研究で著作もあるフルーティスト、ベルナール・デュプラのコレクションです。 この楽器の音色は、とても魅力的です。それは、やはり華やかさとは無縁のしっとりとした味わいで迫ります。モニエはミュンヘン国際音楽コンクールで1位を取っているほどのヴィルトゥオーソですが、この曲ではあえて技巧を誇示せず、なにか素朴な味を出そうとしているようです。したがって、このフルート・パートは今まで聴いてきたどの演奏とも異なった、この作品の本質に迫るものとなっています。 ハープもやはり、19世紀後期に作られたエラールの楽器です。こちらは、あのピリオド・オーケストラの「レ・シエクル」から借りたものなのだそうです。やはり、この時代のピアノのような現代楽器にはない軽やかな音色が魅力的です。 そこに加わるヴィオラのアントワーヌ・タメスティが、なんとも変幻自在の音色とスタイルでその2つの楽器に絡みます。その絶妙のアンサンブルによって、ちょっと驚かされるような表現があちこちに登場しています。 本当にどうでもいいことですが、このCDを紹介した代理店のインフォによると、ここでのトリオの楽器は例えばハープなどはレ・シエクルで「調整」したとあるのですが、これは間違い。フランス語のクレジットでは「レ・シエクルより貸与」となっています。こんないい加減でない、ちゃんとしたインフォを読みたいよ。 で、最後には「チェロ・ソナタ」が、ジャン=ギアン・ケラスのチェロとハヴィエル・ペリアネスのピアノで演奏されています。これは、作品のキャラクターもそうなのでしょうが、この二人によってかなりお茶目な仕上がりになっています。第2楽章のピチカートではノリノリのパフォーマンスを聴かせてくれていますし、最後の楽章もちょっとエキゾティックなモティーフがより際立った味に感じられます。 さらに、それらの「ソナタ」の間に、タンギ・ド・ヴィリアンクールのピアノによってやはりドビュッシーの最晩年の作品「英雄の子守歌」、「アルバムのページ」、「エレジー」、「燃える炭火に照らされた夕べ」の4曲が演奏されます。これも乾いたタッチのピアノがとても物憂げでいい感じ。 久しぶりにいいCDを聴いたな、という気がします。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |
||||||
この作品で用意された楽器は、ヴァイオリン2挺、ヴィオラ2挺、チェロ1挺、コントラバス1挺という弦楽器と、2管の木管楽器(2番フルートはピッコロ持ち替え、2番オーボエはイングリッシュ・ホルンとオーボエ・ダモーレ持ち替え、2番クラリネットはバス・クラリネットとアルト・サックス持ち替え、2番ファゴットはコントラファゴット持ち替え)、チューバのない1管の金管楽器(トランペットはコルネット持ち替え)、そして3人の打楽器奏者と2本のハーモニカ、さらにアコーディオン(ウインドマシーン持ち替え)、ハープ(ウインドマシーン持ち替え)、ギター(ウインドマシーン持ち替え)が加わります。何とも多彩な楽器編成ですね。 そして、24曲あるそれぞれの歌曲も、それらの楽器によって多彩に装飾されています。というより、これは「現代音楽」で言うところの「コラージュ」の手法を駆使して作られたもので、冒頭にあるように、その中ではシューベルトの「冬の旅」は単なる「素材」にすぎません。これも、別のジャンルの「現代音楽」では「サンプリング」と呼ばれている手法ですね。 従って、その「素材」はオリジナルがそのまま使われることもありますし、なんらかの「変調」が加えられることもあるのです。その「変調」とは、具体的には速度やピッチを変えること、あるいはピッチそのものをなくして「ラップ」にしてしまうことなどでしょうか。 これが「作曲」されたのは1993年、その年の9月21日にフランクフルトで、ハンス・ペーター・ブロホヴィッツのテノールと、作曲者自身の指揮によるアンサンブル・モデルンの演奏によって初演されました。その同じメンバーで1994年8月にRCAに初録音が行われています。 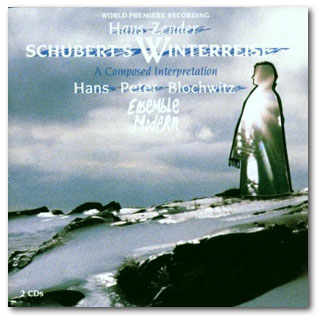 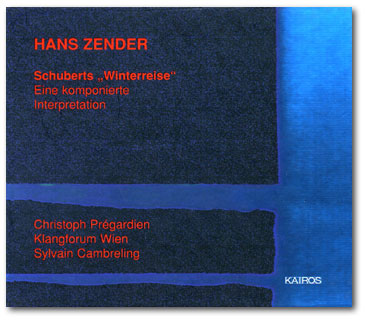 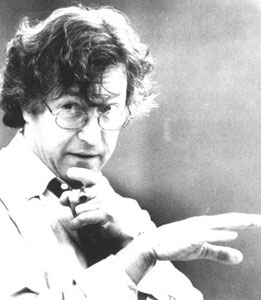 そんな、「冬の旅」オタクのクリストフの息子、ユリアン・プレガルディエンまでもが、このツェンダーの作品を演奏したというのは、なかなか興味深い出来事です。これは、2016年1月21日にザールブリュッケンで行われたコンサートのライブ録音です。この時のユリアンはまだ31歳でした。 つまり、この作品は20年以上経ってもその人気は衰えていないという、「現代音楽」としては稀なヒット作(つまり「古典」)となっていたのです。それはおそらく、それぞれの録音で歌っていたアーティストたちが、シューベルトのオリジナルの部分をとても心を込めて演奏していたからなのではないでしょうか。あるいは、いくらいじられてもシューベルトのオーラは決して薄れることはないということなのかもしれません。 今回のゆりやん、いやユリアンは、その若々しい声でさらにそのオリジナルの抒情性と、時には一途過ぎる心情を見事に聴かせてくれています。おそらく、今までの録音の中では、彼の歌唱がひときわ抜きんでているのでは、と感じられます。 今世紀の私たちは、この作品に接するのは初めてではないはずです。すでにネタバレしているものでもそこから新たな魅力を感じることが出来るというのも、すごいことです。そのように思えるのは、もしかしたら、そこには今の「現代音楽」からはなくなってしまったある種の「力」が、しっかりと残っているからなのかもしれません。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music France |
||||||
ただ、今回は、オペラではなくコンサート形式の上演でした。実際は同じものが3回演奏されています。11月19日と11月26日はサントリーホール、そして、11月23日はびわ湖ホールです。なんせ、オーケストラの編成は16型の弦楽器に、7.4.7.4.-6.4.4.3という管楽器、打楽器奏者が10人、オンド・マルトノが3台という大規模なものですし、そこに9人のソリストと120人の合唱が加わりますから経費は大変なものでしょう。それを読響だけで賄うのは大変なので、びわ湖ホールとの共同プロデュースという形を取って、負担を軽減しようとしたのでしょうね。 そのうちの、サントリーホールでの2回のコンサートの録音を編集したものが、このCDです。26日の公演に行く機会があり、そのレポートがこちらにあります。その時にはピッコロあたりが何度かミスをしていたようなので、そのためのバックアップという意味で、より完璧な記録が残されているのでしょう。 その時にチェックしたマイクは、こんな感じでした。  曲の冒頭のマリンバ群の騒々しい音でも、何の破綻もなく録音されていたことにまずは安心します。オーケストラの音はとことんクリアで、それぞれの楽器が明瞭に聴こえてきます。その後、バリトンのソロが始まっても、まるでマイクがすぐそばにあるようなクリアさで聴こえてきます。合唱と、オルガン前で歌われたソプラノだけは、そのような距離感も感じられました。ただ、オンド・マルトノは、実際に聴いた時にはもっと存在感があったような気がします。なによりも、このノーマルCDではその立体的な配置が全く感じられないのが、とても残念です。これほどの優れた録音がサラウンドで聴けたなら、さらにうんと価値のあるものになっていたはずなのに。 演奏自体の感想は、先ほどのレポートと変わりませんが、CDでの正確な演奏時間は4時間17分、今までのどの録音よりも長くなっています。他の録音と比べつつ冷静に聴き直してみると、やはり音楽の流れが時折滞っていたような感じは否めません。 ただ、合唱のクオリティは、やはりとても高いことも分かりました。以前の録音は全て暗譜で歌われていたのでしょうから、楽譜を見ていた分、正確さが保てたのでしょう。ただ、フランス語の発音はとても気になってしまいます。 そして、ここでは最後の拍手もしっかり収録されていました。しかし、それはエンディングでの大音響の残響が完全に消えてから4秒も経ってから始まるという、なんとも間抜けなものでした。これは、「指揮者がタクトを降ろすまで」お客さんが拍手をするのを待っていたため。そのような指示がパンフレットに載っていて、それが場内アナウンスでも復唱されていましたからね。そんなアホな「マナー」の押しつけは、許せません。 CD Artwork © Tomei Electronics "Altus Music" |
||||||
ただ、その時はあくまで主役は合唱団でしたから納得は出来ましたが、今回は合唱が全く入らないピアノ協奏曲、しかもベートーヴェンの「4番」と「5番」という王道中の王道のピアノ協奏曲のオーケストラを指揮しているではありませんか。またもやびっくりです。 彼女も先日のミンコフスキ同様、NAÏVEから ERATOに変わってしまったアーティスト、どちらのレーベルの趣味なのかは分かりませんが、このジャケットにあるそのベートーヴェンの肖像画は、なんかとても爽やかな感じですね。これらの協奏曲が作られたのは1805年から1809年にかけてですから、1770年生まれのベートーヴェンは30代後半、実際はこんな感じの若々しさだったのかも知れませんね(ということは、このブックレットに書いてある通り、再来年の2020年は彼の「生誕250年」ということになるのですね。個人的には、オリンピックよりもこちらの方がそそられます)。 このピアノ協奏曲が作られた時期には、交響曲では「4番」、「5番」、「6番」が作られています。まさに彼の作曲家としての黄金期ですね。当然、この2曲のピアノ協奏曲はコンサートもレコーディングもおびただしい数のものが存在していますから、そこで注目を集めるためには何らかのセールスポイント(「奇策」とも言う)が必要になってくるのでしょう。そこで、エキルベイとピアニストのニコラ・アンゲリッシュは、ピリオド・オーケストラとモダン・ピアノを協演させることにしました。ただ、いくらなんでも現代のスタインウェイではあまりにもアンバランスですから、「1892年に作られたプレイエル」というのを持ってきました。これは、ベートーヴェンの時代の「フォルテピアノ(=ピリオド・ピアノ)」とは一線を画した新しい楽器ではありますが、まだまだ鄙びた音色を残していて、ピリオド・オケとの共演もそれほど違和感がないものなのでしょう。何よりも、「この楽器だったら、ベートーヴェンが表現したかったことが完全に伝えられるだろう」という指揮者とピアニストの思惑が、ここには込められているはずです。 確かに、「4番」がピアノ・ソロで始まった時に、そのなんとも軽やかで輝きのある音には、先ほどの「爽やかな」ベートーヴェン象が眼前に広がりました。そこに入ってくるバックの弦楽器も、こちらはもちろんガット弦のソフトな感触でそのピアノを包み込みます。少なくとも、このあたりまでは音色的にはこの19世紀初頭と19世紀末とのコラボは成功しているかのように思えます。 しかし、「5番」になると、ピアノとオーケストラの間になにか相容れない溝のようなものが感じられるようになってきました。音色はソフトでも、ピアノはメカニカルな面では堂々たる押し出しを誇っていて、まさにベートーヴェンの時代を超えた大きな音楽を作ろうとしているのですが、オーケストラがなんともサロン的なまとまりに終始しているのですよ。特に木管パートの主体性のなさといったら、もう歯がゆくなってしまうほどです。例えば第2楽章でフルートがテーマを吹くシーンでは、ピアノに隠れてそのメロディが全然聞こえてきません。エキルベイは、「大ホールでも通用するようなピリオド・オケ」を目指しているのだそうですが、そもそもそのような用途に対応していない楽器を使っているのですからそれは無理なことだとは気が付かないのでしょうか。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |
||||||
もちろん、現在コンサートで演奏する時には、そこまで膨らませた人数で演奏することはまずありませんが、ティンパニ奏者だけは最低でも10人必要とされています。さらに、コルネット、トランペット、トロンボーン、チューバ(自筆稿では「オフィクレイド」)によるバンダが4組用意されて、それぞれオーケストラと合唱がいる場所から離れた会場内の4ヵ所に配置される、という点だけは譲れませんから、金管楽器奏者も間違いなく大量に必要になってきます。 ですから、ステージ上のオーケストラの金管セクションはホルンだけ、ということになりますが、曲によってはバンダの出番がない時にそこに他の金管が加わることもあるので、何人かのプレーヤーはその時には移動してくるのでしょう。実際、今回のSACDのブックレットに載っているライブ録音の写真を見ると、金管のスペースだけ空いていることが分かります。 それと同じように、なんと合唱までが「移動」している写真がそのブックレットにありました。  ですから、それがいったい何の曲だったのかを知りたいとは思いませんか?さいわい、このアルバムはSACDのマルチチャンネルが聴けるものですから、サラウンドで再生してみると、なんとなく合唱が前にいるのではないか、という音場が感じられるところが見つかりました。それは6曲目の「Lacrimosa」です。この曲にはバンダが出てきますから、オーケストラの金管がホルン以外はいないのも、それの裏付けにはなるでしょうか。さらに、この前の曲の「Quaerens me」は合唱だけのア・カペラで歌われますから、もしかしたらその時にすでにこの位置に移動していたのかもしれません。 そんな、一味違う演出を取り入れたのは、アンドリュー・リットンの後を継いで2015年からこのベルゲン・フィルの首席指揮者を務めているエドワード・ガードナーです。彼はこのCHANDOSレーベルに、このオーケストラとともにシェーンベルクの「グレの歌」も録音していますから、このような大編成の曲はお手の物なのでしょう。 このコンサートが行われた会場は、ベルゲンにある「グリーグ・ホール」というコンサートホールです。キャパは1500人ですが、ワンフロアなので客席の面積はかなり広くなっています。ステージも、オケ・ピットに相当する部分まで広げて、指揮者の後ろに広い空間を設けていますから、そこにさっきのように合唱が全員(150人程度)立つことが出来ます。 さらに、普通に合唱が立つ場所を作るために、後ろの反響版が下げてあり、横の反響版との間に隙間が出来るのでそこに2つのバンダが入ります。もう2つのバンダは、客席の真ん中を横切る通路の壁際にセットされています。これで、聴衆のほぼ半数は、完全なサラウンドを体験できることになります。 それと同じものを、このSACDでもしっかり味わえます。「Dies irae」や「Lacrimosa」でのスペクタクルな音場を知ってしまうと、もう普通のステレオでは物足りなくなってしまうことでしょう。 合唱は「エドヴァルド・グリーグ合唱団」など全部で4つの団体の集まりですが、なかなかまとまった声で楽しめます。とくに、頻繁に出てくる男声だけの部分が、とてもスマートに聴こえるのは、かなりのハイ・トーンを楽々と出しているからなのでしょう。 SACD Artwork © Chandos Record Ltd |
||||||
ライヒが1971年に作った「ドラミング」は、全部で4つのパートに分かれている大作で、それぞれのパートで使われる楽器が変わります。最初のパートでは「調律された太鼓」という指定で、大小のボンゴをきっちりチューニングして使います。 このパートが、タイトルの「ドラミング」がそのまま演奏として行われている部分です。ここでは、4人の打楽器奏者だけが8個のボンゴを叩き続けるという、かなりストイックな情景が続きます。とは言っても、それはただ叩き続けるだけの単調なものではありません。一人一人は同じリズムパターンだけを叩いていますが、それが奏者ごとに微妙に「ズレて」行くというのが、ライヒの音楽の最大の魅力。8本のマレットによって叩き出される複雑に交錯したリズムと、それに伴って湧き上がってくる「メロディ」は、それまでの音楽の在り方に明確な風穴を開けるものだったのです。 さらに、この作品はボンゴだけのモノトーンの世界の中に、マリンバが入ってくることによって、色彩がガラリと変わります。最初はボンゴの後ろでかすかに聴こえてきたマリンバですが、それは次第に大きくなり、それに伴ってボンゴは徐々に消えていくという、一つの連続の中での「トランジション」が行われる場面、それは、聴いている者にとってはいったいいつの間に楽器が変わってしまったのだろうという不思議な感覚が湧いてくる瞬間となります。 それが、2番目のパートの始まり、そのころには、ボンゴを叩いていた人たちもマリンバのある場所に移ってきて、3台の楽器を9人の奏者が叩くことになります。さらに、このパートでは高い声と低い声の2人の女声ヴォーカリストが加わります。 同じように、3つ目のパートはマリンバからグロッケンへのトランジションによって始まります。ここでは、3台のグロッケンを5人の奏者が叩くとともに、一人は「口笛」をふき、さらに一人のピッコロ奏者が加わります。 そして、最後のパートにはすべての楽器の12人が全員参加して、一大スペクタクルが繰り広げられるのです。 そんな、とてつもなく複雑なことを、この録音では加藤さんが全部一人で行っているのですよ。もちろん、それは多重録音によるものですが、この音楽は言ってみれば「合わせない」音楽なのですから、普通に「一人ア・カペラ」のようなことを行うのとは全く異なる能力が必要になってくるのは明らかです。最後の方では、11人分の音を聴きながら、それに「合わせず」に、新たに別のリズムを刻むことになるのですからね。 それを、加藤さんはいとも楽しげにやってのけていたようです。しかも、ヴォーカルやピッコロまで、とても見事に演奏していました。ピッコロなどは、よくぞこんなにきっちりとした音が出せたものだと驚くばかりです。もしかしたら、うまくいったテイクをそのままサンプリングして使っていたのかもしれませんね。いずれにしても、これは世界で初めてこの作品を「一人だけで」録音したものとなりました。 そもそもこの録音は、ダンスとの共演でリアルタイムに演奏するために行われたものなのだそうです。一つのパートだけを抜いた「カラオケ」をバックに、一人で何種類もの楽器を叩き、歌い、それに合わせてダンサーが踊るというとんでもないことが、名古屋で行われていたんですね。 このアルバムが、サラウンドのSACDでリリースされたのも、日本国内だけなのだそうです。 SACD Artwork © Linn Records |
||||||
そのアーティストの名前は「PaTRAM Institute Male Choir」、この「PaTRAM Institute」というところがいちおう製作者としてクレジットされているので、調べてみたら、フルネームは「Patriarch Tikhon Russian-American Music Institute」つまり「総主教ティーホン・ロシア/アメリカ音楽協会」という教育機関でした。これはロシア正教会のための聖歌を歌う時の指揮者と歌手を育成するために2013年に設立された機関で、現在ではアメリカとロシアの各地で活動を行っているようですね。その名前にある「総主教ティーホン」という人は、アメリカでの布教活動も行った正教会の聖人なのだそうです。割引券を配っていたのでしょうね(それは「クーポン」)。 そこには、プロの歌手が集まった「総主教ティーホン合唱団」という混声合唱団がありますが、ここではその中の男声メンバーを中心にした「PaTRAM男声合唱団」が演奏しています。そしてさらに、モスクワとサラトフの2つの団体のメンバーも加わっています。 そのメンバー表では普通の男声合唱の4つのパートの内訳は10-11-9-12と、ベースの人数が一番多くなっています。しかも、12人のうちの5人が「Bass profundo」、つまり「オクタビスト」ですから、低音はとても充実していることが予想されます。 このアルバムのライナーノーツでは、指揮者のウラジーミル・ゴルヴィクが「実際、このアメリカのレーベルのSACDを最初に耳にするのは、母国の人たちではなく西欧圏の人たちなのですから、そのあたりの配慮をここでの選曲にも込めています」といったようなことを述べています。 そこで集められたのが、この方面では非常に有名なパヴェル・チェスノコフという作曲家が作曲や編曲を行った、徹夜祷と聖体礼儀のための聖歌です。1877年10月25日に合唱指揮者の家に生まれたチェスノコフは、教会音楽関係の教育機関のみならず、36歳の時から4年間、モスクワ音楽院でも作曲と指揮法を学んでいます。 彼は合唱指揮者や作曲家、あるいは教育者として活躍し、生涯に500曲近くの作品を残しています。しかし、ロシア革命以降はその活動は制限され、最後は栄養失調と心臓発作によって亡くなっています。それは大戦中の1944年3月14日のこと、パンの配給の列に並んでいる時でした。享年66歳でした。 「徹夜祷」というと、同じころに活躍したラフマニノフの無伴奏合唱曲(いわゆる「晩祷」)がすぐに思い浮かびます。ただ、ラフマニノフの作品はそれだけで長大な曲集になっていますが、このアルバムはチェスノコフのさまざまな作品から何曲かずつの聖歌をピックアップした、いわば「ベストアルバム」です。その最初の曲は、ギリシャ正教の聖歌を編曲したもので、それはとても洗練されたメロディとハーモニーを持ったものでした。そこからは、「ロシア」とか「スラヴ」といったもので表わされる情感は、ほとんど感じることはできません。 しかし、その次の曲になると、いきなりさっきの「オクタビスト」たちの超低音が聴こえて来て、まさに「ロシア」の大地が広がっています。さらに、3曲目のチェスノコフのオリジナルの作品などは、とてもスマートな和声感を持っていました。そんな感じで、洗練された曲から土臭い曲まで、適度にヴァラエティをもって構成されているのは、やはり「西欧のリスナー」を意識してのことだったのでしょうか。 それを、この合唱団はとてもスマートな歌い方に徹して歌っていました。もちろん、録音もとびっきりの素晴らしさでした。何度かのセッションがもたれたようですが、それぞれに微妙なサウンドの違いがあって、ちょっとオフマイク気味の敬虔な音から、オンマイクで生々しく迫る音まで、いろいろ楽しむことが出来ます。 SACD Artwork © Reference Recordings |
||||||
おフランスのレーベル、HARMONIA MUNDIからも、自国の作曲家ということでこんなアール・デコ風のジャケットで統一された新録音のアルバムが何枚かリリースされています。そんな中で、「ドビュッシーとジャズ」というタイトルのちょっと毛色の変わったものを1枚。 ここでのメインのアーティストは、その名もドビュッシー弦楽四重奏団という、1990年に創設されたアンサンブルです。このサイトでも、以前こちらのモーツァルトの「レクイエム」のリヒテンタール版で聴いたことがありました。それは2008年の録音なのですが、今回そのちょうど10年後にこのアルバムを作った時には、メンバー4人のうちの2人までが別の人になっていました。それはセカンド・ヴァイオリンとチェロの人なのですが、そのチェロの前任者、アラン・ブルニエという人は2005年に加入していますから、今の人は少なくとも3人目のメンバーとなります。弦楽四重奏団というとメンバーは殆ど変らないという勝手なイメージがありますが、ここはそうではないようですね。 そんな、古いメンバーの名前を持ち出したのは、このアルバムではドビュッシーのピアノ曲「前奏曲集」の中から有名な曲を弦楽四重奏をベースにした編曲で演奏しているのですが、その編曲者としてこの方の名前があったものですから。 つまり、タイトルでは「ジャズ」と謳ってはいるものの、全10曲のうちの半分の5曲はジャズ的な要素が全く見られない、原曲を忠実に弦楽四重奏用に編曲したものなのです。それを行っている人のクレジットとして、現在のメンバーとブルニエの名前が挙げられているのですね。ということは、その楽譜は彼が在籍していたころに作られたものなのでしょうから、ここで演奏されているその5曲は、別に今回のために特別に作られたものではなく、彼らのレパートリーとして普通に演奏されてきているものだったのでしょうね。確かに、サブタイトルは「四重奏のための前奏曲集」でした。 ですから、これはあくまでクラシック・ファンのために作られたもの、まずはオリジナルを聴いてもらった後に、ジャズ・ミュージシャンが加わってその対比を味わってもらう、というようなコンセプトなのでしょう。 例えば、ヴィブラフォンのフランク・トルティエが加わった「交代する三度」(第2巻11曲目)などでは、構成はほとんど変わらない中でのトルティエのアドリブ・ソロが楽しめます。 ただ、ピアニストのジャン=フィリップ・コラール=ネヴェン(あのジャン=フィリップ・コラールとは別人)とベーシストのジャン=ルイ・ラシンフォッセが加わった「沈める寺」(第1巻10曲目)は、ドビュッシー弦楽四重奏団のヴァイオリン奏者がいかにもな型通りのソロを聴かせたりして、冗長な印象は免れません。 ですから、この中で心から楽しめたのは、アコーディオンのヴァンサン・ペラニが加わって、「ジャズ」とはちょっと違う不思議なサウンドを醸し出していた「亜麻色の髪の乙女」(第1巻8曲目)と「風変わりなラヴィーヌ将軍」(第2巻6曲目)のメドレーと、ジャッキー・テラソンのピアノが加わったこの中では最長の演奏時間の「Bussi's blues」という粋なタイトルのピースです。もちろん、「Bussi」というのはお侍さんではなく(それは「武士」)ドビュッシーを親しみを込めて呼んだ名前なのでしょうね。 そのテラソンだけは録音も別のスタジオで、ピアノの音が全然別物でした。もしかしたらプリペアされていたのかもしれません。編曲は、ドビュッシーのみならず、ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」の断片まで現れるというぶっ飛んだものです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |