ショパン全作品を斬る
1835年(25才)
次は1836年(26才) ♪
前は1834年(24才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る
- [101] バラード第1番 ト短調 作品23
1836年出版。ドゥ・シュトックハウゼン男爵に献呈。
傑作が目白押しの年である。
ショパンはこの曲をパリ移住の頃から作り始めている。
バラードとはもともと吟遊詩人の歌で、
日本で言えば平家物語を語る琵琶法師の詩吟に相当する。
ショパンはそれを初めて歌詞の付かない絶対音楽に持ち込んだ。
4曲のバラードはどれもソナタ形式風だが、
几帳面なソナタ形式にとらわれてはいない。
ショパンのバラードは物語的な深い楽想に始まり激しい部分もあって途中何度も盛り上がるなど、
古典的アレグロ・ソナタ形式のようにただせわしない音楽ではなく、
また終始緩徐楽章的というのでもなく、
起伏に富むドラマを展開している。
このような交響詩の独奏曲版ともいえる単一楽章器楽曲はそれまであまり無かった。
スケルツォやノクターンなどが他人の創造をショパンが発展させたものとすれば、
ピアノ独奏用バラードこそはショパン独自の創作ジャンルではないだろうか。
ナポリ6の和音に基づくユニゾンのレシタティーヴォで始まる導入は、
ウェーバーの「舞踏への招待」(1819年)のイントロに刺激を受けたようだ。
この低音から上昇するウェーバーのイントロはシューマンにも
「蝶々」(1832年)のイントロを書かせた。
またショパンやリストに師事した素人ピアニストのレンツ自身の話であるが、
彼が初めてリストの前で「舞踏への招待」を弾いたときリストはこの曲を知らなかったが、
そのイントロ数小節を聞いただけで中断させ
「大変いいですね。誰の曲ですか?」
と聞いたという。
それほど「舞踏への招待」のイントロは音楽家達を魅了したということだ。
バラードに話を戻そう。
ト短調の主題を思い入れたっぷりとルバートをかけすぎる演奏をときどき耳にする。
このとき大抵次のように聞こえる。
譜例1
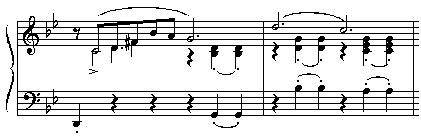
これのどこが誤りかおわかりだろうか。
ショパンの書いた通りに弾けばおのずと大仰な演奏は避けられると思う。
正しい楽譜はここに示そう。
変ホ長調の第2主題がまた素晴らしい。
ノクターンのような楽想だが、
夜というよりは昼下がりの陽光のもとでのまどろみだ。
それに続く三連符を交えての変ホ低音に乗る小終結句はまた一層素晴らしい。
ピアノソナタ第3番第1楽章もそうであるが、
ショパンはときどき素晴らしい小終結を書く。
特に左手伴奏がリズムを刻んで喋り続けるのでなく右手旋律を自由に解き放つよう途切れるところがいい。
この右手音型は第1主題の動機から来ている。
譜例2
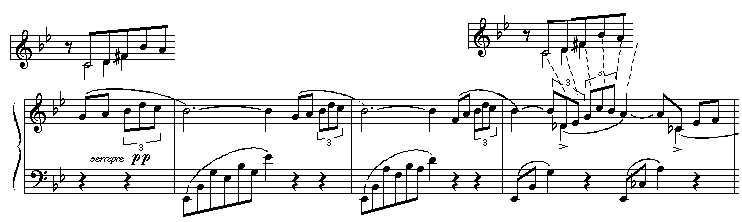
しかし第1主題とは感じが全然違うのであまり気が付かれないのだろうか、
このことが指摘された例を知らない。
この部分はさしずめロマン派の牧神の午後といったところだろうか。
その後展開部に入るが、
前半はあまり「展開」せず、
第2主題がイ長調の高らかなファンファーレでそのまま登場する。
それは完全終止せず、さらに本格的展開部に入るが、
その突入部分の和声推移にちょっと着目したい。
譜例3
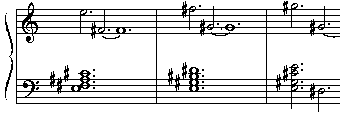
この盛り上がる経過句的和声推移はワルツ第2番、第5番、
練習曲作品25-1などにも見られるが、
チャイコフスキーもよく使っている。
その影響を受けてかシベリウスのフィンランディアにも現れる(皮肉なことに)。
恐らくショパンが最初に発明したものと思われる。
この経過句の後、
ショパンが普段は乱発を避けているfffの指定がある。
スケルツォ第1番にも見られたが、
ショパンは普通はff止まりで、
fffはここぞというときにしか使わない。
3回目に現れる第2主題は1回目と同じ変ホ長調。
しかし今度は左手分散和音にのる疾走感を伴って。
ここで次の右手5連符音型
譜例4
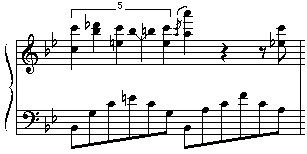
に注目したい。
これは右手上声部がハ音回りのモルデントで右手下声部が属和音のトレモロという二つを重ねただけのことだが、
そのために一つの符尾から二つの符頭を出すという特異な記譜が避けられなくなった。
この音型はノクターン第8番やバラード第2番にも現れる。
ショパン以前にこの双頭の記譜の例はあまり見たことがない。
最後に絢爛たるコーダが待っている。
スケルツォ第1番のコーダも迫力があるが、
このバラードのコーダは一層ドラマ的である。
特に最後、
激しいまま走り切って終わるのでなく、
静けさと激情が交代して終わる。
これはショパンの他の曲にはあまり見られないリスト的ものものしさである。
最後のオクターブ半音階の出始めにもfffが使われている。
如何にショパンがバラードにドラマチックな表現を求めていたかがわかる。
- [102] 即興曲第4番 嬰ハ短調「幻想即興曲」作品66(遺作)
1855年フォンタナ出版。
フォンタナ出版の遺作で最も若い作品番号が付いている曲である。
「この曲は真っ先にみんなに知ってもらわなくては」と思ったのだろうか。
私事になるが、
私は中学に入ったとき高校生の弾くこの曲を聞いて感激し、
一時とりこになったことがある。
同じような思いをした人は多いかも知れないので、
ここでこの曲についてどちらかというと批判的なことを書くのが気が引ける。
しかしどの曲にもそれに特別な個人的思い出を持つ人はいるわけで、
それを気にしていてもはじまらない。
ここは自分の考えを正直に書くしかない。
ショパンがこの曲を出版しなかった理由について文献[1]や[4]に
「モシェレスの曲に似すぎたため」とか
文献[1]に「ある婦人に売ったのでさらに出版社に売るわけに行かなくなったため」とかいう憶測が紹介されているが、
私は基本的にショパン自身の選曲眼にかなわなかったためと思っている。
その主な理由はABAのAの部分、
つまり主部の部分の安易さにある。
伴奏の動きがワンパターンの繰り返しばかりという点は一見練習曲作品25の1やスケルツォ第2番の第65小節目からの部分と同じように見えるかも知れないが、
その実、
香り高さは全然違う。
また左手三連符と右手四連符の重なりに感心する向きもあるかも知れないが、
これは速く弾く場合はそう困難ではないのであって、
むしろここまで終始同じパターンが続くと食傷気味である。
そしてもっと決定的なのは右手の動き、
第7小節後半から第8小節にかけての16分音符は、
ベートーベン「月光」第3楽章第189小節目のカデンツァと同じである。
次の楽譜の上段が「幻想即興曲」下段が「月光」である。
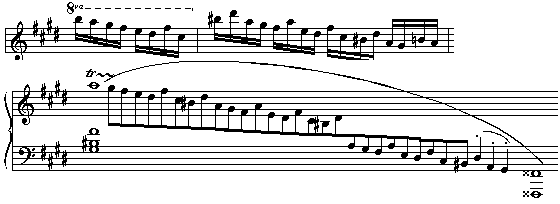
これではショパン自身の厳しい選別の目を通ることはできない。
ではA以外はどうかというと、
中間部Bとコーダが素晴らしい。
特に中間部の旋律は「雨だれ」前奏曲のようだ。
しかしこの中間部も自体もababa形式で、
2回半もabを変奏もなく繰り返している。
Kullak版などはabaに省略するよう勧めている。
中低音で激しく始まるコーダはショパンらしいものだが、
これは動機をうまく活かした迫力あるコーダである。
激しさがおさまると中間部の旋律が低音部に回想され、
静かに曲を終わる。
Aの部分をもっと推敲して自ら出版してくれたらよかったのにとも思うが、
25才のショパンは次々と溢れ出る才能を楽譜にとどめるのに忙しかったのだろう。
結局そういう時間はなかったようである。
ショパンの意に反してショパンの虚像を形作っている名曲といえよう。
- [103] ノクターン第7番 嬰ハ短調 作品27-1
1836年出版。
作品27の二つのノクターンはテレーズ・ダボニー伯爵夫人(オーストリア駐仏公使夫人)に献呈。
この曲とこれに続く作品27の2曲はノクターンの中でも至高の作品となっている。
これまでミ→♭ミ→レの旋律の特異性に触れてきたことがあったが、
この曲では逆に♭ミ→ミ→ファの旋律が特徴的である。
分析すると何のことはない、
短調主和音→長調主和音(=下属調属和音)→下属調主短和音という何の変哲もない和声推移なのに、
旋律から遠く離れた左手低音部の空虚5度伴奏の効果も手伝って、
不思議な雰囲気を醸し出している。
そしてすぐ続くナポリ6。
そしてやっと存分に嬰ハ短調で奏される下降旋律。
ショパンはときどき激昂する中間部を持つノクターンを書いているが、
fffが現れるこのノクターンの中間部の激しさは並ではない。
そしてまた静かな嬰ハ短調に戻り、
最後は光差す嬰ハ長調で終わる。
この作品27の嬰ハ短調と次の変二長調のノクターンのペアとフォーレのノクターン第6番変二長調と第7番嬰ハ短調のペアの調の一致は(順は逆だが)偶然なのだろうか?
- [104] ノクターン第8番 変ニ長調 作品27-2
1836年出版。
作品27の二つのノクターンはテレーズ・ダボニー伯爵夫人(オーストリア駐仏公使夫人)に献呈。
これをノクターンの最高位に位置させる人は少なくないだろう。
ゆっくりしたテンポで3小節もの長きに渡って続く変二長調主和音分散和音に乗る主旋律。
「タイスの瞑想曲」はこの旋律の影響を受けてはいないだろうか。
その後心を揺らす変ロ短調から変ホ短調へ移る副次句。
例のモルデント+属和音トレモロによる双頭符頭の音型(バラード第1番参照)が見られる。
前曲の嬰ハ短調ノクターンが多少哲学的で途中現実世界に引き戻され激昂するところもあったのに対し、
この曲は終始優しさに包まれている。
(しかし再現部はfffと書かれている。
これは少々やりすぎか。
そもそもこの年のショパンの作品には頻繁にfffが現れる。)
それにしても装飾音の宝庫。
和声の絶妙。
旋律美の極致。
そして最後の終止、
スティーヴ・ライヒも顔負けの6連符と7連符の重なり(しかも遅い速度!)。
これは天上へいざなうクリスタルの階段である。
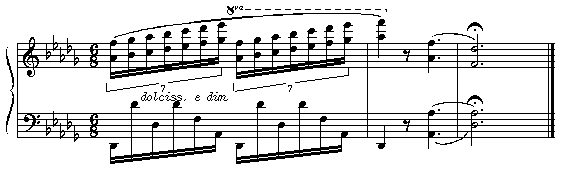
- [105] ポロネーズ第1番 嬰ハ短調 作品26-1
作品26の二つのポロネーズは1836年に出版された。
プラハの作曲家ヨーゼフ・デッサウアーに献呈。
ショパンが番号入りのポロネーズを出版し始めた。
力のこもった序奏で始まる。
その第3小節目両手十本の指全部を使う減七の和音にはfffが付いている。
「イベリア」ではppppとかfffffが出て来るし「悲愴交響曲」ではppppppが出てくるが、
大体において強弱記号はppからffまでで事足りるのであって、
「fよりは強く」か「思いっきり強く」かは解釈に任されるのが普通である。
主部の副次的パッセージ(第25小節〜)は少年期のポロネーズ嬰ト短調を想起させる。
中間部の甘美な変二長調はショパンの十八番である。
次に現れる中音域和音連打を挟む低音と高音の旋律の重なり(第66小節)は練習曲作品25-7(俗称「恋の二重唱」)と感じがよく似ている。
- [106] ポロネーズ第2番 変ホ短調 作品26-2
作品26の二つのポロネーズは1836年に出版された。
プラハの作曲家ヨーゼフ・デッサウアーに献呈。
変ホ短調らしい、
いわくありげな不気味なイントロで始まる。
何か事件が起きそうな前ぶれが徐々に高ぶって行き、
遂に爆発して主題提示される。
またしてもfffだ。
ロ長調の中間部は悲劇的変ホ短調をからかうような諧謔味があり、
対照を際立たせている。
変わり目に奏される変ハ−ニの長六度の下降音型(第45、149、172-173小節)は大変ベートーベン的。
- [107] マズルカ第14番 ト短調 作品24-1
作品24の4つのマズルカは1836年に出版された。
ルイ・フィリップス・ベルティユイ伯爵に献呈
主部はゆっくりしたクヤヴィヤク。
ドミナントから始まるショパン得意の主題は多少バラード第1番の主題を思わせる。
それは第57小節で一層似てくる。
この曲の特徴は音階的旋律において現れる増二度の音程(第3小節や第6小節)で、
これがジプシー音階的に聞こえる。
この主題に対し第17小節からの変ロ長調の楽句はすがすがしく対照的。
ここは指示はないが主題より少し速めに軽やかに弾くべきだろう。
変ホ長調の中間部は三度の重音で奏されるマズル。
- [108] マズルカ第15番 ハ長調 作品24-2
作品24の4つのマズルカは1836年に出版された。
ルイ・フィリップス・ベルティユイ伯爵に献呈
ときどきリディア旋法を使っているショパンの作品の中でも、
最も強烈なリディア旋律の使い方が現れるので、
ショパンの変わった作品ということで必ず指摘される。
主部はオベレク。
イ短調主和音で始まる点が特徴的なハ長調主題。
ヘ長調のクヤヴィヤクに変わるところに問題の箇所がある(第27、35小節)。
ここでは明かなヘ長調旋律にナチュラルBが現れる。
♭の付け忘れでないことを示すため、
必要のないナチュラルの本位記号をショパンはわざわざ付けている。
そしてABA'のこの曲のAとA'の部分はイ短調やヘ長調への転調を含むにもかかわらず臨時記号が全くない白鍵だけという、
ショパンとしては特異な音楽になっている。
これに対しBはショパンらしい黒鍵系の転調の多い旋律になっている。
もう一つ、
4小節の導入と16小節の後奏はこの上なく単純な和声で、
ここだけ取り出すと一見子供か素人が書いた稚拙な音型のように見える。
それがショパンの手にかかると・・・不思議としかいいようがない。
- [109] マズルカ第16番 変イ長調 作品24-3
作品24の4つのマズルカは1836年に出版された。
ルイ・フィリップス・ベルティユイ伯爵に献呈
またまた変イ長調のしつこいつぶやきである。
隣り合う音程を行き来するかと思うと急に飛躍する音型。
中間部も両手とも狭い音程を動くつぶやき。
最後はワルツ第4番(子猫のワルツ)のような音型で消え入るようなアッチェレランドで終わる。
この曲は次の変ロ短調の傑作マズルカへの伏線のようである。
- [110] マズルカ第17番 変ロ短調 作品24-4
作品24の4つのマズルカは1836年に出版された。
ルイ・フィリップス・ベルティユイ伯爵に献呈
内容豊富な傑作マズルカ。
これはインターナショナライズされたマズルカで、
クヤヴィヤクだマズルだという分析はあまり意味がない。
1オクターブ離れた二音から、
上から半音下降、
下から半音上昇させて近づけていく遊びは誰でもやったことがあるのではないだろうか。
それがショパンの手にかかるとこの曲のような魔法のイントロに変身してしまう。
このイントロは2声に聞こえるように弾かなければならない。
その単純音型をそのまま引きずった主題のグラマーなこと。
中間部の不思議なユニゾン(第53小節)。
いかにも「そろそろ終わりに向かいますよ」といわんばかりのコーダ(第115小節から)。
こんなコーダが書けるのもショパンならではである。
少し古い話だがNHK-FM毎朝の「大作曲家の時間」ショパンのシリーズでテーマ音楽だった。
企画者の選曲センスに脱帽。
- [111] マズルカ第44番(ヘンレ版第42番)ト長調 作品67-1 (遺作)
第45番(ヘンレ版第43番)ト短調 作品67-2[240] 、
第46番(ヘンレ版第44番)ハ長調 作品67-3[113] 、
第47番(ヘンレ版第45番)イ短調 作品67-4[229]
を含む作品67の4曲は死後1855年フォンタナ出版。
このト長調マズルカは一般には献呈なしとされているが、
文献[1]には「正式ではないがアンナ・ムオコシエヴィチ嬢に贈られた」とある。
オベレク風音型の主題だが、
元気のある重厚さはマズル的。
一般受けする名曲とは言えないかも知れないが、
ショパン自身が生前に出版していたとしてもおかしくない曲。
- [112] マズルカ第46番(ヘンレ版第44番)ハ長調 作品67-3(遺作)
第44番(ヘンレ版第42番)ト長調 作品67-1[112] 、
第45番(ヘンレ版第43番)ト短調 作品67-2[240] 、
第47番(ヘンレ版第45番)イ短調 作品67-4[229]
を含む作品67の4曲は死後1855年出版。
このハ長調マズルカは一般には献呈なしとされているが、
文献[1]には「正式ではないがアデリーナ・ホフマン夫人に贈られた」とある。
リズムや音型が67-4のイ短調マズルカによく似ている。
その意味で長調のクヤヴィヤクと考えられる。
遅いワルツとも聞こえる。
これもショパンの他のマズルカより劣るわけではないので、
生前に出版していてもよかったと思われる。
バレエ音楽「レ・シルフィード」に編曲されている一曲。
- [113] ワルツ第2番 変イ長調「華麗なる大円舞曲」作品34-1
1838年出版。ジョセフィーヌ・ドゥ・トゥン=ホーエンシュタイン伯爵令嬢に献呈。
社交的華やかさではワルツ第1番に匹敵し、
「華麗なる大円舞曲」の表題がぴったりのワルツだが、
内容は第1番よりずっと濃い。
華々しい序奏に続き六度の歌謡的主題が奏される。
この主題はワルツ15番(遺作)の主題に似ており、
それ自身魅力的だが、
このワルツの他の部分があまりにも素晴らしいのでこの主題はその前座のようになってしまっている。
続くパッセージ
譜例1
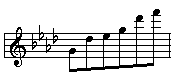
はショパンの好きな音型である。
この音型はワルツ第5番や第12番にも使われている。
第2主題は雄大で4分の6拍子にも聞こえる。
コーダがまた素晴らしい。
ここではバラード第1番で指摘したチャイコフスキー的和声
譜例2:左手に着目
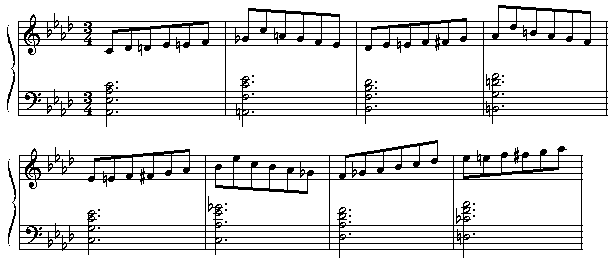
が使われている。
これに低音E♭を常に鳴らせばバラード第1番の譜例3と同種の和声である。
これは練習曲作品25の1「エオリアン・ハープ」で完全な姿を現す。
- [114] ワルツ第9番 変イ長調 作品69-1(遺作)
1853出版。マリア・ヴォジンスカとの別れに際し作られ「別れのワルツ」として有名。
力無く半目を開き後ろ髪を引かれているような旋律がヘ短調っぽく始まるが、
6小節目あたりから変イ長調色が強まり、
8小節目でやっと確立される。
この変イ長調の確立も決然としたものではなく、
マリアに対するショパンの心残りが感じられる諦めの主和音である。
大変いい曲と思うが、
ショパン自身は出版しなかった。
やはりワルツ第13番と同じく私的思い出の詰まった曲なのだろうか。
それにしてもこの曲、
半音下降のところがショパンの絶筆となったマズルカ第51番(ヘンレ版49番)ヘ短調に雰囲気が似ている。
そういえば死ぬ二年ほど前のチェロソナタト短調は青年期のピアノ三重奏曲ト短調に似ている。
後年、
肺病が進行していたショパン最後の年はもう死を予感していたらしいが、
そういうとき人間は原点に帰るのだろうか?
次は1836年(26才) ♪
前は1834年(24才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る