ショパン全作品を斬る
1836年(26才)
次は1837年(27才) ♪
前は1835年(25才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る
- [116] 練習曲 変イ長調 作品25-1
作品25の12の練習曲集は1832から作曲され始め、
1837年に出版、
リストの恋人マリー・ダグー伯夫人に献呈された。
この25-1は通称「エオリアン・ハープ」または「牧童」とも呼ばれる。
この年は一昨年前に似て、
ごく短い曲ばかり4曲しか作っていない。
その理由は何か?
前の1835年には両親とボヘミアの温泉地で再会逗留、
マリア・ヴォジンスカとの恋の始まりがあり、
この1836年にはマリアの家族との楽しいボヘミア逗留、
マリアとの婚約成立、
そして婚約の破談、
新たにジョルジュ・サンドとの交際の始まりなど、
プライベートに悲喜こもごもの事件がいろいろあった。
この年からショパンの音楽は一段と高みを極めているように思える。
筆者の分類では (1) 作品1路線のワルシャワ時代+パリ移住直後、
(2) それを卒業しノクターン、
練習曲作品10、
スケルツォ第1番、
バラード第1番など豪華絢爛な作品を発表して行ったワルシャワ出発直前からパリ時代の初期、
(3) ショパンの代表作というべき主要作品を次々と発表したジョルジュ・サンドとの蜜月時代、
それに (4) 音楽に深みが増し円熟の境地に達した1842年以降と分類される。
この年から (3) が始まると考えられるのである。
ショパンの悲喜こもごもの人生経験が (3) の時代へショパンを開かせたのではないかという気がしてならない。
(2) と (3) の時代の差は練習曲集作品10と25の違いに端的に現れていると思う。
すなわち若さいっぱいの瑞々しい作品10に対する詩的情緒に溢れる作品25である。
特にこの変イ長調練習曲はシューマンが
「むしろ詩である」
と言った通り、
聞く者に至福のひとときを与えてくれる。
さてコーダの手前、
例の第5音に乗る半音上昇の和声が現れる:
譜例1
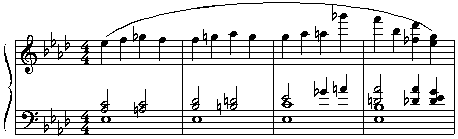
これとチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番第1楽章カデンツァ手前の和声を比べてみよう:
譜例2
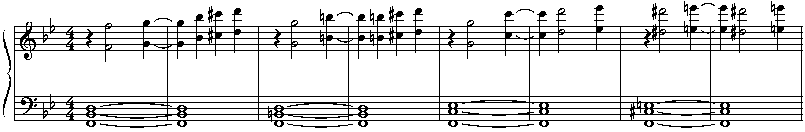
さらにこれは次へ続く:
譜例3
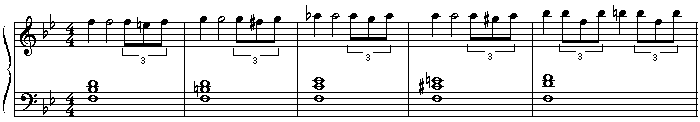
シベリウスはフィンランドがロシアから解放されることを願って「フィンランディア」を作曲した(1899年)が、
チャイコフスキー的和声を使っている:
譜例4
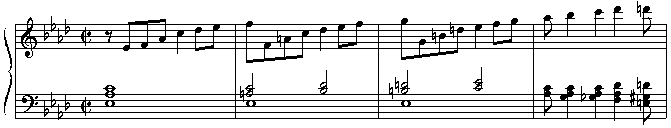
他にも同様な和声の例はあると思われるが、
これらはみなショパンの和声に端を発している。
- [117] 練習曲 ヘ短調 作品25-2
作品25の12の練習曲集は1832から作曲され始め、
1837年に出版、
リストの恋人マリー・ダグー伯夫人に献呈された。
比較的狭い音域内を動くが、
トリルのような繊細さや音階の美しさが魅力的なエチュード。
右手が4分の4で左手が2分の2という複リズムが演奏を難しくしている。
この複リズムはワルツ第5番のテーマ
譜例1
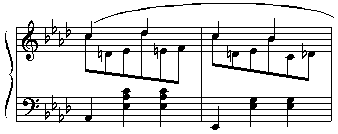
と同じである。
このワルツはそのまま弾けば自然に複リズムが達成されるが、
エチュードOp.25-2の方はつい次のような両手2分の2拍子に陥りがちである(これならそう難しくない)。
譜例2
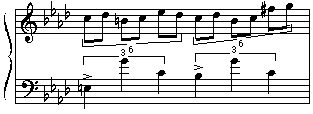
もちろんこれは避けなければならない。
ショパンが書いた通りに弾こうと思うと、
たとえば次のようなアクセントを付けた練習は効果的である:
譜例3
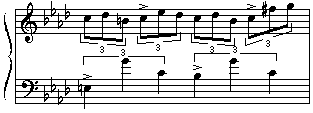
しかしこの練習はクセが残りやすいので気を付けなければならない。
次の3つの変形リズム練習はクセが残らず、
両手の分離に大変効果的である。
譜例4
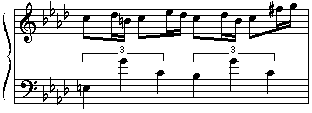
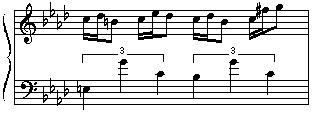
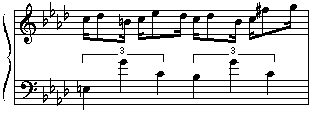
- [118] 歌曲「舞い落ちる木の葉」変ホ短調 作品74-17(遺作)
ポル詩。1859年フォンタナ出版。
ある外国歌曲を初めて聴くとき、
私は歌詞の中身を確かめる前にまず音楽から聴いてしまうことが多い。
この曲を初めて聴いたときもそうだった。
しかし歌詞は意味不明ながらもこの曲の雰囲気には尋常でないものを感じ、
すぐにショパンの歌曲の中でも最高傑作だと思った。
そして歌詞を見てそのことに納得が行った。
これは1830年のワルシャワ陥落を歌った「墓前の歌」だったのだ。
同じくワルシャワ陥落が動機となった「革命のエチュード」「前奏曲ニ短調」「スケルツォ第1番」の激情とは異なり、
この曲も[64] 歌曲「悲しみの川」と同様に深い、静かな悲しみを歌う。
主題のすばらしさはもとより、
途中E♭音だけで戦後の空しさを終始弱音で延々と歌いピアノが和声で縁取る箇所は感動的である。
お経か声明のようにも聞こえる。
混声合唱によるユニゾンで歌っても大変効果的な曲と思われる。
フォルテに盛り上がることはないが、
有節歌曲でなくバラードのように変化して行く物語性がある。
歌曲の場合、
歌手の声域に合わせて転調されることが多いので何調かは普通あまり意味がないのだが、
個人的にはこの曲は原調の変ホ短調で歌って欲しいものだ。
- [119] 歌曲「指輪」変ホ長調 作品74-14(遺作)
ヴィトフィツキ詩。1859年フォンタナ出版。
「僕が君に指輪を贈ったとき一生はずさないと約束したね。
それなのに君は今別の人と一緒になってしまった」
速めのクヤヴィヤクに乗る長調の旋律で悲しい心を歌う。
長調の旋律だが、
もし伴奏をハ短調にしても合うような旋律で、
決して明るくはない。
まるでマリア・ヴォジンスカのことを歌っているようだ。
モーツァルトは境遇と音楽の気分がおおかた無関係だったが、
ショパンはベートーベンと同様、
そのときの境遇がかなり作曲に反映されている。
そしてその傾向は歌曲に著しい。
次は1837年(27才) ♪
前は1835年(25才) ♪
目次 ♪
音楽の間に戻る ♪
詠里庵ホームに戻る