下のアニメーションは,雨滴球に入射した光波の波面がどのようなものになるかをイメージするために,2次元の円形媒質に平面波が入射したとして単純化・模式化して示したものです。
主虹の場合を想定し,屈折率 n=1.331 (ほぼ赤色の光) に設定してありますが,雨滴の大きさに対して光の波長はきわめて小さいため,両者の大きさの関係は適当に設定しています。
雨滴球の上半分に入射する波面のみを 50 波面,もしくは波面の形を知るために1波面のみを描画できるようにしてあります。
先頭の波面が雨滴球外に出たところで動きが一旦止まりますが,「続行」ボタンでさらに継続できます。
「波面の進行方向」と「その延長線」の両方にチェックを入れると,赤い破線が表示されますが,雨滴球外に出た光線は,これらの互いに隣接する延長線の交点の位置から射出されたように進むことになります。
青い太線で示した光線は,主虹ができるときの散乱角を与える光線です(デカルト光と呼びます)。このデカルト光線の方向に最も高密度で光線が集中して射出され,その延長方向にその色の主虹が見えることになります。デカルト光の散乱角は「解説3:散乱角の詳細」の項で求めた (i) 式 θmax で与えられ, n=1.331 の場合,度(°)に換算しておよそ 42.37° となります。
赤い細線は,雨滴の上端に入射する光線の進行方向を表します。
図の左上方に示した赤と青の縦線が波面を表し,青部分はデカルト光線より下方に,赤部分はデカルト光線より上方に入射する波面部分を表します。
スタートボタンを押してみてください。
雨滴球内部に入射するまでは光波面は平面ですが,波面が雨滴内に侵入後,青太線と赤細線がクロスするところ(雨滴内部で反射する少し手前あたり)から赤波面の先端がデカルト光線の内側に折れ始めます。波面がさらに進んで完全に雨滴から出た後さらに少し進むと,赤波面はデカルト光に対して完全に折り返された状態となり,青波面と赤波面が傾いた状態で重なり合うようになります。
傾きの異なる波面同士が重なり合うことが,過剰虹ができる原因なのです。
もう少し詳しく見てみましょう。
◎過剰虹の成因:
先のアニメーションにおいて,波面数を「1波面」に選んでみてください。下図のような折れ曲がった波面が確認できると思います。
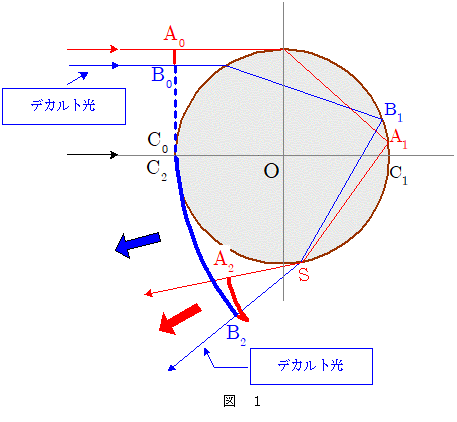
上図(図1)は,波面 A0B0C0 が雨滴上半分に入射した後,この波面全体が雨滴の下半分から完全に出てきた瞬間の様子を示します。
また下図は,先のアニメーションを利用して,入射光線の数を増やして描画したものです。
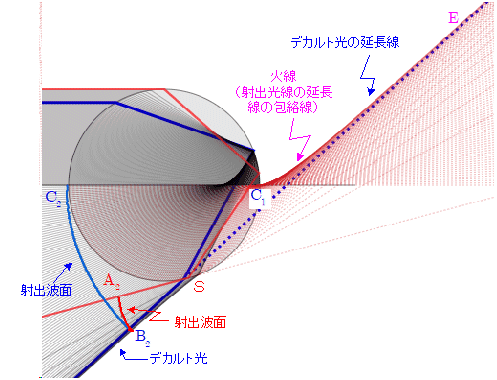
青で示した波面を形成する光線については,これらの光線の延長線がデカルト光の延長線の方向に漸近・密集している様子が分かります(火線=光束を構成する光線(またはその延長線)によってつくられる光線群の包絡線)。これは,デカルト光の方向もしくはその近傍の方向には多くの光線が重なって射出されていて拡散が見られない,つまりそれだけこの方向の光強度が遠方まで保たれる…ということを意味します。
一方,赤で示した波面を形成する光線は上図のほぼ点S付近で交わっており,見かけ上あたかも点S付近から射出されたかのように進むことになります。しかしこれらの光線の進行方向はかなりばらけており,光がS点付近から広く拡散していくことが読み取れます(ばらけ方は延長線(赤の破線)の方を見ると分かりやすい)。しかもそのばらけ方は,デカルト光の方向から離れるほど大きくなっており,拡散傾向が著しくなっています。拡散範囲が広いほど光エネルギー密度は減少しますので,赤い波面は,デカルト光から離れるほど急速に減衰していることを意味します。
以上より,デカルト光の方向に強い光が射出され,その光はその延長方向からやってくるように見える。これが主虹というわけです。
先に,雨滴による散乱角の計算から,散乱角が極値をとる方向としてデカルト光の方向を求めましたが(解説3:散乱角の詳細),光線の進行方向のシミュレーションからもその確認がとれたことになると思います。
では,過剰虹はどのようにしてできるのでしょうか。
その成因の定性的な説明としては,おおよそ以下のようになります。
上述したように,雨滴から出てきた波面は青部分と赤部分とが折れて重なりますが,その波面の傾きがわずかにずれており,要するに傾きの異なる2重波面として波面全体が広がっていくことになります。2重波面では必ず干渉が起こり,青の波面と赤の波面の山と山,または谷と谷が重なり合うことによって強め合ったり,逆に山と谷が重なって弱め合ったりします。
図2は,そのイメージ図です。灰色線 L1 ,L2 ,L3 ,…で示したところが山・山(または谷・谷)の重なるところで,強め合った光波の通り道になります。(赤波面はデカルト光線から離れるにつれ急速に減衰します。このため,強め合うと言っても,デカルト光線の位置における光強度に比べるとかなり弱くなります。)
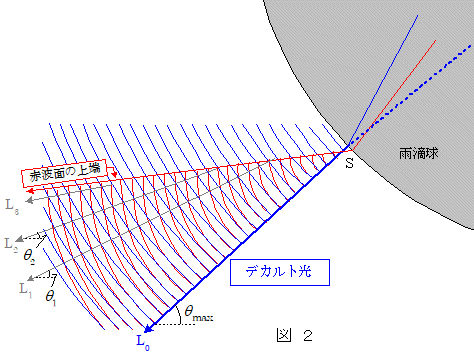
デカルト光の方向( L0 の方向)には青波面も赤波面も垂直になっており,両者の位相が揃っています。そのためこの方向には2つの波は最も強め合います(詳しい計算では,少しずれがあります。次ページ以降で説明します)。つまりこの方向に最も強い光が射出されます。これが『主虹』として見えることになります。
一方, L1 ,L2 ,L3 ,… の方向にもやや強い光が射出されることになり,その延長方向にその波長の色の虹が見えることになります。これが『過剰虹』として見えるのです。
デカルト光の方向に『主虹』,波面の山・山(または谷・谷)が重なる方向に『過剰虹』が見える
図より明らかなように,θmax > θ1 > θ2 > … の関係があり,過剰虹は主虹より低い高度に現れます。
過剰虹の成因に関する定性的な概略はおよそ上記のようになります。
しかし,過剰虹の方向・角度などを定量的に解析しようとすると,話はがぜん難しくなります。
次項以降で,これを説明します。
解説8(波面の式)
虹の話
概要
解説1(解説1:雨滴による虹散乱)
解説2(虹の色と散乱角)
解説3(散乱角の詳細計算)
解説4(反射率)
解説5(虹散乱での反射率)
*** 以下,過剰虹 関連 ***
解説6(波動光学)
解説7(過剰虹成因の概要)
解説8(波面の式)
解説9(虹の光強度の式)
解説10(波動光学による虹)