|
|
|
|
![]()
ダイベン大統領。 佐久間學
ただ、今回は、その「序曲集」というタイトルの後に「オリジナル・バージョン」という但し書きもついています。これに関しては、普段聴かれるものには例えば金管楽器やティンパニが追加されるなどの改訂が施されているのですが、ここではそのようなものをそぎ取った最初の形であるシンプルな編成で演奏されているという意味なのでしょう。さらに、弦楽器も1パート1人という、とてもコンパクトなメンバーです。 なんと言っても、この4曲の中で最も親しみがあるのはフルートのソロがフィーチャーされている「2番」です。以前、この曲の元の形ではソロ楽器はフルートではなくヴァイオリンだった、とか、さらには、オーボエの可能性もあるといったような提案のもとに作られたCDもありましたが、今回は普通のフルート版が「オリジナル」という見解のようですね。 今回のフルート・ソロは、数多くのピリオド・アンサンブルに参加しているイギリスのトラヴェルソ奏者、ケイティ・バーチャーです。2007年にはトレヴァー・ピノック指揮のハノーヴァー・バンドとともにワールド・ツアーに参加していたといいますから、かなり長いキャリアを誇っていますが、まだばあちゃんではありません。なんでも、彼女は9歳の時からフルートを始めたのだそうですが、そのころはもちろんモダン・フルートを吹いていて、アイドルはジェイムズ・ゴールウェイだったのだそうです。ただ、オクスフォード大学を卒業すると、彼女の関心はバロック・フルート(フラウト・トラヴェルソ)に向かい、それからはひたすらこの楽器の修練に励むことになるのです。 彼女のソロでこの曲を聴くのは初めてですが、それはちょっとした驚きでした。これまで聴いてきたトラヴェルソとは、全く次元の異なる演奏なんですよ。何よりもピッチが正確、そして、アンサンブルのセンスがとても素晴らしくて、ヴァイオリンとのユニゾンになっている箇所では、本当にぴったりと、それぞれのセンスまで含めて合っているのです。それと、息がとても長く持つのにも驚きました。最初の「序曲」で出てくるとても長いソロの部分で、全くブレスを取らずに演奏しています。繰り返しの部分では、必ず装飾を加えている、というのも、なんか得をしたな、という気にさせられます。 「ポロネーズ」では、かつてはテーマをそれこそフランス風に複付点音符で演奏することが流行っていたことがありましたが、彼女は普通の付点音符で演奏しています。これまでに様々なやり方が提案されてきましたが、どうやら、これが現時点での着地点と考えていいのではないでしょうか。ここを複付点にしてしまうと、中間の「ドウーブル」の部分とのリズムの整合性が保たれなくなりますからね。 その次の「メヌエット」では、とても軽やかなテンポ、なんだか、初めてメヌエットらしいテンポで演奏しているのを聴いたような気がしました。 その次に有名なのが「3番」ですね。いつも派手に鳴っているトランペットとティンパニがないとちょっと物足りない気はしますが、この弦楽器だけという編成もとても新鮮ですね(こういうのがあるので、最近は「管弦楽組曲」とは呼ばれないのでしょう)。お目当ての「アリア」でも、メロディはソロになりますから、いともあっさりとした仕上がりです。 「1番」と「4番」では、オーボエが入っています。普通はオーボエの方がトラヴェルソよりもちゃんとしたピッチで演奏できるようなのですが、ここでは逆になってましたね。でも、例えば「1番」の「ブーレ」にある、オーボエ2本とファゴットのアンサンブルでは大いに楽しませてもらえました。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |
||||||
その1年後、2020年8月9日に、エディンバラ音楽祭の一環としてトマス・セナゴーの指揮によるロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団によって演奏されたもののライブ録音が、このCDです。その時の映像も、YouTubeで全曲見ることができます。しっかり間隔をとって演奏していますね。 ジモンという人は、シェーンベルクが主催していた「私的演奏協会」のような少人数のアンサンブルによるスタイルで、マーラーの交響曲の編曲を行って来ていて、これまでに1番、4番、5番、6番、9番、そして「子どもの不思議な角笛」を完成させています。 この7番の場合は、楽器はフルート(ピッコロ持ち替え)1本、オーボエ(コール・アングレ持ち替え)1本、クラリネット2本、ファゴット2本、ホルン2本(2番はワーグナー・チューバ持ち替え)、トランペット1本と、打楽器奏者2人、ハープ、ピアノ、ハルモニウムがそれぞれ1台に、弦楽5部という編成です。弦楽器は人数の指定はありませんが、初演の場合(指揮はレオ・マクフォール)は4.2.2.2.1、今回のセナゴーの場合は少し増やして6.5.4.3.2となっています。 ですから、この曲で使われている特殊な楽器は、別の楽器に置き換えられています。第1楽章のテナーホルンはワーグナー・チューバ、第4楽章のギターはヴァイオリンのピチカートで演奏されています。ところが、もう一つ、同じ楽章に出てくるマンドリンは、本物のマンドリンのような音が聴こえて来るのですね。この楽器特有のトレモロもきちんと演奏されています。最初は、ヴァイオリンをピックで演奏しているのかな? と思ったのですが、そんなことはできるのでしょうか。 しかし、調べてみると、この件に関するジモンのコメントが見つかりました。なんと、それは「プリペアド・ピアノ」だというのです。カードではありません(それは「プリペイド」)。そのコメントを元に、先ほどのYouTubeでその「マンドリン」が出てくるところをチェックしてみたら、見事に「プリペア」の様子が分かるカットが見つかりました。  逆に、そのピアノとハルモニウムは、オリジナルのスコアには含まれていない楽器です。ですから、それらの楽器が登場すると、途端にサウンドが安っぽくなってしまいます。特に、せっかく打楽器奏者が2人もいるのに、ティンパニは用意されておらず、それをピアノが代わって演奏しているのですが、第5楽章の頭などはもう情けないのなんのって。あと、ハルモニウムは欠けている金管の補助をやっていますが、これもしょぼいこと。 まあ、でも、そのあたりをそれほど気にしなければ、これはなかなか楽しめる編曲です。先ほどのマンドリンも、普通のオーケストラではまず聴こえてきませんが、ここではもろ主役になってますからね。 CD Artwork © Linn Records |
||||||
そのような時流に達郎も従うべく、1986年に制作された「POCKET MUSIC」というアルバムで、初めてLPと一緒にCDでのリリースも行います。これが、達郎にとっての初めてのCDとなります。この時は、LPは4月23日に発売されましたが、CDは少し遅れて5月10日の発売でした。そして、次の「ON THE STREET CORNWE 2」で、1986年12月10日にLPとCDが同時に発売されるようになりました。 そのあと何枚かは、LPとCDとの同時発売が行われるのですが、ついに1991年リリースのこの「ARTISAN(アルチザン)」というアルバムでは、LPでのリリースは行われなくなっていました。まさに時代の流れ、もはやアナログ・レコードは完全に過去のものになってしまった、という判断が、この頃の音楽業界では当然のことだったのです。 ただ、21世紀に入ると、実はCDの音はLPのアナログ録音よりもおとる、という真実が明らかになってくるのです。そこで、録音現場ではそれまで行われていたCDのフォーマット(16bit/44.1kHz)のデジタル録音よりもよりアナログ録音に近づけるために、24bit/96kHzといった、より解像度の高い「ハイレゾ録音」が行われるようになりました。 それに伴って、LP自体も見直されることになって、達郎のアルバムでCDのみのリリースだったものも順次LPがリリースされるようになったのです。しかし、今回の「ARTISAN」だけは、そのような恩恵を受けることがなく、オリジナルアルバムがリリースされて30年経った2021年に、初めてLPが登場することになりました。 今回のLPは、いつものように本来は1枚に入る物をわざわざ2枚組にして音の良い外周だけにカッティングされています。さらに、クラシック音楽の場合では、どうしても小さな音のところでサーフェス・ノイズが聴こえて邪魔になるものですが、達郎の音楽のように、基本的にリズムセクションが常に大きな音で演奏されているものは、そのようなノイズが全く聴こえなくなりますから、純粋に聴こえてくる音の良しあしが感じられることになります。 このアルバムは、CDでも全曲を聴いたことはありませんでした。とりあえず、以前のベスト盤に入っていた曲が「アトムの子」、「さよなら夏の日」、「ターナーの汽罐車」、「Endless Game」と4曲もあるので、それらをまず比較してみましょう。 まず、これらに共通するのは、LPにおける低音の充実さです。腹の底に響く、といった感じの低音が、CDではちょっとおとなしめになっています。それと、このアルバムではほとんどが生楽器ではなく電子楽器や音源モジュールが使われていますが、それはCDではまさに「電子音」という感じで迫ってくるものが、LPではしっかり角が取れて人の耳に優しいものに変わっています。特に「アトムの子」では、打ち込みで作ったジャングル・ビートをバックに生のパーカッション(浜口茂外也)が大活躍しているのですが、それがLPではバックと乖離せず、しっかり馴染んでいます。CDではちょっと目立ちすぎてやかましい、というか。 そのような、シングルカットされていない曲で、今回初めて聴いた曲では、カバー曲である「Tokyo's A Lonely Town」が、サーフィン・ソングならではの達郎自身のコーラスがとてもカッコよく、気に入りました。 それと、竹内まりやが詞を書いた「Mighty Smile(魔法の微笑み)」も、シャッフル・ビートがポップで素敵でした。  LP Artwork © Warner Music Japan Inc. |
||||||
具体的には、フルートが1本だけの無伴奏の作品と、それにピアノ伴奏が付いたものは合わせて33曲です。フルート2本だけの作品は18曲、それにピアノが入ったものは1曲です。フルート3本では7曲、フルート4本の曲は、「グランド・カルテット」と呼ばれているOp.103しかありません。それ以外に、Op.51の中に、フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ2挺、チェロという編成の曲が3曲あります。ですから全部では63曲になるのでしょうか。 今回のCDでは、その中のフルート3本で演奏される「フルート・トリオ」が取り上げられています。これは、Op.13が3曲、Op.86が3曲、そして、Op.90が1曲ですから、合計で7曲ということになりますね。おそらく、今の時点でその全曲が収録されているアルバムはこれしかないはずです。かなり貴重ですね。 そんなレアなレパートリーを演奏しているのは、「フルート・イースト・トリオ」という名前のアンサンブルです。その名の通り、「東洋」系のフルーティストが3人、いい人ばかり集まっています。内訳はジャケ写の左から台湾人のシュ・ユーチュン、韓国人のソン・ソジョンとパク・ハナです。いずれも女性、とても若くて美人です。  しかし、2019年6月には「ファイナル・コンサート」を開催して、トリオとしての活動に終止符を打ったようですね。現在は、シュ・ユーチュンは台湾の長榮交響樂團、ソン・ソジョンはベルリンのノイエ・フィルハーモニー、パク・ハナはロストックにある北ドイツフィルハーモニーと、それぞれにオーケストラの首席奏者として活躍しているそうです。そんな「青春」の置き土産として作られたのが、2019年3月に録音されたこのCDです。 フルートだけのアンサンブルの場合、2人ではいかにもシンプルすぎますし、かといって4人まで同じ楽器で増やすと、それほど音域の幅が広い楽器ではないので、ちょっと窮屈なアレンジになってしまいます。今回はたまたま3人が集まったのでトリオになったのかもしれませんが、ここでこの3人の演奏を聴いていると、クーラウの場合もやはりこの形態が最も音楽的に充実したものが作られたのだな、と強く感じられます。この3人は音色もよく似ていますし、それぞれにテクニックも抜群です。さらに歌わせ方もきちんと統一されていますから、アンサンブルとしては理想的なメンバーです。ですから、メインのパートは存分に歌い上げていますし、それに合の手を入れるほかのパートも、しっかりそれに寄り添うだけでなく、きちんと独立した声部としての存在感をはっきり示すことが出来ているのです。そんな美点があちこちから見えてくる、素晴らしい演奏です。 そんな中で、きちんとそれぞれの個性も感じることもできます。おそらく、曲によってパートを入れ替えているのでしょう。例えば、Op.13からOp.90になった時に、明らかに1番フルートのメンバーが変わったことが分かりました。曲ごとのメンバーをきちんと表示してもらえれば、もっと楽しめたかもしれませんね。 こういう演奏で聴けば、クーラウの作品はそれぞれに変化があって、続けて聴いても全く飽きることはないのだ、と思うことができます。 CD Artwork © Brilliant Classics |
||||||
それは、奇しくもモーツァルトが生まれてすぐの事でした。このヨンメッリの「レクイエム」は、「モーツァルト以前の、最もよく知られた『レクイエム』」と言われています。というか、モーツァルト自身もこの作品を知っていたとされています。それは、父親のレオポルドの生徒が、この作品の写筆稿を元に編曲を行っていたのだとか。 つまり、この作品は、出版される前に、多くの人によって写譜されて、ヨーロッパ中に広まっていたという、大ヒット曲だったのですね。その写譜の数は完全なものが130点は存在していることが分かっています。なんでも、カサノヴァやロッシーニの葬儀の時にも、この曲が演奏されたのだそうですね。 2020年には、CARUSから世界初のクリティカル・エディションが出版されています。 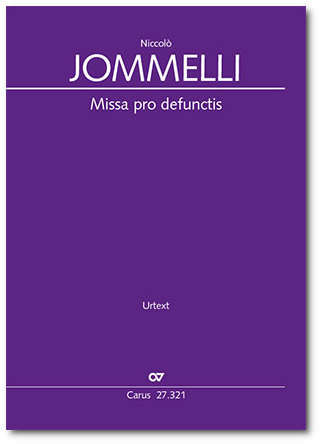  彼らが録音を行ったのは2019年の11月19日から22日までですが、その前の16日にアムステルダムのコンセルトヘボウでこの曲を演奏しています。そのコンサートでは、その後にモーツァルトの「レクイエム」が演奏されました。その時の写真がブックレットに載っていますが、なぜかそれはヨンメッリではなく、モーツァルトを演奏している場面になっています。 なぜそんなことが分かるかというと、このヨンメッリの曲は、オーケストラの編成がとても小さく、少人数の弦楽器とオルガンしかないからです。これは、こちらで全曲動画を見ることができます(モーツァルトはこちら)。 導入のグレゴリア聖歌が、この合唱団の男声メンバー(スコラ・グレゴリアーナ・ギスリエリ)だけで歌われた後、始まった「Introitus」は、とてもシンプルなたたずまいでした。そこで使われているのは、E♭→Cm→Fm7→B♭という200年後のポップス(ポール・アンカの「ダイアナ」とか)で多用されることになる循環コードでした。そのシンプルなメロディを、最初は合唱、続いてソリストたちが歌います。そこで聴こえてきたカウンター・テナーのカルロ・ヴィストーリの声には、思わず耳をそばだててしまいます。なんと滑らかで、伸びのある声なのでしょう。他のソリストたちが霞んでしまいます。 そんな風に、合唱とソリストたちが交代して登場するという形で、全体の音楽も進んでいきます。中には、「Benedictus」のように、ソプラノのソロだけで華麗に歌い上げるナンバーも混じっています。確かにこれは、当時の人気ぶりがとても納得できる、素敵な「レクイエム」でした。 CD Artwork © Outhere Music |
||||||
カウフマンは、今ではオペラ歌手として大活躍ですが、同時にリートもしっかり手がけていました。なんたって、2005年に録音されてHARMONIA MUNDIからリリースされた彼にとって最初のソロアルバムが、リヒャルト・シュトラウスのリート集でしたからね。そこでの伴奏を担当していたのが、ドイッチュです。それ以来、カウフマンは、リサイタルもレコーディングも、常にこのピアニストと一緒に行っているようです。なんでも、この二人はミュンヘン音楽大学時代の師弟同士で、30年来のお付き合いなのだそうです。 彼らはこれまでに何枚かリートのアルバムをリリースしていますが、シューベルトの「冬の旅」を録音した2013年以降はそのジャンルからは遠ざかっていました。 新しいリート・アルバムが作られたのは、皮肉にもこのコロナ禍のおかげでした。欧米諸国のロックダウンのため、オペラハウスは軒並み活動を停止せざるを得なくなった状況下で、リートの録音ならば、それこそ自宅でもできるということで制作されたのが、このアルバムだったのだそうです。実際に、レコーディングは2020年の4月にカウフマンの自宅で行われました。まさに「ステイホーム」の産物です。 そんな出自ですから、ここではとことん「有名な」曲が取り上げられています。全部で27曲収録されているこのアルバムは、さながら「アンコール集」とでも言えるような体裁になっていました。 とは言っても、やはり彼らならではのこだわりはあって、その中にレアな曲を加えるということで、一本芯の通ったものに仕上がっています。そもそもタイトルとなっている「Selige Stunde(至福の時)」というツェムリンスキーの作品などは、初めて聴きました。それと、「Karl Bohm」という作曲家の名前があったので、あのカール・ベームが作曲も行っていたのか、と思ったら、「Böhm」ではなく「Bohm」、「カール・ボーム」という人でした。 アルバムは、シューベルトの「Der Musensohn(ミューズの子)」から始まります。ドイッチュの軽やかな前奏に乗って歌われたカウフマンの声は、なんだかとても雑に感じられました。ピッチがかなりいい加減なんですね。この人、これまではピッチに関してはテノールにありがちなおおざっぱなところは皆無なのではないか、とさえ思っていたのですが、こうなるとごく普通のテノールにしか聴こえません。特に、歌い出しの音が何か探っているようで、ピッチがぴっちりと決まらないのですよ。 この中には、ファースト・アルバムで歌われていたリヒャルト・シュトラウスの「Zueignung(献呈)」と「Allerseelen(万霊節)」の2曲もあったので、それをその2005年の録音と聴き比べてみました。そうしたら、それはまさに雲泥の差、かつての針の穴を通すほどの正確なピッチは、今回はすっかり失われてしまっていたことが分かりました。確かに、表現としては「深み」が増しているのでは、と思えなくもないのですが、その代償で大切なものを失っているのでは、という気がしてなりません。たった15年でここまで変わってしまうとは。 確かに、彼は1969年生まれですから、すでに50歳は超えています。それなりの衰えが来てしまっていて、それを必死にカバーするような歌い方になっているのでしょうか。それにしても、モーツァルトの「Das Veilchen(すみれ)」や「Sehnsucht nach dem Frühling(春へのあこがれ)」などは、もっとシンプルに歌ってほしいのに、という思いが募ります。 ただ、思い切り抜いた声で歌われているブラームスの「Wiegenlied(子守歌)」や、最後に収録されているマーラーの「Ich bin der Welt abhanden gekommen(私は世界から忘れられ)」などには、昔はなかったような「色気」のようなものも感じられます。でも、そんな路線になってしまったのでは、もはやカウフマンではありません。 CD Artwork © JAK GmbH & Sony Music Entertainment |
||||||
ですから、その中には新バッハ全集(出版元はベーレンライター)によるヘルムート・リリンクの一連のカンタータの録音もありました。彼のヘンスラーからのカンタータ全集の一部は、最初はこの「カンターテ」もしくは「ベーレンライター・ムジカフォン」からリリースされていたはずです。 そんなレーベルも、今では別のオーナーに身売りされ、細々とリリースを続けているようです。その最新の録音は、2018年から2019年にかけてレコーディングが行われた「ヴォイスミックス」という名前の女声アンサンブルのアルバムでした。 このグループは8人編成の女声ア・カペラです。メンバー以外に指揮者がいて、そのシュテフェン・シュレイヤーという人によって2015年に作られました。シュレイヤーはドイツのコンスタンツ大聖堂の音楽監督として、そこの聖歌隊の指揮をしていますが、その聖歌隊のパートリーダー級の人を集めて結成されたのが、この「ヴォイスミックス」です。彼女たちは、多くの合唱コンクールで賞をもらっていますし、音楽祭でのコンサートなども行っています。 いずれにしても、女声だけのア・カペラというのは、サウンド的にはベースを欠く形なので、なかなかそれだけで存在を主張することが困難なジャンルです。果たして、彼女たちのチャレンジはどんな成果を見せてくれるのでしょう。 まずは、フィンランドの重鎮合唱指揮者でジャズマンでもある、カリ・アラ=ポッラネンが作ったアルバムタイトル曲「Let it shine!」です。これは、ジャジーでご機嫌なナンバーですが、彼女たちは小気味よいグルーヴでその味を存分に出しています。アレンジの妙でしょうか、あるはずがないベースラインが、ほのかに聴こえてきます。 そして、次の曲がガラリと時代が変わって、ルネサンス期のシャンソン、ピエール・パスローの「Il est bel et bon(うちの亭主はお人よし)」という、超有名な曲です。こんな風に、彼女たちの選曲は、ジャンルや時代を飛び越えてとても自由なものがあります。実は、この曲を初めて聴いたのは「スウィングルII」のバージョンだったのでそれが常に耳に残っているのですが、ここでの演奏はそれよりもソプラノがしっかりしていて聴きごたえがあります。 それが、3曲目、ヴェルディの「聖歌4編」の中の「聖母マリアへの賛歌」という、「純クラシック」になると、なにか精彩がありません。これがオリジナルの編成なのに、とても消極的なアプローチで、合唱としての魅力が全く感じられないのです。それは、続くホルストの「Ave Maria」でも同じこと、なにか音楽自体が受け身に終わっています。 ところが、その後の先ほどのアラ=ポッラネンが編曲した「黒人霊歌集」では、最初の生き生きとした音楽が戻ってきました。ソロを歌うソプラノなどは、全く歌い方を変えてゴスペル風に迫ってきますから、とても同じ人とは思えないほどのインパクトがあります。 どうやら、このアンサンブルは、レパートリーによって得手、不得手がとてもはっきりしているようですね。その印象は、アルバム全曲を聴き通して確固たるものになりました。ドビュッシー(クリトゥス・ゴットヴァルトによる編曲)やプーランクはちょっと、という半面、非クラシックのイディオムが多用されている曲ではとても見事なノリを感じさせてくれるのです。 デイヴィッド・マッキンタイアーというカナダの作曲家の、ひたすら「Ave Maria」というテキストだけで歌われる変拍子の曲などは、とても伸び伸びと歌っていましたし、最後の主に地声で歌われるマンティヤルヴィの「シュード・ヨイク」なども、自家薬篭中といったちょうど良い感じです。 CD Artork © Klassik Center |
||||||
このオペラではメインキャストの2人がほぼ出ずっぱりですが、パウル役がヨナス・カウフマン、マリエッタ役がマルリス・ペーターゼンという、実力もルックスも抜群のテノールとソプラノですから、期待は高まります。 バイエルン国立歌劇場の映像は久しぶりに見ました。そのオープニングでそこのステージが現れたときに、オーケストラ・ピットはこんなに床が高かったのか、という印象がありました。客席から、オーケストラのメンバーがはっきり見えるようなのですよね。当然、音もはっきり聴こえてきますから、まるでリヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」のような雰囲気を持つ前奏曲は、そのオーケストレーションの極上の響きがくっきりと聴こえてきます。もうそれだけでコルンゴルトの世界に入り込むことができます。 ところが、それが終わってブリギッタ役のジェニファー・ジョンストンが歌い始めると、その声がほとんど聴こえてこないのですよ。それまでのオーケストラの音圧があまりにも高かったので、歌手のレベル設定を間違えたのでしょうか。まあ、しばらくすると、エンジニアがそのことに気が付いたのか、あるいはこちらの耳が慣れてきたのか、歌手の音圧はそれほど気にならなくなってきますけどね。 というか、カウフマンにしてもペーターゼンにしても、歌そのものが的確に訴えるものを持っていますから、録音のミスはそれほど影響はないのかもしれません。 そんなソリストたちの存在感とともに、このサイモン・ストーンの演出のインパクトにも、驚かされます。ステージのセットは、第1幕と第3幕は全く同じでパウルの自宅、第2幕はマリエッタの自宅です。ただ、その2つは同じような造りで、回転舞台によって全方向から見られるようになっています。そのパウルの家では、2つの部屋の壁にそれぞれ映画のポスターが貼ってあります。片方は、ジャン=リュック・ゴダールの「Pierrot le fou(気狂いピエロ)」、   このオペラの重要なモティーフは、亡き人の「亡霊」です。演出によっては、パウルの亡き妻であるマリーに別の「役者」を立てたりしますが、ここではもっと手の込んだ手法で、その「亡霊」の存在を明らかにしています。まずは、パウルが「在りしものの教会」と呼ぶ、マリーの遺品を展示した小部屋のセットです。そこには壁から扉まで、マリーのポラロイド写真が何百枚と貼り付けられています。  そして、ここではマリーの「亡霊」が、ペーターゼン自身による末期ガン患者のようなスキンヘッド姿で現れます。それが、先ほどの「気狂いピエロ」の部屋での出来事。一方、リアル・マリエットとの場は「欲望」の部屋なんですよ。わかりやすいですね。 ここでのカウフマンのパウルは完璧でした。というか、彼の歌い方には、どんな時にも生身の人間を感じることができます。そこに、先ほどのポラロイド写真が伏線となって、パウロの妄想の世界が、とても現実味をもって広がることになるのです。 もちろん、それを受けるペーターゼンの、とてもチャーミングな歌と体当たりの演技(この人、50歳を超えていると知って驚いているところです)も完璧、すごいものを見てしまったな、というところでしょうか。 BD Artwork © Bayerische Staatsoper Recordings |
||||||
今回の「第10巻」はイル・ジャルディーノ・アルモニコの演奏、ここでは、初期の傑作、交響曲第6番「朝」、第7番「昼」、第8番「晩」が取り上げられています。 実は1年ほど前にも同じカップリングでの別のアーティストの録音を紹介させていただきました。その時にちょっとした勘違いで、「ハイドンが仕えたエステルハージは二人」と書いてしまいましたが、今回改めて資料にあたってみると「二人」ではなく「3人」だったことに気づきましたので、その本文は訂正させていただきました。 つまり、1761年の5月にハイドンを雇ったのは、最も長く仕えたニコラウス・エステルハージ一世ではなく、その前のパウル・アントン・エステルハージだったのでした(翌年3月に彼は亡くなります)。 このアルバムには、「Les heures du jour(1日の時間たち)」というタイトルが付けられていますが、そのようなタイトルを提示して、ハイドンに3つの交響曲を作らせたのが、このパウル・アントンだったのですね。彼は、自身でもヴァイオリンやフルートを演奏したのだそうです。さらに、彼はライデン大学に在学中から天文学に興味を持っていて、太陽の軌道をテーマにして、それぞれの位置での太陽が、人々にもたらす光と暖かみを描くことを、ハイドンに課したのでしょう。もちろん、それは新しく雇った副楽長のスキルを実際に確かめたいという意味もあったのでしょう。 ただ、別の資料では、パウル・アントンは、同じコンセプトで「4つの弦楽四重奏曲」を作ることを命じたとされています。一説では、最後の「夜」を作らなかったのは、その頃から体調が悪かった雇い主の「死」を暗示するような「夜」のモティーフをハイドンは避けたことによる結果なのではないか、とも言われています。 この頃のエステルハージ家の宮殿は、ウィーンのど真ん中にありました。そこでは、日常的にコンサートが行われていたのだそうで、すぐそばのブルク劇場で上演されていたオペラの一節などが編曲されて歌われていました。実際に、この「晩」交響曲の第1楽章には、そのようにして人気のあった、グルックの「Le Diable à quatre(4人の悪魔)」というオペラ・コミークの中のナンバー「Je n'aimais pas le tabac beaucoup(私、タバコはあんまり好きじゃないのよ)」が引用されています。「晩」のエステルハージ家のたたずまい、といった感じなのでしょうか。 今回のアントニーニの演奏は、1年前に聴いたハンガリーのピリオド楽器の団体のものと比べると、全く次元の異なるものでした。あちらは、おそらく実際のハイドンの時代の様式を再現したものなのでしょう、いかにもおっとりとした、それこそ「時代」が感じられる演奏でした。 それに対して今回の演奏は、まさに「現代」で求められている「ピリオド」の姿です。楽器こそは18世紀頃に作られたもの、あるいはそのコピーですが、そこから醸し出される情感には、「今」でなければ聴くことができない強烈なメッセージが込められています。それは、先ほどの「晩」の終楽章の嵐の描写を聴けば一目瞭然、それこそ、これをパウル・アントンが聴いたらば、びっくりして病気も治ってもっと長生きしたのでは、と思ってしまうほどのインパクトです。 このアルバムでは、ハイドンの意思(?)に背いて、「夜」のためにモーツァルトの「セレナータ・ノットゥルナ」がカップリングされています。 これを聴くことによって、ピリオド楽器による演奏は、決して「古楽」ではない、という認識が新たになることでしょう。 CD Artwork © Haydn Stiftung Basel & Alpha Classics / Outhere Music |
||||||
彼は、歌手であるのと同時に、オルガニスト、そして作曲家としての研鑽も積んでいました。その最初の「師」はベンジャミン・ブリテンだったのだそうです。さらに、モーリス・デュリュフレにも、オルガンを学んでいました。 彼に最も影響を与えたのは、ピエール・ブーレーズの弟子だったリチャード・ロドニー・ベネットです。彼は、「ブーレーズは月謝を受け取らなかった」ということで、アイヴズからも月謝を取らずにレッスンを行ったのだそうです。 アイヴズはキングズ・シンガーズを離れた後は、作曲家、そして合唱指揮者として活躍することになりました。1991年からは、オクスフォード大学のモードレン・カレッジの音楽監督に就任、18年間そのポストにあり、数多くのレコーディングも行っています。この「レクイエム」は、そのカレッジの550周年記念として委嘱されたもので、2008年11月に、モードレン・カレッジのチャペルで初演されました。 そのころ、アイヴズのアシスタントとしてここで学んでいたリチャード・ピネルが、今回2020年3月の録音では指揮を担当しています。演奏しているのはピネルが音楽監督を務めるケンブリッジ大学のジーザス・カレッジの聖歌隊です。この聖歌隊はトレブルパートが少年の団体と、大人のソプラノの団体の2組あって、普通はそれぞれ別々に活動しているのだそうですが、今回は初めて合同で録音に参加しています。それと、ブリテン・シンフォニアとの共演も、初めてのことなのだそうです。 アイヴズの「レクイエム」は、フォーレやデュリュフレの「レクイエム」の流れをくむものなのでしょう、楽章構成も、その2作品とほぼ同じで、「Sequentia」はほとんどカット、その中の「Pie Jesu」だけが「Benedictus」の後に演奏され、最後には「Libera me」と「In Paradisum」が追加されています。演奏時間は40分ちょっとです。 曲はまず、ほとんど聴こえないほどにかすかなサンバル・アンティークの響きから始まります。それは、まるで「儀式」の始まりのよう。その後で歌われるメインテーマは、まさにそんな「儀式」にふさわしい、あらゆる人に受け入れられるようなシンプルで温かみのあるものでした。 オーケストラは小編成ですが、ホルンやフルートのソロがとても上手で、的確にメッセージを伝えています。さらに、「O Domine, Jesu Christe」などでは、まるでデュリュフレの作品のようにティンパニが大活躍で、恐ろしいまでのクライマックスを作り上げています。 と、突然、「Sanctus」の後半の「Benedictus」ではオーケストラが沈黙して、合唱だけのア・カペラの響きが聴こえてきます。次の「Pie Jesu」では、今度は合唱の少年だけによるトレブルパートがテーマを歌います。 終わり近く、「Agnus Dei - Lux Aeterna」では、最初の「Requiem」のテーマが再び登場して、作品全体のコンセプトが再確認されることになります。次の「Libera me, Domine」で、ブリテンの「戦争レクイエム」の中の「Offertorium」の途中、「Sed signifer sanctus Michael」という部分(というか「俺はジャイアン」と酷似したテーマ)が現れるのは、ちょっとしたサプライズ。 そして、最後の「In Paradisum」は、まさにデュリュフレの世界、それがほとんどフェイド・アウトかと思われるような絶妙なピアニシモで消えていくのは、感動的です。まるで究極の食材のよう(それは「トリュフ」)。 大人だけの聖歌隊のソプラノパートが、ちょっと水準に達していないのが、とても残念です。 CD Artwork © Signum Records Ltd |
||||||
さきおとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |