| 餅搗き道祖神と満開の紅梅 |
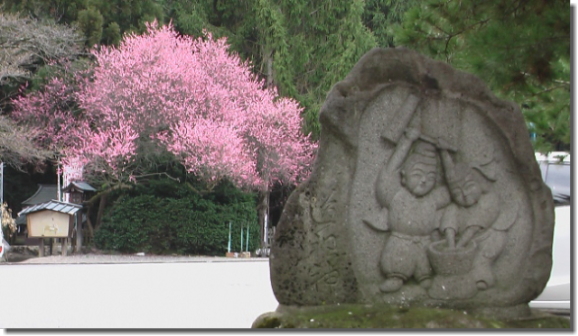 |
穂高神社北側の駐車場にある道祖神。
ちょうど紅梅がキレイに咲いていたので、
絵になると思い撮影してみた。
この道祖神の脇にある看板には、 |
餅搗き道祖神の由来
群馬県安中市東上秋間二軒茶屋に
餅を搗いている男女の双体石像がある。
寛政八年(1769)と銘があり、
部落では昔から道祖神として崇められてきた。
杵を男性、臼を女性に見立て、
男女の睦事を「餅搗き」とし、
夫婦円満の神として祀った。
道祖神に餅搗き像を思いついた
江戸時代の庶民感覚に感心する。
餅は祭りの供物として最も多く用いられ、
また、人生の吉凶禍福に 餅を搗いて供えられることは
極めて多い事である。
寄贈 穂高町有明 田川 博氏 |
とある。
田川さんが群馬の餅搗き道祖神を真似て、
レプリカを作ったものと思われる。
餅搗きをしている道祖神を初めて見た。
動きがあって、立体的で
躍動感があり、非常に面白い。
とても珍しい道祖神である。 |
|
| |
|
|