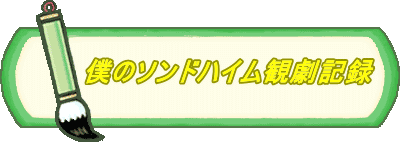
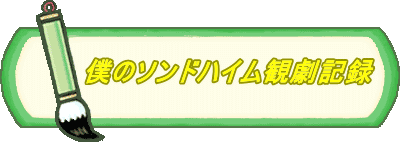
![]()
2006年1月12日 ユージン・オニール劇場(ニュー・ヨーク)
Sweeney Todd
配役:トッド=Michael Cerveris(ギター、オーケストラ・ベル、打楽器)
ロヴェット夫人=Patti LuPone(チューバ、オーケストラ・ベル、打楽器)
アンソニー:Benjamin Magnuson(チェロ、キーボード)
ターピン:Mark Jacoby(トランペット、オーケストラ・ベル、打楽器)
ジョアンナ:Lauren Molina(チェロ)
トビアス:Manoel Felciano(ヴァイオリン、クラリネット、キーボード)
女女乞食:Diana Dimarzio(クラリネット)
ビードル:Alexander Gemignani(キーボード、トランペット)
ピレッリ:Donna Lynne Champlin(アコーディオン、キーボード、フルート)
ジョーナス・フォッグ:John Arbo(コントラバス)
演出:John Doyle
<感想>
トニー賞の常連サーヴェリスとルポンのコンビが主演ということよりも、「たった10人で演じられるSweeney
Todd」という点が最大の話題になったプロダクションです。その是非については後述するとして、まずはどんな舞台だったか、とにかく気づいた点を順を追ってまとめてみます。
その前に1点だけ配役上気づいた点を挙げると、通常男性が演じるピレッリ役をここでは女性が演じています。オペラだと「ズボン役」ということで青年あるいは少年役を女性歌手が演じることがときどきありますが、おっさん役を女性が演じるというのは珍しいことです。
【舞台の基本構造】
・舞台中央奥に天井まで続く棚があり、床屋道具、写真、さび付いた皿、十字架、その他ガラクタが所狭しと並べてある。棚の下にキーボードが据えられている。棚の両側にはドア。
・格子状の床の両端に縦に椅子が並び、歌手兼奏者が座る。その外側にも黒い格子状の床が続く。
・多少入れ替わりはあるが、基本的な人物の配置は以下の通り。
キーボード
(ビードル、ピレッリなどが交代で演奏)
ロヴェット フォッグ
トッド ターピン
アンソニー ピレッリ
ジョアンナ 女乞食
↓
(客 席)
【第1幕】
○バラード
・中央に棺桶、上手手前に口を縛られ、囚人服を着せられ、後ろ手に縛られたトビアス。それがほどかれると序奏が始まり、歌い出す。棺桶のふたが開けられ、白布(後の場面で床屋用の前掛けに使われる)が開かれると中から黒の皮ジャケットを着たトッドが立ち上がる。
○“No Place Like London”
・バラードからそのまま続けて演奏される。
・下手奥でアンソニーが客席を向いて歌う、トッドは棺桶の中に入ったまま(舟に乗っているという設定)やはり客席を向いて歌う。つまり、2人は互いに顔を見合さない。
・女乞食とのやり取りでも3人は客席側を向いたまま。アンソニーがコインを渡すと下手最後尾に座っているロヴェットがトライアングルをチンと鳴らす。
○“The Barber and His Wife”
・トッドは舟から前に出て歌う。その間に棺桶の蓋が閉じられ、白布が被せられる。そこに皿とカップが置かれ、ロヴェットが肘を付いて立っている。
○“The Worst Pies in London”
・アンソニーが去り、トッドが振り返るとすぐにロヴェット歌い出す。破れた網タイツ姿。
・パイを食べさせるのは仕草のみ。トッド、すぐに吐き出す。
○“Poor Thing”
・ロヴェットが歌う間、トッド、上手端の椅子に座っている。
○“My Friends”
・ロヴェット、奥へ向かおうとすると上手側の椅子に座っていた女乞食が立ちはだかる。ロヴェット、彼女を押しのけ、棚の上から白の洗面器を持ってくる。その上の白布を開くと中から剃刀が2本出てくる。
・トッドへの愛を告白し体を彼に寄せながら歌うロヴェット。
○“Green Finch and Linnet Bird”
・棺桶の上に椅子が置かれ、そこにジョアンナ座る。
○“Ah, Miss”
・棺桶の後ろに脚立が置かれ、女乞食はそこに昇って歌う。
・アンソニーは下手奥で歌う。
・鳥を買う場面は省略、しかしターピンの”Dispose it”の台詞は生きている。
○“Johanna”
・アンソニー、脚立に昇って歌う。
○“Pirelli’s Miracle Elixir”
・トビアス、鬘みたいに白紐がたくさん付いた帽子をかぶりながら歌う。
・ロヴェット、チューバを吹きながら舞台上を歩いて回る。正面前に来ると客席に背を向けてお尻フリフリ。
・トビアスと群衆とのやり取り、トッドが「魔法の万能薬」を小便と見抜く場面は省略。
○“Contest”
・棺桶の蓋が棺桶と垂直に置かれ、その両端にマネキンの頭が2つ置かれ、首に布が巻かれる。
・ピレッリは長ったらしい自己紹介を行わず「我輩の薬を小便呼ばわりしたのは誰だ?」の箇所から歌い始める。
・ロヴェットの歌う部分は省略され、代わりに下手の列前から2席目でチェロを弾いているアンソニーが持っているトライアングルを叩く。
・オリジナルはヘ長調だが、ここでは4度下げてハ長調で歌う。
・途中で2人とも舞台前方、つまりマネキンの前に出てきて歌と演技を続ける。トッドはロヴェットの髪の毛を抜いて剃刀の切れ具合を試す。その後マネキンの位置まで戻る。
○“Johanna”
・背広姿のターピン、舞台中央最前の椅子に座って歌うが、鞭打つような仕草はしない。
・棺桶の上にジョアンナが座っている。
・ターピンは歌い終わった後、彼女の後ろの脚立に昇って求婚。
○“Wait”
・脚立は上手端、棺桶の横に移される。アンソニー、そこに昇ってジョアンナとのことをトッドたちに報告。
・ピレッリは棺桶の中で剃刀で首を切られる。すると舞台全体が赤い光で覆われ、血の付いた白衣を着る(以下殺された人物は全て同様)。中央手前でロヴェットが血の入った白バケツを床に置いたもう一つの白バケツに注ぐ。
○“Kiss Me”
・棺桶が縦に立てられ、その奥からターピン判決を下す。
・その前でチェロを持ちながらアンソニーとジョアンナの二重唱。ここでは向かい合い、抱き合いながら歌う。
○“Ladies in Their Sensitivities”
・棺桶が今度は横に置かれ、白布が被せられる。両端に椅子。ターピンとビードルが座る。赤いワイングラスが置かれ、トッドがワインを注ぐ。
○“Quartet”
・引き続きターピンとビードルは棺桶の奥に立ち、トランペットを吹いたり歌ったりしながら手前の2人に加わる。
○“Pretty Woman”
・棺桶は縦に置かれ、その前の2つの椅子にトッドとロヴェット座る。ターピンが来るとロヴェット奥へ。
・アンソニーはトッドの店に乱入する直前まで奥でキーボードを弾いており、ピレッリと交代して登場。
○“Epiphany”
・トッド、白布をジョアンナのように抱いたり、棺桶の壁をジョアンナのように撫でたり、棚の下手に据えられた梯子を昇ったりしながら歌う。
○“A Little Priest”
・最初は横に置かれた棺桶に座って歌う2人だが、人肉パイのアイデアが出てくるとロヴェット、棚から蓋と皿を持ってきてそれらを使いながら歌う。だんだん興に乗ってきた2人は社交ダンス風に踊りながら歌い、最後は棺桶の上に立ち上がってポーズ。
【第2幕】
○“God, That’s Good!”
・ロヴェット、黒のキラキラ衣装で登場。
・トッド、棺桶の蓋を立てて舞台中央に立ち、壁の向こう側にいるロヴェットに呼びかける。
・上手奥のドアのさらに奥からトッドが持ってくるのは床屋用の椅子でなく、白い小さな棺桶。
○“Johanna”
・ジョアンナは上手手前、アンソニーは下手奥、トッドは棺桶の上で白棺桶を抱きながら歌う。犠牲となる客は出てこない。その代わり中央手前でロヴェットが白バケツの血を別のバケツに注ぐ。キーボードの叩き方のせいもあるが背筋が寒くなる感じでなく、淡々とした、リズミカルとさえ言える演奏。
○“By the Sea”
・ロヴェット、棺桶の上の椅子に座り、”FLOUR(小麦粉)”と書かれた白缶の中に入った糸鋸、ドリル、鉈などの手入をしている。その下手側にトッドは座って剃刀の手入をしている。
・ロヴェット、歌いながらドリルを舟のように動かすなど、ノリノリ。
・アンソニーが現れると棺桶が立てられ、その前でトッド、アンソニーに指示を出す。
○“Not While I’m Around”
・オリジナルは変イ長調だが半音下げてト長調で演奏。
・棺桶が横に置かれ、その上にロヴェットとトビアス座っている。ロヴェットは赤いマフラーを編んでいる。
・トビアス、自分でヴァイオリンの伴奏を入れてからサビを歌う。
・調理室には下手奥のドアから裏へ出て上手奥のドアから入ってくる。2人の声にエコーがかかる。ロヴェットは懐中電灯を持って入る。肉挽き機は上手奥のドアのさらに奥にある。
○“Parlor Song”
・ビードルは棺桶に座ってキーボードを弾かずに歌う。ロヴェットはその歌に合わせてディスコ風に踊る。
・トビアスの声は舞台裏からエコー付で聞こえてくる。その間トッドは棚の下手側の梯子に昇って眺めている。
・トッドが戻ってから棺桶に座ったままのビードルに白布を被せ、首を切る。
○“City on Fire!”
・棺桶が立てられ、その手前にジョーナス。その手前にジョアンナがうなだれて座っている。アンソニーはジョーナスのこめかみにピストルを突き付けるが撃てない。代わりにジョアンナが(ピレッリ役の女優が扮する)髪切り人からはさみを奪ってジョーナスを刺して逃げる。
・トビアスは上手手前で白バケツ2つを前にして作業。人肉が材料であることに気づき、上手奥へ逃げる。
○“Final Sequence”
・トッドは下手奥、ロヴェットは上手奥から懐中電灯を持ってトビアスを探す。
・男装したジョアンナは中央手前に座っている。
・女乞食はみすぼらしい服を徐々に脱いでいき、この場面では黒のタンクトップ姿になり、床に縦に置かれた棺桶の中に立つ。トッドに首を切られる。
・ターピンが来ると、白棺桶を棺桶の中に立て、その上に座らせ、白布を被せる。ロヴェットがさりげなく血の付いた白衣をその手前にばさっと置いていく。
・ターピンを始末した後手前に座っているジョアンナの肩に手を置いて尋ねる。剃刀を当てようとした時にロヴェットの”Die!Die!”の叫びが聞こえ、それに気を取られた隙にジョアンナは逃げる。
・ロヴェットが上手奥から出てきて中央手前に立つ女乞食と向かい合う。下手奥からトッドが入ってくると女乞食はトッドの方を向き、そこでトッドは彼女がルーシーだったことを知る。
・トッドはロヴェットを炉に投げ込むのでなく剃刀で首を切る。ロヴェットも血の付いた白衣を着る。
・トッドはふたをした棺桶の上に座る。上手奥から現れたトビアスが棺桶の手前を回って奥に向かった時トッドに気づき、剃刀を取って首を切る。トッドは長いうめき声を上げながら仰向けに倒れる。ロヴェットと女乞食が手前両端でそれぞれ血をバケツに開ける。その後トッドの死体の上に白布を被せる。
・トビアスは囚人服を着せられて後ろ手を縛られ、口にも赤い布を縛られて座らされる。暗転。
○バラード
・冒頭と同じ状態からスタート。ただし、トッドだけは白布を取られ、そこから立ち上がって皮ジャケットを着て歌う。全員舞台前面一列に並んで歌った後キーボード奏者以外散り散りに退場し、最後にトッドが上手奥から退場してドアをがしゃんと閉めて幕。
【評価】
チューバを吹きながらお尻フリフリするルポン(ロヴェット)、さだまさしの「精霊流し」よろしく自分で弾くヴァイオリンで盛り上げてから歌い続けるフェリシアーノ(トビアス)、歌もチェロも巧みにこなし堂々たるブロードウェイ・デビューを果たしたモリーナ(ジョアンナ)、いずれも見事なものです。しかし、そんな出演者たちの奮闘ぶりを見ながら、僕の思いはいつしか全く別の方向へ漂流し始めていました。
ブロードウェイでは主に興行上の理由からオーケストラの規模が年々小さくなってきています。演奏家側の組合はそれに抵抗して一プロダクションあたり劇場(あるいは劇団)側が最低限確保すべき演奏家の数を認めさせていますが、それでも弦の数は弦楽四重奏程度、管楽器になると例えばフルート、クラリネット、サックスを1人で吹かないといけない、みたいな状態になっています。
僕は今回の公演を観て、これはそんな流れの行き着いた先、という気がしてなりません。つまり、とうとう舞台上の俳優とピット内の演奏家との間の境界線すら取り払われてしまった。しかも、この作品に限って言えば、合唱パートまでソロ役の俳優に吸収されてしまったわけです。
このプロダクションは今年のトニー賞の候補に6部門で挙がっていますが、僕が今最も注目しているのは、その中で「ベスト・オーケストレーション」部門を受賞するかどうかです。もし取ったらブロードウェイの公演形態は根本的に変わってしまうのではないか?すなわち、1人で歌えて踊れて演技ができるだけでなく、楽器を(できれば複数)演奏できないとブロードウェイの舞台に立てない、といった時代がゆくゆくは来ることになるのではないか?
そのこと自体かなり深刻な問題であると思いますが、それ以上に気になったことがあります。仮に百歩譲って、出演者の数を切り詰める方向性が避け難いものだったとしても、今回のような試みをする作品として"Sweeney
Todd"がふさわしかったかどうかということです。
"Sweeney Todd"はソンドハイムの中でも人気の高い作品であり、ミュージカル界だけでなく米英のオペラ・カンパニーでも頻繁に演奏される作品です。なぜなら、オペラ関係者にとってもこの作品は「演奏したい」という意欲をわかせるに十分な音楽性を備えているからです。実際オペラ・ハウスで演奏されるのを聴いていると、小規模でも数十人のオーケストラが鳴り響く上で展開される声の競演は、並みのオペラよりずっと聴き応えがあります。
このように、元々音楽が売りのソンドハイム作品の中でもとりわけ音楽的水準の高いこのミュージカルを上演するのに、楽器パートを極限にまで省略してしまうというのは、僕にはどうにも納得できません。せめてソンドハイムの他の作品を検討する余地はなかったのか?例えば"Company"とか(でも"A
Little Night Music"も困るなあ…)。
というわけで、今回の公演を手放しで賞賛する気にはどうしてもなれないのでした。
Into the Woods
配役:魔女=諏訪マリー
パン屋=小堺一機
パン屋の妻:高畑淳子
ジャックの母:天地総子
シンデレラ:シルビア・クラブ
シンデレラの王子・狼:藤本隆宏
赤ずきんちゃん:宮本せいら
ラプンツェル:早川久美子
ラプンツェルの王子:広田勇二
シンデレラの母・巨人・おばあちゃん:荒井洸子
ナレーター・謎の男:鈴木慎平
執事:大森博史
シンデレラの継母:藤田淑子
フロリンダ:花山佳子
ルシンダ:鈴木純子
シンデレラの父:二瓶鮫一
白雪姫・牛:山田麻由
眠れる森の美女・ミルキーホワイト:飯野めぐみ
指揮:吉住典洋
演出:宮本亜門
<感想>
2004年の初演時には観れなかったので、この再演はとてもありがたかったです。とは言え、日本を舞台にした「太平洋序曲」と異なり、ソンドハイムの中でも最も彼らしい作品の一つに宮本さんが正面から取り組まれたということで、正直期待半分、不安半分で劇場へ行きました。
不安と言えば、会場には親子連れが多かったのには驚きました。確かにシンデレラや赤ずきんなど、有名な童話が出てはくるですが、第1幕ではこれらがもつれた糸のようにからみ合い、第2幕ではさらに想像もつかない方向へ話が発展する。しかも、上演時間は休憩を入れて3時間を越える。子供たちにはきつ過ぎないだろうか?
客席に向かって大きく張り出した舞台前面に3件の家、下手からシンデレラ、パン屋、ジャックの家。その前にかけられた幕にそれぞれ”Into””the””Woods”と題名が描かれ、Woodsの”o”の中に目がある。
開演前から鳥の鳴き声がする。聴衆向けのアナウンスはナレーター役の声で、子供向けにやさしく語りかけている。「真夜中を告げる鐘」が開演の合図。
【第1幕】
○オープニング(Prologue)
舞台が暗くなるとまずパン屋の前にナレーター登場。「むかしむかし」と語り始めてから舞台が明るくなり、音楽スタート。プロローグ後半、登場人物がいよいよ森へ向かう場面になると、家と家の隙間から出てきて客席の通路も使って動き回る。3件の家は吊り上げられて、森の場面となる。
以下、天井まで伸びる木々が場面に応じて前後左右に動く。確かに席によっては人物が木に隠れて見えない、といったことがしばしば起こる。ただ、木の動き自体は素早いので場面転換のやり方として違和感はない。
○第2場
赤頭巾から頭巾を受け取ったパン屋、赤頭巾が「おばあちゃんが狼の皮で新しい頭巾を作ってくれる」と聞いて吐き気を催す。
※「素敵な王子様」(A Very Nice Prince)
ホリゾントでは豆のつるが天まで伸びる様子がシルエットで映し出される。
○第3場
ジャックが巨人の国から取ってきた金貨は直径1m以上の巨大なもの。確かに巨人が使っている金貨だから大きくて当然である。
※「苦悩」(Agony)
ラプンツェルの王子が登場すると、その前をシンデレラの王子が飛ぶようにして横切るのでラプンツェルの王子、のけぞる(第2幕も同じパターン)。パン屋の妻は木陰で様子をうかがう。
王子2人が歌っている間、パン屋の妻はシンデレラの王子が抱える幹を反対側から抱えたり、2人が歌い終わる場面では木の陰で両手を広げたりして1人で舞い上がっている。
2人の王子が去った後、家に帰ろうとするパン屋の妻、ジャックの母から話しかけられる。一度目は無視するが「お若い方」と呼ばれると返事。
○第5場
ミルクを飲んだ魔女は舞台奥へ下がってから若返って戻ってくる。
○フィナーレ
天井から無数の細い垂れ幕が下りてきて王子とシンデレラの結婚を祝福。みなでお祝いする一方で、魔女とシンデレラの姉たちなど不幸になった人物たちはオケ・ピットの前で歌う。垂れ幕が落ちると全員一緒に歌うが、ホリゾントには新たな豆のつるが伸びているのがシルエットで映し出される。
【第2幕】
○オープニング
第1幕のプロローグと同じ舞台設定で始まる。ただし、下手のシンデレラの部屋は王宮内の一室。
家がせり上がると舞台中央に巨人の妻が落としたらしい眼鏡の片方が落ちていて、ジャックが抱えて運び出す。
○第2場
ナレーターは下手端に立っているが、同じく下手側半分に集まっている登場人物たちから目を付けられ、巨人の妻に差し出される。投げ捨てられて死んだナレーターを1人見つめる赤ずきんにパン屋の妻は「見ないの」と言って彼女の目を手で覆う。
※「森のひと時」(Moments in the Woods)
パン屋の妻、歌い終わった後舞台奥へ向かって再び歩数を数えながら歩いていくが、そこに巨人の妻の足跡の音が重なり、ホリゾントに映し出された大木が彼女に向かって倒れていく。
※「最後の真夜中」(Last Midnight)
歌い終わった魔女、舞台中央で両手を上げて悲鳴をあげ、地下へと消えていく。
※「みんなひとりじゃない」(No One is Alone)
パン屋とジャックは下手手前に吊るされたブランコに座って歌う。
○フィナーレ
眠り姫が牛のぬいぐるみを持っている。つまり「あたしは第1幕でミルキー・ホワイト役だったのよ」というわけ。最後は生き残った人物(シンデレラ、赤ずきん、ジャック、パン屋と赤ちゃん)が舞台奥に延びる道を駆けていき、それを他の者たちが手を振って見送る。
【セリフ及び訳の問題】
セリフ部分はオリジナルにないものを挿入したり訳を工夫したりすることで、作品の理解を助けようとしているのがよくわかる。その一方で歌詞については適切でない訳が多く、音楽の影が何とも薄くなってしまっている。
プロローグを例に取ろう。まず魔女が呪いについて説明する前に「いいかい、話は最後まで聞くもんだよ」とパン屋夫妻に話す。これはオリジナルにない。
他方プロローグにおける歌詞の中で最も重要なフレーズが2つある。”I wish”と”Into the Woods”である。いずれもこの場に登場する人物のほとんど全員が口にする言葉であり、音楽上もこの2つのフレーズに付けられたモチーフを寄木細工のようにつなげていくことで壮大な音の絵巻を作り上げていくようにできている。
しかし、この2つのフレーズの処理の仕方が異なるのである。すなわち、”I wish”はそのままでは聴衆に理解されないと思ったのか、「お願い」と訳されたのに対し、“Into the Woods”は訳さずそのまま歌わせている。
後者については正にこの作品のタイトルなので原語のまま聴衆に印象付けたいという気持もわからなくはない。
だが”Into the Woods”を日本人がそのまま発音して歌うのは非常に難しい。「イ」「ウ」といった響きにくい母音が並んでいるからである。英語圏の歌手たちはそれでも工夫してうまく歌っている(実際バーナデット・ピータース主演のビデオ版の演奏はすばらしい)が、日本人だとそこだけ何と歌っているのか、わからなくなる。他の歌詞が日本語であるだけに、初めて聴く人には「ああ、『イン・トゥ・ザ・ウッズ』ね」と気付くまでかなり時間がかかるのではないか。それではせっかくの音の絵巻が聴衆に伝わらない。
せっかく他の歌詞を苦労して訳しているのだから”Into the
Woods”も例えば「森の中」といった具合に日本語で歌わせた方が、俳優側も歌いやすいし聴衆も「あ、みんな『森の中』って言ってる」と気付きやすいと思うのだが。
次に、気になったのはAgonyである。プログラムのタイトルは「苦悩」と訳してあるが、「狂おしい」と歌わせたのは誤訳だと思う。
まず、名詞を形容詞に訳していいのかという形式的問題がある。それ以上に内容的にも問題がある。ここでの王子たちのやり取りには、どこか身勝手で滑稽なところがある。純粋無垢の青年(例えば「スウィーニー・トッド」のアンソニー)が恋に落ちて苦しんでいるわけではない。何の苦労もなく育てられ将来は王様になることが約束されている特権階級の人間が恋愛ゲームをやっているのである。それを本当らしい気分にして自らを盛り上げるためにAgonyという言葉を持ち出しているに過ぎない。
その意味では、大げさでどこか嘘っぽいニュアンスの出る言葉に訳した方がいいのではないかと思う。スコアを無視すれば、例えば「断末魔の苦しみ」といった感じだろうか。スコアに合わせるとなると、「苦悩だー」でもいいかもしれない。原語から少し離れるかもしれないが、例えば「地獄だー」「煉獄だー」「拷問だー」でもいいような気がする。
それ以外に気づいた点をいくつか挙げると、第1幕第3場、シンデレラも「階段に接着剤が塗られていたので靴を片方取られた」とパン屋の妻に話す。これもオリジナルにはない。ちなみにここではPitch(松やに)を「接着剤」と訳している。
ラプンツェルと魔女の二重唱、「完璧な世界」(Our Little World)で魔女に”Perfect”と原語で歌わせる理由がよくわからない。
“Midnight”についても、第1幕では”One midnight gone!”を「1日目の夜が明ける」と訳しているのに、第2幕魔女のソロでは「最後のMidnight」と原語のまま。和英どちらかに統一しないと、第1幕とのつながりが観客にはわからない。
【音楽上の問題】
以下、厳しいかもしれないが、将来への期待を込めて、今回の公演の最大の問題点を書いておきたい。
今回の公演に限らず、日本でソンドハイムを上演するに際しての最大の問題は、彼の作品を音楽として捉えられていないことにあると思う。
配役を見てみよう。”Into the Woods”にはソロのナンバー(オペラ風に言えばアリア)のある役が7つ(魔女、パン屋、パン屋の妻、シンデレラ、ジャック、赤ずきん、狼)あるが、その中に音楽大学出の人は1人もいない。「音大以外に専門的な音楽教育を一定期間受けたと考えられる人」といった訳のわからんカテゴリーを設けたとしても、3人に過ぎない。
それ以外の出演者、例えばパン屋役の小堺一機やパン屋の妻役の高畑淳子、いずれもセリフ回しや演技については申し分ない。特に第1幕で子供がほしいために次々と悪事を働かねばならないことに苦悩する場面や力を合わせることの大切さを知って和解する場面など、じーんとさせられる。しかし、歌については残念ながら、到底満足できるものではない。
では、何が一体問題なのか?これは2人に限らず歌のパートがある出演者全員に共通することなのだが、ソンドハイムの作品を演劇として捉え、演劇のアプローチで歌っているのである。もっと言えば、セリフの延長線上として歌っている。だから、強調したい言葉は全てセリフ調になり、ソンドハイムが書いたスコアを逸脱してしまっているのである。
そんなこと言ったら「オペラやブロードウェイの歌手だってスコアを崩して歌ったりセリフみたいに叫んだりするではないか」と反論されるかもしれない。確かにそういうこともあるが、現象として似ていても本質的には全く違う。なぜなら、歌手はまずスコアを正確に追った上で、スコアに書かれてない部分を自分なりに補って歌うからである。そのような表現は、決してスコアを逸脱したものではない。
例えば、先に述べたビデオ版に出てくる出演者たちの歌いぶりを聴いていると、今回の公演とある意味正反対の印象を受ける。すなわち、歌の部分も語っているように聴こえる。まるで歌詞の一語一語が音符にぴたっと貼り付いているように聴こえるのである。
また、スコア上高低とリズムの指示だけあって音程が示されていない部分を聴いていると、歌の部分と区別がつかないくらいオケが鳴らす音楽と溶け合っているのである。つまり彼らは音楽の延長線上としてセリフもしゃべっているのである。
今回の公演を聴いていると、途中までスコア通り歌っていても強調したい箇所になると突然セリフに戻ってしまう。したがって、音楽の流れが中断される。最も正確に歌えていたと思われるシルビア・クラブの歌いぶりでも、ビデオ版の出演者のものと明らかに違う。
確かにソンドハイムの歌は難しい。音楽大学を出ているから歌えるというものではない。しかし、俳優が上記のような歌い方をしているのを聴くと「技術的に歌えないから得意なセリフに変えた」と思われても仕方ないところがある。それでは、いつまでたっても日本におけるソンドハイム上演の質は向上しない。1人1人の歌がなかなかセリフの世界から抜け出せないのに、最後に全員歌う箇所になって、それも最後の最後、例えば第1幕最後の「みんな幸せー!」だけ朗々としたベルカント風の声が響くというのは、どう聴いても変である。
この現状を変えるためには、例えば二期会あたりがソンドハイムに挑戦するのが有効な手段の一つだろう。実際米英のオペラ・カンパニーがソンドハイムを上演するのは珍しいことではない。それを演劇界の人たちに是非観てほしい。
おそらく感想としては今回の公演とは逆に、セリフ回しや演技の拙さばかり目立つことになるかもしれない。プログラムには中島薫さんが「歌唱のみに専心するあまり、演じているキャラクターから離れてしまっては何の意味もないのだ(クラシック系歌手がミュージカルに出演すると、この傾向強し)。」と書かれておられるが、たぶんそうなるだろう。
しかし、日本のほとんどの聴衆は「歌唱のみに専心」したソンドハイム演奏なんて、聴いたことがないのである。二期会あたりが上演すれば、少くともソンドハイムの書いた音楽の魅力は、現在より忠実に再現されるはずである。俳優の皆さんがこんな演奏をどう受け止め、次のソンドハイム上演にどう生かすか?
これこそ僕が「お願い」「かなえてほしい」ことである。
2007年1月5日 日生劇場
Sweeney Todd
別のサイトにアップしました。こちらからご覧下さい。
Company
主な配役:Robert=Raul Esparza(打楽器)
Joanne=Barbara Walsh(オーケストラ・ベル、打楽器)
Harry=Keith Butterbaugh(トランペット、トロンボーン)
Peter=Matt Castle(ピアノ、キーボード、コントラバス)
Paul=Robert Cunningham(トランペット、ドラム)
Marta=Angel Desai(キーボード、ヴァイオリン、アルト・サックス)
Kathy=Kelly Jeanne Grant(フルート、アルト・サックス)
Sarah=Kristin Huffman(フルート、アルト・サックス、ピッコロ)
Susan=Amy Justman(ピアノ、キーボード、オーケストラ・ベル)
Amy=Heather Laws(ホルン、トランペット、フルート)
Jenny=Leenya Rideout(ヴァイオリン、ギター、コントラバス)
David=Fred Rose(チェロ、アルト・サックス、テナー・サックス)
Larry=Bruce Sabath(クラリネット、ドラム)
April=Elizabeth Stanley(オーボエ、チューバ、アルト・サックス)
演出:john Doyle
<感想>
舞台中央に45度傾いた正方形が区切られ、そこがボビーなどの家のリビングルームになる。舞台中央最前(正方形の手前の角)がわずかに客席側にせり出している(以下その部分を「突端」と呼ぶ)。
中央やや下手寄りにグランドピアノ、その奥に飲み物などの入ったワゴン。中央やや上手寄り奥にギリシャ神殿風の柱、しかし下の方はラジエーターが巻かれており、その上はガラステーブル。手前には正方形のガラステーブル兼椅子が3つ。
正方形の区切りの左右奥は、場面に登場しない俳優兼演奏者用のスペース。上手奥には足の高い回転椅子が2列、下手奥は手前に回転椅子、奥にキーボード。
天井には半球状の傘付き蛍光電球が5×5吊るされている。
【第1幕】
○第1場
ボビーはピアノのへりにもたれて立っている。他の人物は舞台裏からお祝いの言葉を投げかける。ろうそくのついたケーキは出てこず、ボビーは火を吹き消す仕草のみ。楽器を持って現れたボビー以外の人物たちは、正方形の辺に沿って回りながら歌い、演奏する。
男性はスーツ姿、ネクタイをしている者もしていない者もいる。女性はスチュワーデスの制服を着るエイプリル以外黒のナイトドレス姿。
○第2場
ボビーはピアノのへりにもたれたまま。ワゴンの前にハリー、手前の椅子にサラ。サラの空手の腕を見せることになると、2人は正方形の両端へ移動。それぞれがまるで「エア空手」のように技をかけ、受けて見せる。身体は組み合っているはずなのに心が全く通っていない様子を見事に表現。
○第3場
ボビーは下手手前の小さな正方形のタイルの上。つまり大きな正方形の区切りの外にいる。そこがテラスという設定。
○第4場
ボビーはタイルの上にいたままで、スーザン&ピーターがジェニー&デヴィッドに入れ替わる。子供がいることを連想させる仕掛けは舞台上にはない。
ボビーは突端に移動。その後ろでサックスを持ったエイプリル、キャシー、マルタがガラス・テーブルの上に立ったり座ったりしながら”You
Could Drive a Person Crazy”を歌い、演奏する。歌の合い間のフレーズを3人でリレーして吹くところなど面白い。
○第5場
マルタはピアノの上に座って“Another Hundred People”を歌う。その手前でボビーとエイプリル、続いてボビーとキャシーのやり取り。
○第6場
ジェニーがラッパ水仙の花束を持って突端で花嫁を祝福する合唱部分を歌う。入れ違いにポールの靴を持ったエイミーが現れて早口ソロを歌う。ジェニーが再び現れるとエイミーは悲鳴を上げてピアノの下に隠れる。
ボビーは突端で”Marry Me a Little”を歌う。
【第2幕】
○第1場
ボビーは第1幕冒頭と同じくピアノのへりにもたれて立つ。その周囲を他の人物たちが第1幕よりは複雑にからむ。ここでもろうそく付きケーキはなく、ボビーは火を吹き消す仕草のみ。
“What Would We Do Without You”の途中でボビーがあひる笛を吹くと、上手側に集まっていた他の人物たちが一斉に白い目で彼を見つめる。
○第2場
ピアノの鍵盤の手前でボビーとエイプリルは抱き合い、その周囲を他の人物たちがからんで歌う。
○第3場
ボビーが”This is why you love New York.”とマルタに声をかけると彼女は”Yes!”と叫んでガッツポーズを作るがやがて白けた顔になり、区切りの奥へ下がる。スーザンも続いて奥へ退場。
ピーターがボビーに”Did you ever have a homosexual experience?”と尋ねると、両奥に座っていた女性たちが一斉に立ち上がってボビーの答えに耳を傾ける。
○第4場
ピアノのへりのあたりにボビーとジョアン。ラリーや他の客が踊る様子は見えない。ジョアンが毒づく客やバーテンダーも舞台上は現れない。
煙草の話をしている間ジョアンは途中で煙草の火を消し、2本目は出さない。
ボビーは突端で”Being Alive”を歌う。
○第5場
ボビーは突端に立ったまま。他の人物たちはボビーを探すがあきらめて退場した後、天井に向かってゆっくり大きな息を吐く。それに合わせてゆっくり照明が落ちていく。
【まとめ】
ドイルの手法、すなわち出演歌手が歌い、演技するだけでなく楽器も担当するというやり方に必ずしも賛成できないことは、前作「スウィーニー・トッド」のところで述べたし、今回も同じ感想を持ったことをまず断っておきたい。ただ、あの時別の作品でできないか、例えば「カンパニー」ではどうか?と書いた。その当時はドイルが次のどの作品を取り上げるかなんて知る由もなかったわけだが、図らずも予測が的中したわけである。
僕の予測にはもちろん根拠があった。音楽面のことである。「カンパニー」の音楽は「スウィーニー」に比べるとオペラ的な要素が薄い。最も大きな違いは、弦楽器よりもサックス・トランペット・トロンボーンなど管楽器の目立つ場面が多いことである。弦はある程度の人数がいないと響きの厚みが出ないが、管なら和音が必要な箇所でも2,3人で十分である。1人で複数の楽器を持たせるようにすればオリジナルの楽譜に書かれた音楽をほぼ網羅し、しかも演奏効果もほとんど損なわずに演奏できるはずである。実際音楽面の物足りなさは全くと言っていいほど感じなかった。
音楽面の不満が少ない分俳優たちの演技によりじっくり注目できたわけだが、この点でも収穫は大きかった。5年前ケネディ・センターで初めて観た時にはよくわからなかった台本上の疑問もかなりスッキリすることができた。
二つ例を挙げる。一つはマルタとボビーの関係である。第2幕第3場の台本を読む限り2人の間に大したことは起こらないのにマルタは以後登場しなくなる。ということは、ボビーとは結ばれなかったわけである。なぜだろうと思っていたが、上述のようにマルタはボビーの”This
is why you love New York.”というセリフで彼への思いが一気に冷めてしまう。最初は「マルタはNYに恋しているからボビー個人が目に入らないのだろう」と思っていたのだが、ドイル演出では、ボビーから「NYに恋する女」と見られたことにがっかりした、という風に読み取れる。
もう一つは大詰め、"Being Alive"から幕切れに至るボビーの動きである。この歌は周囲に振り回されず、かつ頼らず、1人で自立して生きていく決意を表明するソロだと思うが、問題は一番最後、ボビーのろうそくの消し方である。ケネディ・センターで観た時には強い息で一気にフッという感じだったが、今回はフーーッという感じ。「友情」という名のおせっかいや圧力や煩わしさから開放された安堵感のようなものが伝わってきた。思わず納得。
俳優たちはボビー役のエスパルザを始め、芸達者が揃ったという感じ。ただ客の入りが今ひとつで、僕が座った2階席は半分以上空いていた。もったいない。機会があればまた観てみたい。
2008年2月7日他 丸の内ピカデリー1他
Sweeney Todd(映画版)
配役:トッド=Johnney Depp
ラヴェット夫人=Helena Bonham Carter
アンソニー:Jamie Campbell Bower
ターピン:Alan Rickman
ジョアンナ:Jayne Wisener
トバイアス:Edward Sanders
女女乞食:Laura Michelle Kelly
ビードル:Timothy Spall
ピレッリ:Sacha Baron Cohen
指揮:Paul Gemignani
映画用脚本:John Logan
監督:Tim Burton
<感想>
ソンドハイム・ファンとしては、彼の最高傑作の一つである「スウィーニー・トッド」が映画化されるという情報を得て以来、舞台公演の映画化になるのか、それとも完全に映画として製作されるのか、といった点に注目していた。
しかし、いざ封切りが近付くと、少なくとも日本ではジョニー・デップ主演、ティム・バートン監督の新作映画としてもっぱら紹介された。ここ数年の映画をほとんど全く観ていない僕は、恥ずかしながら2人とも知らなかった。ただ調べてみると、デップは「シザー・ハンズ」(1990)で脚光を浴び、「エド・ウッド」(94)、「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(2003)、「チャーリーとチョコレート工場」(05)、「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト」(06)「同/ワールド・エンド」(07)などで実力派俳優として人気が高まってきたことがわかった。そう言われれば、これらの映画の存在自体は知っている。だから顔には何となく見覚えがあった。
バートンにしても、先の「シザー・ハンズ」「エド・ウッド」「チャーリーとチョコレート工場」や「バットマン」シリーズの監督と言われれば、作品だけは知っている。でもそれ以上のイメージはない。
ヘレナ・ボナム・カーターは元々知っていた。初期の「眺めのいい部屋」(86)や「ハムレット」(90)は観ていて、かわいいなあとは思っていた。でもバートンの恋人になっていたとは知らなかった。
あとの出演者のことは全く知らない。プログラムによるとローラ・ミシェル・ケリー以外はミュージカル出演経験がないらしい。はてさてどうなることか?
以下、舞台版との違いを中心に書く。そのため、便宜上舞台版の幕と場面を使いながら映画での流れを説明することとしたい。
○序奏
舞台版では舞台裏から漏れるような小さい音でオルガンが演奏されるのが普通だが、ここでは製作会社のロゴが表示されると大音量のオルガンが鳴り響く。その代わり"Epiphany"の中で"(And I'll) never see Johanna"に付けられた下降音型はあまりはっきり聴こえない。
「トッドのバラード」が始まると画面はもやに包まれる。もやと思ったのは雲の中で、そこから雨が落ち、ロンドンの灰色の街に降る。トッドの床屋の窓にも雨が当たるが、よく見るとそれは血の雨である。血の雨は窓のすき間から床屋に入って椅子の歯車から地下へとしたたり落ちてゆく。地下の厨房にある肉挽き機から人肉ソーセージがミミズのお化けのように飛び出し、血の雨は排水路から下水道へ、そして海へと流れてゆく。天(上流階級)から海底(下流階級)まで、ロンドンの社会を見渡していくようなイメージか。
ここで注目すべきことは、合唱が全く使われていないこと(以降も同じ)。登場人物たちの歌を民衆の合唱の中に埋もれさせたくなかったのだろうか。しかも、合唱パートに相当するメロディを他の楽器で補わず、舞台版と同じように演奏されている。要は「カラオケ版」に近いということ。(ただし舞台版で合唱が"Swing your razor wide"と歌う箇所で女声のヴォカリーズが加わっているようにも聞こえる。)だから初めて聴いた人にはメロディを追えないところが出てきて、わかりにくいかもしれない。
また、サイレンの音も使われない。
【第1幕】
○“No Place Like London”
舞台版では約2時間半かかる作品を映画版では2時間ほどに短縮しているので、当然カットはある。ただ、バラードが収まった後、このナンバーの冒頭で2回繰り返される"No
place like London"のフレーズ(金管がファンファーレ風に演奏)についても、2回目のフレーズ最後の"London"に相当する2音より前は省略されている。時間的にはわずかなのだからこれくらい残してくれてもいいじゃないか、と舞台を観た者なら思う。
船上で歌うアンソニーの手前にかぶるようにして青白く苦りきった顔のトッドが現れ、アンソニーの歌を遮るように"No
place like London"と苦々しく歌う。そして舞台版では次の“The Barber and His Wife”の導入部として歌われる、"There's a hole in the world"で始まる早口調のソロをここで続ける。
帆船が朝もやの中テムズ川を上り、跳ね橋やロンドンの街並が近付いてくる。
○“The Barber and His Wife”
船着場。トッドがアンソニーに向かって歌い始めると、回想シーンとなる。明るくややぼやけた映像、若いバーカー(トッド)がルーシーに抱かれた赤坊のジョアンナに花を見せてあやしている様を、物陰からターピンとビードルが見ている。ターピンがビードルに目配せすると警官2人が現れ、バーカーを殴って連行する。呆然とするルーシーに泣き出すジョアンナ。映画ならではの作り方である。
ここまでトッドとアンソニーのセリフはかなり省略されているが、最も重要なのは、ここで女乞食が登場しないことである。
アンソニーと別れたトッドが向かう先をカメラが先回りする。すなわち早回しでロンドンの街中をどんどん進んでゆき、フリート街に達する。
○“The Worst Pies in London”
ラヴェット夫人のパイ屋はL字型の道路の内側の角にある。今まで舞台版から想像していたイメージと異なり、道幅は広く人通りも多い。
ドアを開けたトッドの姿に気付いたラヴェットは彼を引っ張り込んでテーブルの前に座らせ、パイの埃を吹き払って彼の前に出す。調理台で新しいパイを作りながら歌うが、歌に合わせて麺棒でゴキブリ退治。一口食べたトッドはますます苦い顔になって吐き出し、エールを飲んでもまだのどが苦しそう。
映画版の追加シーンとして、歌い終わったラヴェットはトッドを奥の部屋へ案内する。その途中で彼は2階に続く階段に視線をやる。彼女は彼にジンを勧める。その後彼の「上の部屋を貸さないのか?」のセリフが出てくるのだが、このきっかけとして階段を見せたとしたら、蛇足かもしれない。あるいは、彼の心の揺れを見せるための仕掛けとして使ったのか?(この階段は他の場面には出てこない。)
○“Poor Thing”
ラヴェットが歌い始めると再び回想シーン。夫のいない床屋で泣き明かすルーシー。部屋には枯れた薔薇の花束が積んである。窓の外には新しい花束を持ってルーシーに熱い視線を送るターピンとビードルが見える。その後は歌詞通りのシーンが展開される。
舞台版では"No!"と叫んだ後トッドの"Would no one have mercy
on her?"が続き、これにラヴェットが"So it is you--Benjamin Barker."と聞くと、すかさずトッドは否定し「今ではスウィーニー・トッドだ」と名乗る。
これに対し映画版では"No!"と叫んだ後先にラヴェットの"So it is you--Benjamin Barker."が来て、トッドはこれに答えず"Would
no one have mercy on her?"と聞く。ラヴェットがこれに答えるセリフの中で再びBarkerの名を出すと、トッドはこれを否定して「今ではスウィーニー・トッドだ」と名乗る。
その後ラヴェットがトッドに「金はあるの?」などと聞くやり取りは省略。
店を出たラヴェットは外の階段を昇ってトッドを2階に案内。部屋の中は荒れ果てている。トッドがベビーベッドにかぶせられた布を少し上げると中に顔以外腐り果てた人形が現れる(この人形は“The Barber and His Wife”の回想シーンでルーシーが持っていたもの)。
ラヴェットが床下から布に包まれ、埃だらけの箱を取り上げる。トッドの剃刀の入った箱である。なぜ隠していたか経緯を語るラヴェットのセリフは短縮。
○“My Friends”
トッドが剃刀をかざして歌い始めるとそこに彼の顔が映り、剃刀の向こうにラヴェットの顔がぼやけて見える。この二重唱の意味を一瞬で映像化した見事なアングルだと思う。
ラヴェットはトッドの背後から歌いかけるがもちろん彼の眼中にはない。彼女の顔が剃刀に映ると不快な表情で"Leave me!"と舞台版にないセリフを吐いて彼女を追い出す。
"My right arm is complete again!"(ひょっとしてrightとは言ってなかったかも?)に続くバラードもオケのみで演奏。
○“Green Finch and Linnet Bird”
まず地図を片手にハイドパークを探すアンソニーが登場、ターピンの屋敷の前に出てくる。
次にジョアンナの部屋が映るが、小鳥屋は登場せず、窓辺にかごの鳥が既にいる。彼女は刺繍をしながら外を眺め、アンソニーを見つける。その様子をターピンが壁の穴から覗いている。
アンソニーもジョアンナに気付くが、人気を感じた彼女は窓辺から離れてしまう。
ここで女乞食が登場。アンソニーから小銭を恵んでもらい、ターピンやジョアンナのことを話すところまでは舞台版と同じだが、その後のスカートをたくし上げる下品な踊りはない。
舞台版のアンソニーは女乞食から求められるままに小銭を恵む優しい青年と位置づけられている(その後彼女の踊りに閉口して財布ごと地面に投げて追い出すが)。これに対し、映画版で彼が女乞食に施しをするのはこの時だけなので、ジョアンナのことを聞き出すための方便として小銭を恵んだと見ることもできる。
○“Ah, Miss”
省略。
○“Johanna”
女乞食が去った後アンソニーはすぐこれを歌い始める。ひと通り歌った後、映画版では以下のシーンがある。
屋敷のドアが開き、ターピンが親切そうな表情でアンソニーを招き入れる。書斎に案内し、ウイスキーを勧めるまではいいが、彼が船乗りだと聞くと「さぞあちらの経験も豊富だろうな」と世界中の春画のコレクションを見せ、ジョアンナを見つめた(gander)ことを問い詰める。「今度娘を見つめていたら生まれたことを後悔させてやる」と脅し、いつの間にか部屋の外に立っているビードルに目配せする。ビードルは裏口からアンソニーを追い出し、金属製の杖で打ち据え、荷物を放り投げ、倒れた彼の頭上に落とす。
何とか起き上がったアンソニーは再びこのナンバーを、より強い決意をこめて歌う。
○“Pirelli’s Miracle Elixir”
買い物客でごった返す聖ダンスタン市場。ラヴェットとトッドのやり取りは短縮。舞台版ではビードルがいることをトッドが好都合と考えるのに対し、映画版ではビードルの姿を見ると彼は懐の剃刀に手が行ってしまい、ラヴェットに止められて上着の下に隠す。復讐心に燃えてはいるが冷徹さを失っていない舞台版に対し、復讐心のあまり平静さを保つのも難しいというのが映画版。
ピレッリの小屋のカーテンからトバイアス(トビー)が登場し、ステージで太鼓を叩きながら客寄せし、歌い始める。後でも述べるが、この映画におけるキャスト上最高のヒットは、トバイアス役に少年を起用したことであろう。
舞台版ではトビーの宣伝にトッドやラヴェットだけでなく他の群集(=合唱)も次々と疑問を投げかけ、騒ぎが大きくなったところでようやくピレッリ本人が登場するが、映画版でトビーの歌に加わるのはトッドとラヴェットのみ。したがってやり取りも短縮。
「秘薬」をまがい物と糾弾する場面のセリフもかなり省略。ひげ剃りコンテストとなり、トッドとピレッリの前にそれぞれ客が座ると、2人とも見事な手さばきで前掛けを広げる。ピレッリの前掛けはイタリア国旗の模様。
○“Contest”
ピレッリはまず剃刀を研ぐが、研ぎ布を持ったトビーの親指に剃刀が当たるのか、トバイアスは顔を背けながら痛がっている。トッドはピレッリが最高音を張り上げている間にサッサッサッという感じで剃り終わる。
歯抜きコンテストの場は省略。
ピレッリは5ポンドを払った後客たちに丁寧に一礼してトビーを小屋の中へ蹴り入れる。自分も中に入って当り散らす音が聞こえる。この様子を見たラヴェットは「子どもがこき使われているのを見ると胸が痛むわ」と舞台版にないセリフを言う。トビーを引き取る場面の伏線ということか。他方舞台版ではビードルはトッドの顔が記憶の奥底に残っていたらしく、ラヴェットが慌てて自分の親戚であると言い繕うが、映画版ではビードルはトッドの顔に全く疑いを抱かない。
舞台版ではバラードが続くが、映画版では省略。
○“Johanna”
ターピンが自分を責めた後ジョアンナに求婚する場面だが、省略。その代わり以下のシーンが追加されている。
ジョアンナが門柱の陰に隠れているアンソニーを見つけると、窓を開けて部屋の鍵を彼に向かって投げる。彼は鍵を拾って立ち去るが、その一部始終はターピンに覗き見されている。BGMとしてアンソニーの"Johanna"が流れている。
その後のラヴェットと女乞食のやり取りは省略。
○“Wait”
窓から外を眺め、イライラしながらターピンを待つトッド。それをなだめるラヴェット。2人の姿がひびだらけの鏡に映し出される。
"Wait"を歌い終わった後階段を誰かがかけ上がる音がする。舞台版ではトッドは普通にアンソニーに会うが、映画版ではとっさにドア陰に隠れる。入ってきたアンソニーはいきなりラヴェットの姿を見つけて戸惑う。ジョアンナをさらった後一時かくまってほしいと頼まれたトッドは黙ってうなずくのみ(舞台版では短いながら了解するセリフあり)。
アンソニーが去った後トッドはピレッリとトビーがやってくるのを見つける。舞台版ではトッドとラヴェットがいる店に2人が入ってきて挨拶した後ラヴェットがトビーを連れ出すが、映画版ではトッドが「子どもは上げるな」とラヴェットに指示、彼女はそれに従って階段の下で2人に会い、トビーをパイ屋へ連れて行く。ラヴェット、パイをトビーに食べさせながらなぜピレッリと一緒にいるのかと尋ねる。するとトビーは彼が自分を孤児院から引き取ってくれたのだと答える。
舞台版でピレッリはトッドをゆする歌を歌う途中で殺されるが、映画版ではピレッリが高笑いしている間にトッドは剃刀でなく、まずストーブの上で沸かしている鉄やかんで頭を数回殴る。ピレッリはどっと倒れる。階下でラヴェットもトビーもその物音に気付くが、ラヴェット、とっさにボウルをテーブルにがんがん打ち付けてごまかす。しかし、トビーは仕立て屋へ行く時間であることを思い出し、階段をかけ上がる。トビーが床屋に入るとピレッリはおらず、トッドがやかんからカップにお湯を注いでいる。ピレッリが去ったとの言葉をトビーは信じずここで待つと言うが、トッドはトビーの座った木箱からピレッリの手がはみ出ているのに気付く。
舞台版ではトッドはトビーに「もっとパイをもらいなさい」の後少し間を置いてから「ジンももらうといい」と続けて言うことでトビーを去らせるが、映画版では「もっとパイをもらいなさい」と言われたトビーが「いいえ、ここで待ちます」と拒否。そこでトッドは「この子にジンを飲ませるように」とのラヴェットへの伝言を頼む。ようやくトビーも喜んで店へ下りる。トビーのトッドへの不信感が最初から抜き難いものであることを示している。
トッドは木箱を開けると虫の息のピレッリが起き上がる。ここでトッドは初めて剃刀でピレッリの喉を切り裂く。
○“Kiss Me”
アンソニーとジョアンナの密会の場面は完全にカットされている。これも意図があるようだが、具体的には後述。
場面は法廷。少年に絞首刑の判決を下すターピン。うなだれて泣き出す少年。
○“Ladies in Their Sensitivities”
法廷を出るターピンにビードルは賞賛の言葉。その後のやり取りもかなり省略されているが、その代わり舞台版にない次のやり取りを加え、2人の邪悪さを際立たせている。
ターピン「彼は本当に有罪か?」
ビードル「まあ何かしら悪さはしてますよ」
ジョアンナに求婚したが彼女は喜ばなかったといぶかるターピンに対し、ビードルはすかさず"Excuse
me, my load."と歌い始めるが、言い訳するターピンに対しすかさずトッドの床屋を紹介。つまり、舞台版の"Ladies
in their sensitivities, my load."以下の部分は省略。
○“Quartet”
省略。
パイ屋ではジンをがぶ飲みするトビーにラヴェットが呆れている。彼女が床屋に上がると、血に染まったトッドの袖を見て驚く。でもピレッリを殺した経緯を知ると死体から財布をちゃっかり失敬する。
その時トッドは窓からターピンが近付くのを発見(ビードルがターピンをトッドの店へ向かわせるやり取りは省略)。舞台版でラヴェットはターピンへの復讐を止めさせようとするが、映画版ではさっさと階下へ。
トッドのシャツの左袖は血まみれのまま。彼はあわてて上着を羽織り、間一髪ターピンが入る前に隠す。
○“Pretty Woman”
舞台版で並行して語られるラヴェットのトビーへのセリフは省略。
トッドはターピンのひげを丁寧に剃りながら機会をうかがう。ターピンの顔の右側から回り込むように左の首筋に刃を当てていよいよ決行、というその時、アンソニーが現れ、全ては台無しに。
ターピン、アンソニーと入れ替わりに上がってきたラヴェットのセリフも一部省略。
○“Epiphany”
怒りに燃えるトッドは両手に剃刀を持って街へ繰り出し、人々に片っ端から剃刀を見せたり、人込みの中で剃刀を振りかざしたりする。しかし彼に気付く人はいない。最後に彼は石畳の水たまりの前にうずくまり、再び両手の剃刀を高々と空にかざして"I'm
full of joy!"と叫ぶ。
場面は床屋の中に戻り、椅子の背にひじを乗せてそんなトッドを冷ややかに見つめるラヴェット。放心状態の彼を抱え店へ連れて下り、居間で眠りこけたトビーからジンの瓶を取り上げてトッドに一杯飲ませる。
○“A Little Priest”
ラヴェットは店の窓のカーテンを開けて外を眺めるうちに、ひらめく。歌が進むにつれて窓のカーテンを次々と開けてゆき、終盤ではラヴェットが舞台版と同じく麺棒、トッドは舞台版と異なり肉切包丁を持って踊る。最後2人は窓越しに外に向かって決めのポーズ。それを外から捉えるカメラが一気に引いてゆく。店内では盛り上がっているのに外からは密室の謀議のように見える不思議な映像。
続いて以下の場面が追加されている。
夜、ジョアンナの部屋。彼女が荷物をまとめている。そこへノックもなくターピンがドアを開ける。この家を出て行くというジョアンナに対し、より「適切な」家に移すと言い放つターピン。ビードルが彼女を捕らえ、無理やり馬車に乗せて走らせる。その様子を隠れて見ていたアンソニーは追いかける。ターピンはアンソニーに向かって「俺を殺せ!」と開き直るが、アンソニーは馬車を追う。
他方トッドの店。ろうそくの火の中でルーシーとジョアンナの写真を見つめているが、やがて思い立って自分で椅子を改造。
【第2幕】
次に舞台版で第2幕に相当する場面になるが、ここでも重大な変更がある。舞台版の曲順とは逆に、まず“Johanna”、次に “God, That's Good!”が歌われる。
○“Johanna”
トッドが店に来た客の喉を次々と剃刀で切ってゆく。舞台版ではペダルを踏むと椅子が伸びて足から地下へ落ちる仕組になっている場合が多いが、映画版では椅子は後ろに倒れ、切られた客は頭から真っ逆さまに地下へ落ちる。
その間アンソニーはジョアンナを探してロンドンの街中をさまよい歩くが、ついにフォッグ収容所にたどり着き、格子窓から外を眺めるジョアンナを見つける。収容所前でアンソニーがビードルに見つかり、追いかけられるシーンも省略。
途中から女乞食の“City on Fire!”が加わるのは舞台版と同じ。
この場面の最後の和音が鳴るところでトッドは血だらけの手でルーシーとジョアンナの写真をガラス越しになでる。
○“God, That’s Good!”
ラヴェットの身なりは小ぎれいにはなったが衣裳の色は黒のままで、派手にはなっていない。それにしてもこの場面がやや奇異なのは、見た目は賑やかなのに歌っているのはラヴェットとトビーのたった2人ということである。
仕掛け椅子はトッド自身が作ったので、当然椅子をめぐるトッドとラヴェットとのやり取りは省略されている。しかし、終盤でトッドは店から出て階下の賑わいを眺めている。ラヴェットが店の札を"Sold
out"にひっくり返すが、床屋の新しい客が階段を昇っていくので、再び"Open"に戻す。店にしのび込もうとする女乞食を見咎めたラヴェットがトビーに"Throw
the old woman out!"と2回目に叫ぶところで終わる。
○“By the Sea”
ラヴェットの空想が映像化されている。トッド、ラヴェット、トビーの3人はピクニックに来ている。トッドとラヴェットが並んで敷布の上に座り、トビーは2人から離れて後ろで釣りでもしている様子。
ラヴェットが歌い始めると、場面は砂浜に変わり、トビーと3人で座って海を眺めている。次に海に近い別荘のベランダでビーチチェアに並んで座るトッドとラヴェット、客を呼んでデザートを振舞うラヴェット、海辺の木製の橋で散歩する3人(トビーは背が高くなっている)、教会で結婚式を挙げるトッドとラヴェットといったシーンが次々に現れ、歌い終わると元の情景に戻る。トッドは終始暗い顔をしているが、結婚式の場面では牧師に結婚の意志を聞かれて硬い表情でうなづいたり、ラヴェットに口先だけキスしたり、といったユーモラスな表情もわずかだが見せる。
トッドが歌の途中で再三合いの手のように入れる"Anything you say"は映画版では1回のみ。
舞台版ではこのナンバーはパイ屋の奥の居間で歌われ、引き続き復讐にしか頭のないトッドをラヴェットがたしなめるところにアンソニーがやってくる。映画版ではこのナンバーが終わった後、場面は床屋に変わり、窓から外をぼんやり眺めるトッドにラヴェットが朝食を運ぶ。そして「ルーシーの顔を覚えている?」と聞き、返事がないと「忘れちゃったでしょ」と言い、何とか復讐を忘れさせようとする。そのやり取りの間にアンソニーが入ってくる。ジョアンナの居場所を知ったトッドがアンソニーに入れ知恵する場面も短縮。
次にトッドはラヴェットにトビーを呼ぶよう依頼。ラヴェットは「あの子を巻き込まないで」と言って下りる。舞台版ではトッドはターピン宛の手紙を自分で届けるが、映画版では手紙をトビーに届けさせる。しかも「ターピンに直接渡せ」「寄り道するな」など彼に細かく指示してから行かせる。
○“Not While I’m Around”
舞台版では店の仕事を終えたトビーがラヴェットに報告するところから始まるが、映画版では居間でラヴェットが暖炉の前のソファに足を伸ばして座り、居眠りしている様子。そこへトビーが帰ってくるとラヴェットは「どこへ行っていたの?もうくたくたよ」と尋ねる。トビーは「自分が入っていた孤児院を見てきた」と答える。つまりトッドの使者としてトビーが店を離れたため、この日はラヴェット1人で店を切り盛りしていたことがわかる。
トビーが歌い始めてしばらくは、キーが下がっている(オリジナルは変イ長調、映画版は変ホ長調→ニ長調)以外舞台版とほぼ同じ展開だが、トビーがピレッリの財布をラヴェットが持っているのに気付いて以降、映画版は以下のような展開となる。
警察へ通報しようとするトビーを止めたラヴェットは自分から彼を抱き寄せ、トビーの歌を引き取る。そしてパイ作りを手伝うよう頼み、トビーを地下の厨房へ連れて行く。床にある鉄の扉を開くと階段があり、地下へ通じている。厨房に入るとラヴェットはトビーにまずオーブンを見せ、次に肉挽き機を見せてやらせる(挽き方のセリフも短縮)。
そうやって仕事を任せた後ラヴェットは1人厨房を出て外から扉に鍵をかける。ラヴェットの目に涙。つまり、彼女は財布のことを知られた時点でトビーを殺さざるを得ないと覚悟を決めている。ただ、それは愛するトッドを守るためでもある。
アンソニーが収容所に入り、ジョーナスに案内されて入った金髪女たちの部屋からジョアンナを見つけ、連れ出す。舞台版ではジョアンナが発砲するが映画版では2人とも発砲せずアンソニーが銃を構えるだけ。その代わり残りの女たちが一斉にジョーナスを襲う。
○“Parlor Song”
歌は省略。
トッドとラヴェットが急いでトビーを始末しようと店の前でひそひそ話しているところへビードル登場。トッドは言葉巧みにビードルを店へ誘い込む。その様子を女乞食が物陰から眺めている。
他方地下の厨房でパイを食べていたトビーは中に爪が入っていたのに気付き、やがて肉の原料が何かを知る。そこへビードルが落ちてくるので逃げ出そうとするが扉は開かない。
舞台版では厨房にトビーがいることを知らないトッドがビードルを地下へ落としてしまうのでラヴェットが狼狽するのだが、映画版の場合は意図的にトビーを閉じ込めたので、この点は問題にならない。
○“City on Fire!”
省略。
○“Final Sequence”
トッドとラヴェットが厨房から下水道にかけてトビーを探すが見当たらない。
アンソニーが水夫姿のジョアンナを連れて床屋に入ってくるが誰もいない。しばらくここで待つよう行ってアンソニーは去る。ここでのやり取りで舞台版と決定的に異なるのは、ジョアンナがアンソニーにすらまだ心を開かず、将来に希望を持ちきれていないということである。舞台版の"Kiss
me"が省略されたのも、彼女の心情をこのように解釈すると、ロマンチックな場面は不要になったということだろう。ちなみに2人が語り合う場面はここしかない。
ジョアンナは部屋の中を眺め、赤ちゃんの時の自分の写真を見ているが、ビードルを呼ぶ女乞食の声がするので木箱の中に隠れる。女乞食が子守歌を歌っているとトッドが現れる。そこで彼女は初めて"Don't
I know you, mister?"と尋ねるが、トッドは気にも留めずに喉を切り、地下へ落とす。ただし、女乞食は椅子の後ろに立っていたので、「被害者」たちの中では唯一足から地下へ落ちることになる。
ターピンが登場、椅子に座る。トッドはターピンの喉を剃刀で何度も突き刺してから喉を切るので、たっぷり返り血を浴びる。ターピンを地下へ落とし、剃刀に休むよう歌っていると木箱の蓋がわずかに開いていることに気付き、中からジョアンナを引っ張り出して椅子に座らせる。しかし、地下からラヴェットの悲鳴が聞こえるので「この顔を忘れろ」と凄んで地下へ向かう(舞台版ではサイレンの音にトッドがハッとする隙に逃げ出す)。
地下では虫の息のターピンがラヴェットのスカートの袖をつかんでいる。恰幅のいいビードルと女乞食の上にターピンが落ちてきた分衝撃が少なかったということだろう。女乞食をトッドの気付かないところへ運びかけた時トッドが入ってきて、ラヴェットにオーブンの扉を開けるように言う。炎の明るさでトッドは女乞食がルーシーだったことに気付く。トッドがラヴェットをオーブンに投げ入れるまでのやり取りも短縮。トッドは剃刀を床に落とし、座り込んでルーシーを抱き上げ、膝の上に乗せる。排水溝の下から出てきたトビーが剃刀を拾い上げ、トッドが"He was"まで歌ったところで喉を切る。そこから流れる血がルーシーの顔を覆ってゆく。
【まとめ】
ここまで書けば繰り返すまでもないが、映画版における登場人物たちの描き方は舞台版と少し異なる。最も大きく異なっているのはジョアンナである。彼女は長年の間ターピンに監禁同様の状態に置かれていたために、アンソニーの愛にも素直に応えられず、過去の恐怖から容易に抜け出せそうにない。これではアンソニーと一緒になっても果たして幸せになれるのか、観ている方も不安になる。
それ以外の人物については性格をより単純化、明確化している。トッドは復讐に燃えている割には精神的にもろく、ラヴェットはトッドと結ばれるためには手段を選ばず、トッド以上に計算高く冷徹である。ターピンとビードルはお決まりと言っていいほどの極悪人に仕立てられている。
そして、トビーを子役に演じさせることで、トッドとラヴェットの行動に倫理的な光が容赦なく当てられることになる。2人の悪事はしばしば正直者のトビーの鋭い視線にさらされ、そこから逃れようとしてさらなる悪事を重ねることになる。そう考えると最後にトッドの喉を切り裂くトビーの行為は、母と慕うラヴェットへの復讐であると同時に、天に代わってトッドの罪に罰を与えていると見ることもできる。
ただし、そこで子供のもう一つの側面である幼さがトッドとラヴェットに与えた影響を無視するわけにはいかない。トビーは最初からラヴェットを100%信用し、トッドを100%疑っていた。言い換えれば、ピレッリの一件ではトッドとラヴェットが手を組んでいたことをトビーは最後まで見抜けなかった。しかもそのために一時自分の身の危険を招くことになったことにも気づいていないであろう。
このようなトビーという人物の純粋さと未熟さを表現するには、大人より子供に演じさせる方がはるかに効果的である。バートン監督、恐れ入りました。トビーを演じたエドワード・サンダースも監督の期待に大いに応えたと言っていいだろう。音楽的にも、ボーイソプラノで歌われる“Not While I’m Around”には思わずホロリときた。
他の俳優たちも人物の表現については申し分がない。デップは歌いぶりにやや単調なところが見受けられたものの、監督が意図したとおりのトッド像を示して見せた。ボナム・カーターには少女のような愛らしさと魔法使いの老婆のような意地悪さとが不思議に同居している。歌いぶりもまずまず。そして、ターピンを演じたアラン・リックマンのアンソニーに対する怒りの表情と、"Pretty
Woman"でひげを剃られながら"silouetted"と歌う時のうっとりした表情とのギャップは見事である。ビードル役のティモシー・スポール、ピレッリ役のサーシャ・バロン・コーエンも、それぞれ自分のために書かれた役であるかのように歌い、演じた。
音楽面で最も重要なことは、多くの舞台版より大規模な編成のオケで演奏されたということである。ソンドハイムの中でも「スウィーニー・トッド」の音楽が大管弦楽にふさわしいものであることは、これまで何度も指摘してきた。今回はその意味ではほぼ理想的な条件で音楽が流れている。
プログラムによるとオケのメンバーは総勢64名とのこと。これを元に各パートの人数を推測してみると、
管楽器:フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット(またはサックス?)、ホルン、トランペット各2、トロンボーン3で計15
打楽器:3
ハープ:1
オルガン:1
弦楽器:64−(15+3+1+1)=44→第1V=12、第2V=10、Va=8、Vc=8、Cb=6
といった感じだろうか?オペラ公演と遜色のない規模であることがわかるだろう。指揮のジェミニャーニも思う存分やれたのではないだろうか。
また映画版で追加されたシーンのために新たな曲が追加されているのも嬉しい。例えばトッドが真夜中に椅子を改造するシーンなど、"Johanna"のメロディを変奏したゾクゾクするような音楽が流れていた。
それにしても、昔より高くなったとは言え、映画は1回1,800円。ミュージカル1回観るお金があれば、4,5回は観られる。そのおかげで今回は細かいところまでじっくり確認しながら観ることができた。いやあ、映画って本当にいいもんですねえ。