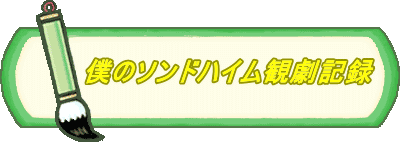
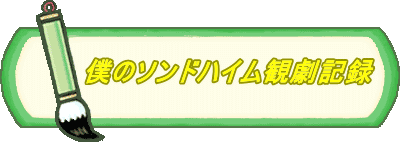
![]()
2005年5月25日 シグニチャー劇場(アーリントン(ヴァージニア州))
Pacific Overtures
主な配役:語り、将軍、天皇=Donna Migliaccio
香山=Will Gartshore
万次郎、米国提督他=Daniel Felton
阿部、占い師他=Steven Cupo
たまて、ペリー提督他=Matt Conner
老人、オランダ提督他=Harry A. Winter
指揮:Jon Kalbfleisch
オケ:Jon Kalbfleisch(キーボード)他計7名
演出:Eric Schaeffer
<感想>
【前置き】
宮本亜門演出で再評価されたと言っていい"Pacific Overtures"ですが、残念ながら昨年ブロードウェイでの彼の演出は、米国の評論家たちをうならせるまでには至りませんでした。
となると、3年前ケネディ・センターで行われた"Sondheim Celebration"で斬新な演出をいくつも見せたエリック・シェーファーがどのような視点でこの作品を取り上げるか、ファンならずとも注目せずにはいられません。ひょっとしたら、この作品の決定版とも言えるプロダクションになるかも。そんな期待に胸ふくらませながら、1年半ぶりにシグニチャー劇場へ出かけました。
出し物によって舞台、客席の位置が自在に変化するシグニチャー劇場ですが、今回はもぎりの先の通路を抜けると正面奥に舞台、そのホリゾント=紗幕の奥にオケ、それ以外の舞台の三方を囲むように客席が設置されています。僕の席は自由席でしたが、舞台下手サイドの最前列に運よく座れました。正にかぶり付きです。
で、どうだったか?先に結論を申しますと、今回のプロダクションをどう評価すべきか、僕の頭の中は長い間混乱していました。その原因は、筋が通っているようでぶれているように見えたり、シェーファーの独創と思われるアイデアと他のプロダクション(特に宮本版)の模倣にしか思えない部分とが混在していたりしたことにあります。だから観ている間どうにも落ち着かないのです。
【1.配役】
順を追って整理しましょう。まず配役ですが、このプロダクションでは俳優がわずか10人しか出てきません。香山役と元々3役をこなす語り手以外の俳優は4つ以上の役を掛け持ちします。特に万次郎役や阿部役の俳優は大変だと思います。ミュージカルの世界ではオーケストラの人数がどんどん減っていく傾向にあり、1人の奏者が木管楽器を何種類も吹いたりヴァイオリンとヴィオラを兼ねたりといったことが当たり前になってますが、配役の面でも同じ傾向が広がってきたのでしょうか?「いやあ、よく10人でやったねえ」と手放しで感心できないのが正直なところです。
むしろシェーファーらしさが出たという点で最初に挙げるべきは、語り手役でしょう。10人のうち女優は2人しかいません。「ああ、たまて役と師範の娘役でしょ?」ブーーッ!1人(Channez
McQuay)は将軍の妻他7役をこなし、気をつけて見ないとどこに彼女がいるのかわからないくらい。
そしてもう1人の女優、ドンナ・ミリアッチョ(2003年「ローマで起こった奇妙な出来事」のドミーナ役)が受け持つのが何と語り手なのです。ただ、これも最初のうちは半信半疑でした。後で述べる出で立ちと声のせいだと思います。となると、このプロダクションでは、女性役は全て男優がやっているということになります。
こう書くと「あ、なるほど、歌舞伎風演出ね」と思われることでしょうが、断定するのはまだ早い。確かに歌舞伎にヒントを得ているのは明らかでしょうが、むしろ歌舞伎における女形を「性の遊び」と捉えて今回のプロダクションに持ち込んだような気がするのです。なぜなら、単に男優に女性役をやらせるだけでなく、女優にも男性役をやらせるからです。最もややこしいのは芸者屋のおかみ役。これはもちろん女性役ですが台本上は男優が演じることとなっています。でも今回はわざわざ女優にやらせています。このような男女間の入れ替わりを演出上のスパイスとして用いているようです。
【2.舞台装置と衣裳】
逆に「歌舞伎風演出」と言い切れない理由の一つが舞台装置です。能舞台のような正方形の木の舞台が客席に向かって張り出しています。これを宮本演出の影響と言わずして何と言えばいいのか?違いは鳥居がないことと、舞台の周りに水が張られていないこと。代わりに奥の両端にいろんな長さの棒が竹林のように立っています。また、ホリゾントの奥に、横長の紙の帯をつなげたような太陽が上半分だけ見えています。
これは僕の勝手な想像ですが、装置デザインも担当したシェーファーとしては、古代ギリシャの円形劇場を日本風にアレンジしたらたまたま能舞台みたいになったのではないかと思うのです。なぜなら俳優の動きを見ると、アンサンブルの場面では舞台の3辺にバランスよく俳優を配置して歌わせるし、ソロの場面でも両端の客に向かって歌うよう巧みに俳優を動かしているからです。少くとも能役者が両脇の客を意識して演じることはないはず。
そして2〜4個の木箱(立方体)を場面に応じて舞台の様々な場所に配置します。正面奥に2つ並べた間に将軍が座るかと思えば、"Someone
in a Tree"では下手に3つ積み上げて木を表現します。
最初のナンバーで集合する登場人物は全員顔を白く塗り、黒無地の学生服風上着とズボンを身に付けています。顔は歌舞伎風だが衣裳はこれまた宮本風(あるいはコシノ風)。髪型は語り手のようにまげを結っている人もいれば、そうでない人もいます。
劇が進むにつれて俳優たちは黒以外の衣裳も着ますが、日本人の目から見ると妙なものが多い。阿部ら幕臣の衣裳は平安時代の貴族が着た束帯風、貴族の衣裳は浴衣風(!)、将軍の母の髪型や老人のひげはどう見ても中国風だし、阿部は第2幕で将軍になると山伏の頭巾(ときん)みたいな冠をおでこに乗せるし…
最も違和感があったシーンが2つ。まず第1幕"There Is No Other Way"で香山が正装するシーン。黒一色の衣裳の上から濃淡様々な青色に染めた着物風上着を羽織り、帯を締めるところまではいいのですが、その後足下の裾をたくし上げて背中の帯の下にはさむ。これじゃあまるでドジョウすくいか岡引(おかっぴき)です。少くとも「浦賀町警察長官」にふさわしい格好ではない。
もう一つは将軍付きの医師が「菊の花茶」を茶道で普通使うお椀で作った後わざわざおちょこに入れて飲ませるシーン。全く同じ仕草を第2幕の万次郎もします。誰がこんな動きを思いついたんでしょう?
シェーファーとしては時代考証にとらわれず自分が見聞きした日本関係情報を基に自由な発想でデザインしたつもりでしょう。でもこちらとしては、アメリカ人はまだ日本文化を誤解しているのか、それともわかった上でわざとアレンジしているのか、判断つきかねる場面が多いのです。気にするなと言われてもどうしても気になってしまうのですね、これが。
【3.台詞回し、演出】
では、みなさんお待ちかね、語り手の第一声、"Nippon"はどんな感じだったか?
これがオリジナル・キャストの歌舞伎風、新国・宮本版の国本風、ブロードウェイ・宮本版のウォン風のいずれとも異なるものでした。「にっぽーん!」と大きな声でゆっくりめに発音していましたが、妙な誇張はなく、あくまで英語劇の枠に収まる表現だったと思います。
その後はブロードウェイ・宮本版に近いスムーズな台詞回し。しかし、テンポは速く、立て板に水を流すような感じ。以前別のソンドハイム作品でも感じたことですが、シェーファーは俳優の台詞にほとんど間を取らせないのですね。ウォンさんでさえ、俳句を引用するところなどはさすがにもったいぶった言い回しをしていましたが、ミリアッチョはさらにあっさりした言い回し。ただし太くてしっかりしたアルトのおかげで何とか語りが頭の中を素通りせずにすむという感じ。
しかし、このような速い台詞回しのおかげで、本来もっと受けるはずの場面が大した反応もなく過ぎ去ってしまうことがしばしばありました。一つだけ例を挙げれば、第1幕第5場で語り手が将軍に変身する場面。語り手がそのまま将軍のいるべき位置に座るだけで、衣裳を替えるわけでもなく何かもったいぶった台詞回しをするでもない。観客の中で何が起こったのか気付かない人もいたでしょうね。彼の演出手法で僕が気に入らない点の一つです。
逆にシェーファー演出と宮本演出の違いが非常に面白い形で明らかになった場面が2つあります。1つは第1幕第5場。宮本演出では、将軍の家臣たちが占いやらお祈りをするたびに黒船の汽笛が響き、何の効き目もないことがわかるわけですが、シェーファー演出では汽笛の代わりに砲声が響き渡る。
もう1つは同じく第1幕の第6場"Poem"の後帰宅した香山がたまての遺骸を発見する場面。宮本演出では香山は終始無言で語り手だけが泣くわけですが、シェーファー演出で香山は最初一声だけ泣き叫ぶ。
どこからこの違いが出たのか?僕は宮本演出が「日本人から見た黒船騒動」であるのに対し、シェーファー演出はやはり「アメリカ人から見た黒船物語」なのだと思うのです。宮本さんが、あの当時の平和ボケした日本人は汽笛くらいの音でも怯えきってしまった、というコンセプトを示したのに対し、シェーファーは「アメリカ人が汽笛みたいな悠長な脅し方をするか?大砲ぶっ放したに決まってるじゃないか」と考えたのではないでしょうか。
香山の反応にしても、宮本さんは「武士なら妻の死を前にしても絶対万次郎に聞こえるようには泣かなかったはず」と確信していたのに対し、シェーファーは「いくら武士だって妻の死を見たら思わず一声くらい泣き叫ぶのが人間として当然」と考えたのではないか。
以下、それ以外に僕が気が付いた演出を整理しておきます。
○第1幕
第2場、香山が出かけた後たまては自害。これも宮本アイデアですね。
第6場、香山のアイデアを聞いた阿部と老中2人は大笑いするが、阿部が彼のアイデアをほめると他の老中2人は怪訝な顔をする。
第9場、小屋はホリゾントに障子のような衝立をおくことで表現。ペリー提督は原宿のコギャルが履くような高足ブーツ(ただし星条旗模様)で登場。
○第2幕
第1場、"Please Hello!"でイギリスの提督は缶入り紅茶をプレゼント、オランダの提督は木靴を履きチューリップを持って登場、ロシアの提督は毛皮のコートから雪を降り散らしながら歌い、フランスの提督はベレー帽をかぶっている。このあたりの処理はさすがにうまいですね。
第4場、香山が手紙を書いている脇をたまてが通り過ぎる。これも日米の演出家の違いを感じさせる場面ですね。
第6場、阿部や香山が殺害される殺陣のシーンはスローモーションで演じられる。
同じく第6場、明治天皇は客席側から白の着物風衣裳で登場、アンサンブルは黒の衣裳、棒術で使うような1mくらいの棒を全員持って"Next"を歌い始める。途中で原爆が落ちるところも宮本アイデアですが、シェーファーはそのことをよりはっきり伝えるため、ホリゾントに原爆投下のシーンを映写。俳優たちはその映像が流れる中後半部を歌っていきます。戦後日本の躍進振りを表す台詞は1991年のロックフェラーセンター買収に始まり、ヤンキースの4番に松井がなったことなど最近の事象を取り上げています。
語り手の最後の台詞の後、アンサンブルが"Next"を連呼するうちホリゾントの太陽が昇ってその完全な姿を見せ、一同がそこへ向かって手を差し伸べるような仕草をして暗転。
【歌いぶり】
いつものことながら、シグニチャー劇場の公演はPAなしですから、俳優たちの生の声を楽しむことができます。もちろんちゃんと発声ができてなかったり、ちょっとしたミスがあったりしたら一目瞭然ですから、怖い面もありますが。
今回に関して言えば、みなよく歌えていたのではないでしょうか。生ってやっぱり聴いていて気持ちがいいもんですね。ちょっとしたことですが、第2幕"Pretty
Lady"の最後の音、水夫の1人がFの低音をしっかり出しているところなど、思わずぞくぞくしてしてしまいました。
先にも述べたミリアッチョが存在感ある語り手役を演じた他、老人やオランダ提督など7役を演じたハリー・ウィンター(2003年"Follies"でBuddy役を好演)が全く異なるキャラクターを見事に演じ分けていたのが特に印象に残りました。
【まとめ】
先にも書きましたが、今回のシェーファー演出を一言で言うなら「アメリカ人が見た黒船物語」だと思います。もう少し詳しく言えば、彼は、アメリカ人が黒船を通じ日本に対して行ったことをアメリカ人に思い起こさせようとしたのだと思います。そう考えると先に述べた衣裳や仕草の混乱も、多少説明が付くような気がします。例えば茶の飲み方など、おそらくアメリカ人の中でもおかしいと思った人がいたはずです。ではなぜあんな動きをさせたのか?それは「ほら、アメリカのみなさん、あなたたちは日本のことをまだこんな風に誤解していませんか?」というメッセージだったのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
日本人観客の1人としては、それはそれで面白いと思う反面、少し物足りない感じがしたのも事実です。なぜなら日本側の登場人物のいろんな言動がアメリカ人向けに発せられているために、シェーファーの日本や日本人に対する思い、考え方が今一つ明確に伝わってこないからです。アメリカの劇場でアメリカの観客に向けて見せているのだから当然なのかもしれませんが、彼の日本観みたいなものがどこかににじみ出ていなかっただろうか、いまだにあれこれ振り返っては頭をひねっているところです。でも、それは彼が日本でこの作品を演出する機会でも来ない限り、見つける方が無理なのかもしれません。
2005年6月22日 バーンズ・アット・ウルフ・トラップ(ヴィエンナ市(ヴァージニア州))
Sweeney Todd
主な配役:トッド=Matt Boehler
ロヴェット夫人=Audrey Babcock
アンソニー:Alexander Tall
ターピン:Jason Hardy
ジョアンナ:Maureen McKay
トビアス:Javier Abreu
女乞食:Hanan Alattar
ビードル:Jason Ferrante
ピレッリ:Nicholas Phan 他
指揮:James Lowe
オケ:ウルフ・トラップ・オペラ・カンパニー管
演出:Joe Banno
<感想>
ワシントンDCから車で約40分、ダレス空港に向かって走る途中で降りるとWolf
Trap国立公園がある。アメリカの国立公園と言えばグランド・キャニオンやヨセミテといった雄大な自然を想像するのが普通だろうが、この公園はユニークで、National
Park for Performing Arts、つまり自然の中で舞台芸術に親しむことを主目的として設置・運営され、そこで行われる様々な催しはワシントンの夏の風物詩となっている。有名なのはFilene
Centerと呼ばれる屋根付野外劇場で、オーケストラのコンサート、ミュージカル、「リバー・ダンス」など多彩な公演が行われる。
その同じ公園内にBarnsと呼ばれる小劇場がある。Barnとは元々納屋、家畜小屋という意味だが、山小屋を大きくしたような感じの建物の中に入ると、内装も全て木造り、シェナンドーあたりへ登山に来たような気分になる。劇場は2階建て、バルコニー席の最前列には1辺30cmはありそうな角材が手すりとして渡されている。客席数は300席強。Filene
Centerと異なり、チケット入手は困難を極める。
毎夏この劇場で若い歌手たちが中心のウルフ・トラップ・オペラ・カンパニーが公演を行う。今年はモーツァルトとともに「スウィーニー・トッド」が取り上げられるというので、とにかく駆けつける。
公演が終わるまで全く気付かなかったのだが、夏にこの作品を上演するというのは、ひょっとしたら歌舞伎座で「東海道四谷怪談」をやるようなものかもしれない、とふと思った。そうか、要は「納涼ミュージカル」か。そんな英語はないだろうが…
それはともかく、ここではお化け屋敷のようなからくりでこのスリラーを見せていく。舞台では「人」の字に似た形に壁が組み合わされている。一見コンクリートの打ちっぱなしのような無機質な壁をよく見ると、あちこちに戸や切り窓が付けられている。下手の壁からロヴェットのパイ屋の調理台が引っ張り出されたり、切り窓が開いて小鳥売りが顔を出したり、中央やや下手寄りの観音開きの扉の奥からジョアンナのいるバルコニーが出てきたり、手品のような感じで場面が変わる。
中央のシャッターが開くとトッドの店になる。殺人用の椅子は客席側に向いて置かれているが、首筋を切った後180度回転させて舞台奥へ死体を送るようになっている。
開演前、一旦舞台が暗転になる。舞台前方に並ぶ通気孔から光が差し始めると、白い椅子が舞台に散乱し、死体があちこちに横たわっている。序曲が始まると死者がが少しずつ甦りながらバラードを歌う。全員コートの下にシャツとズボンを着ているが、首の下は赤く染まっている。
彼ら、すなわち群衆はこの物語の目撃者としての役割も担う。第1幕第1場ではコートで首元を隠し、傘を差してトッドとアンソニーのやり取りを見ているし、第2場でトッドがカミソリとの再会を喜ぶ歌を歌っている時も、途中から群衆が何人か出てくる。彼らは椅子に座って次の場、つまりジョアンナとアンソニーが出会う場面も見つめている。
天井からは、肉屋の冷凍庫にあるみたいなハンガーが下がっていて、第2幕になるとそこに死体、いやおそらくこれからパイの材料になる人肉が吊されている。"City
on Fire"で脱走してきた精神病患者たちはそのまま舞台に残り、女乞食(ルーシー)殺害からトッド自身が命を落とすまでの一部始終を見つめている。
演出のジョー・バンノは米国内の演劇・オペラの演出をする傍らワシントン・ポスト紙のクラシック音楽の演奏批評も手がけている。そんなユニークな経歴のせいか、観客をミュージカルの鑑賞者に終わらせることなく、トッドたちの世界へ引き込み、それこそ新聞記者かパパラッチのような目でこの物語を捉えさせようとしている。
トッド役のマット・ベーラーはフランケンシュタインみたいな大男。少しこもった声で歌いぶりもやや平板だが、動きは身軽。一見ぼーっとしているようで実は「総身に知恵が回りきった」という感じで、これはこれで怖いものがある。ロヴェット役のオードリー・バブコックは、第1幕"The Worst Pies in London"ではもたついていたが、第2幕から声の乗りがよくなり、"By the Sea"はなかなか楽しめた。アンソニー役のアレクサンダー・トールは見た目は悪くないのだが、声が暗い。プログラムには「バリトン」と書かれている。どおりでねえ。こりゃミス・キャストだろう。ターピン役のジェイソン・ハーディがこの日の歌手の中では一番よかった。深みがあるのによく通る低音で、特に第1幕の"Pretty Woman"でのトッドとのやり取りには背筋がゾクゾクした。
オケの弦はヴァイオリン6、ヴィオラ2、チェロ2、コントラバス1。ミュージカル劇場で上演される場合の標準的編成か。僕としてはもう少し弦の厚みがほしい。
いや、ぜいたくは言うまい。小劇場で観る「スウィーニー・トッド」ほどぜいたくなことはないのだから。
2005年6月29日 シグニチャー劇場(アーリントン(ヴァージニア州))
Pacific Overtures
主な配役:語り、将軍、天皇=Donna Migliaccio
香山=Will Gartshore
万次郎、米国提督他=Daniel Felton
阿部、占い師他=Steven Cupo
たまて、ペリー提督他=Matt Conner
老人、オランダ提督他=Harry A. Winter
指揮:Jon Kalbfleisch
オケ:Jon Kalbfleisch(キーボード)他計7名
演出:Eric Schaeffer
<感想>
前回のレポートをアップした後、エミリーさんのご友人の方から、今回のシェーファー演出をどう解釈するかについて、詳細なメールをいただきました。一言で言えばシェーファーは、日本でうまくいったのに味を占め、アフガニスタンやイラクなど世界中の国に自分たちの文明と価値観を押し広げようとする現在の米国の姿を見せようとしたのだ、ということになりましょうか。
今回この解釈を念頭に置きながら観てみました。で、どうだったかと言うと、恥ずかしながらさらに僕の頭は混乱してしまいました。観劇後2ヶ月以上たった今でも整理がつかない状況です。
でも、あまり放っておくわけにもいかないので、現時点の正直な感想を書いておくことにします。僕としてはその方の解釈に一定の説得力を感じたものの、納得するところまではいかなかったということです。しかし「じゃあおまえはどうなんや?」と言われても明快な答えがまだ出せないのです。
今回のPOの解釈については、引き続き僕自身の課題とさせていただきたいと思います。近いうちに何とか僕の考えを整理してこのサイトの別の所にでも書いてみたいと思います。お待たせした上にこんなことになってすみません。