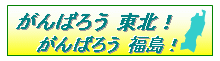CAEとはWhat's CAE
導入時の注意点
CAEソフトウェア(以下CAEソフトと略)の導入は慎重に進めることが肝要です。なぜなら、CAEを上手く活用するには、導入・運用に際し「人、モノ、カネ」が必要になるからです。「CAEソフトを導入すれば全て解決!」とは行きません。安易に「まずは導入して、具体案は後々決めよう」という手法はお勧めできません。
では、CAEソフト導入の際に気をつけることは何でしょうか。少し具体的に考えてみましょう。
【注意1】CAEソフトは値段が高い
CAEソフトの買取価格は基本的に高額(1本数百万円以上)であり、さらに毎年、年間の維持費用(購入価格の15〜20%)が発生します。ソフトウェアのバージョンUPはしなくて良い、質問サポートもなくて良い場合は、維持費用は発生しません。しかし、ハードウェアのOSのバージョンUPは出来なくなりますから、将来も作業環境は固定化されてしまいます。
【注意2】専用設備にはお金と場所が必要
CAEソフトのような科学技術計算をするハードウェアは、基本的に大量のメモリや高性能のCPU、そして書込み性能に優れたハードディクス等を搭載する高額な設備になります。また最低でもPCワークステーションクラスの設備になりますから、大きさもタワー型PC程度になり、設備の設置場所を確保する必要があります。事務所のスペースが足りているかどうか、検討しなくてはなりません。
【注意3】CAEソフトは万能ツールではない
「仮想実験で試作・試験をなくせるのではないか」と考えがちですが、これは出来ません。また、「自然現象では簡単に見える問題」であっても、「物理計算となると難易度が高い問題」があります。このような場合は、試作試験を行った方が短期間で成果がでます。この原因は、CAEソフトが高性能な電卓であるからです。つまり、どんなに素晴らしい電卓でも、計算の仮定を現実に則した形に定義できなければ、答えは現実のものと異なってきてしまいます。
CAEソフトは万能ツールではないのです。検討できる範囲が限られたツールであることを認識しなければなりません。
【注意4】専任の人材を確保する
CAEソフトを使いこなす人材の確保のことです。実はこの部分が一番高いハードルになります。CAEソフトを使いこなすためには、ソフトの使い方はもちろん、有限要素法や差分法といった解析手法、また解析の結果を正しく評価できる学術知識が必要です。CAEソフトは高性能な電卓ですから、入力や設定が誤っていても必ず結果が出てきます。この部分の正誤を判断できる人材が必要です。専任者ともなれば、間接的ですが、技術者の人件費もCAE導入費用と考える必要があります。
【注意5】すぐに成果はでない
CAEソフトを導入すれば直ぐに効果が出てくるのかといえば、そうではありません。CAEソフト運用を本格化させるためには、早くても2年ぐらいの時間が必要です。これはCAEソフトを使う技術者の育成に時間がかかるのと、運用対象への工程構築などCAE技術の浸透に時間がかかるためです。また目標値によりますが、解析精度の向上にも時間がかかります。そのため、「人、モノ、カネ」を確保した上で、いつまでに本格運用したいという計画の策定が必要です。
【注意6】導入目的と効果をハッキリさせることが必要
本来は一番最初に述べたい項目ですが、CAEソフト導入には上記5点という大きな壁を越える必要があるので、敢て最後に持って来ました。すなわち、「人、モノ、カネ」を動かす訳ですから、導入サイドにはしっかりとした動機が必要です。「選択と集中」の理由付けです。「CAEソフトを活用することで何を効率化したいのか」、例えば試作削減による「開発期間の圧縮」、また今まで十分な検討ができなかった「基礎研究への応用」など、成果が見込める明確な動機付けをすべきでしょう。私の経験では、「工数圧縮」を目指すのであれば、工程フローの巻紙解析を行うのも1つの手です。どの部分がCAEで圧縮でき、その波及効果はどの程度か把握できます。CAEは「仮想実験」ですから、モノつくりの分野で「トライ&エラー」を中心に業務を行ってきた部門には効果が大きいでしょう。
さて、この辺が導入の際の6つの【注意点】です。これらを考慮し導入を進めてゆけば、作業は大筋をはずれずに進むのではないでしょうか。 「CAEソフトを導入したが今は眠っている」というのは不幸なことです。 企業技術UPのためのCAEソフトですから、是非有効に活用してください。
バナースペース
二瓶構造解析事務所
〒960-8063
福島県福島市柳町1-10
TEL 090-9030-1379
FAX 024-523-4061