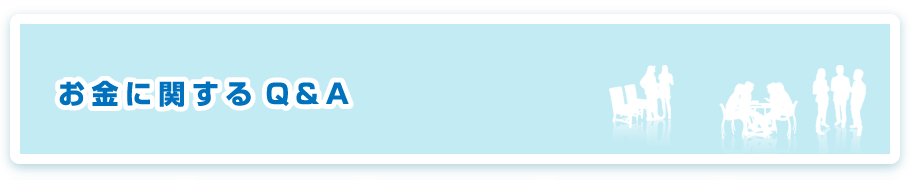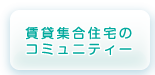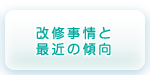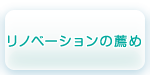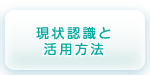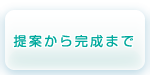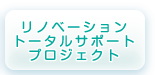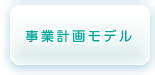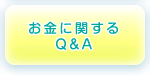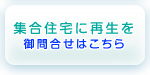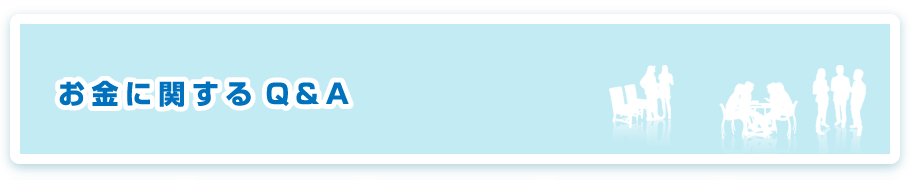
お金に関するQ&A
 現在、サラリーマンですが、金融機関から融資を受けられますか?
現在、サラリーマンですが、金融機関から融資を受けられますか? 一般的に、対象物件の収益性・担保価値、自営業者であるか給与所得者であるか、過年度収入・勤続年数・他の負債残高・保有資産状況など個人属性で総合的に判断されますので、現状の立場は融資可否の判断材料の一要素であって全てではありません。
一般的に、対象物件の収益性・担保価値、自営業者であるか給与所得者であるか、過年度収入・勤続年数・他の負債残高・保有資産状況など個人属性で総合的に判断されますので、現状の立場は融資可否の判断材料の一要素であって全てではありません。
 金融機関からの借入はどのくらいの金額が借りられますか?
金融機関からの借入はどのくらいの金額が借りられますか? 金融機関の対象商品では「~2億」など記載がありますが、上記と同様に対象物件の収益性・物件価額・担保価値の他、建物構造と耐用年数、これに伴う返済期間などの要素によって総合判断されます。
金融機関の対象商品では「~2億」など記載がありますが、上記と同様に対象物件の収益性・物件価額・担保価値の他、建物構造と耐用年数、これに伴う返済期間などの要素によって総合判断されます。
 金融機関からの借入はどのくらいの返済期間で借りられますか?
金融機関からの借入はどのくらいの返済期間で借りられますか? 多くの金融機関の商品募集要件では上限として30年や35年と記載がありますが、物件の構造や耐用年数・経過年数、本人の年齢など、十分に返済可能と見積もられる合理的年数によって決定されます。
多くの金融機関の商品募集要件では上限として30年や35年と記載がありますが、物件の構造や耐用年数・経過年数、本人の年齢など、十分に返済可能と見積もられる合理的年数によって決定されます。
 借入金の返済期間や借入額に影響する建築物の構造と耐用年数について簡単に教えてください。
借入金の返済期間や借入額に影響する建築物の構造と耐用年数について簡単に教えてください。 建物の建築構造によって新築ではそれぞれ木造(22年)鉄骨(34年)鉄筋コンクリ(47年)など定められています。ただし、この耐用年数はあくまで税額計算の為の目安ですので、画一的に適用されるものではなく、対象物件の個別状況・経過年数や詳細な構造の確認が必要です。
建物の建築構造によって新築ではそれぞれ木造(22年)鉄骨(34年)鉄筋コンクリ(47年)など定められています。ただし、この耐用年数はあくまで税額計算の為の目安ですので、画一的に適用されるものではなく、対象物件の個別状況・経過年数や詳細な構造の確認が必要です。
 金利について簡単に教えてください。
金利について簡単に教えてください。 まず、変動金利か固定金利か、の選択は長期の金利予測に結論を委ねてしまいますが、実際には結論を得られませんから、返済計画の立て易さ・当初金利負担、借入残高・手元現金残高といった他の個人的要素がどちらにマッチするのかを重視するのも判断を助けてくれます。また、借入金の返済方法は、元金均等返済と元利均等返済がありますが、これも返済計画の立て易さ・金利負担総額・当初負担額・手元現金残高を事前に確認しておく必要があります。
まず、変動金利か固定金利か、の選択は長期の金利予測に結論を委ねてしまいますが、実際には結論を得られませんから、返済計画の立て易さ・当初金利負担、借入残高・手元現金残高といった他の個人的要素がどちらにマッチするのかを重視するのも判断を助けてくれます。また、借入金の返済方法は、元金均等返済と元利均等返済がありますが、これも返済計画の立て易さ・金利負担総額・当初負担額・手元現金残高を事前に確認しておく必要があります。
 自己資金はどのくらい必要ですか?
自己資金はどのくらい必要ですか? 頭金として物件価額の2割程度、これとは別に諸費用(仲介手数料や各種手続費用・取得税他)負担準備として1割程度が想定されます。借入でどの程度賄えるのかによって結果的に必要となった自己資金が変わりますが、自己資金の有無自体が金融機関評価にも影響し、その後の金利対応や賃貸経営にも影響する為、多く準備すればより有利で安心であることは間違いありません。
頭金として物件価額の2割程度、これとは別に諸費用(仲介手数料や各種手続費用・取得税他)負担準備として1割程度が想定されます。借入でどの程度賄えるのかによって結果的に必要となった自己資金が変わりますが、自己資金の有無自体が金融機関評価にも影響し、その後の金利対応や賃貸経営にも影響する為、多く準備すればより有利で安心であることは間違いありません。
 建築購入時に必要な諸費用とはどんなものでどのくらい必要ですか?
建築購入時に必要な諸費用とはどんなものでどのくらい必要ですか? 仲介手数料や登記手数料・保険料・借入契約諸費用・不動産取得税などがありますが、このうち仲介手数料と不動産取得税は金額も大きいので事前に計算と確認が必要です。総合して物件の1割程度自己資金で準備しておくことが勧められます。
仲介手数料や登記手数料・保険料・借入契約諸費用・不動産取得税などがありますが、このうち仲介手数料と不動産取得税は金額も大きいので事前に計算と確認が必要です。総合して物件の1割程度自己資金で準備しておくことが勧められます。
 建築後の家賃などお金の管理はどのように行うのですか?
建築後の家賃などお金の管理はどのように行うのですか? オーナー自身が行うか又は管理会社に委託して行います。部屋数など負担に応じて選択することになりますが、当然に管理会社によって費用負担や募集審査の対応・入居者対応に差が生じますので、建設後の選択はその後の運営に非常に重要となります。
オーナー自身が行うか又は管理会社に委託して行います。部屋数など負担に応じて選択することになりますが、当然に管理会社によって費用負担や募集審査の対応・入居者対応に差が生じますので、建設後の選択はその後の運営に非常に重要となります。
 家賃収入に関する税金はどのように計算すればよいですか?
家賃収入に関する税金はどのように計算すればよいですか? 個人では、暦年(1/1~12/31)で家賃収入とこれに対応する諸経費を計算して差額を所得として確定申告する必要があります。青色申告を選択すると記帳義務が増しますが控除を受けられます。また、この控除額は所有不動産の貸付規模が関係しますので予め確認が必要です。なお、不動産所得についてどの程度の割合で税額が発生するのかは、各個人の他の所得(給与や事業など)によって異なります。
個人では、暦年(1/1~12/31)で家賃収入とこれに対応する諸経費を計算して差額を所得として確定申告する必要があります。青色申告を選択すると記帳義務が増しますが控除を受けられます。また、この控除額は所有不動産の貸付規模が関係しますので予め確認が必要です。なお、不動産所得についてどの程度の割合で税額が発生するのかは、各個人の他の所得(給与や事業など)によって異なります。
 返済も長期間なので、長期的なお金の流れを把握したいのですが。
返済も長期間なので、長期的なお金の流れを把握したいのですが。 収支計画書と予測損益計算書を作成する必要があります。各年の収入・支出を網羅的に予測し、同時に損益面も予測して作成します。収支計画では現金の流れ全てを予測しますので、借入返済や預かり保証金等も反映しますが、一方で損益計算では借入返済などは関係させず、建物の減価償却費を計上するなど、作成目的に応じて考え方は大きく異なりますので専門家に依頼するなどして綿密に作成してください。
収支計画書と予測損益計算書を作成する必要があります。各年の収入・支出を網羅的に予測し、同時に損益面も予測して作成します。収支計画では現金の流れ全てを予測しますので、借入返済や預かり保証金等も反映しますが、一方で損益計算では借入返済などは関係させず、建物の減価償却費を計上するなど、作成目的に応じて考え方は大きく異なりますので専門家に依頼するなどして綿密に作成してください。
 物件の収益性を向上させるにはどのようにすればよいですか?
物件の収益性を向上させるにはどのようにすればよいですか? 単純には、当初入居者の更新継続入居に努め、通常起こりうる建築経過後の家賃引下げ幅を少なくし、空室率を低く維持する必要があります。ただ、現役世代の減少等、市場は楽観視できないことから、他の物件との差別化を図るため、個人の多様な価値観にまで適応した物件建築の検討が必要です。
単純には、当初入居者の更新継続入居に努め、通常起こりうる建築経過後の家賃引下げ幅を少なくし、空室率を低く維持する必要があります。ただ、現役世代の減少等、市場は楽観視できないことから、他の物件との差別化を図るため、個人の多様な価値観にまで適応した物件建築の検討が必要です。
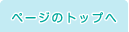

 現在、サラリーマンですが、金融機関から融資を受けられますか?
現在、サラリーマンですが、金融機関から融資を受けられますか? 一般的に、対象物件の収益性・担保価値、自営業者であるか給与所得者であるか、過年度収入・勤続年数・他の負債残高・保有資産状況など個人属性で総合的に判断されますので、現状の立場は融資可否の判断材料の一要素であって全てではありません。
一般的に、対象物件の収益性・担保価値、自営業者であるか給与所得者であるか、過年度収入・勤続年数・他の負債残高・保有資産状況など個人属性で総合的に判断されますので、現状の立場は融資可否の判断材料の一要素であって全てではありません。 金融機関からの借入はどのくらいの金額が借りられますか?
金融機関からの借入はどのくらいの金額が借りられますか? 金融機関の対象商品では「~2億」など記載がありますが、上記と同様に対象物件の収益性・物件価額・担保価値の他、建物構造と耐用年数、これに伴う返済期間などの要素によって総合判断されます。
金融機関の対象商品では「~2億」など記載がありますが、上記と同様に対象物件の収益性・物件価額・担保価値の他、建物構造と耐用年数、これに伴う返済期間などの要素によって総合判断されます。 金融機関からの借入はどのくらいの返済期間で借りられますか?
金融機関からの借入はどのくらいの返済期間で借りられますか? 多くの金融機関の商品募集要件では上限として30年や35年と記載がありますが、物件の構造や耐用年数・経過年数、本人の年齢など、十分に返済可能と見積もられる合理的年数によって決定されます。
多くの金融機関の商品募集要件では上限として30年や35年と記載がありますが、物件の構造や耐用年数・経過年数、本人の年齢など、十分に返済可能と見積もられる合理的年数によって決定されます。 借入金の返済期間や借入額に影響する建築物の構造と耐用年数について簡単に教えてください。
借入金の返済期間や借入額に影響する建築物の構造と耐用年数について簡単に教えてください。 建物の建築構造によって新築ではそれぞれ木造(22年)鉄骨(34年)鉄筋コンクリ(47年)など定められています。ただし、この耐用年数はあくまで税額計算の為の目安ですので、画一的に適用されるものではなく、対象物件の個別状況・経過年数や詳細な構造の確認が必要です。
建物の建築構造によって新築ではそれぞれ木造(22年)鉄骨(34年)鉄筋コンクリ(47年)など定められています。ただし、この耐用年数はあくまで税額計算の為の目安ですので、画一的に適用されるものではなく、対象物件の個別状況・経過年数や詳細な構造の確認が必要です。 金利について簡単に教えてください。
金利について簡単に教えてください。 まず、変動金利か固定金利か、の選択は長期の金利予測に結論を委ねてしまいますが、実際には結論を得られませんから、返済計画の立て易さ・当初金利負担、借入残高・手元現金残高といった他の個人的要素がどちらにマッチするのかを重視するのも判断を助けてくれます。また、借入金の返済方法は、元金均等返済と元利均等返済がありますが、これも返済計画の立て易さ・金利負担総額・当初負担額・手元現金残高を事前に確認しておく必要があります。
まず、変動金利か固定金利か、の選択は長期の金利予測に結論を委ねてしまいますが、実際には結論を得られませんから、返済計画の立て易さ・当初金利負担、借入残高・手元現金残高といった他の個人的要素がどちらにマッチするのかを重視するのも判断を助けてくれます。また、借入金の返済方法は、元金均等返済と元利均等返済がありますが、これも返済計画の立て易さ・金利負担総額・当初負担額・手元現金残高を事前に確認しておく必要があります。 自己資金はどのくらい必要ですか?
自己資金はどのくらい必要ですか? 頭金として物件価額の2割程度、これとは別に諸費用(仲介手数料や各種手続費用・取得税他)負担準備として1割程度が想定されます。借入でどの程度賄えるのかによって結果的に必要となった自己資金が変わりますが、自己資金の有無自体が金融機関評価にも影響し、その後の金利対応や賃貸経営にも影響する為、多く準備すればより有利で安心であることは間違いありません。
頭金として物件価額の2割程度、これとは別に諸費用(仲介手数料や各種手続費用・取得税他)負担準備として1割程度が想定されます。借入でどの程度賄えるのかによって結果的に必要となった自己資金が変わりますが、自己資金の有無自体が金融機関評価にも影響し、その後の金利対応や賃貸経営にも影響する為、多く準備すればより有利で安心であることは間違いありません。 建築購入時に必要な諸費用とはどんなものでどのくらい必要ですか?
建築購入時に必要な諸費用とはどんなものでどのくらい必要ですか? 仲介手数料や登記手数料・保険料・借入契約諸費用・不動産取得税などがありますが、このうち仲介手数料と不動産取得税は金額も大きいので事前に計算と確認が必要です。総合して物件の1割程度自己資金で準備しておくことが勧められます。
仲介手数料や登記手数料・保険料・借入契約諸費用・不動産取得税などがありますが、このうち仲介手数料と不動産取得税は金額も大きいので事前に計算と確認が必要です。総合して物件の1割程度自己資金で準備しておくことが勧められます。 建築後の家賃などお金の管理はどのように行うのですか?
建築後の家賃などお金の管理はどのように行うのですか? オーナー自身が行うか又は管理会社に委託して行います。部屋数など負担に応じて選択することになりますが、当然に管理会社によって費用負担や募集審査の対応・入居者対応に差が生じますので、建設後の選択はその後の運営に非常に重要となります。
オーナー自身が行うか又は管理会社に委託して行います。部屋数など負担に応じて選択することになりますが、当然に管理会社によって費用負担や募集審査の対応・入居者対応に差が生じますので、建設後の選択はその後の運営に非常に重要となります。 家賃収入に関する税金はどのように計算すればよいですか?
家賃収入に関する税金はどのように計算すればよいですか? 個人では、暦年(1/1~12/31)で家賃収入とこれに対応する諸経費を計算して差額を所得として確定申告する必要があります。青色申告を選択すると記帳義務が増しますが控除を受けられます。また、この控除額は所有不動産の貸付規模が関係しますので予め確認が必要です。なお、不動産所得についてどの程度の割合で税額が発生するのかは、各個人の他の所得(給与や事業など)によって異なります。
個人では、暦年(1/1~12/31)で家賃収入とこれに対応する諸経費を計算して差額を所得として確定申告する必要があります。青色申告を選択すると記帳義務が増しますが控除を受けられます。また、この控除額は所有不動産の貸付規模が関係しますので予め確認が必要です。なお、不動産所得についてどの程度の割合で税額が発生するのかは、各個人の他の所得(給与や事業など)によって異なります。 返済も長期間なので、長期的なお金の流れを把握したいのですが。
返済も長期間なので、長期的なお金の流れを把握したいのですが。 収支計画書と予測損益計算書を作成する必要があります。各年の収入・支出を網羅的に予測し、同時に損益面も予測して作成します。収支計画では現金の流れ全てを予測しますので、借入返済や預かり保証金等も反映しますが、一方で損益計算では借入返済などは関係させず、建物の減価償却費を計上するなど、作成目的に応じて考え方は大きく異なりますので専門家に依頼するなどして綿密に作成してください。
収支計画書と予測損益計算書を作成する必要があります。各年の収入・支出を網羅的に予測し、同時に損益面も予測して作成します。収支計画では現金の流れ全てを予測しますので、借入返済や預かり保証金等も反映しますが、一方で損益計算では借入返済などは関係させず、建物の減価償却費を計上するなど、作成目的に応じて考え方は大きく異なりますので専門家に依頼するなどして綿密に作成してください。 物件の収益性を向上させるにはどのようにすればよいですか?
物件の収益性を向上させるにはどのようにすればよいですか? 単純には、当初入居者の更新継続入居に努め、通常起こりうる建築経過後の家賃引下げ幅を少なくし、空室率を低く維持する必要があります。ただ、現役世代の減少等、市場は楽観視できないことから、他の物件との差別化を図るため、個人の多様な価値観にまで適応した物件建築の検討が必要です。
単純には、当初入居者の更新継続入居に努め、通常起こりうる建築経過後の家賃引下げ幅を少なくし、空室率を低く維持する必要があります。ただ、現役世代の減少等、市場は楽観視できないことから、他の物件との差別化を図るため、個人の多様な価値観にまで適応した物件建築の検討が必要です。