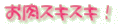
※ 左側にメニューがフレームで表示されていない場合は、お手数ですが「お肉の用語集」 から入り直して下さい。
※ リンク先が正しく表示されない場合がある可能性がある事をお含み置きください。
(50音順)
- 合鴨 - あいがも
- 野生のマガモとアヒルとの雑種のこと。
→ 鴨
→ マガモ
→ アヒル
- アイスバイン - Eisbein(独) - あいすばいん
- 豚のスネ肉を煮込んだ料理名。ドイツの家庭料理。
塩漬けの豚スネ肉を香味野菜とともに長時間煮込んで調理する。
→ スネ肉
- アイテム - あいてむ
- 小売業界においては、「品目」の意味で使われる言葉。
広義では「種類」という意味としても使われる。
一例として、「取扱いアイテム数が豊富だ」という言葉の意味は、「取り扱っている品目・種類が多い」という意味である。
→ SKU
- 合挽き - あいびき
-
→ 合挽き肉
- 合挽き肉 - あいびきにく
- 一般的に牛と豚を混ぜて挽肉にしたもの。
脂質の融点が異なる為、ハンバーグにした時の食味・食感が単一の畜種の挽肉と比べて優れているとされる。
牛70%、豚30%の割合がいちばん良いとされている。
合い挽き肉、合挽ミンチなどと表示・表現されるが同じ意味。
挽肉は消費者の購買頻度が高く、また商品的には鮮度の劣化が早い為、品質の善し悪しは、その販売店のレベルを判断する良い指標である。色変わりが早い挽肉を販売している小売店は原料肉の品質や鮮度・温度管理に気を配っていない小売店だということ。
→ 挽肉
→ ミンチ
→ PI値
- アウトサイドスカート - あうと さいど すかーと
- ハラミの米名。
→ ハラミ
- アウトパック - あうと ぱっく
- 小売店等において、外部の業者等に委託してパック詰めした製品を加工してもらい、それを自社の店頭にて販売する方式 または その商品そのものの事を指す。
外部の業者ではなく、自社でアウトパックの加工センターを手配している企業も少なくない。
メリットとしては、小売店のバックヤード・人員配置の削減・衛生管理面でのリスク回避等があるが、デメリットとしては、物流の調整の難しさ、商品の鮮度管理、何よりも小回りのきく商売の難しさ等がある。
→ インストア
→ 小売店
- 揚げる - あげる
- 料理・調理法の一つ。多量の食用油を高温に熱した鍋等に食材を投入して加熱調理すること。
→ フライ
→ カツ
→ 天ぷら
- アスピック - aspic(仏) - あすぴっく
- フランス料理名。肉や魚のブイヨンを使ったゼリー状の前菜料理のこと。または、肉や魚を用いてゼリー状の料理にした物の事を指す。
日本では 煮凝り(にこごり)とも呼ばれる。
→ 煮凝り
→ テリーヌ
- 厚切り - あつぎり
- 通常より厚くカットしたものを指す。
ステーキ・カツ・焼肉など、食べ応えのある厚切りの需要は確かに存在する。
購入・選択する時のボリューム感、満足感は 価値観の一つの提案である。
ただし、厚くカットすると当然 調理には工夫が必要となる。
→ ステーキ
→ カツ
→ 焼肉
→ 薄切り
- アヒル - あひる
- もともとはマガモである。
野生のマガモを人為的に飼育した結果、アヒルと呼ばれるようになった。
→ 鴨
→ 家禽
- 脂 - あぶら
- 動物の脂肪のこと。食肉業界においては脂は旨味である。健康志向の意識を持つ消費者には敬遠されがちであるが、適度な脂は肉料理の旨味において不可欠である。肉の美味しさは脂の美味しさと言っても過言ではない。
→ 背脂
→ 正肉
- アメリカンドッグ - あめりかん どっぐ
- ソーセージに小麦粉等の衣を付けて串を刺した物を、油で揚げた料理。夏祭りの縁日やコンビニで販売される事が多い。
日本固有の呼び名であり、アメリカではコーンドッグ(corn dog)と呼ばれる。
→ ソーセージ
- 荒挽き - あらびき
- 挽肉にする行程で、荒目に挽くこと。
小売店で販売される挽肉は、2度挽きが主流である。1度目は荒目で挽き、2度目は細目で挽く事が多い。
荒挽きで提供される商品は、やや食感は固いものの その素材の食感を含めた味わいを楽しむ事が出来る。
加工食品である ウインナーでは荒挽きタイプが主流である。
→ 荒挽きウインナー
→ 細挽き
→ ウインナー
→ ソーセージ
→ 挽肉
- 荒挽きウインナー - あらびき ういんなー
- 荒めに挽いた原料を使用したウインナーのこと。
現在の主流であり、食感を楽しめる。
→ 細挽き
→ ウインナー
→ ソーセージ
- 荒利 - 荒利
- とても大雑把に言うと、利益のことである。
もう少し丁寧に言うと、仕入れた商品に対して実際に売れた商品に対する利益のことである。売れ残った物に対してはこの計算に入れない。
粗利とも表現する。
→ 値入れ
→ 売上
- ES - いー えす
- Employee Satisfaction (ES) 。
従業員満足(度)のこと。
小売・サービス業においては、CS(顧客満足(度))を高める為に、ESを高める手法がとられる場合もある。自分たちの仕事や職場に誇りや価値観・プライドを持てなければ 自信をもって顧客に対して サービスの提供は出来ない という理屈である。
→ 従業員満足
→ 顧客満足
- EDLP - いー でぃー える ぴー
- Every Day Low Price の略。
チラシ等の販促経費を削り、チラシを打たなくても毎日がお買い得という商売のやり方のこと。
俗に言うディスカウントストアの形態がこのやり方に当てはまる事が多い。
→ 価格
→ チラシ
→ 特売
→ ディスカウントストア
- 石焼ビビンバ - いしやきびびんば
-
おこげも美味しく食べられるビビンバの事。
日本では焼肉量販店のメニューとして普通にラインナップされている事が多い。
→ ビビンバ
- 炒める - いためる
- 加熱したフライパンや鍋等において、食材を 素早く加熱・調理する事を指す。
料理法において基本の一つである。
→ ソテー
- イチボ - いちぼ
- 牛のモモ肉の呼び名の一つ。
らんいち という呼び名は ランプと イチボ を分割する前の状態の呼び名である。ランプは赤身で とにかくやわらかくて美味しいのに対し、イチポは見た目はサシ気が適度に入り、美味しそうに見えるのではあるが、ランプに比べると食感はやや固い。
薄くスライスしてすき焼きやしゃぶしゃぶ用に商品化するべき。
手切りの焼肉カットでは食感が固い。
→ らんいち
→ ランプ
- 一本物 - いっぽん もの
- ハム等の加工肉において呼称される業界用語。
スライスされずに、丸ごと塊のままで販売される形態の商品の事を指す。
主に年末商戦等に使用される。
→ 加工肉
→ ハム
- イベリコ豚 - いべりこ ぶた
- スペイン イベリア半島で肥育される世界的に有名なブランド豚。特に生ハムは有名で、脂身の栄養価が高く美味しいという評判である。
- 稲わら - いな わら (又は いね わら)
- 米を収穫する目的で稲作が行われた結果として出来る、副産物が稲わらである。日用品や工芸品に利用される他、家畜の飼料としても用いられている。
→ 汚染牛
- インストア - いんすとあ
- 店内加工の事。
→ アウトパック
- ウインナー - ういんなー
- ソーセージの項目の一つ。日本ではJAS規格により定義が制定されており、羊の腸に詰めた物または直径20mm未満のケーシングに詰められたソーセージのこと。
あらびきタイプの物が現在では主流である。
お弁当に入っているとうれしい。
→ あらびき
→ 皮なしウインナー
→ ソーセージ
⇒⇒ 【 JAS規格によるソーセージ分類 (資料) 】
- ウェルダン - うぇるだん - well done[英]
- 肉の焼き加減のひとつ。
特にステーキの焼き方の表現として用いられる。表面だけでなく中心部までしっかりと焼いた状態のこと。ジューシーさは損なわれるが、しっかりと加熱された肉を味わいたい方にはおすすめ。
→ 焼き加減
→ レア
→ ミディアム
- 烏骨鶏 - うこっけい
- ニワトリの品種の一つ。肉はもちろん、皮膚や内臓、骨まで黒い色をしているのが大きな特徴。
栄養学的にも優れているとされる為、肉はもちろん、卵も高価格で取り引きされる。
価格が高価であることの理由は、一般的な小売ルートには乗らない商品の為、希少価値が高いという意味も含まれる。
- 牛 - うし
- ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。多くの品種がある。
→ 牛肉
→ 品種
- 薄切り - うすぎり
- 通常より薄目にカットすること。
食肉・小売業界においては、畜肉をスライサーで商品化する場合は、たいていの場合 この薄切りである。
敢えて 薄切りである事をアピールしたい場合には、「薄切り焼肉」等 と表示して販売することもある。
部位によっては少々 食感が固い部位でも薄く商品化することで 美味しく食べられるものもある。
→ 厚切り
→ 焼肉
- 内食 - うち しょく
- 外食の反意語として使用される言葉。
家庭内で調理して食べる食事のこと。
→ 外食
→ 中食
- 売上 - うりあげ
- 商品やサービスを販売する事によって得られた代金の総額のことである。売上高、売上金額ともいう。
小売店においては、客数×客単価という数式で導かれる。
→ 荒利
→ PI値
→ 客数
- 売り出し - うりだし
- 小売業・流通業界では、通常よりも価格を特別に下げて商品を販売する事の意味。
→ 特売
→ 決算
- エイジング - えいじんぐ
- 熟成のこと。
→ 熟成
- SM - えす えむ
- スーパーマーケットのこと。
→ スーパー
- SKU - えす けー ゆー
- Stock Keeping Unit の略語。流通・小売業において在庫管理に使用される言葉。
商品の種類(=アイテム)ではなく、サイズ(容量)、カラー(色) 等によって SKUは区別される。
食肉業界 小売店の例で 判りやすい例は、トレーパックした「ステーキ肉」という商品(アイテム)において 1枚入り、2枚入り、3枚入りはそれぞれ別のSKUとなる。
→ アイテム
- SPF豚 - えす・ぴー・えふ ぶた
- Specific Pathogen Free の略で「特定病原不在」の意味。
外科手術によって胎児を取り出し、管理された環境で飼育される。特定病原菌とはマイコプラズマ性肺炎・豚萎縮性鼻炎・豚赤痢・トキソプラズマ病・オーエスキー病の5つ。
- F1 - えふ わん
- 食肉業界においては、交雑種のこと。
特に、牛に対して用いられる用語で、日本では主にホルスタインの雌牛と和牛(黒毛和種)の雄牛をかけ合わせた物の間に生まれた物の事を指す。
食肉としての美味しさと、生産効率を求めて様々な交雑種が存在するが、考え方としては、純血種では成し遂げる事の出来ない、家畜としての病気への弱さへの対策などが交雑種を生産する主な理由である。
→ 交雑種
- NB - えぬ びー
- National Bland の略語。
メーカー品のことであり、世間一般に広く通用する品物のことである。
PB(Private Bland)の反意語として使用される言葉。
→ PB
- 塩干 - えんかん
- SMにおける業界用語で、主に 魚の干物の事を指す。
反意語は 鮮魚 である。
→ SM
- 塩漬 - えんせき
- ハムやソーセージを作る行程の一つで、食塩や香辛料などに漬け込むことを指す。発色剤もこの行程で仕込まれるので、使用しない場合は 無塩漬と表示される場合がある。
→ 無塩漬
- OJT - おー じぇい てぃー
- On the Job Training の略語。小売店等において、新人の教育の仕方の一つである。
教育用・訓練用の施設ではなく、実際の現場で働きながら先輩等に指導を受けて 教育するやり方。
会議室による集合教育では得られない、スピード感を持った成長が期待できる。
- オーダー・カット - おーだー・かっと
- お客様の要望・ご注文に対して その場で食肉を切り分けて ご要望に応じた形で提供すること。
対面販売方式の精肉店においては当たり前の販売方式であるが、セルフサービスを主体としたSM(スーパーマーケット)においては、これに対応できるかどうかが、ある意味 その企業姿勢の分かれ目である。
→ SM
→ セルフサービス
→ 注文
→ 対面販売
- おかずメニュー - おかず めにゅー
- 日常の食卓に並ぶ料理の事。
→ ごちそうメニュー
- お好み焼き - おこのみやき
- 料理名。小麦粉を主体として肉や野菜など、「お好み」の具材を入れて焼き上げて食べる料理。肉は豚肉を使用する事が多い。ソースが決め手。日本では特に大阪が有名であるとされる。
→ チヂミ
- 汚染牛 - おせん ぎゅう
- 俗語であり、食肉業界にとっては 好ましくない使われ方の言葉である。
2011年に発生した東日本大震災に起因する、福島原発の事故により 稲わらも放射性物質であるセシウムに汚染された。その汚染された稲わらを餌として与えられた食肉用の牛肉の事を指す。
国が定めた食肉の安全とされる暫定基準値は500ベクレル/kgである。
→ 稲わら
- おたぐり - おたぐり
- 料理名。食用の馬の腸を煮込んだ料理。長野県の伊那から飯田地方において特に好まれる料理。
この地域においては、スーパーマーケットの店頭でも普通に おたぐり の商品名で販売されている。
→ 馬肉
- おつまみ - おつまみ
- 食肉業界においては、酒と一緒に楽しんで頂けるソーセージや生ハム等のことを指す事が多い。中でもサラミ等に代表されるドライソーセージや、魚肉ソーセージがおつまみとして好まれる傾向にある。
調理をほとんどしなくても、購入して来たそのままに近い状態で食べる事が出来るというのが人気の一つである。
→ ドライソーセージ
→ 生ハム
- お肉スキスキ - おにく すきすき
- お肉スキスキ♪のフレーズの曲。
日本国産食肉Jミート拡販の販促の為に制作・オンエアされたテレビCMまたはその曲の事を指す。2003年にテレビCMはオンエアされた。
(当時)モーニング娘の石川梨華 他が出演している。
スーパーの店頭でエンドレステープやCD等で曲が流れた。
製作元は(財)日本食肉消費総合センターである。
→ Jミート
→ (財)日本食肉消費総合センター
- お肉をやわらかくする - おにくを やわらかくする
- 味が美味しいかまずいか、では無く
お肉がやわらかいか、固いか というのは消費者心理としては大きな関心事である。
ぜひこちらの項目も御一読頂きたい。
⇒⇒ やわらかいお肉が食べたい
- お値打ち - おねうち
- [方言] 名古屋を中心とする東海地方で主に使われる表現。
単に価格が安いだけではなく、品質がそれなりに高くて買いやすい価格のこと。
→ 価格
→ 値ごろ
- 温しゃぶ - おん しゃぶ
- 冷しゃぶの反意語。要は普通のしゃぶしゃぶの事である。
業界用語の一つでもある。冷しゃぶと敢えて区別する時にこの言葉を使う。
→ しゃぶしゃぶ
→ 冷しゃぶ
- 改ざん - かいざん
- 記録物等の内容が書き換えられること。
食品・小売・流通業界においては、消費期限・賞味期限を故意に書き換える不当な行為に対して用いられる用語である。
故意でも、過失であったとしても、あってはならない事である。
→ 期限切れ
- 買い占め - かいしめ
-
→ 買いだめ
- 外食 - がいしょく
- 家庭の外で喫食をすること。
→ 内食
- 買いだめ - かいだめ
- 必要以上に買い占めて備蓄する行為のこと。
本当にその物を必要とする人からすれば、手に入りにくくなる可能性が高まるので迷惑な行為とされる。
- 解凍 - かいとう
- 冷凍保存されたものを元の状態に戻すこと。
食品表示の「解凍」とは、冷凍の原料肉を解凍して商品化した物であるという意味の表示である。
消費者が冷凍品を解凍する際には、冷蔵庫内等にて 時間をかけてじっくりと解凍すると品質の劣化を最小限に留めることが出来る。急速な解凍は肉の旨味を損なう。
→ 自然解凍
→ 流水解凍
→ 冷凍
→ チルド
→ ドリップ
- カイノミ - かいのみ
- 牛肉の友バラの一部の俗称。形状が「貝の身」であることからこう呼ばれる。
赤身が多く、やわらかで、味わいも良い。
その形状と大きさから 手切りのカルビ・焼肉に商品化される事が多い。
すき焼きなどのスライスには不向きな感じである。
→ バラ
→ 希少部位
- 買物 - かいもの
- 品物(商品)をお金と引き換えに、手にすること。
目的買い、衝動買いなど買物は楽しいものである。
→ 商品
→ 目的買い
→ 衝動買い
- 顔見せ - かおみせ
- 業界用語。ハレの日の為に、売り込みたい商品を陳列・販売すること。
一例としては、クリスマスに 骨付きチキンを売り込む計画であるならば、普段は販売してなくても、クリスマス当日以前に、実際に販売する商品を陳列・販売することを指す。
顔見せは、少量の販売数量で構わない。小売店が、イメージ作り・宣伝の意味で行う行為。
→ ハレの日
- 価格 - かかく
- 商品を販売するにあたって、その商品の値段のこと。
食肉の販売においては、1個 (1パック)の価格 の他に、100g当り幾らという価格の付け方も普通である。
(例) 100g当り98円で、1パックに312g 盛り付けられた商品の場合は、98円×312/100g= 305.76円 となり、たいていの企業では 小数点以下は切り捨てとし、販売価格は 305円としている所が多い。
価格は消費者にとっても、販売者にとってもたいへん重要な要素である。
品質と価格のバランスは特に重要である。
→ 値ごろ
→ お値打ち
→ 品質
→ 特売
→ EDLP
→ 競合店
- 価格調査 - かかく ちょうさ
- 競合店と戦うために、行う行為である。
→ 価格
→ 競合店
- 家禽 - かきん
- 元々は野生の鳥を、人間の都合に合わせて飼う様になった鳥の事を指す。
→ 合鴨
→ 野生
- 格付け - かくづけ
- 日本食肉格付協会 が定める 食肉の規格についての公的な標準指針。
牛肉の場合は、歩留まりで A・B・C の3等級、肉質で 1〜5 までの5等級の評価がされ、この2つの等級を組み合わせたもの。
A5が最も上等の肉で、C1が最も劣る肉である。
肉質については、次の4項目のそれぞれ すべてにおいて5段階評価され、4項目の中で最も低い等級のついたものをその肉の肉質等級としている。
1.脂肪交雑 2.肉の色沢 3.肉の締まり及びきめ 4. 脂肪の色沢と質
→ 等級
→ 肉質等級
→ 日本食肉格付協会
- 角煮 - かくに
- 豚バラ肉を甘辛く煮込んだ料理のこと。
主に九州地方(鹿児島県)で好まれる料理。
→ バラ
→ 三枚肉
→ 煮豚
→ 焼豚
→ トンポーロー
→ ラフテー
- 加工食品 - かこう しょくひん
- 食肉業界においては、加工肉と同意義。
→ 加工肉
- 加工肉 - かこうにく
- ハム・ウインナー・ベーコン等のことを指す。
食肉の保存性を高める為に、燻製・塩漬等の手法により人為的に加工したもの。
日常の食卓用の他、こだわりのハムなどは、お歳暮・お中元などのギフトにも利用される事が多い。
→ 燻製
→ ハム
→ ウインナー
→ ベーコン
→ 一本物
- 加工品 - かこうひん
- 食肉業界においては、加工肉と同意義。
→ 加工肉
- カシミールカレー - かしみーる かれー
- 特に辛くて美味しいカレーのこと。
詳細な定義は不明だが、インド北部のことをカシミール地方と言うが、この地域でこのカレーが食されているかどうかは現在調査中。
日本の飲食店等では、激辛のカレーのことをこの名称で提供しているようだ。
具材としては鶏肉を使用する。
→ カレー
→ 鶏肉
- かしわ - かしわ
- 鶏肉のこと。日本の特定の地域においての呼称である。
中部地方、関西地区、九州など では一般的に使用されている表現である。
特定の銘柄を指す訳ではなく、鶏(にわとり)の食肉のことを指す意味で使用される表現である。
→ 鶏肉
- 加食 - かしょく
- 加工食品の略。
→ 加工食品
- ガゼット袋 - がぜっと ぶくろ
- スーパーのレジ袋の事。まち付きの袋の事を指す。
以前はスーパーで買い物をすればただで貰えたが、現在は有償の場合が多い。
素材はポリ塩化ビニールである事が多い。
→ レジ袋
- 肩小肉 - かた こにく
-
鶏肉の部位名であるが、一般名ではなく、ややマニアックな部位である。
ムネと手羽元の間の肉のことを指す。
筋っぽく硬めの食感であるが、味わいは良い。
→ 鶏肉
→ セセリ
- かたまり - かたまり
-
畜肉の販売形態の一つ。料理用途別にスライスやカットするのではなく、かたまりのまま販売する手法である。
煮豚、焼豚、角煮、ローストビーフなど、かたまり形態ならではの需要もある。
→ ブロック
- 肩ロース - かたろーす
-
部位名の一つ。
柔らかくて、コクのある味わいで、人気の部位。
→ 部位
- 家畜改良センター - かちく かいりょう せんたー
- 独立行政法人。牛の個体識別番号事業 等を行う。
⇒⇒ 家畜改良センター (外部リンク)
→ 牛個体識別番号
- 家畜伝染病予防法 - かちく でんせんびょう よぼうほう
- 日本の法律の一つ。昭和26年施行。
家畜の伝染病疾患を予防し、畜産の振興を図る事が目的である。
⇒⇒ 家畜伝染病予防法 (外部リンク)
- カツ - かつ
- 料理名。一般的には畜肉に小麦粉・溶き卵・パン粉等の衣を付けて多めの油で揚げたもの。英語のcutlet(カツレツ)が語源であるとされる。
良く似た料理にフライがあるが、エビや白身魚等の魚介類を原料とした料理をフライと呼ぶ事が多い様である。
→ カツレツ
→ 豚カツ
→ チキンカツ
→ フライ
→ 天ぷら
→ 味噌カツ
→ 厚切り
- カツ丼 - かつどん
- 料理名。一般的には 丼に盛られた白いご飯の上に 卵とじにした豚カツがメインの具材として乗せられる。
地域によって様々なバリエーションがある。
→ 豚カツ
→ ソースカツ丼
→ 味噌カツ丼
- カツレツ - Cotelette[仏] - かつれつ
- 料理名。フランス料理のCoteletteが元とされるが、現在の日本においての定義は次のような感じである。
畜肉に衣を付けた物を比較的 少なめの油を用いてソテーしたもの。
原材料として用いられる畜肉は元々は牛肉が基本であったようだが、現在では豚肉も多く用いられる。
カツとカツレツの違いは、揚げるかソテーするかの違いと言っても良い。
→ カツ
→ ソテー
- カテゴリーキラー - かてごりー きらー
- 家電商品・衣料品・ドラッグなどの ある特定の分野商品だけを特化して、多量販売を目的に低価格で品揃えした小売店の形態。
商圏内の総合スーパーがその商品ジャンル(カテゴリー)の販売に苦戦を強いられる事からカテゴリーキラーと呼ばれる。
→ 業態
- かぶり - かぶり
- 食肉の部位名における業界用語。
リブロースや内モモの部位において、外側に巻きついた様な部分の事を指す。
リブロースのかぶりは外して、焼肉カットにすれば 上ロース として通用するし、内モモのかぶりは カレー・シチュー用の角切りカットや、もしくは牛丼用の小間切れカットなどに向く。
→ 業界用語
- 鴨 - かも
-
渡り鳥として知られる。
食肉業界においては、合鴨(アイガモ)の事を指す事が多い。
→ 合鴨
→ マガモ
- ガラ - がら
-
食肉業界においては、骨の意味で使われる言葉である。
ダシを取る為に使われる用途で、鶏ガラは商品として普通に流通している。
豚ガラは小売店ではあまり目にしないが、専門店等で流通している。
→ 鶏ガラ
→ 豚ガラ
→ げんこつ
- 唐揚げ - からあげ
- 料理名。鶏肉に衣を付けて油で揚げた料理のことを指すことが多い。
モモ肉を使用するとジューシーな味わいで、お弁当にもよく登場する。
→ 鶏
→ フライドチキン
→ チキンナゲット
→ 油淋鶏
- カルパス - かるぱす
- 現在の日本ではセミドライソーセージの事を指す俗称である。
語源は、ロシア語でソーセージの意味である kolbasa であるとされている。
→ おつまみ
→ ソーセージ
→ セミドライソーセージ
- カルパッチョ - かるぱっちょ
- 定義はやや曖昧ではあるが、加熱をしていない「生」の牛薄切り肉に「パルミジャーノ・レッジャーノ」と呼ばれるイタリアのチーズをかけたもの。
日本国内では、やや適当な感じで使用されている言葉のひとつ。
肉以外のアレンジメニューとして、魚を原料とした食品においても、日本ではカルパッチョの名前を使った商品がある。
→ 生食
- カルビ - かるび -
 - galbi [韓国語] - galbi [韓国語]
- 韓国におけるカルビとは、バラ肉を使用した料理の名前である。
骨付きで食べる事も多い。
日本国内の焼肉料理店や小売店では、かなりテキトーにメニューブックや品名に表現される事も多いようだが、本来の意味を尊重したい。
バラ肉以外の赤身のモモ肉等をカルビ肉という名称で提供している光景は、消費者を馬鹿にしている印象を受ける。
→ バラ
→ 骨付きカルビ
→ 公正取引委員会
→ 上カルビ
- カレー - かれー
- 香辛料を用いて野菜や肉などを具材として作る料理のこと。
インドのカレーと日本で食されるカレーとは違う点の方が多い。
現在の日本ではカレーライスという料理が一般的に認識されている。
→ キーマカレー
→ カシミールカレー
- 皮なしウインナー - かわなし ういんなー
- ウインナーは元々は 羊の腸 に原料肉を詰める製法で商品化されてきたが、現代においては 天然腸を使用した商品は逆に少なくなりつつある。
天然腸の代わりとなる人工的なケーシングにてウインナーを作り、後から皮となるケーシングを取り除いた物を 皮なしウインナー と呼ぶ。
小さな子どもでも 皮が口の中に残る事を気にすることなく、楽しめるのが特徴である。
→ 絹挽きウインナー
→ ウインナー
- 肝臓 - かんぞう
- 食肉業界においては、レバーという。
→ レバー
- 元旦営業 - がんたん えいぎょう
- 小売業界において、その昔は正月は休日とする事が普通であったが、大手総合スーパー等を中心に現在では、元旦を含めた正月営業は普通の事となっている。
・・・が、従業員の福利厚生も含めて、これで良いのかという議論はある。
→ 正月営業
- 広東 - かんとん
- 広東料理を参照。
→ 広東料理
- 広東料理 - かんとん りょうり
- 中国南部の広東省を中心にした地域の料理のことを指す。
→ 中華料理
→ 春巻き
- 管理監督者 - かんり かんとく しゃ
- 「経営者と一体的な立場」 ・ 「出退勤の自由」 ・ 「地位にふさわしい待遇」の条件を満たすもの。(厚生労働省)
→ 管理職
→ 名ばかり管理職
- 管理職 - かんりしょく
- 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」のこと。(労働基準法第41条2号)
民間企業では課長職以上のことを管理職と呼ぶ場合が多い。
→ 名ばかり管理職
→ 管理監督者
- 関連販売 - かんれん はんばい
- 小売店の販売手法の一つ。買い上げ点数をアップさせる為に、売り込みたい商品と一緒に関連する商品も一緒に販売すること。
一例として、バーベキュー肉を販売する際に、塩・コショーや焼肉のタレ、更には調理器具であるバーベキュー網や固形燃料、アウトドアを意識して紙皿なども一緒の場所で販売する。
値下げをせずにもう一品売り込もうという取組みである。
→ クロス販売
→ コラボ
- キーマカレー - きーまかれー
- インド料理の一つ。いわゆる普通のカレーと違うのは「挽肉」を主に多く使用する事。
日本でのキーマカレーでは鶏の挽肉を使用する事が多い。
米飯の他、ナンやチャパティと共に食べる。
→ カレー
→ ナン
→ チャパティ
- 希少部位 - きしょう ぶい
- 供給量が少ない為、価値が高いと される部位のこと。
本来の意味は 皆が欲しがるのに、なかなか手に入らないといういう意味。
グルメ番組等で しばしば 使用される言葉であるが、 過大表現も見受けられがちなので、消費者は注意をすべきである。本当に美味しくて価値のあるものなら問題は無いが、希少部位だからと言って、何でも美味しくて価格に見合った物であるとは限らないという話。
本当の所、「希少部位」という言葉に対する ルールや定義は 無い。
→ 部位
→ シャトーブリアン
→ サンカクバラ
→ トモサンカク
→ カイノミ
- 偽装 - ぎそう
- ほかの物とよく似た色や形にして人目をあざむくこと。
偽装事件は犯罪であり、決してあってはならない事なのにも係わらず、食品の偽装事件は後を絶たない。一般消費者はもとより、他の真面目に取り組んでいる企業や人にとっては非常に迷惑な話である。
消費期限・賞味期限のごまかしの場合は、改ざんという用語が用いられる。
→ 改ざん
- 期限切れ - きげん ぎれ
- 消費期限・賞味期限が過ぎた物に対して使用する用語。
食中毒予防の見解からも、充分に留意したい。
→ 自己責任
- 絹挽き - きぬびき
- 挽肉を挽く行程で、非常にきめ細かな細挽きにすること。
→ 細挽き
- 絹挽きウインナー - きぬびき ういんなー
- 細挽きウインナーのこと。
滑らかな食感を目指した商品だが、現在の市場では消費者にあまり支持されていない。
→ 細挽き
→ ウインナー
- キムチ - きむち
- 白菜などの野菜を主にした朝鮮半島の漬物のこと。
日本では焼肉料理店で提供される他、鍋料理であるチゲの具材としてもよく利用される。
→ 焼肉
→ チゲ
→ 豚キムチ
- 切り落し - 切り落とし - きりおとし
- スライスした平切り肉を直接トレーに盛り付ける商品のこと。
小間切れとは区別される。
すき焼き用やしゃぶしゃぶ用のスライス肉は、1枚の肉をある程度均一の大きさに商品化するが、原料肉の切り始めや切り終わりなどを、切り落し として商品化する事が多い。品質には変わりがないが、見た目やサイズの不揃いという理由だけで価格はお値打ちになっている事が多い。
複数の部位の端材を主原料とする小間切れとは違い、切り落しの場合の部位は単一である場合が多い。
切り出し と表現される事もある。
→ スライス
→ 小間切れ
→ 部位
- 客数 - きゃく すう
- 小売店等の業界において、来店して実際にお買い上げいただいた消費者の人数のこと。
実際の運用では、レジを通った清算回数をカウントしている事が多いようだ。
家族連れの複数の人数であっても、清算回数にて運用される。
ガム1個でも、カゴに山盛りのお買い上げでも、客数は清算回数に応じてカウントされる。
→ 売上
- 客動線 - きゃく どうせん [業界用語]
- 小売店内において、お客様がお買い物をされる際にたどる道筋のこと。
小売店においては、こういう順番に買物をして頂きたいという思いを込めて、いろんな知恵や工夫を重ねている。
→ 動線
- 客注 - きゃく ちゅう
- お客様の注文品のこと。
→ 注文
- 逆ロス - ぎゃく ろす [業界用語]
- ロスの反対の意味。
あるべき在庫(帳票上の推定在庫) に対して、実在庫の方が多い事を指す。
あり得ない事ではあるが、実際の商売の現場では こういった事も起こりうる。
その原因の多くは、伝票操作の誤りであることが多い。
→ ロス
→ 売価修正
- キャッシャー - きゃっしゃー
- スーパーマーケットのレジ業務において、チェッカーのサポートとして金銭授受を行う人・又はその行為について指す。
POSレジの場合、混雑時は2人制で運用される場合もある。POSを通す人をチェッカーと呼び、金銭授受を行う人をキャッシャーと呼ぶ。
→ チェッカー
→ スーパーマーケット
- 牛 - ぎゅう
-
→ 牛 (うし)
- 牛脂 - ぎゅうし
- 牛の脂のこと。
→ ケンネ脂
→ ヘット
- 牛すじ - ぎゅうすじ
- 牛のアキレス腱のこと。または筋(すじ)の付いた肉のこと。地域により食され方は様々だが、煮込んでおでん種に使われる事が多い。
→ スジ
- 牛タン - ぎゅうたん
- 牛の舌のこと。
焼肉料理においては、ポピュラーであり、人気メニューの一つである。
一般的には、塩味でネギ等の薬味を用いて食する。
食肉業界において、牛タンは内臓肉の扱いである。
→ 焼肉
→ 内臓
- 牛刀 - ぎゅうとう
- 包丁の種類の一つであり、精肉用のポピュラーな包丁である。
洋包丁であり、片刃である。
筋引き包丁が引いて使うことを前提にしているのに対して、牛刀は押して使うことを前提としている。
→ 包丁
→ 筋引き包丁
- 牛丼 - ぎゅうどん
- 牛肉を使った料理の名前の一つ。
小間切れの牛肉と玉ねぎ等の野菜を醤油系のだし汁等を使用して煮込んだものを具材として、炊いた米飯の上に盛り付けて食べる料理。
家庭料理でもあるが、ファーストフードの外食産業としても一つのジャンルを築いている料理である。
→ 吉野家
- 牛肉 - ぎゅうにく
-
食用の牛のこと。日本では地域により消費量がかなり異なる。
一般的には 牛肉はごちそうメニューの位置付けである事が多いが、関西ではおかずメニューの位置付けであるようだ。
牛肉は 和牛を代表する食肉を前提とした牛や、乳牛を食肉に利用する物まで 畜種や品種など様々である。
日本では霜降りの牛肉や スライスされた牛肉が好まれる傾向が強いが、アメリカ等では赤身のブロック肉が好まれる傾向がある。
→ 和牛
→ 霜降り
→ 畜種
→ 品種
- 牛めし - ぎゅうめし
- 一般的には牛丼と同じ。
外食チェーン店の松屋においては、提供するメニューの名前は牛めしとしている。
→ 牛丼
→ 吉野家
→ 松屋
- 業界用語 - きょうかい ようご
- その業界の中でしか通用しない 言葉・用語 のことである。
食肉業界においても、当然色々な業界用語が存在する。
- 狂牛病 - きょうぎゅうびょう
- 牛海綿状脳症のこと。
日本では 2001年(平成13年) 9月に発生が初めて確認された。
→ BSE
→ 特定危険部位
→ トレーサビリティ法
- 餃子 - ぎょうざ
- もともとは中華料理。
挽肉などの具材を小麦粉ベースの皮で包んで焼いて食べる料理。
具材の種類も現在では豊富であるが、調理方法も焼く以外に、揚げる・煮る・蒸すなどバリエーションは様々である。
豚の挽肉を用いる事が多いが、牛豚の合挽き肉を使用する場合もある。
→ 挽肉
→ 焼餃子
→ 水餃子
- 業種 - ぎょうしゅ
- 日本標準産業分類に基づいて定められている。
小売、卸売、流通など、と分類される。
さらに、小売業的には、ざっくり言うと「何を売っているか」が業種の事である。一例としては、酒、肉、魚、野菜、・・・等である。
→ 日本標準産業分類
→ 業態
- 競合 - きょうごう
-
→ 競合店
- 競合店 - きょうごう てん
- 商売敵(しょうばい がたき)の事。
チェーンストアの場合、自社競合も・・と言うのは笑えない現実。
→ 自社競合
→ 価格調査
→ チェーンストア
- 業態 - ぎょうたい
- 小売業においては、販売する店の規模の事を指す言葉として用いられる事が多い。
一例としては、百貨店、総合スーパー(GMS)、スーパーマーケット(SM)、コンビニエンスストア(CVS)、ディスカウントストア、等である。
→ 業種
→ 小売業
→ スーパーマーケット
→ コンビニエンスストア
- 去勢 - きょせい
- 食肉業界においては、雄(オス)の家畜(主に牛)の肉質を良くする為に行われる行為、またはその行為によって得られた商品の事を指す。
子孫繁栄に必要な生殖機能を経つ事によって、食肉としては品質が上がる。
→ 牛肉
→ 経産
→ 未経産
- 魚肉ソーセージ - ぎょにく そーせーじ
- 畜肉では無く、魚肉を主原料としたソーセージ風の商品のこと。
定義としては、「魚肉の原材料に占める重量の割合が50%を超え、かつ、植物性たん白の原材料に占める重量の割合が20%以下であるものに限る」(JAS規格)とされている。
常温で保存可能な商品が多い。
→ フィッシュソーセージ
→ JAS規格
→ ソーセージ
→ ホモソーセージ
→ 畜肉
- キワモノ - きわもの
- 際物という言葉からきている表現。
ハレの日等、その時にしか売れない商品の事を指す。
一例としては、クリスマスの骨付きチキンや、子どもの日の菖蒲・ゆず、彼岸の団子など。
→ ハレの日
- 串揚げ - くし あげ
- 料理名。食材を串に刺して油で揚げた料理のこと。食材に小麦粉やパン粉等の衣を付けて調理する事が一般的である。
食材には、食肉の他、魚介類、野菜など何でも良い。食肉業界においては、串カツと呼ばれる料理のことを意味する場合も多い。。
→ 串カツ
→ 串焼き
- 串カツ - くし かつ
- 料理名。食材を串に刺し、小麦粉やパン粉等で衣を付けた物を油で揚げた料理のこと。串揚げとも呼ぶ。食材には、食肉の他、魚介類、野菜など何でも良い。日本国内での地域によって具材も調理方法も食べ方も様々である。
→ 串揚げ
→ 串焼き
→ オイルフォンデュ
- 串フランク - くし ふらんく
- 串に刺したフランクフルトのこと。
夏場のバーベキューシーズンに需要が高い。
アウトドアで炭火で焼いて食べる、串付きフランクフルトは美味しい。
→ バーベキュー
→ フランクフルト
→ ソーセージ
- 串焼き - くし やき
- 料理名。その名の通り 食材を串に刺して焼いたもの。
食肉業界においては、ほぼやきとりの意味である。
一般的には、肉だけではなく、野菜を串に刺した料理の事も含む。
→ やきとり
→ 串揚げ
- 苦情 - くじょう
- 商品・サービス等について顧客から不満等の御意見を寄せられること。
→ クレーム
- グレイビー - ぐれいびー
- 調理された肉から出る肉汁を使用して作られるソースのこと。
炒めた小麦粉や片栗粉に肉汁を加えて作る。
アメリカでは、ローストビーフやミートローフ、ステーキ等にも使われる。
- クレーマー - くれーまー
- 悪意を持って小売店・販売者側に何らかの要求をしてくる、面倒臭い消費者のことを指す俗称。
販売店側にとっては面倒臭いの一言である。
→ 苦情
→ クレーム
- クレーム - claim(英) - くれーむ
- 苦情とほぼ同意語であるが、小売店の現場においては、より対処に難易度の高いスキルを要求される物を指す場合が多い。
明らかに理不尽な内容や、誠意ある形や対応を求められる行為を要求される事例に使用される言葉である。
claim の本来の意味は提言である。
→ 苦情
→ クレーマー
- クロス - くろす
- クロス販売の略。
→ クロス販売
- クロス販売 - くろす はんばい
- 関連販売のこと。
小売業界の店舗において、部門や部署を超えた商品を品揃えして販売する手法。
→ 関連販売
- 黒毛和牛 - くろげ わぎゅう
- 和牛の品種の代表格。
和牛と表示する事が出来るルールは、日本の法律で厳しく決められている。
和牛は全部で4つの品種からなるが、そのうちの一つである黒毛和種の事である。出荷量ベースで和牛の過半数を超え8割程度とされる。
→ 和牛
→ 黒毛和種
- 黒毛和種 - くろげ わしゅ
- 牛の品種の一つであり、和牛の代表的な品種である。
見た目は毛色等が黒色であり、肉質は脂肪交雑が密に入りやすく、食肉としては濃厚な味わいであり、日本人の好みである。
流通量では、和牛の80%以上が黒毛和種であるとされている。
→ 和牛
→ 品種
- 黒豚 - くろぶた
- バークシャー純粋種の豚肉。
法律上の定義では、国産・外国産を問わない。
きめ細かなやわらかな肉質と、旨みが特徴。
種としては小柄な事と脂身が多く歩留まりが悪い為、食肉としての量があまり取れないのが難点。
日本では高級な豚肉として位置づけられ、鹿児島産であることが ブランドとされる時代があった。
→ バークシャー種
→ 白豚
- 燻煙 - くんえん
- 食品を保存性を高めることを目的とした手法として、香りの良い木材などを燻してその煙を食材にあてることにより加工する技術・技法のことを指す。
→ 燻製
→ 加工肉
- 燻製 - くんせい
- 食肉などの傷みやすい食材を燻煙することにより保存性を高めることを目的に加工すること。
→ 燻煙
→ 加工肉
- 経産 - けいさん
- こどもを産んでいる事を指す。
食用の牛肉においては、メスの場合、こどもを産んでいるか いないかによって、その肉質の評価が異なる。
未経産の方が肉質の評価が高い。
→ 未経産
→ 去勢
- 景品表示法 - けいひんひょうじほう
- 不当表示や過大な景品類の提供を規制する法律。
独占禁止法の特例法として制定された。正式には 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)という。
→ 優良誤認
→ 公正取引委員会
- ゲームミート - げーむみーと - game meat[英]
- 日本では牛豚鶏 以外の肉の事を指す場合が多いが、狩猟(ゲーム)で得た食肉の事を指す用語。
→ ジビエ
- 下段 - げだん
- SM(スーパーマーケット)において いちばん売りたい商品を陳列する場所のこと。
多段ケースにおける販売方法において、最も下の段に商品を陳列・販売すること。
コンビニとは異なり、SM等の小売店の主力となる陳列ケースである多段ケースにおいては、最も消費者の目を引きやすく、陳列量もたくさん確保できる 売り込み場所となる。
その大切な場所で、何をどう販売するかは、販売者にとっては重要な位置付けであり、下段販促などという言葉もある程である。
→ 多段ケース
→ 平台
→ 販促
- 月桂樹 - げっけいじゅ
- ここではローレルを参照して欲しい。
→ ローレル
- 決算 - けっさん
- 企業がどれだけ儲かっているのか、または損失を出しているのかを世間に公表すること。
日本では、会社法という法律に基づき、上場企業においては四半期(1年に4回)毎に、財務状況を報告する事が義務付けられている。
流通・小売業界においての本決算は2月に集中しており、この時期は業績のつじつまを合わせる為に、決算謝恩セールなどと銘打って、売り出しを行う企業もある。
→ 棚卸
→ 売り出し
- 結着剤 - けっちゃくざい
- 食品の保水性を高め、形状を保ったり食感を良くするために加えられる材料のこと。
主な結着剤として、ピロリン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウムなどのリン酸塩や、カゼインナトリウムなどがある。
→ 添加物
- 欠品 - けっぴん
- 小売業界において、商品が売場に並ばないこと。
期待して来店されたお客様に対しては、大変な迷惑をかける事象である。
メーカーや物流の諸事情において、欠品が生じる場合がある。
品切れ という用語とは、厳密には意味合いが異なる。
→ 品切れ
- げんこつ - げんこつ
- 豚の骨の中でも、特に上質なスープが採れるとされている 膝関節の大腿骨 のことである。見た目の形状が人間の拳に似ている事からこう呼ばれるようになった。
主にラーメンのスープとして利用される。
→ ガラ
→ 豚骨
- ケンタッキー - けんたっきー
-
→ ケンタッキーフライドチキン
- ケンタッキーフライドチキン - けんたっきー ふらいど ちきん
- 元祖フライドチキンの小売・飲食店。
日本では1970年より営業している。1939年にカーネル・サンダースが編み出したこだわりのレシピ・製法にて店舗内にての手作りがモットー。
→ フライドチキン
⇒⇒ ケンタッキーフライドチキン (外部リンク)
- ケンネ脂 - けんね あぶら
- 牛の腎臓の周りに肥大した脂のこと。主にすき焼用の脂として用いられる。小売店ではたいてい無料のサービスとして提供していることが多い。
和牛の脂は濃厚で上質な旨みがあるので、このケンネ脂で調理すれば大抵の料理はとても美味しく仕上がる。
→ 牛脂
→ ヘット
→ ラード
- 原料原産地 - げんりょう げんさんち
- 産地表示の方法のひとつ。
食肉の原産地か、加工地かを明確に区分する為の表示のルールであり、JAS法で定められている。
食肉を小売店が販売する場合、食肉そのものを販売する場合は通常通りの産地表示を行うが、パン粉付けや味付けなどの加工を伴った形で、食肉が素材として販売される場合には原料原産地表示をする。加工場所や加工する為に使用した物の産地ではなく、原料である食肉の産地がどこの物であるかを明確にする為の表示方法。
→ 国産
→ 産地表示
→ JAS法
- 交雑種 - こうざつしゅ
- かけあわせの意味。食肉業界では、牛・豚・鶏を問わず、低コストで生産効率の良いものを求め、様々な交雑種が存在する。
一例 : 黒毛和種の雄牛×ホルスタイン種の雌牛の他、和牛間交雑種、肉専用種と乳用種など。
交雑種のことをF1という場合もある。
→ 品種
→ F1
→ 純血種
- 香辛料 - こうしんりょう
- スパイスのこと。
→ スパイス
- 広告 - こうこく
- 企業等の宣伝活動のこと。小売業界においても、テレビ・新聞・新聞の折り込みチラシ・看板・ダイレクトメール・ネットメール等の方法で幅広く広告を行っている。
→ チラシ
- 公取 - こうとり
-
→ 公正取引委員会
- 公正取引委員会 - こうせい とりひき いいんかい
-
日本の行政機関の1つで、独占禁止法を運用するために設置された。
また独占禁止法の特別法である下請法の運用も行っている。
⇒⇒ 公正取引委員会 (リンク集)
- 厚生労働省 - こうせい ろうどう しょう
-
日本の行政機関の1つで、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進、並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2001年に厚生省と労働省が統合されて現在の厚生労働省となった。
食肉業界に深い係わりを持つ、食品衛生法を管轄する機関である。
⇒⇒ 厚生労働省 (リンク集)
- 口蹄疫 - こうていえき
-
家畜の伝染病の一つ。人間には感染しない。
伝染力が高く、家畜業界においては問題となる事が多い。
発生が確認された場合は、他の良好な家畜に伝染しないように、家畜伝染病予防法に基づいて殺処分される。
- 小売業 - こうりぎょう
- 業種の一つ。生産者(メーカー)や卸売り業者から仕入れた商品を、最終消費者に販売する業種のこと。
仕入れた物に何らかの付加価値を加えて販売する事が小売業の常である。
→ スーパーマーケット
→ GMS
→ 業種
→ 業態
→ 付加価値
- 小売店 - こうり てん
- 消費者に商品を販売する店のこと。
小売店は生産者やメーカー・卸売業者から商品を仕入れて、消費者へ販売する。
→ 小売業
→ 業種
→ 業態
- コーンドッグ(corn dog) - こーん どっぐ
- アメリカンドッグ(和製英語)を参照。
→ アメリカンドッグ
- 顧客満足 - こきゃく まんぞく
- 企業において、顧客に満足してもらえる指標のこと。度合いとして語られることが一般的である。
CS (Customer Satisfaction) と 略して表記される。
顧客満足を得る為には、従業員満足が必要である という議論から この言葉が使用されることが多い。
→ 従業員満足
- 国産 - こくさん
- 日本国内で生産・製造された物の総称。
食肉の場合、生体(生きている状態)で国をまたいで移動があった場合は、最も長い期間肥育・飼育された場所が産地となるという定義がある為、出生地が表示上の産地とならない場合もある。
→ 原料原産地
- 国産牛 - こくさん ぎゅう
- 日本国内で肥育された牛肉の総称。
法律では 品名に表示する為のルールが様々に制定されている。
和牛 と 国産牛 は まったく違うものと言ってもいい。
→ 和牛
- ごちそうメニュー - ごちそう めにゅー
- とっておきの時に食べる料理の事。
→ おかずメニュー
- コチジャン - こち じゃん
-
→ コチュジャン
- コチュジャン - こちゅ じゃん
- 韓国料理で日常的に利用される調味料である。
もち米麹と唐辛子の粉等を原料とした発酵食品である。ビビンバには欠かせない調味料であるが、御当地では基本調味料の一つの位置付けである。
→ ビビンバ
- 個店チラシ - こてん ちらし
- 業界側からの視点でのチラシの種類の一つ。
チェーンストアにおいては、本部チラシと個店チラシという物が存在する。
チェーン店にも係わらず、ある特定の店舗にだけ有効な内容のチラシが個店チラシである。そのチラシの内容は他のチェーン店では反映されない。
その地域ならではの消費者の需要や要求に応えた、きめ細かな内容のチラシを作る事が可能である。
→ チラシ
→ 本部チラシ
- コトPOP - こと ぽっぷ
- セルフサービス式のスーパーマーケットにおいては、商品名と価格を記したPOPは第2の販売員の位置付けであるが、商品の魅力だけではなく、新たな付加価値として調理方法も含めたその商品の特徴をアピールする表示物全般の事を指す。「価値の見える化」がキーワードだが、販売員からお客様への短い手紙という解釈。
→ POP
- 小肉 - こにく
- 鶏肉の部位名の1つ。首の周りのことを指す。
セセリという名前で呼ばれる事も多い。
食感は固いが、味わいは楽しめる部位である。
→ 鶏肉
→ 肩小肉
→ セセリ
- 小間切れ - こまぎれ
- 食肉として、最も消費者に支持されるアイテムの1つである。
安価、どんな料理にも使える、調理しやすいサイズ、等の理由で おかずメニューとしては大活躍の位置付けである。
販売者側からの観点では、焼肉や すき焼き等の商品を加工した後に出る端材を集めて商品化した物を「小間切れ」として販売する事が多いようだ。
小間切れや挽肉(ミンチ)など、PI値の高いおかずメニューの品質(鮮度・価格)の良し悪しが、その小売店のレベルの良し悪しと言っても過言ではない。
→ 切り落し
→ 挽肉
→ 小売店
→ PI値
- コラボ - こらぼ
- コラボレーション - collaboration
共同して制作する事を指す。
小売店においては、例えば、肉を売る為に 調味料や野菜などを一緒に販売する事を指す。
→ クロス販売
→ 関連販売
- こわい - こわい [方言]
- 名古屋弁で固いという意味。
「この肉こわくない?」と聞かれた時の意味は、「この肉は固くないですか?」という意味である。
- コンセ - こんせ
- コンセッショナリー(concessionary)の略語。
大型スーパー等で、売場を借りて出店している専門店チェーンの事。
惣菜、鮮魚、精肉、寿司、漬物など 販売するジャンルは様々である。
契約に従い、コンセは大家に対して賃料等を支払う仕組みになっている。
消費者から見れば、そのスーパーの集中レジにて精算する為 利便性が高い。
→ スーパー
→ テナント
→ 専門店
- コンビーフ - こん びーふ - corned beef[英]
- 塩漬調理された牛肉のこと。缶詰で提供される場合が多い。
保存食やおつまみとしての需要が高い。
牛肉以外の原料が使用されているものは、コンミート等と呼ばれる。
→ コンミート
- コンミート - こん みーと
- 以前は、ニューコンビーフ等と呼ばれていた時代もあったが、原料として、牛肉を使用した物がコンビーフ、それ以外の畜肉を主原料とした物は、コンミートと呼ばれるようにルールが変更された。
→ コンビーフ
- コンビニエンスストア - こんびにえんす すとあ
-
- 小規模な店舗において食料品や生活必需品の日用雑貨品を多品種・少量数、品揃え・販売する小売業の形態。定休日はほぼ無く、長時間営業する。
→ 業態
- コンプライアンス - こんぷらいあんす - compliance [英]
-
- ここでは企業コンプライアンスの事。
企業が法令やルール等に沿って活動することを指す。
法令遵守と呼ばれることも多い。
- サーロイン - さー ろいん - sir loin
- ロース肉の中でもより上質な部位。牛肉に用いられる用語で、ロースを頭側から数えて10本目の肋骨と11本目の肋骨間で切断した腰側の部位をサーロインと呼び、頭側はリブロースと呼ぶ。
きめ細かなやわらかな肉質であり、ステーキとしては上級な部位とされる。
ロース肉の英名は ロイン[loin] である。
→ ロース
→ リブロース
- サイコロステーキ - さいころ すてーき
- 一口大に加工・カットしたステーキ肉のこと。
小売店においては、一枚肉から加工した物と、成形肉として販売される物がある。
ステーキと言えばごちそうメニューの位置付けであるが、サイコロステーキはおかずメニューや、お弁当にも活躍する位置付けのメニューである。
→ 成形肉
- サイミート - さいみーと
- 鶏肉の部位名の1つ。骨付モモ肉の関節より上半分のことを指す。
→ 鶏肉
→ ドラムスティック
- サガリ - さがり
- 牛の焼肉用のアイテムとして、焼肉店などで提供される。
横隔膜のハラミと混同されることも多々ある模様。一頭の牛から取れる量が少ないことから稀少部位とされる事もあるみたいだが、実際には内臓肉の一部でしかない。価格が安い事から食べ放題等の安売り店で、提供される事も多い。
米名 ハンキングテンダー
→ ハラミ
- 先入れ先出し - さきいれ さきだし
- 小売店における商品陳列の基本的な方法。業界用語。
先に仕入れた商品を、先に店頭に陳列して販売するという意味。
日付管理の基本である。
→ 前出し
- さくら肉 - さくらにく
- 食用の馬肉の俗称。桜の花のように色鮮やかな肉色からこの呼び名が付いたという。馬肉を食用とする地域は日本でも限られており、熊本、甲信越、東北地方などとなっている。
→ 馬肉
- サシ - さし
- 牛肉を評価する時によく使われる言葉。
赤身肉である筋肉の中に脂肪がきめ細かに網目状に広がっている状態を、サシが入っている、表現される。
サシがよりきめ細かに たくさん入っているほど、その評価は高くなる。
高級牛肉は脂肪に旨みがあり、舌触りや食感、やわらかさなど、サシが入っているほど、実際に美味しい。
→ 霜降り
→ 牛肉
- サッカー - さっかー
- スーパーマーケット等のレジ業務において、チェッカーのフォローとして包装業務に携わる人・又はその業務の事を指す。
イギリス英語では袋詰め作業する店員を sacker と呼ぶが、日本ではスーパーで袋詰めを専門に行う係員はいない。
昨今では多くの自治体においてレジ袋が有料化された事により、消費者が基本的に袋詰めをする為、スーパーマーケットにおいては サッカー業務はさほど重要では無くなりつつある。
→ サッカー台
→ スーパーマーケット
→ チェッカー
→ キャッシャー
- サッカー台 - 作荷台 - さっかー だい
- スーパーマーケットにおいて、レジで精算を終えた後に、店舗の買物カゴから、消費者が持ち帰る袋に移し替える場所の台のこと。
→ スーパーマーケット
→ チェッカー
→ キャッシャー
- ザブトン - ざぶとん
- 牛肉の部位の「肩ロース」の一部 の俗称。
その見た目の形状から「ザブトン」と呼ばれる。
とても柔らかくて、供給される量も少ないことから希少部位とされる。
焼肉屋さんでは「ハネシタ」という名称で提供される事が多いようだ。
→ ハネシタ
→ 肩ロース
→ 希少部位
- サムギョプサル - さむ ぎょぷさる - 삼겹살 [韓国語]
- 豚バラ肉を使用した韓国料理のこと。
厚めにスライスした豚バラ肉を焼いて、好みの調味料やみそ・キムチなどと共に食べる料理。レタスに巻いて食べるとおいしい。
バリエーションは豊富である。
→ バラ
→ サンチュ
- サラミ - さらみ
- ドライソーセージのジャンルの一つ。
原材料を牛肉および豚肉のみで作った物をサラミと定義している。
→ ドライソーセージ
→ セミドライソーセージ
→ おつまみ
- ザワークラウト - ざわー くらうと - Sauerkraut[独]
- 料理名。キャベツを乳酸発酵させた料理の事である。
ドイツでは、ソーセージの付け合わせとしてポピュラーである。
→ 酢キャベツ
- サンカクバラ - さんかくばら
- 前バラ (または 肩バラとも呼ばれる) の部位の一つで、上カルビと呼ばれる所。
サシが良く入り、食感は柔らかく、旨みも濃厚。稀少部位の一つ。
→ 上カルビ
→ バラ
→ 希少部位
- 産地 - さんち
- 生産地のこと。食肉業界においては表示に関して一定のルールがある。
→ 産地表示
- 産地表示 - さんち ひょうじ
- 複数の法律や規約により表示が義務づけられている。
食肉の場合、最も肥育期間が長かった場所。複数の食肉が混合された形態で販売される場合は、重量の多い順にそれぞれの産地を表示する。
JAS法、食品衛生法、食肉の公正競争規約などの法律や規約によって表示方法が定められている。
→ 原料原産地
→ JAS法
- サンチュ - さんちゅ - 상추 [韓国語]
- レタスに良く似た野菜のこと。
焼いた肉をサンチュに包んで食べる。韓国の焼肉料理においてはポピュラーな食べ方である。
→ 焼肉
- 三枚肉 - さんまいにく
- 豚バラ肉のこと。
赤身と脂身が交互に層を成して見える形態から、俗称として呼ばれる。
→ バラ
- CS - しー えす
- Customer Satisfaction (CS) 。
- 顧客満足(度) のこと。
小売店においては、商品の品質・価格・品揃え、更には店舗機能や、従業員の接客態度やレベル等の総合的なサービスにおいて CSは決まるといわれている。
→ 顧客満足
→ ES
- GMS - じー えむ えす
-
- General Merchandise Store の略。
→ 総合スーパー
- 仕入れ - しいれ
-
- 小売業において、販売する為の商品を手配すること。
具体的には、発注という作業に基づいて商品を取引先から購入するである。
仕入れた物に付加価値を加えて、消費者に販売するのが小売業である。
→ 発注
→ 小売業
- Jミート - じぇい みーと
-
- 日本国産の食肉の事。
(財)日本食肉消費総合センターが定義・アピールしている呼称である。
Jビーフ、Jポーク、Jチキン等の呼称を設定している。
→ (財)日本食肉消費総合センター
- 塩 - しお
-
- 調味料の食塩のこと。
こだわりの塩や、塩味をベースとしたスープや調味料、すき焼きのタレまで色々存在するが、素材の持ち味を活かした調味料としておすすめ。
- しぐれ煮 - しぐれに
-
- 料理名。
元々は蛤(はまぐり)を原料として、生姜等の薬味を使って煮詰めた料理の事を指すが、現在においては、牛肉を原料としたものに生姜等の薬味を使って煮詰めた料理の事を指す事もある。
- 仕越し - しこし [業界用語]
-
- 翌日以降の為に 前日から商品の準備する事を指す。
→ まわし
- 自己責任 - じこ せきにん
-
- 人間・各個人 自らの責任において判断・対応をすること。
買いだめした品の 期限切れの商品をまだ食べられますか?とか、いちいち販売店に電話してくるな、という意味。
- 試食 - ししょく
-
- 食品において、味はかなり大切な要素である。
新しく取り組む商品、売り込みたい商品の味を知ってもらう為に、小売店において実際にお客様に食べてもらい、味を知ってもらうこと。
売り込む従業員においても、その味を知らなければ自信を持ってお勧めする事は出来ないので、従業員においても試食は大切な要素である。
→ 試食販売
→ マネキン
- 試食販売 - ししょく はんばい
-
- 小売店において、販売する商品をお客様に実際に食べてもらう形を取る、販売形式のこと。
新商品や、売り込みたい商品について比較的多く行われる手法。
購買においては、食品は味が大きな要素を占める事からという理由であるが、小売店そのものの にぎわい性や活気づけなどもプロモーションの一つである。
販売する側からすればそれなりの経費はかかるが、匂いや味のアピールは次に繋がる提案として取り組むことも多い。
→ 試食
→ マネキン
- 自社競合 - じしゃ きょうごう
-
- 本来は商売敵である、他社の企業と戦うべきなのに、近隣の自社の店舗と戦うことを指す。
→ 競合店
→ チェーンストア
→ ドミナント
- 七面鳥 - しちめんちょう - turkey(ターキー)[英]
- キジ目シチメンチョウ科の鳥。クリスマスの丸焼き料理として有名。
鶏よりも大きく、脂身が少ないのが特徴。
クリスマス料理として西洋では一般的だが、日本では鶏が用いられることが多い。
→ ローストチキン
→ 鶏
- シチュー - しちゅー
- 肉や野菜等を煮込んで作った洋風料理。ビーフシチューやクリームシチューが代表的であるが、バリエーションは多岐に渡る。
スープとよく似ているがこれらを明確に区別する定義は無い。
シチューはメインの料理になる傾向が強く、スープはそうでない場合が多い。
牛肉でシチューを作るなら、スネ肉を強くお勧めしたい。
手間暇はかかるが、煮込む程に味わいは増し、手間をかけただけのシチューが出来る事と思われます。
→ スープ
→ ポトフ
→ スネ肉
- ジビエ - じびえ - gibier[フランス語]
- 野生に生きている鳥獣を食用として捕獲したもの。
フランス料理業界の用語である。
→ ゲームミート
- 品切れ - しなぎれ
-
- 商品が売場に無いこと。
期待して来店されたお客様に対して迷惑をかけるので、大きな悪である。
小売業界における専門用語の一つであるが、欠品という用語と区別している企業もある。
狭義ではあるが、品切れとは販売者側の責任(ミス)による事を指す。発注を間違えた等による理由が多い。
対して、欠品は 外部環境等により、メーカーや物流事情等により商品の納品が間に合わずに売場に並ばなかった事を指す。
→ 欠品
→ ロス
- シフト - しふと
-
- シフト勤務の略。小売業のみならず労働形態において一般的に使用される言葉。早番・遅番など、従業員を売上波動に応じて勤務計画を立てて配置、勤務させる形態を指す。
スーパー等の小売業界も大手では、年中無休・長時間営業が当たり前になって来ているが、従業員はずっと働き続ける訳にはいかないので、計画に基づいて働こうという思想である。
→ 年中無休
- 脂肪交雑 - しぼうこうざつ
-
→ BMS
- 霜降り - しもふり
- ・特に牛肉の高級部位で用いられる表現で、赤身の中に脂が細かくきれいに入っている状態のこと。見た目の通りで霜が降ったような様からこのように呼ばれる。
・調理用語としては、肉や魚に熱湯をかける または 湯通しして 下処理をする事を意味する。鶏肉のささみをしゃぶしゃぶ風の調理方法(食べ方)の事を「しもふり」とも呼ぶ地域もある。
→ サシ
→ 牛肉
→ 鶏肉
→ しゃぶしゃぶ
- 社員販売 - しゃいん はんばい
- 自社の商品をより安い価格で購入できる制度を仕組みのこと。
社員(従業員)への福利厚生の意味と、少しでも自社での売上高の貢献に寄与して欲しいという意味も込められているようだ。
企業によっては、期間を限定した特別にお買い得な社販を設定している所もある。その場合は事前予約制である事が多いようである。
従業員販売と同意。社販と略される事もある。
→ 社販
- 尺 - しゃく
- 日本古来の距離や長さを示す単位。1尺は0.303メートルである。スーパーにおいては現代においても売場のケースの長さ等を示すのにこの単位が使われている。
→ 什器
- JAS - じゃす
-
→ JAS規格
- JAS法 - じゃす ほう
- 正式な名前は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」。
「JAS規格制度」と「品質表示基準制度」の2本立てであり、食料品等の品質や表示について定めた法律のことである。
→ JAS規格
⇒⇒ JAS法とは (農林水産省) (外部リンク)
- JAS規格 - じゃす きかく
- 日本農林規格のことであり、Japanese Agricultural Standard の略。
「JASマーク」でおなじみ。
→ JAS法
⇒⇒ JAS規格について (農林水産省) (外部リンク)
- JASマーク - じゃす まーく
- 食肉業界においては、ハム・ベーコン・ソーセージ等に規格が制定されており、その品質に見合った商品にはそのマークが付与される仕組みとなっている。
JASマークは企業が申請する事によって交付される仕組みとなっている為、マークが無いからと言って品質に問題があるという事にはならないのが現在のジレンマである。
→ JAS規格
- シャトーブリアン - Chateaubriand[英] - しゃとー ぶりあん
- 牛のヒレ肉の中でも最も中心部の太い部分を使ったステーキのこと。
希少価値の高いヒレ肉の中でも、最も中央部の太い部分のことを指し、最高級とされる。
食肉用の牛は生体で1頭あたり とてもアバウトではあるが、だいたい500kgくらいの重量であるが、シャトーブリアンは約800g程度しか取れない。それほど希少価値の高い部分である。
→ ステーキ
→ ヒレ
→ 希少部位
- 社販 - しゃはん
- 社員販売の略。従業員販売と同意。
→ 社員販売
- しゃぶしゃぶ - しゃぶしゃぶ
- 薄くスライスした肉を 煮えたぎった湯の中に通してタレを付けて食べる料理。タレはポン酢やごまだれが美味しい。
肉は牛肉を用いることが一般的とされるが、豚や鶏でも何でも良い。野菜も一緒に食べる。
外食産業としては高級料理としての位置付けとされる。
→ スライス
→ 豚しゃぶ
→ 蒸ししゃぶ
→ 焼きしゃぶ
- シャモ - 軍鶏 - しゃも
- もともとはタイ産のニワトリの一種。闘鶏用の鶏であった。
食用としても用いられ、味が良い為人気があるが、供給される数が少ない為、高級食材の位置付けとなっている。
→ 鶏
- シャリアピン・ステーキ - しゃりあぴん ・ すてーき
- 玉ねぎのみじん切りに漬け込んだ後に焼き上げたステーキのこと。
玉ねぎには たんぱく質を分解する酵素 が含まれており、お肉を軟らかくする効果がある。
→ ステーキ
- 什器 - じゅうき
- 商品を販売する為に陳列する台・器具や商品をより目立たせるための器具などの事を指す。
→ 商品
→ 陳列
→ 販促
→ 尺
- 従業員販売 - じゅうぎょういん はんばい
- 社員販売と同意。
→ 社員販売
- 従業員満足 - じゅうぎょういん まんぞく
- 企業において、従業員が企業に対して抱く思いの指標。
顧客満足という言葉の対比として使用されることが多い。
ES (Employee Satisfaction) と略して表記される。
顧客の満足度を語るには、従業員の満足度が高くなければ ならないという風潮が前提にあるとされる。
→ 顧客満足
- 熟成 - じゅくせい
- 食肉においては、取れたてやおろしたてが美味しいとは限らない。
と畜してから、ある一定の期間を寝かせる事により、旨味が増す。
一般的な期間よりも更に長い時間をかけて熟成する事を、エイジングと呼ぶ事もある。
旨味が増すが、販売者的には、乾燥して商品重量が減ったり、表面の鮮度劣化が始ったりと、リスクも高い。
→ エイジング
→ 寝かす
→ 冷やし込み
- 主任 - しゅにん
-
→ チーフ
- 純血種 - じゅんけつしゅ
- 家畜を交配する際に、同じ品種内で交配をすること。かけあわせをしないことを指す。
→ 交雑種
→ 品種
- 生姜 - しょうが
- 植物の名前。食材や香辛料・薬味として用いられる。
根っこの部分を擦りおろした物が香辛料として使われる。
→ 生姜焼き
- 正月営業 - しょうがつ えいぎょう
- 小売業において正月に営業する事は、近年では普通の事となっているが、一部の大手スーパー等においては、従業員の福利厚生の意味合いも込めて、正月営業を撤廃して休日とする動きもある。
- 生姜焼き - しょうが やき
- 料理名。やや厚めにカットした豚ロース肉を用いるのが一般的ではあるが、部位はロース肉以外でも、肩ロース肉やモモ肉でも、お好みである。
生姜汁を加えた、醤油・酒・みりん等の調味料を用いるのがポイント。肉の臭みを消して、食欲をそそる。白いご飯に良く合う日本料理の一つである。
→ 生姜
- 上カルビ - じょう かるび
- 焼肉屋のメニューでよくある表示ではあるが、その定義は無い。
バラ肉を使った焼肉の事をカルビと呼ぶが、バラ肉の中でも こだわった部位を「上カルビ」と表現しているようであるが、定義が無い以上、適当な感じである。
→ サンカクバラ
→ カルビ
→ バラ
- 松竹梅 - しょうちくばい
- 比較販売のこと。
→ 松竹梅 商法
→ 比較販売
- 松竹梅 商法 - しょうちくばい しょうほう
- 小売店による比較販売の手法の一つ。
一例を挙げると、販売店が焼肉を売り込みたい時に、いちばん売り込みたい品を「竹」と設定する時、比較の為にそれより上や下のグレードの商品を一緒に陳列販売すること。
消費者の心理として、自分で選んで購入したという満足感も得られる。
蛇足だが、松竹梅とは、「上・中・下」の品ぞろえのことである。
→ 比較販売
- 消費期限 - しょうひ きげん
- 傷みやすい食品に表示される食用可能期限のこと。
開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限を製造者が定めて表示する。
概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材に対して用いられる。
→ 賞味期限
→ 偽装
- 消費者庁 - しょうひしゃ ちょう
- 2009年に発足した日本の行政機関の一つである。
食肉業界に係わりの深い項目としては、食品を販売する時点での表示等がある。
⇒⇒ 消費者庁 (リンク集)
- 商品 - しょうひん
- 物品を販売をする、販売者側からの視点の言葉である。
スーパーなどの小売店に陳列されている物は、すべて商品である。
顧客(消費者)はレジにて代金を払う事によって、自分の物とする事が出来る。
平たく言うと、会計が終わるまでは店の物である。
ちなみに 物の価値(価格)は、その品物の需要と供給のバランスによって決まる。
→ 買物
→ 非売品
- 商品部 - しょうひん ぶ
- チェーン展開する小売店においては、仕入れ業務を本部が一括して行う仕組みを取っている所が多い。その商品を仕入れる本部の部署の事、またはその担当バイヤーの事を商品部と呼称する。
→ バイヤー
→ 本部
- 正肉 - しょうにく
- 枝肉から切り出した部分肉から骨を取り除いた肉。一般的には余分な脂肪その他を除去した肉を指す。
正肉を商品化する際に発生する物のことを副産物と呼ぶ場合がある。
→ 副産物
- 賞味期限 - しょうみ きげん
- 風味を損なうことなく、美味しく食べられる期限のこと。
消費期限とは区別される。
→ 消費期限
- 食中毒 - しょく ちゅうどく
- 原因は様々であるが、食品を摂取する事によって下痢や嘔吐など中毒症状を起こす事を指す。
まれには死亡するケースもある。
原因としての多くは、食材が細菌やウイルスに汚染されていたという事が多い。
消費者が特に気を付けるポイントは、次の2点。
1. 食肉は加熱調理して食べること。
2. 調理に使用するトング(又は 菜箸)と、喫食用の箸を明確に分けること。
→ 生食
→ トング
- 食品安全委員会 - しょくひん あんぜん いいんかい
- 食品安全基本法にの制定により、設立された内閣府直轄の委員会。
関係機関から独立して、中立的にリスク評価を行う機関。
→ 食品安全基本法
- 食品安全基本法 - しょくひん あんぜん きほん ほう
- 食の安全を守る為に制定された法律。2003年(平成15年)施行。
食品衛生法を補完する形の法律として位置づけられる。狙いは「国民の健康の保護」という位置づけだが、集団食中毒事件や、心無い企業による産地偽装を取り締まる為の法律として効力を発揮する事が期待される。
内閣府管轄の法律として位置付けられ、食品安全委員会が設置される。
→ 食品安全委員会
→ 食品衛生法
- 食品衛生責任者 - しょくひん えいせい せきにんしゃ
- 食品衛生責任者養成講習を受講した者。保健所に届け出が必要である。
- 食品衛生法 - しょくひん えいせい ほう
- 食品や添加物の規格・使用方法・表示方法等について定めたもの。
食品の安全を維持・確保する為に制定された法律で、厚生労働省によって維持・管轄される。
1948年に施行され、2003年に改訂されている。
→ 厚生労働省
- 食品表示 - しょくひん ひょうじ
- 小売店が販売する際の食品表示のルールについては、複数の様々な法律に対応する必要がある。主な所では、農林水産省の管轄するJAS法、厚生労働省の管轄する食品衛生法 の2つであるが、その他にも 計量法、景品表示法、不正競争防止法、健康増進法、薬事法 等の法律、更には、業界団体の定める規約やルール等に対応する必要がある。
2009年に消費者庁が発足し、消費者の立場に基づいて法律やルールを一元管理する事となったが、消費者の求める表示に法律が対応するのには 今しばらくの時間がかかりそうである。
小売店等の販売する側も、表示のルールに対応する為にかなりのエネルギーを費やしているのは事実である。
(この項目の更新日 2012年5月)
- 食品表示検定 - しょくひん ひょうじ けんてい
- 食品表示検定協会 が行う 試験制度のこと。
2009年より試験制度がスタートしている。
→ 食品表示
- 食品表示法 - しょくひん ひょうじ ほう
- 消費者庁が管轄する法律の名前。
消費者の立場に立ったわかりやすい表示を目指している。
→ 食品表示
→ 消費者庁
- 食品添加物 - しょくひん てんかぶつ
- 食品を製造する時に添加される物の総称で、着色料・保存料・発色剤などがある。
→ 着色料
→ 保存料
→ 発色剤
→ 結着剤
- 食肉 - しょくにく
- 食用とする鳥獣の肉。
→ 畜肉
- 食肉公正競争規約 - しょくにく こうせい きょうそう きやく
- 各都道府県単位で、公正取引委員会の定める規約を基本として制定されていたが、平成7年に全国統一規約が認定された。
→ 全国食肉公正取引協議会連合会
→ 公正取引委員会
- 食肉小売品質基準 - しょくにく こうり ひんしつ きじゅん
- 農林水産省が、畜産局長通達をもって食肉小売業界に対する指導行政の一環として定めたもの。途中で改訂されているとは言え1977年に定められたこの基準は現代にそぐわない部分もあるように思われる。
内容は、消費者が適正な商品選択が出来るように牛肉・豚肉の小売店での部位名の表示ルールを定めたもの。
⇒⇒ 食肉小売品質基準 (表示に関する資料)
- 白豚 - しろぶた
- 明確な定義のある用語ではないが、黒豚の反意語として用いられる。
黒豚ではない、普通の豚のこと。
→ 黒豚
→ 豚
- ジンギスカン - じんぎすかん
- 羊の肉を焼いて食べる料理の事。
日本では、北海道や長野県等で特に好まれる料理である。
煙突状に尖った形の鍋を使用して調理する事でも有名である。
→ 羊
→ ジンギスカン鍋
→ ラム
→ マトン
- ジンギスカン鍋 - じんぎすかん なべ
- ジンギスカンをする為の調理器具のこと。
煙突状に尖がった中央部から、脂を落とす為に設計された周辺部という形状である。野菜を周辺部に配置して、肉を中央部分にに貼りつける様にして焼き上げる様にして調理する。
→ ジンギスカン
- 真空パック - しんくう ぱっく
- 保存方法の1つ。ハムやウインナーなど、長期保存を目的とした食材・原料などをフィルム等で覆い、空気を抜いて酸化を防ぐもの。現在では酸素のみを抜いたガスパックなどの手法も一般的である。
→ 保存
- 真空もれ - しんくう もれ
- 真空パックのフィルム等に傷が付いたりして、真空状態が保たれなくなること。目に見えないような小さな傷でも保存に問題をきたす場合がある。
→ 真空パック
→ ピンホール
→ 保存
- 水餃子 - すい ぎょうざ
- やや厚手の皮を用いた餃子を、お湯で茹でて食べる料理。
正式な定義は無いが、スープ餃子と呼ばれる事もある。
茹でた後に冷やして食べる、夏の水餃子もアリである。
→ 餃子
→ スープ餃子
→ 焼餃子
→ ワンタン
→ 点心
- 水分活性 - すいぶんかっせい
- 食品中の水分含有量ではなく、微生物が成育する為に必要な水分の割合を示す値。水分含有量だけではなく、糖質や食塩濃度によってもこの値は変わる。
→ 生ハム
- スーパー - すーぱー
- スーパー・マーケット。(supermarket、 SM )のこと。
現在では普通に「スーパー」という言葉が認識されているが、正しくはスーパーマーケットの略語である。
→ スーパーマーケット
→ SM
- スーパーマーケット - すーぱー まーけっと
- セルフサービス方式を主体とした大規模小売店のこと。
「スーパー」と略して呼称される事も普通である。
顧客は自らの意志で陳列されている商品を買物かごに入れ、集中レジにて精算をするシステムである。
セルフサービスの意味は、ノーサービスでは無い。
→ 業態
→ セルフサービス
→ ノーサービス
→ SM
→ GMS
→ 大規模小売店
- スープ - すーぷ
- 肉や野菜を煮込んだ洋風料理のこと。
シチューと区別する明確な定義は無いが、スープの方がより汁が多く、具が少な目であることが多い傾向にある。
→ シチュー
→ ポトフ
→ 鍋スープ
- スーパーセンター - すーぱー せんたー
- 食料品・日用品を中心に生活に必要な物が何でも低価格で揃う、集中レジ方式の広大な敷地と駐車場を兼ね備えた店。低層構造であることが多い。
→ ディスカウントストア
- すき焼き - すきやき
- スライスした牛肉を、割り下と呼ばれる調味料を用いて焼く、もしくは煮る料理のこと。地域によって用いる肉の畜種や、調理方法など様々である。
「鋤焼」という表記がされる場合もある。
→ 割り下
→ 鍋料理
- 酢キャベツ - す きゃべつ
- 料理名。酢を用いて調理したキャベツの事を指す。
ザワークラウトのアレンジ料理として、酢酸発酵させなくとも、酢を調味料としてキャベツとともにソーセージ等を煮込み調理した、料理の事も指す。
日本では、こちらの方が一般的かも。
→ ザワークラウト
- スジ - すじ
-
食肉業界においては、商品を正肉として成形する際に取り除く筋(すじ=筋肉)の事である。
牛肉のスジは、おでんや、その他の煮込み料理として使われる事も近年では多い。
とても固くてそのままでは食用に向かないが、長時間煮込む事によって、その食感や味わいを楽しむ人も増える傾向にある。
一般的にはなかなか流通していない部位となる為、スーパー等の小売店では入手が難しい場合もある。
おでん目的の、串に刺した状態の牛スジは、アキレス腱の部分である事が多い。
→ 牛スジ
→ 内臓
→ 正肉
→ 副産物
- 筋引き - すじ ひき - スジ ひき
-
食肉を販売するにあたって、スジを取り除くこと。
筋引きの名の通り、包丁を引いてスジを取り除く行程である。
→ スジ
→ 包丁
- 筋引き包丁 - すじびき ほうちょう
-
スジを引くための包丁である。
包丁の種類においては、洋包丁で 牛刀より刃の部分が細身で片刃であるのが特徴。引いて使用することが前提の包丁である。
→ 筋引き
→ 包丁
- スタミナ - stamina[英] - すたみな
- 体力・持久力を意味する英語。
食肉業界においては、スタミナメニューなどというコピーで売り込みを計る事も多い。
- ステーキ - すてーき
- 肉を厚めに平らにカットして焼く料理。
主に牛肉であることが多い。調理方法が単純であるが故に、焼き加減でその味わいはかなり変わるので、焼き方にはこだわりを持つ人も多い。
日々のおかず的なメニューではなく、ここぞという時のごちそうメニューとして登場する機会が多い。
→ 焼き加減
→ ビフテキ
→ ポークステーキ
→ トンテキ
→ サーロイン
→ テンダーロイン
→ シャトーブリアン
→ シャリアピン・ステーキ
→ 厚切り
- スパイス - spice - すぱいす
- 調味料の一種で、香辛料のこと。肉料理は臭みや生臭さが調理の際に課題となるが、それを打ち消す為に用いられる事が多い。主に植物から作られる。
代表的なスパイスとしては、胡椒や、生姜などが挙げられる。
→ 香辛料
→ ローレル
- スパム - SPAM - すぱむ
- アメリカのHormel Foodsという会社の商品名である。
一般的には、ランチョンミートを缶詰した物のことを指す事が多い。
要はハムの事であるが、缶詰にした事により保存性が高いことが利点である。
→ ランチョンミート
→ ハム
- スネ肉 - すねにく
- スジが多く硬いが赤身の肉である。主にふくらはぎ等の部位。
非常に濃厚な旨味であるが、そのままでは固く食べにくい。
じっくり煮込むシチュー等の料理に向く。
また、挽肉にして餃子の具などとして用いれば、美味しく食べる事が出来る。
→ シチュー
→ チマキ
- スライス - すらいす
- ミートスライサー等の機械を用いて薄くスライスした肉のこと、またはその手法。
すき焼き用、しゃぶしゃぶ用、冷しゃぶ用、焼きしゃぶ用に使われる肉はスライス肉を用いる。肉を大量に消費するアメリカではブロック肉やステーキカットの肉が小売体系として主流であるが、日本においてはスライス肉の方が主流である。
→ 手切り
- 背脂 - せ あぶら
- 豚のロース肉の脂。食肉業界では余計な脂を取り除く目的でトリミングする。豚の背中側に付いている良質な脂。ラーメン業界でスープのコクを増す目的の為に使用されることもある。
→ ロース
→ トリミング
→ 正肉
→ 脂
- 成型肉 - せいけいにく
- 食肉・内臓等を結着剤を用いて貼り合わせたもの。
端材の有効利用であり、上手に商品化されたものは食感もやわらかで価値がある。
→ サイコロステーキ
→ 結着剤
- 生鮮食品 - せいせん しょくひん
-
小売業界における業界用語。傷みやすい食品のこと。
具体的には、野菜・フルーツ・魚・肉などの事である。
鮮度は商品価値の最も大きな要素の一つである。
→ 冷蔵
→ 鮮度
- 精肉 - せいにく
- 料理に使用出来るように加工した食肉のこと、また、加工する行為のことを指す場合もある。
英語では table meat と呼ばれる。
→ 食肉
→ 料理
→ 加工
- 精肉店 - せいにく てん
- 精肉の専門店。個人で運営される規模の店のことを指す事が多い。
精肉だけではなく、手作りのコロッケなどの肉総菜が人気である事も多いが、現在は大手量販店などに押されて 精肉店は少なくなりつつある傾向である。
→ 精肉
→ 肉総菜
→ 量販店
- 精肉部門 - せいにく ぶもん
- 大規模小売店の部門の1つ。精肉を担当する部門。
店内で精肉する部門のことを元々は意味する言葉であるが、現在では外部で加工した物を仕入れて陳列するだけの小売店も増えつつある。
→ 精肉
→ 小売店
→ 部門
→ アウトパック
- セール - せーる - sale[英]
- 本来の意味は販売の事であるが、現在の日本では、大売り出しや特売・バーゲンなど、通常よりもかなり価格を下げて販売する事の意味として使われている。
→ 売り出し
→ 特売
→ バーゲン
- セット - せっと
- 盛り合わせ の意味で用いられる用語。
一例として 焼肉セット、鍋物セット、しゃぶしゃぶセット等。
セットにされたパックを購入すれば、たいていの基本的な需要に応えられるようなイメージで商品を提案する。
→ 焼肉セット
- セセリ - せせり
- 鶏肉の部位の1つで、首の周りの事である。
食感は固いが、味わいはある。市場の流通量は少なくマニアックな食材である。
下処理をした後、味付けをして焼肉材料として食する事をお薦めする。
→ 鶏肉
→ 小肉
- セルフサービス - せるふ さーびす - self service
- スーパーマーケットにおいて主流の方式。顧客は陳列されている品物を自らの意志によって買物かごに入れ、レジにて代金を支払う仕組み。
商品を選ぶ・運ぶなどの行為を顧客(消費者)が行う事を指す。
専門店や百貨店などと対比の意味で使われる言葉。
→ スーパーマーケット
→ 専門店
→ 百貨店
→ ノーサービス
- セミドライソーセージ - せみ どらい そーせーじ
- ドライソーセージの一つ。
JAS規格により その定義が定められており、水分量が35%以下だとドライソーセージであり、35%より多く55%以下の物をセミドライソーセージと呼ぶ。
→ おつまみ
→ ドライソーセージ
→ サラミ
- 鮮度 - せんど
- 生鮮食品の新鮮さの度合いを示す表現。
生鮮食品は、新しいほど美味しいし、その商品価値が高い。
小売店においては、価格だけではなくその鮮度が問われる。
消費者も小売店も、もっと鮮度に気を配るべきである。
→ 生鮮食品
→ 要冷蔵
→ 商品価値
- 専門店 - せんもん てん
- ここでは、スーパー等の大規模小売店舗内において、コンセ または テナント として出店している専門企業のことを説明する。
あらかじめパックに詰めた食肉を販売するだけではなく、顧客のその場での注文に応じて 希望の食肉をグラム単位で量り売りする形態がその最大の魅力である。
昔ながらの町のお肉屋さんでは、当たり前の事ではあったかもしれないが、現在ではそれが魅力となっている。
価格は多少割高であったとしても、欲しいものを欲しい分量だけ、その場で提供してもらえるというのは嬉しいものだ。
→ 注文
→ オーダーカット
→ コンセ
→ テナント
- 総合スーパー - そうごう すーぱー
- 食料品や日用雑貨品だけではなく、衣料品や家電・家具などの様々な商品を総合的に品揃えしている特徴がある店舗やその企業のこと。
GMS (General Merchandise Store) とも言う。
チェーンストアの形式をとっている企業が多いようだ。
→ GMS
→ SM
→ チェーンストア
- ソースカツ丼 - そーす かつどん
- 料理名。カツ丼のバリエーションの一つ。
カツを卵とじにしない状態で、白いご飯の上に 千切りにしたキャベツを盛り付けた上にカツを乗せた後にソースで味付けをする。
長野県駒ケ根市付近で有名な御当地グルメとされる。
→ カツ丼
- ソーセージ - そーせーじ
- 畜肉を、保存目的で挽肉にした後 調味・燻製してケーシングした物を指す。
日本ではJAS規格に基づいて、ウインナー・フランクフルト・ポロニアというカテゴリーに分類される。
→ 畜肉
→ 燻製
→ ウインナー
→ フランクフルト
→ ボロニア
→ 挽肉
⇒⇒ JAS規格によるソーセージ分類 (表示に関する資料)
→ 魚肉ソーセージ
- ソテー - そてー - sauter [フランス語]
- 西洋料理の基本的な調理法の一つ。充分に熱した鍋やフライパンで、食材を炒める事を指す。
→ 炒める
- ターキー - たーきー
-
- 七面鳥のこと。
→ 七面鳥
- 対面 - たいめん
-
- お客様に対して 販売員がついて 接客販売する事。
狭義で平ケースのことを指す。
→ 対面販売
→ セルフサービス
- 対面販売 - たいめん はんばい
-
- セルフ販売の反意語。
販売員が付いて接客して販売する事を指す。
専門店では当たり前の販売方式であるが、セルフサービスを主体とするSM(スーパーマーケット)等においては、あえて区別する意味で このような表現を使用する。
→ セルフサービス
- タコス - たこす
-
- 料理名。メキシコが発祥の地。
牛・豚・羊などの食肉を細かく刻んだ具材に、とうもろこしを原料として作ったトルティーヤと呼ばれる皮に 具材を乗せたり、包んだりして食べる。
→ タコライス
- タコライス - たこらいす
-
- 料理名。米飯にタコスの具材を乗せた沖縄発祥の料理。
バリエーションは様々であるが、キーワードは 牛挽肉・レタス・サルサ と言ったところだろうか。
→ タコス
- タジン - たじん
-
- 現在の日本では、蒸し料理の事を指す。
本来の意味は、調理器具の鍋のことで、とんがり帽子風の特徴的な形をしている。
モロッコやチュニジア等の北アフリカ地方が発祥の地である。
食材は 肉・魚・野菜何でもありで、少量の水で煮込むのではなく、蒸すのがポイント。
具材の旨味や栄養素を逃すことなく調理、そして食する事が出来る。
- タジン鍋 - たじん なべ
-
- とんがり帽子風の形状が特徴的な調理器具のこと。
または、その調理器具を用いて作られる料理ののこと。
→ タジン
- タタキ - たたき
-
- 食肉業界においては、牛のタタキの事を指す。
ブロック状の牛のかたまり肉を 表面は焼くものの 中心部は加熱しない状態で、生食として提供する料理の事を指す。
各種 薬味や調味料を添えて食べる事が多い。
食品衛生法等の法律上の見解では、生食に位置付けられる為、小売店においては 商品としての食肉のタタキ を販売する事はかなりハードルが高いのが現状である。
→ 生食
→ ローストビーフ
- 多段ケース - ただん けーす
-
- 小売店における販売用の什器のこと。
平ケースの反意語でもある。
主に定番品を中心に販売する為の什器で、品揃えやアイテム数をより多く陳列する為に使用されることが多い。その名の通り、複数の棚があり、基本的に商品は選びやすく買いやすいように、カテゴリー毎に縦陳列によって販売される。
→ 平ケース
→ 縦陳
→ 下段
- 竜田揚げ - たつた あげ
-
- 料理名。厳密に定義されるものではないが、唐揚げの一種である。
食材を油で揚げる所は基本的に一緒であるが、竜田揚げの場合は 事前に醤油・みりん等で食材に下味を漬け込むところが大きく違う。
→ チキン惣菜
→ 唐揚げ
- 縦陳 - たて ちん
-
- 縦陳列の略であり、業界用語。
多段ケースにおける商品陳列において、カテゴリー別に分けてきれいに陳列・販売すること。
肉の場合では、焼肉用、ステーキ用、しゃぶしゃぶ用、すき焼き用 等々、料理用途別にそれらの商品が綺麗に縦方向に区別して陳列・販売提案なされている様、又はそのような販売方法を指す言葉。
目的は、お客様が見やすく、選びやすく、買いやすい 売場である。
→ 多段ケース
→ 陳列
→ カテゴリー
- 棚卸 - たな おろし
-
- 商品の在庫数を調べて、利益がどれだけ出ているのかを調べる作業のこと。
→ 決算
- タレ - たれ
-
- 液状の合わせ調味料のこと。
食肉業界においては、焼肉、すき焼き、牛丼、豚丼等、色々な料理があるが、主に和風な料理に関して「タレ」という言葉を用いる事が多いようだ。逆に洋風な料理に対しては、ソース・ドレッシングなどという言葉が使われる。
タレに関しては、かなり細分化されていて、食材用にそれぞれに有名なタレが存在し、小売されている場合が多い。一例としては、トンテキ用・生春巻き用・焼き鳥用など様々である。
→ つけダレ
→ ソース
→ ドレッシング
- タン - たん
-
- 舌のこと。
牛や豚等の舌を焼肉材として食する際の呼び方である。
→ 牛タン
→ 豚タン
- 団子 - だんご
-
-
→ 肉団子
- タンドール - たんどーる
-
- インド等で使用される粘土製の窯型オーブンのこと。
→ ナン
- タンドリーチキン - たんどりーちきん
-
- インドの鶏肉料理。ヨーグルト・香辛料に漬け込んでからタンドールと呼ばれる窯で焼き上げる。
→ タンドール
- チーフ - ちーふ
-
- 小売業の世界において、各部門の責任者のこと。主任とも言う。
→ 主任
→ 部門
- チェーンストア - Chain store - ちぇーん すとあ
-
- 同じ看板を用いて、同等の商品の品揃えやサービスの提供をコンセプトに、多数の店舗展開を行う経営手法のこと。
消費者に対してはどこの店でも同じサービスが受けられるという安心感、企業としては単一化された運営マニュアルや本部主導の商品の品揃えが出来るというメリットがある。
フランチャイズとは区別される。
→ 総合スーパー
→ フランチャイズ
- チェッカー - ちぇっかー
-
- スーパーマーケットのレジ係のこと。
会計をチェックということからの語源と推測される。
基本的にレジ係は1人で、清算業務を行うが、煩忙時等は2人で行う場合もある。2人目はキャッシャーやサッカー業務を行う。
→ キャッシャー
→ サッカー
→ スーパーマーケット
- チキン - chicken[英] - ちきん
-
- 鶏(にわとり)のこと。
→ 鶏
- チキンカツ - ちきん かつ
-
- 料理名。鶏肉を原料としたカツのこと。
一般的にはカツと言えば豚肉を原料とする事が多いが、鶏肉を原料とした場合にチキンカツと呼ぶ。
部位はモモ肉の他、ムネ肉も普通に使用される。
大衆料理の位置付けである。
→ 鶏
→ カツ
- チキンナゲット - ちきん なげっと
-
- 日本ではファーストフード店のメニューとして有名である。
鶏肉に衣を付けて油で揚げた料理の事を指す事が多い。
アメリカの家庭料理では、油で揚げずに焼いて食べるものらしい。
略して ナゲット と呼ばれることもある。
部位に指定は無いが、価格の安いムネ肉が使用されることが多い。
→ 鶏
→ 唐揚げ
→ チキン惣菜
- チキン惣菜 - ちきん 惣菜
-
- 食品スーパー等で販売される加工食品で、鶏肉を原料とした 唐揚げや、チキンナゲット等の事を言う。
→ 鶏
→ 唐揚げ
→ チキンナゲット
→ フライドチキン
→ 竜田揚げ
- 畜肉 - ちくにく
- 食肉であり、と畜場法に基づいた と畜場で、と殺・解体された家畜の肉のこと。
牛、豚、馬、羊、やぎの5種類。
→ 牛
→ 豚
→ 馬
→ 羊
→ やぎ
→ と畜場法
→ 食肉
- 畜種 - ちくしゅ
- 畜肉の種類の事。一般的には、牛・豚・鶏の事を指す事が多い。
→ 畜肉
- チゲ - ちげ
- 朝鮮半島の鍋料理のこと。
チゲ=鍋 の意味であるので、日本で良くある表記の「チゲ鍋」はややおかしい表記である。
キムチチゲが有名であるが、バリエーションは多い。
→ 鍋料理
- チヂミ - ちぢみ
- 韓国の料理の名前。日本で言う所の「お好み焼き」に似ている。
小麦粉や米粉を主原料として、ニンジン・ニラ・玉ねぎなどを入れて薄く焼き上げる。
タレに付けて食べるのが一般的である。
→ お好み焼き
- チマキ - ちまき
- スネ肉の事。その見た目の形からの名称。
→ スネ肉
- チャーシュー - ちゃー しゅー
- 中国の広東料理である。「叉焼」と表記する。
現在の日本においては、焼豚や煮豚のことをチャーシューと表現される事も多い。
ラーメンの具材として人気。
→ 焼豚
→ 煮豚
- 着色料 - ちゃくしょくりょう
- 見た目を良くする為に、食品に添加する物の総称。合成着色料と天然着色料がある。日本では食品衛生法という法律で、使用方法などが厳しく規定されている。
→ 添加物
→ 食品衛生法
- チャパティ - ちゃぱてぃ
- インド等で一般的なパンの事である。カレーの付け合わせとして食べる。
全粒粉(小麦粉)が原料で、発酵せずに焼く。ナンはタンドールで焼いた物の事である。
→ ナン
→ キーマカレー
- チャンスロス - ちゃんす・ろす
- 小売店等において、売上機会損失のこと。
欠品や品切れ、等が主な理由であるが、本来は 売れるはずだったのに、販売者側の諸事情によって売れなかった事について指す用語。
→ ロス
- 注文 - ちゅうもん
- ここではお客様からのご注文品のこと。
インストア加工の食肉小売販売店においては、売場に陳列してある商品をお買い上げいただくだけではなく、お客様からのご要望に応じて商品をその場で用意して提供するスタイルを実施している場合もある。
専門店では当たり前の事かもしれないが、スーパー等の小売店ではこういった注文を受ける事が出来る仕組みは、そもそも無いか、または減少傾向である。
→ オーダーカット
→ 客注
→ 専門店
- 調味料 - ちょうみりょう
- 料理の際に、素材の味を引き立てる為、または料理そのものの味を調える為に使用される食品添加物のこと。
日本の代表的な調味料としては、塩、砂糖、醤油、みりん、味噌、酢などがある。
香辛料は調味料の一種ではあるが、スパイスとして定義したい。
→ 添加物
→ スパイス
→ 調理
- 調理 - ちょうり
- 食材と調味料を合わせて、加熱などの過程を踏まえて料理する行為。
→ 調味料
→ 料理
- チョッパー - ちょっぱー - chopper
- 食肉業界においては、原料肉を細かくして 挽肉にする機械のことを指す。
→ 挽肉
- チラシ - ちらし
- 小売業界においては、広告の為に 新聞折り込みにて不特定多数の消費者の元に届ける紙媒体の物を指す。
とにかくお客様に来て頂きたいという思いから、人気商品の価格を下げたり、イベントの案内など、内容は様々である。
→ 広告
- チルド - ちるど
- 5℃以下の保存温度帯のこと。
JAS法では、冷蔵と区別され、5℃以下で凍結しない温度帯の事である。
食品は冷凍してしまうと品質が変わる為、温度管理は重要である。
また一度も冷凍させていない商品の意味として使われる事もある。
→ 冷凍
→ 生
→ JAS法
- 陳列 - ちんれつ
- 小売店において、商品を顧客に判りやすく並べること。
フェース数や全体の陳列量、また 売り込みたい商品と比較させる品との対比など、並べると言っても、販売者側の意志の入れ方は様々な手法がある。
→ POP
→ コトPOP
→ 什器
→ フェース
- つくね - つくね
- 畜肉等を細かく擦り潰したり挽肉状にした物を、つなぎ等をあわせて団子状または棒状ににしたもの。
鍋料理や、焼き鳥のメニューとして一般的である。
畜種としては、主に鶏肉が使用される事が多い。
→ つみれ
→ 肉団子
- つけダレ - つけ だれ
- 食材をより美味しく食する為の調味料の一つである。
一般の調味料は、食材を調理する際に用いるのに対して、つけダレは調理が終わった後に、食べる直前にドレッシングの様にして食材に添加して用いるのが特徴である。
食肉業界においては、焼肉や、焼きしゃぶに用いる事が多い。
→ タレ
→ 調味料
- つみれ - つみれ
- 魚のすり身を原料としたものをつみれと呼ぶ事が多いようだが、現代ではその定義も曖昧である。
あらかじめ団子状に成形されておらず、ペースト状で販売される物を「つみれ」と呼ぶ事もある。
畜肉を原料としたものはつくねと呼ぶ事が多い。
鍋料理の具材として人気。
→ つくね
→ 肉団子
→ 畜肉
- 詰め放題 - つめほうだい
- 小売店等における販促の手法の一つ。
消費者は、用意された商品を 販売店の用意した規定の袋等に 自らの力量によって入れて購入する。
1袋で○○円という販売価格の設定なので、よりたくさん入れた方がお得になる。
販売者側は、利益は度外視でこういった企画を設定する事も多く、人気企画である事が多い。
→ 販促
- ディスカウントストア - でぃすかうんと すとあ
- 基本は安売り店の事であるが、商業施設の規模・品揃えも含めて圧倒的に大きな小売業態の事を指す事が多い。
現在では、ほぼスーパーセンターの意味。
→ スーパーセンター
- テーブルミート - table meat[英] - てーぶる みーと
- 精肉のこと。
→ 精肉
- 定例販促 - ていれい はんそく
- 時期を決めた販促計画のこと。毎週○曜日は△△がお買い得など。
日にちの語呂合わせによる、「なんとかの日」もこれに当てはまる。
→ 販促
→ 肉の日
→ 鶏の日
- 手切り - てぎり
- 肉のカットの方法のひとつ。
包丁とまな板を用いて、人の手において一つずつカットする方法。
焼肉用、ステーキ用等の食材はたいていはこの方法でカットされる。
→ スライス
- テナント - てなんと
- 集合施設において賃料を払うことにより出店する店舗のこと。
大規模小売店においてよく見られるケース。施設経営者にしてみれば魅力あるテナントを集めたいという思い、出店する企業からすれば 魅力ある商業施設において賃料を払ってでも営業活動をしたいという思いの両立からそのバランスは保たれている。
→ コンセ
- デパート - でぱーと
- Department Store の略。大経営の総合小売店。
百貨店 と同じ意味。他のスーパー等の小売店と比較して 品揃えや販売方法・店舗の作り方や見せ方において、あらゆる意味で 格を重んじる傾向がある。
→ 百貨店
→ 業態
- 出前 - でまえ
- 調理をされた食品を顧客の所まで届ける行為のこと。又は その商品の事を指す。
寿司・ピザ等が有名であるが、様々な形態・サービスがある。
出前は 中食(なかしょく)として、定義される。
→ 中食
- 手巻き焼肉 - てまき やきにく
- 手巻き寿司の焼肉版。ルールは無用で、焼いた肉をサンチュやレタス等の葉っぱに巻くも良し、具材には焼肉として牛肉や豚肉・鶏肉を巻いても良し、更には魚介類も用意しても楽しい。
中に巻く具材をたくさん用意すると楽しいのはもちろんだが、外側の巻く皮の部分もたくさん用意すると楽しい。
サンチュやレタスの野菜系はもちろん、春巻きの皮や、海苔を用意しても楽しい。
→ サンチュ
- テリーヌ - terrine[仏] - てりーぬ
- 現在の日本においては、豚肉等の原料を挽肉にした物を 野菜等と一緒に焼き上げた物を指す事が多いが、本来の定義は 専用のテリーヌ鍋で焼き上げて鍋のまま提供される料理の事である。フランス料理においては、前菜の位置付けである。
日本では 特にクリスマスシーズンに加工食品として提供される事が多い。
→ アスピック
- 添加物 - てんかぶつ
-
→ 食品添加物
- テンジャン - てんじゃん
- 韓国の調味料の一つで、大豆を発酵させて作る。日本で言う所の味噌に近い。
- 点心 - てんしん
- 中華料理。メインの食事では無く、軽食のことを指す。
現代の日本においては、食事は1日に3食という事が一般的であるが、中国においては地域においてはそうでは無い場合もあり、朝食をも含めて点心という場合もある。
点心の特徴としては、蒸したり焼いたり様々ではあるが、小麦粉ベースの皮に包んだ餡を具材とした、味付けは甘いものである事が多いようだ。
→ 飲茶
- テンダーロイン - てんだー ろいん - tenderloin[英語]
- ヒレ肉のこと。
→ ヒレ
- 天ぷら - てんぷら
- 料理名。主に魚介類や野菜を具材として、小麦粉を主体とした衣に包んだ物を油で揚げた料理の事を指す。
食肉業界ではあまり使われない用語である。
→ フライ
- とうがらし - とうがらし
- 牛肉の部位名でカタ肉の一部のこと。
→ トンビ
- 等級 - とうきゅう
-
→ 格付け
- 凍結 - とうけつ
-
→ 冷凍
- 動線 - どうせん
-
→ 客動線
- 投入 - とうにゅう
- チェーンストア店舗においては 店舗担当者による発注・仕入れの他に、本部による投入と呼ばれる仕入れが行われる場合がある。
マスメリットを活かして通常より安い納価で仕入れる事が出来るメリットや、新規売込み商品など強制的にチェーン店舗全店で販売展開したい場合等によく使われる手法である。
デメリットとしては、店舗担当者は自分の発注した商品ではない為、販売に関する情熱が弱くなりがちな傾向が見受けられがちである。
→ 仕入れ
- 特招会 - とく しょう かい
- 特別招待会の略語。
小売店等においては、自店の顧客に対するサービスの為、特別に安く販売するセールを行う事があるが、会員カード等を保有している顧客に向けての限定サービスの事を指す場合が多い。
顧客に対しては事前にダイレクトメール等で、特招会の開催日を告知する他、当日は一般客は入店出来ない、もしくは会員になってもらう等の措置・手法を用いる事もあるようだ。
消費者にとっては安価で買物が出来るメリットがある他、販売店側にとっては、顧客の囲い込みの意味合いが強い。
- 特定危険部位 - とくてい きけん ぶい
- BSEの原因とされる異常プリオンが蓄積されやすい牛の脳や眼球、脊柱、脊髄(せきずい)、小腸の一部など。食べると感染の恐れがあるとされており、食品として利用することが食品衛生法などで禁じられている。
→ BSE
→ 食品衛生法
- 特売 - とくばい
- 特別に安い価格で販売すること。
小売業界においては、競争の為に 利益を度外視して 非常に安い価格で商品を販売する事もある。
競合店との競争が大きな要素を占めるが、自社の人気付け等、様々な販売戦略の一環として行われている。その商品や、その行為の事を 特売 と呼称する。
EDLPの反意語としても用いられる。
→ 価格
→ 売り出し
→ セール
→ EDLP
→ ロスリーダー
- 特別招待会 - とくべつ しょうたい かい
- → 特招会
- と畜 - とちく - 屠畜
- 家畜等の動物を殺すことを意味する言葉である。
屠畜 という感じは常用漢字では無い為、「と畜」とここでは表現する事にする。
命を頂く意味をきちんと理解したい所である。
→ と畜場法
- と畜場法 - とちくじょう ほう
- と畜に関する日本の法律のこと。昭和28年(西暦1953年)に制定された。
食肉に関する基本的な定義と、公衆衛生の観点からの法律である。
→ と畜
- どて - どて
-
地域にもよるが、牛スジ肉や、豚の内臓を原料として調理した料理名のこと。
バリエーションは様々であるが、味噌仕立ての味付けである事が多いようだ。
どて煮、どて焼き等、の呼称がある。
→ スジ
→ 内臓
- とばす - とばす
-
業界用語。何らかの事情で利益度外視での安価で売り切ること・・のようだ。
- とぶ - とぶ
-
業界用語。とても良く売れること。
- ドミナント - どみなんと
- チェーン展開する小売店舗において、ある一定の地域において集中的に店舗展開をする形態を指す。
メリットとしては、チェーンとしての顧客に対する認知度の向上と、物流の配送の利便性、広告のし易さ等が挙げられる。
デメリットは、自社競合。
→ チェーンストア
→ 自社競合
- トモサンカク - ともさんかく
- モモ肉の一部であるシンタマの更に一部。基本的に赤みの部位ではあるが、適度にサシも入り モモ肉の中ではかなり柔らかく生食として利用されることもある。稀少部位。
→ 部位
→ モモ
→ 希少部位
- トモバラ - ともばら
- 友バラとも表記する、部位名。牛肉において使用される言葉。
ざっくり言うと、後ろの方のバラ肉の事。
外バラと中バラのことを、トモバラ(友バラ)と呼ぶ。
→ 部位
→ 前バラ
→ バラ
- ドライソーセージ - どらい そーせーじ
- 食肉を乾燥させて作った保存性の高い食品のこと。
→ ソーセージ
→ サラミ
- ドライソーセージ - どらい そーせーじ
- 食肉を乾燥させて作った保存性の高い食品のこと。
→ ソーセージ
→ サラミ
- ドラム - どらむ
- ドラムスティックの略語。
→ ドラムスティック
- ドラムスティック - どらむ すてぃっく
- 鶏肉の部位の名称。
骨付きモモ肉の関節より下半分の事を指す。
→ 鶏肉
→ サイミート
- 鶏 - とり - (にわとり)
- にわとりのこと。
日本の食肉事情において欠かす事の出来ないおかずメニューである。
→ にわとり
→ 唐揚げ
→ やきとり
→ 家禽
- 鶏ガラ - とりがら
- 鶏の骨のこと。料理を作る為のスープを作るダシを取る為に利用される。小売店で入手する事が出来る。
→ ガラ
- 鶏肉 - とりにく
- にわとりを食用に加工したものを指す言葉。
ごちそうではなく、おかずやお弁当メニューとして日本では広く支持されている。
大量生産される食用の鶏はブロイラー(broiler[英])とも呼ばれる。
→ 鶏
→ 若鶏
→ ブロイラー
→ かしわ
→ 品種
→ 畜種
⇒⇒ 鶏の畜種・品種 (畜種別特徴)
- トリミング - とりみんぐ
- 余計な部分を取り除くこと、またはその行為を指す言葉。
正肉を整形する過程で、脂を取り除くこと。
→ 脂
→ 正肉
- 鳥インフルエンザ - とり いんふるえんざ
- 鳥が感染するインフルエンザのこと。
家畜業界においては、他の健全な鳥がダメになってしまう事を恐れている。
具体的には、発症が確認された場合の対応として農場毎の殺処分等が行われるが、生産者にとっても、消費者にとっても悲しい現実である。
・・未来への防御策として、健全な家畜も処理されてしまうのである。
→ 殺処分
→ 家畜衛生法
- ドリップ - どりっぷ
- 生鮮食品がスーパーなどの店頭において陳列された際に、時間経過にともなって肉汁が出た状態の肉汁の事を差す言葉。
見た目にも美しくないし、鮮度劣化が進行している状態である。
冷凍品を急速に解凍した場合にもドリップはよく出る。
細胞膜が破壊されて、肉の旨味である要素が流れ出た状況である為、ドリップはもったいないし、その本来の旨味を逃している状態である。
→ 解凍
→ 生鮮食品
- トレサビ法 - とれ さび ほう
- → トレーサビリティ法
- トレーサビリティ - とれー さびりてぃ
- 食品のトレーサビリティとは、追跡可能性のこと。
いつ、どこで、誰が、どのようにして その食品を作ったのか、追跡して調べることが出来るようにするシステムのことを指す。
何かしらの問題が発生した時に、どの時点においてどのような問題があったのかを追跡して調査する事が容易になる。
→ トレーサビリティ法
- トレーサビリティ法 - とれー さびりてぃ ほう
- 食肉業界においては「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」のこと。生産・流通の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するための牛個体識別情報伝達制度(牛トレーサビリティ制度)を構築するために、2003年(平成15年)6月に公布された。
BSEなどの問題が発生した時に、流通している牛肉が本当に安全かどうかを溯って調べることが出来るシステム。
具体的には、10桁の牛個体識別番号を指定された方法により検索する事により、その牛肉の生産履歴を調べる事が出来る。
→ 牛個体識別番号
→ 家畜改良センター
→ トレサビ法 (略語)
→ 狂牛病
- 豚カツ - とんかつ
- 料理名。豚肉に衣を付けて油で揚げた料理のこと。
→ カツ
→ カツレツ
→ 味噌カツ
→ 揚げる
→ フライ
→ カツ丼
- トング - とんぐ
- 食材を掴む目的で用いられる器具のことである。ピンセット状の形態であるが、その大きさや細かい形状は様々である。
屋外で行うバーベキューでは、熱源から焼く人を守る手助けとなる他、通常の焼肉でも 食中毒予防となる為、焼く為の器具と 実際に自分が食べる為の箸は明確に分けましょう。
→ 焼肉
→ 食中毒
- 豚骨 - とんこつ
- 豚の骨のこと。
主にラーメンのスープとして利用される。
→ げんこつ
→ ガラ
- 豚コレラ - とんこれら
- 豚やいのししが感染する病気の名前。
強い伝染力と高い致死率が特徴で、日本では家畜伝染病予防法で家畜伝染病に指定されている。
- トンテキ - とんてき
- 豚肉を原料としたステーキ料理のこと。
ステーキという料理は一般的には牛肉を原料とした物の事を指す事が多い為、豚肉を原料とした場合をあえて「トンテキ」と呼ぶことがある。
日本国内では、北海道や三重県の四日市などで有名である。
一般名は、ポークステーキと呼ぶ。
→ ステーキ
→ ポークステーキ
- 豚トロ - とんとろ
- 世間では、豚の霜降り肉の総称として認識されている言葉だが、農林水産省の定める 食肉小売品質基準 の部位名としては正式には存在しない。
実際には、頬からカタ(肩)の部分を豚トロと呼称されている。
トロという表現が景品表示法の優良誤認に該当する可能性が高く、豚トロという商品名で販売するのは現在の法律ではグレーゾーンである。
- トンビ - とんび
- 牛肉の部位で、カタ肉の一部のこと。
とうがらしと同じ。
カタ肉は肉質は固いが旨味が濃厚な部位ではあるが、トンビは赤身が多くやわらかいのが特徴。1頭の牛からとれる量が少ない為希少価値が高い。
→ とうがらし
- トンポーロー - とんぽーろー
- 日本では、豚角煮の事を指す。
中国料理名。東坡肉と書く。豚のバラ肉を角切りにして物を甘辛く調味してみ込んだ料理のこと。
→ 角煮
- 内食 - ない しょく
- 内食(うちしょく)と同じ。
→ 内食
- 内臓 - ないぞう
- 食肉業界においては、正肉以外の部分を指す。
一般的には、レバー等が内臓として有名であるが、タンやサガリ、ハラミも食肉業界においては内臓の扱いである。
→ 正肉
→ タン
→ スジ
- 中落ちカルビ - なかおち かるび
- 正式名称ではない。牛のバラ肉のあばら骨の間の肉を削ぎ落とした部分をこの名前で呼んでいる業者や、販売店もある。マグロの中落ちが同様の部位である事からこの名前で呼ばれるようになったらしい。
→ カルビ
- 中食 - なか しょく
- 家庭の中では無い所で調理された食品を、家庭に持ち込んで食すること。又はその商品の事を指す場合もある。
出前を取る行為も中食に含まれる。
家庭内で調理して食べるのは「内食」。レストラン等に出かけて食べるのは「外食」。外部で調理された物を家庭に持ち込んで食べるのが「中食」となる。
→ ミールソリューション
→ 内食
→ 外食
→ 出前
- 中バラ - なか ばら
- トモバラの一部のこと。部位名。
外バラと中バラを合わせてトモバラという。
→ バラ
- ナゲット - なげっと
-
→ チキンナゲット
- 名古屋コーチン - なごや こーちん
- 鶏の肉用品種名の一つ。愛知県特産である。正式な品種名は「名古屋種」。
肉も卵も美味しいと定評がある。
⇒⇒ 名古屋コーチン協会 (外部リンク)
- 夏巻き - なつ まき
- 生春巻きの別名。
→ 生春巻き
- 名ばかり管理職 - なばかり かんりしょく
- 本来管理職にはあたらない職務の者を「管理職」として、残業代が企業から支払われないケース等が社会問題視されている。
- 鍋 - なべ
- 調理器具の一つ。やや深さのある事が多い。煮る、揚げる、焼く等の加熱を目的とした調理用具である。
または、鍋料理の事を指す。
→ 鍋料理
- 鍋料理 - なべ りょうり
-
鍋のまま食卓に提供される料理の事を指す事が多い。
メニューは多岐に渡り、一例として、ちゃんこ鍋・すき焼き・湯豆腐・水炊き・おでん・しゃぶしゃぶ等がある。
家族団らんで鍋を囲むというイメージも強いが、個食鍋という一人で食べる鍋もある。
→ すき焼き
→ 蒸ししゃぶ
→ チゲ
- 鍋スープ - なべ すーぷ
-
ここでは狭義として、鍋料理の素となるメーカー製の液体状の物を鍋スープと呼ぶ事にする。
「○○鍋の素」というレトルトパウチ系の鍋スープが市販されている。
お手軽で、それなりの味わいが家庭で楽しめる。
有名飲食店とのコラボも盛んである。
→ 鍋料理
→ スープ
- 生 - なま
-
食肉業界においては、一度も加熱調理されていない事を指す事が多いが、別の見解として 一度も冷凍されていない事を差す場合もある。
→ 冷凍
→ チルド
→ 生食
- 生食 - なましょく
-
食肉等を加熱調理をせずに そのまま生で食べる事を指す。
現在の日本の小売店においては、生食用として販売される食肉は基本的には無い。
食肉は加熱調理して食べましょう。
食中毒予防の観点からも、我々・消費者自身も危険が無い様に気を付けたい。
→ ローストビーフ
→ 馬刺し
→ タタキ
→ ユッケ
→ レバー
→ 食中毒
- 生春巻き - なま はるまき
- ベトナム料理の一つ。ライスペーパーにエビを主体とした具材を用いた料理。
別名 夏巻き
→ 春巻き
→ ライスペーパー
→ 夏巻き
- 生ハム - なまはむ
- 加熱殺菌をせずに作られたハムのことで、塩漬後の水分活性が、0.96以下になるように定められている。
→ プロシュット
→ 塩漬
→ ハム
→ パンチェッタ
→ 水分活性
- 生レバー - なま ればー
- 加熱処理をせずに生でレバーを食する事、又は提供すること等を指す言葉。
2011年に牛の生レバー提供の飲食店における集団食中毒事件 を発端にして 2012年7月より 食品衛生法の改定により、飲食店では生レバーの提供が出来なくなった。
→ レバー
→ レバ刺し
→ 食中毒
- ナムル - なむる
-
韓国の家庭料理。もやしやワラビなどの山菜・野草など等を主原料として、塩ゆでしたりゴマ油等の調味料でしつらえた物を指す。
→ ビビンバ
- ナン - なん
-
インド料理店等でカレーを食する時に一緒に食べる、小麦粉を原料としたパンの様な物のこと。
厳密には、タンドゥールと呼ばれる窯の内側に貼りつけて焼いた物の事である。
→ チャパティ
→ タンドール
- 軟骨 - なんこつ
-
食肉業界においては、鶏肉の軟骨のことを指す事が多い。
ヒザ軟骨と、ヤゲン軟骨がある。
ヒザ軟骨は丸い形状で、主に唐揚げに適す。
ヤゲン軟骨は主に串に刺してヤキトリのメニューとして適す。
ともにコリコリとした食感を楽しむ。
→ ヒザ軟骨
→ ヤゲン軟骨
- 肉 - にく
- ここでは、食肉の事を指す。
一般的には、牛肉・豚肉・鶏肉 のことである。
日本国内でも、地域によって主に食する畜種は分かれるようである。
主に関東では豚肉、関西では牛肉がおかずメニューとして消費されているようである。
肉じゃが・カレーライス等のおかずメニューにどんな肉が入るか、という観点である。
→ 食肉
→ 畜種
- 肉質等級 - にくしつとうきゅう
- 歩留まりと、肉質の評価を総合的に判断したもの。
数字が大きいほど、高評価である。
→ 格付け
→ 歩留まり
- 肉じゃが - にく じゃが
- 料理名。日本的な料理とされる。
畜肉をスライスしたものと、じゃがいも等を醤油ベースの調味料で味付けし、煮込んだ料理。
使用する畜肉は、関東では豚肉、関西では牛肉が用いられることが多いようだ。
→ 料理
→ 畜肉
- 肉専用種 - にく せんよう しゅ
- 乳用種の反意語。
食肉用に肥育・流通する牛肉のこと。
和牛は肉専用種に含まれるが、和牛という名前を謳う(うたう)には日本の法律(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 = JAS法)で厳しい条件が付けられているので、和牛と謳えない条件のものは肉専用種という名前になる。
一例 : 両親が和牛であっても、日本国内で出生・飼養されていない場合など。
→ F1
→ 乳用種
→ 和牛
- 肉総菜 - にく そうざい
- 食肉を主原料した総菜のこと。
コロッケ、ハンバーグ、メンチカツ、つくね、等 様々である。
美味しくてお手頃価格の肉総菜を販売する店は、その品を看板メニューとしてある意味人気があったりもする。
→ 精肉店
→ ホームミール
→ ミールソリューション
- 肉団子 - にく だんご
- 畜肉等を挽肉にして、つなぎ等をあわせて団子状に成形した物。
調理方法は様々で、焼く・煮る・揚げるなど豊富である。
ミートボールと同意語である。
→ つくね
→ ミートボール
- 肉の日 - にく の ひ
- 毎月 29日を 語呂合わせで 肉の日とするもの。
毎月の定例販促として、特売を実施している小売店もあるようだ。
→ 焼肉の日
→ 販促
- 煮凝り - にこごり
-
ゼラチン質の多く含まれる 肉や魚などを煮た際の煮汁が冷えて固まった物を指す。
煮込んだ時の具材の旨味などが凝縮されており、次の料理に利用するのに都合が良い。
敢えて 煮凝りの形として提供する料理も珍しくは無い。
→ アスピック
- 二重価格 - にじゅうかかく
- 実際に販売したことのない価格を比較対照価格として、一般消費者に誤認を与える不当表示のこと。
景品表示法 (公正取引委員会) がガイドラインを定めている。
⇒⇒ 公正取引委員会 (リンク集)
- 煮豚 - にぶた
-
- 豚肉のかたまりを煮込んで作る料理のこと。
焼豚、チャーシューとも呼ばれる事が多いが、言葉の定義は厳密には無い。
薄くスライスしてラーメンの具材として使用する事も多い。
日本で流通しているチャーシューは煮豚である事が多い。
→ 焼豚
→ チャーシュー
- 日本食肉格付協会 - にほんしょくにくかくづけきょうかい
- 食肉の格付けを行う社団法人。
牛肉と豚肉においてそれぞれの等級表示の規格、格付けを行っている。
⇒⇒ 日本食肉格付協会 (リンク集)
- (財)日本食肉消費総合センター - にほん しょくにく しょうひ そうごう せんたー
- 日本国産の食肉をアピールする位置付けの財団法人。
⇒⇒ (財)日本食肉消費総合センター (リンク集)
→ お肉スキスキ
→ Jミート
- 日本標準産業分類 - にほん ひょうじゅん さんぎょう ぶんるい
-
- 総務省が管轄する、日本の業種についての取り決めのこと。
⇒⇒ 総務省 (外部リンク)
→ 小売業
→ 業種
- 乳用種 - にゅうようしゅ
- 牛乳を生産する為の牛の品種のこと。
日本の乳用牛の品種は9割がホルスタイン種である。
その他の品種としては、ジャージー種・ブラウンスイス種・ガンジー種・エアシャー種・等がある。
肉専用種の反意語。
→ 肉専用種
- にわとり - ニワトリ - 鶏
- 食肉業界においては、鶏肉のことである。
一般的には、肉や卵を食用とする為に、人為的に手を加えた家禽である。
→ 鶏
→ 鶏肉
→ ブロイラー
→ 家禽
- 鶏の日 - にわとり の ひ
- 毎月28日を語呂合わせで、鶏の日とするもの。
企業によっては、毎月の定例販促として特売をかける所もあるようだ。
→ 定例販促
- 値入れ - ねいれ
- 販売する側において、計算上の利益のこと。
販売する前に計画する段階で使用される用語である。
実際の現場においては、売れ残って値引きをしたり、廃棄が発生したりもするが、それらを想定しないで、計算上で得られる利益の額や率を指す言葉である。
実際に売れた結果については、荒利という言葉を使う。
→ 荒利
- 寝かす - ねかす
- 熟成のこと。
→ 熟成
- ねぎま - ねぎま
- 肉とねぎを交互に挟んで串に刺した料理のこと。
肉は鶏肉や豚肉である事が多い。ねぎは長ねぎである事が多い。焼鳥のメニューとして、またバーベキューのメニューとして人気の品である。
- 値ごろ - ねごろ
- お客様が買いやすい価格のこと。
品質と価格のバランスにおいて、品質が高くて なおかつ 良心的な価格設定である事を指す言葉。
価格が安い事だけを指すのではなく、品質がそれなりに高いものに対して使用する用語である。
→ 価格
→ お値打ち
- 値下げ - ねさげ
- 小売業においては、当初の設定した価格を変更して安く販売すること。
→ 値引き
- ネットショッピング - ねっと しょっぴんぐ
- インターネットに接続された情報端末等を利用して買物をすること。
ネット通販という言葉が一般的である。
→ ネット通販
- ネットスーパー - ねっと すーぱー
- インターネット等に接続された情報端末を利用して、スーパーで販売されている商品を購入出来るシステムの事。
生鮮食品を実在する地域のスーパーの小売価格と同等の価格で購入する事が出来、しかも宅配サービスにて消費者のお宅まで配達するサービスの事である。
当日中の宅配が基本である。
配達エリアは限定されている事が多く、配達料金の設定については各社様々であるが、ある一定の金額の注文金額を超えると配達料は無料サービスとしている所が多いようだ。
ネットスーパーは、ネットショッピング・ネット通販とは区別される。
→ ネットショッピング
- ネット通販 - ねっと つうはん
- インターネットに接続された情報端末等を利用して、買物をするシステムの事。又はその行為を指す。
自宅に居ながらにして、希望の品を購入出来るシステムは便利である。
工業製品はもとより、食品においてもその便利さゆえに今後は需要が高まりそうな気配である。
→ ネットスーパー
- 値引き - ねびき
- 鮮度管理や、商品入れ替えの為に、設定した価格より安く販売すること。
値下げとほぼ 同意語である。
→ 値下げ
- 年中無休 - ねんじゅう むきゅう
- スーパーなどの小売店において、店舗の営業形態が、定休日が年間を通じて無い事を指す。
企業側の視点としては販売機会の拡大を理由として、年中無休を消費者の利便性を測るという口実で実施・アピールさられている感が強い。
→ 定休日
→
- 農水 - のうすい
- 農林水産省のこと。
→ 農林水産省
- 農林水産省 - のうりんすいさんしょう
- 日本の行政機関の一つ。食料の安定供給の確保等が目的である。
食肉業界においては、産地偽装事件などの不祥事が相次いだ為、農水の立ち入り検査などが各事業所に対して頻繁に行われるようになった。
⇒⇒ 農林水産省 (外部リンク)
- ノーサービス - のー さーびす - no service
- ここでは セルフサービス という用語の補足として紹介する。
スーパーマーケットの定義はセルフサービスが根幹にあるが、実はノーサービスでは無い。
ノーサービスとは、言葉通り、顧客に対して販売店は一切のサービスをしない事であるが、実際のスーパーマーケット等の小売店においては、顧客のあらゆる要望に対応出来るように、各種 様々な接客サービス・対応を行っている。
セルフサービス = ノーサービス では無い。
→ セルフサービス
→ スーパーマーケット
- バークシャー種 - ばーくしゃー しゅ
- 日本では いわゆる黒豚のこと。豚の品種の一つである。
もともとは、イギリスのバークシャーとウィルッシャー地方の在来種にシアメース種、中国種及びネオポリタン種などを交雑した品種である。
脂は多いが、肉用種としての品質・肉質は良い。
→ 黒豚
→ 品種
- バーゲンハンター - ばーげん はんたー
- 定価での商品は購入せずに、値下げされた商品のみを狙う魔物。
値下げが行われる日時を的確に把握しており、買い物籠には、値下げされた品物しか入らない。
性質の悪いハンターにおいては、「もっと安くして」と要求してくる。
- パートタイマー - ぱーと たいまー
- 非正規雇用であり、時間単位で賃金が支払われる労働者のこと。
労働法という法律では、1週間の労働時間が 通常の労働者よりも短いものを指す という定義になっている。
一般的には、雇用に関しての契約は、生涯では無く1年単位等の期間を区切った契約になっている事が多い。
- バーベキュー - ばーべきゅー
- 現在の日本においては野外で肉などを直火で焼く料理のこと。
元々の意味は、比較的低温で長い時間をかけて蒸し焼きにし、柔らかくなるまで調理した物を指す。
BBQ などと表記する事もある。
→ 焼肉
- 売価修正 - ばいか しゅうせい
- 主に値下げの事を指す場合が多い。
計画した売価よりも何らかの理由により、値下げして販売すること。又は その値下げ販売した事により、伝票の操作をすること。
→ ロス
→ 自動売価修正
- 売台 - ばいだい
- 商品を陳列して販売する為の什器であり、ワゴンのような形状の台のことが多い。
主に常温販売することが前提。
→ 平台
- バイヤー - ばいやー - buyer
- 仕入れを行う役割の人のことを指す。
メーカー等と商談を行い、仕入れ価格も含めて売れる商品を手配する大切な役割である。
→ 商品部
→ 商談
→ 投入
- HACCP - ハサップ - はさっぷ
- Hazard Analysis and Critical Control Point の略。
食品を製造する際に安全を確保する為の手法や行程のことを指す。
- 馬刺し - ばさし
- 食肉用の馬の肉を加熱せずに生で食べる料理、またはその肉の事を指す。
日本でも限られた地域で好んで食される。
ロース、赤身、脂身等を馬刺しとして食する。一般的には生姜醤油などの調味料でそのまま食べる。
お盆や正月などに特に消費量は増加する。
→ 馬肉
→ 生食
- 発色剤 - はっしょくざい
- 食品に含まれる色素に作用して見た目を良くするもの。食品添加物。
ハムやソーセージに多く使用される発色剤として、亜硝酸ナトリウムなどがある。
→ 食品添加物
→ 無添加
- 発注 - はっちゅう
- 小売業界において、商品を仕入れ先に注文すること。
発注方法は様々で、電子端末、FAX、電話 等がある。
仕入れ過ぎは 値引きや廃棄等のロスにつながるが、仕入れ量が足りないと売上の機会ロス(チャンスロス)となる為、発注は大切な業務の位置付けである。
→ 仕入れ
→ 投入
→ ロス
- 馬肉 - ばにく
- 食用の馬の肉のこと。日本では限られた地域ではあるが、熊本・甲信越・東北地方等で主に食される。
生のまま 馬刺し として、または すき焼き等として食される事が多い。
加熱せずに食べる馬刺しは有名であるが、鮮度は高くても畜肉を生で食べる事にはリスクが伴う事を考えたい。
栄養学的には、低カロリーでしかも栄養価が高い。
肉色の見た目から「さくら肉」とも呼ばれる。
→ さくら肉
→ 馬刺し
→ おたぐり
- ハネシタ - はねした
- ザブトンに同じ。
→ ザブトン
- ハム - はむ
- 本来の意味は豚のモモ肉を塩漬処理したもので、過去において骨付きのものが普通の時代には、骨なしのものをわざわざ「ボンレスハム」(Boneless - ham)と呼んでいた。
現代の日本では、ハムと言えばたいていはロースハムの事を指すことが多いが、外国とは事情が異なり、ロースハムは日本固有のものと考えるべきだろう。
量産して流通しているロースハムは、豚ロース肉を塩漬・燻煙・ボイルなどの過程を経て商品化される。
→ 塩漬
→ 燻煙
→ 生ハム
→ ロースハム
→ プレスハム
→ スパム
→ JASマーク
- ハムカツ - はむ かつ
- ハムに衣を付けてカツレツにしたもの。
安価なプレスハム等を主原料としたジャンクフード的な位置付けである。
→ プレスハム
→ カツレツ
→ ハム
→ カツ
- バラ - ばら
- 畜肉の部位名。主に牛肉や豚肉に用いられることが多い。
脂肪分が多く、濃厚な旨みがあるのが特徴。
焼いても煮込んでも、味わいとして濃厚でリッチな食味を楽しむ事が出来る。
牛肉の手切りの焼肉料理としては、カルビが有名である。
豚肉のスライスの鍋物料理としてはキムチ鍋、また夏場はごまだれを使用した冷しゃぶが美味しい。
焼豚、煮豚、角煮といった豚肉料理にもおすすめの部位。
脂肪分が多いので、消費者の嗜好として好き嫌いが別れる所ではあるが、味わいとしてはかなり秀逸なレベルの部位である。
→ 三枚肉
→ 部位
→ カルビ
→ 骨付きカルビ
→ 上カルビ
→ サンカクバラ
→ サムギョプサル
→ 角煮
→ 焼豚
→ 煮豚
→ 部位
- ハラミ - はらみ
- 牛の焼肉用のアイテムとして人気がある。
横隔膜付近の赤身の肉であるが、内臓肉である。やわらかくて食べやすい。焼肉店では臭みをごまかす為に、通常は濃い目の味付けのタレに漬け込んで提供されることが多い。
米名 アウトサイドスカート
→ サガリ
- 春巻き - はるまき
- 広東料理。肉やキノコ・タケノコを細かくしたものを小麦粉ベースの皮に包んで油で揚げた料理のこと。立春の頃に新芽が出た具材を用いたことからの名称の由来だそうである。
→ 広東
→ 生春巻き
- パルマ - ばるま - Parma
- イタリアのこと。
イタリア共和国エミリア=ロマーニャ州パルマ県のコムーネの一つである。
日本では本格的な生ハムの産地として知られている。
→ 生ハム
→ プロシュット
- ハレの日 - はれのひ
- 社会慣習等、日常とは異なった特別な日の事を指す。
小売業界においては、商売チャンスである。父の日、クリスマス、お盆など、その社会慣習ならではの需要がある為、しっかりと取り組みたい。
→ キワモノ
- パワーセンター - ぱわー せんたー
- 広大な敷地内に、カテゴリーキラーと呼ばれる店舗を複数店舗集めて営業する形態のこと。
→ 業態
→ カテゴリーキラー
- 販促 - はんそく
- 販売促進の略。
飾り付けのポスター等の装飾物の事であったり、景品等を用意するキャンペーンの事であったりと広い意味で使われている言葉。
単にチラシ折り込み等の広告戦略の事を指す場合もある。
→ 什器
→ 販売促進
→ 定例販促
- パンチェッタ - ぱんちぇった
- 生ベーコンのこと。豚のバラ肉を塩漬けにして作る。燻製・燻煙処理を行わない為、生ベーコンと呼称される。
生ハムのようにそのまま食べるのが日本式。
→ ベーコン
→ 生ハム
- バンドル - ばんどる
-
→ バンドル販売
- バンドル販売 - ばんどる はんばい
- 小売業においての販売方法の一つ。○個で△△△円というように複数の商品をまとめて購入すると割安になるようにして、消費者にまとめて購入させる動機付けをする手法。
テープなどで商品を巻いて販売する方法も含まれる。
元値を通常よりも高めに設定しておいて、たくさん購入させるのは違法である。
→ ミックスマッチ
- ハンバーグ - はんばーぐ
- 挽肉に玉ねぎ等のみじん切りにした野菜と香辛料・パン粉などを混ぜ合わせて、主に円形に成型して焼いた料理。大抵のこどもの好きな料理の一つである。
焼き加減が難しいが、煮込みハンバーグなら誰でも簡単に調理出来る。
英語では hamburg steak と表現する。
→ 挽肉
- 販売時点情報管理 - はんばい じてん じょうほうかんり
- 小売店において、精算と同時に 販売に関する 各種情報を収集・分析するシステムのこと。及び、その手法の事を指す。
→ POS
- 販売促進 - はんばい そくしん
- 商品をより効率良く、多く販売する為に取る為の様々な手法のこと。
飾り付けであったり、チラシであったり、価格設定や陳列方法など、その手法は様々である。
略して 販促 と呼ばれる事もある。
→ 販促
- PI値 - ぴー あい ち - Purchase Index
- 流通・小売業界用語。ある特定の商品がどれだけ多くの顧客に支持されているのかを数量ベースの割合で測る指標である。レジ通過客数1,000人当たりにおいて何個売れたかという計算になる。
算式は、PI=(購買個数/客数)×1000 である。
PI値は金額ベースではなく数量ベースで分析する指標であるが、店舗の売上規模や前年比とはまた別の考え方で測る事の出来る指標であり、チェーンストアでは、客単価・平均単価とともに、金額PI値も経営分析に使用される指標である。
→ POS
- BSE - びー えす いー
- 牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy:BSE)の略。牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不能等の症状を示す悪性の中枢神経系の疾病。
→ 狂牛病
→ 特定危険部位
- BMS - びー えむ えす
- 牛肉における サシ のこと。日本語では「脂肪交雑」という言葉を使う。
Beef Marbring Standard の略で、格付けを決める為に必要な、肉質等級を決める項目の一つ。赤身の肉に脂肪がどれだけキメ細かなサシ(脂肪)が入っているかという、見た目を決める為の基準。0〜12までの基準がある。
⇒⇒ 画像参考資料 (外部リンク) (日本食肉格付協会)
→ 脂肪交雑
→ サシ
→ 格付け
- PB - ぴー びー
- Private Bland の略であり、自社開発商品のこと。
小売業界においては、メーカー品ではなく自社のオリジナル商品で商売をしたいという思いから、各社とも自社開発商品を展開する傾向は年々拡大傾向にある。
価格は安く、品質は高く(もしくはそれなりに) が PB商品のメリットであり、企業にとっては、値入れ が入る設定になっているのが最大のメリット。
反意語はNB(National Bland)である。
→ NB
→ 値入れ
- 比較販売 - ひかくはんばい
- 販売手法の一つ。売れ筋アイテムをより売り込むために、同じカテゴリー内でより高価な物やリーズナブルな物を陳列し、販売する。
→ 松竹梅 商法
- ピカタ - ぴかた
- イタリアの料理名の一つ。
うす切りにした肉を下味を付けた後に、小麦粉をまぶして 溶き卵とチーズを用いてソテーした料理の事を指す。
日本では豚肉を用いる事が多いが、魚であるタラ等を用いる事もある。
→ ポークステーキ
→ ソテー
- 挽肉 - ひきにく
- 食肉をミンチチョッパー等の器具で すり潰した食材のこと。
ハンバーグ、餃子、つくね等に利用される。そのままでは食感が固い部位でも、すり潰すことによってやわらかく、美味しく食べることが出来る。
鮮度劣化が速い為、いつも鮮度の高い挽肉を販売している小売店は優秀であると判断しよう。
小売店においては、購買頻度(PI値)の高いアイテムの1つである。
法律上は、生鮮食品ではなく、加工食品として分類される。
→ ハンバーグ
→ 餃子
→ ミンチ
→ 合挽き肉
→ チョッパー
→ 小売店
→ PI値
- ヒザ軟骨 - ひざなんこつ
- 鶏肉のヒザの部分にあたる軟骨の事を指す。
形状は丸い形である。衣を付けて唐揚げにして食べるとおいしい。
コリコリとした食感を楽しめる。
→ 軟骨
- ビシャモン - Bishamon - びしゃもん
- ハンドリフトの事。正式名称は、ハンドパレットトラック。
Bishamonはハンドパレットトラックのメーカー名であるが、何故か私の業界ではこれの事をビシャモンと呼んでいる。
- 飛騨牛 - ひだうし
- 岐阜県の銘柄牛の1つである。
生体の状態を「ひだうし」と呼び、食肉の状態では「ひだぎゅう」と呼称する。
ルーツは昭和50年代の安福(やすふく)号を種牛として飛騨牛が世間に認められるようになる。
- 飛騨牛 - ひだぎゅう
- 銘柄牛の1つである。
見た目のサシはそれ程でもないかもしれないが、味わいはとても濃厚であるのが特徴。
定義としては、岐阜県で14ヶ月以上肥育された黒毛和種で、肉質等級が3等級以上のものを指す。
・・この定義は平成14年12月に改訂になったものであり、それ以前の定義では、岐阜県の中でも飛騨地方で肥育されたもので、肉質等級が5等級以上の物しかこの銘柄名を使用出来なかった。
→ 肉質等級
→ 銘柄牛
→ 黒毛和種
- 飛騨牛銘柄推進協議会 - ひだぎゅう めいがら すいしん きょうぎかい
- JA全農岐阜の組織。
⇒⇒ 飛騨牛銘柄推進協議会 (外部リンク)
- 羊 - ひつじ
- 羊のこと。ラムやマトンとして食される。
食肉の観点のメリットは宗教を超えて食する事が出来る事である。
→ ラム
→ マトン
- ビビンバ - びびんば
- 韓国料理。丼等の器にご飯を盛り付けて、ナムルを盛り付けてかき混ぜて食べる料理の事を指す。上に乗せる具材はバリエーションが豊富であり、実際の所、正しい定義はない模様である。
→ 石焼ビビンバ
→ ナムル
- ビフテキ - びふてき
- ビーフ ステーキ (Beef steak)の略語。フランス語の bifteck から来た言葉だという説もある。
牛肉のステーキの事である。現代ではステーキと言えば一般的に牛肉の事を指すが、以前はわざわざ「牛肉のステーキ」であるという意味を込めて、ビフテキと呼ぶ時代があった模様である。
→ ステーキ
→ 牛肉
- 冷やし込み - ひやしこみ
- 精肉業界の一部の小売店において行われている、手法。
食品は何でも 作りたて、切り立てが良いというのは実は間違いである。
特に食肉業界においては、「熟成」や「発色」という言葉が使われる事が多いが、食肉に関しては、ある程度の時間や期間を置いた方が、より美味しく食べる事が出来る事例があることは事実である。
小売店において、原料肉を加工した後すぐに店頭にて販売せずに、作業場内の冷蔵庫にて冷却する事を冷やし込みと言う。
食肉においては、切りたてよりも、あるていどの時間(期間)を置いた方が、商品価値が高まるからである。
→ 熟成
- 百貨店 - ひゃっかてん
- デパート と同じ意味。
大経営の総合小売店。多層構造の建物であらゆる種類の商品を総合的に販売する。実演販売や、ディスプレイによる提案などの要素を多く取り入れている販売形態であることが主流。安売りではなく、ブランドと呼ばれる高級品・高額品を接客販売による手法で販売する事が多い。
→ デパート
- 平ケース - ひらけーす
- 小売店における販売用の什器のこと。平台とも言う。
ここでは要冷蔵の商品を販売する為の 冷蔵機能を備えたものを説明している。
多段ケースの反意語でもある。
多段ケースにおいては定番商品の品揃え、又はアイテム数重視の商品陳列が基本とされることが多いが、平ケースにおいては単品量販、又は催事色の高いスポット販売に使用される傾向が強い。
マネキンを使った試食販売に有効である。
→ 平台
→ 多段ケース
- 平台 - ひらだい
- → 平ケース
- 平場 - ひらば
- → 平ケース
- ヒレ - ひれ
- 主に牛肉や豚肉等の畜肉において用いられる部位名。
一頭から採れる重量が極めて少ない為、希少部位の位置付けとされる。
キメが細かくとてもやわらかな肉質である。スジや脂身が無く、肉本来の味わいを堪能出来るが、やや内臓肉に近い味わいである。
レストランではテンダーロインステーキという名前で販売される。
→ 部位
→ テンダーロイン
→ シャトーブリアン
- 品種 - ひんしゅ
- 食肉業界においては、「血統」の意味で使われる言葉。
違う品種をかけあわせて交配した物は、交雑種と呼ばれる。
→ 交雑種
→ 和牛
→ ホルスタイン
- 備長炭 - びんちょう たん
-
和歌山県産の 樫(かし)・ウバメガシ を原料とした、木炭のこと。
通常の炭よりも、煙が出ず雑味が少ないという理由で、食品を焼き上げるのに適するとされている。
- ピンホール - ぴん ほーる - Pinhole
-
針で開けたような小さな穴のこと。真空パックなどのフィルム包装に何らかの原因で傷がついて穴が開いた時などに使う言葉。
- 部位 - ぶい
- 食肉におけるの部分の名称のこと。
農林水産省が定めた「食肉小売品質基準」によって表示基準が統一されている。牛肉の場合は、ネック、カタ、肩ロース、リブロース、サーロイン、ヒレ、バラ(肩バラ、トモバラ)、モモ(シンタマ、内モモ)、外モモ、ランプ、スネの11部位。
小売店においては、部位名の表示が義務付けられている。
→ 小間切れ
⇒⇒ 【 部位別特徴 】
- フィッシュソーセージ - ふぃっしゅ そーせーじ
-
→ 魚肉ソーセージ
- 風評被害 - ふうひょう ひがい
- 根拠のない噂などにより受ける被害のこと。
食品の事故や事件に関しては、マスコミの報道のされ方により、とても大きな影響を受ける事が多い。
消費者も冷静に判断をする必要がある。
- フェース - ふぇーす
- 商品を陳列する際の業界用語。
商品の顔(フェース)をどのように見せるのか、数量的にいくつ横や縦の方向に並べるのか等 計画段階で使われる事が多い。
多段ケースに商品を陳列する際には、下段は平積み、それより上の段はフェースアップ(商品を立てかける)陳列をするなど、の手法がある。
→ 陳列
→ 前出し
→ 什器
- フォアグラ - ふぉあぐら
- ガチョウまたは鴨の肝臓を使った料理のこと。
無理矢理たくさんの餌を与え、脂肪のたくさん入った肝臓を人工的に作る。
フランス料理であり、ソテーしたり、パンに塗って食べる。世界三大珍味の一つとされる。
→ レバー
- 付加価値 - ふか かち
- 本来の姿に何らかの価値を加えること。
小売業界においては、仕入れた商品に対して何らかの価値を加えて販売する。
新しいメニュー(食べ方)の提案であったり、使いやすい量目の盛り付け、関連販売の取組み、値ごろな販売価格、その方法は様々である。
→ 関連販売
→ 小売業
→ 値ごろ
- 副産物 - ふくさんぶつ
- 食肉業界においては、正肉の反意語として用いられる用語。
正肉を作り出す時に、それに付随して発生する物の事である。
一例としては、内臓やスジなどのこと。
→ 正肉
→ 内臓
→ スジ
- 部署 - ぶしょ
- 企業の組織を表現する用語であり、全体を区分けした部分。
小売業においては、衣料、食品、日用雑貨品、業務、などと区分される。
部署をさらに細分化したものが部門である。
→ 部門
→ 小売業
- 豚 - ぶた
- 食用の肉の畜種として一般的である。
元々はイノシシを家畜としたもので、日本だけではなく世界中で広く飼育、食用とされている。免疫力が比較的高く、飼育・肥育するのに比較的容易な家畜である。
栄養学的には、疲労回復に役立つと言われるビタミンB群を多く含み、成長に不可欠なタンパク質を多く含む。
品種は多く、主な品種としては、大ヨークシャー種、中ヨークシャー種、ランドレース種、デュロック種、バークシャー種、ハンプシャー種などがある。
食肉用の豚肉としては単一品種の豚肉はまれであり、複数の品種の掛け合わせであることが一般的である。
→ 黒豚
→ 品種
- 豚ガラ - ぶたがら
- 豚の骨のこと。料理を作る為のスープを作るダシの素材として利用される。スーパーなどの一般的な小売店では入手は難しい。
→ げんこつ
→ 豚骨
→ ガラ
- 豚キムチ - ぶた きむち
- 豚肉とキムチを合わせた料理の名前。
外食産業においては、丼物のメニューとして提案されたのが始まり。
家庭料理では、豚バラ肉の薄切り肉とともにキムチを合わせた物が広く支持されている。
当初は、酒の肴にという料理かもしれないが、現在の日本においても、おかずメニューとしても徐々に広まっている。
→ 豚
→ バラ
→ キムチ
- 豚キムチ - ぶた きむち
- 豚肉とキムチを合わせた料理の名前。
外食産業においては、丼物のメニューとして提案されたのが始まり。
家庭料理では、豚バラ肉の薄切り肉とともにキムチを合わせた物が広く支持されている。
当初は、酒の肴にという料理かもしれないが、現在の日本においても、おかずメニューとしても徐々に広まっている。
→ 豚
→ バラ
→ キムチ
- 豚コレラ - とん これら
-
→ 豚コレラ
- 豚しゃぶ - ぶた しゃぶ
- 豚肉の薄切り肉を用いたしゃぶしゃぶ料理のこと。
しゃぶしゃぶは以前は、牛肉の高額な部位を使用する特別なごちそうメニューの位置付けであったが、現在では家庭料理の一つである。
牛肉よりも安価な豚肉を用いたしゃぶしゃぶ料理のことを、あえて「豚しゃぶ」と呼ぶことがある。
→ しゃぶしゃぶ
- 豚タン - ぶた たん
- 豚の舌のこと。
焼肉材料として用いられることが多い。
加工肉としてオードブルの提案とした商品もある。
→ タン
→ 牛タン
→ 加工肉
- 豚肉 - ぶた にく
- 食用の豚のこと。
日本国内においては おかずメニューの位置付けとして広く食されている。
関西方面では、食文化的な観点から 肉と言えば牛肉の事を指す事が一般的な為、お好み焼き等に用いる豚肉は敢えて「豚肉」と呼称する。
→ 豚
→ 食肉
- 歩留まり - ぶどまり
- 仕入れた物を販売する際に、実際に商品として販売出来る比率の事を指す。
肉の場合、仕入れた原料肉は骨やスジ、脂、汚れ、ドリップ等 商品にはならない物が付いている場合があるので、それらを取り除く必要がある。
仕入れた原料が仮に10kgの重量であり、取り除いた物の重量が仮に1kgであった場合には、実際に商品として販売される重量は9kgとなる。この場合の歩留まりは 90% (9割) となる。
- 部門 - ぶもん
- 企業の組織を表現する用語であり、全体を区分けした部分。
部署よりは、さらに細分化された表現である。
小売業の世界においては、一般食品部門、生鮮食品部門などという意味。
生鮮食品部門はさらに、精肉(畜産 )、鮮魚、青果部門などと細分化される。
→ 部署
→ 小売業
- フライ - ふらい
- 料理・調理名。多めの熱した油に食材を投入して調理する方法。又はその調理方法において調理された料理の事を指す。
→ カツ
- フライドチキン - ふらいど ちきん
- 鶏肉料理。日本で一般的に知られているフライドチキンとは、骨付きの鶏肉をスパイシーな味付けで油で揚げた料理のことである。
日本の家庭料理では、唐揚げという名前が一般的である。
→ 唐揚げ
→ 鶏
→ 鶏肉
- プライム - ぷらいむ - Prime
- アメリカ牛の肉質の格付けにおいて、上級のこと。
USDA(米国農務省)による牛肉の格付けは8段階に設定されているが、そのいちばん上の格付けである。
→ USDA
- プライベートブランド - ぷらいべーと ブランド - Private Bland
- PBと略す。
→ PB
- プライムリブ - ぷらいむりぶ - Prime Rib
- アメリカは Las Vegas や Beverly Hills などに店舗を構える高級肉料理店「Lawry's 」の有名料理として知られる。ステーキのような極厚切りカットのローストビーフのこと。とてもやわらかくてめちゃめちゃ旨い。
→ ローストビーフ
- フランクフルト - ふらんくふると
- ソーセージのカテゴリの一つ。
日本ではJAS規格により基準が定義されており、豚の腸に詰めた(もしくは直径20mm以上36mm未満)物をフランクフルトと定義している。
バーベキューにおいては、串刺しにしたフランクフルトが人気である。
→ ソーセージ
→ バーベキュー
⇒⇒ 【 JAS規格によるソーセージ分類 (資料) 】
- フランチャイズ - franchise - ふらんちゃいず
- 小売業界におけるチェーン展開の手法の一つ。
本部とオーナーという位置付けで、本部の営業活動に賛同する者がオーナーとしてフランチャイズ店舗を運営する。
同じ看板・商品・サービスレベルをキーワードに 店舗としては複数・無限大に増殖するが、ビジネスとしては色々な課題もあるようだ。
→ チェーンストア
- ブルー・オーシャン - ぶるー・おーしゃん - Blue Ocean
- 経営戦略用語。競争や競合の無い未開拓の領域で新しい商売をする事。具体的には付加価値の見える化、鮮度の価値の提供、素材だけの提供では無い消費者の要求に応える形での小売方法の確立等々が挙げられる。
→ レッド・オーシャン
→ ライブ販売
- プレスハム - ぷれす はむ
- 元々は、畜肉の端材等を利用して圧力と熱を加えて固めた加工食肉のこと。安価に提供出来る為、それなりの需要があったようだが、現在では贈答品としても使用される品質の認められたジャンルとして確立されている。
→ ハム
- ブロイラー - ぶろいらー - broiler[英]
- 食肉用に大量生産される鶏肉の総称である。
具体的な品種としては、チャンキーなどがあげられるが、人為的に大量に生産される鶏肉のことを指すことが多い。
→ 鶏
→ 鶏肉
→ 品種
→ 食肉
- プロシュート - ぷろしゅーと
- → プロシュット
- プロシュット - ぷろしゅっと - Prosciutto
- 日本ではイタリア産の生ハムの事を差す。
イタリアでは豚のもも肉のハムのこと。塩漬けにした後、乾燥させて製造する。
日本ではプロシュートとも表現される。
→ 生ハム
- ブロック - ぶろっく
- 食肉の販売形態の一つで、かたまりのまま販売すること。
→ かたまり
- ベーコン - べーこん
-
豚のバラ肉を塩漬けして燻製したものが本来の定義である。
もともとは傷みやすい食材を保存する意味で加工していたが、現代においてはその定義もやや変わりつつある。
一般的な調理用途としてはベーコンエッグや、スープ、炒めもの料理、シチューなどに多く用いられる。
量販店ではスライスされた物が一般的であるが、ブロックタイプの物も根強い人気がある。
→ 燻煙
→ バラ
→ パンチェッタ
- ヘット - へっと
- 牛の脂を精製した食用油脂のこと。
牛脂とも呼ばれるが、ヘットという場合には精製された加工した脂のことを差す場合が多い。
→ 牛脂
→ ケンネ脂
- 変色 - へんしょく
- 色が変わること。
- 包丁 - ほうちょう
- 様々な種類が存在するが、精肉業界においては 牛刀・筋引き包丁などが一般的である。
家庭用の一般的な包丁は両刃であることが多いが、精肉用の包丁は片刃であることが多い。
使い方も色々であり、スジを引く場合は引いて使うが、焼肉用のカットやステーキ用のカットなどには、押して使うことが多い。
→ 筋引き包丁
- ポーク - ぽーく - pork(英語)
- 豚肉のこと。
→ 豚肉
- ポークステーキ - ぽーく すてーき
- 豚肉のステーキのこと。
ステーキと言えば一般的には牛肉の事を指す事が多いが、豚肉をステーキにしたものをあえてこう呼ぶ場合もある。
→ 豚肉
→ ステーキ
→ ピカタ
- ホースラディッシュ - horseradish[英] - ほーすらでぃっしゅ
- 西洋わさびのこと。
薬味として使われる。ローストビーフの薬味には欠かせない。
レホール(又は レホーネ)・山わさび・ワサビダイコン と呼ばれることもある。
レホールはフランス語である。
- POS - ぽす
- Point of sale system のこと。日本語では 販売時点情報管理 と言う。
現在のスーパーやコンビニエンスストア等の販売店においては、もはや主流のシステムである。
商品に付いたバーコードを会計時のレジシステムが読み取る事によって、どの商品が、いつ・いくらで・どれだけ 売れたかを集計・分析する事が出来る。
→ バーコード
- ホスピタリティ - hospitality[英] - ほすぴたりてぃ
- 「おもてなし」と表現される事が多い。
マニュアルがある訳ではなく、接客サービス業として、お客様にいかに満足・喜んでいただけるか、を主軸としている。
サービス業としては、お客様の要望に応える事はもはや当たり前の事であり、お客様の期待値を超える 「感動」を呼ぶ応対 が求められる風潮になりつつある。
→ サービス
→ サービス業
- 細挽き - ほそびき
- 畜肉を挽肉にする行程で、荒挽きから細挽きにすること。
加工食品であるウインナーでは荒挽きタイプが主流であるが、小売店における挽肉においては 荒挽きの後に細挽きをかけた2度挽きである細挽きが主流である。
→ 挽肉
→ 荒挽き
→ 絹挽き
→ ウインナー
- 保存 - ほぞん
-
そのままに保つこと。食肉は傷みやすいために、その昔から保存性を高める工夫が色々となされてきた。干物、塩漬け、冷蔵、冷凍、真空パック、ガスパック、保存料添加、等々。
→ 保存方法
→ 保存料
- 保存方法 - ほぞん ほうほう
-
食品衛生法では、保存温度が守られた時の期限表示のルールを決めている。
常温とは(おおよそ15℃から25℃)のことである。
→ 消費期限
→ 賞味期限
- 保存料 - ほぞんりょう
- 食品の腐敗や変色を防止する為に用いられる食品添加物のこと。
その使用方法や、使用量については食品衛生法で厳しく規定が定められている。
→ 食品添加物
→ 食品衛生法
- ポトフ - ぽとふ
- 肉類やソーセージと、野菜を煮込んだもの。フランスの家庭料理。
野菜は大きめにカットされ、スープは 塩・胡椒・ハーブなどで味を調えたものである事が多い。
もともとは具とスープを別々に食べる料理だが、日本においては必ずしもそうではない傾向である。
→ シチュー
→ スープ
- 骨付きカルビ - ほねつき かるび
- 一般的には牛のバラ肉の骨が付いた状態の食肉のことを指す。
骨の周りのゼラチン質を含めて、骨付き肉は実際に旨い。
焼いた肉を、はさみを用いつつ切り分けて食べるのも美味しい。
→ カルビ
- 骨付き肉 - ほねつき にく
- 日本の食肉業界においては、骨付きの肉の販売はどちらかと言うと少数派である。海外では骨付き肉の需要もそれなりに高いようである。
日本では、クリスマスに人気の高い鶏肉の骨付きモモ肉や、夏場のバーベキューシーズンに需要のある豚の骨付きバラ肉等が一般的である。
→ マンガ肉
→ 串フランク
- POP - ポップ - ぴー・おー・ぴー
- 商品名や価格、そのセールスポイントなどを記した広告媒体のこと。
Point Of Purchase の略である。
セルフサービスを主とした小売店においては、販売員に代わる重要な役割を担う。
→ コトPOP
- ホモソーセージ [商品名] - ほも そーせーじ
- 丸善の魚肉ソーセージの事である。
ここでいう「ホモ」とは、「homogenize」(均一にする)という意味からとった商品名である。
丸善の本社は東京であるが、長野県エリアでは絶大な支持を得る人気商品である。
食べてみると実際に美味しい。
魚肉ソーセージの域を超えた、食感と風味・味わいが楽しめる。
→ 魚肉ソーセージ
- ホルスタイン - ほるすたいん
- 牛の品種の一つ。日本では乳用種としての位置付けである。
つまり「牛乳」を生産する為の牛であり、食用としての位置付けは低い。
牛の生体の見た目は 白・黒の斑点が特徴である。
→ 牛
- ホルモン - ほるもん
- 内臓肉の総称。元々は廃棄される事が前提の「放るもん - ほおるもん」が呼称の由来であると言われている。
- ボロニア - ぼろにあ
- ソーセージのカテゴリの一つ。日本ではJAS規格により基準が定められており、牛腸を使用した物、または直径が36mm以上のソーセージの事を指す。
やわらかな食感のソーセージ。厚めに切り分けて焼いて食べるとおいしい。
→ ソーセージ
⇒⇒ 【 JAS規格によるソーセージ分類 (資料) 】
- 本部 - ほんぶ
- チェーンストア形式をとる小売業界において、計画や指示を出す部署の事である。
企業の規模にもよるが、本部による一括仕入れによる販売は 同等の品質でより競合店舗よりも安い価格で販売することができるメリットなどがある。
→ チェーンストア
- 本部チラシ - ほんぶ ちらし
- 業界側からの視点でのチラシの種類の一つ。
チェーンストアにおいては、本部チラシと個店チラシというものが存在する。
チェーン全店において有効なチラシの事を本部チラシという。
本部商談においてマスメリットを活かした内容となる傾向が強い半面、その地域ならではの特色や強みを反映する事が難しいので、大雑把な内容になりがちである。
→ チラシ
→ 個店チラシ
- 本部投入 - ほんぶ とうにゅう
-
→ 投入
- 前出し - まえだし
- 商品整理の事。小売店の店舗における業界用語。
陳列されている商品を整理して、お客様に買いやすいようにすること。
→ 先入れ先出し
- 前バラ - まえばら
- 部位名。牛肉において使われる言葉。
牛肉のバラの部位名は ざっくり言うと、前バラと友バラの2つに分けられる。
前バラは肩バラと同意語。
→ バラ
→ トモバラ
→ 部位
- マガモ - 真鴨 - まがも
- カモ目カモ科の鳥のこと。渡り鳥として知られる。
食肉業界における鴨は、合鴨である事が多い。
→ 合鴨
→ 鴨
- マスメリット - ます めりっと - mass merit
- 大量生産・大量仕入れ等の手法により、商品の仕入れ価格を下げること。顧客にはよりお値打ちな価格で商品を提供し、更には販売者側としては利益を少しばかり余分に取りたいという思いから生まれた手法。
実際には 大量に仕入れた商品を、大量に販売するスキルが問われる。
- 松阪牛 - まつさかぎゅう - まつさかうし
- 三重県松阪市およびその周辺で肥育される黒毛和種のこと。
高級なブランド和牛として認知されている。
以前は肉質等級A5等級以上の最高級の品質の物しか、その名を語ることが許されなかったが、2002年に規約が改定されており、肉質等級にかかわらずある一定の条件において松阪牛という名前を付けることが可能となっている。
未経産の雌牛である事が条件となっている。
→ 肉質等級
→ 経産
- 松屋 - まつや
- 牛めし等のメニューを提供する外食チェーン店のこと。
→ 牛めし
⇒⇒ 松屋 (外部リンク)
- マトン - まとん - mutton
- 成羊肉のこと。
生後12ヶ月以下の羊の肉をラムと呼ぶのに対して、それ以上の月齢の羊の肉をマトンと呼ぶ。
臭みが無くやわらかな肉質のラムに対して、マトンはそれなりの癖がある食肉であるが、特製のタレに漬け込む等の工夫において好まれる地域や文化もある。
→ ジンギスカン
→ ラム
- マネキン - まねきん
- スーパーマーケット等において試食販売を行う人材派遣会社から派遣されたセールスの人員のことを指す。小売業の業界用語である。
メーカーの経費にて手配してもらう事が多い。
→ 試食販売
→ メーカー
- まわし - まわし [方言]
- 名古屋弁で「準備」という意味。
まわしをする は「仕込みをする」という意味である。
→ 仕越し
- マンガ肉 - まんが にく
- 定義は無いが、アニメやマンガに登場するインパクトのある肉のことを指す。
たいていは、骨付きで大きな肉の塊である。
アニメ「はじめ人間ギャートルズ」がマンガ肉の代表格とされているようだ。
→ 骨付き肉
- マンナン - まんなん
- とても ざっくり 表現すると 「こんにゃく」 の事。
→ マンナンレバー
- マンナンレバー - まんなん ればー
- レバー風味のこんにゃく食品のこと。
レバ刺しをどうしても食べたいという需要に応える為の 疑似商品。
実際に食べてみるとレバ刺しと遜色ない程 良く出来ている。
→ レバ刺し
→ 生レバー
→ 生食
- ミートローフ - みーとろーふ - meatloaf
- アメリカの家庭料理。牛や豚 または その合挽の挽肉に卵・パン粉・玉ねぎのみじん切りなどを加えて練り合わせ、オーブンで焼き上げる料理のこと。
日本のハンバーグと似ている。
→ ハンバーグ
- ミートボール - みーとぼーる
- 挽肉を香辛料やつなぎと練り合わせ、一口サイズの球形状にした料理のこと。
→ 挽肉
→ ハンバーグ
→ 肉団子
- ミールソリューション - みーる そりゅーしょん
- 調理に関する手助けをする事、もしくはその商品・商材のことを指す。
家庭内の調理において、下ごしらえから始まる調理は時間と手間のかかかるものであるが、スーパー等における小売店の取組みの一つとして、簡便に調理が出来る商品・商材の取組みの事を指す。
具体的には、下ごしらえが既にされており、後は焼くだけ・揚げるだけの商品・商材のことを指す。
→ 中食
- 見切り - みきり
- 小売店において、販売価格を当初の計画よりも下方修正して、値下げをすること。
鮮度管理の為に、売れ残った品、もしくは売れ残りそうな品の価格を値下げする行為のことである。
→ 値下げ
→ 値引き
- ミスジ - みすじ
- カタの一部。サシが多く入り、柔らかく旨みも濃厚。稀少部位。
→ 部位
- 味噌カツ - みそ かつ
- 料理名。味噌を調味料として食する豚カツのこと。
一般的には豚カツはソースを調味料として食するが、愛知県名古屋市周辺では味噌を調味料して食する事が多い。
名古屋地区で言う味噌とは、八丁味噌のことを指す事が普通であり、大豆を原料した赤い色が特徴の甘辛い味噌である。
→ カツ
→ 味噌カツ丼
- 味噌カツ丼 - みそ かつ どん
- 料理名。カツ丼の調味料の主役として味噌を用いる料理。
名古屋地域では赤味噌を文化とした地域である。
この場合の赤味噌とは、八丁味噌のことを指す事が普通であり、大豆を原料した赤い色が特徴の甘辛い味噌である。
→ カツ
→ カツ丼
- ミックスマッチ - みっくす まっち
- 小売業界における専門用語。バンドル販売、まとめ売りとも言う。
一例として、1個298円の商品を複数の種類を用意して陳列し、1個では298円ですが、3個買えば798円にしますよ、という販売手法。
販売側の意図としては、一人あたりの単価(客単価)を上げたいという思いが込められている。
→ バンドル販売
→ 小売業
→ 客単価
→ 品種
- ミディアム - みでぃあむ
- 肉の焼き加減のひとつ。
特にステーキの焼き方で用いられる表現。レアとウェルダンの中間を指す。表面はしっかりと焼いた状態で、中心部は肉汁が楽しめるような焼き具合。
→ 焼き加減
→ レア
→ ウェルダン
- ミディアムレア - みでぃあむ れあ
- 肉の焼き方のひとつ。
特にステーキの焼き方で用いられる表現。ミディアムとレアの中間を指す。やわらかい食感と肉汁の旨みを楽しめる焼き加減とされる。
→ 焼き加減
→ レア
→ ミディアム
→ ウェルダン
- ミンチ - みんち
- → 挽肉
- 無塩漬 - むえんせき
- ハム・ソーセージ等を作る行程で発色剤を使用しないこと。
→ 塩漬
- 蒸ししゃぶ - むし しゃぶ
- 鍋料理の一つ。煮込むのではなく、蒸すのがポイント。
野菜と一緒にお肉を食べられるのが嬉しい。
専用の鍋等も市販されているが、ホットプレートでも調理できる。
→ 鍋料理
→ しゃぶしゃぶ
→ スライス
→ 焼きしゃぶ
→ タジン
- 無添加 - むてんか
- 添加物を使用していない事を表現する意味であるが、小売店で販売される食品に添加物が使用されていないことは少ないと考えるべきであろう。
合成保存料や着色料が使用されていないと解釈するのが妥当。
→ 添加物
- 銘柄牛 - めいがら ぎゅう
- 世間一般に名の通ったブランドの牛肉のこと。
銘柄牛の定義は実はあって無い様なもので、各地域の様々な団体がそれぞれの定義を設定している。そして銘柄牛=和牛と言う訳でもない。
有名な銘柄牛は消費者の支持を受ける為、価格としては割高になる傾向が強い。
よく知られている銘柄牛の一例としては、松阪牛や神戸牛などがある。
→ 牛肉
→ 和牛
- メーカー - めーかー
- 一般的には製造業の会社のことを指す。
小売業から見た解釈では、商品を製造し提供してくれる企業のことをメーカーと呼ぶ。
→ 小売業
- 盛り合わせ - もりあわせ
- 1つの皿やパック等に、複数の食材を盛り付けたもの。
→ セット
- 焼き加減 - やき かげん
- ここでは牛肉のステーキの焼き具合について記す。
レストラン等でステーキを注文した際に、焼き方についても注文をする場合の焼き加減の言葉である。一般的には次の3段階の表現であり、よりジューシーさを味わえる「レア」、程良い焼き具合の「ミディアム」、そしてよく焼いた「ウェルダン」である。
さらに「ベリーレア」、「ミディアムレア」、「ベリーウェルダン」などという注文の仕方もある。
アメリカでは赤身の肉が比較的好まれる傾向があり、赤身肉は加熱すると固くなる傾向が強いので、レアやベリーレア等という生焼けに近い 焼き加減の注文の仕方もあるかと思われるが、日本では霜降りの肉が好まれる傾向が強く、ある程度焼いても食感はそれほど固くならないので、焼き加減は本当にその人の好みである。
→ ステーキ
→ レア
→ ミディアム
→ ウェルダン
- 焼餃子 - やき ぎょうざ
- 餃子のこと。
餃子には様々なバリエーションがあるが、日本でいう餃子はこの焼餃子が一般的である。
焼餃子と言いながら、実は、調理法的には 蒸し焼きをしている事が一般的である。
→ 餃子
- 焼きしゃぶ - やき しゃぶ
- スライス肉を焼いて食べる料理。「しゃぶ」という名前に惑わされがちだが、焼肉メニューとしての提案・食べ方である。
スライス肉は手切りの肉に比べて、その肉厚が薄いので、すぐに焼けるし食べた時の食感がやわらいという特徴がある。タレはこってり系の味付けではなく、さっぱり系の柑橘果汁などをベースにしたものがオススメである。
→ 焼肉
→ 手切り
→ スライス
→ しゃぶしゃぶ
- やきとり - やきとり - ヤキトリ - 焼き鳥 - 焼鳥
- 鶏肉などを一口大の大きさに切ったものを串に刺してあぶり焼きにした料理。調味の仕方は大きく分けて2種類で、タレと塩が一般的である。
部位により、様々なやきとりがあるが、モモ、ねぎま、皮、レバー、つくね 等がある。
→ 鶏
→ 串焼き
- 焼肉 - やきにく
- 肉を焼いて食べる料理名、又はその行為の事を指す。
一般的には、一口大にカットした牛肉又は豚肉を、網を用いた炭火で焼いたり、ホットプレートなどで焼いてタレを付けて食べる。特に作法などは無いので、美味しく楽しく食べたい。
→ バーベキュー
→ 焼きしゃぶ
→ キムチ
→ トング
- 焼肉セット - やきにく せっと
- 焼肉という料理を楽しむ場合、色々なお肉を少しずつたくさんの種類を食べたいという需要に合わせて提案する商品。
1つのパックに複数の焼肉用のお肉等が盛り付けられているものを指す。
→ 焼肉
→ セット
- 焼肉の日 - やきにく の ひ
- 8月29日を語呂合わせで「焼肉の日」としている。
→ 肉の日
→ 焼肉
- 焼豚 - やきぶた
- 本来の意味は、豚かたまり肉にタレ等の調味料を塗って焼いた料理のことであるが、現在の日本においては、煮て調理したものを「焼豚」と呼ぶ事も多い。
→ 煮豚
→ チャーシュー
- ヤゲン軟骨 - やげんなんこつ
- 鶏肉の軟骨のこと。
胸の部分の軟骨である。
主に串に刺してヤキトリメニューとして調理、提供される事が多い。
塩コショウ等の基本的な味付けだけで充分に楽しめる。
コリコリとした食感を楽しめる。
→ 軟骨
- やわらかい - やわらかい
- 固いの反意語。
消費者が食肉に求める需要として最も大きなポイントの1つである。
味が美味しいかどうかと言うよりも、「やわらかい」かどうか、がとても大きく求められている。
食肉はどんな部位でも薄くスライスしてしまえば、たいていは許容範囲でそこそこやわらかく食べられるものである。
ブロック肉等をやわらかく食べる為には、食材の特性に合わせた調理方法もある程度は要求されるものであり、安い肉をやわらかく食べようと思うならば、ある程度の知識と手間が必要である。
→ やわらかいお肉とは?
- US - ゆー えす
- アメリカのこと。
産地を指す場合の略語として使用されることが多い。
The United States of America の略。
→ 産地
- 優良誤認 - ゆうりょう ごにん
- 実際に販売する物よりも良い品質や、サービスであると消費者に誤解を与えること。
景品表示法という法律において禁じられている。
品質、サービス、価格等において適用される。
以前は 公正取引委員会 の管轄であったが、2009年以降は消費者庁の管轄である。
→ 景品表示法
→ 公正取引委員会
- 油淋鶏 - ゆーりんちー
- 中華料理名。鶏の唐揚げに、たっぷりのねぎと酢醤油ベースのタレをかけた料理のこと。
日本では骨なしの唐揚げ肉を用いられる事が多いようだ。
冷めても美味しく、日本ではどちらかと言うと夏向きの料理の位置付け。
→ 唐揚げ
- USDA - ゆー・えす・でぃ・えー
- アメリカ合衆国農務省のこと。United States Department of Agricultureの頭文字の略。
- ユッケ - ゆっけ - 육회 [韓]
- 韓国の料理名。主に牛のモモ肉を原材料として細かく刻んだ物を、ごま油・コチジャン等で味付けし、卵黄を乗せてそのままかき混ぜて生で食べる。
日本でも焼肉料理店等では普通に提供されていたが、2011年に発生した食中毒事件を受けて、食肉を非加熱で食べることへのリスクについて議論が高まった。
→ 生食
→ 食中毒
- 輸入物 - ゆにゅう もの
-
原料原産地が、日本ではない外国の物であること。
日本国内の消費者は、国産のものをもとめる傾向が強いようだ。
→ 原料原産地
- 要冷蔵 - ようれいぞう
- 表示に関する用語。
商品の品質保持の為に、冷蔵が必要である事を知らせる表示のこと。
詳しい温度帯も合わせて表示することとなっているが、10℃〜0℃という温度帯を表示されている商品が多い。
→ 冷蔵
- 吉牛 - よし ぎゅう
- 外食産業の 吉野家 を指す略語。
→ 吉野家
- 吉野家 - よしのや
- 牛丼を主としたメニューを提供する フランチャイズ ファーストフード店。1899年創業。「早い・安い・旨い」のコピーは鮮烈。
外国産の原料肉を使用し、日本人の嗜好に合わせたメニューの開発と提案・提供している企業体。
→ 牛丼
⇒⇒ 吉野家 (外部リンク)
- ラード - らーど
- 豚の脂を精製した食用油脂のこと。風味や味わいを増す為にラーメンや豚カツなどに用いられることが多い。
→ 牛脂
→ ケンネ
- ライスペーパー - らいす ぺーぱー - rice paper
- 米を原料としたもので、薄くシート状に加工して乾燥したもの。
生春巻きを包む為の皮として主に使用される。水で戻して使用する。
→ 生春巻き
- ライブ販売 - らいぶ はんばい
- 実演販売の事。切り売りや量り売り等、提供する形態は様々であるが、小売店において消費者の面前で五感にアピールする事に価値を付加する販売方法。
→ ブルー・オーシャン
- ラフティ - らふてぃ
-
→ ラフテー
- ラフテー - らふてー
- 沖縄の郷土料理。
一般的には角煮と呼ばれる料理のことであるが、豚バラ肉を皮付きのままとても柔らかくなるまで煮込んだ料理である。
ラフティとも。
→ 角煮
- ラム - らむ - Lamb
- 子羊の肉のこと。
生後12ヶ月以下の若い羊の肉を指す。それ以上の月齢のものはマトンと呼ばれる。
ラムはマトンに比べてやわらかいのが特徴である。
日本国内の食肉需要は比較的少ないが、世界的には宗教にかかわらず食べることが出来る食肉として位置づけられている。
→ 羊
→ ジンギスカン
→ マトン
- らんいち - らんいち
- 牛のモモ肉のこと。
ランプとイチボに分割される前の状態を指す。
→ ランプ
→ イチボ
- ランチョンミート - luncheon meat(英) - らんちょんみーと
-
日本ではSPAMと呼ばれる缶詰の事を指す事も多い。
豚肉・牛肉等を主原料とした挽肉を香辛料を加えて加熱調理した食品のこと。
再加熱せずにそのまま食べる事が出来るので、昼食利用に適しておりこの名が付いたとされている。
→ スパム
- ランプ - らんぷ
- モモ肉の一部。腰からお尻にかけての大きな赤身で、特に柔らかい部分。とても柔らかく旨みがあるがクセがない。
見た目のサシ気はあまりないが、とにかくやわらかくて味わいがある。オススメ。
水分量が多い為、商品化してからの鮮度劣化は早い。
→ イチボ
→ らんいち
- リブ −りぶ
- 骨付きのあばら肉。またはリブロースの略。
→ リブロース
- リブロース − りぶ ろーす
- 部位名であるが、特に牛肉に用いられる。
厳密な定義としては、ロースを 助骨で数えて10本目と11本目の間で分割し、頭側をリブロース、腰側をサーロインと呼ぶ。
その形状から、リブロースはより丸くて面積を多く採れる事から、すき焼き・しゃぶしゃぶ用に提供される事が多く、サーロインはより細長い形状から、ステーキ用として提供される事が多い。
リブロースは「かぶり」と呼ばれる物が付いているのが特徴。
霜降りが入りやすく、とてもやわらかで濃厚な旨味である。
かぶり を外したリブロースは、ロース芯とも呼ばれる。
→ ロース
→ サーロイン
→ かぶり
- 料理 − りょうり
- 調理する過程 と 調理された完成系 の両方を指す言葉。
→ 調理
→ 料理名
- 料理名 − りょうり めい
- 料理された名称。
→ 料理
→ 調理
- 臨店 −りんてん
- チェーンストア等の業種における業界用語で、本部スタッフが指導の為に各営業店舗を巡回することを指す。
本部からの意志を伝えたり、指示通りの売場対応が出来ているかのチェックの意味合いが強いが、店舗の意志や要望を本部に伝える機会でもある。
→ 業種
→ 本部
- レア - れあ
- 肉の焼き加減のひとつ。
特にステーキの焼き方で用いられる表現。表面だけを焼いて中心部は生に近い状態のことを指す。肉本来の旨みを楽しむには適しているが、万人向けではない。
→ 焼き加減
→ ミディアム
→ ウェルダン
- レイアウト - れいあうと
- 小売店の現場では、売場レイアウトとは売場の見取り図であり、図面によって作業をするメンバーに指示を出す意味合いが強い。
棚割り図、平面図など各種いろいろな形式があるが、商品の陳列・発注・商品加工などメンバーがそのレイアウト(= 指示書)に基づいて作業をする。
→ 陳列
→ 発注
- 冷暗所 - れいあんしょ
- 温度が低く、直射日光が当たらない場所。
具体的な温度帯表示等の既定は、法律上は特に制定がない。
- 冷しゃぶ - れいしゃぶ
- スライスした豚肉(または牛肉)を熱湯にくぐらせてから、冷やした生野菜と一緒に盛り付けて、ドレッシング状のタレをかけて食べる夏向きの料理。
野菜をたくさん摂取できるのがメリット。
→ しゃぶしゃぶ
→ 温しゃぶ
→ 焼きしゃぶ
- 冷蔵 - れいぞう
- 食品の鮮度維持の為に冷やすこと。
JAS法での温度帯は、10℃以下のことを指す。
5℃以下のチルドとは区別される。
→ 要冷蔵
→ チルド
→ 冷凍
- 冷凍 - れいとう
- 肉塊の中心部分まで凍結状態となり、この状態が保持されていること。
→ 生
→ チルド
→ 冷蔵
→ 解凍
- レジ袋 - れじ ぶくろ
- スーパー等で買物をした時に、以前は無料でもらえた袋の事。
→ ガゼット袋
- レディース・デー - れでぃーす・でー [業界用語]
- パートタイマーさんだけで運営する日のこと。
小規模な店舗において、社員が所定の休日を取得する為に、パートタイマーと呼ばれる主に女性労働者のみで店舗運営をする日のこと。
→ パートタイマー
- レッド・オーシャン - れっど・おーしゃん - Red Ocean
- 競争が激しく、主に価格を下げて競い合う状態を指す。消費者にとっては短期的には良い事の様に見えるかもしれないが、長期的に見て小売業という企業が健全な形で存続出来ない可能性の高い状態は、あらゆる意味で異常である。
→ ブルー・オーシャン
- レバー - ればー - liver
- 肝臓のこと。食肉業界においては、牛・豚・鶏などの肝臓のことをレバーと呼ぶ。
日本の料理では、レバニラ炒め・ヤキトリのレバーが有名である。
栄養学的には鉄分や葉酸を多く含み、貧血や妊婦に良いとされている。
フォアグラは、人為的に作られたガチョウのレバー料理のことである。
→ 肝臓
→ フォアグラ
→ マンナンレバー
→ やきとり
→ レバ刺し
→ 生レバー
- レバ刺し - れば さし
- レバーを加熱調理せずに生で食する事 又は その料理名を指す言葉。
食品衛生上の見解から、鮮度に係わらず 現在においては レバーを加熱せずに 生で食べるのはダメである。
→ レバー
→ 生レバー
→ マンナンレバー
- レホーネ - れほーね
- 西洋わさびのこと。
→ ホースラディッシュ
- ロース - ろーす
- 肉の部位の一つ。
肩から腰にかけての背肉であり、やわらかくて美味しい。
英名では ロイン (loin) である。
ロースの語源は ロースト (roast) に適した肉という事からの和製語とされる。
→ リブロース
→ サーロイン
→ 部位
→ ロースト
- ロースト - ろーすと - roast[英]
- 肉などをオーブンなどで直火で焼くこと。またはあぶり焼きにすること。
調理方法の一つで、かたまり肉や骨付き肉などを調理することを指す場合が多い。
コーヒー豆を煎ることもローストという。
- ローストチキン - ろーすと ちきん - roast chicken[英]
- 鶏を丸ごと焼いた料理。
日本ではほぼクリスマスのディナーの一品とされるが、西洋では七面鳥が使われることが多い。
食べる時に切り分けるのに少々のコツがいるが、丸焼きは旨みが逃げにくく肉はジューシーで、皮の部分は香ばしく、美味しく食べられ、しかも贅沢な感じを演出することが出来る。
→ 七面鳥
→ 鶏
- ローストビーフ - ろーすと びーふ
- 牛肉のブロック肉を蒸し焼きにした料理のこと。薄くカットして食べる。
調理された肉汁を元にして作られるグレイビーと呼ばれるソースとともに、ホースラディッシュなどの薬味とともに食べると美味しい。
日本ではクリスマスや父の日などのごちそうディナーとして食される機会が多い傾向にある。
日本の食品衛生法という法律においては、「特定加熱食肉製品」という分類に定義され、その安全性について厳しく管理されている。
→ グレイビー
→ ホースラディッシュ
→ 生食
- ロースハム - ろーす はむ
- 豚のロース肉を主原料とした加工食品のこと。現在の日本においてハムと言えばこのロースハムの事を指す事が普通である。
小売店においては薄くスライスされた形態の物がパック詰めされて販売されている事が多い。
→ ハム
- ローレル - laurel(英語) - ろーれる
- 月桂樹の葉を乾燥させた物。香りが爽やかで豊かであり、シチューなどの煮込み料理に使用すると、肉の臭みを消す効果がある。
→ 月桂樹
→ スパイス
- ローリエ - laurier(フランス語) - ろーりえ
- ここではローレルを参照して欲しい。
→ 月桂樹
→ スパイス
→ ローレル
- ロス - ろす
- 損失のこと。利益や在庫が何らかの理由により減る、もしくは無くなる事を指す言葉。
小売業界においては、値下げ等による 売価修正ロスや、万引き等による 品減りロスという概念がある。
それらとは別に、売上機会損失という意味合いでの、チャンスロスという概念もある。
→ 逆ロス
→ ロスリーダー
→ チャンスロス
- ロスリーダー - ろす りーだー
- 損をしてでも販売する商品(アイテム)の事を指す。
小売店においては、集客を図る為に無理な特売をかける事もある。
その商品(アイテム)においては損であっても、小売店全体として プラスにする為の知恵と工夫である。
広告料として置き換えて、集客を図りたいとの意味も込められている。
→ 特売
→ ロス
- YTS - わい てぃー えす
- 某小売企業にて一時期スローガンの様に使用された言葉。「よって、たかって、やる システム」の略語なんだそうな。みんなで盛り上げようよ、という意味なのか。
- 若牛 - わかぎゅう
- 乳用種牛(主にホルスタイン牛)で、食肉用に専用に肥育した概ね24ヶ月齢以内から生産された牛肉のこと。(社)全国肉用牛振興基金協会の登録商標である。
⇒⇒ (社)全国肉用牛振興基金協会 (リンク集)
- 若鶏 - わかどり
- その名の通り、若い鶏のことを指す。
出生後3ヶ月のことを指す。
食肉用として大量生産される 鶏肉は ブロイラーが代名詞である。
→ 鶏肉
- 和牛 - わぎゅう
- 日本人の好みに合わせる為に様々な工夫や努力が積み重ねられている。
国産牛という表示からは区別される 別格の表示である。
とてもやわらかで 濃厚な旨味は、一度食べたら忘れられない味として人々の記憶に刻まれる程の価値があり、ここぞ というごちそうメニュー (お祝い・記念日・年末・正月など) として、是非とも味わっていただきたい畜種・品種である。
日本の法律では「和牛」という表示を使用出来る定義は かなり厳しく定められており、品種においては「黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種」の4品種のみで、なおかつ 日本国内で出生・肥育されたものに限定される。(食肉の公正競争規約、農林水産省 食肉表示のガイドライン)
また、これらは 専門的な用語の分類として 肉専用種として位置付けられる。
→ 牛肉
→ 国産牛
→ 黒毛和牛
→ 肉専用種
→ 品種
→ 銘柄牛
⇒⇒ 全国食肉公正取引協議会 (AJMIC) (リンク集)
- 割り下 - わりした
- すき焼きのたれの事。醤油をみりんや他の調味料で割ったもの。割った下地ということから割り下と呼ばれる。
→ すき焼き
- ワンタン - わんたん - 雲呑
- 肉や魚介類を細かくした餡を具材として、小麦粉の皮に包んでスープにして食べる中華料理のこと。
→ 水餃子
|