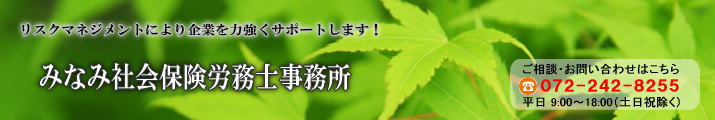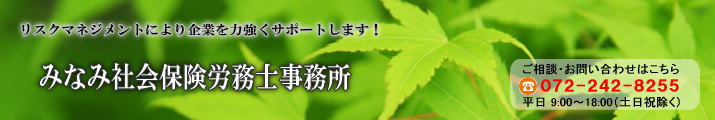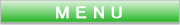
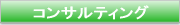
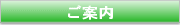
|
����������
��590-0079
���{��s���V��5-32
�V���r��504
TEL�F072-242-8255
FAX�F072-242-8256
|
|
|
|
|
HOME > �A�ƋK���E�e�Г��K�� > �A�ƋK���Ɋւ���Q&A
�P�D�u�A�ƋK���v�Ƃ͉���
���J�������̏ڍׂ�E��Ŏ��ׂ��K�������߂������̂��ƁB
�P�D�A�ƋK���Ƃ́H
�@�A�ƋK���Ƃ́A�J�������̏ڍ���A�E��ɂ����Ď��ׂ����[�������߂������̂��Ƃ������܂��B�����̘J���҂��ٗp���A���̖ړI�ɉ����ĘJ��������ɓ������āA���ʂ̘J���������߁A���炷�ׂ����[�����߂Ă������Ƃ͏d�v�ł��B
�@�����ŘJ����@�́A�펞10�l�ȏ��̘J���҂��g�p����g�p�҂ɁA�A�ƋK���̍쐬�`�����ۂ��Ă��܂��B
�@�쐬�����A�ƋK���́A�������J����ē����ɓ͂��o���ƂƂ��ɁA���Y���Ə���J���҂Ɏ��m���Ȃ���Ȃ�܂���B
�Q�D�A�ƋK�������̏d�v���́H
�@�E��ɂ����ĘJ��������E�ꃋ�[�����ɂ��Ă̗������H���Ⴂ�A���ꂪ�����ƂȂ��ăg���u�����������邱�Ƃ��悭����܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ�h�����߂ɂ́A�J�����Ԃ�����Ȃǂ̘J�������������K���Ȃǂ��A�ƋK���ɂ͂�����ƒ�߁A�J���҂ɖ��m�Ɏ��m���Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@�A�ƋK���ɒ�߂�ꂽ���e�́A�������e�������I�Ȃ��̂ł������A�P�Ȃ�E�ꃋ�[�����āA�X�̘J���҂Ǝg�p�҂Ƃ̊Ԃ̌_����e�ƂȂ�܂��B
�@�E��œ����J���ґS���ɑ��ēK�p����郋�[����J���������A�A�ƋK���Ɉꊇ���Ē�߂ēK�p���邱�Ƃɂ��A�J���҂̓���I�E�W�c�I�ٗp�Ǘ����\�ƂȂ�A���Ǝ�ƘJ���҂̖�ł̖��p�̑����𖢑R�ɖh�����Ƃ��ł��܂��B
�R�D�A�ƋK���̍쐬�`��
�@�A�ƋK���ɒ�߂Ă����ׂ������ɂ��ẮA�K����߂鎖���Ƃ��ĘJ��@89���ɗ���Ă���J�����ԁE�x�e�E�x���E�x�ɁA�����A�ސE�Ɋւ��鎖��(���َ��R���܂�)�����u��ΓI�K�v�L�ڎ����v�ƁA���x��������ꍇ�ɂ͏A�ƋK���ɒ��Ă����ׂ��Ƃ���Ă����u���ΓI�K�v�L�ڎ����v�Ƃ�����܂��B
�@�O�q�̂Ƃ���A�A�ƋK���ɋK�肳�ꂽ���e�́A�g�p�҂ƌX�̘J���҂Ƃ̖�̘J���_��̓��e�ƂȂ邱�Ƃ���A�A�ƋK���̍쐬�ɓ������Ă��J���ґ��̈ӌ��悷�����Ƃ��`���t�����Ă��܂��B
�@���Ȃ킿�A���Y���Ə���J���҂̉ߔ����őg�D����J���g��������ꍇ�ɂ͂��̘J���g���A���Y���Ə�ɉߔ����g���������Ȃ��ꍇ�ɂ����Y���Ə�̉ߔ������\��������ӌ������Ȃ���Ȃ�܂���B
�@����Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ́A30���~�ȉ��̔����ɏ�����܂��B
�Q�D�A�ƋK���ƁA�@�߂�J������A�J���_��Ƃ̊W��
���@�߂�J������ɔ�����A�ƋK���̊Y�������͖����B�A�ƋK���Œ�߂��ɈႵ�Ȃ��J���������߂�J���_��̊Y�������͖����ƂȂ�܂��B
�P�D�A�ƋK���Ɩ@�߂Ƃ̊W
�@�A�ƋK���́A�@��(�@���A���߁A�ȗ߂��܂�)�ɔ����Ē�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@
�@���ɁA�J��@��Œ�����@���Ɉᔽ����A�ƋK���̓��e�́A���̕����ɂ��Ė����ƂȂ�A�����ƂȂ��������ɂ��ẮA�J��@���̊�ɂ�����ƂɂȂ�܂��B
�@�܂��A�J��@�̂悤�ɋ��s�I���́A�����I���͂̂Ȃ��@�K�Ɉᔽ���镔���ɂ��Ă��A�����Ǒ��ᔽ(���@90��)�Ƃ��Ė����ƂȂ�܂��B�s������(�����J���)�́A�@�߂ɒ�G����A�ƋK���̕ύX�𖽂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�Q�D�A�ƋK���ƘJ������Ƃ̊W
�@�A�ƋK���́A��L�̂悤�ɁA�@�߂ɔ����Ă͂����Ȃ����Ƃ͂������A���Y���Ə�ɂ��ēK�p������J������ɔ����Ă͂Ȃ�܂����B
�@�J������Ƃ́A�c�̌�����ʂ��ĘJ�g�����ӂ������e�����ʂɎ��܂Ƃ߂āA�o���������܂��͋L�����������������܂��B
�@�A�ƋK���̍쐬�`���͎g�p�҂ɂ���܂����A�g�p�҂��쐬�����A�ƋK�������A�J�g�o�����c�̌��E�J�g���c���̂����ō��ӂ����܂Ƃ߂��J������ɁA�A�ƋK���ɑ��ėD�z�������͂�F�߂Ă��܂��B
�@�������A�J������ɂ͘J���g�����̘J���������̑��J���҂̑ҋ��Ɋւ����ɂ��Ē�߂�����(�K�͓I����)�̂ق��ɁA�g���f���̑ݗ^���Ƃ������g�p�҂ƘJ���g���Ƃ̏W�c�I�J�g�W�Ɋւ�����(���I����)�������܂��B
�@�J��@92���̑ΏۂƂȂ�̂́A�A�ƋK���̓��e���J������̋K�͓I�����ɔ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B�s������(�����J���)�́A�J������ɒ�G����A�ƋK���̕ύX�𖽂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�R�D�A�ƋK���ƘJ���_��Ƃ̊W
�@�u�A�ƋK���Œ�߂��ɒB���Ȃ��J���������߂�J���_���́A���̕����ɂ��Ă͖����ƂȂ�B�����ƂȂ��������́A�A�ƋK���Œ�߂��ɂ���v
�@���̋K��ɂ��A�A�ƋK���́A���̐E��œK�p�����J�������̍Œ����߂������Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�@�Ⴆ�A�A�ƋK���ł̓p�[�g�^�C�}�[�̒���������1000�~�Ƃ��Ă����Ȃ���A�ʂɒ��������J���_��J�������ʒm���ł͎���900�~�Ƃ����ꍇ�ɁA���̃p�[�g�^�C�}�[������900�~�ō��ӂ��Ă����Ƃ��Ă��A�u�A�ƋK���̒�߂��ɂ��v�Ƃ����A�����I���͂ɂ��A����1000�~�Ō_�������������ƂɂȂ�܂��B
�@�t�ɁA�A�ƋK���ł͎���1000�~�Ƃ��A�ʂ̘J���_�ł́A����1100�~�Ƃ����ꍇ�ɂ́A����́u�A�ƋK���Œ�߂��ɒB���v�Ă���̂ŁA���̎���1100�~�̍��ӂ͗L���ƂȂ�܂��B
�@�܂��A�J���_��J�������ʒm���ɂ͋K�肪�����܂��A�A�ƋK���ɂ͋K�肪����Ƃ����������ɂ��ẮA�A�ƋK���̋K�肪�K�p����܂��B
�@�Ⴆ�A�J�������ʒm���ɂ͌��C�Ɋւ���K�肪�����Ȃ����A�A�ƋK���ɂ͌��C�Ɋւ���K�肪������Ƃ������ꍇ�ɂ́A�A�ƋK���̋K��Ɋ�Â��J���҂͌��C��u�`�������ƂɂȂ�܂��B
�R�D�A�ƋK���̍쐬�E�͏o�`��������u�펞10�l�ȏ�̘J���ҁv�Ɋ܂܂��J���҂͈̔�
�����Ј��A�p�[�g�^�C�}�[�A�����Ј������܂߂ē��Y���Ə�̍ݐЎҐ��ɂ��܂��B
�P�D�A�ƋK���̍쐬�E�͂��o�`���Ƃ�
�@�펞10�l�ȏ�̘J���҂��g�p����g�p�҂́A�J���҂̉ߔ����g���܂��͉ߔ�����\�҂̈ӌ�����)�A�J��@89������̓��e�̏A�ƋK�����쐬���A�����̘J����ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�ᔽ�����ꍇ�ɂ�30���~�ȉ��̔����ɏ�����܂��B
�@�������A�펞10�l�����̎��Ə�ł��A�ƋK�����쐬���邱�Ƃ͖]�܂����B���̏ꍇ�ɂ́A�g�p�҂͓͂��o�`�����܂���B
�Q�D�A�ƋK���̍쐬�P��
�@�A�ƋK���́A�����Ƃ��āA���Əꂲ�Ƃɍ쐬���邱�ƂƂ���Ă��܂��B
�@�����Ƃł����Ă��A�Ⴆ�A�����{�ЂƖk�C���̐�������Ƃł́A�Ζ������Ζ����e�����啝�ɈقȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@�A�ƋK���̓��e�ɁA���������E��E�Ɩ��̎��Ԃf�����邽�߂ɁA���Ə�P�ʂł̍쐬���`���t���Ă���̂ł��B
�R�D�u�펞�v�g�p����҂͈̔�
�@�A�ƋK���̍쐬�`��������̂́A���Y���Ə����펞10�l�ȏ�̘J���҂��g�p���Ă���g�p���ł��B
�@�펞10�l�ȏ���g�p.���Ă��邩�ۂ��͑O�q�̂Ƃ����ƒP�ʂł͂Ȃ��A���Ə�P���ł݂܂��B�܂��A�ғ��l���ł͂Ȃ��A�ݐЎҐ��Ŕ��f���܂��B
�@�u�펞�v�g�p���Ă���J���҂ɂ́A���ɗՎ��I�E�Z���I�Ȍٗp(�Ⴆ�ΔN���Z�[�����̕��������̗Վ��A���o�C�g��)�̏ꍇ�͊܂܂�Ȃ����A���͏펞�g�p�����Ƃ��ăJ�E���g���邱�ƂƂȂ��Ă���A�L���J���_��ł��邩�ۂ��͖₢�܂����B
�@����A�^�ɗՎ��I�ٗp�łȂ���Ώ펞�g�p����҂͈̔͂Ɋ܂߂܂��B
�@�u�펞10�l�ȏ�v�̘J���҂��g�p'���Ă��邩�ۂ��̔��f�ɓ������ẮA���Ј��͂������A�p�[�g�^�C�}�[�A�����Ј��A�_��Ј������܂߂ăJ�E���g���܂��B�ٗp�`�Ԃ̈ٓ��͖₢�܂���B
�@���������āA�p�[�g�^�C�}�[������A�_��Ј��ł����Ă��A�펞�g�p����Ă���҂ł���A�l���Ɋ܂߂ăJ�E���g���܂��B�܂��A�o���Ј���A�x�E���̎҂��ݐЎҐ��Ɋ܂߂Ĕ��f���܂��B
�@����ɁA�J��@41��2���̊Ǘ��ē҂��A�J���҂ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��̂ŁA�펞�g�p'�����҂Ɋ܂߂čl���܂��B
�S�D�h���J���҂ƏA�ƋK��
�@�h���掖�Ǝ傪�h���J���҂�����Ă���ꍇ�ɂ́A���̔h���J���҂͔h����Ƃ̊ԂŌٗp�W�ɂ͂Ȃ����߁A�h����̎��Ə�̏펞�g�p����J���҂͈̔͂ɂ͊܂܂�܂���B
�@�h���J�������K�p�����̂́A�h�������Ǝ�(�h����m)�̏A�ƋK���ł���B�h����Ђł́A�h�����̔h���J����������ȊO�̘J����(�Ⴆ�Ήc�ƒS���҂⎖������)�Ƃ����킹�ď펞10�l�ȏ��̘J���҂��g�p���Ă���ꍇ�ɂ́A�A�ƋK���̍쐬�`�����܂��B
�S�D�A�ƋK���ɂ́A��̓I�ɂǂ̂悤�ȍ��ڂ��L�ڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���
���J�����ԁE�����E�ސE�W�͕K����߂Ȃ���Ȃ�܂���B����ȊO�̎����ł��A�u��߂�����ꍇ�v(���x��݂���ꍇ)�ɂ͋L�ڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�P�D�A�ƋK���̐�ΓI�K�v�L�ڎ����Ƃ�
�J��@89���́A���Ɍf���鎖���ɂ��āA�A�ƋK���ɕK����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă��܂�(��ΓI�K�v�L�ڎ���)�B
�A�ƋK�����쐬����ɓ������ẮA
�@�n�ƁE�I�Ƃ̎����A�x�e����A�x���A�x���A�J���҂�2�g�ȏ�ɕ����Č�ւɏA�Ƃ�����ꍇ�ɂ����Ă͏A�Ǝ��]���Ɋւ��鎖��
�A����(�Վ��̒���������)�̌���A�v�Z����юx�����̕��@�A�����̒��ߐ肨��юx�����̎����A'�����Ɋւ��鎖��
�B�ސE�Ɋւ��鎖��(���ق̎��R���܂�)
���Ȃ݂ɁA�B�̑ސE�Ɋւ��鎖���̂����A�u���ق̎��R�v�ɂ��ẮA����16�N1��1���{�s�̉����J��@�ɂ����Đ�ΓI�K�v�L�ڎ����Ƃ���A�A�ƋK������̓I�ȉ��َ��R���L�����邱�Ƃ��`���t�����܂����B
�Q�D�A�ƋK���̑��ΓI�K�v�L�ڎ����Ƃ�
�@�J��@89���́A���Ə�ɂ����Ď��Ɍf���鎖���ɂ����u��߂�����ꍇ�v�ɂ́A�A�ƋK���ɋL�ڂ��邱�Ƃ��`���t���Ă��܂�(���ΓI�K�v�L�ڎ���)�B
�@�u��߂�����ꍇ�v�Ƃ́A�����̋K���݂���ꍇ�͂������A�s���̊��s(�J�g���s�A�J�����s)����K�Ƃ��Ď��{����Ă���ꍇ�ɂ��A�A�ƋK���ɋK���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������܂��B
�@���Ȃ킿�A�J�g���s��J�����s�A���K���A���L�ɊY������ꍇ�ɂ́A�A�ƋK���ɖ����K���݂��āA�J���҂Ɏ��m���Ȃ���Ȃ�܂���B
�A�ƋK�������ΓI�K�v�L�ڎ����́A
�@�ސE�蓖�̒�߂�����ꍇ�ɂ����ẮA�K�p�����J���҂͈̔́A�ސE�蓖�̌���A�v�Z����юx�����̕��@�A�ސE�蓖�̎x�����̎����Ɋւ��鎖��
�A�Վ��̒�����(�ސE�蓖������)����эŒ�����z�̒�߂�����ꍇ�ɂ����ẮA����Ɋւ��鎖��
�B�J���҂ɐH��A��Ɨp�i���̑��̕��S���������߂�����ꍇ�ɂ����ẮA����Ɋւ��鎖��
�C���S����щq���Ɋւ����߂�����ꍇ�ɂ����ẮA����Ɋւ��鎖��
�D�E�ƌP���Ɋւ����߂�����ꍇ�ɂ����ẮA����Ɋւ��鎖��
�E�ЊQ�⏞����ыƖ��O�̏��a�}���Ɋւ����߂�����ꍇ�ɂ����ẮA����Ɋւ��鎖��
�F�\������ѐ��ق̒�߂�����ꍇ�ɂ����ẮA���̎�ނ���ђ��x�Ɋւ��鎖��
�G���̂ق��A���Y���Ə�̘J���҂̂��ׂĂɓK�p����鎖��
�T�D�A�ƋK���ւ̋L�ڎ����̂����A���Ɂu���فv�Ɋւ����߂͂ǂ̂悤�ɂ���悢��
�����ق̋�̓I���R����ю葱���Ȃǂ��ڍׂɋK�肷��B
�P�D�A�ƋK���ɂ�������ق̎��R�̖���
�@�J��@89���́A�u�ސE�Ɋւ��鎖���v���A�ƋK������ΓI�K�v�L�ڎ����Ƃ��Ă��܂��B�����āA����16�N1��1���{�s�̉����J��@�ɂ��A���́u�ސE�Ɋւ��鎖���v�ɁA���ق̎��R���܂܂�邱�Ƃ����炩�ɂ���܂����B
�@����́A�J�g�����Җ�ɂ����āA���قɂ��Ă̎��O�̗\���\�������߂邽�߂ł���A���̉������ɂ́A���������ٌ����p�@�����J��@�ɋK�肳���ƂƂ��ɁA�J��@15�����J�������̖����ɓ������Ă��A���ق̎��R����ΓI�K�v�L�ڎ����Ƃ���܂����B
�Q�D���ًK��ɒ�߂Ă����ׂ�����
�@���قɊւ���K��ɂ��ẮA�J��@89���ł́A���ق̎��R�̖��m�������߂Ă��܂����A��ʓI�ɂ́A���قɂ��āA���ق̎��R�A���ٗ\���A���َ葱�������A�ƋK�����ɒ�߂邱�Ƃ������B
�@�u���ق̎��R�v�Ɋւ��ẮA�@������ق��֎~����Ă���ꍇ�����邽�߁A�K�艻����ɓ������Ă��A�����̖@���̒�߂ɒ�G���Ȃ����̂Ƃ��邱�Ƃ��K�v�ł���B
��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�Ȓ�߂���������B
�@�J���҂̍��ЁA�M���A�Љ�I�g���𗝗R�Ƃ������
�A�J���҂̋Ɩ���̕����A���a�ɂ��x�Ɗ���Ƃ��̌�30����̉��فB�Y�O�Y��̏������J��@65���̒�߂ɂ��x�Ƃ������(�Y�O6�T��[���ٔD�P�̏ꍇ��14�T��]�ȓ��A�Y��8�T��ȓ�)�Ƃ��̌�30����̉���
�B�J���҂��J����ē@�ւɐ\���������Ƃ𗝗R�Ƃ������
�C�J���҂������ł��邱�ƁA�����J���҂������A�D�P�A�o�Y���A�܂��͎Y�O�Y��̋x�Ƃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ������
�D�����J���҂��A�j���̋ϓ��ȋ@��E�ҋ��Ɋւ��鎖�Ǝ�̑[�u�ŕ�W�E�̗p�A�z�u�E���i�A����P���A���̕�����������ђ�N�E�ސE�E���قɌW��J�g�����ɂ��ēs�������J���ǒ��ɉ��������߂����ƁA�܂��͔z�u�E���i�A����P���A���̕��������A��N�E�ސE�E���قɌW��J�g�̕����ɂ��ēs���{���J���ǒ��ɒ���̐\��(��W�E�̗p�͒���̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ�)���������Ƃ𗝗R�Ƃ������
�E�J���҂��玙�x�ƁA���x�Ƃ���юq�̊Ō�x�ɂ̐\���o���������ƁA�܂��͂������擾�������Ƃ𗝗R�Ƃ������
�F�J���҂��J���g���̑g�����ł��邱�ƁA�J���g���ɉ������A�܂��͉������悤�Ƃ������ƁA�J���g���̐����ȍs�ׂ��������Ɠ��𗝗R�Ƃ������
�R�D���َ��R���ǂ̂悤�ɒ�߂邩
�@�A�ƋK���ɋK�肷����ق̎��R�̓��e�ɂ��āA�@�߂ɔ����Ȃ�����ɂ����ẮA���i�̐��G�͂���܂���B�������A�����J��@�ł́A�u���ق́A�q�ϓI�ɍ����I�ȗ��R�������A�Љ�ʔO�㑊���ł���ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�́A���̌����𗔗p�������̂Ƃ��āA�����Ƃ���v�ƒ�߂Ă���A����܂��ċK���݂��邱�Ƃ��d�v�ł��B
���L�ڗ၄
�恛����(���ʉ���)
�P�D�]�ƈ������̂����ꂩ�ɊY������Ƃ��́A���ق��邱�Ƃ��ł���B
�@�Ζ����т܂��͋Ɩ��\�����������s�ǂŁA����̌����݂��Ȃ��A���̐E���ɂ��]���ł��Ȃ����A�A�ƂɓK���Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�Ƃ�
�A�Ζ����������s�ǂŁA���P�̌����݂��Ȃ��A�]�ƈ��Ƃ��Ă̐E�ӂ��ʂ������Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�Ƃ�
�B�Ɩ���̕����܂��͎��a�ɂ��×{�̊J�n��3�N���o�߂��Ă����Y�����܂��͎��a�������.���ꍇ�ł����āA�]�ƈ������a�⏞�N�����Ă���Ƃ��܂��͎邱�ƂƂȂ����Ƃ�(��Ђ��ł���⏞���x�������Ƃ����܂ށB)
�C���_�܂��͐g�̂̏�Q�ɂ��ẮA�K���Ȍٗp�Ǘ����s���A�ٗp�̌p���ɔz�����Ă��Ȃ����̏�Q�ɂ��Ɩ��ɑς����Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�Ƃ��D���p���Ԓ��܂��͎��p���Ԗ������܂łɏ]�ƈ��Ƃ��ĕs�K�i�ł���ƔF�߂�ꂽ�Ƃ�
�E�恛�����ɒ�߂钦�����َ��R�ɊY�����鎖��������ƔF�߂�ꂽ�Ƃ�
�F���Ƃ̉^�c��̂�ނȂ�����܂��͓V�Ў��ς��̑�����ɏ������ނȂ�����ɂ��A���Ƃ̌p��������ƂȂ����Ƃ�
�G���Ƃ̉^�c��̂�ނȂ�����܂��͓V�Ў��ς��̑�����ɏ������ނȂ�����ɂ��A���Ƃ̏k���E�]���܂��͕���̕������s���K�v�������A���̐E���ɓ]�������邱�Ƃ�����ȂƂ�
�H���̑��O�e���ɏ������ނȂ�����������Ƃ�
�Q�D�O���̋K��ɂ��]�ƈ������ق���ꍇ�́A���Ȃ��Ƃ�30���O�ɗ\�������邩�A�܂��͗\���ɑウ�ĕ��ϒ�����30�����ȏ�̉��ٗ\���蓖���x�����B�������A�J����ē����̔F����đ恛�����ɒ�߂钦�����ق�����ꍇ����ю��̊e���̂����ꂩ�ɊY������]�ƈ������ق���ꍇ�́A���̌G��łȂ��B
�@���X�ق��������]�ƈ�(1�������Ĉ��������ٗp�����҂������B)
�A2�����ȓ��̊�����߂Ďg�p����]�ƈ�(���̊������Ĉ��������ٗp�����҂������B)
�B���p���⒆�̏]�ƈ�(14�ڂ��Ĉ��������ٗp�����҂������B)3��1���̋K��ɂ��]�ƈ��̉��قɍۂ��A���Y�]�ƈ����琿���̂������ꍇ�́A���ق̗��R���L�ڂ����ؖ�������t����B
�U�D�A�ƋK���̍쐬�E�ύX���̈ӌ�����̑ΏۂɁA�ߔ�����\�҂Ƃ��đI�o�ł���J���҂͈̔͂ƑI�o���@
���Ǘ��ē҂͑I�o�Ώۂ��珜�����B�I�o���@�́A���[�A���蓙�̕��@�ɂ�閯��I�Ȏ葱���ɂ��B
�P�D�ӌ�����`���Ƃ�
�@�g�p�҂��A�ƋK�����쐬�܂��͕ύX����ꍇ�ɂ́A���Y���Ə�ɘJ���҂̉ߔ����őg�D����J���g��������ꍇ�ɂ͂��̘J���g��(�ߔ����g��)�A���Y�g�����Ȃ��ꍇ�ɂ��J���҂̉ߔ������\�����(�ߔ�����\��)���ӌ����Ȃ���Ȃ�܂����B
�@�J��@2���́u�J�������́A�J���҂Ǝg�p�҂��A�Γ��̗���ɂ����Č��肷�ׂ����̂ł���v�Ƃ��ĘJ�������̘J�g�Γ�����̌������߂Ă��܂��B
�@�O�q�̂Ƃ���A�A�ƋK���́A�g�p�҂ɂ��̍쐬�`�����ۂ����Ă��܂����A���̘J�������̘J�g�Γ�����̌������A�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�ɓ������Ă��w�������Ƃ��ē����A�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�ɓ������Ă͘J���҂̒c�̓I�ӌ������Ƃ��`���t���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�쐬�E�ύX�����A�ƋK���̘J����ւ̓͂��o�ɓ������ẮA�ߔ����g���܂��͉ߔ�����\�҂̈ӌ����̓Y�t���K�v�ł��B
�Q�D���Y���Ə�́u�ߔ����v�Ƃ�
�ߔ����g������ы�������\�ґI�o�ɓ������Ắu�ߔ����v�Ƃ́A���Y���Ə�̍ݐЎ҂��Ȃ킿��ʏ]�ƈ��͂��Ƃ���Ǘ��E�A�p�[�g�^�C�}�[�A�A���o�C�g�A�����A�_��Ј��A�o���Ј����܂߂��J���҂̋������ɒB���Ă��邩�ۂ��Ŕ��f����B
�R�D�������g���Ƃ�
�@�ߔ����g���Ƃ́A���Y���Ə�̘J���҂̉ߔ����őg�D����J���g���̂��Ƃ������܂��B�ߔ����̍l�����͏�L�̂Ƃ���ł���A�J���҂�����I�Ɍ��������J���g���ł��邱�Ƃ�v���܂��B
�@�]�ƈ��̑唼���������Ă���]�ƈ��W�c�ł����Ă��A�Ј����e�r��̑�\�҂������I�ɉߔ�����\�҂ƂȂ邱�Ƃ͂ł��܂����B
�S�D�T������\�҂̗v���ƑI�o�葱��
�@�ߔ����g���������Ȃ����Ə�ɂ����ẮA�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�ɂ��Ă̈ӌ�������s�����Ƃ𖾂炩�ɂ��āA�ȉ��̗v���E�葱����������̂����A�ߔ�����\�҂�I�o���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�u�g�p�҂ɂ��w�����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�J���҂̉ߔ�����\�́A�J��@41��2���ɋK�肷��ē܂��͊Ǘ��̒n�ʂɂ����(������Ǘ��ē�)�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�@�J���҂̒c�̓I�ӌ����\���ɔ��f����Ȃ������ꂪ���邩��ł��B�����āA���[�A���蓙�̕��@�ɂ�閯��I�Ȏ葱���ɂ��I�o���ꂽ�҂łȂ���Ȃ�܂���B
�T�D�T������\�҂ւ̕s���v��舵���̋֎~
�@�g�p�҂́A�J���҂��ߔ�����\�҂ł��邱�Ƃ������͉ߔ�����\�҂ɂȂ낤�Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��ĕs���v�Ȏ�舵�������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�V�D�p�[�g�^�C�}�[�̏A�ƋK���̓p�[�g�^�C�}�[�̑�\�҂���ӌ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ���
���K�{�Ƃ܂ł͂����Ȃ����A�ӌ����������悤�w�߂�B
�P�D�ꕔ�̘J���҂ɓK�p�����A�ƋK���̍쐬�͉\��
�@�J��@89���Ɋ�Â��A�펞10�l�ȏ�̘J���҂��g�p����g�p�҂́A���Y���Ə�̂��ׂĂ̐l�ɉ��炩�̏A�ƋK�����K�p�����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���Ə�ɁA�ٗp�`�Ԃ̈قȂ鐳�Ј��A�p�[�g�^�C�}�[�A���������g�p���Ă���ꍇ�ɁA��̏A�ƋK���ł��ׂāv�̌ٗp�`�Ԃ̘J���҂��J�o�[����̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��ɏA�ƋK�����쐬���邱�Ƃ͉\�ł��邵�A�J���Ǘ���͂ނ���]�܂����Ƃ����܂��B
�@�ʒB(��63.3.14�150�A��11.3.31�168)���A���ꎖ�Ə�ɂ����āA�J��@3��(�ϓ��ҋ��̌���)�ɔ����Ȃ�����ɂ����āA�ꕔ�̘J���҂ɂ��Ă̂ݓK�p�����ʌ̏A�ƋK�����쐬���邱�Ƃ͍����x���Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
�@���̏ꍇ�ɂ́A�A�ƋK���̖{���ɂ����āA���Y�ʌ̏A�ƋK���̓K�p�ΏۂƂȂ�J���҂ɌW��K�p���O�K��܂��͈ϔC�K���݂��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�Ȃ��A���Ј��p�Ƃ͕ʓr�ɁA�p�[�g�^�C�}�[�A�ƋK��������A�ƋK�����߂��ꍇ�ł����Ă��A�������܂߂ĘJ��@89���̏A�ƋK���ƂȂ�̂ł����āA���ׂĂ�J����ɓ͂��o�邱�Ƃ��K�v�ł��B
�Q�D�ӌ�����`���ɂ���
�@�p�[�g�^�C�}�[�A�ƋK��������A�ƋK�����̈ꕔ�̘J���҂ɓK�p�����A�ƋK���Ɋւ��ẮA�J��@90��1���̉ߔ����g���܂��͉ߔ�����\�҂ւ̈ӌ�����ł́A�ΏۘJ���҂̈ӌ����\���ɔ��f�ł��Ȃ��ꍇ�����蓾�܂��B
�@�Ⴆ�A���Ј��݂̂�g�D����傫�ȘJ���g��A�������A���Y���Ə�̘J���҂̋�������g�D���Ă���悤�ȏꍇ�A���Y���Ə�̃p�[�g�^�C�}�[�A�ƋK��������A�ƋK�����쐬�E�ύX����ɓ������Ă��A�J���g��A�̑�\�҂̈ӌ����悪�`���t�����Ă��܂��B
�@�J���g��A�̑�\�҂͐��Ј��ł��邩��A���̃p�[�g�^�C�}�[�A�ƋK��������A�ƋK���̓��e���K�p�����킯�ł͂Ȃ����A�J��@��̎葱���Ƃ��Ă͂���ł悵�Ƃ���Ă��܂��B
�@�������A�J��@2���̘J�������̘J�g�Γ����茴�����炷��A���ۂɓK�p�ɂȂ�p�[�g�^�C�}�[������̈ӌ����悪�]�܂����B
�@�܂��A�p�[�g�^�C���J���@�Ɋ�Â��u�p�[�g�^�C���J���w�j�v�ł��A�u���Ǝ�́A�Z���ԘJ���҂ɌW�鎖���ɂ��ďA�ƋK�����쐬���A���͕ύX���悤�Ƃ���Ƃ��́A���Y���Ə��ɁA�Z���ԘJ���҂̉ߔ����őg�D����J���g��������ꍇ�ɂ����Ă͂��̘J���g���A�Z���ԘJ���҂̉ߔ����őg�D����J���g�����Ȃ��ꍇ�ɂ����Ă͒Z���ԘJ���҂̉ߔ������\����҂̈ӌ����悤�ɓw�߂���̂Ƃ���v�Ƃ��Ă��܂��B�Ȃ��A�����́A�����D�̂��̑��̈ꕔ�̘J���҂ɓK�p�����A�ƋK���Ɋւ��Ă��Y������ƍl�����܂��B
�W�D�J���ґ����ӌ����ɔ��Έӌ�����������A�����܂��͋L����������ۂ����ꍇ�̏A�ƋK���̌���
�����Έӌ��⏐�����ۂ̏ꍇ�ł��J��͎����܂����A������̌��̖͂��͕ʁB
�P�D�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�ɓ������Ă̈ӌ�����`��
�@�g�p�҂��A�ƋK�����쐬�܂��͕ύX����ꍇ�ɂ́A�ߔ����g���܂��͉ߔ�����\�҂̈ӌ������A�ӌ����L��������(�ӌ���)��Y�t���ď����̘J����ɋ����o�Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�A�ƋK���̓͂��o�ɓY�t���ׂ��ӌ����́A�J���҂��\����҂̏����܂��͋L������̂�����̂łȂ���Ȃ�܂���B
�Q�D�u�ӌ����Ȃ���ΐc��Ȃ��v�Ƃ�
�@�J��@90��1���́u�ӌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ́A���������Ƃ����Ӗ��ł����āA�J���҂̒c�̓I�ӌ������߂�Ƃ������Ƃł���B
�@���ӂ�Ƃ��A���c�̂������肷��Ƃ����Ƃ���܂ŗv��������̂ł͂Ȃ��Ɖ�����Ă��܂��B
�@���Ȃ킿�A�ߔ����g����ߔ�����\�҂̈ӌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̕\�����ꂽ�ӌ��ɍS������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����킯�ł��B
�@�������A�J���҂̒c�̓I�ӌ��d���ׂ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�Ȃ��A�J������ɂ����āA�u�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�ɂ��Ă͘J���g���̓��ӂčs���v�u�J���g���Ƌ��c�̂������肷��v�Ƃ��������ӖȂ������c����߂��Ă���ꍇ�ɂ́A�P�ɘJ���g���̈ӌ����݂̂Ȃ炸�A���ӂȂ������c���o�Ȃ��ōs��ꂽ�A�ƋK���̍쐬�E�ύX�͖����Ƃ���܂��B
�R�D�J���ґ������Έӌ�����������A�����܂��͋L����������ۂ����ꍇ
�@�ʒB(��24.3.28�373)�́A�u�A�ƋK���ɓY�t�����ӌ����̓��e�����Y�K���ɑS�ʓI�ɔ�������̂ł���ƁA���蕔���Ɋւ��Ĕ�������̂ł���Ƃ��킸�A�����̔��Ύ��R�̔@�����킸�A���̌��͂̔����ɂ��đ��̗v��������������A�A�ƋK���̌��͂ɂ͉e�����Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B
�@�܂��A�g�p�҂��ӌ������ƔF�ߓ���̂ɏ\���Ȏ�i��s�����Ă���ɂ�������炸�A�J���ґ����ӌ����ɏ����܂��͋L����������Ȃ����Ƃ�����܂��B
�@���̂悤�ȏꍇ�ɂ��ẮA�u�J���g�����̈ӂɈӌ���\�����Ȃ��ꍇ���͈ӌ����ɋL�����Ȃ��ꍇ�ł��A�ӌ��������Ƃ��q�ϓI�ɏؖ��ł������A���������悤�戵��ꂽ���v�Ƃ̒ʒB(��23.5.11�735�A��23.10.30�1575)������܂��B
�@�������A�����́A�J��@�ᔽ�Ƃ��Ď�舵�����ۂ��̍s�����Ǒ��̌����ł����āA���ۂɁA�쐬�E�ύX���ꂽ�A�ƋK���̌��͂��ŏI�I�ɔ��f����͍̂ٔ����ł��B�A�ƋK���̌��́A���ɘJ�������̕s���v�ύX���̌��͂Ɋւ��ẮA�ٔ���ɂ����ẮA�J���ґ��Ƃ̋��c�E�����A�c�̌��̌o�ܓ������f�v�f�Ƃ��ďd������Ă��邱�ƂɁA���ӂ���K�v������܂��B
|
|