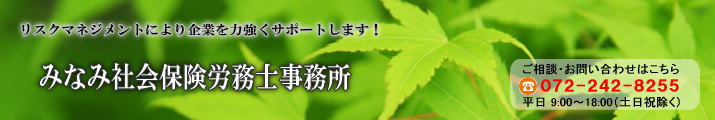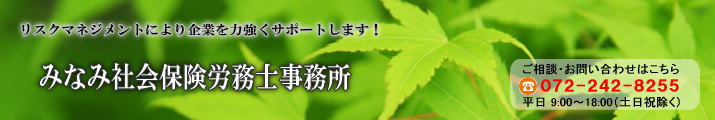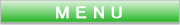
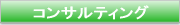
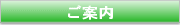
|
����������
��590-0079
���{��s���V��5-32
�V���r��504
TEL�F072-242-8255
FAX�F072-242-8256
|
|
|
|
|
HOME > ���N�ی��E�����N���ی�
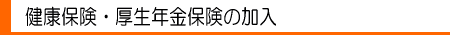
�����N�ی���
�@�J�Еی����Ɩ���i�ʋΏ�j�̕ی����̂ɑ��ĕی����t���s���̂ɑ��A���N�ی����Ɩ��O�̕ی������ɑ��ĕی����t���s���܂��B
�P�D�K�p����
�@���A�n�������c�̖��͖@�l�̎��Ə��ł������펞1�l�ȏ��̏]�ƈ����g�p������́A�K�p�Ǝ�ł���l�����ł������펞5�l�ȏ��̏]�ƈ����g�p������̂ɓK�p����܂��B�i�K�p�Ǝ�ł���l���Ƃł����ď펞5�l�����̏]�ƈ����g�p������́A��K�p���Ƃł���l���Ƃ͐l���ɌW��炸�C�ӓK�p���Ə��ƂȂ�܂��j
����K�p�Ǝ�Ƃ́�
�@�_�ыƁA���Y�ƁA�{�Y�Ɠ��̑�1���Y�Ƃ̎���
�A�����X�A���e�X�A�G�X�e�e�B�b�N�T�������̗��e�E���e�̎���
�B�f��̐��얔�͉f�ʁA�����A���̑����Ƃ̎���
�C���فA�����X�A���H�X���̐ڋq��y�̎���
�D�ٌ�m�A�ٗ��m�A���F��v�m�A�ŗ��m�A�Љ�ی��J���m���̖@���̎���
�E�_�ЁA���@�A����̏@���̎���
�Q�D��ی���
�@�K�p���Ə��Ɏg�p�����ҁB
���@�l�̑�\������A�������@�l�Ɏg�p�����҂Ƃ��Ĕ�ی��҂ɂȂ�܂��B�l���Ǝ�͓K�p���O�B
���K�p���O�ƂȂ�ҁ�
�@�D���ی��̔�ی��ҁi���a�C�ӌp����ی��҂������j
�A�Վ��Ɏg�p�������ŁA���X�ق����������i1�����Ĉ��������g�p�����Ɏ������ꍇ�A�������������ی��҂ƂȂ�j
�B�Վ��ɂ��悤�������ŁA2���̊������߂Ďg�p�����ҁi����̊��Ԃ��Ĉ��������g�p�����Ɏ������ꍇ�A�������������ی��҂ƂȂ�j
�C���Ə������ݒn����肵�Ȃ����̂Ɏg�p������
�D�G�ߓI�Ɩ��Ɏg�p�����ҁi��������p������4�����Ďg�p�����\��̏ꍇ�A���������ی��҂ƂȂ�B4�������̗\��ŁA�Ɩ��̓s�����ɂ�肽�܂���4�����Ă���ی��҂ƂȂ�Ȃ��j
�E�Վ��I�����̎��Ə��Ɏg�p�����ҁi��������p������6�����Ďg�p�����\��̏ꍇ�A���������ی��҂ƂȂ�B6�������̗\��ŁA�Ɩ��̓s�����ɂ�肽�܂���6�����Ă���ی��҂ƂȂ�Ȃ��j
�F�������N�ی��g���̎��Ə��Ɏg�p������
�G�ی��Җ��͋��ϑg���̏��F��������
�R�D��ی��҂̎��
�@��ʂ̔�ی��ҁi�K�p���Ə��Ɏg�p�����ҁj
�@���ٓ����ی���
�@�C�ӌp����ی��ҁi�K�p���Ə���ސE��A���̗v���������ҁj
�@����ސE��ی��ҁi���N�ی��g���ł��鎖�Ə���ސE�����ҁj
�S�D��}�{�҂͈̔�
�@��ی��҂̒��n�����A�z��ҁi�������܂ށj�A�q�A���A�햅�ł����āA��Ƃ��Ĕ�ی��҂ɂ�����v���ێ������
�A��ی��҂�3�e�����̐e���ŏ�L�@�ȊO�̎҂ł����āA���̔�ی��҂�����̐����ɑ����A��Ƃ��Ĕ�ی��҂ɂ�����v���ێ������
�B��ی��҂̔z��҂œ͏o�����Ă��Ȃ��������㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ�����̂̕���y�юq�ł����āA���̔�ی��҂�����̐����ɑ����A��Ƃ��Ă��̔�ی��҂ɂ�����v���ێ������
�C��L�B���z��҂̎��S��ɂ����邻�̕���y�юq�ł����āA�����������̔�ی��҂�����̐����ɑ����A��Ƃ��Ă��̔�ی��҂�����v���ێ������
����}�{�҂ƔF�߂��鐶�v�ێ��W�̔�����
�@�N�Ԏ�����130���~�����i60�Έȏ����͂����ނˌ����N���ی��@�ɂ����Q�����N���̎v���ɊY��������x�̏�Q���ł���ꍇ�ɂ�180���~�����j�ł����āA���A��ی��҂̔N�Ԏ�����2����1�����ł���ꍇ
�A��L�@�ɊY�����Ȃ����A��ی��҂̔N�Ԏ���������Ȃ��ꍇ�A���̐��т̐��v�𑍍̏��I�Ɋ��Ă��āA���Y��ی��������̐��т̐��v�ێ��̒��S�I�������ʂ����Ă����ƔF�߂���ꍇ
�B��ی��҂Ɠ���̐��тɑ����Ă��Ȃ��ꍇ�A�N�Ԏ�����130���~�i60�Έȏ㖔�͏�Q�҂�180���~�j�����ł����āA���A��ی��҂���̉����ɂ������z��菭�Ȃ��ꍇ
���N�ԔN���́A���I�N���⎸�Ɠ����t�ɂ��������܂݂܂��B
�����ꐢ�т̔�����
�@��ی��҂ƏZ���y�щƌv�������ɂ���҂������A����ːГ��ɂ��邩�ۂ����킸�A��ی��҂����ю�ł���K�v�͂Ȃ��B
���葱����́A�Z���[�Ŕ��f���܂��B
�T�D�ی������i����26�N3�����`�A���{�j
���{�Ǐ����N�ی��E�E�E10.06%
���ی����E�E�E1.72%
�U�D�ی����t�̎��
����ی��҂̎��́�
�@�×{�̋��t
�@���@���H���×{��
�@���@�������×{��
�@�ی��O���p�×{��
�@�×{��
�@�K��Ō�×{��
�@�ڑ���
�@���a�蓖��
�@������
�@�o�Y�玙�ꎞ��
�@�o�Y�蓖��
�@���z�×{��
�@���z��썇�Z�×{��
����}�{�҂̎��́�
�@�Ƒ��×{��
�@�Ƒ��K��Ō�×{��
�@�Ƒ��ڑ���
�@�Ƒ�������
�@�Ƒ��o�Y�玙�ꎞ��
�������N���ی���
�@�J���҂̘V��A��Q���͎��S�ɂ��ĕی����t���s���܂��B�����N���Ɠ��l�ɋƖ���O���킸�s���܂��B
�P�D�K�p�Ǝ�
�@���N�ی��Ɠ����i�A���A�����N���̂��D���ی��̔�ی������K�p���Ə��ƂȂ�j
�Q�D��ی���
�@�K�p���Ə��Ɏg�p�����70�Ζ����̎�
�@���̗v���͌��N�ی��Ɠ����i�A���A�����N���̂����ϑg���̑g���������K�p���O�ƂȂ�j
�R�D��ی��҂̎��
�@���R��ی��ҁi�K�p���Ə��Ɏg�p�����70�Ζ����̎ҁj
�@�C�ӒP�Ɣ�ی��ҁi�K�p���Ə��ȊO�̎��Ə��Ɏg�p�����70�Ζ����̎ҁj
�@����C�Ӊ�����ی��ҁi�V��N���̎���L���Ă��Ȃ�70�Έȏ�̎ҁj
�@�C�ӌp����ی���
�S�D�ی������i����26�N9�����`����27�N8�����j
��ʂ̔�ی��ҁE�E�E17.474%
�B�����E�D���̔�ی��ҁE�E�E17.688%
�T�D�ی����t�̎��
�@�V������N��
�@��Q�����N��
�@��Q�蓖��
�@�⑰�����N��
�@�E�ވꎞ��
���Љ�ی��̉����E�ی����̔[�t��
�P�D�Љ�ی��̐V�K����
�@�Љ�ی��i���N�ی��A�����N���ی��j�́A�K�p���Ə��ƂȂ���������������������5���ȓ����Љ�ی��������������N�ی��g�����V�K�K�p�͓����o���܂��B
���葱���́A���N�ی��ƌ����N�������ɍs���܂��B
�Q�D�Љ�ی��̎Z��
�@�Љ�ی��̕ی����́A���i�擾���Ɍ��肳�ꂽ�W����V���z�����Ƃ����N8�����܂œ����������������܂łɔ[�t���܂��B�i�Œ�I�����ɒ������ϓ����������ꍇ�A���̗v�������Ή��肳���ꍇ������܂��j
�@���N7��1�����ݔ�ی��҂ł���҂ɂ��āA4���`6���Ɏ����^�x�����z��W����V���z�����L�ڂ����u�Z���b�́v���Љ�ی����������͌��N�ی��g���ɒ�o���܂��B�����Ō��肳�ꂽ�W����V���z��9�����`���N8�����܂ŗp�����A�ی��������̕W����V���z�����ƂɌv�Z����܂��B
�@���̈�A�̍�Ƃ��u�Z��v�Ƃ����A���N7��1������7��10���܂łɍs���܂��B
 �@�l��ݗ��������葱����������Ȃ� �@�l��ݗ��������葱����������Ȃ�
 ���܂Ŏ���������Ă����]�ƈ������߂Ă��܂� ���܂Ŏ���������Ă����]�ƈ������߂Ă��܂�
�@�@��
 �A�E�g�\�[�V���O���������Ă���D�D�D�@�@�ȂǂȂ� �A�E�g�\�[�V���O���������Ă���D�D�D�@�@�ȂǂȂ�
|
 |
|
|