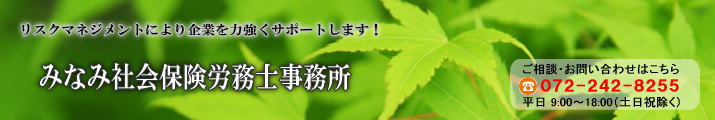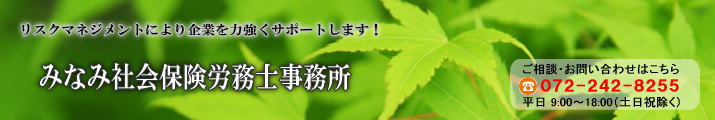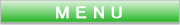
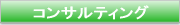
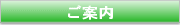
|
����������
��590-0079
���{��s���V��5-32
�V���r��504
TEL�F072-242-8255
FAX�F072-242-8256
|
|
|
|
|
HOME > ��������㗝

�P�D����Ȍo������܂��H
�@�ސE�����Ј�������e�ؖ��X�ւ��͂�����H
�@�J���҂Ƙb�������Ĕ[�����đސE���Ă�������͂��Ȃ̂ɁA�u���ٗ\���蓖�����x�����������A�x�����̂Ȃ��ꍇ�͖@�I��i���Ƃ�܂��v���Ăǂ��������ƁH
�@�m���ɘb������������ł��J���҂͓ˑR�̂��ƂŃr�b�N�����Ė�������炸�Ԏ������Ă��܂����Ƃ������悤�ł��B�������u�ސE�����߂�ꂽ�����فv�Ǝv���Ă��܂��̂ł��B
�@���e�ؖ��X�ւ͂����܂ňӎv�\���̈�̎�i�Ȃ̂ŁA�K���]���K�v�͂���܂���B�������A�ꍇ�ɂ���Ă������������i���ȂǂłƂ��Ƃ����肩������܂���̂ŁA��������̂ł͂Ȃ��A������x�b���������Ƃ��]�܂����ł��傤�B
�A�L���x�ɂ�S�ď������đސE�������Ɛ\���o�Ă������D�D�D
�J����@��̗L���x�ɂ́A
�u�L���x�ɂ�J���҂̐������鎞�G�ɗ^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�������ꂽ���G�ɗL���x�ɂ�^���邱�Ƃ����Ƃ̐���ȉ^�c��W����ꍇ�ɂ����ẮA���̎��G�ɗ^���邱�Ƃ��ł���B�|�J��@��39��43���|�v
�ƂȂ��Ă���A�g�p�҂ɂ����G�ύX��������܂��B
�@�������A���G��ύX�ł���̂͘J���`����������Ɍ����A�ސE���ȍ~�ɂ͕ύX�ł��܂���B�܂�A�������s�g�ł��Ȃ��̂ł��B�ސE���ɍ��킹�ėL���x�ɂ�\�������ƁA�@���̎�|���狑�ۂł��܂���B
�@���̂��߂ɁA�A�ƋK�������u�ސE���͋Ɩ��ɕK�v�͔͈͂ň��p���ɉ����邱�Ɓv�Ȃǂ��߂Ă����A���Ȃ��Ƃ����p���ɉ����Ȃ��J���҂ɂ͑Ή��ł��܂��B
�B���ԊO�J�������ۂ��ꂽ��H
�@���ԊO�J���́A�R�U�����������͂��o�Ă���A�A�ƋK�����u�Ɩ���̓s���ɂ���ނȂ��ꍇ�ɂ́A�R�U����ɂ�莞�ԊO�J���𖽂��邱�Ƃ�����v�|�̒�߂�����A���͈̔͂Ŏ��ԊO�J���𖽂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����J���҂����ԊO�J���̋`��������̂ɋ��ۂ����ꍇ�A�Ɩ����߈ᔽ�Ƃ������������̑ΏۂƂȂ�܂��B����ł��A�c�Ƌ��ۂ𗝗R�ɍŏI�I�ɒ������ق����P�[�X���L���Ƃ���Ă��܂��B
�@�������A�J���҂Ɏ��ԊO�J���ɉ������������R������Ƃ��ȂǁA�ނ�݂Ɍ������Ή�������̂��������̗��p�ƈ�����ꍇ������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�Q�D�����g���u�����N���Ă��܂�����H
�@�������N�A��Ƒg�D�̍ĕ҂�l���J���Ǘ��̌ʉ��ɔ����A�J���W�Ɋւ��鎖���ɂ��Ă̎��Ǝ�ƌX�̘J���҂Ƃ̊Ԃ̕������������Ă��܂��B����畴���̍ŏI�I�ȉ�����i�Ƃ��Ă��ٔ����x������܂����A���̂��߂ɂ������̎����������̔�p���K�v�ƂȂ�܂��B
�@������A�J�g�ԃg���u�����N�����Ă��܂����ꍇ�̉������@�Ƃ��ẮA�ٌ�m�Ɉ˗����ٔ��ʼn�����}��Ƃ����̂�����܂ł̎�i�ł����B
�@�������A����13�N10��1�������ʘJ�������������i�@���{�s���ꂽ���Ƃɔ����A����15�N4��1���̎Љ�ی��J���m�@�̉����ɂ��A�Љ�ی��J���m����������㗝�l�Ƃ������Ǝ��܂��́A�J���҂̑㗝�l�ɂȂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@�������������J�ōs���A�v���C�o�V�[�͕ی삳��܂��̂ň��S�ł��B
����������Ƃ́D�D�D��
�@�����҂̊ԂɊw���o���҂ł����O�҂�����A�o���̎咣��v�_���m���߁A�ꍇ�ɂ���ẮA���҂��̂�ׂ���̓I�Ȃ�������Ă����ȂǁA���������ҊԂ̒������s���A�b�����𑣐i���邱�Ƃɂ��A�����̉~���ȉ�����}�鐧�x�ł��B
�R�D��������葱�̗���
��������\���i�ʏ�͘J���҂��炳��܂��B���Ǝ傩��̐\�����\�B�j
�@��
���O�����̎��{�i�s���{���J���ǁj
�@��
��������̊J�n�E�s�J�n�̌���i�s���{���J���ǁj�E�E�E�ʏ킠������\��������1�T�ԑO��
�@��
���������ψ���ɂ�邠������E�E�E����1���A1�`2���Ԓ��x�ōs���܂�
�@��
���������E�E�E������́u�a���v�Ɠ��l�̌���
����
��������Ő襥��o���ɂ܂����������̈ӎu���Ȃ��A��1�`2�����̏������ԓ��ɑo���̍��ӂ������Ȃ��ꍇ
 �Z�N�n���Ȃǔ���J�ʼn��������� �Z�N�n���Ȃǔ���J�ʼn���������
 �v���ɉ��������� �v���ɉ���������
 ���܂��p���|�������Ȃ��D�D�D�@�ȂǂȂ� ���܂��p���|�������Ȃ��D�D�D�@�ȂǂȂ�
|
 |
|
|