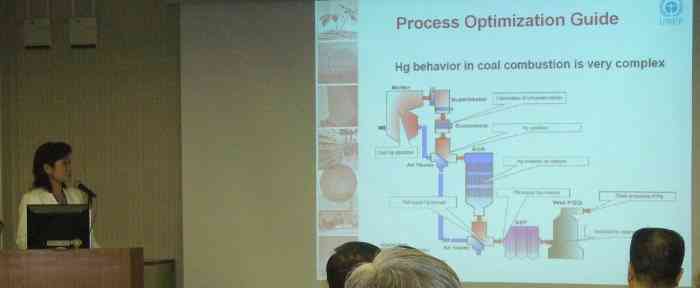|
UNEP 2011�N9��25���`28���@�_��
INC3_�A�W�A�����m�n���Q���� �F���ԁ@���@�i���w�������s��������j http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ �f�ړ��F2011�N9��29�� �X�V���F2011�N10��13�� �iNGOs/���Ȉӌ��������j�X�V ���̃y�[�W�ւ̃����N�F http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC3_AP_Kobe/110925-27_INC3_AP_Kobe.html �P�D�͂��߂� �Q�D�e�N�j�J���E�u���[�t�B���O �R�D�{��c�@�h���t�g�e�L�X�g�S36�����̌��� �S�DNGO �̖{��c�ɂ����锭�� �T�DNGOs/���Ȉӌ��������i�X�V�j �U�D���ۏ��֘A���� �P�D�͂��߂�
�@2011�N9��26���`28���A�_�ˍ��ۉ�c�� �Łu�����{�Ԍ��ψ����3���iINC 3�j�̏����̂��߂̃A�W�A�����m�n���v���J�Â���A9��26���ߑO�̃e�N�j�J���E�u���[�t�B���O�ƁA27���܂ł̖{��c�ɎQ�������̂ŁA���̊T�v����܂��B �@�܂��A9��27���̃����`�^�C���y�і{��c�I����̗[���A�Q�� NGOs �Ɗ��ȂƂ̊Ԃňӌ������������A�L�Ӌ`�Ȉӌ��������s�Ȃ��܂����B �@���A9��28���ŏI���͐��{��\�c�����ōs�Ȃ�ꂽ����J�Z�b�V�����ł����B �@��c�̔w�i�A�T�v�A���ʂȂǂɂ��ẮA���Ȃ̕��\��������23�N9��29���u�����{�Ԍ��ψ����3���̏����̂��߂̃A�W�A�����m�n���v�̌��ʂɂ��āi���m�点�j���������������B http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14266 ���g�p����F �@�p��i�{��c�j�A�p��/���{��i�e�N�j�J���E�u���[�t�B���O�j ����c�������F �@���L UNEP �E�F�u�T�C�g����ꕔ����\�B http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/RegionalPreparations/ AsiaPacificRegion/InformationforparticipantsAPmeeting/tabid/56159/Default.aspx ����c�i�s Mr. Teruyoshi Hayamizu (Japan): regional coordinator�i�n��R�[�f�B�l�[�^�j Mr. Muhammed Khashashneh (Jordan) and Mr. Xia Yingxian (China) bureau members for the region Mr. Fernando Lugris, Chair of the INC Mr. Per Bakken, Special Adviser, UNEP/Division of Technology, Industry and Economics ���Q�����F25�J�� Bhutan, Cambodia, China, Cook Islands, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Japan, Jordan, Kiribati, Kyrgyzstan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Singapore, Sri Lanka, Syrian Aran Republic, Thailand and Vietnam. ���I�u�U�[�o�[�F��ƊW�ҁA��w�W�҂Ȃ� ���Q��NGOs�F �@7�c��7�l�@�ʐ^������
�Q�D�e�N�j�J���E�u���[�t�B���O�i9��26���ߑO�j ��ꕔ�FUNEP ���E����p�[�g�i�[�V�b�v�E�v���O���� Part I: UNEP Global Mercury Partnership Programme (09:40-10:20)
1) Ms. Desiree Narvaez (UNEP Secretariat): �f�Y���[�E�i���o�G�c���iUNEP�����ǁj ���E����p�[�g�i�[�V�b�v�̊T�v�F�w�o���Ƌ��P�A�y�сA�A�W�A�����m�n��ɂ�����]�萅��̊��I�ɓK�ȊǗ��̂��߂̏C���I�v�V�������́j "Overview of the Global Mercury Partnership: Experiences and Lessons Learned" & �gRevised Options Analysis for the Environmentally Sound Management of Surplus Mercury in Asia Pacific�h 2) ��؋K�V ���m�i�������������^UNEP����A���^�������p�[�g�i�[�V�b�v�j �h����̗A���Ɖ^�������iUNEPMFTP�j�C�j�V�A�e�B�u�Ɛ���̉^���ƗA�����ɂ��Ă̊֘A�����h Dr. Noriyuki Suzuki (National Institute for Environmental Studies, Japan (As a member of the UNEP Partnership for Mercury Transport and Fate Research, lead by Dr. Nicola Pirrone, CNR Institute for Atmospheric Pollution, Italy)): "UNEP Global Partnership for Mercury Transport and Fate Research (UNEPMFTP) Initiative and Related Research on Mercury Fate and Transport issues" ��F���{�ɂ����鐅��Ǘ��̂��߂̌���Z�p Part II: Current Technologies for Mercury Management in Japan (11:00-12:20) 1) �R�� ���i���{�d���H�Ɖ�^�p�i�\�j�b�N������� ���C�e�B���O�Ёj �h�d�����̐���팸�Z�p�h Mr. Masanori Yamauchi (Japan Electric Lamp Manufacturers Association (Panasonic Corporation Lighting Company)) : "Technology for reducing mercury in lamps" 2) �^�疾�` ���i���{�\�[�_�[�H�Ɖ�^�N�������G���W�j�A�Y������Ёj �h������g�p���Ȃ��d�C�����Z�p�̊J���h Mr. Akiyoshi Manabe (Japan Soda Industry Association (Chlorine Engineers Corp., Ltd)): "Development of Electrolysis Technology without Mercury" 3) �H�� ���i���{�z�Ƌ���^�H�c���B������Ёj �h�H�c���B������Ђ̐���Ǘ����{�h Mr. Yoshito Kudo (Japan Mining Industry Association (Akita Zinc Co., Ltd.)): "Mercury Management Practice at Akita Zinc Co., Ltd." 4) �������l ���i���{�Y�Ƌ@�B�H�Ɖ�^�O�H�d�H������Ёj �h�����A�����j�E�������ɂ�鐅�⏜���V�X�e���h Mr. Tatuto Nagayasu (The Japan Society of Industrial Machinery Manufacturers (Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)): "Mercury Removal System with NH4Cl Injection" �R�D�{��c�@�h���t�g�e�L�X�g�S36�����̌����@�i9��26���ߌ�`27���j ����v�Ș_�_�̗��@�iUNEP�ɂ�����j
A. �O��
�S�DNGO �̖{��c�ɂ����锭�� �i9��26���ߌ�`27���ߑO�j �@NGO��7�l�S�����A�{��c�Ŕ������s�Ȃ��܂������A���̂������e�����ł������̂ɂ��Ĉȉ��ɏЉ�܂��B
�T�DNGOs/���Ȉӌ������� �i11/10/13�j�C�� �@�A�W�A�E�����m�n���ɎQ������NGO 7�c�́i7�l�j�́A9��27���i�j�����`�^�C���y�і{��c��̗[���A���ȁi�����ے��ȉ�4�l�j�Ɣ��ɗL�Ӌ`�Ȉӌ��������s�Ȃ����B
�@�E���ۓI�ȍ��ӂƂ̊W �@�E���{�̐���A�o/�ۊǂɂ��� �@�E����Y�����i�I�v�V����3 �@�E���u�̗A�o���� �@�E���₪�g�p����鐻���v���Z�X �@�E���Ƃ̍��ۖf�Ձi��4���j �@�E����Ƃ̍��ۖf�Ձi��5���j �@�E�`���C�i�E�m���y�[�p�[ �@�E���ۏ��֘A���� �����ۓI�ȍ��ӂƂ̊W NGO 1�F��1��bis�̃p���O���t1 "������͑��̏��ɂ����錠���Ƌ`���ɉe�����y�ڂ��Ȃ�"�́A �s�K�v��WTO�ً̈c�\�����Ă��������邱�ƂɂȂ�B���l�ȕ������X�g�b�N�z�������ł���Ă��ꂽ�����ۂ��ꂽ�BNGO�̓p���O���t2��"���̊֘A���鍑�ۓI����Ƒ��݂Ɏx�����������Ŏ��{����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�"�Ƃ��镶�����x������B���{��������x�����邱�Ƃ�]�ށB �����{�̐���A�o/�ۊǂɂ��� NGO 2�F���{�������A�o���Ă��邱�Ƃ͐��E�̂m�f�n�ɂ悭�m���Ă���BEU�y�уA�����J�͂��łɗA�o�֎~�����肵�Ă���B������̗v���ɂ�����炸�A���{������A�o���֎~����A�e���ɑ傫�ȃC���p�N�g��^����B���{���{�͂ǂ̂悤�ɍl���邩�H ���ȁF���̖��ɂ��Ă͉��x�������Ă��邱�Ƃł��邪�A�A�o�͐��������ׂ��ł���A�����͋��炭�A������̉��ɁA�X�g�b�N�z�������̂悤�Ȍ`�Ő�������A���I�ɓK�ȕۊǂƊǗ����Ȃ���邱�ƂɂȂ�B���{�̗]�萅��̑����͔�S�������B�v���Z�X����̂��̂ł���A���{�ł͂����Ђ���������ƓI�ɍs�Ȃ��Ă���B����̂��߂̃R�X�g�͐���A�o�ŃJ�o�[����Ă���A�A�o���֎~����Ɖ���̂��߂̃R�X�g�����ƂȂ�B�܂��A�o���֎~����Ɖ������̕ۊǂ̕K�v�������邪�A���{�ɂ͒n�k�A�䕗�Ȃǂ�����A�K�ȉi�v�ۊǏꏊ��T���̂�����A�Ǘ��ӔC�̖�������B����ɐ�����艻�ȂNjZ�p�̖�������B�����͐���A�o�֎~�^���������肷��O�ɋc�_����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ł���A2013�N�̐����ł̐�����̑��܂ł̎c���ꂽ2�N�ԂŌ��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͏��m���Ă���B����܂ł͗A�o�֎~�^�����ɂ��ĉ��Ƃ������Ȃ��B NGO 3�F���{�͍l�������Ăق����B�A�����J���i�v�ۊǎ{�݂͎����Ă��Ȃ��B���݂���̂�40�N�ʂ�ڏ��Ƃ���ꎞ�ۊǎ{�݂ł���A�ŏI�����ł͂Ȃ����A�A�o�֎~�����߂��BEU�ƃA�����J�̗A�o�֎~����ŁA����̎s�ꉿ�i�͏㏸���Ă���A���v�ጸ�ɍv�����Ă���B���{�͔N��150�g����A�o���Ă��邪�A���{�����E�̐��⋟���팸�̒��ԓ��������A�āA���A���Ő��E��50���߂����팸�ł���B�A�W�A�ł̑傫�Ȏ��v�͏��K�͋��̍z�iASGM�j�ł���B�����͐���Y���Ă��邪�A�o�͂��Ă��Ȃ��B���{�̏́A�A�����J�̋��̍z���ɕ��Y���Ƃ��Đ��₪������Ɣ��ɂ悭���Ă���B���{���Ƃ肠�����A�����J�Ɠ��l�Ɉꎞ�ۊǂ��l����悢�̂ł͂Ȃ����H�ۊǂɗv����]�萅��ʂ��X�y�[�X���傫���Ȃ��B ���ȁF���{����̈ꎟ�A�����͕����邪�A���������̓A�����̓���͓���B���≿�i�㏸�́A�]�萅��̗A�o�ɉe����^���Ă��邩������Ȃ����A�A�o�ʂ͉��i�����ł͂Ȃ��A�ɗʂ���v�ɂ��ˑ�����悤�ł���B�Ȃ��A�I�y���[�V�����͘A���ł͂Ȃ��o�b�`�ł���ƕ����Ă���B�Ƃ���ŁA�A�����J�̐���A�o�֎~�@�Ăɂ��Ē��ׂ��̂ŁA���₵�������Ƃ�����B���̖@�ẮA�����̏ؖ����icertificate�j������ΗA�o�ł���̂�����A�^�̐���A�o�֎~�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����H NGO 3�F���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B����͗A�o�֎~�ɂ�����Ə��v���Z�X�ł���A���Ɍ��肳��Ă���B�A�����́A���ɋ��������Ȃ��A�K�ɊǗ�����AASGM�Ɏg�p����邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�Ə��̊��ԂƗʂ����肳��Ă���B�A�����J�̗A�o�֎~�@�Ă͎����N�������B ���ȁF�Ə��̈Ӑ}�����Ɍ���I�ł��邱�Ƃ͗��������B NGO 1�F�A�o�^�ۊǂ̖��ɂ��Č��_���o���̂ɁA�ǂ̂悤�ȃ^�C�����C�����l���Ă���̂��H���\�͂ǂ̂悤�ɍs�Ȃ��̂��H ���ȁF���{�̗A�o/�ۊǖ��ɂ��ē����ł̌������n�߂Ă��邪�A���������𑱂���K�v������B�R�X�g�A�Z�p�A�ꏊ�̖��Ȃnj������ׂ������̑��ʂ�����A���A������b���̂͂܂���������B�i�ݕ������ɒx���̂͏��m���Ă��邪�A���̖��̏d�v���͏\���ɔF�����Ă���B�c�_�𑬂߁A2012�N�x���ɂ͏��ւ̉��炩�̑Ή���������K�v������Ǝv����B����͗A�o/�ۊǖ�肾���ł͂Ȃ����̖��������ł���B2012�N�x���ɂ͌��J�̏�ŋc�_���邱�ƂɂȂ�Ǝv���B�ŏI�����2013�N�̊O����c�̑O�ɍs���A�@�I�Ȍ��_���������ƂɂȂ邪�A���Ȃ��Ƃ��R�X�g����A�Z�p�A�ꏊ�A�{�݂ȂǂɊւ���T�v�ɂ��ẮA���S�ł͂Ȃ��Ă�INC 5�O�Ɏ������Ƃ��K�v�ł���B�A�o���𐧌�����X�g�b�N�z�������̌o��������̂ŁA����Ɠ��l�ȓ��e���t�H���[���邱�Ƃ͉\�ł��邪�A����ȏ�̂��Ƃ������悤�Ƃ���ƁA���{�����ŋc�_���K�v�ƂȂ�ł��낤�B�A�o�֎~�Ƃ����Ăѕ��ɂȂ�̂��ǂ����ۏ͂ł��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��X�g�b�N�z�������̂悤�ȗA�o�����ɂ͂Ȃ�ł��낤�B�Ƃɂ����A���{�͂��ׂ����Ƃ͂��̂ŋ}�����Ȃ��łق����B ������Y�����i ��3���I�v�V����3 �y���z�F��3���I�v�V����3�́A����i���A(1) �֎~�A(2)�i�K�I�p�~�A(3)�K�{�p�r��3�̃J�e�S���[�����ĊǗ�����Ƃ������e�ł���A�_�ˉ�c�ł͑����̍����^�ӂ����������AZMWG�͔����Ă���BNGO�́A�I�v�V����2�i�l�K�e�B�u�E���X�g�E�A�v���[�`�j���x�����Ă���B NGO 3�F�I�v�V����3�ɂ�3�̖�肪����B1�Ԗڂ̖��́A��4�߂Ɏ������悤�ɁA(1) �֎~�A(2)�i�K�I�p�~�A(3)�K�{�p�r�̏ڍׂ��A���������ǂɒ�o������ĂɊ�Â��A"����c�iCOP�j�����肷��"�Ƃ��������ł���B����͐��{�Ԍ��ψ���iINC�j�Ō��肳���ׂ��ł���BCOP�͑����̒�Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���̌���ɂ͉��N��������ł��낤���A10�N��������Ȃ��B2�Ԗڂ̖��́A���i�̃J�e�S���[�Ԃ̈ړ��Ɋւ���ڍׁ^�菇�����܂��Ă��炸�A���̈ړ�������Ƃ������Ƃł���B3�Ԗڂ̖��́A�܂��N���J�e�S���[���̐��i���Ă��Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ̐��i���c�_�����̂�������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B ���ȁFZMWG�̌����͑��̍��ɂ��C���v�b�g���Ă���̂��H NGO 3�F����A�W�A��c�⑼�̒n���ł��Љ�Ă���B �����u�̗A�o���� �y���z�F ��6�� ���i �I�v�V����1�@��4�߂̋L�q [4. �e���́A���̏��̉��ɁA���p�\�ȍŗǂ̋Z�p�Ƃ��ē��肳��鑕�u�̏ꍇ�������āA���̏��̂ǂ̂悤�Ȕ���ɑ��Ă��AAnnex C �Ƀ��X�g����Ă��鐅��Y�����i�����邽�߂̑��u�̗A�o�������Ă͂Ȃ�Ȃ��A���́AAnnex C �Ƀ��X�g����Ă��鐅��Y�����i�����邽�߂̑��u�̂��߂̕⏕���Aaid credit�A�ۏؖ��͕ی��v���O��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B] ��7�� �v���Z�X�@��6�߂̋L�q [6. �e���́AAnnex D �Ƀ��X�g����Ă���ǂ̂悤�Ȑ����v���Z�X�ł̎g�p���Ӑ}����Ă���@��̗A�o�������Ă͂Ȃ炸�A�܂��A����v���Z�X�ւ̈ڍs�̈ꕔ�Ƃ��Ċ����̎{�݂ɂ����鐅��r�o�̒ጸ��ړI�Ƃ���ꍇ�������āA���̂悤�ȋ@��̂��߂̕⏕���Aaid credit�A�ۏؖ��͕ی��v���O���������̏��̂ǂ̂悤�Ȕ���ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B] NGO 3�F��X�́A����Y�����i�����邽�߂̑��u������ɗA�o����邱�Ƃ�]�܂Ȃ��B���l�ȋL�q���A��7�� �v���Z�X ��6�߂ɂ�����B�����́A�{���Ɋ܂܂��ׂ��ł���B ���ȁF������g�p����v���Z�X����肷�邱�Ƃ͗e�Ղł��낤���A������g�p���鑕�u����肷��͎̂��ۂɂ͓���̂ł͂Ȃ����H�@������ɂ��Ă�NGO�̎w�E�ɂ��Ă͗��ӂ���B �����₪�g�p����鐻���v���Z�X �y���z�F��7���@����g�p�v���Z�X�̂��߂̋��e�p�r�Ə��Ɋւ�3�̑�Ă���1�߂Œ�Ă���Ă���B�I�v�V����1�́A�|�W�e�B�u�E���X�g�E�A�v���[�`�ł���A�Y������v���Z�X��Annex D�Ƀ��X�g����Ă���B�I�v�V����2�́A�l�K�e�B�u�E���X�g�E�A�v���[�`�ł���A����͑�8���̉��ɋ��e�p�r�Ə�����v���Z�X�������āA�S�Ẵv���Z�X���ň�ʓI�ɐ���͋֎~�����B�I�v�V����3�́A'�֎~'�A'�p�~'�A'�K�v�s��'�̃v���Z�X�����X�g���邱�Ƃ��Ă��Ă��邪�A���i�Ɋւ��铯�l�Ȓ�Ă̂悤�ɁA��̓I�ɂ͉�����Ă���Ă��Ȃ��B NGO 3�F�����̉��r���m�}�[�����iVCM�j�v���Z�X�Ɋւ��A�v���Z�X�Ɋւ����7���ɂ͊�{�I�ɂ�3�̃I�v�V���������邪�A���e�p�r�Ə��ɂ͖�肪����BNGO�Ƃ��Ă̓I�v�V����2�i�l�K�e�B�u�E���X�g�E�A�v���[�`�j���]�܂����B ���ȁFVCM�͒����ŗL�̖��Ȃ̂Ŏ戵��������B���{�͊�{�I�ɂ͐���g�p�v���Z�X���g�p���Ă��Ȃ��̂ŁA�v���Z�X�ɂ��ăI�v�V����2�͓��{�ɂƂ��Ė��Ȃ��ł��낤���A�����ɂ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��BNGO�̎w�E�ɂ��Ă͗��ӂ���B �����Ƃ̍��ۖf�Ձi��4���j�i11/10/13�j NGO 3�F��4���2�߂ł́A��������A�o���邽�߂ɂ́A���1�́A"�A�������珑�ʂɂ�鎖�O���ӏ��ƗA���͋K�肳�ꂽ�ړI�̂��߂����ł��邱�Ƃ������ؖ���������Ă���"���Ƃ����߂Ă���B�������A���2�́A"�����A�o�������̂悤�ȍ��ӏ������߂�Ȃ�A�A�����̏��ʂɂ�鎖�O���ӂ�����Ă���A�܂������@�����̂��Ƃ����߂���́A���̖@�������������ǂɒ�o���Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�����ǂ͂�������c�ɓ`�B���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�"�Ƃ��Ă���B�������A���̑��2�͐��{������̗A���ɓ��ӂ���v������߂�̂ŁANGO�͎�����Ȃ��B ���ȁF���1�Ƒ��2�̈Ⴂ�͉����H NGO 3�F���1�͕��ՓI�ȁiuniversal�j�v���ł���A��ɋ��߂��邪�A���2�͕��ՓI�ȗv���ł͂Ȃ��A�A�o���̖@���Ɉˑ�����B ���ȁF��X�Ƃ��ẮA�f�Վ葱���ɂ��ẮA�S�Ă̗A�o���ɍ��ӏ��iconsent�j�Əؖ����icertification�j��K�v�Ƃ���̂͏d�����S�iheavy burden�j�����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���邪�A������ɂ�������{�̎��s���Ɖ^�p�Ɏ��{�\���̗��ʂ��l�����Č�������K�v������ƍl���Ă���B��4���2�ߑ��1�̂悤�Ȃ����ŁA�A�������ASGM�ł̎g�p���~�߂�̂ɏ\���ł���Ǝv�����H NGO 3�F����́A�������鑤�̊Ǘ��̖�肾�B ���ȁF�A�o���̐��{�Ƃ������Ƃ��H�@�A�����ɊǗ��ӔC������̂ł͂Ȃ����H NGO 3�F�Ⴆ�A100�g���Ƃ����ʂ̃A�}���K���Ȃ�A����A�o��������͂��������ƃ`�F�b�N�ł���B ���ȁF�ꎟ�A�o��Ȃ����ł��邪�A�A�o��̓���͓���B�Ⴆ�A�V���K�|�[������l�X�ȓA�o��ɑ�����ł��낤���A�ꎟ�A�o�������̃t�H���[������͓̂���B NGO 1�F�ꎟ�A�o���͐ӔC��A�o���ɃV�t�g�ł���B NGO 4�F�ЂƂ̗�Ƃ��āA�C���h�l�V�A�ł͗A����������Ă���A���Ǝ҂�1�`2�Ђ����ł���B ���ȁF����ł́A�C���h�l�V�A�ł͗A�������ASGM�ł͎g���Ȃ��Ƃ������Ƃ��H NGO 4�F�����ł͂Ȃ��B�s���icorruption�j���s�Ȃ��Ă��邵�A�ʊւł̌��E������B NGO 1�F�C���h�l�V�A�̗�ł��A�u���b�N�E�}�[�P�b�g�̑��݂�����B�u���b�N�E�}�[�P�b�g�͋K���ł��Ȃ��B ������Ƃ̖f�Ձi��5���j�i11/10/13�j NGO 3�F��5���̕����ł͔���Ƃ̖f�Ղ͗e�ՂƂȂ�B���̗��R�́A��2�߂��������Ă���A���̑�2�߂͎����I�ɑ�1�߂̗v�����ɂ��邩��ł���B��2�߂͉����������Ă��Ȃ��B��2�߂̉��ł́A��{�I�ɂ͂ǂ̂悤�ȗp�r�̐���ł�����Ɩf�Ղł��邱�ƂɂȂ�B ���ȁF���{�̊�{�I�ȗ���Ƃ��ẮA�K�Ɏ��{�\�ȗA�o�Ǘ����x�����邱�Ƃ��d�v�ƍl���Ă���B���炭��1�߂Ƒ�2�߂̊Ԃɉ��炩�̐߂��Ă��ׂ��ł��낤�B�X�g�b�N�z�������̏ؖ����icertification�j�Ɋւ�������̂悤�Ȃ��̂�t��������̂���Ă�������Ȃ��B NGO 3�F���̒ʂ肾�B��������Ƃ̖f�Ղ�]�ނȂ�A���̂悤�ȕ����邱�Ƃ��`���Ƃ��ׂ����B NGO 1�F�X�g�b�N�z�������ɂ������Ăɉ����āA�o�[�[�����̗v����K�p���邱�Ƃ��ł���B���Ȃ킿�A���Ɣ���̖f�Ղ́A���̉��ɓ��ꃌ�x���̋K���ɏ]���ׂ����B ���`���C�i�Y�E�m���y�[�p�[�i11/10/13�j �y���z�F�n���Ɍ����Đ�����ɑ��钆���̃A�v���[�`���������L���A���t�Ȃ��̉��L�����i1�t�j�����\����܂����B China's Non-paper: Explanatory Note on the Menu-Order Approach to the Implementation of the Instrument �@���̃y�[�p�[�ɂ��Ă�NGO�^���Ȃ̈ӌ��������s�Ȃ��܂������A���e�����G�Ȃ̂ŁA�����ł͋c�_�̓��e�͏ȗ����A�m���y�[�p�̓��{�ꉼ������L�Ɏ����܂��B �`���C�i�Y�E�m���y�[�p�[
���̎��{�ɑ��郁�j���[�����A�v���[�`�Ɋւ���������� China's Non-paper: Explanatory Note on the Menu-Order Approach to the Implementation of the Instrument ����F���ԕ��^���w�������s�������� �T �@�I���� �@������Ɋւ�����Ɍ�����^����UNEP ���c 25/5�ŋK�肳��Ă���悤�ɁA��28�߂�"���{�Ԍ��ψ���Ɏ��̂��Ƃ��l������悤���߂Ă���B
�@���̊J���͎��{��ړI�Ƃ��Ă���A���������Ď��{�͏��̒��j���Ȃ��B �@������́A���E�̋��ʂ̒���ł��邪�A���ɂ́A�ꎟ�̍z�A����Y�����i�A�v���Z�X�A�p���������Ȃǂ��܂ށA���鍑�ɂƂ��Ă̓���̖��ł���B����`���̋K���ƊǗ����S�Ă̍��ɓK�p�\�Ȃ�A�قȂ鍑�̓���̏��l�������ׂ��ł���B �@���̓����́A�J���r�㍑�ɂ��@�I�ɍS���͂̂���`���̎��{�����ƋZ�p�I�x���̗��p�\������ł���Ƃ������Ƃł���B �@���Ǝ��{�v��̒�o�́A���̎��{�Ə���𑣐i���邱�Ƃ��ł������Ɗ֘A����ł��낤�B �V���̃A�v���[�`�̉^�p �����Ǝ��{�v��iNIP�j�̊J�� �@�e���́A�����̓���̏��l�����A������"���j���[�����A�v���[�`�imenu-order approach�j"�ƌĂ����̕����̒��ʼnʂ������ׂ��`�����J�o�[���A���{�v����J�����邱�Ƃ��]�܂��B�Ⴆ�A����p�����Ɋ֘A������肾��������������Ȃ����ɂ��ẮA�{���A����p�����̏����ɓ����������{�v�悪�J�������ł��낤�B���g�ނׂ��L���͈̖͂�������鍑�ɂ��ẮA���{�v��͂��̍������S�Ă̖����J�o�[���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@���̓_�ɂ��āA���{�v������グ�邽�߂̎�����Ƃ��āA�ЂƂ̃e���v���[�g���J������A����c�iCOP�j�ɂ���Ďx�������ł��낤�B���̃e���v���[�g�́A���j���[�Ƃ��Ă̖�ڂ��ʂ����A�e���͂��̂悤�ȃ��j���[���Q�Ƃ��Ď����̎��{�v����쐬����ł��낤�B���̃��j���[�́A�@�I�S�������Ɣ�S�������̗������J�o�[����S�Ă̋`���̕�I�ȑg�ݍ��킹�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��낤�B �����Ǝ��{�v��iNIP�j�̃��r���[�Ə��F �@���Ǝ��{�v��iNIP�j�́A���r���[�̂��߂ɋZ�p�o�ϐ��ƃO���[�v�iTEEG�j�ɒ�o����ATEEG�́A����c�iCOP�j�ɍŏI���r���[�Ə��F����������ł��낤�B���Ǝ��{�v��iNIP�j�̒��ŁA�@�I�S���͂̂���`���̂��߂ɁA�^�C�~���O�E�X�P�W���[���A�K���ڕW�A�\�Z�Ȃǂ��܂ލs���v��ƂƂ��ɁA���ɂ���ċ��߂���v�f���J�o�[����ł��낤�B����c�iCOP�j�ɂ���č��Ǝ��{�v��iNIP�j�����F�����A�X�P�W���[���Ɋ�Â��ڕW�ɂ���Č��܂�@�I�S���͂̂���`���̎��{�̂��߂̊���������ɏ��F�����ł��낤�B �U�D���ۏ��֘A���� �i11/10/13�j 1. �X�g�b�N�z�������
|