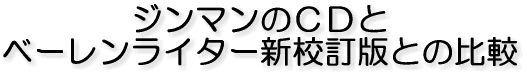
「モダン楽器によるベーレンライター新校訂版に基づく世界初録音」がうたい文句の、デイヴィッド・ジンマンによるベート−ヴェン全集の第3弾、第3番と第4番のカップリングがついに発売になりました。前作が出たときに第3番について予言したことがぴったり当てはまっていたので、ちょっぴりコワイ気もします。しかも今回はあの予想をさらに上回るようなとんでもないことをやってくれているので、感慨もひとしおです。
ちなみに、現時点で出版されているベーレンライター版は1.2.3.8.9.の5曲です。したがって、ジンマン盤と比較できるのは第8番とこの第3番だけということになります。
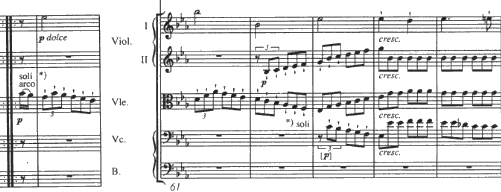 |
| ※ベーレンライター版(BA 9003)の84-85ページより転載 |
ヴィオラとチェロのsoliという表示は、一人で弾くのではなく、そこが単独のメロディーであることを表わしているというのが、校訂者デル・マーの見解でした。ところがジンマンは前作の交響曲第8番では同じような箇所を一人の奏者に演奏させていたので、きっとここでも“solo”にするだろうというのが私の予言でした。
しかし、ジンマンは私のそんな予言をあざ笑うかのように、もっととんでもないことをしでかしてくれました。ヴィオラとチェロはおろか、なんとヴァイオリンまでも“solo”にしているのです。
正直に告白しますと、わたしはジンマンの演奏は大好きなんです。しかめっ面ではないスッキリと風通しの良いベートーヴェン像はオリジナル楽器だけではなくモダン楽器でも再現出来るのだということを、この演奏で実証した功績は偉大です。今回とりあげた「エロイカ」の第3楽章トリオのホルン3重奏の軽快さなどは、まさに目から鱗が落ちる思いでした。
ところが、私が問題にしたいのは「ベーレンライター新校訂版を使っている」と明言していながら、ベーレンライター版の通りには演奏していないという点です。なかには第2楽章の241小節で1拍目おもての十六分音符にスラーをつけるとか、第4楽章の213小節のフルートの上昇音からスラーを取るとか、素直にこの新改訂版の指示に従っているところもあるのですが、これまでさんざん見てきたように、肝心のところではデル・マーの意向にそむいて好き勝手なことをやっているのです。もちろん、オーボエの装飾や上の音から始めるトリルなどは、時代的な習慣として容認は出来ますが、「これはやらない方が良い」と言っていることをこれだけしつこくやっているのでは、これはもうベーレンライター版とは縁もゆかりもない「ジンマン版」とでも呼ぶしかないわけです。ですから、いっそのこと「ジンマン版に基づく世界初録音」というキャッチコピーにでも変更して、自分の解釈で信じた道を堂々とすすんで行っ てくれれば、な〜んにも問題はないのです。それにしても、ライナーノーツまで書いている校訂者のジョナサン・デル・マーは、いったいどんな思いでこのCDを聴いたのでしょうね。