|
|
|
|
![]()
���y�̂��߂̃A�q�[�W���B ���v�ԛ{
 �^�C�g���́u�T�[�N���\���O�v�Ƃ����̂́A�`���R�b�g��2003�N�Ƀo�[�~���K���̍����c�̂��߂ɍ��A2004�N�ɏ�������Ă���̂ł����A�����2019�N�ɉ������A���N�Q���ɂ��̉��������̃R���T�[�g�ƕ��s���Ă��̃��R�[�f�B���O���s���܂����B ���̋Ȃ́A���������Ǝ��������A�����ăs�A�m�Q��ƂS�l�̑t�҂ɂ�鐔�����̑Ŋy��Ƃ����Ґ��ō���Ă��܂��B�e�L�X�g�́A�A�����J�̐�Z�������̎����A�p��ɖ����̂��g���Ă��܂��B�����́A�`���R�b�g�ɂ���đI��āA�������Ɓu�a���v�A�u�c�����v�A�u���l�v�A�u���l���v�A�u�s�N���v�A�u�V�N���v�A�u���v�Ƃ����V�̕����ɐU�蕪�����Ă��܂��B �������́A�����ɂ��ȃq�[�����O������Ղ�̖L���ȃn�[���j�[�̋ȂŁA�e�B���p�j���A�N�Z���g�����Ă��܂��B �u�a���v�́A�T���q�̃��Y�~�J���ȋȂŁA�~�j�}�����A�}�����o��{���S�ŕ������悤�Ȋ����A���̌�ɁA�A�E�J�y���ŃR���[�����̋Ȃ������܂��B �u�c�����v�́A�܂��g���u���̍������A�L���L�������s�A�m�ƑŊy���BGM�ɏ���ĉ̂��܂��B�����ɁA��͂菭���̃\�����A�ƂĂ��i�C�[�u�Ȗ������A�Ō�͐Â��ȗ͂��������L���b�`�[�ȍ��������Œ��߂������܂��B �u���l�v�ł́A���q���t�̓��������Y�~�J���ȋȂł݂�Ȃɏj������钆�A�����������Ƃ�Ƃ�������������܂��B �u���l���v�́A��͂蚒�q���t�̓��������Ղ葛���̂悤�ȃG�l���M�b�V���ȋȂł��B�Ŋy�킪�劈��B �u�s�N���v�ł́A�[�݂̂���R���[�����A�Ŋy��̃A�N�Z���g���o�b�N�ɉ̂��܂��B �u�V�N���v�́A�����g�̂悤�ȃ��H�J���[�Y���o�b�N�ɁA�Â��ȃ��V�A�����̃R���[��������܂��B �u���v�́A�܂������̃\�����̂�ꂽ��A�����悤�ȃA�E�J�y��������܂����A�₪�đŊy��Ɛ���オ��A�Ō�́uWe shall live again�v�Ƃ����̎��ŁA�Â��ɏI���܂��B�����ɂ́A���҂͂₪�Đ��܂�ς��Ƃ����u�T�[�N���v�̎v�z������Ă��܂��B �J�b�v�����O�Ƃ��āA1990�N��̏I��育��A�`���R�b�g����Ƀg���u���̂��߂̋Ȃ��W���I�ɍ���Ă������̂S�̍����Ȃ��̂��Ă��܂��B�ŏ��̂R�Ȃ̓g���u���̂��߂̋ȁA�}���A���i���w������g���u���̍����c���̂��܂��B�V���R�y�[�V�����ɂ�郊�Y�~�J���ȁuLike A Rainbow�v�A�V�q�̐��E�ςɂ��[���ȃe�L�X�g������������f�B�ŕ�uAll things pass�v�A�����ĂƂĂ��L���b�`�[�ȁuCircles of motion�v�ƁA���ꂼ��ɖ��͓I�ȋȂ��A�q��̂Ȃ����Ŋ��\�ł��܂��B �Ō�́A��l�̍����c�ɂ�鉉�t�ŁA�X�[���́u�_���Ȕ����v�Ƃ���Ă���T�̌��t���e�L�X�g�ƂȂ��Ă���uWalking the red road�v�ł��B�܂�Ń��Q�e�B�̂悤�ȃN���X�^�[���o�b�N�ɁA�L���b�`�[�ȃ����f�B���[���n�[���j�[���ĉ̂���A�����������̂���Ȃł��B ���̂�����̋Ȃ̂��߂̃e�L�X�g��T���Ă���ԂɁA�`���R�b�g�́u�T�[�N���\���O�v�̍\�z���Ђ�߂����̂������ł��B�m���ɁA���̃A���o���S�̂ɂ́A�e�L�X�g�ɂ����y�ɂ��A�����炩�Ń|�W�e�B�u�ȃe�C�X�g�Ǝ��R���h���S���Y���Ă��܂��B����́A�p���f�~�b�N�ł̍�����A�卑��遂�ɂ��d���Ȃǂ�ڂ̓�����ɂ��Ă��A���̉���������������Ȃ�����l�����������̂悤�ɒ������܂��B CD Artwork © Signum Records |
||||||
���̋Ȃ́A�V���X�^�R�[���B�`�̌����Ȃł͍ł��Ґ����傫���̂������ł��B�Ƃ͌����Ă��A����Ȋy�킪�g���Ă���킯�ł͂���܂��A�؊NJy��̓N�����l�b�g�����͂S�l�K�v�ł����A���̑��͂R�l���ő��v�ł��B�l���������̂͋��NJy��B���ʂ̕Ґ��ɁA���ǂ����̃o���_�ł����10�l�K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�����ɁA�n�[�v���Q��Ƀs�A�m�������܂����A�Ŋy������ɑ����A�t�҂͂V�l�K�v�ł��B�����Č��y����A��ȉƂ̎w��ł̓t�@�[�X�g���@�C�I�����͍Œ�16�l�A�\�ł����20�l�ƂȂ��Ă��܂��B�R���g���o�X�ł��Œ�W�l�A�ō���12�l�ł��B�ł�����A���ꂾ���̐l�����A���ׂĎ��O�Řd����I�[�P�X�g���́A���E���T���Ă�������قǂ�������܂���B �����h�������y�c�́A�I�[�P�X�g���̃����N�Ƃ��Ă͏�ɐ��E�̃g�b�v10�̒��ɂ͓����Ă��܂����A�l���I�ɂ́A�Ⴆ�x�������E�t�B���Ȃǂɂ͂��Ȃ萅���������Ă��܂��B�Ȃ��āA�t�@�[�X�g���@�C�I�����̐��������o�[��14�l�������Ȃ��̂ł�����ˁi�x�������E�t�B����21�l�j�B�NJy����A�x�������E�t�B���̂悤�ɂ��ꂼ��̃p�[�g�Ŏ�ȑt�҂��Q�l���Ƃ����ґ�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��āA�P�l�̎�ȑt�҂��S�v���O�����ʼn��t���Ȃ�������܂���B �ł�����A���̘^���ł��A���y��t�҂͑S���o�����Ă���悤�ł����A����ł��V���X�^�R�[���B�`�̎w��ɂ͑���Ă��܂���B�NJy��ł́A�؊ǂ͉��Ƃ��Ȃ�܂����A���ǂł͑�ʂ̃G�L�X�g�����ق��Ă��܂��B�����Ƃ��A���ǂɊւ��ẮA���̋Ȃ��G�L�X�g���Ȃ��ʼn��t�ł���I�[�P�X�g���́A���E���T���Ă��قƂ�ǂ���܂���B���{�ł́A�ł��T�����ƌ����Ă���NHK�����y�c�ł��A�����ł��B�n���̃A�}�`���A�I�[�P�X�g���Ȃǂł́A���y��͔����̓G�L�X�g���ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�ˁB ����ȕҐ��ł�����A�R���T�[�g�ł̃_�C�i�~�b�N�����W�́A�ƂĂ��傫�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̘^���̏ꍇ�A�Ȃ̖`���͂قڃ}�b�N�X�߂��̉����Ŏn�܂�܂�����A�����ł��܂�₩�܂����Ȃ�������Ń{�����[����ݒ肷��ƁA�s�i�Ȃ��n�܂����Ƃ��ɍŏ��̃X�l�A�E�h�����⌷�y��̃s�`�J�[�g���S���������Ȃ��Ȃ��āA�����������Ȃ��̂łǂ��Ȃ����̂��ȁA�Ǝv���Ă���Ƃ����Ȃ�t���[�g���������Ă���A�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B���Ƃ����āA���ꂪ�������邮�炢�ɐݒ肵�Ă����ƁA���̍s�i�Ȃ̍Ō�ŋ��ǂ̃o���_���o�Ă���Ƃ��ɂ́A�܂��Ɏ������قǂ̑剹�ʂɑς��Ȃ�������܂���B �u�o���_�v�Ƃ����̂́A���I�œ�����Ȃ��ƌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������i����́u�p���_�v�j�ł͂Ȃ��A�I�[�P�X�g���̖{�̂Ƃ͕ʂ̏ꏊ�ʼn��t�����y��Q�̂��Ƃ��w�����t�ł��B���̃R���T�[�g���s��ꂽ�����h���̃o�[�r�J���E�Z���^�[�̓X�e�[�W���v���Z�j�A���̒��ɂ���̂ŁA������͂ނ悤�ȃo���R�j�[�͂Ȃ��̂ł����A�T���E���h�Œ����Ă���Ɩ��炩�ɃX�e�[�W�̋��ǃZ�N�V�����Ƃ͕ʂ̏ꏊ����o���_���������Ă��܂��B���ꂾ���̂��ƂŁA��ȉƂ��Ȃ����̂悤�ȕҐ��ɂ����̂����A�ƂĂ��悭�����ł��Ă��܂��܂��B ���̋Ȃ̒��ł́A�NJy��̒����\�����p�ɂɏo�Ă��܂��B�����́A���ɂ͉��t�҂ɂƂ��Ă͂قƂ�Ǎ���̂悤�Ɋ������邱�Ƃ�����قǂł��B����ɑς��āA�����ɂ��̃\���𐁂������l�ɂ́A�S���甏��𑗂肽���Ȃ�܂��B ����Ȓ��ŁA��Q�y�͂Ƀt���[�g�Q�{�ƃA���g�E�t���[�g�Ƃ����A�����炭�V���X�^�R�[���B�`�͂��������Ŏg�����g�ݍ��킹�łׂ̍��������̃��Y���ɏ���āA�o�X�E�N�����l�b�g�̂�͂蒷��ȃ\�����p�ӂ���Ă��܂����A���ꂾ���͂��܂薾�Ăɂ͒������Ȃ������̂��A�ɂ��܂�܂��B SACD Artwork © London Symphony Orchestra |
||||||
�����̓���y��́A�����Ƃ����I�[�P�X�g���ł͂�����̐l�������o�[�ɂȂ��Ă��܂��B�x�������E�t�B���̏ꍇ���ƁA�I�[�{�G��1�Ԃ̃p�[�g�𐁂���ȑt�҂�2�l�A2�Ԃ̃p�[�g�𐁂��l��2�l�A�����ăR�[���E�A���O�����P�l�A�Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��B �����āA���݂̃R�[���E�A���O���t�҂��A����̃A���o���̎�l���A�h�~�j�N�E���H�������F�[�o�[�ł��B �ނ̕��e�́A�o�C�G���������̌���̃I�[�P�X�g���̃R�[���E�A���O���t�҂ł����B�������A�ނ��X�̎��ɍŏ��ɑI�y��̓I�[�{�G�ł͂Ȃ��t���[�g�ł����B�����āA14�ɂȂ������ɃI�[�{�G�ɓ]�����܂��B���e�́A�������Ɣނ̂��߂Ƀ��[�h������Ă��ꂽ�����ł��B�₪�Ĕނ́A�N���E�f�B�I�E�A�o�h�̎w������EU���[�X�nj��y�c�̎�ȃI�[�{�G�t�҂ƂȂ�A�����ɃJ�������E�A�J�f�~�[�ł��A�����̎�ȑt�ҁA�V�F�����x���K�[�Ɏt�����܂��B�����āA1994�N�Ƀx�������E�t�B���̃R�[���E�A���O���t�҂̃I�[�f�B�V�����ɍ��i���A����ăx�������E�t�B���̒c���ƂȂ�܂����B��������͋����Ċ�����ł��B �x�������E�t�B���̉f�������Ă���ƁA�ނ��\�������t���鎞�̃A�b�v�Ȃǂ́A�Ȃɂ��S�C����قǂ̋ٔ������`����Ă��܂��B�����ɂ́A�܂�ō�ȉƂ̍����h�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����قǂ́A�I�[�����Y���Ă��܂��B ����ȃ��H�������F�[�o�[�������ŋߘ^�������\���A���o���ł́A�x�������E�t�B����40�N���e�������Ă��郔�@�C�I�����̃}�f���[�k�E�J���[�]�[���͂��߂Ƃ��铯����������������T�C�h���ł߂Ă��܂����B �A���o���́A�o�b�n�́u���t�ȁv����n�܂�܂��B�������A�o�b�n�ɂ͂��̊y��̂��߂̋��t�Ȃ͂���܂��A�����������̎���ɂ̓R�[���E�A���O���Ƃ����y�펩�̂�����܂���ł����i�܂��u�I�[�{�G�E�_�E�J�b�`���v�ƌĂ�Ă��������������j�B�ł�����A����́u�C�[�X�^�[�E�I���g���I�v�̒�����A�P�Ȗڂ́u�V���t�H�j�A�v�Ƃ���ɑ����u�A�_�[�W���v���ŏ��̂Q�̊y�́A�����ďI�y�͂́A�X�Ȗڂ̃I�[�{�G�E�_���[���̃I�u���K�[�g���������A���g�̃A���A���A���̃I�u���K�[�g�ƃA���g�̃\���𗼕������ċ��t�ȂɎd�グ�����̂ł��B��������������̂ŁA���̊y��̃C���[�W����V�����A�y���Ȗ����y���߂܂��B �Q�Ȗڂ́A�L���ȃh���H���W���[�N�́u�V���E�v�̑�Q�y�͂ł̂��̊y��̃\���𒆐S�ɕҋȂ������́A������A�ƂĂ���������Ƃ������Ɏd�オ���Ă��܂��B �R�Ȗڂ̓s�A�m���t�ŃV���[�x���g�̗L���ȑ����ȁiOp90-3�j�B���̊y��Ȃ�ł͂̏z�ċz�ŁA�ƂĂ������t���[�W���O�������Ղ�Ɖ̂�����ł��܂��B �S�Ȗڂ����́A2014�N�̃��g���ƃx�������E�t�B���Ƃ̃��C�u�^���ŁA�V�x���E�X�́u�g�D�I�l���̔����v�ł��B���߂āA�I�[�P�X�g���̒��ł̔ނ̑��݊����ۗ����Ă��邱�ƂɋC�Â�����܂��B �T�Ȗڂ́A�R�[���E�A���O���ƌ��y�O�d�t�̂��߂̃I���W�i���̍�i�A�W�����E�t�����Z�́u�R�[���E�A���O���l�d�t�ȁv�ł��B�y���Ȋy�͂Ƃ����Ƃ�Ƃ����y�͂����݂ɂT�W�܂�����i�ŁA�t�����Z�Ȃ�ł͂̃G�X�v�������ڂł��B���y��̃p�[�g�����ꂼ��Ɋ���̂ŁA�R�[���E�A���O���Ƃ̊|���������������̂ł��B �Ō�́A���[�O�i�[�́u�g���X�^���v����A��R���̏��t�̌�ɂ��̊y�킾���ʼn��t�����q���̉̂ł��B���������͑f�p�ȃe�C�X�g���������Ȃł����A����͂����A���h�����Ĉ��|����܂��B���̗���ŁA�u�W�[�N�t���[�g�v�̑�Q���ɏo�Ă���A��͂肱�̊y�킾���̊��m�ȃ\���������Ă݂��������ł��ˁi�j�B CD Artwork © SUPRAPHON a.s. |
||||||
������ɂ��Ă��A���̂Q�̉̋ȏW�͍L�����D����Ă��āA�����̉̎肽���ɂ��^�����c���Ă��܂��B���ʂ́A�u�~�̗��v�̓o���g�����o�X�A�u���������ԏ����̖��v�̓e�m�[�����̂��Ă���悤�ł��ˁB�������A�ʊ��ɕʂ̐���̐l�����킵�Ă�����̂�����܂����A�j���ł͂Ȃ������ɂ���ĉ̂��Ă�����̂�����܂��ˁB ����́A�J�E���^�[�e�m�[���ɂ��A�u���ԏ����v�ł��B�̂��Ă���̂̓C�F�X�e�B���E�f�C���B�X�A�ق��̐l��������������̂��Ă����̂�������܂��A���ۂɒ����̂́A�ނ̂��̂����߂Ăł��B ����܂ŁA�����̉̎�̂��̂��Ă��܂������A�ł��X�^���_�[�h���ȁA�Ǝv����̂̓y�[�^�[�E�V�����C���[�ł��傤���B�ƂĂ��l�������ꂽ�A�[�݂̂��鉉�t�������悤�ȋC�����܂��B �������A����̃f�C���B�X�́A���̃V�����C���[�Ƃ͂܂�ňႤ�A�v���[�`�Ŕ����Ă��܂����B�܂��A�������J�E���^�[�e�m�[���ł�����A���ʂ̃e�m�[���Ƃ͂܂�ňقȂ鉹�F�ł��B�����āA��������͂��܂�f��I�ȕ\���͒������Ă͂����A�t�@���Z�b�g�Ȃ�ł͂̂����ƕs����ł͂��Ȃ�����`����Ă��܂��B������Ƌ����ł����i����́u�R���Z�b�g�v�j�B �����ŁA���߂Ă��̉̎���������Ɠǂ�ł݂܂����B����������A���̎�l���͕��ҐE�l�̏C�s�̂��߂ɁA�e���i�}�C�X�^�[�j�����߂Ċe�n�𗷂��Ă���k��A�Ƃ����ݒ�ł����A����͑�l�т��u�N�v�Ƃ����C���[�W�ł͂Ȃ��A���������Ⴂ�A�قƂ�ǁu�K�L�v�̂悤�Ȑ��Ԓm�炸�́u�j�̎q�v�Ƃ������͋C�������������܂����B�����炭�A�����o�����Ȃ��悤�ȃE�u�Ȏq�Ȃ̂ł��傤�B�ł�����A���R���ǂ蒅�������ԏ����i���m�ɂ́u�������v�j�ɂ����e���̖��i�����j�Ɉ�ڂڂꂵ�Ă��܂��܂��B����͂����炭�u���Ⴂ�v�̂悤�ŁA���̕��͂قƂ�Ǒ���ɂ��Ă��Ȃ��l�q���A���̒�����͊_�Ԍ����܂��B����Ȃ̂ɁA�V�Ȗڂ́u���ǂ������v�ł́A�Ȃ�̃G���B�f���X���Ȃ��̂ɂ�������ɁuDein ist mein Herz�i�l�̃n�[�g�͌N�̂��́j�v�ƌ��߂��Ă��܂�����ɁX�����ł��ˁB ������10�ȖځuTränenregen�i�܂̉J�j�v�ł́A�ǂ����������������������̂�������܂��A��Ɂutraulich zusammen�i�ꏏ�ɒ��ǂ��j�v�i������A�j�̎q�̒P�Ȃ銨�Ⴂ�j��݂ɍ����Ă��܂��B�K�����Ɋ��ɂ܂��ė܂𗬂��ƁA���ꂪ�g��ƂȂ��čL����܂����A���͂�������āu�J���~���Ă�������A�A��ˁv�ƌ����܂��B�����ƁA�A�邫��������҂��Ă����̂ł��傤�ˁB �܂�A���������������A�f�C���B�X�̉̂���͒ɂ��قǓ`����ė���̂ł��ˁB���̎���10�ȖځuMein!�i�l�̂��́I�j�v�̍Ō�A�uDie geliebte Müllerin ist mein!�i�����镲���̖��́A�l�̂��̂��I�j�v�́A�̎��Ƃ͗����ȁA�Ȃ�Ǝ��M�Ȃ����ȉ̂����ł��傤�B�ł�����A����͌���14�Ȗڂ́uDer Jäger�v�ł���Ă�����l�ɖ��͖����ɂȂ��Ă��܂��A�j�̎q�̓t����Ă��܂��Ƃ����v���b�g�́A�����ȕ����ɂȂ��Ă���̂ł��ˁB �����āA18�Ȗڂ́uTrockne Blumen�i���ڂ߂�ԁj�v�͔߂������܂��B�uDer Mai ist kommen, Der Winter ist aus.�i�T�������āA�~�͋���j�v�Ȃ�Ă��Ƃ͐�ɋN���Ȃ��̂ɁB���̋ȂŃV�����C���[�͂��Ȃ�Z�I�I�ȉ̂��������Ă��܂����B����͂���ŁA�f���炵���\���ł����A�f�C���B�X�̉̂���͂���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă��A�S���̎��R�̂ł��̔߂����A�Ȃ����`����Ă��܂��B CD Artwork © Signum Records |
||||||
�g�D�[�}��1704�N�Ƀ{�w�~�A�̏����Ȓ��̋���̃I���K�j�X�g�̑��q�Ƃ��Đ��܂�܂����B���������납�特�y������A�̎�A���邢�̓e�I���{�⃔�B�I���E�_�E�K���o�t�҂Ƃ��ĉ��y�Ƃւ̓���i��ł��܂����B�싅�ւ̓��ɂ͐i�݂܂���i����́u�q���[�}�v�j�B �₪�āA�{�w�~�A�����̌��V�@�ō��c���ł���t�����c�E�t�F���f�B�i���h�E�L���X�L�[���݂̃I�[�P�X�g���ɁA��ȉƌ��J�y���}�C�X�^�[�Ƃ��Čق��܂��B���݂̓E�B�[���ł��E�����������̂ŁA��Ƀv���n�ƃE�B�[���̊Ԃ��������Ă���A�g�D�[�}���ނƈꏏ�ɃE�B�[���֕����Ă��܂����B �₪�Ĕނ̓E�B�[���ɏZ�ނ悤�ɂȂ�A�����ŁA���݂̌v�炢�������āA�����̋{��y���̃��n���E���[�[�t�E�t�b�N�X�̒�q�ƂȂ�܂��B�����Ńg�D�[�}�́A�Έʖ@���݂�����w�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B 1734�N�ɁA�v���n�̑吹���̃J�y���}�C�X�^�[���S���Ȃ��āA���̌�C�҂��W���Ă������Ƃ�m���āA�ނ��̋��ւ́u�A���v���n�߂�ƁA���݂����X�ɗ��h�Ȑ��E��������Ă���܂����B�������A���̐��E�v���n�ɓ͂�������ɂ́A���łɌ�C�҂͌��肵�Ă����̂������ł��B�g�D�[�}�́A�d���Ȃ��A�E�B�[���̔��݂̂��Ƃł̐E�����l�X�Ƒ����邱�ƂɂȂ�܂����B ���̌ق��傪�S���Ȃ鏭���O�A1741�N�ɁA�g�D�[�}�͂��̑O�N�ɖS���Ȃ����J�[���U���̖��S�l�G���[�U�x�g�E�N���X�e�B�[�l���V���ɑn�݂����I�[�P�X�g���̃J�y���}�C�X�^�[�ɏA�C���܂��B�������A�ޏ���1750�N�ɖS���Ȃ�ƁA���̃I�[�P�X�g�������U���Ă��܂��܂��B ���̌�A�g�D�[�}�̓t���[�̍�ȉƁA���t�ƁA���邢�͋���҂Ƃ��Ċ��܂��B1768�N�ɂ͍ȂƂ��ʂ�A�E�B�[���𗣂�ăQ�[���X�̏C���@�ɓ���A�����ł̗�q�̂��߂̋Ȃ���葱����ƂƂ��ɁA���犈���������܂��B�����āA1774�N�ɁA�E�B�[���̕a�@�ŖS���Ȃ�܂��B �u���N�C�G���v�́A�J�[���U�����S���Ȃ����Q�N��ɁA�ނ̈�̂��J�v�c�B�[�i�[�[�����Ɏ��߂�ꂽ���ɉ��t����܂����B���̌�A�Ȃ̃G���[�U�x�g�E�N���X�e�B�[�l���S���Ȃ���1750�N�ɂ����t����Ă��܂��B �Ґ��́A�S�l�̃\���X�g�ƂS���̍����c�ɁA���y���t�ƒʑt�ቹ�A�����Ƀg�����{�[���ƃg�����y�b�g�Ƃ���{���ƃe�B���p�j�������܂��B�������A�\���X�g�ƍ����̓o��V�[�����▭�ȃo�����X�������Ă��āA�������̂�O�������܂���B���ɂ͌ÓT�I�ȃt�[�K�Ȃǂ��g���܂����A����Ɠ����Ƀz���t�H�j�b�N�ȕ����������A�o���b�N�������ÓT�h�ւ̋��n�������Ă��邱�Ƃ��@���ɂ킩��܂��B �ނ̉��y�́A�n�C�h����[�c�@���g�ɂ��e����^�����̂������ł����A�����v���Ē����Ă���ƁA���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�Ɋm���Ɏ��Ă��镔����������܂��B�Q��ڂɏo�Ă���uKyrie�v�ł̓t�[�K���g���Ă��܂����A���̃e�[�}�����[�c�@���g�̂��̂Ɖ��ƂȂ����Ă��܂��B�����uDies irae�v���A�g�����y�b�g�ƃe�B���p�j�̃r�[�g�̕��͋C���悭���Ă܂��ˁB����ɁA�uDomine Jesu Christe�v�ɂ��A��������Ȍ���������܂��B�����Ƃ��A���t���ꂽ�̂̓��[�c�@���g�����܂��O�ł�����A����͂����̋��R�H �����P�Ȃ́u�~�Z���[���v�͐��m�ȍ�ȔN�͕�����܂��A��͂�G���[�U�x�g�E�N���X�e�B�[�l�̃I�[�P�X�g������̂��̂��Ƃ���Ă��܂��B������́A�c�B���N�ƃt���[�g�i���R�[�_�[�j�������Ă��āA���ꂼ��Ƀ\���̃I�u���K�[�g��S�����Ă��܂��B��������A�����ƃ\�������݂ɏo�Ă��āA�y���߂܂��B ���t���Ă���u�`�F�R�E�A���T���u���E�o���b�N�v�́A1998�N�ɍ��ꂽ�s���I�h�y��̒c�̂ŁA�����ƃ\���X�g�����̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��B������A�\���X�g�����͂��ׂč����c�̃����o�[�ł��B�K�x�ɃX�g�C�b�N�ȉ��t���A�S�n�悩�����ł��ˁB CD Artwork © SUPAPHON a.s. |
||||||
����ɖ����߂��̂ł��傤���A����DG�����ꂩ��Q�N���o���Ă��Ȃ�2021�N10���ɁA���x�̓x�������E�t�B�����W�����E�E�B���A���Y�̎w���ōs�����R���T�[�g�̃��C�u�������[�X���Ă��܂����B�ŏ��A���̏���m�������́A�S�����̈Ӗ���������܂���ł����ˁB����Ȃ��傤���Ȃ��u��Ԑ����v�Ƃ������A�u��C�ڂ̃h�W���E�v���u���Ȃ�������Ȃ��قǁA���̋ƊE�̌o�ϓI���y���͎�̉����Ă����̂ł��ˁB �O�l�A������l�X�ȃ��f�B�A�̑g�ݍ��킹�ʼn���ނ��̌`�Ԃ�����Ă��܂����B���̂�����CD��BD�Ƃ����p�b�P�[�W���A�w�����Ă݂܂����B����́ACD��BD�����ꂼ��Q���Ƃ����u��ՐU�镑���v�ł����ˁB�܂�A�O���CD�͂P�������Ȃ������̂ŁA�R���T�[�g�̋Ȗڂ̂������̓J�b�g����Ă��܂����B�����āABD�́A�f���̂���BD�ƁA�����R���e���c������BD-A�̂Q���ł��B������A�e�ʂ��O��̔{�ɂȂ����Ƃ������ƂŁA�����f�[�^�̃X�y�b�N�����T�C�Y�̑傫��24/192�ɂ܂Ŋg�傳��Ă��܂��i2�`�����l���X�e���I�����ŁA�T���E���h��24/96�j�B �����A���̉f�����̂́A���łɃx�������E�t�B���̔z�M�T�C�g�A�u�f�W�^���E�R���T�[�g�z�[���v���琶�z�M����Ă��܂����A�A�[�J�C�u�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�ł�����A���łɂ��������������́A���̂悤�ȃ��r���[�����J����Ă��܂����B�܂��A�f�批�y�ɂƂĂ��ڂ������Ȃ�ł͂̓I�m�Ȋ��z�Ȃ̂ł́A�Ǝv���܂��B �����A���t�ȑO�ɁA�܂��A���ʂɍ����Ă���؊ǃZ�N�V�����̃����o�[�ɉ�������a��������܂����B   ����͏�k�ł����A���������R���T�[�g�}�X�^�[���炵�Č������Ƃ̂Ȃ��l�ł����ˁB������ƌÂ��x�������E�t�B���̃T�C�g�ł̎ʐ^��������肱��Ȑl�͂��Ȃ������悤�ȁB ������s�v�c�Ȃ̂́A�Ō�̃N���W�b�g�ł��B  ������������A���̐l�����͂��ꂱ���u�J�������E�A�J�f�~�[�v������̐��k�ŁA���ɗD�G�Ȑl�����̓��ʂȃR���T�[�g�ʼn��t����@���^����ꂽ�̂�������܂���ˁB�����A���ꂾ���́u�G�L�X�g���v�������Ă��܂�����A���͂₱��̓x�������E�t�B���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂���B���ɖ؊ǃZ�N�V�����́A����ɃI�[�P�X�g���̉��F�ɂ�������Ă��܂�����A����͕�����Ȃ��u�U���\�L�v�ɂق��Ȃ�܂���B�E�B�[���E�t�B���ł݂͂�Ȑ��K�̃����o�[�������̂ɁB ����́A���́u�G�L�X�g���v�̐l�������ƂĂ���肾�������ƂƂ́A�S���ʎ����̘b�ł��B����ȁu�x�������E�t�B�����ǂ��v���āA���ׂĂ̋Ȃ̌�ŃX�^���f�B���O�E�I�x�[�V�������s���Ă����t�B���n�[���j�[�̒��O���āE�E�E�B����A�ނ�́A�I�[�P�X�g���������o���O�A���́u�w���ҁv���o�ꂵ�����ɁA���łɑS�������オ���Ă��܂����ˁB CD & BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
������́u��U�w�v�̕��́A�o�b�n�ɂ��ȂI���K����i�̃A���o���ł��B�uBACH�v�Ƃ����ނ̖��O���h�C�c��̉����ɂ��Ă�ƁA���{��ł́u�σ��E�C�E�n�E���v�ƂȂ�A�����������ĒZ�O�x�オ��A�܂�����������Ƃ�������ɂȂ�܂��ˁB���́A������ƑO�q�I�ȉ�������e�B�[�t�ɂ�����i�Ȃǂ��A�����ł͉��t����Ă��܂��B �g���Ă���I���K�����A�����h���̊ό������ŁA�̃_�C�A�i�܂̌������ȂǃC�M���X�����̌����s���Ɏg���Ă�����Z���g�E�|�[���吹���ɂ���y��ł��B���̃I���K����1697�N�ɍ��ꂽ���̂ł����A����ȗ����x�����C����āA���Ɏ����Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ����Ă����j�[�N�Ȃ̂́A���݂ł͓d�C���̃A�N�V�����łP�̃R���\�[�����瑽���̃I���K�����R���g���[�����Ă���A�Ƃ������Ƃł��傤�B����������₩�i����́u�����\�[���v�j�B ���ꂪ�A�I���K���̔z�u�}�ł��B 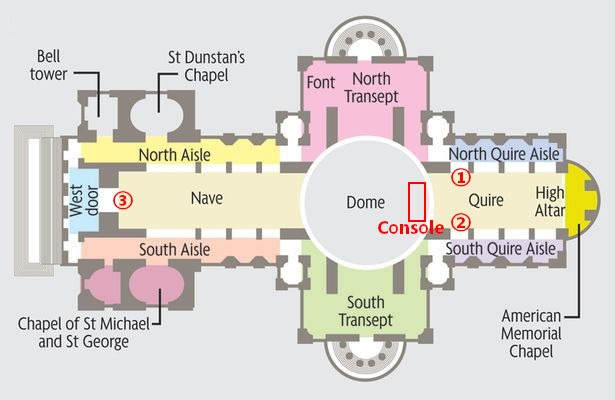   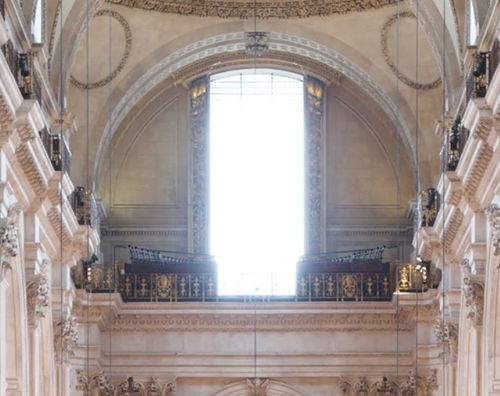 �^���̎��̃��C���}�C�N�̈ʒu�́A�����炭�N���C���ɂ���Q�̃I���K���̊Ԃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�T���E���h�Œ��������ɂ́A�܂��ɂ��ꂼ��̊y��̉����������荶�E�̕ǂ��璮�����Ă��܂��B �P���ڂ�SACD�́A�܂��̓o�b�n���g�́u�t�[�K�̋Z�@�v����́u�R���g���v���N�g�D�XXIV�v�ł��B���̍�i�̍Ō�̋ȂŖ����ɏI����Ă��܂����A��������I�l���i���C�I�l���j�E���b�O��1968�N�Ɂu�����v�����AEMI�ɘ^�����Ă��܂����B����������2020�N�ɉ����������̂��A���̂ł͉��t����Ă��܂��B �����āA�����f���X�]�[�����c�������M�e���烋�h���t�E���b�c����͂�u�����v�������u�\�i�^�v�����t����܂��B����́A�o�b�n�́u�}�^�C�v�ɓo�ꂷ��L���ȃR���[�������ɂȂ��Ă���A�������uBACH�v���������Ă��܂��B����ɁA�V���[�}���ƃu���[���X��������u�t�[�K�v�������܂��B�����A�����A�����܂ł͒����Ă��Ă�����Ƒދ����Ă��܂��܂��B �Ƃ��낪�A�Q���ڂɂȂ��ă��X�g�́u�o�b�n�̖��ɂ��O�t�Ȃƃt�[�K�v���n�܂�����A��R���̃I���K���̉��F���h��ɂȂ��āA�C�P�C�P�̉��y�ɕς��܂����B����́A��{�I�ɋ���̗�q�̎��̊y��A�Ƃ�������𗣂�āA�ƂĂ����F�̑��ʂȁA�����ł̃I���K�j�X�g�A�T�C�����E�W�����\���̌��t�����u�܂�ŃJ�����I���̂悤�ȁv���̂������ɂȂ����u�Ԃł����B���[�h�ǂ̓����I�ȉ��F��A�g�������ɂ���ĂȂ�Ƃ����߂���������������X�g�b�v�ɂ���āA���̃I���K�������̉\���𑶕��ɔ������n�߂��̂ł��B ���̃��X�g�̋Ȃ̃t�[�K�̍Ō�̕����i�g���b�N�T�j��46�b������ł́A�����Ȃ��قǂ́u���C�����E�g�����y�b�g�v���^��납�璮�����Ă��܂��B����́A�T���E���h�łȂ���킩��Ȃ��T�v���C�Y�ł��B ���[�K�[���o�āA�Ō�̃J���N���G���[�g�̍�i�ɂȂ�����A�������̊y��̂Ȃ����܂܂ɁA���̉��F�ƕ\���͂ɂЂꕚ���Ă��܂��܂����B�Ō�́A�X�E�F���������Ẵf�B�~�k�G���h�̂Ȃ�Ɣ������������Ƃł��傤�B SACD Artwork © Chandos Records Ltd |
||||||
���̃I�[�P�X�g���́A���͐�قNj������I�[�P�X�g���Ɠ������炢�̒������j�������Ă��܂����B�����A���̎��̂������ɃR���T�[�g���s���I�[�P�X�g���ł͂Ȃ��A�����ς�X�^�W�I�ʼnf�批�y�Ȃǂ���ɉ��t����u���R�[�f�B���O�E�I�[�P�X�g���v�ł����B�ȂA300�{�ȏ�̉f��̃T�E���h�g���b�N��^�����Ă����Ƃ����܂�����A���������̂ł��B���̒��ɂ́A1958�N�Ƀo�[�i�[�h�E�n�[�}�����q�b�`�R�b�N�́u�߂܂��v�̂��߂ɏ������T�E���h�g���b�N�̂��߂̃X�R�A�Ȃǂ��܂܂�܂��B�N���V�b�N�̘^�����s���Ă��āAEMI�ɂ̓R�����E�f�C���B�X��W�����E�o���r���[�����w���������^���Ȃǂ��c����Ă��܂��B 2018�N�ɁA�w���҂̃W�����E�E�B���\�����A���̃I�[�P�X�g���̖��O�̂��ƂɁA�N�ɉ����E���̃I�[�P�X�g�������ȑt�ҋ��̃����o�[��\���X�g�������W�߂ă��R�[�f�B���O���s���Ƃ����v���W�F�N�g���n�߂܂����B����A���{�́u�T�C�g�E�L�l���v�̂悤�ȃX�[�p�[�E�I�[�P�X�g���Ȃ̂ł��傤�B�����āA2019�N�ɂ͂��̃��[�x������u�f�r���[�A���o���v�ł���A�R�����S���g�̌����Ȃ����C���ɂ����A���o���������[�X���܂����B2021�N�ɂ́A�X�^�W�I���яo���ă��C�����E�A���o�[�g�E�z�[���ł́u�v�����X�v�ŃR�����S���g�����������C�u���s���Ă��܂��B �����炭�U���ڂƂȂ邱�̃A���o���ł́A�����F���̍�i�����グ���Ă��܂����B�����̍�i�����ɏo���̂�20���I�̏����ł������A���ꂩ����͂�100�N�߂��o�Ƃ��Ƃ��Ă��܂��B����Ȓ��ŁA�Ⴆ���[�c�@���g��x�[�g�[���F���̂悤�ɁA�ŏ��ɏo�ł��ꂽ�y�������āA���A��ȉƂ̃I���W�i���ɋ߂��y������낤�Ƃ����������o�Ă��Ă��܂��B���ۂɁA2018�N�Ƀx���M�[�Őݗ����ꂽ�uXXI Music Publishing�v�ł́A���̂悤�ȃR���Z�v�g�̂��ƂɃ����F���Ȃǂ̐V�����y�������X�Əo�ł��Ă��܂��B�����āA������g���Ę^�����ꂽ�A���o���Ȃǂ����łɓo�ꂵ�Ă��܂��B�ȑO���Љ�����g�ƃ��E�V�G�N���́u�W����̊G�v�Ȃǂ��A���̈�ł��ˁB�m���ɁA�����ł̓N�[�Z���B�c�L�[�ɂ���Ď肪�����ꂽ�����������Ɂu�I���W�i���v�̌`�ɂȂ��Ă��܂����ˁB ����̃A���o���ł́A�u�}�E���[���E�����v�Ɓu�{�����v���A���ꂼ�ꂱ�̏o�ŎЂ̊y���ɂ�鐢�E���^���ɂȂ��Ă���̂������ł��B�����ŁA�܂��͂���ȑO�̍ŐV��EULENBURG�̃X�R�A���茳�ɂ������̂ŁA��������Ȃ��璮���Ă݂܂����B�ł��A���ɕς���Ă���悤�ȂƂ���͌�����܂���ł����ˁB�^���́A���ꂼ��̊y�킪�������蒮�����Ă��āA�����̊y�킪�d�Ȃ����Ƃ���ł��������蒮���������܂�����A�����炭�A�_�C�i�~�N�X�ȂǍׂ����w��̈Ⴂ���x�̍Z���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����A���̋Ȃ̍Ō�ɏo�Ă��錷�y��̃g�D�b�e�B�ł̏����ɑS�������鉹�F�ɂ́A�������肵�Ă��܂��܂����B�^����ꂪ����Ȃ̂ŁA���Ȃ�c���������̂ł����A���ꂪ�S����������Ă��܂���B ����ȊO�̎��^�Ȃ́A�u���E���@���X�v�A�u�����t�̒��̉́v�A�u�S�������̃p���@�[�k�v�A�u����Ŋ����I�ȃ����c�v�ł��B��������A��͂茷�y��̑��݊����ƂĂ��ŁA�A���T���u���ł��S�̂ɂ��Ȃ₩����^����A�Ƃ������Ƃ��܂�Ŋ������܂���B�NJy��̃\�����A���Ƀt���[�g�͂Ȃ�Ƃ�������ȉ��ŁA�S�����͂������邱�Ƃ͏o���܂���ł����B ���̂����肪�A�u�ꔭ�I�P�v�̌��E�Ȃ̂ł��傤���B SACD Artwork © Chandos Records Ltd |
||||||
�����Ńt���[�g�����t���Ă���̂́A1994�N�Ƀx�������ɐ��܂ꂽ���[�����E�V���^�C�j���K�[�Ƃ����A�܂�20��̃t���[�e�B�X�g�ł��B�܂������Ă܂���i�u���̐l���v�ł͂���܂���j�B�ޏ��́A14�̎��ɁA���߂ăx�������E�h�C�c�����y�c���o�b�N�Ƀ\�������t���Ă����̂������ł��B���ꂩ��́A�N���X�e�B�[�l�E�w���}���A���X���B�^�E�V���e�[�Q�A�n���X�Q�I���N�E�V���}�C�U�[�ȂǂɎt�����A20�̎��Ƀx�������E�t�B���̃J�������E�A�J�f�~�[�ɎQ�����܂��B ����ɁA2015�N����2019�N�܂ł́A�u���V�A�E�h�C�c���y�A�J�f�~�[�v�Ƃ����v���W�F�N�g�ł̎�ȃt���[�g�t�҂Ƃ��āA�Q���M�G�t�̌O���������܂��B�����āA2019�N����́A�f���b�Z���h���t�����y�c�̎�ȑt�҂ɏA�C���Č��݂Ɏ���A�Ƃ����L�����A�ł��B�����ɏo���X����˂��i��ł��銴���ł��ˁB �ŏ��ɉ��t����Ă���̂́A�c��ȃt���[�g�̍�i��������t���[�h���q�E�N�[���E�́u�E�F�[�o�[�́w�I�C���A���e�x�̎��ɂ��ϑt�ȁv�ł��B����́A�I�y���ł͍ŏ��ɃI�C���A���e�̕v�A�h���[�����A�������ꂽ����Ɏc���Ă����Ȃ��v���ĉ̂��uUnter blüh'nden Mandelbäumen�i�ԍ炭�A�[�����h�̖̉��Łj�v�Ƃ����Â������f�B�̃��}���c�@�̃e�[�}��p�����ϑt�Ȃł��B�܂��́A�N�[���E�����ӂ̕��t�_�����𑽗p����������肵�����t����n�܂�܂����A���̒ቹ���獂���܂ł��삯������p�b�Z�[�W���A�S�������̂Ȃ����x�ȉ��F�Ő��������Ă��邱�ƂɁA�����������܂����B���ɒቹ�̋P�������|�I�ł��ˁB �Q�Ȗڂ́A�u�J���������z�ȁv�Ńt���[�g�W�҂ɂ͂��Ȃ��݂̃t�����\���E�{���k�́u�o���[�h�Ə��S�����̗x��v�Ƃ����A�������Ȃł��B�O�����������Ƃ����u�o���[�h�v�ł��̌�ɂƂĂ��Z�I�I�ȃ_���X�������Ƃ����A���Ȃ�̓�Ȃł��B������A�V���^�C�j���K�[�́A�ڂ̊o�߂�悤�ȃe�N�j�b�N�őN�₩�ɉ��t���Ă��܂��B �R�Ȗڂ��A1961�N���܂�̃I�[�X�g�����A�̍�ȉƃu���b�g�E�f�B�[����2004�N�ɍ�����uDemons�v�ł��B���̐l�̍�i�͉��x�����������Ƃ�����A���Ɖ����ȍ앗���Ǝv���Ă����̂ł����A����͌���t�@�i�{���A�O���b�T���h�A�d���A�t���b�^�[���X�j����g�����A���@���E�M�����h�ȍ�i�ł��B�Ƃ͌����Ă��A�Ⴆ�A���h���E�W�������F�̎�p�I�ȍ�i��A�I�����B�G�E���V�A���̃X�P�[���Ȃǂ��_�Ԍ����āA�����Ɋy���߂܂��B�������A���̂悤�ȃC���M�����[�ȑt�@�����̂Ƃ������A�ʊ��ɂ��̃��b�Z�[�W������ɂ����V���^�C�j���K�[�̌��т��傫���������Ƃ́A�����܂ł�����܂���B �����܂�Ԃ��_�ɂ��āA�㔼�ɂ͂܂����}���e�B�b�N�ȍ�i�����т܂��B�܂��̓J�[���E���C�l�b�P�̃\�i�^�u�E���f�B�[�k�v�ł��B������A���̍�i�ɂ͌������Ȃ��ቹ���ƂĂ��ǂ����Ă��Ė��͓I�ł��B�����A��R�y�͂ł����Ɖ̂�����łق����ȁA�Ƃ����̂��ґ�Ȃ��肢�ł��傤���B�����炭�ޏ��������琔�N��ɂ͂���Ȃ��Ƃ͊ȒP�ɃN���A���Ă��邱�Ƃł��傤�B �Ō�́A�`���̃E�F�[�o�[�Ɍĉ������̂��A��͂�E�F�[�o�[�̃I�y���̃e�[�}���g���Ă���A�|�[���E�^�t�@�l���́u�w���e�̎ˎ�x���z�ȁv�ł��B�O���́u�J�������v���l�A�I�y���̒��̖����������X�Ɠo�ꂷ��y�����A�������A����Ȃ��A�ޏ��͊y�X�ƒ������Ă���܂��B ����قǂ̉��Ɖ��y��������Ă���V���^�C�j���K�[�ł�����A�����炭�A������͌��݂̃|�X�g��肳��ɂ����ƃ����N�̍����X�e�[�^�X�ɂ��ǂ蒅���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B���̃f�r���[�A���o���Œ�����ޏ��̉����A���Ђ��̂悤�ȃI�[�P�X�g���̒��Œ����Ă݂������̂ł��B SACD Artwork © Ars Produktion |
||||||
�e���V���e�b�g�́A1983�N�ɂ��̃I�[�P�X�g���̉��y�ēƂȂ�A���X�̖������c�����ƂɂȂ�̂ł����A1985�N�ɂ̓K���ǂ��A1987�N�ɂ͉��y�ē����C���Ă��܂��܂��B�ł�����A���ꂪ�^�����ꂽ����́A�܂��ɕa���Ɠ����Ă��������ɂ�����܂��B �����ɁA���͂₻�̔�����ł��̏��͂ق��̉̎�Ƃ͎����̈قȂ鍂�݂ɒB���Ă����W�F�V�[�E�m�[�}���������܂��B �R���T�[�g�̃v���O�����́A���ׂă��q�����g�E�V���g���E�X�̍�i�Ő�߂��Ă��܂����B�܂��́A�I�[�P�X�g�����t�ɂ��̋Ȃ��T�ȉ��t���ꂽ��A�I�[�P�X�g�������őg�ȁu���l�M���v�A�����āA�Ō�́u�T�����v����u�V�̃��F�[���̗x��v�ƁA�I�Ȃł��B �܂��A�I�[�v�j���O������u�c�F�c�B�[���G�v�ł́A���̑O�t�̃I�[�P�X�g���̊J���I�ȃT�E���h�ɂ���āA�u���ɃV���g���E�X�̐��E���L����܂��B����ɓ�����Ẵm�[�}���̑�ꐺ���A�܂��ɔޏ��ɂ����������Ȃ��C���p�N�g���ӂ�鉹�y�A����������C�����E�t�F�X�e�B�o���E�z�[���̂��q����́A��l�ɂ��̏�ɋ����킹���K�������݂��߂Ă����ɈႢ����܂���B �S�Ȗڂɂ́A�����Â��ȋȒ��́u�q��́v���̂��Ă��܂����B���̂悤�ȋȂł́A�m�[�}���̑@�ׂȈ�ʂ��͂����肵�܂��B�����������I�[�P�X�g���ɏ���āA�ޏ��͂ƂĂ����J�ɉ̂��Ă��܂��B���̋Ȃł́A�`���̕������Ō�ɌJ��Ԃ����̂ł����A�����ł̓I�[�P�X�g���[�V�������ς���Ă��܂��B�㔼�ɂ́A�O���ɂ͂Ȃ������t���[�g�̑��������A�ق�̏����Ȃɍʂ���������܂��B����ɉ����āA�m�[�}���̉̂��A�����ɕω����Ă���̂��悭������܂��B ���̃R�[�i�[�̍Ō�͗L���ȁu����v�B���̋��̂����悤�ȃG���f�B���O�ɁA�q�Ȃ���͖����̔���ł��B ���̃R�[�i�[�ł́A��]���Ĕ����I�[�P�X�g���[�V�����ŁA���Ƃ��Õ��ȃe�C�X�g�́u���l�M���v�����t����܂��B�����m�̂悤�ɁA����́A�����G�[���̋Y�Ȃւ̕t�����y�ŁA���Ƃ��Ƃ̓����������y��t���Ă��܂������A������A�V���g���E�X�̑��_�̃z�t�}���X�^�[�����㉉�������ɁA���y���V���g���E�X����������̂ł��ˁB�܂�ŃR�[�X�����̂悤�ɁA�ꖡ������V���g���E�X�𖡂������ɂ́A����ł����C���f�B�b�V���́u�T�����v�ɑ�����҂����܂낤�Ƃ������̂ł��B �����āA���́u�V�̃��F�[���̗x��v���A�q��ł͂Ȃ��n�C�e���V�����Ŏn�܂�܂��B����́A��萟�܂����Ƃ���̂Ȃ��A���F�̉��y�ł����B������x����I�[�{�G��t���[�g�̃\�����A�ƂĂ��N�₩�ł��B ���ꂪ�I����Ĕ��肪��������A�m�[�}���̍Ăт̓o��ł��B�I�y���Ƃ��ẮA���̑O�̋Ȃ̊ԂɃG���e�B�b�N�ȗx����I���āA���̑㏞�Ƃ��ċ`���Ɂu���J�i�[���̐��~�������ǁA�悢���ȁ[���H�v�Ɩ]�ނ̂ł����A������������邱�Ƃ͂���܂���B�������A���܂�̎��X���ɍ��������āA���̐��^��ė����Ƃ�����n�܂�Ō�̃V�[���ł��B����͂����A���|�I�A�ޏ��̃��m���[�O�͊����ł��B ���ꂪ��������r��āA�`���ƕ�e�̐������镔���̓J�b�g����āA���̌�ɏo�Ă���u�����A���J�i�[���B���͂��O�̐O�ɃL�X�����Ă��܂����v�Ŏn�܂镔���ł́A�m�[�}���̓_�C�i�~�N�X�𗎂Ƃ������ł͂Ȃ��A�����f�B�������Ȃ������A�قƂ�nj��Ƃ�������̂����ŁA���̕s�C������\�����Ă��܂��B����́A�w�������Ȃ�قǂ̕\���͂ł��B�ł�����A�`���́u���̏����E���I�v�Ƃ������сi����͓����Ă͂��܂��j�͕K�R�ƂȂ�̂ł��B ����́A�܂��Ɂu��Ձv�ł��B CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |
||||||
���ƂƂ��̂�����ɉ��A���B
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |