|
|
|
|
![]()
具合、どうでんな?.... 佐久間學
フローレンス・フォスター・ジェンキンスという人の演奏(もちろん録音で)を聴いたことがありますか? SP時代に録音されたもので、かつてはかなりの「珍盤」として好事家のみが知っていたアイテムなのですが、最近ではCD化もされて、簡単に聴くことが出来るようになっています。
SCHUBERT
Die schöne MüllerinSigrid Althoff(Pf)
Gus Anton/
Camerata Vocale(Quartettverein "Die Räuber")
VMS/VMS 162
RCA/09026-61175-2
ジェンキンスさんというのは「自称」ソプラノ歌手、幼少の頃から音楽家になる夢を持っていたのですが、41歳の時に父親の遺産を相続すると、そのお金(現金っす)でリサイタルを開くようになり、ついにはカーネギー・ホールでのデビューをも飾ったという華麗な経歴の持ち主なのです。しかし、その歌ははっきり言って「音痴」、音程もリズム感も全くなかったにもかかわらず、本人は大歌手であると信じて疑わなかったというギャップが大評判を呼んで、彼女のリサイタルは常に満員だったということです。その「評判」の片鱗を伝えるのが、このCDなのですが、中でも白眉はモーツァルトの「魔笛」からの「夜の女王のアリア」。タイトルを言われなければ、それがあの「ハイF」の連続するコロラトゥーラの難曲だとはまず分からないという、ハチャメチャな世界が広がっています。涙ぐましいのは、そんなデタラメな歌にきっちり合わせようと努力している(もちろん専属の)伴奏ピアニストの姿です。かくしてこのCDは、人々が音楽から「笑い」という特別な感情が伴った感動を得たいと思った時には必ず引き合いに出されるという、名誉ある地位を獲得することになったのです。
このような巧まざるところから爆笑を誘うという「名盤」は一朝一夕に生まれるものではありません。逆に、最初から「笑い」を狙って作られたものなどは、とても悲惨な結果を呼んでいるものが多く、笑いどころか聴いていて辛くなってしまうものの方が多くなってしまいます。そんな中で、久々に「名盤」たり得るものに出会えました。もちろん、最初からそのつもりで買ったものではありません。しかし、聴いてみればそれは紛れもなく本当の「笑い」を誘うもの、喜びもひとしおです。
タイトルは「美しき水車小屋の娘」、もちろん、有名なシューベルトの歌曲集を、全曲男声合唱のために編曲したというものです。演奏しているのは「盗賊」というあだ名を持つドイツの合唱団、最初にレパートリーにしたのがロシア民謡の「12人の盗賊」という、男声合唱の定番の曲だったというのが、その名前の由来だそうです。そして、グス・アントンという、まるでマーラーとブルックナーのファーストネームをつなげたような冗談っぽい名前の方が、指揮とそしてこの男声用の編曲を行っています。
ピアノ伴奏はオリジナルのまま。ですから、まず「さすらい」の浮き立つような軽快なピアノが聞こえてきます。その間に、聴いている人は次に出てくるメロディを心の中で思い浮かべ、どんな表現で歌ってくれるのか、楽しみな一瞬を持つことになるのです。ゲルネのような深いニュアンスでしょうか、はたまたボストリッジのようなとことん「濃い」表情でしょうか。ところが、そこで聞こえてきたものには、メロディーすらありませんでした。ハーモニーのパートがあまりにも頑張っているために、肝心のメロディが全く聞こえてこなかったのです。そのハーモニーすらも一人一人の音程がことごとく違っているので、全体としては全く「ハモる」ことはないのですから、すごいものです。メロディが聞こえないのであれば、表現など感じられるわけもありません。最後の「小川の子守歌」までの20曲の間、一体どこが「水車小屋」で、どこが「娘」なのか分からないまま、唖然として聴き続けることになるのです。
歌っている本人達はいたって真剣、そしてピアノ伴奏の人も、決してペースを乱されることなくしっかり弾いているというあたりが、ジェンキンス盤の精神を見事に現代に伝えています。そう、こんな面白いCD、絶対に狙って出来るものではありません。
イシュトヴァーン・シゲティという、1952年生まれの現代ハンガリーの作曲家の作品集です。彼の名前を聞くのはこれが初めてですが、ライナーによると、主に電子音楽とかライブエレクトロニクスの分野で重要な位置を占めている人のようですね。最近になって「普通の」曲も作るようになってきたとか、その中で、フルートが加わった編成の曲が集められているのが、このアルバムです。
ISTVÁN SZIGETI
Chamber Music with FluteIstván Matuz, Gergely Matuz, Mária Salai,
Zoltán Gyöngyössy, János Bálint(Fl)
Marcato Ensemble
Erkel Chamber Orchestra
HUNGAROTON/HCD 32360
演奏家として参加しているフルーティストは全部で5人、その中でイシュトヴァーン・マトゥスとヤーノシュ・バーリントは聴いたことがありますが、それ以外の人は初めて耳にするものです。ゲルゲリー・マトゥスという方は、他の場所でもイシュトヴァーンと共演していることが多いので、もしかしたらイシュトヴァーンの息子か何かなのかもしれません(ご存じの方は、ご一報下さい)。
1曲目、フルートソロのための「Ritornello」は、おそらくそのイシュトヴァーンが、曲の誕生に何らかの関わりがあるのでしょう。彼ならではのテクニックを駆使したかなりシリアスな仕上がりになっています。中でたびたび登場する長いインターバルのグリッサンド(半音進行ではない、本当のグリッサンド、これはフルートにとっては至難の技です)が印象的です。エンディングで聞こえるちょっと不思議なビブラートは、電子音楽の「変調」のパロディなのでしょうか。
そのあとには、この作曲家の守備範囲の広さを示すかのような、かなり「ポップ」な曲が並びます。イシュトヴァーンにチェロとピアノが共演する形の「Why not?」(なぜか英語のタイトル)のメロディアスなことといったら。次の、3本のフルートのための「That's for You」は、まるでバルトークの「弦チェレ」のような神秘的なカノンで始まりますが、次第にミニマル風のパターンが強調されたものに変わります。全員がフラッター・タンギングで演奏するとか、楽器に何かリードのようなものを付けて突拍子もない音を出すというような「お楽しみ」も存分に味わえます。
続いての「トリオ」は、フルートになんとツィンバロン2台というユニークな編成、リリカルな部分をリズミカルな部分で挟むというわかりやすさ、その両端部分の民族カラー満載の明るすぎるリズムがなかなかです。真ん中の部分でのツィンバロン同士の微妙な音程のズレが生み出す「揺れ」も聞きものでしょう。
次のハンガリー語のタイトル(意味不明)の曲は、フルート、オーボエ、チェロ、ピアノという編成、2本の管楽器が溶け合った響きと流れるようなメロディが魅力的です。ここでフルートを吹いているのがマーリア・サライという人なのですが、このアルバムのフルーティストの中にあって彼女だけ格段に洗練された音を聴くことが出来ます。イシュトヴァーンあたりはまさに現代曲しか吹けないような特殊なフルートですから、そんな中では彼女の音はひときわ精彩を誇ることになります。
「AD(ri)A」という曲は、マリンバなどが加わったアンサンブルをバックに多数のフルートとファゴットがまったり絡み合うという、殆どヒーリングの世界です。弦楽合奏に2本のフルートとファゴットという編成の「トリプルコンチェルト」は、まさにバロック協奏曲のパロディ、心和むようなひとときを味わえます。
そして、最後に控えているのが、8分59秒の間、全くブレスをとらないで演奏するという、ハンガリー語でそのまま「ブレスなし」という超難曲。こういうものはイシュトヴァーンの十八番だったのですが(彼の作品に、そういうものがあります)、これを息子(かどうかは分かりませんが)のゲルゲリーが吹いているのが、興味深いところです。生半可な人がこの循環呼吸を使うと、「重患」になりますからご注意を。
1990年に録音され、1992年にリリースされたアイテムが、「モーツァルト祭」に便乗してお安くなって出直りました。なかなか貴重なモーンダー版による「ハ短調ミサ」、おそらくこれは、1988年のホグウッド盤に次ぐ、この版の2番目の録音だったのではないでしょうか。それ以後は、私の知る限り2004年のマクリーシュまで、これを取り上げる人はいなかったはずです。
MOZART
Mass in C MinorNancy Armstrong, Dominique Labelle(Sop)
Jeffrey Thomas(Ten), Richard Morrison(Bas)
Andrew Parrott/
Boston Early Music Festival Orchestra
Handel & Haydn Society Chorus
DENON/COCQ-84143
アンドルー・パロットという人は、かつて1980年代にはEMIのREFLEXEシリーズなどで「タヴァナー・プレイヤーズ」などを率いて活発な録音を行い、幅広い活躍をしていた指揮者でした。学究的なアプローチとみずみずしい演奏という相反するはずの側面をともに満たした、数々のユニークな成果を私達に提示してくれていたはずです。しかし、最近イギリスからアメリカに拠点を移してからは、ぱろっとその消息が忘れられているように見えるのは、ただの錯覚なのでしょうか。今では、ガーディナー、ホグウッド、ノリントンといった、かつて同じフィールドでしのぎを削った仲間たちに比べると、ちょっと目立たない存在になってしまっていることは否定できません。
この録音も、アメリカのアーティストを率いてのものです。もちろんオリジナル楽器の団体ではあるのですが、何気なく聴いていたのではモダン楽器のオーケストラではないかと思えるほどの屈託のない明るさが、ちょっと気になってしまいます。確かにピッチは低く、フルートなどが入ってくると紛れもない「オリジナル」ではあるのですが、あまりにふくよかすぎる弦楽器の響きに違和感を抱く人は多いのではないでしょうか。響きと同時に表現も、「オリジナルって、もっとストイックなものじゃなかったの?」という感想を持つには十分なものがありましたし。
ただ、かなり高レベルの合唱は、安心して聴いていられます。そんな大人数ではないのですが、二重合唱になってパートの人数が少ない時でも、しっかり個々の声部の音が確保されているのは、さすがです。そして、この未完の作品のテキストを補うために、単旋律の聖歌を挿入しているという措置も、いかにもパロットらしいやり方です。
ところで、この曲の「Sanctus」では、トゥッティで3回「Sanctus」と繰り返された後に続く「Dominus Deus Sabaoth」という歌詞の部分は、きちんと自筆稿に基づく校訂を行った1985年の「エーダー版(ベーレンライター)」以降の楽譜(というより、そもそも1882年のブライトコプフ全集版でさえ)では、最初の1小節はヴァイオリンが「ジャンジャン、ジャララ」というパターンを演奏するだけで合唱は休み、次の小節から歌い出すという形になっています。モーンダー版の現物は手元にないので正確なことは言えませんが、他の演奏家はこの小節に合唱を入れていないので、おそらくエーダー版を踏襲しているはずです。しかし、なんとここで、パロットは合唱を歌わせているではありませんか。確かに、これは最初の小節から合唱が入るというシュミット版(録音では「シュミット/ガーディナー版」と「シュミット/ヴァカレツィ・ヴァド版」しか聴くことは出来ません。パウムガルトナーの1958年の録音はランドン版+K262、一部でシュミット版と伝えられているのは「ガセネタ」です)やランドン版(オイレンブルクのスコアには小さな音符で表記されているので「オプション」という意志が感じられますが、ペータースのボーカルスコアではしっかり普通の音符で印刷されています)の演奏になじんだ人にはかなり違和感のあるものです。実際、「ベーレンライター版」と謳っているにもかかわらずこの部分を指揮者の裁量で歌わせているクリヴィヌのような人もいることですし。しかし、あえて厳格な(はずの)モーンダー版を選んだあのパロットがこんなことをやっている姿には、かなり意外な面を見てしまったという感慨がわいてしまいます。
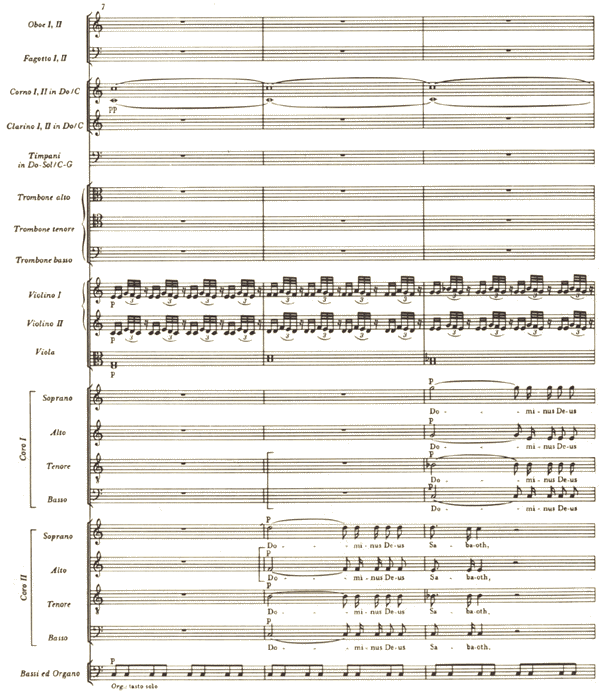
エーダー版「Sanctus」のスコア、7小節目から。
ウィグモア・ホールのライブ録音シリーズ、新録音だけだと思っていたら、「Archive」ということで、昔の貴重な音源も混ざっていたのですね。この、ペーター・シュライヤーという、いつもきちんとブローをしてヘアスタイルには気を使っている名テノール(それは、「ドライヤー」・・・ちょっと引っ張りすぎ)のリサイタルも、そんな一例です。64歳となった年、1999年には「歌手」としては引退することになるシュライヤーが、その8年前、1991年の7月1日に行ったリサイタルをBBCが録音、放送したものが、このCDの音源です。
Schubert Songs Peter Schreier(Ten)
András Schiff(Pf)
WIGMORE HALL/WHLive0006
シュライヤーの声は、「リリック・テノール」と呼ばれる、細やかな情感を伝えるには最も適したものです。それは、特にモーツァルトのオペラでは最高の成果をもたらしています。声の甘さからいったらもっと魅力的な人はいるのかも知れませんが、テキストの内容を的確に表現する力からいったら、彼ほどのドン・オッターヴィオやタミーノはかつては存在してはいなかったはずです。特に、ソット・ヴォーチェで歌われた時に広がる高貴な世界といったら、まさに「至芸」の趣さえ漂っていました。それと同時に、ワーグナーあたりではローゲやミーメといった一癖も二癖もある性格的なキャラクターにこそ、彼の資質は結実していたのです。これも、テキストに対する深い洞察がなせる業でしょう。
今回のCD、一応あのトニー・フォークナーがリマスターを行っていますが、元々は放送用の音源ということで、声もピアノも少し潤いの乏しい音になってしまっているのが、ちょっと残念なところでしょうか。しかし、そんな録音上のクオリティの低さも、コンサートの雰囲気が手に取るように伝わってくるという「記録」としての側面が強調されているものと受け取れば、それほど気にはならなくなってきます。事実、最初に演奏された「白鳥の歌」の1曲目「愛のたより」(ここでシュライヤーは、出版された順序に演奏しています)が終わったあとの、何とも言えない安堵のため息のような客席のどよめきは、このコンサートの密度の高さを端的に伝えてくれるものでした。それほどの緊張感を強いられるほど、シュライヤーの歌には、最初から高いテンションが宿っていたのです。
さらに、4曲目の「セレナーデ」の、甘さとは全く無縁の、まるで突き放すような厳しさはどうでしょう。それはまるで、歌詞の中にある「愛の痛みLiebesschmertz」を訴えかけるような厳しさです。単なるナンパの歌だと思っていたこの曲の中にこんな歌詞があったことに初めて気づかされたぐらい、これは恐るべき演奏です。こういうものを聴く事によって、私達はシュライヤーの最大の特質が、言葉と音楽の極めて高い次元での結びつきである事をいやでも知る事になるのです。
この曲集の最後の「ドッペルゲンガー」では、その幅広い表現力に改めて感服させられます。ここには、それこそタミーノの持つノーブルなたたずまいから、ミーメが演じる絞り出すような苦悩の世界までが凝縮されている事を感じないわけにはいきません。そして、それをその場で聴いている人たちが、その余韻を、ピアノの音がダンパーで消されるまで固唾をのんで味わっている様も、ここには生々しく「記録」されているのです。
ピアノのシフの、シュライヤーにピッタリ寄り添うサポートも、驚異的です。ある瞬間、ピアノの音が全く聞こえなくなり、人の声でもピアノ伴奏でもない一体化した音のかたまりが聞こえてきた事があったのを、確かに体験する事が出来たぐらい、それは完璧な「伴奏」でした。
おそらくアンコールなのでしょう、最後に歌われた「ミューズの子」で見せた、まるで全てのものが吹っ切れたような開放感は、逆にそこに至るまでの緊張感の大きさを感じさせるものでした。そのあとに訪れる盛大な拍手が、この夜のリサイタルの充実度を物語っています。
1926年に生まれて1998年に亡くなったフランスの作曲家ピエール・ヴィレットは、パリ音楽院ではあのピエール・ブーレーズと同じ時期に学んだ人ですが、その作風は同じファーストネームを持つこの「アヴァン・ギャルド」とは全く異なるものになっています。彼の音楽の出発点はグレゴリアン・チャントや中世の音楽、そしてジャズでした。フォーレ、ドビュッシーあたりの流れをちゃんと受け継ぎ、プーランクやメシアン、そしてデュリュフレのようなテイストを持つに至ったその作品のエッセンスは、この、彼の手になる全てのモテットを収録したアルバムによって存分に味わうことが出来るでしょう。
VILLETTE
Choral WorksStephen Layton/
Holst Singers
HYPERION/CDA 67539
そのデュリュフレの助力によって、1941年、15歳でパリ音楽院に入学したヴィレット少年が作った最初のモテットが、「Ave verum」です。ここには、まだ後年のような色彩的なハーモニーは感じることは出来ませんが、曲の最後が終止していない和音などというのは、かなりユニークなものがあります。そして、この「解決しない和音」は、後の彼の合唱曲の一つの特色ともなるのです。1954年ごろに作られたフランス語による「Hymne à la Vierge」は、美しいメロディーとジャズ風の和声が心地よい曲です。こんな素敵な曲を、将来妻となる女性に捧げるのですから、なかなかの情熱家でもあったのでしょう。
彼は1957年にはブザンソン、そして1967年からはエクサン・プロヴァンスの音楽院の校長という職務に就くことになります。ブザンソン時代に作られた「Strophes polyphoniques pour le Veni Creator」は、グレゴリアン・チャントをそのまま使うという、非常に珍しいものです。「polyphoniques」とあるのは、最後の「amen」に対する、これも非常に珍しいポリフォニックな処理。その結果、この曲は、他のモテットとは全く異なるたたずまいを持つことになりました。
彼の合唱作品は、フランス国内よりは外国、特にイギリスで早くから認められていました。その先鞭をつけたのが、ウースター大聖堂聖歌隊の指揮者だったドナルド・ハントです。1970年の半ばに、彼はヴィレットのモテットを数多く演奏会で取り上げたり、レコード録音を行います。このレコードが作曲家の耳にとまり、この2人は終生深い友情で結ばれることになるのです。そして、1983年には、その友情の証として、23年ぶりとなるモテットの筆をとります(1960年から、彼はモテットを作っていません。この間、1970年と1981年には、かなり大きなフランス語によるミサ曲を作っています)。「Attende, Domine」というその曲は、印象的な全音音階を、彼ならではの和声で彩るという、新しい境地を拓くものでした。そして、そこにはフランスの合唱音楽の伝統に根ざした豊かな世界が広がっています。
1987年に校長の職を引退してからは、作曲に専念できるようになり、そこでこのジャンルでの最高傑作と言える「Inviolata」が誕生します。最も多い部分では20声部にもなるという複雑なスコアからは、ある時は寄り添い、ある時は全く異なる音楽を奏でるという、信じがたいほど壮大な宇宙を感じることが出来るはずです。そして、その様な一つのピークを形作ったあとに作られた5つのモテット「O quam amabilis」、「Notre Père d'Aix」、「O quam suavis est」、「Jesu, dulcis memoria」、「Panis angelicus」からは、すっかり力の抜けた、清らかな世界が味わえます。それはまさに芳醇なハーモニーの極み、エンディングに仕掛けられたほんのちょっとした「罠」は、まさに老獪のなせる業でしょうか。
おそらくこれが初めてとなる「モテット全集」は、彼の作品が最も愛された国の演奏家による録音によって、豊かすぎるほどの命を吹き込まれることになりました。その完璧なハーモニーは、あくまで自らの意志でのみ曲を作り、それによって神の栄光に迫ろうとした彼の音楽を見事に形あるものにしています。その上で、レイトンの求めるダイナミックスに応じることが出来るだけの資質がホルスト・シンガーズに備わっていたならば、何も言うことはなかったのですが。
ワーグナーの「指環」のステレオによる全曲録音といえば、ジョン・カルショーが1958年から1965年にかけてスタジオで行ったものが、「世界初」とされています。しかし、そのカルショー自身もその著書「Ring Resounding」の中で述べているように、これに先だつ1955年に、すでにそのカルショーのレコード会社DECCAが、バイロイト音楽祭の「指環」全曲をステレオでライブ録音していたのです。その時に、この生まれて間もないテクノロジー「ステレオ」の技術担当として、実際にその録音に立ち会ったのが、後に「チーム・カルショー」の一員となるゴードン・パリー、彼がバイロイトで得たノウハウが、後のスタジオ録音の際に大きく寄与している、というのが、カルショーがその著書の中でこの録音に関して触れた記述です。その前の「その録音の商業的発表を妨げるさまざまな契約と直面(黒田恭一訳)」という述懐こそが、まさにこのCDが50年の歳月を経て初めて世に出た録音である事を裏付けるものなのです。
WAGNER
Die WalküreAstrid Varnay, Gré Bouwenstijn(Sop)
Ramón Vinay(Ten), Hans Hotter(Bas)
Joseph Keilberth/
Orchester der Bayreuther Festspiele
TESTAMENT/SBT4 1391
そんな貴重な「お宝」、先日の「ジークフリート」に続いての、「ヴァルキューレ」の登場です。他の2作も順次リリース、今年中には「世界初」のステレオ録音による「指環」が全てCDで揃う事になります。
定評のあるTESTAMENTのマスタリング、そしてもちろん、当時最先端を誇っていたDECCAの録音技術は、この50年前の録音から、信じられないほど生々しい音を届けてくれました。弦楽器の音はあくまで艶やか、もちろん第1ヴァイオリンが上手から聞こえてくるというバイロイト独自のシーティングが、きっちりとした音場となって伝わってきます。管楽器も目の覚めるようなクリアな録られ方、ソロ楽器もはっきりと聞こえます。そして何にも増して素晴らしいのが、ステージ上の歌手の声です。制約の多いライブ録音で、これほど多くのソリストがしっかり「オン」で捉えられているのは、殆ど奇跡に近いものがあります。第3幕の冒頭の、ヴァルキューレたちがお互いを呼び交わす場面など、とてつもないリアリティに溢れています。これで50年前の録音!
そんな素晴らしい録音で、「凄さ」を存分に味わえるのが、ブリュンヒルデ役のアストリッド・ヴァルナイです(そういえば、これはCDだけではなく、ヴァイナル盤も発売されるとか)。第3幕半ばでのヴォータンに対するモノローグの鬼気迫る歌唱には、圧倒されてしまいます。よく響く低音を生かして、完璧に自分の歌として歌わない限り決して生まれないような独特のルバートを交えて奏でられるこの「アリア」は、まさにライブ録音ならではの格段の魅力を持つ事になりました。しかし、それに対するヴォータンのハンス・ホッターは、この10年後にカルショーのセッションに臨む時には、もはやコントロールのきかないビブラートでボロボロになってしまう予兆を感じさせる、うわずった音程が気になってしょうがありません。
カイルベルト指揮のこの劇場のオーケストラは、この録音がまさに「記録」としての価値を持つ事をまざまざと見せつけてくれるものでした。これによって私達は、半世紀前の「ワーグナーのメッカ」ではどのような演奏がなされていたかを、まさに今録音されたばかりのようなみずみずしい音によって、手に取るように知る事になるのです。指揮者の趣味もあるのでしょうが、それは煽り立てるエネルギーは有り余るほどあるくせに、繊細さが決定的に欠けているという、「無骨」などという形容詞すら褒めすぎかも知れないと思えるほどのものでした。金管楽器の乱暴なまでの力強さがそれに花を添えます。「ヴァルハラのテーマ」を吹くワーグナーチューバほどのおおらかさはありませんが、その音程のアバウトさには、つい微笑みを誘われてしまいます。
カルショーが彼の「指環」を制作した時には、バイロイトが反面教師になったと、先ほどの著書では述べられています。それはもちろんヴィーラント・ワーグナーの演出に対するコメントなのですが、もしかしたらその中にはこんなオーケストラの印象も含まれていたのでは、と想像してしまうほど、それは醜いものでした。
このCDは、以前「ビクター」から出ていた合唱曲50タイトルがこういうレーベル名でリイシューされた時に同時に発売されたものでしたから、そのシリーズのいわば「サンプラー」としての性格しか持ってないものなのだろうと、手を伸ばすのを控えていたアイテムです。しかし、それはある意味で殆ど正しい見方だったのですが、よく見るとそのシリーズには含まれていなかった音源なども見つかるではありませんか。中には、あの坂本龍一が2005年に作った「合唱曲」なども。そう、確かに限りなくただのコンピレーションに近いものではありますが、これは1900年に作られた滝廉太郎の「花」から始まる日本の合唱曲の歴史を、その坂本龍一まで綿々と50人の作曲家の作品で綴るという、実はかなりしっかりしたコンセプトを持ったものだったのです。
日本の合唱まるかじり 日本伝統文化振興財団/VZCC-52/3
それならば、時代順に並べれば良いのでは、と誰しも思うことでしょうが、ここでは敢えて作曲家の名前を「あいうえお順」で並べたということで、なかなかシュールなたたずまいを見せることになりました。原爆の惨状を無調に託したシリアスというには重すぎる曲のすぐあとに、「タランタラ、ランタララン」というリフレインを持つ脳天気なほどの軽やかな歌が続いたとしても、それがこの国の「合唱曲」の多様な側面を象徴するものだと、笑って許してしまいましょう。
確かに、ここには50人の作曲家による50通りの語法によって作られた「多様な」作品が並んでいます。しかし、その105年という決して短くはないスパンの間に生まれたものとしては、恐ろしく似通ったものが集まっているな、という印象は避けられないのではないでしょうか。大半のものは西洋の音楽の模倣という、この国の作曲界がたどった道からは当然の様相を見せているのは、やはり、仕方のないことだと受け止める他はないのでしょうか。最も新しい坂本龍一の「Cantus Omnibus Unus」という、おそらく昨年は全国の合唱団が歌ったであろう曲にしても、その中に流れているのはエストニアの作曲家アルヴォ・ペルトあたりに代表されるような中世ヨーロッパ音楽への回帰指向です。ドイツ・ロマン派の模倣から始まったこの国の合唱は、「現代」においても「西洋」からの呪縛から逃れることは出来ないのでしょうか。
そんな中にあって、確かに私達の「血」に由来する音楽を目指していた間宮芳生や、三木稔の作品には、今聴いても新鮮な息吹を感じることが出来るはずです。もし、柴田南雄の作品が、初期の習作ではなく後のシアターピースなどが収録されていたのであれば、そこを経て松下耕あたりに至るまでの道筋もより明らかに感じられたことでしょう。同じような理由で、もう少し選曲に対する配慮があれば、湯浅譲二のアヴァン・ギャルド性がここまで浮いてしまうこともなかったはずです。もっとも、武満徹にそれを求めるのは酷というものでしょうが。その結果、アルバムの中で最も印象に残ったものが東海林修の「怪獣のバラード」だったというのは、皮肉なことです。
録音も、1960年代という、殆ど「歴史的」といっても差し支えないものまで含まれていますから、注意深く聴くことによって、そこからは自ずと演奏史のようなものも浮き出てきます。作曲者清水脩自身が指揮をしている「月光とピエロ」を歌っているのは、東京混声合唱団と二期会合唱団という「プロ」。しかし、その、いかにもソリスト然としてアンサンブルを拒み続けているかのような高慢な歌い方は、今のハイレベルな合唱の世界では全く通用しないものであるのは明らかでがしょう?
ところで、以前こちらでこのシリーズの一環のアルバムをご紹介した時に、「『心の四季』の最近の楽譜には無声音の指示が加わっているのかもしれない」と書いたことを裏付けるものが見つかりました。2004年のものにはしっかり記されている無声音の指示(×印の音符)が、1975年の楽譜にはなかったのです。
2 みずすまし 17小節目
1975年 女声版第3刷
2004年 混声版第61刷
NAXOSというレーベル、出来た当初は名曲を「安く」提供するだけの文字通りのバジェット・レーベルだったのですが、いつの間にかある特定の作曲家の作品を全て録音するという、極めて特異なレーベルに変身していたのですね。つい最近も、グラズノフのちょっとマイナーな曲を探していたら、見事にここのカタログの中に見つかって大喜びをしたところ、例の日本人作曲家のアンソロジーも好調に進行中のことですし、このレーベルからは目が離せません。
GAUBERT
Complete Works for Flute 3Fenwick Smith(Fl)
Sally Pinkas(Pf)
NAXOS/8.557307
2003年に第1集がリリースされたフェンウィック・スミスによるゴーベールのフルート曲全集も、たった3年でめでたく完成、第3集が手元に届きました。ソナタが中心の第2集は、そなたに印象に残るような演奏ではなかったためにレビューは書きませんでしたが、今回のものには「世界初録音」となるトランスクリプションが入っているので、初物好きとしては何をおいても触れなければ。
ご存じのように、ゴーベールといえばフルートの教育者としての面が特に重要に思われています。そのために、音階やアルペジオの練習を毎日行うための日課練習を編んだり、教授を務めていたパリ音楽院の卒業試験のための課題曲(この中に収められている「ノクチュルヌとアレグロ・スケルツァンド」)を作ったりしたわけです。そして、その様な、ある意味「指の練習」だけに終わらない確かな音楽性を身につけるための教材として彼が注目したのが、古今の名曲でした。それは、よく知られたシンプルなメロディをピアノ伴奏とフルートソロの形に編曲(といっても、殆ど「素」のままですが)する事によって、旋律の歌い方を学び、表現する力をつけさせようというものです(これは、後に弟子のマルセル・モイーズにも受け継がれ、「Tone Development Through Interpretation」という練習曲に結実することになります)。
その様な趣旨で、ゴーベールが、ルイ・フルーリーやフェルナン・カラージェとともに編纂した曲集「Les Classiques de la flute」は、1927年にリュデュック社から出版されました。ここでゴーベールが担当した分は30曲以上に及びますが、そのうちの12曲だけが、ここでは紹介されています(全集じゃないじゃん!)。そして、その中には、グルックの「精霊の踊り」のように、すでにフルーティストのレパートリーとして多くの録音が出ているものも含まれており、ちょっとびっくりさせられてしまいます。ということは、これらの編曲はもはや「ゴーベール編曲」というプロファイルを離れて、殆ど「パブリック・ドメイン」といった様相を呈しているのでしょう(事実、「著作隣接権」はすでに切れていますし)。つまり、ここでの「世界初録音」というのは、この曲の本来の編曲者をきちんとクレジットした、というところに意味があるということになりますね。同じように、今まではゴールウェイが最初に編曲したのだと思っていたシューマンの「トロイメライ」も、実は「元ネタ」があったのだということに、初めて気づかされることになるのです。
その結果、演奏者のスミスは、殆ど「名曲集」の域を出ないこれらの編曲を、そんな文脈の中で再構築するという困難な仕事に立ち向かうことになりました。しかし、この演奏からは、まさにゴーベールが目指した「表現する力」の成果が見事に達成されたものを感じることが出来るはずです。「模範演奏」として聴くにはあまりにも豊かすぎるエモーションが、私達の心にストレートに届くことでしょう。
「2L」という聞き慣れないレーベル、ノルウェーのレコーディング・エンジニアのモーテン・リンドベリという人が2001年に創立したものです。クラシックから現代音楽、ジャズ、そしてフォーク・ミュージックと、彼の趣味が反映されたアイテムが今までに40種類近くリリースされているマイナー・レーベルです。言ってみれば、ノルウェー版ECMでしょうか。このアルバムでも、プロデュースとマスタリング、そしてジャケットデザインまで、このリンドベリさんが一人で手がけているという、まさに手作りの肌触りです。特に彼はSACDのサラウンドにこだわっているようで、「モノラルは白黒写真、ステレオはポラロイドでしかないが、サラウンドでは、本物のみずみずしさが味わえる」とまで言い切っていますから、このフォーマットに寄せる信頼は相当なものなのでしょう。事実、このアルバムでも、リアチャンネルに教会の残響をふんだんに取り入れた音場設定は確かに「みずみずしさ」にあふれる生々しいものには違いありません。ただ、2チャンネルでしか再生できない時には、その残響が過剰に元の音にかぶってしまって、明晰さが失われてしまうという、最近のハイブリッドSACDによく見られる欠点が露呈はされてしまいますが。
Immortal Nystedt Øystein Fevang/
Ensemble 96
Bærum Vokalensemble
2L/2L29SACD(hybrid SACD)
「イモータル・バッハImmortal Bach」という名曲で合唱界ではとみに有名なノルウェーの重鎮作曲家ニューステットは、このアルバムが録音された時には89歳、「これからも長生きして良い曲をたくさん作って下さい」という思いを込めたのでしょうか、「イモータル・ニューステット」というちょっと粋なタイトルが素敵です。穀物が好きなんですね(それは「芋を食べるニューステット」)。「IB」こそ1987年に作られた「古典」ですが、その他の曲は1999年から2003年という、まさに出来たばかりの曲が揃っているところからも、この作曲家に対するリスペクトが窺えます。
「IB」を聴き慣れた耳には、これらの曲はえらく「丸い」印象を受けてしまいます。晩年になれば、かつての「尖った」側面はひとまず仕舞い込んで、オーソドックスなものを目指す、というのは誰しもたどる道なのかも知れません。しかし、その結果こんな温かい作品がたくさん生まれるのであればそれも幸福なことなのでしょう。「アンサンブル96」という、オスロ・フィルの専属の合唱団が1996年に解散させられた時に、そのメンバーによって結成されたグループは、高度に均質化された響きを持ちながらも、そんな温かさをふんだんに振りまいて包み込むような大きな音楽を味わわせてくれています。その女声メンバーも何人か参加しているもう一つの女声合唱団による「Nytt re livet(新しきは人生)」という曲が、特に充実した響きを堪能させてくれるものでした。
その様な滑らかな曲を聴いたあとに件の「IB」を味わうことにより、この曲の本質が理解できることになります。それは、バッハのコラールをいかにクラスターで解体しても、最後には純粋な3和音に終結するという、実に分かりやすいコンセプトだったのです。それをはっきり示してくれたこの演奏に比べると、ARS盤では「壊れた」ままで終わってしまっていることが、そしてHM盤では、その「壊し方」があまりにも過激すぎるということが、自ずと分かってくることでしょう。
グバイドゥーリナの2005年の新作、フルート協奏曲が届きました。T・S・エリオットの詩からの引用が表題としてついていますが、「希望と絶望の偽りの顔」とでも訳すのでしょうか、なにやら意味深です。作曲家自身のライナーノーツによると、「異なった音程の音を同時に鳴らす時に生じるパルス」が、「希望」やら「絶望」のメタファーとなっていると言うことなのですが、ちょっとこの「理論」自体に理解不能なところがあって、それが作品の中にどのような形で反映されているのかを知覚するのは、私の能力の範囲を超えています。
GUBAIDULINA
The Deceitful Face of Hope and Despair
Sieben WorteSharon Bezaly(Fl)
御喜美江(Acc)
Torleif Thedéen(Vc)
Mario Venzago/
Gothenburg Symphony Orchestra
BIS/SACD-1449(hybrid SACD)
それよりも、おびただしい数の打楽器と、ピアノやチェレスタも含むという巨大なオーケストレーションが生み出す振幅の大きい音色の変化を楽しむという聴き方の方が、ストレスが少なくて済むのでは。何しろ、冒頭の本当に何も音がないところからドラムがかすかに鳴っている、という場面は、CDプレーヤーが壊れてしまって、隣の神社でやっているお祭りの神楽かなんかが聞こえてきたのでは、と本気で思ってしまうぐらいの、リアリティにあふれるものでしたから。もちろん、そこに金管楽器がまるでクセナキスのような深刻なアコードを打ち込み始めれば、それがこの作曲家のいつもの手口だと分かることになるのですが。
弦楽器のグリッサンドなどがフィーチャーされてますますクセナキスっぽくなったあたりで、アルトフルートのソロが始まります。しかし、フルート曲が好きな聴き手であれば、この最初のテーマには言葉を失ってしまうことでしょう。その「As→G→A」という、半音下がって全音上がるという音形は、ヴァレーズの「Density 21.5」という古典的な名曲のテーマと全く同じものなのですから。これがさまざまな高さで何度となく繰り返されますから、嫌でもヴァレーズが連想されてしまうということになってしまいます。一体、これは何の「メタファー」なのでしょう。
妙に「武満」っぽい響きが聞こえる中で、最初に訪れるクライマックスでは、普通のフルートに持ち替えたベザリー嬢の得意技、「循環呼吸」によるクロマティックスケールの嵐を堪能できますよ。そして後半は、タムタムに導かれてバスフルートの登場です。チューバやチェロともども、瞑想的でしっとり聴かせる場面が訪れます。ここでも「ヴァレーズ」が聞こえてくるのが耳障りですが、なかなか美しい場面ではあります。そして、エンディングでは、再度お約束の循環呼吸に舌を巻いて頂きましょう。ウィンドチャイムの驟雨が減衰していく頃には、この曲を献呈者のベザリー嬢以外のフルーティストが取り上げることはあるのだろうか、という感慨がわいてくることでしょう。
もう一つの協奏曲は、1982年に作られたチェロと「バヤン」のための「7つの言葉」、もちろん、聖書にある十字架上のイエスの7つの言葉という、シュッツやハイドンの作品で有名な題材によるものです。バヤンというのはロシア特有のボタン式アコーディオン、昔はやったロシア民謡「トロイカ」の2番だかの歌詞に「響け若人の歌/高鳴れバイヤン」というくだりがありますが、その「バイヤン」です。余談ですが、ロシア人はお寿司が大好きだとか、中でも、トロとイカが・・・。
ここでは、そのバヤンはアコーディオンによって演奏されています。こちらのオーケストラは弦楽器だけ、渋い音色に支配される中で、6つ目の「言葉」でいきなり現れるアコーディオンのソロによる荒れ狂うようなカデンツァが衝撃的です。そして、最後の「言葉」の、まるで全てが浄化されたような風景は、大きな感動を呼び起こすことでしょう。作品としては、こちらの方がはるかに深みに達しているのでは、と感じられる瞬間が、そこにはあります。
さきおとといのおやぢに会える、か。
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |
|
|