| 年 |
月・日 |
で き ご と |
| 1870 |
明治3 |
10月18日 |
国豊橋(現国道25号)が完成。11月13日に堺県に届け出、許可される。 |
| 1873 |
明治6 |
5月13日 |
通行難渋の場所には早く仮橋を設けるよう堺県が布達。 |
| 8月18日 |
堺で紀州街道の大和橋の架け替え工事が起工される。 |
| 11月11日 |
7ヵ村の戸長が発起人となって新架橋の願い出が行われ、即日許可される。柏原村・船橋村・国府
(こう)村・市(いち) 村・弓削(ゆげ)村・田井中村・道明寺村の7ヵ村。7人の戸長は架橋掛となる。 |
| 11月23日 |
7人の架橋掛が連署して、堺の大和川仮橋の払い下げを県に嘆願する。
払い下げの申請をした時点では落札された後であったが、落札額に3円の増金をし、それ落札者への手数料
として渡した上で払い下げを受けることができた。 |
| 12月18日 |
架橋費用を有志の寄付でまかなうため、『新架橋勧進帳』が各村に廻される。 |
| 12月14日 |
この日、払い下げ代金170円50銭を支払うため、架橋掛が堺県から翌年3月30日までの約束で250
円の拝借金をし、その中から支払う。 |
| 1874 |
明治7 |
1月23日 |
大和川新大和橋架橋の工事を開始。工事は堺の2業者が請け負う。 新橋の計画は、長さ106間、幅
1間半、両手すり付き、当初請負額は400円。 |
| 2月23日 |
新橋が落成。25日に渡り初めと県庁の見分があり、完成となる。県より「新大和橋」と命名される。 |
| 3月31日 |
拝借金250円の返済期限に寄付金が足らず、架橋掛7人が個人出資する。県に寄付助成を願い出る。 |
| 6月00日 |
この時点でも架橋費用が99円70銭の不足となる。 |
| 8月29日 |
堺県から寄付金50円が下がり、残り不足額49円70銭は架橋掛7人と世話人12人が追寄付をして、
ようやく決算を済ます。 |

tetsudo.eki/domyoji-sen/m-yamatogawa-shuhen.png)


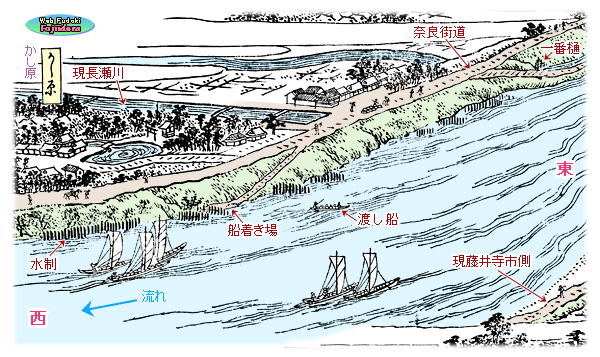

tetsudo.eki/domyoji-sen/kanantetsudo2961-2.jpg)





