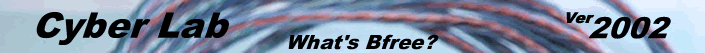
『S-Report』 3/31号 時代が変わる 社会が変わる 地域通貨で変わる 「日本地域通貨フォーラム」
3月18日、東京港区の女性と仕事の未来館で「日本地域通貨フォーラム」(主催 財団法人さわやか福祉財団)が開催された。
さわやか福祉財団堀田力理事長の開会挨拶の後、基調講演として東京大学の丸山真人教授が「地域通貨は何処へ行くか」とトヨタ自動車の岸本周平氏(元大蔵省)の「地域通貨の法的問題」が行われた。
丸山真人教授はカール・ポランニーの市場経済外のサブスタンスエコノミーや江戸期の藩札に触れながら地域における地域通貨のあり方を述べた。
岸本周平氏は元大蔵省の立場から現在の政府の地域通貨に関する法的問題や施策の問題点を指摘し、民による地域通貨による地域再生を語った。
その後、アースデイマネー(東京都渋谷区)、千姫プロジェクト(兵庫県姫路市)、Jファンド(Jファンド事務局)、時間通貨(さわやか福祉財団・全国)などの国内各地の実践者による全国の活動事例が紹介された。
パネルディスカッション「地域通貨の理想と現実」では堀田力理事長のコーディネートにより、エコミュニティーネットワーク代表加藤敏春氏、ピーナッツ倶楽部、村山和彦氏(㈱みんなのまち代表)、ゲゼル研究会代表森野栄一氏、岸本周平氏というこれまでの地域通貨を切り開いてきたパネリストにより討論が行われた。
この中では地域通貨がいろいろな意味で壁にぶつかっており、これを超えて地域通貨の新しい時代を切り開くための方法について語られた。多様な意見が出されたが、新しい時代のニーズに答えるための地域通貨のあり方、地域通貨の情報通信技術(ICT)の活用、などで共通していた。
また、併設たれた地域通貨展示ブースおいて行われた全国から参加した地域通貨の説明は会場があふれるほどの盛況だった。
丸山真人教授が冒頭で指摘したように日本において地域通貨は常に新しい形が生まれており、新たな可能性も開けている。
(財)住宅総合研究財団 第6回「住まい・まち学習」実践報告・論文発表会に下記2点を発表します。
7.「こどもをきっかけとするまちづくりへの視点-異世代での協働、交流が育んだもの- 」
田中恒明(地域情報研究所)
執筆者 田中恒明、長岡素彦(地域情報研究所)、山口邦子(共立女子大学)
9.「上尾ビレッジカフェ「地域通貨で問題解決」-まち育てのひとつとしての地域通貨ビオトープ- 」
長岡素彦(さいたま地域通貨フォーラム/地域情報研究所)
第6回「住まい・まち学習」実践報告・論文発表会
日 時 2005年4月2日(土)13:30~17:30 終了後、交流会を開催します。
会 場 建築会館302・303会議室
(JR田町駅,都営地下鉄三田駅(浅草線・三田線) 徒歩5分、港区芝5-26-20 tel?:03-3456-2051)
参会者 学校関係者、建築系・教育系などの研究者・実務者ならびに大学院生・学生、まちづくりなどの活動家、関心のある保護者の方などです。
(財)住宅総合研究財団では、1993年より住教育委員会を設置し、住教育フォーラム等の活動を行っています。また、各分野・学会に分散している住まい・まち学習関係者が分野を越えて集い、成果・情報を交換・蓄積していくために論文集の作成・発表を6年前より毎年実施し、これまでに、学校教育・都市計画・建築・造園・美術・まちづくりなど幅広い分野の方々から、130編を越える論文が寄せられています。
委員長 延藤 安弘(NPO まちの縁側育くみ隊 代表理事)
委 員 小澤紀美子(東京学芸大学教育学部教授)
委 員 木下 勇(千葉大学園芸学部助教授)
委 員 町田万里子(元 筑波大学附属小学校教諭)
委 員 細田 洋子(建築と子供たちネットワーク仙台)
委 員 奈須 正裕(立教大学文学部 教授
第6回「住まい・まち学習」実践報告・論文発表会聴講者募集 定員 50名 (申込み先着順)
参加費 無料 (ただし交流会は会費1,000円)
参加申込 こちらのフォーム,または,faxで
(1)参加内容(発表会,交流会),(2)氏名,(3)所 属,(4)連絡先住所,(5)e-mail,(6)電話,(7)faxを下記まで送信して下さい。
*お断りする場合はご連絡いたします http://www.jusoken.or.jp/jukyoiku_form.htm
申込・問合先 (財)住宅総合研究財団 住教育担当
〒156-0055 世田谷区船橋4-29-8 tel 03-3484-5381,fax 03-3484-5794
こどもの声が大人を動かす!メッセージ募集 2005/03/29
こども環境学会が、2005年こども環境学会大会開催(4月22日~24日)に伴い、こどもシンポジウム「子どもから大人へのメッセージ」の開催を予定しており、こどもたちからの意見を募集している。
こども環境学会は「学問の領域を超えて、こどもを取り巻く環境=「こどもの環境」の問題に関心や係わりのある研究者や実践者が集い、共に研究し、提言をし、実践してゆくなかで、こどもの成育に寄与する環境科学を確立し、こどものためのよりよい環境を実現する」ために昨年設立された。
今年は大人がこどもについて論議するばかりでなく、こどもの参画を促すために、こどもから「こどもの参画サイト みんなの声(BLOG)~みんなの声が大人を動かす!募集中!」で意見を寄せてもらったり、こどもシンポジウム「子どもから大人へのメッセージ」で発言をしてもらったりして、こども環境学会のアジェンダに反映したいとのことだ。
こどもの声が大人を動かす!だからみんなの声を聞かせてほしい!
こども環境学会会長 仙田満
2005年こども環境学会大会実行委員長 福岡孝純
こども環境学会(事務局 東京工業大学内)が開催する「2005年こども環境学会・大会および国際シンポジウム」では都市化社会の中で事故や犯罪の危険に晒されているこどもたちの現状に鑑み、テーマを「こどもの安全と健康のための環境」と題し、ハード(物的環境)とソフト(社会的・文化的環境)の両面からの安全な環境づくりとこどもたち自身の安全能力や健康の向上に向けて討論をし、こどもの安全と健康のための環境づくりの具体的な方向を見出したいと思います。 本大会ではこどもたちが主役の「(仮称)こどもシンポジウム」の開催を予定しており、こどもからの意見を下記の通り募集します。また、その意見をみて、こどもに「(仮称)こどもシンポジウム」のパネラーもお願いします。
こども環境学会はきみたちが大人にぶつけたいメッセージを大募集
1.お願い
4月23~24日、こども環境学会の年に1度の大会が開かれます。そこで、大人にぶつけたいメッセージを募集します。テーマは一応「こどもの安全と健康のための環境」っていうものだけど、だいたい、こどもって大人が「安全」やら「健康」を考えるってどんな気持ちなのかなぁ。
それにさ、そもそも、こどもの「安全」とか「健康」って何だと思う?
たくさんのメッセージまってるョ!
みんなの声が大人を動かす!
ホントじゃ!!
2.いつまで
1次締め切りは4月10日まで。
3.だれが 20才になってなければ誰でもいいよ。
4.どこに、どうやって
ホームページ「みんなの声が大人を動かす」から、パソコンおくってね。メッセージは短くてもいいよ。
http://www.children-environment.org/kids/,
5.どうなる ホームページ「みんなの声が大人を動かす」にきみの意見がのります。
それに、こどもの意見を聞く大人からお返事ものります。
この意見の中から、2005年こども環境学会大会「(仮称)こどもシンポジウム」の参加をお願いすることがあります。 きみも、学会で大人に言いたいことを言おう!!
6.保護者・関係者の皆様
頂いたお子さまのメッセージやプライバシーの取り扱いにつきましては細心の注意を払います。
ご参加をお願いするお子様については事前に個別にご連絡しご相談をさせていただきます。
【こども環境学会とは】
学問の領域を超えて、こどもを取り巻く環境=「こどもの環境」の問題に関心や係わりのある研究者や実践者が集い、共に研究し、提言をし、実践してゆくなかで、こどもの成育に寄与する環境科学を確立し、こどものためのよりよい環境を実現することが、『こども環境学会』の目的です。
こども達のために豊かな成育環境を実現することに関心を持っておられるすべての方々の参加をお待ちしております。
こども環境学会は、2004年5月の設立大会「こどもと環境:都市化の中のこどもたち」で、ロビン・ムーア氏(ノースカロライナ州立大学教授)、ロジャー・ハート氏(ニューヨーク市立大学教授)らをお招きして国際シンポジウムを開催しました。昨年度の大会においては、こどもたちを取り巻く環境の変化がこどもたちの成育に様々な影響を与えていることが幅広い学問分野から問題提起され、こどもたちの環境の改善に取り組んでいる様々な団体からは、その取り組みなどが紹介されました。
【本件のお問い合わせ】 こども環境学会 事務局長 中山豊
〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1(東京工業大学大内)
URL:http://www.children-environment.org
E-mail:info@children-environment.org
「みんなの声が大人を動かす!」専用メール: kids@children-environment.org
◆■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇
♪スキルアップのフルコース♪ ~パート1~
前菜・スープを召し上がれ♪
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇
「春だ!自分に向き合い、新しい仲間を探してみない?」
●日時:平成17年4月9日(土) 10:00~16:00
●場所:サイサンKSビル8階ホール(大宮駅徒歩10分)
http://www.saisan.net/
●主催:彩の国学生ボランティアネットワーク
●協力:埼玉県社会福祉協議会
●内容:
○食前酒~初対面でも打ち解ける方法
○前菜・俺流サラダ ~自分のやりたいことを見つけよう
○スープ・十人十色スープ ~仲間を見つけていい味だそうよ~
○メインディッシュは
6月11日(土)・8月13日(土)・10月8日(土) 12月10日(土)・2月11日(土)で食べよう!
●シェフ(ファシリテーター)
○武田三奈さん(自分が変わる世界が変わるワークショップ)
○茂木昌克さん(ユース・トーク未来代表)
○彩の国学生ボランティアネットワーク
●参加費 学生 500円 一般 1,000円
●申し込み方法
下記フォームをvc@fukushi-saitama.or.jp へ
・・・・・・・・・・・ 申し込みフォーム ・・・・・・・・
氏名(フリガナ);
所属団体名(あれば):
学生参加者の方は学校名と学年:
連絡先 〒:
住所:
電話番号:
携帯番号:
Eメール:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●彩の国学生ボランティアネットワークってなあに?
埼玉県内を中心とした大学、地域のボランティア同士の情報交換や横のつながりをつくるために有志によって設立されたネットワークです。
メールでの情報交換や、2ヶ月に1回(偶数月)に定期的にサロンを開催しお互いのスキルアップをはかっています。
●今後のスケジュール
5月7日・8日合宿
1日目「アイスブレイクだよ~大運動会」 2日目「テーマ別分科会」 防災・まちづくり・こどもをテーマに語ろう。
●問い合わせ先 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
電話048-822-1192 FAX048-822-1449
Eメール:vc@fukushi-saitama.or.jp 担当:秋山
---------------------------- ------------------
4月3日(日)『のりのり(海苔)ウォークラリー開催!』
海苔のまち「大森」をめぐるスタンプラリー!
どなたでも参加いただけます!(10歳以下は保護者同伴)
春休みの家族イベントに、お友達と健康づくりに・・・是非ご参加下さい!
団体さま歓迎!
・ゴールした方にはもれなく海苔に関するステキな商品をプレゼント!
・さらに抽選で豪華海苔商品も当たる!
・また、お名前に「の」と「り」のつく方!特典があります!
(数量限定 証明するものをおもち下さい)
■参加費:300円(当日受付) 定員500名
■チェックポイント:こらぼ大森(スタンプカード発行)→海苔の松尾(平和島) →くじらオブジェ→海苔博物館→海苔会館→大森町商店街→海苔の碑 →こらぼ大森(約4km)
■受付時間:9時30分から12時30分
■受付場所:こらぼ大森(大田区大森西2-16-2
京浜急行平和島駅から徒歩7分駐輪可)スタート、ゴールとも:こらぼ大森
★平和島駅から参加したい方は、予約を!転送歓迎! 平和島駅から参加したい!という方はあらかじめメールemail : info@oomori-cafe.comにて「お名前」「連絡先」「参加人数」と「平和島駅」到着時 間をお知らせ下さいスタンプカードを平和島駅でお渡しします。
★当日はゴール地点のこらぼ大森で海苔イベント「みんなでつくろう!手巻きずし」 も開催しています!一日海苔づくしでお楽しみ下さい!
■雨天決行
■主催:大森まちづくりカフェ
■お問い合わせ 大森まちづくりカフェ事務局 たかだあや
[〒] 143-0015 東京都大田区大森西2-16-2 こらぼ大森内
[tel/fax] 03-3768-0051
[URL] http://www.oomori-cafe.com/
---------------------------- ------------------
参加と協働を考えるサロン
●日時:平成17年4月20日(水)午後7時00分~8時30分
●場所:浦和市民会館(さいたま市)浦和駅下車徒歩8分
●ゲストスピーカー 県こども家庭課 小峰さん 「次世代育成支援行動計画」や「子育て応援団」などについて
●参加費:500円(資料代)
●「参加と協働を考えるサロン」の申し込みは・・・ ・
協働→参加のまちづくり市民研究会(http://machiken.org)まで
・ E-mail:in-fo@machiken.orgまでお申し込みください。
・ なお、電話での問い合わせは (担当・矢嶋)までお願いします。
『 ケーススタディ・ノート 協働でまちをつくるのだ!
-埼玉におけるNPOと自治体の協働に関する事例調査報告書 』 (愛称 「協まち本」)
編集・発行: NPOと自治体を考える自主研究会 (現)協働→(による)参加のまちづくり市民研究会
特定非営利活動法人さいたまNPOセンター
頒価: 1,000円(送料別) 発行: 2004年1月 A4版・116頁
◆ 第3回「日本NPO学会賞(研究奨励賞)」受賞! ◆
2005年3月21日、「日本NPO学会第7回年次大会」において、『協まち本』が第3回「日本NPO学会賞(研究奨励賞)」を受賞いたしました。NPOが取り組んだ調査研究では初めての受賞です。
▼NPOと自治体職員が見て・聴いて・考えた…
・NPOと自治体職員がいっしょに協働事例のアンケート調査・ヒアリング調査を実施。さらに、具体的な事例検討(ケーススタディ)から「協働のあり方」をまとめた他に例を見ない調査報告書。 ・「協働のあり方」では、「まちは誰のもの?」「公益や公共とは?」から解きほぐし、「協働でまちをつくるのだ!」を大胆に提案。よりよい協働のために、NPOと自治体に必要な20のポイントを提示。
・NPOと自治体の「協働」を考える関係者に必読の書!
▼「NPOと自治体を考える自主研究会」とは…
・2000年11月に、NPO法人さいたまNPOセンターの呼びかけで発足した、NPO活動実践者と自治体職員が「NPOと自治体の協働」のあり方を考えるプロジェクト。
・2004年6月のプロジェクト終了後、活動をさらに発展させるため、同年10月、有志のメンバーで「協働→(による)参加のまちづくり市民研究会」(略称「協まち研」)を設立しました。
・「協まち研」は、まちの課題を市民一人ひとりの参加によって解決するための「協働」のあり方を研究・提案する活動を、NPOと自治体職員のメンバーで行っています。
本書は、NPOの入門書でも、協働の概論書でもありません。本書を読んでいただきたいと考えるのは、現に協働にとりくみ、あるいは、これからとりくもうとされているNPO活動実践者や自治体職員の方々です。とくに総論では、協働を始める段階や、協働にとりくんでいる段階、協働を振り返る段階で、議論や実践にご活用いただけるように、NPOと自治体にとって必要と思われることを20の提案にまとめました。また、協働にとりくむ前提として、解決しようとするまちの課題や「公益」「公共」をどのように考えればいいのか、そして、「協働」で何を目指そうとしているのかについても、できるだけわかりやすいことばで解説しました。
本書は、NPOで活動する者と自治体職員による研究会のメンバーが、具体的な事例や現場から協働のあり方を考え、双方の視点でいっしょになって議論し、そのポイントをまとめたものです。まだまだ協働の多くが手さぐりでとりくまれている現状のなかで、一つの方向を示すことができたのではないかと考えています。本書が、それぞれのまちで、NPOと自治体とが協働にとりくむ際の一助となり、新しい公共を創造する「協働のまちづくり」に結びついていくことができれば幸いです。
●書籍のご注文は…
・下記の「注文書」にご記入の上FAXでお送りいただくか、注文書の内容をEメールでお送りください。
・・> FAX: 0480-67-1383
・・> Eメール: pavian@mtc.biglobe.ne.jp
・書籍代金と送料(送料は1冊・210円)のお支払いは、お届けする書籍に郵便振替払込書を同封いたしますので、到着後1週間以内にお近くの郵便局で払込みをお願いします。また、払込手数料はご負担願います。
---------------------------- ------------------
こども環境学会・2005年度大会および国際シンポジウム「こどもの安全と 健康のための環境」
開催日 2005年4月22日(金)~24日(日)
会 場 建築会館(東京都港区芝5-26-20)
主 催 こども環境学会 http://www.children-environment.org/
問合せ こども環境学会事務局(担当:中山、井上、西本)
〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1 東京工業大学内
TEL: 03-5734-3163, FAX: 03-5734-2923 Mail to: info@children-environment.org
参加費
大会参加(4月22日~24日)会員4,000円、学生会員3,000円、非会員4,500円
国際シンポジウム(4月23日13時~17時) 会員4,000円、学生会員3,000円、 非会員4,500円
懇親会(4月23日午後18時より) 3,000円
都市化社会の中で事故や犯罪の危険に晒されているこどもたちの現状に 鑑み、テーマを「こどもの安全と健康のための環境」と題し、ハード(物的環 境)とソフト(社会的・文化的環境)の両面からの安全な環境づくりとこどもた ち自身の安全能力や健康の向上に向けて討論をし、こどもの安全と健康のための環境づくりの具体的な方向を見出したいと思います。
研究者のみならず、こどもの環境づくりや子育て支援に取り組む幅広い実践者、子育て中の家族の方々、そしてこどもたちなど多くの方々の参加を期待しております。
開催概要
〇4月22日(金) 12:00~18:00
エクスカーション(活動実践施設の見学ツアー)町田市玉川学園子どもクラブ、ころころ児童館、ゆう杉並、羽根木プレーパークにて前夜祭
〇4月23日(土) 9:00~18:00
開会講演:千田満氏「こどもの安全と健康のための環境」
基調講演:イアン・ロバーツ氏「こどもと交通戦争」
国際シンポジウム:こども事故防止の専門家、神戸のWHO健康開発総合研究センター(WKC)の都市健康学者、韓国の児童学者、パキスタンの母 子保健学者、スポーツ環境学者らの参加により、国際的な枠組みの中で こどもの安全と健康を守る環境づくりを考えます。
分科会:23日11:00~12:20
1)「安全で楽しいあそび環境づくり」(千田満氏ほか)
2)「こどもが事故にあわないまちづくり」(木下勇氏ほか)
3)「住環境と母子の健康生活」(織田正昭氏、小澤紀美子氏ほか)
総会:17:00~
懇親会:18:00~
〇4月24日(日)9:00~17:00
分科会:24日9:00~10:20
4)「環境としての学校」(汐見稔幸氏ほか)
5)「こどもを犯罪から守るまちづくり」(中村攻氏ほか)
6)「こどもと情報文化環境」(高山英男氏ほか)
特別講演:10:40~ 平山宗宏氏「わが国の母子健康の流れと今後の課題」
ポスターセッション発表:12:00~
中庭でのワークショップ:12:00~
子どもから大人へのメッセージ:13:00~
※子どもの声を募集中 http://www.children-environment.org/kids/
総括セッション(アジェンダの採択):16:00~
---------------------------- ------------------
「ユビキタスネット社会の実現に向けて」
さて、国連「世界情報社会サミット(WSIS)」のテーマ会合「ユビキタスネット社会の実現に向けて」のお知らせです。
2003年2月に第一回「世界情報社会サミット(WSIS)」の準備過程で日本のNGOが集まり、WSIS日本NGO委員会(Japan NGO Coordination Committee for WSIS)を形成しました。
今回のテーマ会合「ユビキタスネット社会の実現に向けて」では政府と国際機関が主催ですが、そのWSIS日本NGO委員会を基礎に「市民が企画する市民社会セッション」として 『人間中心の包括的な開発志向のユビキタスネット社会』の企画をしてまいりました。
この度、その概要が決まりましたのでお知らせすると共に、参加申し込みのご連絡をします。
WSISテーマ別会議「ユビキタスネット社会の実現に向けて」 -いつでも、どこでも、何でも、誰でも- 目的 「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単にネットワークに接続できる「ユビキタスネット社会」の概念が、各国の政府や産業において大きな注目を浴びている。ユビキタスネット社会では、あらゆる人や物が結びつき、これまでとはまったく次元の異なるICT利活用の新たな革命が起こることが予想される。そこでは、人に優しい心と心の触れ合いが実現し、利用者の視点、利便性が融けこむとともに、個性ある活力が湧き上がる社会が実現されることが期待されている。 世界情報社会サミット(WSIS)ジュネーブ基本宣言及び行動計画でも、全ての人々が、ユビキタスに手頃な料金でアクセスが可能となる情報通信インフラを開発すること等の重要性が強調されている。この考えは、ユビキタスネット社会のビジョンとまさに共通するものである。そこで、ユビキタスネット社会に関するWSISのテーマ別会議を日本において開催することとし、その実現に向けた具体的方策や想定される課題への取組みについて提言をまとめる。
開催時期及び場所 2005年5月16日(月)、17日(火) 東京(京王プラザホテル)
主催者(共催)総務省、ITU、国連大学
会 場 東京 京王プラザホテル(東京都新宿区西新宿2-2-1 TEL:03-3344-0111)
参加者 各国政府、国際機関、民間企業、シビルソサイエティー(市民社会)等から約400名程度
会議構成
・開会式
・オープニングプレゼンテーション
・オープニングステートメント
・プレナリー
・分科会
(1)技術が拓く情報社会への展望
(2)人材育成(知識共有)
(3)デジタル・ディバイドへの取組
(4)人間中心の包括的な開発志向のユビキタスネット社会-市民社会セッション
(5)ユビキタスネット社会の実現に向けて
展示会場内で、ブロードバンド・モバイル・電子タグ等、ユビキタスネット社会に関連する最新技術、サービス、アプリケーションなどの展示を行う。
「ユビキタスネット社会の実現に向けて」 http://www.wsis-japan.jp/index_j.html
締め切りが4/4となっていますが、その後も可能です。
国連サミットの会合で政府と国際機関が主催ですが、前回と同じく”WSIS 4 ALL” の原則でおこなっています。
”WSIS 4 ALL” この意味を私はこう解釈しています。
"The World Summit on the Information Society For All"
「世界情報社会サミットはNation (国)、International organization(国際機関)、Private sector (民間、私企業等)、Civil society・NGO's(市民社会・NGO)の4者すべてのためのものである。」
長岡の記事等
世界情報社会サミット開幕へ http://preview.janjan.jp/world/0312/0312069150/1.php
アジアの市民が描く、情報社会の未来像 http://www.janjan.jp/living/0310/0310237690/1.php
ICT(IT)は誰のもの - WSIS 4 ALL http://www.e-tiiki.net/wk/2.htm