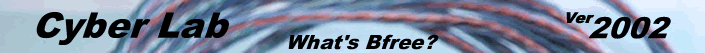
�@�w�r�|�q�����������x�@�@11/13���@�@�����o������n�܂���S���S�̂܂��Â��� �|�@�܂��Â���̂��炽�ȓW�J�����߂ā|�P�V
�@25�A26���ɑ�2��u���S�E���S�܂��Â��胏�[�N�V���b�v�v���A���S�E���S�܂��Â��胏�[�N�V���b�v���s�ψ����ÁA���n��i�㉇�F���t�{�E�����ȁE���y��ʏȁE�����Ȋw�ȓ��j���ÂŁA������w�i���n��j�ƖL�ʑ�w�Z�ōs��ꂽ�B
�@�@ �@�@
�@��_�W�H��k�Ђ₢�낢��Ȏ��̂̋��P�����ƂɁA���X��E���������t�{�A�e���������܂ł���������Ń��[�N�V���b�v���s�����̂ł���A�����2��ڂł���B
�@�J��ł͈�o���s�ψ���ψ��������{�̈��S���S�̐��͏c����ł��܂������Ȃ����Ƃ���̓I�ɏq�ׁA�S���e�n�̈��S�E���S�̂܂��Â�����H��������L���A�n��E���Ԏ哱�̖h�Ѓl�b�g���[�N���������邱�Ƃ��d�v�ł���Əq�ׂ��B
�@
�@���̌�A���n�撷�̑㗝�A��c��c���A������w�w���㗝�̈��A���������A�n���̔��_�𗬉�̋��H���̂ЂƂ����͊J��O���理���o���̏����𑱂��Ă����B
�@���̐����o���ɂ��u���̂����������H�R�[�i�[�v�ł̒��H��A�e�[�}��ʂ̐V����[�N�V���b�v�u���������܂��I�v���n�܂����B
�@ �u���������܂��I�v�͒P�Ȃ���S���S�̊�������̔��\�E���������ł͂Ȃ��B�Q�l�ɂȂ�m�E�n�E�����L���A�n��̈��S���S�܂��Â���̋�̈Ă��܂Ƃ߁A�Ō�ɍu���ł���\�����B
�@�u���������܂��I�v�ƕ��s���āu���n����_�𗬉�v���s��ꂽ�B
�@���n���103�Z�̏��E���w�Z�őg�D����Ă���u���_�^�c�A����v�́A�ЊQ���ɋ���̏��E���w�Z����_�Ƃ��ĉ^�c���邽�߂ɖh�ЌP�����s���A�������犈�����Ă���B
�@���̌𗬉�ł͔��_�^�c�̎d�g�݂Ȃǂ����\���ꂽ�B���ɁA��_�W�H��k�Г��������ł������X�e�B���i�_�ˎs�j�̔�Ў��̊w�Z�̌��ɎQ���҂͐^���ɕ��������Ă����B���_�^�c���瓾�����̂ɂ��ނ悤�ȁu�������m�b�v�ł������B
�@26���́A�֓���k��80���N�L�O�v���O�����Ƃ��āA�ߋ��̋��P�Ɋw�ԍu���E�ӌ������Ȃǂ��s���A���������A�u�m�b�ƍH�v�œ������I�v�u ���S�E���S�̂܂��Â���v��i�߂Ă�����ŕ�������̉������@�ɂ��āA���ꂼ��̗�����čl���A�Ō�ɍu���Ŕ��\���s��ꂽ�B
�@NPO�@�l�������̂��̃|�[�^���T�C�g�́A���[�N�V���b�v��u�������̂��̃|�[�^���T�C�g�W�v�ɂ����āA�n�k�Łu���Ȃ������v��͍����Ă������A�����NPO�A��ƁA�s���A���ƂƂƂ��ɒn�悩��l����ϐk�⋭�Ƃ����u�m�b�ƍH�v�œ������I�v��}���Ă����B
�@��_�W�H��k�Јȍ~�A�����[���A���{�̍ЊQ�����Ƃ̘_�c�͐s�����ꂽ�ł��낤�B �@���A�K�v�Ȃ̂͐��{�̍ЊQ��V�X�e���̊��p���܂߂āA�n��E���Ԏ哱�̖h�Ѓl�b�g���[�N�Łu�m�b�ƍH�v�œ������I�v��}�邱�ƁA���{����ƂɌ��ꔭ�̗L���Ȗh�Б����A���s�����邱�Ƃł���B
�@���҂��A�ЊQ�ɑ������Đ����o���������ŕs���������悤�ȁu����̘_�c�v�ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȋ�����ӌ��Ɏ����X����K�v������B
�@ �@�_�c���d�v�����A����ЊQ�ɔ����A�����o���̏������I
�@
�@
�@�� ����̗\��ɂ��� ��
�@�G�R�v���_�N�c2003 �@
�@�����F 12��11��-13�� �@
�@�ꏊ�F�����r�b�N�T�C�g
�@
���e�F����A�n������(NGO)�ł̓G�R�N���j�b�N�t�F�C�V�X�E���z��w������w�Ȃ̊w���Ɓu�G�R�v���_�N�c2003�v�ɎQ�����A�w���A�m�f�n���q����Z���Ƌ��ɒn��A���X�X�ɂ����Ď��{�\�ȕ��@�Ő������G�R�v���_�N�c�̊��p���s�����Ƃ�W���A���\���܂��B
�@�@�G�R�v���_�N�c2003�̓��u�[�X�@�@
�@ http://xmldb.exism.co.jp/eco2003/search.asp?ID=85r0z
�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@��Q�V��W�F���_�[�Z�b�V���� �u�ق�Ƃɗ����ł���́H�ǂ�������ł���́H�`�d���Ǝq��āE�����̓W�]�`�v �@��w�ŁA�E��ŁA�ƒ�ŁA�q��ĂȂǂ̐����ƁA�d���A�w�Ƃ̗����̌���́A�ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H�l�X�ȑ�w�ɂ�����E����w�������ۈ�T�[�r�X�ɂ��Ă̒����i��؎��j����ɁA��Ƃ̑����Ŋ���{�w�̎Љ�l�@���E�R�Ɏ�����ƎЉ�ɂ�����d���Ɖƒ됶���ɂ��Ă̍őO���̘b����A��w�����łS�l�̂��q����̕��e�ł������c�����j���ɂƂ��Ẳƒ�Ǝd���̗����̎��ۂ����������܂��B
�@���̊F����Ƃ̃t���[�E�f�B�X�J�b�V�����̎��Ԃ��݂��Ă���܂��B�ǂ����A�F���܁A�ӂ���Ă��Q�����������B
�����@���@�P�P���P�X���i���j�P�W���R�O���`�Q�O���R�O��
����@��@������w�r�܃L�����p�X�V���قV�R�O�P����
���u���[�N�E���C�t�E�o�����X�̌���Ƃ��̐�i�I��g�݂̎���v
�E����ҁ@�R�ɐ��q�� �i���������@�o�c���v���Ζ��E������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C�������ȉ@���j �E�R�����e�[�^�[�@��c�b��i������w���w�������j
������w���̌����@��،j�q�� �i������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C�������ȉ@���j
�����@�Á@������w�W�F���_�[�t�H�[���� ������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C��������
���{�Z�b�V�����ɂ��Ă̂��₢���킹�� �@������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C��������
�@����O���[�vhug-kumi E-mail�A�h���X keiko@hev.rikkyo.ne.jp
�W�F���_�[�Z�b�V�����͒N�ł��C�y�ɎQ���ł���A�b�g�z�[���Ȋw�K��ł��B�\�����݂�Q����͈�ؕs�v�ł��B�ڂ����́A���L�܂ł��₢���킹���������B
��������w�W�F���_�[�t�H�[�����ɂ��Ă̂��⍇����
�@�L���搼�r�܂R�|�S�R�|�P�@������w�r�܃L�����p�X�~�b�`�F���قP�K
�@��&�e�����@�O�R�|�R�X�W�T�|�Q�R�O�V �@���������^�^�������D�������������D�����D����
�@
�@
�@
��������������������������������������������������
����P�P���P�W���i�j�R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�E�l�b�g���[�N ������J�Â������܂��̂ł��m�点�\���グ�܂��B ����͂b�a�m���������@�{�i����ɂ����g�̍Ő�[�̊���
�����Љ�������܂��B�e�[�}�́u�s���Ƃm�o�n�̘A�g�v�B �{�ȃe�[�}�ł��ˁI �s���̕����A�m�o�n�̕����A�g�̂�������ꂩ��̕������� �w�Ԑ�D�̋@��Ǝv���܂��B
��������������������������������������������������
�@�R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�E�l�b�g���[�N �@�@�@
�@�Q�O�O�Q�N�x��U�����J�Â̂��m�点 �w�s���Ƃm�o�n�̘A�g�|�v��Z�p�������̎��g�݁x
�@���݁A�����̖������S�̕ω��A�s���̍����N���ȂǎЉ�o �Ϗ̕ω�����s���Ƃm�o�n�̘A�g�̂�������͍�����Ă� ��B�v��Z�p�������i�j�f�j�j�́A���̂�����Ɋւ��钲���ɂ�
���āA��t���A���l�s���������̎����̂ŃR���T���e�B���O�� ���H���Ă���B����́A�j�f�j�����g��ł����t���A���l�s �̒����܂��A����̍s���Ƃm�o�n�̘A�g�̕�������ۑ蓙
�ɂ��ĕ���B
�y�u�t�z�i���j�v��Z�p�������@�@��\������@�{�i�a�v�@��
�y�����z�P�P���P�W���i�j �P�X���O�O���`�Q�O���R�O�����x�i�J��P�W���S�T���j�i�u�`�P���Ԏ��^�����R�O���j
�y�ꏊ�z����c��w�����J���Z���^�[�P�Q�O���قS�|�Q�O�T���� �@�Z���F�V�h�摁��c�ߊ����T�P�R
�@�@�@�@ ����������c�w����k���T��
�y����z�R�T��
�y���z�i�������x�����������j
��ʁF4,000�~�s�������̏Љ�͕s�v�ƂȂ�܂����I�t �@
������F2,000�~ �@�^������F3,000�~ �@�{�����e�B�A����F1,000�~
�u���I������߂��̈��H�X�ō��e��i����F���Ԃ�3,000�~ ���x�j���s���܂��B���s����낵�����͕����Ă��\�����݉������B
�y�\�����ݕ��@�z ����E���e��Q���̗L���� �����O�A�Z���A�A����A���[���A�h���X�L�̏� �����ǁ@�L�����ĂɃ��[���ł��\�����݉������B
���\�����݃��[���A�h���X�@YRP00224@nifty.ne.jp ����̕��͂����O�Ƃ��o���݂̂����m�点�������B
�y���₢������z �b�a�m�����ǒ��@�L���@070-5564-0363 �@�i�\�Ȍ��胁�[���ł��₢�����������j
�u�t�v���t�B�[���F �{�i�a�v�i���Ȃ��@�����Ђ��j 1960�N���܂�A������w�H�w���s�s�H�w�ȑ��ƁB������Ќv ��Z�p��������\������B�Z�p�m�i���ݕ���s�s�y�ђn���v
��j�B�R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�E�l�b�g���[�N�������� �n�������̂̓s�s�v��}�X�^�[�v�����A�Z��}�X�^�[�v�����̍� ��A�n��v�����B��K�͒ᖢ���p�n�̊J���\�z�E�v�����B
�R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�Ɋւ��錤����������Ƃ���B�R�~���j�e �B�E�r�W�l�X�E�l�b�g���[�N�̑n�݂ɌW���B�����W�N���瓌���s �r���̋N�Əm�̃R�[�f�B�l�[�^�[���߂�B
�����F�i��������ꕔ���M�j�ĊJ���n��v�搧�x�̎�����i���傤 �����j�A�V�����s�s���Z�̒�āi�����Ёj�A�C�M���X�̓s�s�Đ��� ���i���y�Ёj�A�܂��Â���L�[���[�h���T�i�w�|�o�Łj�A�V����̓s
�s�v��Q�s���Љ�Ƃ܂��Â���i���傤�����j�A�s���܂��Â���K�C�h �i�w�|�o�Łj�A�n������C�ɂ���R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�i���傤�����j
������������������������������ C.B.N. �R�~���j�e�B�E�r�W�l�X�E�l�b�g���[�N
�@�@http://www.cbn.jp �@�@�����ǒ��@�@�L���@�C �@�@�@YRP00224@nifty.ne.jp �@