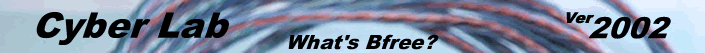
−まちづくりのあらたな展開を求めて−13
コミュニティ・ビジネスという言葉も定着してきました。
コミュニティ・ビジネスの提唱者の細内信孝氏(C.B.N.コミュニティ・ビジネス・ネットワーク理事長)によるとコミュニティ・ビジネスとは
「住民自らが自分たちの地域を元気にするために、あるいは地域の問題を解決するために、主体的に取り組んでいる事業」
「地域を元気にするコミュニティ・ビジネス」細内信孝
つまり、コミュニティ・ビジネスとは「地域での住民による住民のための事業」だと思います。 さて、現在コミュニティビジネスの講座も数多く実施されています。
今月、東京大田区の大田文化の森でも「コミュニティ・ビジネス入門講座」(大田文化の森運営協議会 、C.B.N.コミュニティ・ビジネス・ネットワーク
共同開催事業)が開かれました。
「『コミュニティ・ビジネス』について勉強する講座です。地域 の人による地域の元気づくりビジネスとして注目を集める『コミュニティ・ビジネス』とは?
地域や自分の『元気づくり』に取り組みたい方、地域へ関わりながら仕事をしたいと思っている方、地域の課題や問題の解決方法を探している方、必修の講座です!
」
「地域も元気!私も元気!コミュニティ・ビジネス入門講座」大田文化の森
この講座は大田文化の森で開催され、私も大変お世話になっている大田区在住のC.B.N.コミュニティ・ビジネス・ネットワーク事務局長の鵜飼修さんが講師となり行われました。
この講座のあり方自体がまさに「地域での住民による住民のためのもの」でした。
まず、大田区の大田文化の森は一般的にみれば生涯学習センターと文化施設の複合施設ですが、市民参加による運営が特色です。
具体的には、講座・イベント企画実施はテーマ毎に実行委員会をつくり文化プレーヤーの中のディレクターが文化会議・役員会の承認を得て行い、講師やイベンターの選定を行い、サポーターやボランティアが実施をサポートします。また、区民からの公募企画や事業企画も積極的に進められています。
今回の「コミュニティ・ビジネス入門講座」もこのよう形で開かれたものでした。
次に、講師の鵜飼修さんは会社勤めの傍ら、コミュニティ・ビジネスの実践活動に多く携わり、九州などでまちづくりも行われている方です。また、この頃は大田区のまちづくりにも参加されており、そのこともあってこの講座を開催されました。
さて、講座は三回でしたが、コミュニティ・ビジネスの基礎から、コミュニティ・ビジネス実践者のお話を聞き、最後は簡単な事業企画書づくりまで行いました。
この最後の簡単な企画書の発表でこんな実例がありました。
その参加者の方は大田区にビオトープ(生き物の生息・生育園)をつくることで子供たちや地域の人が自然と親しむことを目的に活動されているそうです。大田区にはビオトープ(生き物の生息・生育園)が無いので、子供たちや区民のためになるので区役所にこれをつくるように何回も陳情しても相手にしてくれないとのことです。この「地域の問題を解決」するためにはどうしたらいいのか分からないのでこの講座に参加したということでした。
鵜飼さんは陳情という考え方をやめてビオトープ(生き物の生息・生育園)を事業として考えることを提案し、その参加者の方の想いから事業可能性までを丁寧に聞き出し、いろいろなアドバイスをされました。
その参加者の方がこのアドバイスを聞いて、このようなことを話し合える場所が必要だと発言したのを鵜飼さんが受けて大田文化の森でコミュニティ・ビジネスのサロンを継続的に開催することを提案されました。
まったく、最初から最後まで見事なまでの「コミュニティ・ビジネス」の展開でした。
さて、「まちづくりのあらたな展開」の13は「コミュニティ・ビジネス」です。
「コミュニティ・ビジネス」には多様な定義があり、それはそれでいいのだとは思いますが、やはり「コミュニティ・ビジネス」の基本は「住民自らが自分たちの地域を元気にするために、あるいは地域の問題を解決するために、主体的に取り組んでいる事業」でしょう。
まちづくりにおいても、先ほどの方のように地域のためといいえ、陳情ばかりしているようでは物事は進みません。だからといって、安易に地域の事業を民間委託を行うことでも問題は解決しません。それは民間委託では委託されている企業(営利企業)は市場原理の基準で儲からないものはやらないか、やっていても撤退してしまうからです。
そのためには住民が行政にだけに頼ることなく、市場原理とは別の価値で、地域のために事業として行う「コミュニティ・ビジネス」が必要となります。
また、この意味で、これからのまちづくりのある部分はこのような「地域での住民による住民のための事業」を行うということてはないでしょうか。
参考「新しい社会起業」(1/9号 「新しい社会起業」)
今回も関係者、特に鵜飼修さんと大田文化の森のみなさん感謝します。
鵜飼修さんが九州で行われているまちづくりです。
大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブ
炭鉱のまちの地域資源を活かした、まちを元気にする様々な活動の提案・実施
主な活動 地域事業活動、
イベント活動、研究・勉強会、芸術文化活動、調査研究活動
福岡県大牟田市、熊本県荒尾市を中心に広がる「三池炭鉱」関連の産業遺産の保存・活用を通じたまちづくりに取り組む市民団体です。
炭鉱のまちの地域資源を活かした、まちを元気にする様々な活動の提案・実施を通じて、20世紀の日本を支えた「炭鉱のまちの風景・心象を次世代へ継承する」ことを目指します。
連絡先 大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブ
〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町150 有明工業高等専門学校 建築学科 新谷研究室 気付
omuta-arao_fun-owner@egroups.co.jp
サイトhttp://homepage2.nifty.com/omuta-arao_fun/