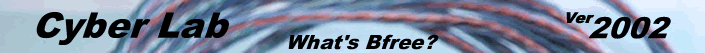
すべての人に思いやりを持った、やさしい、気持ちのこもったシンボル
1月23日に彩の国さいたま芸術劇場(さいたま市)の周辺は雪が降りました。最寄り駅でも駅前の通路はある程度雪かきされていましたが、スロープは凍結による危険防止のため使用禁止になっていました。
この雪の中、「第2回ユニバーサルデザイン全国大会in埼玉」は「ハートいっぱい、まち・もの・くらしづくり」をテーマに開催されました。
「まちづくりとユニバーサルデザイン」をテーマにした第1分科会では座長の田中直人氏(摂南大学工学部教授)が駅前のスロープの凍結の話から、ユニバーサルデザインを取り巻く全体の状況のについて述べられました。 それから、まず、砂川敏文氏(北海道帯広市長)が「帯広オリジナル」「雪国仕様」といった地域特性のあるユニバーサルデザインを行政と市民が協働して行うことを、石川紀文氏(アクセシブル盛岡代表)はユニバーサルデザインによって自分たちが楽しく遊べるまちづくりを目指すお話がありました。
また、森崎康宣氏(わだちコンピューターハウス主任研究員)はユニバーサルデザインを掲げた愛知県の中部国際空港に対して基本構想の段階から障害を持っている人の設計への参画を空港管理会社に提言し、障害を持っている人、設計者、空港管理会社・航空会社の協働によるユニバーサルデザイン実現という大変な事例を、興津吉彦氏(埼玉県新都心調整室長)はやはり新都心建設のユニバーサルデザインや建設後の取り組みについてご報告頂きました。
当日、雪が降ったからだからではないですが、埼玉のように雪の少ない地域と帯広や盛岡のように雪の多い地域との「ユニバーサルデザイン」にも違いについて語られ、「ユニバーサルデザイン」にも地域性があり「ユニバーサル」であっても地域性に配慮した多様な取り組みが重要であるということが論議されました。また、中部国際空港に対する障害を持っている人の設計参画の中でもそうですが、障害を持っている人に限らず、多様な障害をどのように捉えて調整していくことなどが重要なポイントでした。
「ものづくりとユニバーサルデザイン」「くらしづくりとユニバーサルデザイン」の分科会でもそれぞれ活発な報告や論議がなされ、それを受けて総合シンポジウムでは重要な論議が展開されました。
その中で会場から、小澤勇氏(さいたま市の身体障害者福祉会青年部)の災害や非常時の対応とユニバーサルデザインの問題が提起され、その重要性が確認されました。
そして、これからのユニバーサルデザインについて 日常の中でのユニバーサルデザインはこれからも議論を積み重ね進歩しつづけるであろう。阪神大震災の例もあるが、今後は災害時・非常時のユニバーサルデザインも真剣に議論をしていかなければならない。 という展望が開けました。(詳細は下記のサイトをご覧下さい。)
「第2回ユニバーサルデザイン全国大会in埼玉」
http://www.pref.saitama.jp/A02/BP00/universal/universaltop.html
この他にもたくさんのプログラムがありましたが、市民(県民)参加による報告が二つありました。
ひとつは、さいたま市立西浦和小学校での「小学校におけるユニバーサルデザイン・ワークショップ」による「学校のユニバーサルデザインマークをつくろう」の活動で、森田ひろみ先生と生徒さんによる発表が行われました
生徒さんの感想−「みんなが一目見てわかるようにマークを考えるのはとても大変でした。ユニバーサルデザインとは、すべての人に思いやりを持った、やさしい、気持ちのこもったシンボルのようなものだと思いました。」
http://www.pref.saitama.jp/A02/BP00/universal/zenkoku/youshi.htm
もうひとつは、私も参加した大人の「岡目八目隊」による埼玉県内各地での「まちのユニバーサルデザイン」の調査で、岡目八目隊を代表して、川口市在住の小田清美さんが発表されました。
この「岡目八目隊は車いすの方、看護士、主婦など様々な立場の人で構成され、買い物客の目線に立った調査活動がなされました。調査の結果について、商業主の方々との意見交換会が行なわれました。」 (この点についてはとてもここでは語り尽くせないので引用にとどめておきます。)
http://www.pref.saitama.jp/A02/BP00/universal/zenkoku/youshi.htm
この「第2回ユニバーサルデザイン全国大会in埼玉」ではこのような会議や発表の内容も重要でしたが、この大会自体を「だれもが参加しやすいユニバーサルデザインの考え方を活かしたやり方」で開催したことが意義があったと思います。会場へのアクセス、会場の配置、各種サイン、手話通訳はもちろん、スクリーンに表示されるパソコン要約筆記、音声ガイド、男女の区別のためのトイレの芳香剤まで配慮が行き届いていました。
しかし、何よりも数多くのボランティアの方々がユニバーサルデザインへの考慮の欠けた今回の会場の建物(「デザイン的には優れている」建物なのでしょうが)を補い、細やかに多くの人の力となって、一番大切な「ホスピタイリティ(気遣い・おもてなし)によるユニバーサルデザイン実現」をはかっていました。
参考 「だれもが参加しやすいユニバーサルデザインの考え方を活かした会議・講演会実施ガイド」
埼玉県(総合政策部文化振興課ユニバーサルデザイン担当)
http://www.pref.saitama.jp/A02/BP00/universal/2002_july/media/contents.pdf
さて、「まちづくりのあらたな展開」の七つめは「ユニバーサルデザイン」です。
「ユニバーサルデザイン」については過去何回かこのレポートでも(2002/1/31号「有田焼のインパネ」など)お伝えしてきました。「国籍、年齢、性別、障害の有無にかかわらず誰もが使いやすいように施設、商品(環境、メディア、ソフ トフェア、サイト)などをデザインする」 ユニバーサルデザインは今までは商品や施設などの分野が先行してきました。
これからは今回の大会の運営のように、まちづくりはもちろん、イベント、施設運営や日常のいろいろな活動にも積極的に取り入れていくことが重要になってきました。
また、今までの「ユニバーサルデザイン」は「ユニバーサル」を求めるあまり、地域性を捨象したり、生活感覚に乏しかったり、「バリア・障害というカデコリー」でしてしか捉えないような傾向がありましたが、これからは地域性や多様な障害や生活のあり方を前提に日常的生活感覚で調査検討したものが求められてきます。
これから、まちづくりを多様な人で推進するためにはユニバーサルデザインが必要不可欠てす。
しかしそれは、「まちづくりのためのユニバーサルデザイン」ではなく、「まちづくりはユニバーサルデザイン」であり、「ユニバーサルデザインのためのまちづくり」でもなく「ユニバーサルデザインはまちづくり」という方向ではないでしょうか。
そして、「まちづくり・ユニバーサルデザイン」を進めるために一番重要なのは今回のボランティアの皆さんのようにホスピタイリティ(気遣い・おもてなし)によるユニバーサルデザイン実現ではないでしょうか。
最後に、この点を素直に表現した西浦和小学校の生徒さんの発表の”ことば”でこのレポートを終わりたいと思います。
「ユニバーサルデザインとはすべての人に思いやりを持った、やさしい、気持ちのこもったシンボルのようなものだと思いました。」
最後に主催者、事務局、講演者、参加者、すべての皆さんに感謝します。
特に、ユニバーサルデザインの考え方を活かした会場運営をされたボランティアの皆さん、またボランティアの皆さんと一緒に活動されたバリアフリーシアタージャパンの皆さん、そして、一緒に調査をさせて頂いた「岡目八目隊」の皆さん及び関係者に深く感謝します。
第34回全国ボランティア研究集会・山形県庄内集会
同集会実行委員会
年に一度、全国各地でボランタリーな活動に取り組む人びとが、 世代や分野、立場の違いを超えて大集合し、交流や情報交換を行う場です。
全V研は、草の根のボランティアの、ボランティアによる、ボランティアのための集会です。
先駆的な事例に学び、生き方・想いを伝えあい、これからの指針と暮らしのあり方を模索します。
2月9日(日)
場所 鶴岡市文化会館 12:30〜
受付開始 13:30〜13:45
オープニング 13:45〜16:30
開会式〜全体会 16:30〜
各分科会開催地へ移動〜交流会 庄内地域14市町村
2月10日(月)
場所 分科会 庄内地域14市町村 9:00〜17:00 17:00〜
分科会から移動 18:30〜 大交流会 鶴岡市(湯野浜温泉)
2月11日(火・祝)
場所酒田市総合文化センター
9:00〜12:00 全体会〜閉会式
社団法人日本青年奉仕協会
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL:03-3460-0211 FAX:03-3460-0386 Mail:program@jyva.or.jp
http://www.jyva.or.jp/program/nvc/syounai_index.html