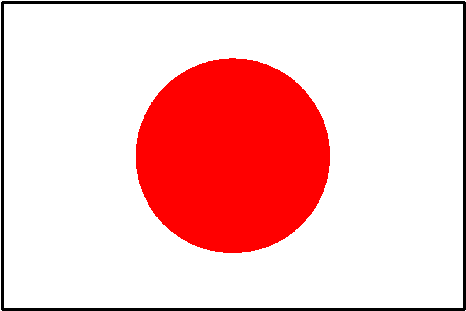 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › プロジェクトの概要 › 日中双方の合意事項 › 日中合同中間評価報告書(2004.03.18) |
中華人民共和国
黒竜江省酪農乳業発展計画
日中合同中間評価報告書
2004年3月18日
哈爾濱市
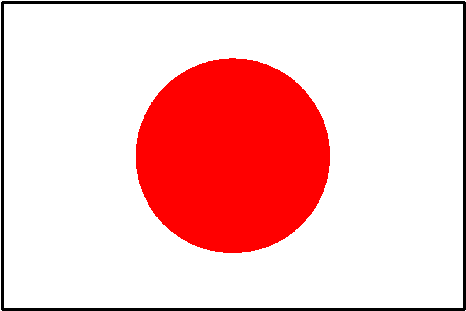 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › プロジェクトの概要 › 日中双方の合意事項 › 日中合同中間評価報告書(2004.03.18) |
|
|
中国政府は国家開発第9次5カ年計画(1996年〜2000年)において、食糧増産を中心とする農業の発展、増強を重視しており、これを受けて黒竜江省政府は、「黒竜江省を農業大省から農業強省へ転換し、全国の農業生産基地とする」という目標を掲げている。
黒竜江省は、寒地で冬期間が長いことから、畜産業が年間を通じて収入を得ることができる産業として期待されている。他方、黒竜江省は広大な草地面積と未利用飼料資源を有していることから、酪農が盛んであり、牛乳と乳製品の生産量は全国第一位となっている。黒竜江省政府としても、酪農乳業の発展を重視しており、「半壁江山(農業に占める畜産業の割合を半分にする)」のスローガンの下、酪農乳業の振興に努めているが、牧草の質が低い、一頭当たり乳量が低い、飼料の開発が遅れている等の問題をかかえている。
かかる状況から、中国政府は1996年8月、日本国政府に対し、酪農と乳製品の製造技術に関する新技術の開発研究を行うプロジェクト方式技術協力を要請してきた。
この要請を受けて、日本側は2001年4月に実施協議調査団を派遣し、プロジェクト実施に係る討議議事録(R/D: Record of Discussions)が署名され、同年7月1日から長期専門家が派遣され、5年間の技術協力が開始された。プロジェクト開始後は、2002年4月と2003年1月に、それぞれ運営指導調査団が派遣され、具体的な活動計画(PO)が策定された。
今般、プロジェクト協力期間の中間点(3年目)に達したため、プロジェクトの開始から現在までの進捗状況を日本側、中国側合同で評価し、円滑なプロジェクト運営に資するよう適切な助言・指導を行うために運営指導(中間評価)調査を実施することとなった。
| 上位目標:酪農乳業の発展を通じ、黒竜江省の酪農家の所得が向上する。 | |
| プロジェクト目標:黒竜江省に適した酪農乳業モデルが確立する。 | |
| 成果:1. | モデル地域の酪農家が良質な飼料を生産できる。 |
| 2. | モデル地域の酪農家が乳牛の適切な飼養管理を行えるとともに生乳の品質が向上する。 |
| 3. | 乳製品の品質向上・多様化が図られる。 |
| 活動:1. | 飼料生産 |
| 1-1.小規模な草地改良技術 | |
| 1-2.未利用資源の飼料化技術 | |
| 1-3.サイレージ調製技術 | |
| 1-4.飼料分析技術* | |
| 1-5.アルファルファ採種技術* | |
| 1-6.モデル牧場における飼料生産技術の実証展示 | |
| 2. | 飼養管理 |
| 2-1.乳牛の飼養管理技術 | |
| 2-2.搾乳衛生管理技術 | |
| 2-3.受精卵移植技術* | |
| 2-4.モデル牧場における乳牛の飼養管理技術の実証展示 | |
| 3. | 原料乳品質管理 |
| 3-1. 原料乳の品質管理技術 | |
| 4. | 乳製品製造 |
| 4-1. 乳製品製造技術 | |
| 4-2. 乳酸菌収集、保存及び培養技術 | |
| (1) | プロジェクト開始から現在までの実績と計画達成度をR/D、PO及びPDM(2003年2月承認版)等に基づき、評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性)に沿って日本側・中国側双方で総合的に調査、評価する。 |
| (2) | プロジェクト後半の活動計画について協議し、必要な助言を行い、必要に応じて計画の修正を行う。 |
| (3) | 円滑なプロジェクト運営のために取るべき措置について協議し、結果を日本、中国両国政府及び関係当局に報告・提言する。 |
JICAにより組織された日本側評価調査団と、黒竜江省の関連機関により組織された中国側評価調査団は、中間評価を実施し、必要な提言を行うために合同評価委員会を結成した。
中国側の評価委員の選任にあたって、本来であれば直接プロジェクト活動に参加しているC/P及びC/Pに準ずる関係者は除外すべきであるが、日中間の事前調整が今回の合同評価開始時点までに整わず、結果的にプロジェクト活動に深く関与している関係者を選任せざるを得なかった。しかしながら、合同評価委員会は、評価活動及び評価結果の取り纏めに際し、公平性・中立性が十分確保されるよう最大限努力した。
| 日本側評価委員 | ||
| 総括 | 中川 和夫 | 独立行政法人国際協力機構 農業開発協力部長 |
| 酪農振興 | 工藤 茂 | 独立行政法人家畜改良センター岩手牧場 種畜課長 |
| 乳製品 | 齋藤 芳孝 | 雪印乳業株式会社国際部企画グループ 課長 |
| 計画管理 | 中堀 宏彰 | 独立行政法人国際協力機構農業開発協力部畜産園芸課 職員 |
| 通訳 | 松井 美穂 | 財団法人日本国際協力センター研修監理部 研修監理員 |
| 中国側評価委員 | ||
| 総括 | 張 秀鳳 | 黒竜江省畜牧局 副局長 |
| 計画管理 | 李 凡 | 黒竜江省科学技術庁国際合作処 処長 |
| 酪農振興 | 于 徳平 | 安達市先源郷 郷長 |
| 乳製品 | 冷 贏 | 国家乳業工程技術工程センター生産部門品質検査部 エンジニア |
| 通訳 | 田 静 | 乳業サイト通訳 |
| 李 高 | 酪農サイト通訳 | |
合同評価委員会は、PCM手法に基づき以下に掲げる評価5項目による分析の観点から評価調査を実施し、合同評価報告書を取りまとめた
| 3/9 | 日本人専門家(打ち合わせ) 第1回合同評価委員会(評価方法説明) |
| 10 | 黒竜江省科学技術庁、畜牧局(表敬) 安達市畜牧局、先源郷政府(調査) |
| 11 | 安達市近郊酪農家、集乳所(視察) 安達市先源郷友誼牧場(酪農サイト実績確認調査、C/Pによる活動報告) |
| 12 | 黒竜江省畜牧研究所(調査) |
| 13 | 移動 |
| 14 | ハルピン近郊酪農家・集乳所視察 日本人専門家(打ち合わせ) |
| 15 | 国家乳業工程技術研究センター(乳業サイト実績確認調査、C/Pによる活動報告) 実施管理室調査 |
| 16 | 第2回合同評価委員会(調査結果報告、合同評価報告書案作成) |
| 17 | 第3回合同評価委員会(合同評価報告書案協議) |
| 18 | 第4回合同評価委員会(合同評価報告書署名) 合同調整委員会(合同評価報告書説明、質疑応答、ミニッツ署名・交換) |
中間評価に当たっては、2003年2月に開催された合同調整委員会により承認された現行PDMを使用した。
合同調整委員会は日中両国のプロジェクト関係者との意見交換を通じ、現行PDMの一部修正の必要性を認識した。修正は、プロジェクトの基本方針等の大枠は変更せず、よりわかりやすい表現に変更するなど軽微なものが中心となっている。また、未設定であった成果3の一部の指標の数値目標も加えた。合同調整委員会は現行のPDMを附表1に示すPDM(案)に修正することを提案する。主な変更箇所は以下の通り。
プロジェクト開始から本調査時まで、プロジェクト活動に必要な資機材及びローカルコストとして2,199万元を負担した。
協力実施に当たり、討議議事覚書に沿って各活動分野にかかるカウンターパート、プロジェクト運営管理責任者及び必要とされた通訳を含む延べ84名を配置した(附表5参照)。
協力に必要な友誼牧場及び国家乳業行程技術研究センターの土地、建物、専門家執務スペース及び必要な施設を提供している。
プロジェクト開始から調査時点までに、一般現地活動費、現地適用化活動費及び施設整備費として総額約1,510千元(約2000万円)相当を負担している。
2001年7月1日から調査時点までにチーフリーダー、業務調整員を含む各分野の長期専門家延べ10名と各分野の短期専門家延べ16名が派遣され、さらに1名の短期専門家が今年度派遣予定である。
プロジェクト開始から調査時点までに各分野でカウンターパート19名が日本で研修を受け、さらに1名の本邦研修が今年度実施予定である
プロジェクト開始から調査時点までに約17,304万円相当の機材が供与された。また、長期・短期専門家派遣に伴い必要となる携行機材として1,118万円相当が供与された。
附表8のとおり、成果1「モデル地域の酪農家が良質な飼料を生産できる」の各活動は、1-1、1-2及び1-6を除いて概ね予定通り実施された。
活動1-1「小規模な草地改良技術」については2003年度の天候不順(前半の旱魃、後半の多雨)の結果、大型機械体系での実証は実施できなかったため、2004年度より実施する。
活動1-2「未利用資源の飼料化技術」についても天候不順の影響の他、尿素処理によるサイレージ調製技術の現地適用化試験の実施回数が少ないため、2004年度に継続して実施する。
活動1-6「モデル牧場における飼料生産技術の実証展示」に関しては、確立した技術体系をもとにマニュアルを作成することになっており、活動1-1、及び1-2の進展に伴って活動を本格化させる。また、酪農家や酪農指導者層にモデル牧場の存在と意義がまだ十分に知られていないため、安達市畜牧局を通して酪農関係者の来訪を促す。
成果2「モデル地域の酪農家が乳牛の適切な飼養管理を行えるとともに生乳の品質が向上する」では、除角、削蹄等の基本技術を着実に定着させるとともに、乳房炎の検査技術がC/Pに移転された。しかしながら、新牛舎建築の遅れ、機材供与の遅れにより搾乳牛管理に関する諸技術の移転が遅れているため、2004年度に継続して実施することとする。特に、乾乳・分娩牛管理に関しては新牛舎建築の遅れに加えて、ミルキングパーラーの稼働の遅れにより搾乳牛との分離管理が出来ず技術移転が遅れている。また、活動の遅れに伴って各種管理マニュアルの作成も遅れているため、活動のペースを早める必要がある。
活動3-1「原料乳の品質管理技術」に関し、国家乳業工程技術研究センターの生産部門(以下生産部門とする)へ牛乳を供給しているハルピン市近郊の集乳所の状況及びその原料乳品質の現状を把握するなどベースライン調査はほぼ完了した。また、C/Pを日本に派遣して、日本の乳業メーカー及び酪農関係の協同組合での原料乳品質管理を習得させるなど、C/Pの基礎知識の習得に務めている。個別検査技術として搾乳衛生指導に関し、酪農サイトの専門家と連携をとって、ハルピンの酪農家に対して指導を行っている。地域とサイトを超えた協力が、このプロジェクトの活動の中で醸成されてきている。 なお、生産部門では、工場の原料乳受け入れ検査標準が確立し、乳製品製造に適さない乳質、例えば抗生物質を含む生乳は、発酵乳製造に回さないなどの対応が取られるようになった。受け入れた原料乳から、抗生物質が検出される頻度は、いまだ30%ほどあり、今後の原料乳品質管理の強化が必要である。
さらに、今後開発されるチーズと発酵乳の新製品の製造に適する原料乳の調達確保には、今後一層の指導と改善が必要である。
活動4-1「発酵乳製品製造技術」のうち発酵乳部門ではSARSによる渡航制限により、C/P研修及び短期専門家派遣が6ヶ月間中断し、発酵乳製造の技術移転は停滞した。その後、渡航制限の緩和により短期専門家によるスタータ製造技術の指導と発酵乳に関する講義を実施し、C/P研修によるスタータ製造技術習得のフォローアップを行実施した。また、2004年4月には短期専門家による機能性乳酸菌に関するセミナーが予定されている他、発酵乳製造の試作機器も到着予定であることから、プレーンヨーグルトやバラエティヨーグルトの試作開発が可能となり活動の遅れを十分取り戻すことが可能である。
チーズ製造部門ではC/Pに対し、本邦研修によるチーズ製造に関する基礎的な技術移転を行った。また、短期専門家派遣によりプロセスチーズ製造技術とナチュラルチーズ製造技術に関する技術指導を行うとともにC/Pの技術の定着度をフォローした。
なお、ナチュラルチーズの試作は繰り返し実施され、長期専門家からC/Pへチーズ製造技術の伝承が行われつつある。ナチュラルチーズ製造の基本技術は、将来中国国民の味覚嗜好にあったプロセスチーズ開発に対して、重要なノウハウとなると考えられる。
乳酸菌収集、保存及び培養技術部門に関しても本邦研修と短期専門家の派遣の組み合わせにより、乳酸菌収集技術に関してC/Pに基礎的な技術移転がなされた。また、クリーンベンチ、インキュベーター、凍結乾燥機、凍結庫など必要な装置機材は、導入が遅れたもののすでに設置は完了しており、菌株のスクリーニング、培養及び保存の技術はC/Pに移転された今後の技術移転は順調に実施されるものと期待される。
乳酸菌収集、保存及び培養技術は、将来、乳製品製造の品質管理、オリジナル製品の開発及び製造コストの削減にとって重要なノウハウとなると考えられるため、引き続き地道に技術移転していく必要がある。
プロジェクト開始当時のモデル地域で生産されたコーンサイレージ用トウモロコシ生産量は2,500kg/ムーであったが、調査時点では3,000kg/ムーに増加している。また、モデル地域で生産された乾草生産量は340kg/ムー(プロジェクト開始当時)であったが、2003年度の天候不順の影響で200kg/ムーであった(なお、コ―ンサイレージ用トウモロコシは先源郷3牧場実績、乾草生産量は友諠牧場生産実績である)。
モデル地域における乳牛1頭当り平均乳量は5,300kg(プロジェクト開始当時)であったが、調査時点では5,422kgに向上している。また、モデル地域で生産される生乳の総菌数は200万個/ml(プロジェクト開始当時)であったが、120万個/mlに減少し乳質が改善された。モデル地域で生産される生乳の全固形分率については11.6% (プロジェクト開始当時)であったが、11.7%で僅かに向上している。
生産部門では、受け入れ時に原料乳の官能検査を実施し、正確な温度測定を行うことを製造標準化したことで、最終製品の品質向上に係わる基礎的な製造条件を確立した。特に、発酵乳製造部門では、ヨーグルトの酸度のバラツキ(標準偏差)を小さくし、安定した商品が製造できるよう改善の努力を行っている。これらの試みは、生産部門の乳製品の品質向上に貢献する成果である。
チーズ製造部門では、5種類のナチュラルチーズの試作開発を延べ30回実施し、そのナチュラルチーズや輸入チーズを原料に、90品のプロセスチーズの試作開発を行った。これらの試作開発作業を推進しながら、将来オリジナリティのある商品化候補を提供するための基礎的な製品開発システムを確立しつつある
上位目標及びプロジェクト目標に関し、2001年に発表された「中華人民共和国国民経済・社会発展第十次五ヵ年計画」(2001〜2005)とそれに連動している「黒竜江省国民経済・社会発展第十次五ヵ年計画」(2001〜2005)において農業が重視されており、「農民収入増加」及び「農業強化」の重要性が強調されている。また、黒竜江省の五ヵ年計画のうち、酪農乳業の発展を促すために制定された「黒竜江省酪農乳業振興計画」(2002〜2005)においては、酪農乳業の振興を通じた農民の増収・農業と農村経済構造の調整を目標としている。さらに、黒竜江省安達市政府でも乳業の発展を開発の柱とする「安達市原料乳基地建設発展優遇政策」が策定されており、当プロジェクトの位置付けは国家の開発政策及び地方政府の開発政策と整合性がある。
特に、2004年3月に開催された全国人民代表大会では「農業の基礎的な地位を強固なものとし、農民の増収と食糧の増産を実現する」ために、5年後をめどに農業税を廃止する方針が示されるなど農村の経済的弱者の救済に力点が置かれている。本プロジェクトのターゲットグループのほとんどが飼養規模1〜3頭程度の零細酪農家であり、経済的にも弱い立場に置かれていることから、本協力の実施は妥当といえる。
聞き取りをした先源郷の酪農家は経営規模の拡大を願っていること、酪農に代わる有望な産業がないことから酪農家のニーズが高いことがうかがえる。また、安達市の乳業会社が乳業サイトの日本人専門家にチーズ製造技術について問い合わせるなど、プロジェクトの成果への関心が高い。
日本としては、2001年に策定された「対中国経済協力計画」で貧困克服のための支援を協力の大きな柱の一つとしてあげ、また、JICAの対中国国別事業実施計画においても都市・農村構造調整の一環として「地域間格差の是正」を重点課題としているなど、日本の援助政策とも整合性がある。さらに、日本の酪農も昔は少頭飼いであり、徐々に規模拡大を実現したことから、日本の経験を十分に活用することができるものと思われる。
活動及び成果はある程度順調に進展しているものの、中間評価時点ではプロジェクト目標は達成されていないため、有効性を実績で評価することはできなかった。現時点では、プロジェクト目標達成のための新たな成果の設定の必要性もプロジェクト目標達成の障害となる外部条件も認められない。
プロジェクト活動実施にあたり、機材調達の遅れ、SARS発生による専門家派遣、本邦研修実施の延期等いくつかの阻害要因はあったものの、日本側の投入は効率よく実施された。また、中国側も、C/Pの配置、施設整備費、ローカルコスト等十分な投入を行った。
投入規模に関しては日中双方かなりの投入を実施しているが、実施サイトが2つに分かれていること、関係機関が多数であること、協力分野が酪農分野から乳業分野と幅広いこと等、プロジェクトの特殊性のためであって、不必要な投入は見あたらなかった。
酪農、乳業両サイトの活動のモニタリングは月に一度開かれるサイト毎のC/P会議によって実施されており、活動実施に当たり効果的に活用されている。また、両サイト間の意見交換は半年に一度開催されるモニタリング委員会でなされている。
プロジェクト目標が達成される際の負のインパクトは今のところ予測されない。
プロジェクト目標である酪農乳業モデルが対象地域で確立し、中方がプロジェクト終了後に必要な対応(普及の実施等)を取り、対象地域を越えて広く普及されれば、酪農家の収入増加につながることが十分見込まれる。また、酪農セミナー開催により、酪農家の酪農経営安定及び酪農技術向上の関心は高くなるなど大きなインパクトを与えている。さらに、乳業関係者からの問い合わせが増えており、乳業セミナーによって更なる波及効果が期待される。
友誼牧場及び国家乳業工程技術研究センターは既存の組織であり、今後も継続して存続する機関である。また、日本で研修を受けたC/P及び専門家から技術移転を受けたC/Pの定着率が高い。プロジェクト開始から現在まで中国側の予算措置も十分なされていることから、プロジェクト後半及び終了後も安定的に予算措置がなされ、政策的にもその方針が維持されれば自立発展の見込みは高いと思われる。
しかし、実施管理室は今回の日中協力プロジェクトの為に臨時的に黒竜江省畜牧局内に設置された部署であり、行政組織内での明確な位置づけが永続性を含め明確でない。終了時評価時までに中国側が策定する普及計画の中で、この実施管理室をどの様に位置付け、その機能権限等は如何なるものかを含め、明確にする必要がある。 なお、2004年3月に開催された全国人民代表大会では5年後をめどに農業税を廃止する方針が示されるなど農家支援に関する政策的な支援が整いつつある。
合同評価調査団は日中のプロジェクト関係者との意見交換及び現地視察を踏まえ、評価5項目に沿ってプロジェクトを評価分析した結果、施設建設及び機材調達の遅れ、天候不順及びSARS等の影響により一部の活動が遅延したものの、中日両国関係者の努力により、プロジェクトはほぼ予定通り進展していることを確認した。技術移転に必要な基本的な施設整備及び機材調達がほぼ完了した状況の下、プロジェクト後半期は、技術移転を中心に活動を実施することになるが、次章に述べる提言に留意しつつ酪農乳業両部門の活動を実施すれば、2006年6月までのプロジェクト協力期間内にプロジェクト目標の達成は十分見込まれる。
附表1に示すPDM変更案を合同調整委員会に提案する。合同調整委員会で正式に変更承認を受けた後、プロジェクトは以下に述べる点を早急に検討すべきである。
プロジェクト関係者にとってPDM及びPOの利用は単なる義務ではなく、適切に利用された場合には効果的かつ効率的なプロジェクト運営のための手段となる。プロジェクトの全関係者がその手法を理解し、プロジェクト運営のために利用することがプロジェクト目標の達成のために不可欠である。また、残された期間でプロジェクト目標を達成するには、成果の達成度を適切に管理する必要がある。具体的な方策としては、プロジェクトの成果を定期的にモニタリングし、情報の収集者、情報の集約者、情報の判断者、判断結果のフィードバック先を明確に決めておくことが重要であり、それらを含んだ成果管理システムを早急に確立すべきである。
合同評価委員会が提案したPDM(案)の上位目標を達成するためには、プロジェクトによって確立される、「酪農乳業のモデル」を如何に普及させるのか、その具体的計画を2006年1月頃予定されている終了時評価までに、中国側が主体となり策定する必要がある。普及計画の策定にあたっては、以下の点に留意する必要がある。
日中双方は、マスコミ、ホームページ、セミナー等あらゆる手段を通じて、酪農、乳業関係者のみならず一般国民を含めて、本プロジェクトに関する広報活動を引き続き積極的に展開する必要がある。
本プロジェクトのように、多くの機関が参加し、その連携が不可欠となるプロジェクトでは、プロジェクト全体の調整を担う合同調整委員会、実施管理室の役割は大きく、これに対する日本側専門家チームの指導、助言も重要である。
これらの総合調整機関を十分に機能させるためには日中双方の緊密な連携が不可欠である。