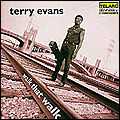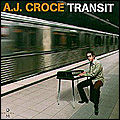2000.5.20

|
 |
Binaural
Pearl Jam
(Epic) |
|
for What's In? Magazine
過去5枚のアルバムからの曲を万遍なく取り上げ、パール・ジャムの強く太いグルーヴが時代に左右されないものであることを雄々しく主張してみせた傑作ライヴ盤が出たのが一昨年暮れ。去年の夏には新作の録音にとりかかったというニュースが流れ、10月に行なわれたブリッジ・スクール・ベネフィット・コンサートではシングル「ナッシング・アズ・イット・シームズ」を含む新曲が数曲披露され……。
インターネットのニュースサイトから次々送られてくるEメールでは収録曲が徐々に固まっていく様子を体験することもできた。じわじわとファンの期待を高め、ついにその全貌を明らかにした7作目だ。健康問題で脱退したジャック・アイアンズに代わって前ライヴ盤に参加した元サウンドガーデンのマット・キャメロンがそのままメンバーとして正式加入。ここ数作続いたブレンダン・オブライエンとのコンビネーションをいったん解消し、チャド・ブレイクにプロデュースを依頼しているのも新味か。
チャド・ブレイクとパール・ジャムとの相性については賛否分かれそうだが、ニール・ヤングとともに今や唯一グランジという方法論を有効に機能させている得難い存在としてのパール・ジャムも、彼らなりの試行錯誤を続けているわけだ。エディ・ヴェダーはもちろん、ジェフ・アメントを中心に他のメンバーもなかなかいい曲を提供。チャド・ブレイク独特のくすんだ音像とのマッチングも面白い。轟音の裏側に見え隠れする切なさに胸が震える。
|

 |
Swagger
Flogging Molly
(Side One Dummy) |
|
素性はまったく知りません。女性フィドラーを含む7人組。スティーヴ・アルビニの指揮のもと、シカゴで録音されたものだけれど、音のほうは音圧ぶいぶいのオルタナ・ケルティックというか、アイリッシュ・パンクというか…。
ポーグスとか好きな人には絶好かも。ヒャーララーとケルトっぽいフィドルやアコーディオンやケルティック・フルートが情緒たっぷりに鳴った直後、ドコドコドコドコッとぶっといリズム隊が切れ込んでくる感じは、ワンパターンっちゃワンパターンだけど、まじ燃えます。歌いっぷりもアイリッシュっぽくて。あちら出身なのかな。とはいえ、アメリカン・パンカビリーっぽくなる瞬間も少なからず。ライヴで鍛えているんだろうな。演奏のグルーヴがとてつもない。かっこいい。ポーグスよりぐんとロックンロールしてます。
|

 |
Hot Rail
Calexico
(Our Soil Our Strength/Quarterstick) |
|
ここでデビュー盤を取り上げて、こちらでセカンドを取り上げた連中の新作。ファーストは完全宅録で、やがてセカンドではスタジオでのちゃんとしたレコーディングも交えるようになって。
で、今回はさらにスタジオ・レコーディング・アルバム的濃度を強めた仕上がりへ。臨時ユニットからちゃんとしたバンドへとしっかり歩んできた感じ。セカンドが若干、中途半端な仕上がりだったけれど、あれが本盤への途中経過だったんだなと今わかった。以前のような歪んだトワンギー・ワールドというよりは、オルタナな視点からとらえたテキサス/メキシコ・ミュージックって感じになってきた。インスト、歌もの、ともども、胸をえぐくかきむしるマイナー・メロディがすごいです。こりゃ傑作だ。
|

 |
Allow Me
Jules Shear
(Zoe/Rounder) |
|
前作にあたるこれとか、ここのところ地味めなアルバムで渋く勝負していたジュールズ・シアが、今回はきっちりバンドを従えたポップな新作を作り上げた。
フォーク、ロックンロール、パワー・ポップ、ソウル、カントリーなどの交じり具合が最適。ディランやバーズからの影響も色濃く感じられるけれど、とともにビートルズを筆頭とするブリティッシュ・ポップの味なども見事に採り入れて。さすがの懐の深さ。スチュワート・ラーマン、マーク・イーガン、スーザン・カウシル、ヴィッキ・ピーターソン、スージー・ローチなどがバックアップしてのニューヨーク録音。かつてザ・バンドが『ジェリコ』で取り上げていた「トゥー・スーン・ゴーン」がラストに入っていて。しみます。
|

 |
Come To
Where I'm From
Joseph Arthur
(Real World/Virgin) |
|
3枚目くらいかな。そのスジではけっこう評価されている新世代シンガー・ソングライター。ピーター・ゲイブリエルがこの人の曲を取り上げていたっけ。Tボーン・バーネットとの共同プロデュース、数曲をチャド・ブレイクがミックス…という、そこそこ気になるラインアップによる新作をリリースした。
くすんだ音像の中、アシッドなフォークものとか、ローファイなループとハーモニー・ポップふうのコーラスを従えたギター・ポップとか、生ギターとターンテーブルが交錯するストーリーテラー系の曲とか、なかなか刺激的な音作りが展開される。ベックほどキッチュではないし、トム・ウェイツほど渋くないし、ラテン・プレイボーイズほどハイパーでもないけれど、奇妙な吸引力を持つアーティストだと思う。わりとメロディ作りのセンスもあるし、歌詞も深そう。
何よりも、音像の壊し方とか、緊張感の演出とかがうまい。矛盾して聞こえるかもしれないけど、その辺のやり口がかなりキャッチーです。ちょっととっちらかりすぎな感触もあるけれど…。
|

 |
Silver & Gold
Neil Young
(Reprise) |
|
すでにここで詳しいデータをご報告ずみだったニール・ヤングの新作。往年の名盤『ハーヴェスト』以降、『カムズ・ア・タイム』を経て『ハーヴェスト・ムーン』へと至る流れをくんだ、淡々としたアコースティカルな1枚で。美メロ満載。年輪を重ねてさらに渋さを増した歌声も胸にくる。
『ハーヴェスト・ムーン』のときは、ほのぼのと、ノスタルジックなサウンドに乗せて“だって、ぼくは今でも君を愛しているんだ。君がまた踊るところを見たいんだ。このハーヴェスト・ムーンの上で”と歌われるタイトル・チューンに思わず涙腺を緩ましたものだけど。今回はやっぱり「バッファロー・スプリングフィールド・アゲイン」かなぁ。“また、あいつらに会いたいな”というフレーズにはぐっときました。それを受けて作られたような「グッド・トゥ・シー・ユー」にも胸が震えるし。「ダディ・ウェント・ウォーキン」での唐突なメジャー・セヴンスにも、変わらぬニール・ヤング節を感じて、泣けたし。
ただ、ドラムはやっぱりケニー・バットリーのほうがいいなぁ。バットリーは事故以降もう叩けないって噂も耳にしたので、仕方ないことだけど。もちろん、本盤の場合はジム・ケルトナーが叩いていて。ケルトナーも見事。何ひとつ文句ないのだけれど。でも、なーんかね。どっかが違うんだよね。なんだろう。ダメさ加減とか?(笑)
|

 |
Gung Ho
Patti Smith
(Arista) |
|
for Music Magazine
新生パティ・スミスのサード・アルバムといったほうがしっくりくるか。パティに加え、レニー・ケイ、ジェイ・ディー・ドハーティ、オリヴァー・レイ、トニー・シャナーンという顔ぶれによる3枚目の新作だ。往年のニューヨーク・パンク・サウンドを思い起こさせる4などもあるが、全体的な音作りはずいぶんと洗練されている。むしろ、沈静した印象の強かった感動のカムバック作『ゴーン・アゲイン』(96年)や続く『ピース・アンド・ノイズ』(97年)のほうがラフでワイルドな音像をともなっていたかも。そういう意味では、一見あまり破綻のない1枚のように聞こえてしまうかもしれない。
が、さすがは即興詩人。どの曲も、相変わらず決められた歌詞通りには展開しない。ブックレットに添えられた歌詞を見ながら聞いていると、歌いながら思いつくまま語句を入れ替えたり、描写を微妙にずらしたりしているパティの様子が生々しく伝わってくる。「ストレンジ・メッセンジャーズ」など圧巻だ。曲の後半に向かうに従って大元の歌詞からどんどんと離れ、我を忘れたかのようなシャウトへと突入する。もともとの歌詞は奴隷問題を扱っているのだが、そんなテーマからさえも離脱して、やがてドラッグに対する激しく切迫した抗議までが飛び出す。そうしたパティならではの“堂々たる破綻”を余すところなくすくいあげた1枚と理解すれば、これはもうパティ・スミスならではの変わらず強力な新作だ。国内盤にはブックレットに掲載された元の歌詞に対応した訳詞が付いているけれど、時間的な制約を承知で無理を言えば、このパティの即興に対応する訳詞もぜひ付けてほしかった気がする。
歌詞的には、マザー・テレサを尊敬するパティならではというか、神の視点からの歌とさえ思える「ワン・ヴォイス」や「ロー・アンド・ビホールデン」など、取りようによってはずいぶんと高い位置から愛、平和、人生について説いているようにも聞こえなくはない。学校での銃撃事件やWTOの暴動など、トピカルな問題にも言及しているが、主に取り上げられているのが奴隷制度の歴史だったり、ホー・チ・ミンのことだったり…。こうした、ある種お勉強っぽいテーマ設定を、それだけで“辛気くさい”と敬遠する人も多いのかな。ただ、正直、それじゃもったいないと思う。特に、カスター将軍の妻の人生にインスパイアされたという「リビーズ・ソング」など、カントリー色をたたえた素朴なサウンドに乗って吐露されるのは夫の帰還を待ち続ける女性の気持ちで。これとか、最愛の夫を失ってシーンにカムバックしてきたパティ自身の心情と重ね合わせて泣くこともできるし。ダークなグルーヴに乗せて、ひとかけら、青春っぽい感触がよぎる「ゴーン・パイ」のような曲もあるし。聞き込むほどに魅力が増す。こんな53歳、圧倒的だ。
|

 |
Ecstasy
Lou Reed
(Reprise) |
|
58歳で、これだもの。今回はニール・ヤングとかパティ・スミスとか、ベテラン・ロッカーのアルバムをいろいろ取り上げたけど、とにかくルーさんも含めてこのあたりの人たちの底力には圧倒されます。フェルナンド・ソーンダーズ、マイク・ラスケ、トニー“サンダー”スミス、そしてルー・リードという鉄壁の(そしてもっとも原初的な)布陣で制作された4年ぶりのスタジオ・アルバム。内省的なバラードも、独特のギター・リフをともなったロックものも、すべて寄り道なしに核心へとずばっと迫っていく。
ところどころ、ホーンが入っていたり、ローリー・アンダーソンによるヴァイオリンが入っていたりはするけれど、歌詞も音も、本当に余分なものは何ひとつなし。コウベを垂れつつ居住まいを正しちゃいますよ。
|

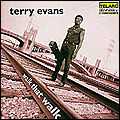 |
Walk That Walk
Terry Evans
(Telarc) |
|
だいぶ間が空いたものの、こいつに続くソロ4枚目。
今回ホルヘ・カルデロンは不参加ながら、ジム・ケルトナーがドラムに返り咲き。もちろんライ・クーダーも全面参加。3曲のカヴァーも含め、独特のゴスペル・ベースの歌声をたっぷり聞かせてくれる。最近はライ・クーダーがこのテの音を作ってくれないから。『パラダイス・アンド・ランチ』とか『チキン・スキン・ミュージック』あたりのライ・クーダーが好きな人は、テリー・エヴァンスに期待するほうが正解かも。
|

 |
One Endless Night
Jimmie Dale Gilmore
(Windcharger/Rounder) |
|
ぼくもラジオでかけたら反響続々。ピーター・バラカンさんもラジオでかけて反響続々だそうです。なかなか輸入盤屋さんにも入ってこないし、聞く機会は少ないけれど、聞けば絶対気に入る。そんな音楽の代表かも。屈強のテキサス・シンガー・ソングライター、ジミー・デイル・ギルモアがハイトーンからラウンダーへと移籍して放った新作だ。
今回はバディ・ミラーが全面バックアップ。ブッチ・ハンコック、ウィリス・アラン・ラムジー、タウンズ・ヴァン・ザント、ジョン・ハイアット、ジェシ・ウィンチェスター、ジェリー・ガルシア、スティーヴ・ジレットらの曲を渋くカヴァーしまくって。「マック・ザ・ナイフ」までやってるからなぁ。声が苦手…という人が多いようだけれど、この人の場合、ウィリー・ネルソンあたりと同様、メロディに対してどんなふうにアプローチしているかって側面から聞くべき歌い手で。そうしたシンガーとしての魅力を味わうにはこのカヴァー盤、かなりイケてると思います。
|

 |
Pink Pearl
Jill Sobule
(Beyond/BMG) |
|
カントリーとはまた別の顔を持つナッシュヴィルのポップ・シーンを取り仕切る親玉、ブラッド・ジョーンズとがっちりタッグを組んでアルバム作りを続けているジル嬢。3作目? よくわかりませんが、ぼくにとってはこれが3枚目のジル・ソビュール作品だ。
ブラッド・ジョーンズと組んでいるだけに、お仲間のスワン・ダイヴとか、あの辺の連中とも相通じるハイセンスなクロスオーヴァー・ポップ盤に仕上がっている。過去の作品よりもコンパクトかつアイデア豊かにまとまっているかな。初期のリッキー・リー・ジョーンズっぽく聞こえる瞬間も。
|

 |
Wow & Flatter
Kyle Vincent
(SongTree) |
|
待望の新作。これが出たのが97年だから、だいぶ待たされました。日本ではその間、独自に未発表アルバムが1枚、ひっそりとリリースされたことがあったけれど、とにかく待ちました。
ルビナーズのトミー・ダンバーとジョン・ルービン、ヴェルクラのリック・メンク、パーセノン・ハックスリー、近ごろベンチャーズのアルバムとかでも名前を見るデイヴィッド・カーなど、パワー・ポップ・ファンにとってたまらない名前がずらり。といっても、もちろんパワー・ポップというよりは、ハイセンスでポップなシンガー・ソングライターって感じの仕上がりになっていて。前作同様、胸しめつける美メロ満載だ。
しかし、前作と打って変わって、今回は自分が設立したインディ・レーベルからのリリース。確かにねー、こういう音楽を聞いているアメリカ人っているんだかどうだか、なんとも想像がつかない。このテは日本のポップス・ファンが思い切り応援するしかないでしょう。まじに。
|

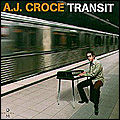 |
Transit
A. J. Croce
(OmTown) |
|
以前、監修させてもらったCDガイドブック『シンガー・ソングライター』でもこの人のファースト・アルバムをピックアップしたのだけれど。ジム・クロウチの息子さんで。といっても、親父さんのようなフォーク路線ではなく、むしろ一時のトム・ウェイツとか、ランディ・ニューマンとか、ジョン・サイモンとか、モーズ・アリソンとか、そっちに通じる味を持った人だった。
けど、今回の新作はちょっと路線が変わって。ビートルズ、ゾンビーズ、スクイーズ、エルヴィス・コステロなど、ブリティッシュ・ポップの影響を強く全面に押し立てている。ニュー・ラディカルズ、ホール、ジェーンズ・アディクションなどと仕事しているマイケル・ジェイムスがプロデュース。なかなかキャッチーでポップな仕上がりになっている。この人はキーボード弾きだけれど、エッジのきいたギターとかもうまくフィーチャーされていて。好感持てます。
|

 |
Figure 8
Elliott Smith
(Dreamworks) |
|
for What's In? Magazine
通算5枚目、メジャー移籍後2枚目。98年夏にリリースされた傑作『XO』以来の新作だ。99年1月には来日もあったし、暮れには映画『アメリカン・ビューティ』のサントラでビートルズのカヴァーを聞かせてくれていたし、今年のアタマ、インターネット・ユーザーには非公式のブート音源も含めMP3による本盤収録曲の先行公開があったりもしたので、さほどご無沙汰感はないかも。とにかく、ばっちり。期待を裏切らぬ1枚だ。ポスト・グランジ世代ならではの個的で、かつ諦観に満ちた彼の“青い”歌声の魅力にいったんハマった者にとってはたまらない仕上がりだ。うれしい。
トム・ロスロックとロブ・シュナッフを共同プロデューサーに迎え、ジョーイ・ワロンカーらをバックに配しての録音。コステロさんちのピート・トーマスなども参加し、インディーズ時代の内省的で簡素な音作りとはひと味違う、豊かで緻密なアンサンブルを聞かせてくれる……というわけで、人脈的にもサウンド的にも前作の流れをそのまま引き継いだ仕上がりだ。意外なほどハードなアプローチを聞かせる曲もあるが、もちろんエリオットならではのパーソナルな世界観というか、ロマンチックな甘さと行き場のない苦しさ/切なさが微妙に交錯するまなざしは変わらず。ドラムをともなったポップでソリッドな楽曲群も素晴らしいけれど、やはり主にアルバム後半のほうに並んでいるアコースティック弾き語り系の曲がしみます。曲によってさりげなくあしらわれたストリングスとの絡みも泣ける。
|

 |
Makin' Love Is
Good For You
B. B. King
(MCA) |
|
間もなくエリック・クラプトンとのコラボレート・アルバムのリリースも待ちかまえるB・B御大。私ね、自慢なんですけどね、この人のコンサートをプロデュースしたことがあるですよ。すごいですよ。ぼくがプロデュースした最大級の大物はこの人と、五木ひろしかな(笑)。
で、それはともかく。自らプロデュースを手がけたこの新作。必殺のポップ・スタンダード「シンス・アイ・フェル・フォー・ユー」とか、ボニー・レイットでもおなじみ、バーバラ・ルイスの「アイ・ノウ」とか、トニー・ジョー・ホワイト作のアルバム・タイトル・チューンとか、マディ・ウォーターズの「ドント・ゴー・ノー・ファーザー」とか、A・C・リードの「アイム・イン・ザ・ロング・ビジネス」とか、興味深いカヴァーものに加えて、B・B自ら6曲のオリジナルを提供。ライヴでのレギュラー・バンドをバックに従えてのストレート・アヘッドなブルース・アルバムだ。うれしい。やはり自らプロデュースを手がけていた98年の『ブルース・イン・ザ・バイユー』の続編って感じ。
いやー、年取ったなぁ…って瞬間もあるけど。そういう問題じゃないから。出来、悪いわけがないね。ありがたく頂戴します。
|

|