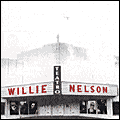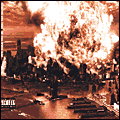1998.1.3

|
 |
Groovegrass 101
The Groovegrass Boyz
(Reprise)
|
|
ボストンを本拠にするセッション・ミュージシャン/プロデューサーのスコット・ラウズを中心とするプロジェクトのアルバム。1993年にレコーディングされたものだとか。
で、どういうプロジェクトかと言うと、タイトル通り、グルーヴィなファンク/ヒップホップと伝統的ブルーグラスの合体プロジェクト。なんじゃそりゃ……って感じなんだけど。まさにそのものの音に仕上がっている。なんでもスコットさんが93年ごろにジョン・アンダーソンとかオズボーン・ブラザーズとかのリミックス・ダンス・ヴァージョンで話題を集めた直後に制作されたものらしい。
なもんで、ドク・ワトソン、マック・ワイズマンといった伝説のブルーグラス・プレイヤーを招き、一方ではブーチー・コリンズを迎え、ジェリー・ダグラス、バーニー・レドンなど腕ききにバックアップさせつつ、サンプリングやら何やらでぐしょぐしょにした仕上がり。大半はオリジナルだけど、ビル・モンローやらカーター・ファミリーやらのブルーグラス・スタンダードのカヴァーも入っていて、まあ、どっちかというとカヴァーもののほうが意図がくっきり表われていてキャッチーかも。
|

 |
Live On Two Legs
Pearl Jam
(Epic)
|
|
for "Music Magazine", Dec. 1998
現代の海賊ライヴ盤/プロモ・ライヴ盤キングのひとつ、パール・ジャムがついに初の公式ライヴ・フル・アルバムをリリースした。夏ごろから出るぞ出るぞと噂になってはいたものの、98年の新作『イールド』の発売からほんの10カ月。こんなに早く実現するとは思ってもみなかった。
例のティケットマスターとのいざこざとか、客もライヴを録音し放題というバンドの基本方針とか、ビデオ・クリップをほとんど作らず雑誌にも自らは出ていかず…というプロモーション法とか、もろもろ考え合わせて、やはりパール・ジャムがもっともこだわっている表現の場はライヴなのだろう。そういう意味でも絶対に見逃せない1枚。ファースト・アルバムから2曲、その他の4枚のアルバムから3曲ずつというベスト盤的選曲に加え、ラストをしめる楽曲として95年にコラボレートしたニール・ヤングのカヴァーも聞かれる。まさにこれまでの集大成という感じだ。これでブート市場や、300を超えるライヴMP3ファイルで溢れかえるパール・ジャムWEBシーンが少しは落ち着くのか、いっそう盛り上がるのか…。
手元のプロモーション用資料にはまだ詳しい録音年月日などのデータはないのだが、様々な雑誌などで目にした情報によれば、すべて『イールド』の発売に合わせて行なわれたツアーからの音源らしい。2月のハワイに始まり、3月のオーストラリアを経て、6月から9月いっぱい北米各地を回ったこのツアーは、ティケットマスターともめて以来、初のフル・スケール・ツアーだったはず。バンドの気合の入り具合も違う。たぶん北米での録音だろうから、オーストラリア公演以降、健康問題で脱退してしまったジャック・アイアンズに代わるドラマーとして元サウンドガーデンのマット・キャメロンを据えた最新ラインアップによる演奏に違いない。ぶっとく、充実したグルーヴ満載だ。
いい曲は多いのに個人的には今ひとつポイントがつかめずにいた『ノー・コード』あたりの楽曲も、ここでは見違えるよう。11とか、スタジオ盤以上の切実さをもって胸にがつんと飛び込んでくる。“無題”と題された短い新曲(?)6も、ライヴでは『ノー・コード』収録の「ハビット」のイントロ部分で演奏されていたもののひとつらしい。ちょっと軽視しがちだった『ノー・コード』にもう一回じっくり立ち返ってみようかという気分にさえなった。結局こいつらの底力は、やはりライヴでないと実感できないってことか。異国のファンにとって特にありがたい盤です。とともに、パール・ジャム未体験者が初めて接するべき1枚としても絶好の存在ってことになりそうだ。日本ではどうだか知らないけど、アメリカじゃ2枚組アナログ盤も出るとか。良さそう。
|

 |
Bali
Wondermints
(Neosite/Epic)
|
|
for "What's In?" Magazine, Dec. 1998
ブライアン・ウィルソンやエリック・カルメンのお気に入りバンドってことで注目を集め、本国アメリカよりも一足先に日本でデビューを飾ったワンダーミンツ。映画『オースティン・パワーズ』にも出演/曲提供していたし、来年予定されているブライアンのソロ・ツアーのバック・バンドをつとめることにもなったようだし。近ごろ何かと取りざたされることも多い。そんな彼らがレコード会社を移籍して、久々のサード・アルバムをリリースした。今回も日本先行発売。アメリカでのリリースは99年の春ごろだとか。
ラテン風味あり、ジャズ風味あり、バカラック調あり、パワー・ポップあり、エリック・カルメン調の壮麗バラードあり。これまで以上にバラエティ豊か。モンキーズ、ブライアン・ウィルソン、タートルズ、バカラック、ピンク・フロイド、アバなどの隠れた名曲をカヴァーしまくった前作で見せた雑多かつ貪欲な音楽的志向性を、今度はオリジナル曲で再構築した仕上がりと解釈すればいいのかな。いい曲ぞろい。中心メンバーのダリアンをはじめ、メンバーそれぞれのポップ・ミュージックに対するマニアックな愛情がいい形で発揮されている。アルバム・タイトルは、収録曲1曲ごとに音楽スタイルがコロコロ変わるこの感じを表現しているらしい。島から島へと夢の音楽旅行……ってわけ。
60年代から、ビーチ・ボーイズやフィル・スペクター、モータウン・レコードの諸作をはじめ無数のレコーディング・セッションに参加してきた偉大な女性ベーシスト、キャロル・ケイのゲスト参加ってのも、やー、うれしくなるくらいマニアックだね。
|

 |
Industry and Thrift
Bad Livers
(Sugar Hill)
|
|
これって4枚目? 5枚目? テキサス州オースティンを本拠に活動するロカビリー/ブルーグラス/カントリー/フォーク/パンク・バンド、バッド・リヴァーズの新作です。9月ごろアメリカでは出たようだけれど、先日ようやく渋谷タワーで入手。
今回もいろいろやってます。チューバとバンジョーが妙なコンビネーションを聞かせるスポークン調のオープニング・チューンに始まって、時にはストリングスやアコーディオン、果てはドラム・マシーンまで導入しつつ展開するBLワールド。東欧調の旋律も飛び出したりするし。わりと保守的な風潮が強いブルーグラス・シーンにあって、デイヴィッド・グリスマンあたりとはまた違う、もっと乱暴なやり口で様々な狼藉を働いているわけで。
上のグルーヴグラスあたりとともに、むしろロック・ファンこそが評価しないといけない連中だ。
|

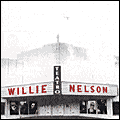 |
Teatro
Willie Nelson
(Island)
|
|
夏ぐらいにアメリカで出て、12月に日本盤も出たウィリー・ネルソンの新作。タイミングがずれちゃったけど、とりあえず今さらながらここでも紹介しておきます。
大方が過去の自作曲。新曲とカヴァーが数曲ずつ。まとめあげたのはダニエル・ラノワ。大半の曲でエミルー・ハリスがデュエット・パートナーとして、ラフな、しかし味わい深いハーモニー・ヴォーカルを聞かせている。ルシャス・ジャクソンのメンバーの参加も話題だ。
で、ね。内容はいいわけですよ。なんたってウィリー・ネルソンだし。ダニエル・ラノワだし。ディランの新作でも発揮されていたラノワの愛情と洞察力のようなものもきっちり聞き取れて。ただ、このアルバムを取り上げたミュージック・マガジン誌のアルバム・ピックアップで、岡村詩野さんが“ウィリー翁も(中略)お節介な後輩によって生まれ変わることになった”とか“そのお節介を買って出たのがダニエル・ラノワだったというのはこちらの思惑通り”とか“キャリア半世紀の重鎮を変える”とか、評者である彼女も含む“後輩”こそがこのアルバムの主役であるかのような書き方をしていて。
もちろんそういう聞き方もあるんだろうなと想像はつく。評者は自分を“ウィリー・ネルソン初心者”であると定義したうえで書いているので、当然もっとウィリー・ネルソンの諸作を聞き込めば考えが変わるかもしれないことを前提にした発言なのだろうとも思う。なので、特にツバとばしてまで反論しようとは思わないけれど。
ただ、“こちらの思惑”とか“重鎮を変える”とかいう奢った表現にはどうしてもひっかかるわけです。ディランにせよ、ここでのウィリー・ネルソンにせよ、ぼくの場合、やはり主役はあくまでも彼らだと思う。優秀な後輩であるラノワに身をまかせようと決めたのも彼ら自身だろうし、ラノワにしても彼ら偉大な先達を“変えた”のではなく、彼らの中にあらかじめ息づいている素晴らしい要素をラノワ流のやり口で増幅してみせただけなんだろうし。そういう視点から聞かないと、本盤の本来の魅力を見誤りそうな気が、ぼくにはする。“こういう音が今は旬だから”的な刹那っぽい視点でのみ本盤が語られちゃう危険性も少なくない。
まあ、どんな形であれウィリー・ネルソンの図抜けた才能にスポットが当たるのはうれしいんだけど(笑)。それを承知のうえで、ちょびっと反論してみました。日本盤のライナーにあった“彼(ラノワ)の仕事が気に入っていたんで、ダニエルについていったんだ”というウィリー・ネルソンの言葉に表われた彼の意欲と、時代感覚と、どんな音のただ中に飛び込もうと何一つ変わらぬ彼の堂々たる才能とにこそ最大の賛辞を送りたいものです。
|

 |
Tical 2000: Judgement Day
Method Man
(Def Jam)
|
|
ウータンのセカンド・アルバムってのは、本当に本当に心から楽しみにしていた。だけれど、実際に出てみたら、あの、なんともすすけたような、ドープな、かつファンキー&パンキーだったファーストに比べると、妙に物わかりがよくなっちゃった感じで。デビュー盤をリリース以降、大人気を博して、結果的に時代のど真ん中へと押しやられてしまった彼らにしてみれば当然の内容だったとは思ったけれど、それにしてもねぇ。ヒップホップ新時代の期待を一身に背負うウータン・クランって図は、なんだかウータン・クランって気がしなくて。複雑な気分だった。
そんなウータンのセカンドとファーストの関係が、このメソッド・マンの場合にも当てはまりそう。彼のファーストは、ここ数年のヒップホップ・ムーヴメントの勢いをピークへと引きずりあげた重要なアルバムのひとつだったわけで。あの盤に充満していた気鋭ならではのやばい雰囲気こそが、まさに新時代のロックンロールとしてのヒップホップを象徴していたと思う。で、今回の新作には、やはり時代のスーパースターのひとりとして大物感を漂わせるようになってしまったメソッド・マンの堂々たる“ど真ん中”感があって。これまた複雑な気分で聞き終えた。
でも、やはりこの人ならではのダーティなバックトラックはかっこいい。新年の幕開けを粉砕してスタートする1曲目から、ぐーっと陰鬱なムードに貫かれた重戦車ビートまみれ。けっして洗練されることのないタフなラップぶりも得がたいものだ。長いブランクがなければ、もっと素直に接することができた1枚かもしれない。先入観がなくなるまで気長につき合ってみようかな。
|

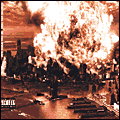 |
Extinction Level Event
(The Final World Front)
Busta Rhymes
(Elektra)
|
|
その点、このバスタ・ライムズのほうは、もともと野望というか、成り上がり感というか、ポップな方向性というかを全面に押し立てていたところがあって。アメリカン・ポップスの王道のひとつとして君臨する現在のラップ・シーンの在り方のようなものともさほど違和感なく共存できている気がする。
フリップモード・スクワッドの面々はもちろん、ミスティカル、ジャネット・ジャクソン、そしてなんとオジー・オズボーンまで動員してのイケイケ盤。もちろん彼に関してもいちばん胸をざわつかせてくれたのはソロ第一弾アルバムだったわけで、その事実はこのサード・アルバムが出た今も変わらないけれど。やはりバスタの磁力はすごいや、と。思い知らされたワタクシでした。
|

|