世 界 で は(世界史略年表へ)
よ こ は ま で は
略年表
[北・東アジア] <モンゴルの統一> 中国が北部に金、南に南宋と分かれていた頃、 北方のモンゴル高原ではテムジンがモンゴル諸 部族を統一してチンギス=ハン(太祖)の称号を 受けて、モンゴル帝国が誕生しました。 チンギス=ハンは「千戸制」により中央集権的な 支配を固め、モンゴル軍を率いて1221年にイス ラムのホラズム朝を、1227年には西夏を滅ぼし 強力な遊牧国家を作りました。 チンギス=ハンが死んだあと第3子のオゴタイ =ハンがクリルタイ(族長会議)で推されて即位 、太宗を名のり、南宋と共同して金を滅ぼしまし た。 チンギス=ハンの長子ジュチの子バトゥはヨー ロッパ遠征に出発、ロシアに侵入し主要都市を 次々と攻略したほか、その一隊はポーランド・ハ ンガリーに侵入して1241年ポーランドのワール シュタットでドイツ・ポーランド連合軍を破り、 ヨーロッパ世界に脅威を与えました。 やがてオゴタイ=ハンの死によりモンゴル軍は 帰国を始めましたが、バトゥは対立しているグ ユク(オゴタ=ハンの長子)が即位しようとして いる事を知り、そのままロシアに留まってキプ チャク=ハン国を建て、その後ロシアは長くモン ゴルの支配下に置かれました。 グユクが死んだのち即位したモンケ=ハン(憲 宗)の弟、フラグは西アジアに遠征してアッパー ス朝を滅ぼして、イランを中心にイル=ハン国を 建国しました。 1259年には約30年にわたって抵抗してきた高 麗も屈服して、モンゴル帝国は東は中国北部か ら西は西アジア・ロシアにわたる大帝国になり ました。(モンゴル帝国の最大領域) <モンゴル帝国の分裂> チンギス=ハンの死後、皇位をめぐる争いが激 しくなり、4代目のモンケ=ハンが急死した後、フ ビライ=ハン(世祖)が遠征先で正式の族長会議 にかけずに即位すると末弟のアリクブカとの間 に戦いがはじまり、更にオゴタイ=ハンの孫のハ イドゥも挙兵して、フビライに抵抗、これによっ てオゴタイ、チャガタイ、キプチャク、イルの四 ハン国はそれ迄の属国的立場から脱して分離独 立、モンゴル帝国はフビライ=ハンの宗家(本家) と四ハン国に分裂しました。<フビライの元建国> ハイドゥを中心とするオゴタイ、チャガタイ、 キプチャクの三ハン国に対抗するためにフビラ イは中国全土の支配を目指し、1271年に都を大 都(現在の北京)に移して国号を中国風に元と改 めました。 フビライはその間も南宋への侵略を続け1279 年これを滅ぼして元による中国全土の支配が完 成しました。 元の領土はフビライのとき最大となり、日本へ の遠征(コラム・フビライの日本遠征)も試みましたが 鎌倉武士の奮闘と暴風雨のため失敗しました。 フビライは少人数のモンゴル人で多くの中国 人を支配するためモンゴル人第一主義をとり、 中央政府の要職や地方行政機関の長をモンゴル 人が独占しましたが、圧倒的多数を占める中国 人を支配するために色目人を利用しました。 都は大変賑わい、道路も整えられ駅伝制がつく られイタリア商人の子として生まれたマルコ= ポーロは元の上都(現在の内モンゴル自治区)を 訪れ、フビライに仕え、帰国後「東方見聞録」を口 述しました。 (コラム・マルコ=ポーロと東方見聞録) [西アジア] <オスマン帝国> 1194年セルジューク朝が滅びたのち、1258年チ ンギス=ハンの孫フラグの率いるモンゴル軍が バクダードを攻め落とし、これまで形の上だけ でも続いていたアッパース朝も滅び、フラグが 現在のイラン、イラクを中心とした地方にイル= ハン国をつくりました。 トルコ族の一派のオスマン家はオスマン一世 の祖父のときに、モンゴル軍に追われて小アジ アのアナトリアに移住して1299年に族長オスマ ン一世の下にオスマン帝国をおこしました。 帝国はやがてヨーロッパとアジアにまたがる 大帝国になります。 [ヨーロッパ世界] <イギリスのマグナ=カルタ> -マグナ=カルタの制定- イギリスではヘンリ二世のあとリチャード一 世についで、ジョン王が即位しましたがフラン ス王との戦いに敗れ、ノルマンディをはじめフ ランス本土にあったイギリス領の殆どを失い、 国内の貴族たちの反乱を招くことになり、ジョ ン王は譲歩して1215年貴族たちの要求するマグ ナ=カルタ(大憲章)に調印しました。 -模範議会の開催- ジョン王のあとをついだヘンリ三世は大憲章 を無視した政治を行なったため1265年イギリス の貴族たちは騎士や市民の代表を含めて議会を 開きました。これが模範議会といわれるもので、 イギリス議会の起源となりました。 その後イギリス議会は高位聖職者と大貴族、騎 士と市民がそれぞれ合同して会議を持つように なり、上院(貴族院)と下院(庶民院)の二院制議 会として成長することになります。 <フランスの三部会> -カペー朝- フランスの地ではフランク王国が分裂して出 来た西フランク王国がフランスの原形となりま した。 987年ユーグ=カペーがカペー朝を開きました が諸侯の勢力が強く、王領も北部を中心とする 狭い地域に限られておりカペー家のフランス統 一は妨げられていました。 -三部会- 1180年フィリップ二世が即位しイギリス王ジ ョンとの戦いなどを通じて王領地を拡大しまし たが、1285年即位したフィリップ四世は更に王 権を強めようとして、戦費調達のため聖職者へ の課税を強行したことからローマ教皇と衝突し たためフランス支配層の支持を得ようとして、1 302年パリに聖職者・貴族・市民の代表を集めて 三部会を開き、その支持を得て翌年ローマ教皇 のポニファティス八世をローマ郊外のアナーニ に監禁しました(アナーニ事件)。 <教会勢力の衰え> 王権の伸張とローマ教会の堕落により教会の 力は衰えはじめます。 -教皇のバビロン捕囚- アナーニ事件ののちフィリップ四世はフラン スのボルドー出身の教皇クレメンス五世を南フ ランスのアヴィニョンに移しました。以後7代69 年に亘って教皇はアヴィニョンにとどまり、事 実上フランス国王の監視下に置かれました。こ れを古代ユダヤ人が新バビロニアに連れて行か れた「バビロンの捕囚」にちなんで「教皇のバビ ロン捕囚」といいます。 (参考・バビロンの捕囚とユダヤ人) -教会の大分裂(大シスマ)- 1377年ローマ教皇グレゴリウス十一世はアヴ ィニョンからローマに帰りました。翌年教皇が 亡くなったためイタリア人のウルバヌス六世が 教皇に選ばれるとフランスは対立する教皇クレ メンス七世をアヴィニョンにたてました。 以後1417年まで教皇がローマとアヴィニョン の二ヶ所に並び立つことになり、教会の力は一 層衰えました。
トルコ語と同系の諸言語(チュルク諸語)を話す諸 部族のことで原住地は定説がありませんが、紀元前 3世紀末にはモンゴル高原北部を中心に遊牧民とし て活躍していたことが知られています。 6世紀半ば頃、アルタイ山麓から起った突厥が中央 アジアをおおう大帝国となり、その後同じトルコ系 のウィグル族、キルギス族がこれに代わったのち、 モンゴルの圧迫を受けトルコ系諸族は10世紀以後 は西アジア方面での活動が盛んになりました。 トルコ系諸族の一派だったオグズ族が西方へ移動 し、11世紀に入るとイラン領内に侵入してセルジュ ーク朝を開き、13世紀にはアナトリアまで移動して きたオグズ族の別の一派がオスマン帝国の基礎を 築きました。 10世紀末には中央アジアのトルコ系諸族の一部が イスラム教に帰依し、その後トルコ系諸族の大部分 はイスラム化し、イスラム社会の形成に大きな影響 を与えました。
<鎌倉幕府の御家人> 壇ノ浦(山口県)で平氏を滅ぼした源頼朝は 1192(建久3)年鎌倉に幕府を開き、武士による 政権が始めて東国に生まれました。 頼朝は土地を仲立ちとして武士たちと「ご恩 と奉公」の主従関係を結びました。 この関係を結んだ武士を御家人といいます が、横浜あたりの御家人には鴨志田氏、馬場氏 、石川氏、都筑氏、荏田氏、長田氏などを名乗る 武士がいましたが、現在でも横浜の地名にそ の名をとどめています。東漸寺釈迦堂(横浜市磯子区) <北の守りー証菩提寺ー> 栄区の証菩提寺は石橋山の合戦(1180=治承 4年)で、大庭景親に攻められた源頼朝の命を 救い戦死した佐奈田義忠を追悼するために建 立されましたが、金沢から円海山にぬけて続 く金沢道の脇にあり、鎌倉の東北すなわち鬼 門にあたるため鎌倉の守りとしたものと考え られています。 洗練された阿弥陀三尊像があることでも知 られていますが、源氏滅亡後は北条氏が直接 管理し、その後は足利氏の祈祷寺となりまし た。<畠山重忠> 有力な御家人であった畠山重忠は源頼朝か ら非常に信頼されていた東国武士で、現在の 埼玉県を本拠地としていました。 畠山氏は平安時代以来、武蔵の国衙に対して も影響力を持った秩父一族を代表する豪族で したが、1205(元久2)年子息重保と北条時政の 娘婿の平賀朝雅との対立を背景として、武蔵 国への進出を目指す時政の策略によって武蔵 国の二俣川で殺されました。 この事件の後、時政の子義時は武蔵国に勢力 を伸ばし執権政治を強力に進めるようになり ました。 横浜の源氏御家人
畠山重忠の首塚(旭区・鶴ヶ峰本町、重忠の首が 愛甲三郎によって斬られ祀られたところと伝えら れています) <鎌倉幕府と横浜の開発> 鎌倉幕府にとっては合戦があった場合、戦に 参加した武士に対して恩賞として与える土地 を確保する必要がありました。 畠山氏滅亡の1年半後の1207(承元1)年北条 時房は武蔵守(長官)となり、地頭たちに武蔵 の開発を命じましたが、本格的に開発が行な われたのは、のちの延応・仁治年間(1239~42) で、それまでにはなお諸豪族と戦わなければ なりませんでした。 横浜市内では1239(延応元)年小机郷鳥山等 の荒野が北条氏の手によって開発されまし た。1241(仁治2)年には近隣の武蔵野が開発さ れ多摩川から用水が引かれましたが、大変大 規模な工事だったと伝えられています。 <東漸寺と鎌倉幕府> 磯子区にある東漸寺は名越北条氏の北条定 長によって建立され、桃渓徳悟(宏覚禅師、建 長寺開山の蘭渓道隆の高弟)によって開かれ ましたが、周辺は景勝地であったため鎌倉五 山の禅僧たちが好んでこの地に来遊し、詩を 作ったり学問を論じました。 この中には無学祖元、一山一寧、東明慧日、東 里徳恵といった高僧もおり鎌倉での政治、宗 教、文化活動の疲れを癒すため、鎌倉に近い風 光明媚なこの土地を訪れたのです。 釈迦堂にある梵鐘は称名寺鐘や相模国分寺 鐘や円覚寺鐘などの名鐘を残した物部国光の 作といわれ、国の重要文化財となっています。
 阿弥陀三尊像(証菩提寺蔵)
阿弥陀三尊像(証菩提寺蔵)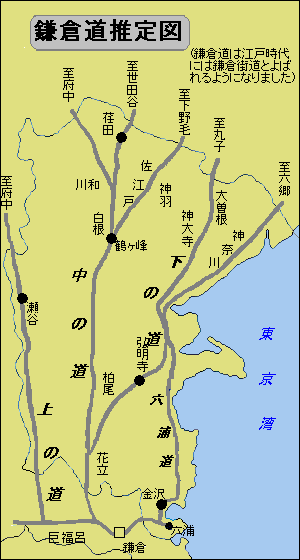 横浜周辺の鎌倉道
横浜周辺の鎌倉道前のページへ
次 へ
トップページへ
1192 源頼朝、征 夷大将軍と なり鎌倉に 幕府を開く 1205 畠山重忠が 北条時政の 陰謀により 二俣川で殺 される 1233 鎌倉将軍家 が平子経久 に平子郷内 石河村を安 堵する 1239 小机郷鳥山 などが開発 される 1241 朝夷奈切通 しが開かれ る 1260 この頃称名 寺がつくら れる 1275 この頃金沢 文庫ができ る 1333 鎌倉幕府滅 亡


