| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |
|
No.196 大雪山 |
| 黒岳石室に一泊して、北海岳、緑岳を経て大雪高原温泉に下りました。今回は天候に恵まれず、特に2日目は最悪で、歩くのが精一杯の山行になりました。 日時 2017年(平成29年)7月11日(火)〜12日(水) 天候 7月11日(火) 曇後雨 7月12日(水) 雨(強風)後晴 同行 なし 7月11日 所要時間 黒岳リフト終点(11.35) ←1時間→ (12.35)8合目(12.45) ←25分→ (13.10)9合目(13.15) ←45分→ (14.00)黒岳頂上(14.10) ←20分→ (14.30)黒岳石室 7月12日 所要時間 黒岳石室(5.45) ←1時間10分→ (6.55)北海岳登り口(7.00) ←25分→ (7.25)休憩所(7.35) ←1時間10分→ (8.45)北海岳(8.45) ←1時間40分→ (10.25)白雲岳分岐(10.30) ←45分→ (11.15)白雲岳避難小屋(11.35) ←40分→ (12.15)白雲岳避難小屋分岐(12.15) ←25分→ (12.40)緑岳(12.40) ←2時間→ (14.40)エイコの沢ガレ場(14.40) ←45分→ (15.25)第1お花畑入口(15.30) ←50分→ (16.20)大雪高原山荘 山行概要 7月11日(火) 層雲峡〜黒岳石室
層雲峡で、ロープウェー、リフトと乗り継ぎ、リフトの終点でいつものように少し早めのおにぎりの昼食を取りました。おにぎりを食べ終え、目の前のロッジにある入山ノートに行動予定を記入して、歩き始めました。雪融けの後の水溜りが道のあちこちにあります。ひとしきり急坂を登って、ベンチのある八合目で少し長い休憩を取り、更に九合目で一息入れ、黒岳の頂上に着きました。今日は雨が降り出しそうな曇で、この天候のためかここまで行き交う人が少なかったのですが、黒岳の頂上では逆にこれまでにないほど大勢の人たちがいて、結構な賑わいを見せていました。私もこの人たちの一角に加わり、あたりの景色を眺めて休みをとりました。 日射しがなく、周りは雲が多いので、頂上からの眺めはあまり面白いものではありません。10分ほど休んで頂上を後にし、今日の目的地の黒岳石室へ向いました。花の写真を写しながらのんびり歩いていましたが、黒岳石室が見えた辺りで、気にしていた雨がポツポツ降り出したので足を速めました。黒岳石室の前に広がる残雪を歩いている時に本降りになっていましたが幸い衣服はほとんど濡らさずにすみました。石室で泊る手続きをしてカイコ棚の2階の一角に自分の居場所を取りりました。 今日は雨なので、外では食事の支度や食事ができません。石室の入口にある炊事エリアで同宿者(この日は10数名、5〜6パーティ?)に混ざって夕食を作るとともに湯を沸かして、明日の飲料水を作りました。 食事が終われば、後は寝るだけです。シュラフに入ってうとうとして時を過ごし、消灯前にある小屋番の明日の天気予報(雨は今夜中に上がり、明日天気は回復に向う。)を聞いて、眠りに落ちましたが、夜半、屋根をたたくものすごい雨音で何回か目を覚ましました。 7月12日(水) 黒岳石室〜大雪高原山荘 朝3時ごろ目がさめましたが、寝袋でうとうとして、午前4時を過ぎたところで寝袋から起き出しました。今回は,荷を軽くしたかったので寝袋は持参せず石室で借用しました。そのためか、朝のザックのパッキングは随分楽に感じました。朝食は湯を沸かしてアルファ米のおかゆを食べる予定でしたが湯を沸かすのが面倒になり、昨日の昼食用にコンビニで買ったおにぎりの残りを朝食にしました。 朝食を終え、出発です。雨は上がっており、雲の切れ間から青空も見えます。昨晩の小屋番の天気予報どおり、今日はこのあと好天が期待できそうだと思って石室を出発しました。 石室を出るとすぐこれから向かう北海岳が見えますが、山頂は未だ雲の中です。更に進んで雪渓を歩き終えたところで赤石川の渡渉地点が見えてきました。いつもは残っている渡渉地点の雪がすっかり融けてなくなっています。近づいてみると幾つかの飛び石は水面下にあり、登山靴を水中に入れないと渡れません。慎重にかつすばやく飛び石を伝って対岸へ渡りました。幸い靴の中まで完全に濡らさずに渡れました。  赤石川を渡ったところで小雨が降りだしたので、北海沢の手前で雨具をつけましたが、いずれ雨は上がるだろうと考え、このときは上衣だけ着て、ズボンをはきませんでした。これが後述のように、大失敗でした。 赤石川を渡ったところで小雨が降りだしたので、北海沢の手前で雨具をつけましたが、いずれ雨は上がるだろうと考え、このときは上衣だけ着て、ズボンをはきませんでした。これが後述のように、大失敗でした。北海沢を渡り、沢の右岸をしばらく上流側に歩くと、見慣れた北海岳の登り口を示すマークが現われました。ここで、いつものように一休みです。ここからしばらく潅木の中の深くえぐられた道を歩きますので、風がさえぎられますが登るにつれて風が強くなって行くのが木を揺らす風音で分かります。これに加えて、上空の雲がどんどん近づいてきます。やがていつも休みを取る休憩用のベンチに着いた時には、辺りはすっかりガスに覆われ、しかもかなり強い風が吹いていて休むような環境ではありませんでした。ここはベンチで休まず少し先の木陰で風を避けて休みを取りました。 休憩所を過ぎて登りがきつくなり、大きな段差を越えると北海岳から延びる稜線に沿って歩くようになります。道はフラットになるのですが、あたり一面ガスに覆われていて、強い風が正面から吹き付けてきます。雨具をつけていないズボンがみるみるうちに湿ってきました。やがて北海岳から延びる稜線の上に出ると風は一段と強烈になりました。下を向いて、北海岳の頂上に立つことだけを考えて歩きました。やがて今日の最初の目標の北海岳の頂上に着きましたが、強風で立っているのが苦痛です。頂上の写真を写しただけで北海原へ下りました。下る時に道を間違えていないか念を入れて導標を確認しました。 北海原へ下っても強風は収まりません。休むことなく右手から強烈な風が吹いており、視界もせいぜい20mぐらいしかありません。しかも横なぐりの雨粒が霧雨に混ざるようになり、歩くのだけで精一杯になりました。視界がなく右手から強風にあおられるので、時おり左手へ流されているような錯覚に陥ります。ほぼ予想通りに白雲岳手前の休憩用のベンチが現われた時はホッとしました。ここで休憩を取ることにしたので、雨具のズボンをはくことも考えたのですが、風があまりに強く、雨具を飛ばされることを懸念して、雨具のズボンははきませんでした。 登山道はここから、大きく左へ曲がり雪渓に入りますが、今年は雪の量が少なく、すぐ夏道があらわれ、これで終りかと思ったときに、また雪渓が現れました。この雪渓では風は弱まりましたが、視界がほとんどありません。雪渓上に張ってあるガイドロープを頼りに歩きました。 雪渓が終り、白雲岳十字路への登りでまた風が強くなり、雨も本降りになりました。たどり着いた白雲岳十字路も強風でとてもゆっくり休む気になれません。今日は吹きさらしの小泉岳へ登らず、ここから白雲岳避難小屋へ一端下ることにしてました。十字路から少し歩いたところでやっと風があまり当らない場所を見つけ、ここで雨具のズボンをはきましたが、ズボンは既にびっしょり濡れていました。雨で沢のようになった登山道を下り、白雲岳避難小屋に入ってやっと一息つけました。小屋番が入口の一角で昼食を取ってもよいと言うので、ここで昼食にしました。昼食は昨晩湯を入れて作っておいたアルファ米の赤飯です。食欲はあまりありませんが、シャリバテを起こしても困るので、無理やり茶碗一杯分ぐらいの赤飯を詰め込みました。 昼食を終え、しばらくすると下半身が濡れているため少し寒気を感じるようになったので、避難小屋を後にしました。小屋番に休ませてくれた礼を言い、外へ出て写真を写そうとしたのですがカメラがウントモスントモいいません。バッテリーを交換してみたのですが、状況は同じです。カメラは雨でびしょ濡れで、壊れたようです。小屋を出て、雪渓を横切り小泉岳と緑岳の稜線へ出て、緑岳へ向っていると、目の前に黒い影が現われました。今日山中で会う初めての登山者で、比較的若い男女のペアでした。お互いにこれから先の風についての情報を交換しましたが、この先、白雲岳の避難小屋の手前の雪渓まで下ると風が弱くなると伝えると喜んでいましたが、私の方は緑岳を下りきるまで強風が続くと言われ少々がっかりしました。 強風とガスと雨の緑岳を越え、その先の岩場の下りで強風にあおられて難渋し、ほぼ下りきったところで、目の前の視界が突然ひらけて、青空が見えたときは思わず顔がほころびました。緑岳を下りきった少し先にある周りが開けている広場で、ザックやポールを投げ出し、雨具を脱いで大休止にしました。 このあと、すっかり天候が回復した中をエイコの沢のガレ場で雪面に降りて、第二お花畑、第一お花畑と歩いて急坂を下り、大雪高原山荘で露天風呂に浸かって至福のひと時を過ごしました。 このルートを歩くのは今回が4回目です。初めて歩いた時も小泉岳から雨になり、緑岳では今回と同じような悪天に見舞われました。山の天気は変わり易いと言われますが、大雪山では特に強く感じます。なお、今回は、視界のない中を長く歩きましたが、GPSに過去の山行で得たトラックデータを入れていたので、道に迷うというプレッシャーはありませんでした。もしこのGPSを持っていなかったら、北海岳の頂上の手前で引き返していたと思います。 「山の花」に以下の花の写真を追加しました。 エゾルリソウ、チシマヒョウタンボク、エゾノタカネヤナギ |
|||
| 7月11日 層雲峡〜黒岳石室 | |
 |
リフト乗り場 天気がよければここから黒岳が眺められるのだが、この日は雲にかくれて見えなかった このリフトはザックを降ろして前に抱えて乗るように要求される |
 |
リフト終点 リフト終点が黒岳の七合目 正面のロッジの前を通って黒岳に登って行く ロッジの窓口に入山者名と歩くコースなどを記載するノートが置かれている |
 |
七合目 前述のようにリフト終点が七合目と黒岳ロープウェイのホームページに記載されているが、七合目の標識はリフト終点から10分ほど歩いたところに立っている 表示が頂上側にあるので、下から歩いてくると単なる棒杭に見える カシミールで標高を確認したところ、リフト終点が約1530m、この標識の設置位置が約1570mだった |
 |
八合目 私の足だとリフトの終点から1時間ほどかかるので、格好の休憩所になっている ここの標高は約1720mだから、標高約1530mのリフト終点から標高差にして190mほど登ったことになる 例年、この辺りから花が多くなる |
 |
黒岳頂上 標高1984.3mと表示した標識が立っている 大きな石や岩が転がっており、頂上は広い ここは携帯(NTTドコモ)が繋がる 黒岳の頂上は周りに雲が湧いていていることが多い この日も曇天で北海岳は眺められたが北鎮岳や凌雲岳は雲の中だった |
 |
黒岳から見た北海岳 最近は歩くルートが大体分かるようになり、北海沢から頂上へ向う登山道が見分けられるようになった 一見緩い登りだけに見えるが、実際には結構きつい登りもある |
 |
黒岳石室 バイオ式のトイレがあり、給水タンクに炊事や飲むための水がある この水は自由に使えるが、煮沸が必要(エキノコックス予防等のため) 寝場所で火気の使用は禁止で、入口に簡単な炊事場所がある 雨でなければ、殆どの人は外の休憩用のベンチで食事の支度をしている 場所によって携帯(NTTドコモ)がつながる |
| 7月12日 黒岳石室〜大雪高原温泉 | |
 |
黒岳石室(入口側から奥を見る) 手前右側の建屋が管理人の居る棟で、我々が泊る石室はその奥にある 出発時、雨は上がっており、青空も見えたので、このまま天気は良くなると思って、黒岳石室を出発したが、そうはならなかった |
 |
黒岳石室付近から見た北海岳 黒岳石室を出るとすぐ目の前に北海岳が正面に眺められるが、この日山頂は雲の中だった この先で雪渓を下り、赤石川と北海沢を渡る |
 |
赤石川渡渉地点 渡渉地点の雪はすっかい無くなっていた ここ数年毎年今頃の時期にここを通るが雪がなくなっていたのは今回が初めて ここを渡り、写真の雪面を登って林に入り、これを抜けると目尾の前に北海沢の渡渉地点が現われる 北海沢の渡渉地点は未だほとんど雪に蔽われていた |
 |
北海岳の登り口 登り口を示す黄色のマークが岩に描かれている 初めてここを歩いた時、又来るとは夢にも思わなかったが、黒岳石室〜北海岳間を歩くのはこれで7回目になった |
 |
休憩所 休憩用のベンチが2つあり、北鎮岳が正面に眺められる見晴らしの良いところだが、この日は雲の中で、何も見えなかった 風も強くこの日は、少し先の木陰で風を避けて一休みした 花時には、周辺に沢山の種類の花が咲いている |
 |
エゾノツガザクラ 上の写真の休憩所を過ぎて、しばらく歩いたところで群生していた 手前の白い花はチングルマ 今回花の写真はこれが最後となった |
 |
北海岳頂上 強風かつ視界がほとんど無く、いつもは見かける登山者は0だった 風が強くて、この写真を撮って逃げるように北海原へ下った |
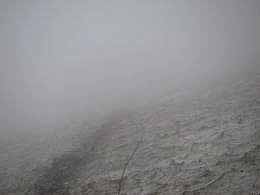 |
白雲岳付近の雪渓 視界はほぼ0に近く、足元のガイドロープだけを見て歩いた この雪渓は未だ大きく、今回のように視界がない場合は、このガイドロープが無ければお手上げになる |
 |
白雲岳十字路 晴れていれば見晴らしが良いので、一息入れるのに格好の場所だが、この日はガス、雨、しかも強風で人影は見られなかった メモ代わりに使用しているカメラの写真はこれが最後となり、この後はぬれて動作しなくなった |
 |
エイコの沢ガレ場 これまでこのような地肌が見えなかったが、ここも雪融けがすすんでいて、これまでとだいぶ様子が異なっていた メモ代わりのカメラが使えなくなったので、ここからはマクロレンズ付きの花の写真用のカメラで写真を撮った |
 |
第二お花畑 ここで下から登ってきた地元の登山監視員と思しき人と出会った(写真左の方に写っているのだが、この写真では分かり難い) 第一お花畑の標識を立ててきたと言っていた 問われるままに今日の山中の天気のことを二三話した 緑岳手前で会った2人組のパーティーと合せ今日山中で会う3人目の人である |
 |
第一お花畑 この日は木道がすっかり顔を出していたが花は未だ何も咲いていなかった これまでの悪天が信じられない好天下を歩いた |
 |
見晴台 第1お花畑と大雪高原山荘の中間辺りにある ここに立っている導標には、高原0.5km、とあるが、実際にはもっと距離がありそうで、大雪高原山荘まではここからが長い |
 |
大雪高原山荘 緑岳から下山してきてここに泊るのは今回が4回目で、大雪山は山の花とここの露天風呂へ入るのが目的のようになった ここの責任者も私を覚えてくれていて、この日は到着が遅れたが、温かく出迎えてくれた 満室になってもせいぜい30名程度なので、風呂や食堂に混雑感がないのも魅力である |
 |
大雪高原山荘のフロント 写真手前側にお土産が並べられている ここは携帯もwifiもつながらない 外への連絡は固定電話のみで、回線はフロントと共用のため、フロント使用時は使えないと表示されている |
このページの先頭へ


