
RENTAI 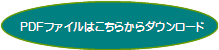
月例給、一時金ともに引き上げ
月例給は、すべての年齢層で引き上げ
一時金の引き上げは期末、勤勉の両方に配分
10月28日から始まった給与改定交渉が、最終提示(PDF参照)をもって11月12日に終了した。
給与改定の効果
職種・年齢別の月例給、一時金(ボーナス2回分)と年間の増額予測は概ね次のようになる。
県立学校事務職員 行政職(一)
| 年齢 | 級・号 | 月 | 一時金 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1・13 | 13,500 | 73,700 | 235,200 |
| 30 | 2・28 | 11,700 | 69,100 | 209,700 |
| 40 | 4・34 | 11,800 | 78,100 | 220,000 |
| 50 | 5・81 | 12,000 | 93,300 | 243,000 |
| 60 | 6・73 | 12,500 | 93,300 | 243,000 |
| 61~ | 5・85 | 8,500 | 60,300 | 161,900 |
| 再 | フル | 10,500 | 41,400 | 167,700 |
| 任 | 31H | 7,400 | 27,800 | 116,400 |
| 用 | 15.5H | 3,700 | 13,900 | 58,200 |
県立学校実習教員 教育職(一)
| 年齢 | 級・号 | 月 | 一時金 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1・13 | 13,500 | 73,700 | 235,200 |
| 30 | 2・28 | 11,700 | 69,100 | 209,700 |
| 40 | 4・34 | 11,800 | 78,100 | 220,000 |
| 50 | 5・81 | 12,000 | 93,300 | 243,000 |
| 60 | 6・73 | 12,500 | 93,300 | 243,000 |
| 61~ | 5・85 | 8,500 | 60,300 | 161,900 |
| 再 | フル | 10,500 | 41,400 | 167,700 |
| 任 | 31H | 7,400 | 27,800 | 116,400 |
| 用 | 15.5H | 3,700 | 13,900 | 58,200 |
県立学校教諭 教育職(一)
| 年齢 | 級・号 | 月 | 一時金 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1・13 | 13,500 | 73,700 | 235,200 |
| 30 | 2・28 | 11,700 | 69,100 | 209,700 |
| 40 | 4・34 | 11,800 | 78,100 | 220,000 |
| 50 | 5・81 | 12,000 | 93,300 | 243,000 |
| 60 | 6・73 | 12,500 | 93,300 | 243,000 |
| 61~ | 5・85 | 8,500 | 60,300 | 161,900 |
| 再 | フル | 10,500 | 41,400 | 167,700 |
| 任 | 31H | 7,400 | 27,800 | 116,400 |
| 用 | 15.5H | 3,700 | 13,900 | 58,200 |
表中の金額は、各年齢に在職する最多人数の「級・号」を基本に、 税と各種掛金を引く前の十円の位を四捨五入したものである。
なお、一時金は、扶養家族がないものとして計算した。
4月遡及改定により、20歳前後の職員に12月末頃に支給され る差額は、月例給に近い額となる。
働き方改革を絵に描いた餅にするな!―
25年度教育委員会交渉
11月28日、愛知県・自治センターにおいて、25年度の教育委員会交渉を行いました。
はじめに挨拶に立った伴委員長は、「教育委員会の皆さんが、教職員の職場環境の改善に日々努力されていることに 敬意を表します。昨年12月の文科省の「教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査」を始めとする 様々な調査結果が公表されましたが、すべての調査が、教員が依然として過酷な長時間労働の下にあることを示しています。 昨年9月には、県は「働き方ロードマップ」発表しましたが、現状を考えると極めて楽観的な目標設定と考 えざるを得ません。国も県も、本気で教職員の「働き方改革」を推進しようというのであれば、それに見合った予算を投入 すべきです。教育委員会の奮闘を強く期待します。」と述べました
県教委の代表からは、「皆さんには、日頃各校で様々な課題に尽力いただいていることに感謝している。 要求の内容には、関係課から現時点での考え方を説明する。今後も皆さんと話し合って適切に対応していきたい。」 という趣旨の挨拶がありました。
1.働き方改革ロードマップ
昨年9月に県教委が策定した「働き方改革ロードマップ」の 進捗状況について質したところ、時間外在校等時間の縮減については、初年度の目標すら達成できていないことが 明らかとなりました。
2.部活動の地域移行
中学校の一部では進んでいるものの高校では、先行きがまったく見えない状況です。
部活動全員加入については、県立高校145校中まだ35校で全員加入を義務づけています。 教員全員を顧問として配置している学校は137校で、見直しは遅れています。部活動総合指導員の配置も わずか48校(35%)しかなく、全校複数配置を強く求めました。
また、部活動指導ガイドラインについては、遵守状況のみならず、周知の状況にも疑問があることを指摘し、 周知と遵守について強い指導を求めました。
3.開錠・施錠時刻と電話対応
各校の開錠・施錠時刻の目安(朝は7時半以降、夜は19時)について、両方をずらして間の時間を縮めた学校が3割強、 いずれか一方をずらした学校が2割強あるとの回答があり、さらなるとりくみの強化を求めました。
一方、留守番電話機能を備える学校は22校しかなく、活用実態までは把握されていません。全校での設置と業務時間に 対応した切り替えが必要であることを強調しました。
4.環境整備
教科準備室・実習室等への空調設置については、体育館等への整備の後、考えていきたいと回答するものの 具体的なスケジュールは示されていません。
高校でのエレベーター設置については、課題として認識しているとの回答に止まりました。
5.ハラスメント対策
ハラスメントの相談窓口を 第三者機関とすることについては、検討を渋っています。 現在、総合教育センターに窓口を設けていますが、過去に門前払いのような扱いを受けたこと、 担当者が退職校長や教員関係者であることの問題点を指摘し、強く実現を迫りました。
