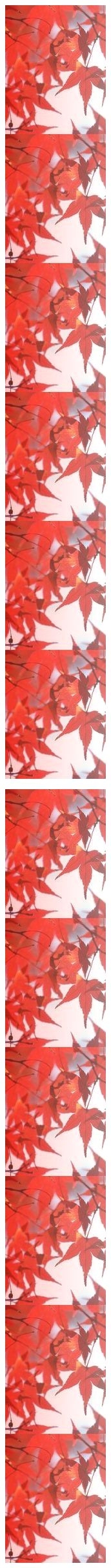冬。「思いやり」という善意をまとった「同情」が行われる季節。思い出すことがある。
さして季節感のある出来事ではないのだが、遠い遠い昔、私が小学校に通って二年目の冬のことだ。
その学校は、校舎や校庭の有様はすっかり変わってしまったけれど今も同じ場所にある。
場所は同じでも、通学路はすっかり変わった。当時、舗装されていた(と思う)道は昔からある街道筋一本で、
それ以外は土の地面だった。街道筋を歩くのはほんのわずかで、私たちはほとんど、家と家の隙間にできているような
狭い道をくねくねと歩いた。
だいたい1.5キロくらいの距離を、朝は通学班というグループでまとまって行く決まりだった。
当時は家並みも疎らで、道の脇は、屋敷の縁にある背の高い木々だったり桑畑や芋畑だったり、
放課後の子どもたちの遊び場になる藪山だった。そんな、リヤカーが通ると
体を横にしてやり過ごさなければならないくらいの細い道を毎日通った。
学校に近づくと、家が多くなって、石垣を高く積んだ上に蔵を構えたお屋敷もあった。その横を通る道は一年中じめっと暗かったが、
通り抜けると平屋の長屋の脇で、もう一つ角を曲がれば学校だと低学年の子も足取りが軽くなるのだった。
二軒続きの長屋が並んだ裏手には、トタン塀があって、誰かがその波トタンに手指をかけて音を出しながら歩くと、
みんなダンダンダンと真似をするので、時々「こら!」とか「うるさい!」と叱られた。
小学生たちは「わーッ」とむしろ楽しそうな声を上げて駆け抜けた。人のことなどお構いなしの無邪気で無礼な集団。
私も、その隅っこにいた。
この通学路の途中で、時々、「えっさ」と呼ばれる人にあった。
「さ」は人の名に付けて敬意を表す接尾語から来た呼び方だが、昔は気の置けない知人の間でそんな呼び方をするのを聞いたことがある。
「えつお」さんとか「えいいち」さんとかいう本名があるのだろうが、その人はいつも、誰からも、
小さな子どもからも「えっさ」と呼ばれていた。
歳は小学生から見れば「おじさん」と言うくらい。少し髪が伸びかけた坊主頭で、不精髭には白いものも混じっていた。
身なりはいつも同じで、くすんでくたびれたシャツを着て決まって腰に御用聞きが着けるような厚手の紺の長い前掛けをしていた。
薄いゴム草履を引きずるようにして、拳を内側に向けた手をぶらぶらさせながら歩いた。顔はいつもちょっと笑ったようで、
片方がゆがんだ唇から涎が垂れているのを見たこともあった。
この人を見ると「うぇー、えっさがおる」と誰かが言い、その横を避けるようにしてみんな通り抜けた。私も、その一人だった。
私には通学路で怖いものが二つあった。一つは当時多かった野良犬で、もう一つは「えっさ」だった。
歳末の寒い日だった。どういうわけか私はその日一人で下校していた。途中で、畑から大きな犬が出てきたのに出くわした。
怖気て棒立ちになった私は、その野良犬の向こうに、手をぶらぶらさせて来る異形の人を見た。通らなければならない道なのに足が動かない。
野良犬は舌を出してこちらを見ている。ちょっと笑ったような顔で近づいて来た「えっさ」は、犬の脇でその横腹を足で押すようにして止まった。
そして、体の横で腕をぶらぶらした。
通してくれようとしているんだ、とっさにそう思った。
押されてうなる犬に怖じることなく「えっさ」は足で押している。その横を、私は恐る恐るだけれど速足で通り過ぎた。
曲がり角まで来てちょっと振り返ったら、「えっさ」はまだ足で犬を押さえていた。笑ったような顔だけこちらに向けて。
この時も、このあとにも、私は「ありがとう」の一言を言えていない。
歳末の寒い日になると、今もこの、無垢の善意を思い出す。 (さ)